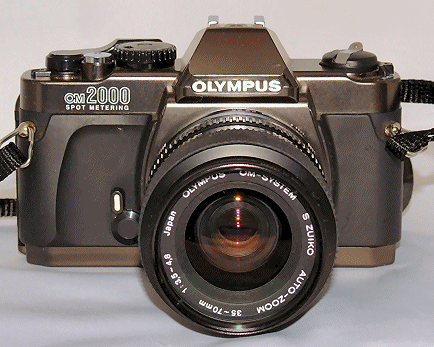idle talk34c
三井の、なんのたしにもならないお話 その三十四(2013.06オリジナル作成/2024.3サーバー移行)
私のカメラ遍歴(その三)
11.コニカビッグミニ <1991.8購入>
90年代はあまりカメラを買うという事態はありませんでした。
手持ちので十分という観もあったでしょう。
それでも買ったのは、オートフォーカス○○カメラの先駆け、コニカの製品でした。「コニカビッグミニBM201B」というのです。やはり「いつでも、どこでも、誰でも撮れる」式のは欲しかったし、なにより手軽さ優先でした。
オートフォーカスカメラもコニカの初代「ジャスピン」より、機能も外観も使い勝手もだいぶ進歩し、見た目もスマートコンパクトになり、そのうえ実はいままで持ったことがなかった「デート写し込み機能つき」であるのは有り難いことでした。おかげで、これで撮ったフィルムは撮影年月日をいまでも確実に確認できます。
ただ、予想されたこととはいえ、オートフォーカスの怪しさも実感しました。ファインダーのねらいがはずれると、「オートでフォーカスを外してくれるカメラ」になってしまいます。近年のオートフォーカスはコンデジでさえ、かなり「自動で被写体を捜し、ピントを合わせてくれる」ほどになっているし、もちろんAFの方式自体の変化で、ファインダーど真ん中のものしかとらえてくれないわけでもない、その意味柔軟性も高くて、めったに「外してくれない」ようになってきたと実感します。しかし初期の赤外線照射方式では、そのへんは無理であったようで、よくあるのは、二人並んだところを記念写真に撮ると、見事に中抜けで、後ろにピントが合っているというヤツでした。
まあ、別のところにも書いたように、コニカビッグミニのF3.5/35mm程度のレンズでは、晴天屋外など条件さえよければ相当広い範囲にピントが合ってしまう、目測でもほぼ外さないのでして、AFだ、すごいだろというのはホントはどのくらいのものか、ちょっと怪しい感じもしますが。それに、この頃のAFの画像というのは、近くの人物などなら、(真ん中に入っていれば)よくピントが合うのですが、距離無限大の遠景になると、なにかぼやっとした写りになりがちで、がっかりさせられるものです。
いろんなところへのお供をしてくれ、98年の再度のロンドン滞在にも一年間つきあってくれたコニカビッグミニですが、誠に不幸な最期を迎えました。突然、裏ぶたと本体の間をつないでいたフレキシ回線が切れてしまったのです。開け閉め可動するところである以上、ここの品質の問題があったのかも知れません。
こういう故障は、昔のように回線をハンダ付けして直すなんていうことは不可能、カメラ修理の「名人」のひとでも、似たようなジャンクボディをどっかから捜してきて、丸ごと部品を移し替えるでもしなければ、直せないでしょう。それでも、電子回路関係はフレキシ回線部分と、基板と、ICなどがおそらく一体で作られているでしょうから、どうにも手の打ちようもなかった可能性も大です。
まあ、裏ぶた部分への回線が切れても、撮影はできたのかも知れませんが、ここで見切りをつけました。後継機を買ったので、ビッグミニもお役目は果たしてくれたと申し、合掌黙祷するところでしょう。
コニカビッグミニのスペック詳細は、F3.5/35mm沈銅レンズ、3.6〜1/500secシャッターでプログラムEE式、EV2〜17対応、赤外線ノンスキャンアクティブ式AF(フォーカスロックあり)、フィルムオートローディング・オートワインディング、フラッシュマチックストロボ内蔵、セルフタイマー付といったところです。電池別(CR123A使用)で190gの重さを含め、機能や使い勝手は完全に現在のコンデジと同じと言えましょう。これで当時24,800円でした。
この項の画像、当初のものは間違いでした。
なにせ、コニカビッグミニの「遺影」は残っていないので、また肝心のコニカは消滅し、コニカミノルタももうカメラは製造販売していないので、そのカメラに関するアフターサービスを請け負っている(つまり、ソニーは「ひとの尻ぬぐいなどまっぴらごめん」と、おいしいとこだけ買い取った)ケンコー・トキナー社のサイトを探して、「カメラヒストリー」のところで画像を見つけたのですが、これは「初代ビッグミニ」でした。どうりで私の記憶とはかなり違うなと思っておりました。
あらためてビッグミニBM201の画像を探すに、web上のひとさまのものを勝手にリンクするのもはばかれるので、次善の策で、当時のカタログ雑誌掲載のBM201の写真をスキャンして載せることにしました。これも問題なしとはしないでしょうが、まあ公開されていたカタログ画像ですから。
12.オリンパスOM2000 <1998.9購入>
いつまでも妻のOM2を「横取り」していては後ろめたいということもあってか、むしろオリンパスのOMレンズを使うために買ったのが、このOM2000というほとんど知られていない、オリンパスの公式史にもひっそりとしか載せられていない、日陰者のような代物でした。
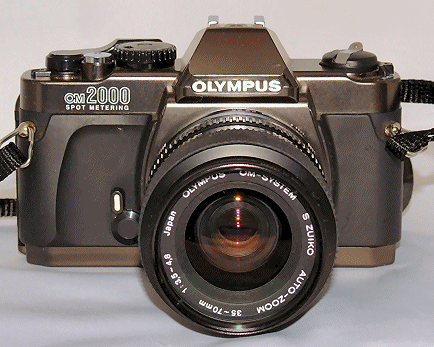

知る人ぞ知る、これはオリンパスが作ったのではなく、Co社製のOEMなのです。ですから、OMシリーズの特徴の一つだったレンズマウントまわりのシャッターダイヤルとかもなく、当時のごく平凡な一眼レフの風体で、実際「シャッター速度1/2000まで」というほかに売りもありません。Co社が同じボディフレームであちこちにOEM供給していたというのも有名な話で、ですからOM2000と並べてみると、よく似たのがしばしば見つかります。
ほかに隠れた性能ながら、1/2000を実現した縦走りメタルフォーカルプレーンシャッターのおかげで、X接点ストロボ同調が1/125まで可能であるものの、本来オリンパスのボディじゃないから、TTLダイレクト測光制御のOMストロボは使えませんでした。メリット乏しいですね。「スポット測光切替」というのもいまひとつ特徴ではありました。ただ、フィルム巻き上げレバーを収めるとシャッターロックになるというのは、電池の無駄な消耗は防げましょうが、いざというときにシャッターが落ちなくて焦るという事態も招いた気がします。だいたいシャッター自体は電子制御じゃないので、電池を気にする意味もあまりないのですし。
まあ、ですから「OMレンズが使えるCoカメラ」とも称され、特徴乏しいだけでなく、OM1同様の定点合致露出合わせ方式に戻ってしまったのをいまさら買う必然性もなかったのですが、なにより安かったのです。ズームレンズ(これまたとてもチープ)、ケース付で「メーカー希望小売価格」5万円でしたから。実際にはもちろんもっと安く手に入れたのです。
これをどのような経過で買ったのか、調べてみるとうえに書いたように1998年9月に○○バシカメラ横浜駅前店で購入と、保証書に記されています。そうなると、同年の3月末にはロンドンに旅立っているので、9月に父の死で一時帰国をした、その時以外には購入機会がありません。前のページに書いたように、OM2を翌年8月に修理に出しているので、おそらく98年3月末に旅立った際にはOM2を持っていった、しかし調子が悪いため、この一時帰国の際に、代わりとしてOM2000を購入、そちらを持ってロンドンに戻った、そういうことになります。
おまけのズームレンズはかなりひどいもので、がっかりさせるような写りでした。以来私はずっとズームレンズ不信に陥っていて、2000年代のデジイチ復活で、ようやく「いまどきのズームは向上著しい、よく写る」と実感するようになった次第です。ですから、OM2000にももっぱら、以前からの単焦点レンズを用いていました。
総合評価として、OM2000はそれほど悪くもなかったのですが、AEに慣れてしまっている身として、ピント合わせには集中しても、適正露出をつい忘れてしまうという失敗はかなりやりました。人間慣れと怠惰化は恐ろしいものです。それは別にカメラのせいではなく、慎重にやればいいだけのことですが。
ちなみに、ロンドンで写真の現像焼き付けを出していた店は、代金を払うと「当店ブランドの」フィルムを一本おまけにくれるという仕組み、販売競争の激化を反映している一方、このタダフィルムはASA(ISO)200という中途半端な製品でした。おかげで、遂にフィルムを「買う」ことはなかった次第。
OM2000はいまでも健在ではあるものの、デジカメ中心の今日では容易に出番はありません。強いてフィルムで撮ろうという時にはブローニーの番だし、35mmで撮るのなら、AFでもある、ニコンの方に頼ってしまいます。マニュアル35mm機はもう、永眠の時かも知れません。OM2000自体、AF時代到来でカメラづくりに大いに迷いだしたオリンパス最後のフィルム一眼レフとも言えるのであり、だから自分のとこで作る気がおこらなかったのでしょうが、その意味、博物館に飾るべきものなのかも。
13.コニカビッグミニF <2000購入>
うえに書いたように、初代ビッグミニであったBM201Bは「突然死」してしまい、やはりこれがないとファミリーカメラとして不便なので、ビッグミニFを買いました。
使い勝手はよく似ている(ていうか、AF化した○○◇ョンカメラはどこのでもほぼ同じ、ファインダーを覗き、カメラを向けてシャッターを押しさえすればいいわけです)し、性能もF2.8/35mmレンズ、4〜1/450secシャッター、プログラムEE、オートワインド、セルフタイマー内蔵となっています。フラッシュマチックストロボ付、デート写し込み機能付はもはや定番です。前のビッグミニに比べるとレンズが一段明るくなり、性能向上とも言えましょう。それでひとまわり小さく、重さは電池別180gと、一段と軽量化しました。
不満の残った遠景撮影時には、セルフタイマーと同じボタンを使って「遠景モード」を選べるようになったのも進歩でしょう。露出補正や、ストロボ発光や同調のアレンジなど、いろいろいじれるのも特徴のようですが、あまりそのへん機能をつけすぎると、「誰でもボタンを押しさえすれば撮れる」利点が失われるのも考え物です。
当時各カメラメーカーは、AFカメラにやたら機能・性能てんこ盛りでの末期的競争に陥っていました。その一つのポイントが「ズーム比」でした。どこの製品も同じように自動化の極地、残るはズームレンズの売りくらいで、コニカも38-150mmズームとか相当に無理したようなレンズをつけて懸命に売り込んでいたわけです。もっともコニカの場合、このまっただ中で、ビッグミニのような固定焦点レンズのまんまを守る、あるいはTTL自動測光、レンジファインダー使用のレンズ交換式フォーカルプレーンシャッター高級機を出すとか、あの手この手を模索したのも特徴でした。ただ残念なことに「薬石効なく」、2000年代デジカメ全盛の時代を迎えると、コニカはあえなくギブアップ、ミノルタにいったん吸収されたものの、そのコニカミノルタも2006年にはすべてのカメラの製造を中止、ソニーに譲渡し、コニカのカメラは消えてしまったわけです。
メーカーは消えても、私のところのビッグミニFは残っています。この「競争と優勝劣敗」の構図はまさしくデジカメ時代にも再現されたわけで、その際には「ズーム比」に代わって「画素数」で各社しのぎを削り、「行くとこまで行って」相次いで共倒れ、あるいは吸収されていく、他方で「レンジファインダー復活」や「高級感漂う」マニュアル動作重視品で独自の勝負とか、結局20年前となにも変わりませんね。そして、私の手元には古典的な製品が残る次第です。「ファインダーが付いてる」ことを別とすれば、いまどきコンデジともあまり変わらないのですが。
98年3月末にロンドンに持っていったのはビッグミニBM201Bと、うえに書いてしまいました。ところが、ビッグミニFに買い換えたのが正確にはいつなのか、実は手元で十分確認できませんでした。そうすると、ロンドンと英国などの風景を収めたのは、本当はビッグミニFである可能性も出てきました。
というような事情で迷ったのですが、ビッグミニFを買ったのが2000年でほぼ間違いないだろうということで、1998-99年にロンドンに持って行っていたのは、前身のビッグミニBM201と推定可能になりました。
ビッグミニFを買ったときの正確な記録が残っていなかったし、これの発売は1997年にまでさかのぼれるせいなのですが、私が買ったのは2000年以降であることを推定させる材料は見つかった次第です。
14.リコーFF1s <1998.3購入>
98年のロンドン行きの直前に中古で買っています。
長く使っていたFF1がかなりくたびれてきたので、たまたま店頭で見つけたその後継機FF1sに飛びついたのでしょう。ということは、こちらをロンドンに持っていったのですね。中古価格で当時36,750円でした。FF1sは発売当時の1980年で希望小売価格36,000円とあるので、かなりいい値がついていたものと言えます。まあ、FF1を買った頃にすでに後継改良機が世に出てきていたわけですが。
後継機ですから、FF1と外観も動作も機能もほとんど変わりません。F2.8/35mmのレンズ、プログラム電子シャッター2〜1/500sec、プログラムEE、アルバダファインダーと前玉回転目測ピント合わせ、セルフタイマー付といったところ。もちろんスプリングカメラ様のフォールディングタイプはまったく同じです。
中古で買った1998年当時は、もうAF機全盛の時代で、リコーもFFを冠しながら、似ても似つかぬAF○○機を相次いで市場に出し、しのぎを削っていた頃でした。物好きもいいところであったわけですが、好きな人間も少なからずいたので、こんな値段で売られていたのでしょうし、以後もめったに中古店でも見かけません。
これもいまだ現役ですが、買って10年足らずでさすがにだいぶくたびれ、ぼろぼろになってきた裏ぶたまわりのモルトプレーンの交換を修理業に頼みました。ともかく、製造以来ならいまではおそらく30年は経っていることになるので、この出来からしてもいまだ現役という方が奇跡に近いものです。
デジカメ全盛の今日、FF1sの有利さはひとつだけあります。ポケットに忍ばせ、離着陸時の機内から窓外の風景を撮ることです。まあ、乗務員が飛んできて、「デジカメ使用禁止です!!」とのたまうに、「これはデジカメじゃないんです。フィルムカメラと言うんですよ」とやおらこたえる、これをやってみたくてたまらないのですが、残念ながら一度もそういう事態が起こりません。もっとも、「離着陸時は一切の電子機器は法令で使用禁止」なんてしつこく徹底されても、平気でデジカメで撮り出す輩は決して珍しくないし、それどころかこの頃は手元のスマホを向けるし、それを客室乗務員が止めに入るという光景も見たことないので、まあ実質黙認放置状態なのかも。期待がかなわず、機体も揺るがず、つまらんですね。
☆これにも、それぞれの画像の説明を載せます。
| BIGmini | 横浜金沢自然公園から |
| OM2000 | ロンドンリッチモンドの丘から |
| BIGminiF | 知床 |
| FF1s | 常盤台キャンパスの一隅 |
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
静かなりし90年代、デジカメ化怒濤の21世紀は、つぎです。
その四へ