誰も知らない傑作TVドラマ『道頓堀川』(NHK・1982)についての、続きです。
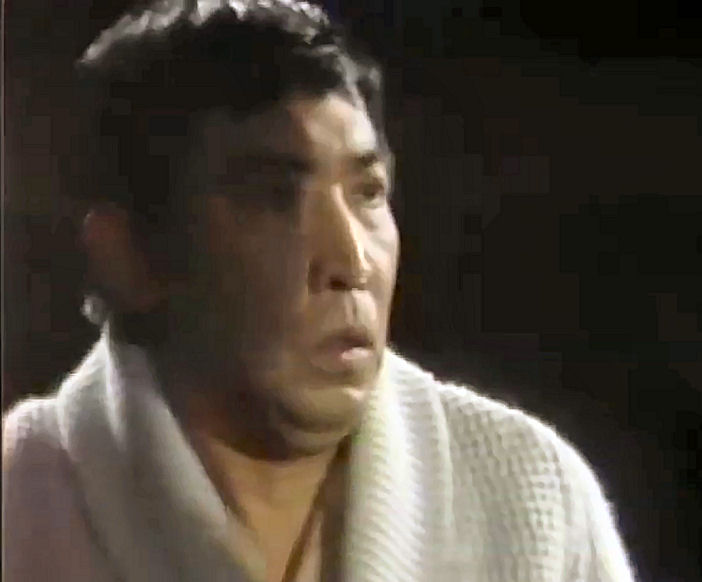 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
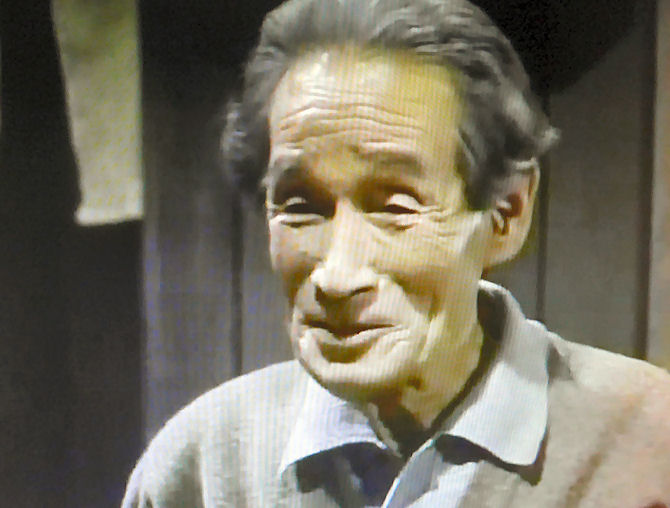 |  |
 | 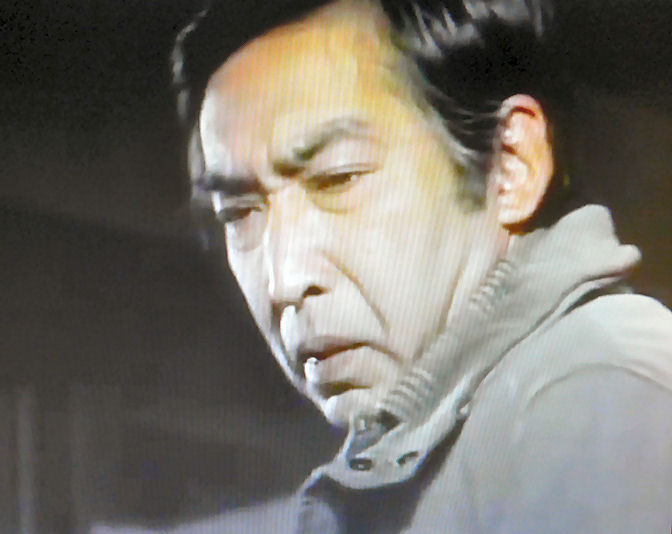 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
|
描かれたこと、描かれなかったこと こうした一連の物語の流れを振り返っているうちに、あることに気がつきました。 ドラマ『道頓堀川』は、ある意味では「不倫」の男女関係の展開とそれがもたらしたものを描いたとも言えるのですが、その「不倫」(この言葉は好きではないのですが、「婚外恋愛」なんて書いても、かえって妙になります)自体は、ほとんど描かれないのです。 邦彦の父(だいたい、名前も出てきません)は、妻以外の女としょっちゅう関係を持っていて、邦彦の回想でも、「お父ちゃんのあれは病気だから」と母の口癖であったそうです。ただ、弘美との関係にはさすがの母も激怒し、狂ったようになったとも語られます。実際、それだけのめり込んでいたというのも、邦彦の父との思い出の場面で父の口から語られます。「あの女は特別や」「母ちゃんがどんなに怒っても、どうにもならんのや」と。そして、父が弘美と暮らすアパートに、酔った勢いで邦彦を招き入れ、その生々しい「若い女の部屋」の雰囲気に、中学生の邦彦の心が動揺したと思い出させるのです。 けれども、この場面で弘美は戻ってこず(「お仕事中」だったのでしょう)、すれ違いで終わります。ですから、邦彦には物語の展開のなかで、7年の後に突然訪ねてきた弘美との出会いがはじめてとなります。そのため、結局「父と弘美が一緒にいる」場面は一切ありません。ふたりが深い仲であった、どうにも切れない関係であった、父の急病がふたりを断ち切ったと、せりふのうえで回想されるだけで終わります。
「不倫関係」のなかで駆け落ちした、鈴子と易者杉山の場合もそうです。ふたりが一緒にいる、というのは、政夫を連れて逃避行に出る、大阪駅の待合室での場面だけです。杉山が切符を手に入れ、ふたりの元に戻って、三人でホームに向かう、これを吉岡が偶然目撃していた、という「大変な出来事」になってしまうわけですが、前後の描写は一切ありません。そこからすべては四年の後、政夫とともに大阪に舞い戻った鈴子に飛んでしまいます。 三人が暮らした天草での場面描写などというのは一切なし、すべては言葉でのみ語らせる、というのは、物語を雑然とさせない意味も読み取れましょう。あくまで大阪ミナミのお話なのです。でも、この駆け落ちに至る、鈴子と杉山ののめり込む不倫関係などというものも、出てこないのです。あくまで、突然妻子に「逃げられた」鉄男の視点で語らせるという構成も読み取れるものの、逆にいささか唐突、想像力を醸しがたい不可解な流れになったことも否定できません。実は原作『道頓堀川』では、杉山と鈴子の肉体関係を相当あけすけに描写しています。邦彦の父と弘美の関係を含め、そういった所をぜんぶオミットしたのは、どういう意図あっての脚本でしょうか(もちろん、出演者のスケジュールや撮影の都合、ロケやセット設定なども関係し得たでしょうが)。 ですから、結局鈴子と杉山の関係というのは、鉄男が易をみて貰った、三人の最初の出会いの場面で、しなを作り、愛想で「来客をもてなす」彼女に、杉山の無遠慮な目が向けられる、それだけしか出てこないのです。
いや、「おとことおんなの仲」「せっくす的描写」などという、おかたいNHKのドラマにふさわしくないようなものは一切オミットというわけではないですよ。鈴子に惚れ込んだ鉄男は、彼女を引きつけ、いろいろ面倒をみ、ついには鉄男の部屋で「寝ます」。「ことのあと」、布団にくるまっている鈴子、横に座ってたばこを吹かす鉄男、そこでは鈴子が鉄男の恋情に身も心も任せ切っているようで、ふたたび抱き合います(四年間の逃避行、二年間の別居ののち、結局元の鞘に収まって抱き合ってしまう二人の「性衝動」も描写され、息子政夫はこれに「何をしようとしているか、子供にもわかる」「とてもいやな気がした」と回顧します。二人は夫婦なんですから、妙ですが)。ですから、のちに鈴子に裏切られた鉄男の絶望感と憤り、憎しみの深さが描き出されるわけではあるものの、鈴子と杉山の関係というものに、説得力を欠くことも否定できません。
それに比べ、邦彦とまち子の関係の描き方が非常に淡泊で、夜中、店の二階で抱き合ったまま、「ことの手前で」終わってしまうのは、そんなに深い意図もなかったのかも知れません。その前には、行方不明になったまち子の愛犬小太郎を探しに、二人で界隈を歩き回り、日も暮れて道頓堀の明かりを眺めながら、まち子が邦彦の肩に頬寄せ、二人は衝動的に口づけを交わします。流れは一気に燃え上がるものの、肉感的にはそれまで、です。深作版映画の方は、二人の交情をメインに据え、松坂慶子の豊満な裸身と真田広之とのからみで売った、それとは真逆の方向をドラマの作者や演出者らがめざしたというのであれば納得できます。別に、演じた辺見マリが「拒否した」わけでもないでしょう。 ただ、寄る辺を失い、戦後の街をさまよっているところを鉄男に救われ、ご飯も食べさせて貰ったアキが、その晩鉄男のところに泊めて貰って、小さな胸を押さえ、「今夜はいやや、お風呂に入ってきれいにしたから!」と抵抗のそぶりを見せる、これは生々しい印象を残しますね。鉄男にはもちろん、彼女がどんなことをして生きていたのか想像できます。「ウンな鶏ガラみたいなからだ、売ってもなんぼにもならんやろ」の台詞とともに、彼はアキをいたわり、カネを持たせてやるわけですが、妻に逃げられた鉄男の「性衝動」はどうなっていたのかなど、妄想をめぐらせる余地があります。まあ、こんな少女に手を出すほどの男ではないでしょう。
|
(2020.10.24)
それから
記したように、ドラマ『道頓堀川』を見る方法は遮断されてしまったようですが、web上では関連する情報が拡散されてもいます。
ググると、「ドラマ 道頓堀川」で出てくるのは、真っ先に私のこのwebページであり、また画像も検索されます(まあいまのところ、訴追はされていません)。ただ、ほかにも出てくるものがあり、たとえばこの「ドラマ 道頓堀川」の台本がネットオークションにあがったことがあるようです。誰か落札して入手したようですが、出所はどこなんだろ。出演者誰かの遺品かな。
ほかに目立ったところでは、もう還暦を迎えた内藤剛志の「回想」で、この『道頓堀川』出演のことに言及されているようです。『京都新聞』2019年11月12日号のインタビュー記事で、『道頓堀川』での藤田まこととの共演の経験を語り、「正確なセリフ回しに、現場に応じた演技の引き出しの多さ、スタジオにたたずむ風情‥……。所作一つ一つに、「俳優という仕事は職人である」と圧倒された」と記されています。
同じことを、NHKの「スタジオパークからこんにちは」で、内藤氏は述べていたそうで、テレビ初演であるとともに、ここでの藤田まこととの共演で、「演技とは何か」を深く教えられたとも。
まあ、藤田まことにしたたかにぶん殴られる役だったんですから、忘れられるわけないかも。
さて、そうなると現在では人気を誇る役者内藤剛志の原点は、「ドラマ 道頓堀川」であったと誰もが認めざるを得ないわけですが、そのものを誰も見ていない、見られない、そもそも知らない、誠に珍なる事態になるわけですね。「え、ドートンボリガワって、真田広之だろ」とかね。でも、NHKは再放送はできないんだろうな。内藤氏の回顧は、期せずして突っ込みどころだな。
|
内藤剛志の回顧なども語られた「スタジオパークからこんにちは」という放送は、こうした番組裏話などを含め、結構面白いテーマのも多かったのですが、私は残念ながらこの回を見逃してしまいました。あくまで、「ながら」視聴であったせいもあります。そして、放送ももう終わってしまいました。平日の昼過ぎという時間帯は結構難しい、またいろいろ重大な報道などで潰れることも多かったゆえのことでしょう。
ですから、実際の彼の『道頓堀川』出演に寄せるいまの思いの言など、聞けていないのですが、これは結構反響もあったようで、この内容をスナップ画像を交えて綴ったblogも公開されています。しかも、番組の中で『道頓堀川』での彼の登場場面映像も出てきたらしく、それを撮ったスクショも載っているのです。ということは、NHKはこの放送時、断片的に40年前のドラマの場面を流した!!ということなのですな。完全お蔵入りでもなかったわけで。 |
(2012.08.15)
断ち切られた「家族のかたち」
『道頓堀川』を何度も見ているうちに、新たな発見というか、今更気がついたこともあります。
この物語には、当たり前のような「家族」がいないのです。
もちろん言うまでもなく、中心人物である鉄男と鈴子、そして政夫は「夫婦と息子」の典型的な家族の原初形のはずなのですが、鈴子が2歳の政夫を連れて出奔、4年ののちに困窮して出戻り、それから2年あまりたってまた一緒に暮らしだすものの、1年で鈴子は他界、結局一緒の暮らしが続いていたのは、結婚当初も合わせて5年足らずの日々のことであったとなります。鈴子の死から数年のちには息子政夫は父親の元から飛び出し、学校も退学、玉突きに賭けて放浪の身となり、結局もとには戻らないのですから、家族は完全解体、まさに鉄男が述懐したように、「杉山の見立て通り、一家離散になる」定めの結果は動かしがたいわけです。
語り手・邦彦はすでに父母を亡くして、ひとりぼっちの身です。しかも父は長く家に寄りつかず、そとの女のところを転々とし、弘美のもとで急の病になり命を落としてしまう、その後母も亡くなる(母の出てくる場面は、弘美のところで急病に倒れた夫の入院先に駆けつけるが、その顔にはすでに白い布がかけられていたという一場面のみで、その母の死の詳しい事情もドラマのなかでは語られませんが)、20歳過ぎでまさに誰も面倒を見てくれない天涯孤独の境遇になってしまっています。物語のエピローグでは、邦彦の向学心を支えてきてくれた鉄男と邦彦が雇い主とアルバイト従業員といった関係を超えた、新たな絆を築いていくことを暗示させますが、それはあくまで可能性でしかありません。
そして、鉄男の戦友であり長年の親友・相棒であった吉岡もずっと天涯孤独、独り身です。「こんな身体の中年親父、誰が相手するかいな」と自嘲しながら生きてきた彼ですが、「家族」への憧れもあり、飲み屋の仙子に惚れ、結婚を申し込みます。「俺かて嫁さんもろうて、なにが悪いんや」とその思いを鉄男に熱く語り、冷ややかな評価を受けます。そして予想通り、結局は振られ、去られてしまいます。やはり親子ほどの年の差に無理がありました。
小料理屋の雇われ女将マチ子は芸者上がりで、パトロンの老画商に身請けされたかたちです。その旦那を「好きなんでしょ」と問われ、「そんなこと考えたこともないわ」と投げやりにこたえるのみ、ひとを愛する、そうした関係に我が身を置くことのかなわない、悲しい身の上が続きます。だからこそ、年下の邦彦に思いを寄せ、愛を注ごうとするものの、そこに人生をかける勇気もないことを悟らされる、「どうもならん」自分自身への絶望を自覚するしかありません。物語の始めから終わりまで、ひととひとのつながりから外れた境遇を味わい、それに逆らって生き方をもとめ、そしてさだめのなかに閉じこもるしかない、悲しい存在です。
邦彦の父が「一番のめり込んだ」女である弘美は、何年過ぎようとも、その思い出をどうしても捨てきれないほどやはり惚れていたわけですが、自分のもとで死なせてしまった以上、後悔と未練とつらい思い出に浸るしかありません。息子邦彦に会うのも、そのひとの面影と思い出を語れる相手がほしい、そこに尽きてしまいます。しかも彼女は、「ちゅうっくらいのひとやった」という妙な回想をします。素晴らしい人物、男前、稼ぎ手、芸達者、そうではない、しかしまた逆でもない、だからこそ心から離れない、離しようもないという心理でしょうか。裏を返せば、そのときには自分も一番、女として輝いていたという思いでしょうか。
それでも弘美は、ドラマ終盤で、新たな「男を見つけ」、その人と一緒に仕事していくことになったという事情を邦彦に語ります。「またも」妻子持ち、仕事もうまくいってない、そういった中年男の「面倒を見る」、その先の彼女の人生に、安定した夫婦と家族の暮らしを描くことは難しい、邦彦の覚える危惧を弘美は否定はしません。「ま、いいやないの、あのひとはあのひとや」、この割り切りは、この物語の人間関係観の一つのまとめ方のようです。
鉄男を神様のようにあがめ、頼りにする焼き肉屋経営のユキは、いっぱし女実業家となって、あらたに梅田の地下街にステーキハウスをだす計画を進めています。けれども彼女はずっと独り身のようです。戦後貧苦と身寄りない状況にあえいでいた彼女は鉄男に救われ、また何度も助けてもらったわけですが、のちに「台湾のひとに世話になり」、店を始めることになる、しかしその人も死んでしもうたということで、ひとりで商いに打ち込み頑張ってきたという20年でした。
邦彦の父を終生の恩人と呼ぶ金兵衛、その娘由紀子の親子は、この物語では例外的に安定した家族関係のように見えます。ふぐ料理の小さな店を営む父のおかげで短大にも行かせてもらっているわけですが、なぜか終始、由紀子の母親というのは出てきません。その理由は語られないものの、死別したのではないかとも想像されます。店の手伝いをろくにしてくれんとぼやく父に対し、「お父ちゃんは世間並みの給料をくれないから」と逆らう由紀子、それで冬休みのスキー合宿の費用を稼ぐために、邦彦の紹介で「リバー」で働くことにします。「大学の授業なんて出んでも大丈夫」と割り切るなど、「さばけた」「世知に長けた」由紀子ですが、その辺には母親の影のないことがうかがえます。
このように、この物語には「絵に描いたような」幸せそうな夫婦・子らといった「家族のかたち」は一切出てきません。むしろそれが無残に壊される、引き裂かれる展開のみで構成されているのです。そこにこそ、作者らの思いが溢れんばかりに込められているわけであり、そしてだからこそ、「うけることがなかった」ドラマ作品のさだめともなったのでしょう。
→ つぎへ
