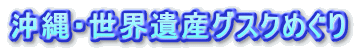
2010.1.23 〜 1.25
![]()
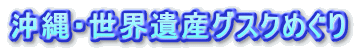
2010.1.23 〜 1.25
![]()
1日目 中部国際空港 → 那覇空港 → 今帰仁城 → 美ら海水族館 → 名護(泊) 2日目 名護 → 座喜味城 → 勝連城 → 中城城 → 識名園 → 那覇・おもろまち(泊) 3日目 おもろまち → 首里城 → 那覇空港 → 中部国際空港 |
日本100名城めぐりも残すところ少なくなってきた。今回は3城が選定されている沖縄の城(グスク)をめぐる旅。100名城の今帰仁城、中城城、首里城に加え、座喜味城、勝連城と、平成12年(2000)に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録された5城を3日間で回る。 1日目、朝8時45分のJAL3251便のジャンボ機で出発。今回もクラスJのシートでゆったり。会社更生法適用で、いろいろ心配なJALであるが、客室乗務員の方々は、何とか今の状況から再起しようと頑張っているように感じる。頑張ってほしいものである。 11時15分那覇空港到着。天気予報どおり曇っていて、残念ながら青い空は望めない状況。空港から送迎バスに乗ってレンタカー会社へ。さすがに観光地だけあって客も多い。結局レンタカーで出発できたのは12時だった。車を沖縄自動車道・那覇ICへと走らせ、最初に向うのは今帰仁城。 許田ICで降り、一般道を走り、1時間30分ほどで今帰仁村グスク交流センターのところの駐車場に到着。前日から「今帰仁グスク桜まつり」が開催されていて、観光客でいっぱいである。寒緋桜ではあるが、沖縄ではこの時期から桜が咲く。城跡でも既にピンク色の花が咲き始めていた。交流センターで入場券を購入し、城跡へ向う。 今帰仁城の創建は13世紀末から14世紀初めといわれ、15世紀前半には本丸、大隈、志慶真門郭などからなる現在の姿になったと考えられている。1383年に怕尼芝が今帰仁城主となり、その後三代にわたって北山王を名乗ってこの地を支配したが、中山王尚氏によって1416年に城は陥落した。曲線を描いた壮大な石垣が見事である。ひととおり城跡を散策してから、今帰仁村歴史文化センターを見学する。 今帰仁城の次に向かったのは、本部町の海洋博公園内にある沖縄美ら海水族館。こちらも多くの観光客で賑わっている。水族館のシンボルでもある1階から2階を貫く水量7,500m3の世界最大級の「黒潮の海」水槽には、巨大なジンベエザメやマンタが泳ぐ。館内を順に見て回ってから、外へ出て、マナティ館、ウミガメ館、イルカラグーンと回ってから、同じく公園内にある海洋文化館へも入館。沖縄だけでなく、アジア・太平洋地域を中心とする海洋文化の成り立ちとその歴史、海を通じて運ばれた文化の伝来と発展、民族相互の交流の姿を学べる施設である。見学後、車へ戻り、この日の宿泊地・名護へと向かい、到着後ホテルへチェックイン。 2日目、ホテルをチェックアウトし、レンタカーを沖縄自動車道・許田ICへと走らせる。この日は天気も回復してきそう。沖縄自動車道を石川ICで降り、まず最初に目指すのは、読谷村にある座喜味城。100名城には選定されなかったが、世界遺産に登録されているグスクである。国道58号から右折して県道をしばらく走ると、読谷村立歴史民俗資料館のところの駐車場へ到着。資料館はまだオープンしていなかったので、先に城跡を散策することにする。 座喜味城は、15世紀の初頭、読谷山の按司護佐丸によって築かれたといわれる。標高120m余の丘陵に立地し、二つの郭からなっており、それぞれの郭にはアーチ石門が造られていて、アーチがかみ合う中央にくさび石がはめられているのは他のグスクには見られないそうである。城跡を隅々まで探索してから、時間になったので資料館へ行き、展示を見学する。 資料館を出て車へ戻り、次に向かうのはうるま市(旧勝連町)にある勝連城。こちらも同じく100名城には選定されなかったが、世界遺産の一つである。読谷村から国道58号を嘉手納町方面へ走り、嘉手納ロータリーで左に曲がって県道を与勝半島の方へと向かう。沖縄市を抜け、うるま市へ入ってしばらく行くと、右手の丘陵の上に石垣が見えてきて、自然とテンションが上がる。城跡から県道を挟んで向かいにある勝連城跡休憩所の駐車場へ車を停め、徒歩で急坂を登っていくと四の郭へ到着。ここから見上げる石垣は壮観である。 勝連城は、13〜14世紀に茂知附按司により築城されたといわれ、琉球王国が安定していく過程で国王に最後まで抵抗した有力按司・阿麻和利が最後の城主。阿麻和利は、中城の護佐丸を1458年に滅ぼし、さらに王権奪取を目指し首里城を攻めたが大敗して滅んだ。四方に眺望のきく孤立丘を取り込んで築かれており、四つの郭からなる。各郭は珊瑚質石灰岩の切石を使って曲線状に築かれており、最高所に位置する一の郭には瓦葺きの建物やアーチ式の門があったと伝えられている。下から順に、三の郭、二の郭、一の郭と登っていくと、両側に海が見え、平安座島や伊計島などを結ぶ海中道路も見え、天気もよく気分爽快である。ひととおり散策してから、休憩所内の展示を見学する。 予定しているスケジュールより少し早めに行動できているので、海中道路の途中にあるうるま市立海の文化資料館へ行くことにする。海中道路は、与勝半島と平安座島を結ぶ全長4.7kmの海上を走る道路で、中間地点のロードパークには「海の駅あやはし館」があり、その2階の海の文化資料館では、山原船や木造船など海にまつわる民俗資料などが展示されている。 海中道路をUターンして戻り、次に向かうのは100名城に選定されている中城村にある中城城。もちろん世界遺産である。国道329号から右折してしばらく走ると、駐車場へ到着。案内所で入場券を購入し城跡散策へ。 中城城は、14世紀後半に先中城按司によって築かれ、15世紀前半に尚巴志の家臣・護佐丸が増築したとされ、北東から南西にかけて6つの郭が並んでいる。1458年、勝連城主阿麻和利の策略によって滅ぼされた。グスクの中では最もよく遺稿が残っていることで知られる。順路どおり裏門から入って、北の郭、三の郭、二の郭、一の郭、南の郭と回り、正門から出て駐車場へ戻る。 その後、城跡から車で1、2分のところ、北中城村にある国の重要文化財・中村家住宅を見学。中村家の祖先は豪農で、護佐丸が中城城に移ったときに共に移り、その近くに居を構えたという。主屋は18世紀中頃の建築とされ、戦禍を免れた貴重な家屋である。 中村家住宅見学後、那覇市内へ向けて車を走らせるが、スケジュールに余裕ができたので、世界遺産登録されている識名園へ行くことにする。識名園は琉球王最大の別邸で、国王一家の保養や中国皇帝の使者である冊封使の接待の場にも利用された。1799年に造営された廻遊式庭園で、池の周辺に御殿、築山、花園などを配置され、池には大小のアーチ橋が架かる。 識名園から宿泊地の那覇新都心・おもろまち方面へ向かい、平成19年(2007)に開館した沖縄県立博物館・美術館へ行き、博物館部分を見学。その後、おもろまちの沖縄DFSでレンタカーを返却し、徒歩でホテルへ向かいチェックイン。夕方、ゆいレールに乗って、県庁前のパレットくもじ4Fの那覇市歴史博物館を見学してから、小禄にある「琉球新麺 通堂」でラーメンを食べる。 3日目、ホテルをチェックアウトし、100名城に選定されている首里城を訪れるため、ゆいレールに乗って首里駅へ行く。そこからはバスも出ているのだが、時間もあるので徒歩で向かうことにする。首里城は、言うまでもなく琉球王朝の王城で、最大規模のグスク。創建年代は明らかではないが、三山時代には中山の城として用いられていたことが確認されている。尚巴志が三山を統一し琉球王朝を立てると、首里城を王家の居城として用いるようになり、同時に首里は首府として栄え、第二尚氏においても変えられることはなかった。太平洋戦争の沖縄戦で破壊され、戦後に跡地は琉球大学のキャンパスとなったが、大学移転後に復元事業が推進され、正殿はじめ様々な建物や門などが復元された。 駅から、首里城公園方面へ歩き、県立芸術大学の間を抜けていくと、その先の左手に、第二尚氏の菩提寺として建立された円覚寺跡がある。そこからさらに石垣沿いに進んでいくと、世界遺産に登録されている園比屋武御嶽石門がある。これは国王が外出するときに安全祈願をした礼拝所であり、尚真王の時代の1519年に建てられたとされている。沖縄戦で一部破壊されたが、昭和32年(1957)に復元された。 駅からは15分ほどで、インフォメーションセンターである首里杜館へ到着。パンフレットをもらってから、守礼門、歓会門、瑞泉門、漏刻門、広福門と順にくぐっていく。まだ券売所が開くまで時間があったので、系図座・用物座の中へ入る。8時20分に入場券を購入し、奉神門前で8時30分に始まる開門の儀式「御開門(うけーじょー)を見てから御庭へ入る。さすがに平日でも観光客がいっぱい。正殿は向かって左側が漆の塗り直し作業中で、シートで覆われており、景観がよくない。南殿、書院・鎖之間、正殿、北殿の中を見学してから外へ出て、西のアザナからの眺望を楽しんで、木曳門から首里杜館へ戻った。 その後、金城町の石畳道を下っていって散策する。日本の道百選に選ばれている道で、琉球石灰岩で舗装された琉球王朝時代を偲ばせる石畳道。尚真王の時代(1477〜1526)に首里城から南部への主要道路として整備されたという。NHKのドラマ「ちゅらさん」に出てくる那覇の古波蔵家の外観として使われた家もある。 再び石畳道を上り、これも世界遺産に登録されている一つである玉陵へ行く。玉陵は第二尚氏王統の歴代国王が葬られている陵墓。三代尚真王が父の尚円王を葬るために建築したもので、沖縄県最大の破風墓であり、中室、東室、西室の3つの建築物に分かれている。これも太平洋戦争で大きな被害を受け、現在見られる大部分は復元されたもの。 玉陵見学後、首里城前からバスで首里駅へ行き、そこからゆいレールで那覇空港へ向かう。那覇空港からは、13時55分発のANA306便で中部国際空港へ帰ってきた。琉球の歴史に触れる旅であった。 |