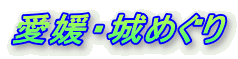
2009.7.31 〜 8.1
![]()
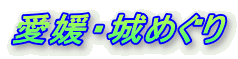
2009.7.31 〜 8.1
![]()
大阪 → 1日目 → 宇和島 → 大洲 → 松山(泊) 2日目 松山 → 今治 → 福山 → 大阪 |
今回の日本百名城めぐりは、1県で5つの城が選定されている愛媛。現存天守も2つあり、名城ぞろいである。 まずは前日の夜に大阪まで行き、そこから夜行高速バスで早朝に宇和島へ入ることとする。夜行バスは時間を有効に使うにはもってこいの交通手段。3列独立シートで、乗り心地も悪くはない。朝6時30分に宇和島バスセンターに到着。最初に目指す宇和島城の城山のすぐ下であるが、その前に宇和島駅まで歩いて特急券を買って再び城山へ戻る。 宇和島城は、藤堂高虎が慶長元年(1596)から6年を費やして築いた城で、高虎移封後、富田氏を経て伊達政宗の長男秀宗が入り明治まで続いた。本丸には、寛文6年(1666)に建てられた、層塔型の二代目天守が現存している。 城山をぐるりと回って、搦手側から、現存する上り立ち門をくぐって登っていく。代右衛門丸の下を通って、長門丸、城山郷土館の建つ藤兵衛丸から二之丸から本丸へ。小ぶりながら非常に趣のある天守が印象深い。9時の開門までまだ1時間30分以上もあるので、いろんな角度から写真を撮りまくる。城山は地元の方のウォーキングにも利用されているようで、何人もの方が本丸まで上がって来て、天守をぐるっと1周して下りていかれた。8時前から係の方が天守の中へ入り掃除を始められた。外でずっと待っていると、8時30分頃に中へ入れていただけた。貸しきり状態で天守の中を見て回る。やはり、現存天守はいい。 天守見学後、城山郷土館を見て、井戸丸を通って、桑折長屋を見たところで、列車の時間までまだしばらくあったので、もう一度搦手側へ戻り、市立伊達博物館へ向うこととする。藩主伊達家伝来の品が多数展示されている。その後、徒歩で宇和島駅へと行く。 宇和島駅からJRの特急宇和海に乗り、伊予大洲駅で下車。大洲は「伊予の小京都」と呼ばれるまちである。 駅から街を流れる肱川の方へ歩いて行くと、川越しに大洲城が見えてくる。肱川の対岸から眺める城の景色は本当にすばらしい。対岸から何枚か写真を撮って、橋を渡って天守へ向う。 大洲城は、14世紀前半に宇都宮豊房の築城とされている。その後、戸田勝隆、藤堂高虎、脇坂安治と城主が代わり、元和3年(1617)加藤貞泰が入封後、明治まで続いた。天守は明治21年(1888)に取り壊されたが、平成16年(2004)、市制50周年記念に古写真や天守雛型を基に内部まで正確に木造復元された。台所櫓、高欄櫓、苧綿櫓、三の丸南隅櫓の4つの櫓は現存している。 台所櫓から中へ入る。やはり木造で正確に復元されただけに、非常にすばらしい。肘川を渡って窓から吹き込んでくる風が非常に涼しくて心地よい。天守見学後、少し離れたところにある「お殿様公園」へ行く。ここにもう一つの現存する櫓の三の丸南隅櫓と、旧加藤家住宅主屋が建っている。この住宅は、映画「男はつらいよ」の撮影でも使われたとか。 ひと通り見学後、途中、無料の市立博物館を見てから駅へ戻る。 伊予大洲駅から再びJRの特急宇和海に乗って、松山へ向う。この日、四国地方は梅雨明けしたようで、陽射しがまぶしく暑くなってきた。 松山駅へ到着後、駅の観光案内所で一日乗車券を買って、市電に乗り、次の目的地・湯築城へ行く。道後公園駅で下車、目の前が湯築城跡。一般には湯築城というより道後公園という方が知られているのだろう。公園の中には「子規記念博物館」もある。 湯築城は、室町期以降、伊予国守護所として河野氏の伊予統治の中心となったところ。天文4年(1535)に河野弾正少弼通直が二重の堀をめぐらした堅固な城とした。現在、土塁が残り、武家屋敷や土塀、道路、排水溝などが復元されている。土塁の断面の様子が見学できる土塁展示室もある。 再び道後公園駅から市電に乗って、警察署前で下車。徒歩でロープウェイ乗り場へ行き、ロープウェイに乗って、松山城へ向う。歩いても登れるが、暑いので上りは楽をさせてもらう。 松山城へ来るのは2回目。現存12天守の一つ。ロープウェイを降りて、10分ほど歩いて天守へ向う。山上にある複雑な構成の天守群や多数の門や櫓を見るとワクワクしてくる。 松山城は、加藤嘉明が関ヶ原の戦いの戦功によって伊予を与えられ、慶長7年(1602)に築城を開始したことに始まる。現存する天守は、火災で焼失した後、嘉永5年(1852)に再建されたもので、比較的新しいもの。加藤氏の時代には城は完成せず、蒲生氏を経て松平氏の時代に完成した。 天守群の中を見て回ってから、帰りは黒門口登城道を下って、二之丸史跡庭園へ行く。中を見学し、県庁裏登城道から登り石垣を見てから、市電に乗り、宿泊のホテルへ向う。 2日目、ホテルをチェックアウトし、松山駅へ。前日に梅雨明けしたはずなのに、朝から時折雷も伴ってすごい雨である。7時22分発の普通列車で今治駅へ向うが、列車も遅れ気味である。 5分ほど遅れて今治駅へ到着。歩いても行ける距離であるが、雨が激しいので、バスに乗って今治城へ向う。今治城前のバス停で下車。 慶長7年(1602)、藤堂高虎が瀬戸内海の築城予定地に海砂をかき集めて築城を開始したのが今治城で、慶長13年(1608)に城が完成、三重の堀には海水が取り入れられていた。天守は昭和55年(1980)に、平成2年(1990)には山里櫓、平成19年(2007)には二の丸の鉄御門が復元整備された。どんどん雨が激しくなる中、雨宿りも兼ねて天守の中の展示を見学。じっくり見学したが、雨は止むことはなく、仕方なく城を後にした。 今治からの帰途をどの経路を取るかであるが、高速バスでしまなみ海道を通って、福山へ行くこととする。今治城から歩いて10分ほどで、今治桟橋のバス乗り場へ到着。そこから福山駅行きの高速バスに乗る。瀬戸内海に浮かぶ島をつなぐいくつかの橋を渡って本州へ。雨もようやく上がってきた。1時間30分ほどで福山駅前へ着いた。 ここにも100名城に選定された福山城があるので、新幹線に乗る前に見学していくこととする。城は駅北口の目の前にある。おそらく一番駅から近い城ではなかろうか。福山城は、水野勝成が元和5年(1619)に入封し築いた。徳川幕府の西国経営の拠点としての重要な位置づけを与えられた。京都の伏見城から移築されたとされる伏見櫓が現存している。天守は五重六階地下一階の層塔型で北面の外壁が鉄板で覆われていたというが、昭和20年(1945)の空襲で焼失した。現在の天守は昭和41年(1966)に鉄筋コンクリートで再建されたもので、福山城博物館となっている。 外観の写真を撮ってから博物館の中を見学。鏡櫓や月見櫓、鐘櫓などを見て回り、現存する筋鉄御門、伏見櫓を見てから駅へ戻った。新幹線のホームからも写真を撮る。伏見櫓の写真を撮るには、ホームからが一番。 福山駅からは新大阪駅まで、JR西日本の「ひかりレールスター」に乗る。2列×2列のグリーン車並みのゆったりしたシートで乗り心地は最高。 |