![]()
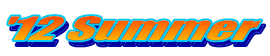 2012.7.6 〜 7.8 |
![]()
1日目 中部国際空港 → 函館空港 → 五稜郭 → 函館 (泊) 2日目 函館 → 江差 → 上ノ国 → 北斗 → 函館(泊) 3日目 函館空港 → 中部国際空港 |
本格的に城めぐりをするようになって訪れる機会が少なくなっていた北海道へ久しぶりに渡る。でも中心は道南の城郭。 中部国際空港8:00発のANA391便で函館空港へ。空港到着後、函館バスの路線バス「とびっこ」に乗ってまずは五稜郭を目指す。五稜郭公園入口のバス停で下車し、そこから歩いて向かう。 五稜郭自体は4回目の訪問。今回は、前回訪れた時はまだ復元工事中であった箱館奉行所へ入るのが一番の目的。隅々までたっぷりと時間をかけて見学。最後はやはり五稜郭タワーからの眺めを楽しむ。 五稜郭の見学を終え、まだホテルのチェックインまでは時間があるので、市電に乗って函館駅の方へ向かう。松風町の「滋養軒」で遅めの昼食に塩ラーメンを食べてから、ベイエリアの赤レンガ倉庫群の方までぶらぶらと歩いていく。 赤レンガ倉庫は、明治末期に商港函館の最初の営業倉庫として建造されたもので、現在は、クラシカルなレンガ造りの倉庫群が、ビアホールやレストラン、ショッピングモールなどとして再利用されていて、函館のウォーターフロントのシンボルとなっている。 赤レンガ倉庫群を見て回った後は、そのまま元町の方まで行ってみる。 元町地区は、江戸時代から箱館奉行所が置かれ行政の中心地と位置付けられていたところで、各国の領事館や近代的な洋館、また、西洋文化の象徴とも言える教会などが建ち並ぶ。また、多くの坂道があり、そこからの景色もすばらしい。 この後は、末広町の電停から市電に乗り松風町まで移動してホテルにチェックイン。1日目は終了。 2日目、朝から予約しておいたレンタカーで出発。函館駅前からスタートし、国道227号で江差方面を目指す。江差へ入って日本海へ突き当たり、海沿いを走っていくと、大きな帆船が見えてくる。本来の目的地へ行く前にちょっと寄り道したのは、開陽丸青少年センター。ここには、幕末の徳川幕府の軍艦で、慶応4年(1868)に暴風雪のため江差沖で沈没した「開陽丸」が実物大で復元されている。 開陽丸を見学してから車を上ノ国町へ走らせ向かったのは、今回の一番の目的であった上ノ国勝山館跡。 勝山館は、後の松前氏の祖となる武田信広が、1470年頃に築いたといわれる山城であり、16世紀末頃まで武田(蠣崎)氏の日本海側での政治・軍事・北方交易の一大拠点であったところ。康正3年(1457)に起こった「コシャマインの戦い」で、武田信広はアイヌの首領コシャマイン父子の首も討ち取り、その功績により、蠣崎氏の跡を継いで、勝山館を築いたという。館は、夷王山の中腹、日本海を見下ろすことができる、宮ノ沢と寺ノ沢に挟まれた広い尾根上にあり、三段の大きな平地となっている。現在は、国指定史跡としてきれいに整備され、ガイダンス施設も建っている。 勝山館跡の見学を終え、もう一度国道227号を走って北斗市まで戻る。次に向かったのは、これも国指定史跡となっている松前藩戸切地陣屋跡。戸切地陣屋は、安政2年(1855)、蝦夷地全域を直轄領とした幕府が、外国船に対する警備のため、松前藩に命じて築造させた西洋式築城法による陣屋。その形状は、四稜郭となる稜堡式築城で、東側の稜堡が突出して築かれており、そこに6基の砲座が配置されている。明治元年(1868)、榎本武揚ら旧幕府脱走軍が鷲ノ木に上陸し、陣屋を守備していた松前藩兵は大野付近で会戦するが撃破され陣屋に退却。さらに陣屋への追撃を受け、陣屋守備隊は自ら陣屋に火を放ち、松前と箱館へ退却したという。国指定史跡としてきれいに整備がなされており、見事な土塁や空堀などを見ることができる。 戸切地陣屋跡から函館市内へ戻り、次に向かったのは陣川町にある四稜郭跡。これまた国指定史跡。 四稜郭は、明治元年(1868)12月、五稜郭に蝦夷共和国を樹立した榎本武揚ら旧幕府脱走軍が、翌明治2年(1869)3月、新政府軍の攻撃に備えて背後を固めるため、五稜郭の北方約3kmの丘陵地に築いた洋式の台場で、士卒約200名、付近の村民約100名を動員して、わずか数日で完成させたといわれる。東西約100m、南北約70mの範囲内に築かれた蝶が羽を広げたような形の稜堡で、周囲に土塁と空壕を巡らせ、四隅に砲座が設けられたが、建物は造られなかったという。明治2年(1869)5月11日、新政府軍の箱館総攻撃が開始され、四稜郭と五稜郭の間に位置する権現台場を占領されると、旧幕府脱走軍は退路を断たれることを恐れ、数時間の戦闘の末、五稜郭へ敗走したという。 四稜郭跡から車を函館空港方面へ走らせ、この日最後に向かったのは志苔館跡。 志苔館は、一説によると室町時代の領主であった小林重弘によって築かれたといい、道南12館のの一つであった。コシャマインの戦いで康正3年(1457)5月14日、アイヌ軍に攻め落とされるが、その後、武田信広がコシャマイン父子を討ったことにより、小林良定が志苔館を回復して館主となった。これ以降も、アイヌと和人の戦いは続き、永正9年(1512)には東部アイヌの首長であったショヤ・コウジ兄弟が蜂起し、この戦いで志苔館は再び襲撃されて陥落し、館主・小林良定は討死した。その後、小林氏は松前に移住して蠣崎氏に従属したため、志苔館は廃館となった。館跡は、函館市の中心部から約9km離れた函館空港のすぐ南側の標高25m程の海岸段丘南端部に位置しており、東西70〜80m、南北50〜65mのほぼ長方形の形で、四方は土塁で囲まれ、その外側には壕が巡らされている。ここも、昭和9年(1934)に国史跡に指定されている。 充実の4城を巡り、この日の予定は終了。函館駅前でレンタカーを返却し、ホテルへ戻る。 3日目は、飛行機が午前の便であるため帰るだけ。ホテルから歩いて函館駅へ行き、駅前から空港行きのバスに乗って函館空港へ。10:00発のANA392便で中部国際空港へ帰ってきた。 |