
3−Dお月見!
対象年齢:3-D画像の制作は,中学生以上。ちょっとパソコンや写真のテクニックが必要です。
おとながデモンストレーションすれば,小学校中学年ぐらいからOK!
旧暦の8月15日は仲秋の名月…「十五夜」。
旧暦の9月13日は後の月…「十三夜」。
まぁるいお月さまを見ることができます。
むかしの人は,どんな気持ちで月を見ていたのでしょう?
あんまりメカを使わない観察をしてみましょう。
それから,「現代風」の観察もひとつ。
カメラとパソコンで,月の3-D(立体)写真を作ってみましょう。
文字通り,「月を立体的に観察する」お月見です。
1)むかしの人の観察をやってみよう
【用意するもの】
特に用意するものはありませんが,双眼鏡があるとべんりです。
月面図や月齢のわかるデータブックなど(「天文年鑑」:誠文堂新光社 など)があると,もっとわかりやすい。
【観察しよう】
観察する日は,満月に近い日を選びます。月齢で言うと,12〜16ぐらい。小さい子は,おそくまで起きてると眠くなっちゃうので,早めの月齢を選んで,手早く観察しましょう。
月齢や月の出る時刻は,新聞などに出ています。
さぁ,月のもようを見てみましょう。

月の黒っぽいところは,「海」と呼んでいますが,月には水はありません。月の「海」は,クレーターの少ない,たいらな場所なのです。
むかしの人は,月のもようを見て,いろいろなものを考えました。日本では,「うさぎのもちつき」と言われていますが,どんなかたちに見えますか?
外国でも,月のもようを見て,いろいろなかたちを想像しています。
ちょっと紹介しましょう。
 |
おなじみの,ウサギのもちつき。 日本では,こんなふうに見ます。 |
 |
カニ。片方のハサミが大きい。 |
 |
本を読む少女。 右のほうが頭で, ロングスカートをはいています。 読書の秋? |
 |
女性の横顔。 黒い部分を髪,目,口に見立てたものです。 日本人離れした顔? …そりゃ,日本人の発想じゃないから…。 |
2)月の3−D写真を作ってみよう
ちょっとしたアイデアで,月がボールのように見える,3-D(立体)写真が作れます。
ぜひ,挑戦してみてください。
【用意するもの】
望遠レンズのついたカメラ;一眼レフカメラが使いやすい。なるべく300mm以上の望遠が欲しいのですが,なければ,双眼鏡とカメラを組み合わせて,望遠撮影することもできます。デジタルカメラで撮影すれば,画像の加工が簡単です。
デジタル処理をする場合,パソコンや画像処理ソフト,必要に応じてスキャナなど。
【やってみよう】
まず,月の写真を撮影しなくてはいけません。
月の撮影テクニックを簡単に紹介しましょう。
月はレンズの焦点距離の1/110ぐらいのサイズで,フィルムに写ります。月の模様が見える程度に大きく撮るためには,最低でも300mm,できれば600〜2000mmぐらいのレンズが必要です。望遠レンズにテレコンをつけても構いませんが,双眼鏡や望遠鏡があったら,接眼レンズの後ろにカメラのレンズをぴったりくっつけて,撮影することもできます。カメラのレンズの焦点距離に,双眼鏡や望遠鏡の倍率をかけた値が,合成して得られた焦点距離になります。カメラのピントは無限大,絞りは開放にし,双眼鏡(望遠鏡)でピントを合わせ,露出を変えて何枚も撮影しておきます。撮影するときは,三脚などで撮影機材を固定したほうが,楽に撮影できます。
最近は,超望遠機能のあるデジカメも出ていますので,それを使えば,簡単に月の写真が撮れます。デジタルビデオカメラで撮影し,スチル画像を取り出してきてもいいでしょう。デジカメやデジタルビデオの場合,自動露出に頼ると,露出オーバーになります。マニュアルでいろいろと調整してみてください。
デジカメで月を写すノウハウは,別館の「お気楽天体写真工房」で,もっと詳しく解説しています。
月の撮影ができるようになったら,いよいよ3-Dの原画を撮影します。
おおよそ,月の南中時刻の2時間前と2時間後に,できる限り同じ条件で撮影します。
デジタル機器で撮影した場合,すぐに結果が見え,撮影後にアングルや色調の調整をするのも簡単です。こうして,数時間の時間差のある,同じような形の画像を作ります。
これを立体的に見るときに,いちばん簡単なのは「裸眼立体視」でしょう。
先に撮影した画像を右眼,あとに撮影した画像を左眼で見ます。
「平行法」で見る場合,左右の月の画像は,5〜5.5cmほどずらして置きます。
以下に作例を出しておきます。
左の画像は左眼,右の画像は右眼で見てください(つまり,平行法で見ます)。
左右の月の中心を結んだ距離が5〜5.5cmになるように,パソコンのモニタを調整してください。
調整が難しい場合は,画像を一旦ダウンロードし,適当にレイアウトしてプリントアウトしたものを使うといいでしょう。
左右の眼で見た像が一致すると,月が,数m離れた場所から見たボールのように,立体的に見えてきます。
 |
 |
もっと3−D写真を見てみたい人は,別館の「ステレオ月面写真」へ!
【でも,どうして?】
(ちょっとくわしい説明)
私たちはどうして,ものが立体的に見えるのでしょう?近くにあるものを,片目ずつ眼をつぶって,左眼で見た映像と右眼で見た映像を比べてみましょう。左右の映像には,微妙なズレがあります。これは,左右の目で見る角度が違うために起こるのです。この角度のズレを「視差」と言い,この微妙な違いを脳の中で処理して,立体感を認識しているのです。
さて,月は地球から38万kmぐらい離れていますから,人間の目では,左右の「視差」を作るのは困難です。そこで,地球に視差を作ってもらうことにします。
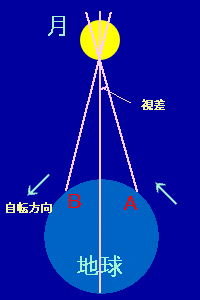 |
[視差が作れる理由] これは,地球を北極のほうから見た図です。 Aの地点で月を撮影し,何時間か後に,もういちど月を撮影します。 すると,地球は自転しているので,Bの位置から月を見ることになります。 つまり,A地点とB地点では,すこしだけ違う角度から月を見ることができ るのです。この角度の差が「視差」となるわけです。 |
地球は自転していますから,たとえば北緯35度の場所で,月の南中時刻の2時間前と2時間後では,私たちのいる場所は,約5000kmも移動しています。この4時間の間に,月はほとんど変わらずに,地球の方を向いているので,地球の自転による移動距離を「視差」として使えます。いわば,左眼と右眼の距離を,5000kmに広げてやったわけです。これなら,38万km離れた月も,数m先にあるボールを見るような感じで,立体視が出来るわけです。