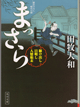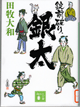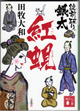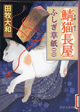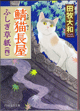|
「まっさら−駆け出し目明し人情始末−」 ★★☆ |
|
|
|
上手いなぁ、本当に上手い! 主人公を始め、登場人物たち各々の人物造形がすごく良い。そのうえ、真っすぐなミステリと思いきやその背後にはもっと深刻な疑惑があったという複層構成。そして最後には、清濁合わせ大きく呑みこんでしまうような広がりある結末。 文庫書下ろしというのは余りに勿体ない、と思う次第。 つい1年前まで掏摸を生業としてきた六松、十手持ちにしては珍しく清廉潔白な人物という評判をとる“稲荷の紋蔵”に見こまれてその手下に。1年におよぶ見習い期間を経てようやく一人住まいを許されます。 ところが、六松が住むことになった根来長屋で亀吉という住人が溺死。何故かその弔い一切が六松に押し付けられます。 何らかの事情があるらしいのですが、どうも六松はその事情から遠ざけられているらしい。 そこから六松は、初めて自力でその謎に立ち向かうことになります。 その六松の口癖は「真っ平、真っ新(まっさら)」。以前の生業はすっかり忘れ去り、目明しの手下として精進し、新しい真っ当な人間になるという決意を自分に戒めるための言葉です。 いうなれば、六松を主人公にした時代もの青春&成長・再生ストーリィ+ミステリという趣向。 終盤、新たに六松の眼前に立ち塞がった謎には、六松だけでなく読み手まで引きずり込まれ、ついつい不安を感じさせられてしまう処がお見事。 ※再び会いたい登場人物(紋蔵、千枝、新助、おみつ等々)ばかりですが、田牧大和さん、これまでも簡単に折角の作品を単発で終わりにしてきています。さて、本作品についてはどうなのでしょう? 続編を是非期待したい処です。 事の始め壱/事の始め弐/1.亀吉/2.久太と庄次/3.貫平/4.佳江/結び |