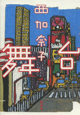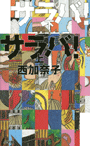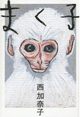|
●「きりこについて」● ★★ |
|
|
2011年10月
|
きりこはとびっきりぶすな女の子でしたが、赤ん坊の頃から両親が愛情たっぷりに「可愛いなぁ、きりこちゃんは」と繰り返し言っていたものだから、自分はとりわけ可愛い女の子であると信じ込んで生きてきた。 ところがある日・・・・、きりこの人生を変えたその一言をきっかけに、学校へ行くのを止め、愛する黒猫のラムセス2世とともに家に閉じこもってしまう。 それから数年後、予知夢をみたきりこは、夢の中で泣いていた女性を救うため、ラムセス2世に付き添われて再び足を外へ踏み出します。 そんなきりこが、紆余曲折を経て、人生における真実を見つけ出すまでを描いたストーリィ。 ぶすな女の子と黒猫という取り合わせから児童向け小説を予想したのですが、コミカルでヘンな少女時代が描かれたかと思えば、その後は一転してファンタジー小説のヒロインのごとき様相を纏ったかと思えば、最後はやっぱりきりこのビルディングスロマンのようにして終わる、という、読んでいるその先の展開が全く予想つかない、面喰い続けるというストーリィ。 これは児童向け小説なのだろうか、大人向け小説なのだろうかと迷わされつつ、読み手の予想に反し続ける展開に翻弄されながら読み進んだ先には、何だか判らないけれど愉快で楽しそうな広場が広がっていた、というよう読み心地。 悪戯心溢れるストーリィ展開がお好きな方に、是非お薦め。 |