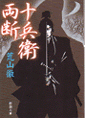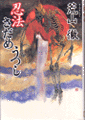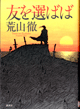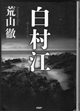|
高麗軍が対馬、壱岐で繰り広げた島民虐殺、それへの報復として繰り返された倭寇。
そんな朝鮮と日本の歴史を背景に高麗と倭国の攻防を描いた伝奇歴史小説4篇。
「以蒙攻倭」は、元朝の使節団が北条時宗をいきなり襲うところから始まります。
元に倭国を侵略させ、自らの利を得ようとする高麗の陰謀。その手先となった丹術(忍術)遣いと対決し高麗の陰謀を挫くべく、高麗国にただ2人上陸した日本武士と少女がいた。
ストーリィ展開も背後にある歴史も面白く、すんなりと楽しめた一篇。
それに対し「忍法さだめうつし」とその続編「怪異高麗亀趺」は奇想天外の度が大きく、私の好みを越えてしまった感じ。
この2篇、呪術もしくは忍法、それにエロティックな要素が絡む分、山田風太郎を髣髴させてくれます。とくに後者は、タイムマシンが出てくるばかりかガメラまで登場(モスラに次いで今度はガメラかよ!)するのですから、なんともはや。
その空想の飛躍ぶり、山田風太郎に伍して譲らずといった荒山さんの意気込みを感じます。
日本史における外国との交流というと頭に浮かべてしまう相手はとかく中国なのですが、日本と朝鮮の間にこれ程濃密な関わり合いがあったのかと、頭にガツンと一撃!してくれる歴史小説。そこにこそ、本書を読む甲斐があるというもの。
最後の「対馬はおれのもの」は、対馬侵略に執念を燃やす父王に反旗を翻し、親日に国論を転回させた李氏朝鮮第4代世宗を描いた一篇。改めて日朝近代史を知ったという、感動が残りました。
そんな日朝の歴史にもかかわらず、明治の世に日本が朝鮮国を蹂躙するような侵略を行なった歴史に強い痛みを感じます。(※角田房子「閔妃暗殺」)
※なお世宗=李祹は、日本の平仮名に倣ってハングル文字を創製したという不滅の功績を残した王、とのこと。
以蒙攻倭/忍法さだめうつし/怪異高麗亀趺/対馬はおれのもの
|