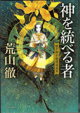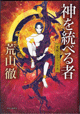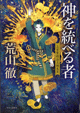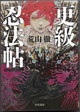| 11. | |
|
「神を統べる者−厩戸御子倭国追放篇−」 ★★ |
|
|
2021年02月
|
少年・厩戸御子(後の聖徳太子)を主人公とし、日本〜中国〜天竺(インド)にまで舞台を広げる、長大な歴史物語シリーズの幕あけの巻。 まず冒頭、厩戸御子はまだ7歳。しかし、既に百済語・漢語を自在に読み書きし、数多くの仏教経典を読んでいたばかりか全て諳んじているという、類まれな才能を発揮していた。 時代は崇仏派の蘇我馬子と、廃仏派の物部守屋が凌ぎを削っていた時代。その中で厩戸御子は、仏教の真実を知ろうとあらゆる仏教経典を読み漁っていた訳ですが、そんな厩戸御子の異能ぶりを危険視したのが現帝である敏達天皇。 仏教を敵視する敏達天皇は、伊勢神宮からの神託を理由に、厩戸御子の暗殺を謀ろうとします。 厩戸御子の才能に期待をかける物部守屋は、主張の差を超えて蘇我馬子と共闘し、厩戸御子を大和から脱出させます。 護衛を命じられて御子に同行するのは、守屋配下の女性剣士=柚蔓(ゆずる)と、馬子配下の剣士=虎杖(いたどり)。 想像力を発揮しての広大なストーリィとはいっても、荒山徹さんらしいのは、禍霊が登場したり、果てはゾンビまで登場。 とはいっても所詮本巻は、幕開けのストーリィ。 異能を発揮する厩戸御子に、男女2人の護衛剣士という組み合わせ。そして、日本古来の女神が登場するかと思えば、ゾンビまで登場。さらにインド人修行僧、道教の道士まで登場し、これからの破天荒な面白さを十分期待させてくれます。 いったいどれだけ長い物語になるのかと畏れつつも、今後の展開が楽しみです。 仏教の是非をいろいろな人物をして語らせているところも、十分面白いですし。 第一部 大和/第二部 筑紫/第三部 揚州 |