
|
| |||

|
| |||
|
第2楽章概説 |
●スターリンの肖像
時間にすると4分弱だが、テンポが早いため音符数の多い楽章。すごい勢いで演奏されるこの嵐のような無窮動スケルツォは「証言」の中で「スターリンの肖像」と表現されて以来、そのイメージを拭い去ることが難しい。この楽章の第一主題とファンファーレに見られるその要因を以下に3つあげる。第一主題が、ショスタコーヴィチが最も共感していた作曲家、ムソルグスキーの歌劇「ボリス・ゴドノフ」の出だしの音型を連想させる点、この楽章を通じてSBCに含まれDSCHにはない
B 音が重要な役割を果たす点も見逃せない。
第一主題
|
|
|
|
ムソルグスキ「ボリス・ゴドノフ」プロローグ冒頭
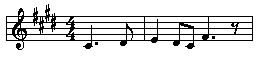 「ボリス・ゴドノフ」はプーシキン原作の民衆と皇帝の物語。冒頭は愚かな民衆が皇帝に操られる有り様を描く。 |
mid |
“スターリン”のファンファーレ
軍隊を思わせるクレッシェンドのかかった小太鼓に続いてティンパニがB音でリズムを刻み、その上にトランペットとトロンボーンとチューバによって奏される。
交響曲第10番第2楽章より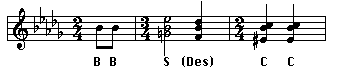 |
mid |
|
交響曲第7番第1楽章中間部 いわゆる「侵入」の動機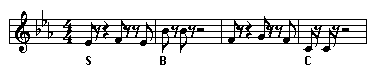 |
mid |
リズムが“ファンファーレ”と酷似。
|
●テンポの謎
| 楽譜のテンポは二分音符=176であるが、これはほとんど演奏不可能である。死後刊行され、多くの音楽学者がその仕事に携わっ た旧ソ連時代の全集版においても訂正されていないことからすると、これは印刷ミスではなく意図的な「演奏不可能な速さで」という指定と思える。 |
mid(二分音符=176) |
テンポ変化のない楽章なので演奏時間と速度を計算するのは簡単。356節のうち7小節が3/4、あとは全て2/4なので二分音符=176 では、2分強となる。手元の CD を調べると、一番遅いインバルが4:38、ロジデストヴェンスキ が4:20前後(複数)、コンドラシンが4:06、ヤルヴィとハイティンクが4:03 であり、指定のテンポのほぼ倍遅い。これらの指揮者は「四分音符=176の印刷ミス」という解釈なのだろうか。初演したムラヴィンスキ のCD(初演から2年後の1955の演奏)では3:48(四分音符=189 に相当)。これは「四分音符=176の印刷ミス」という解釈とは思えず、初演の前に聞いたショスタコーヴィチとワインベルクのピアノ演奏(その二人の録音したCDでは3:40、すなわち四分音符=196)を念頭に置いているものと考えられる。
トリオの部分も大きな気分の変化はなく、演奏を突然止めたような終結部まで一気に進む。スケルツォ主部後半に新たな素材があらわれるため、A B Trio A Coda の形。
|
71 |
主部 前半 |
短三和音の2つの打撃で開始し、全曲のモチーフである全音・半音の順次進行が(これも2回)それに続く。せき立てるような低音部の動きの上に、木管がやはり順次進行で始まる第一主題を高音で叫ぶ。 |
|
75 |
主部 後半 |
軍隊を思わせるクレッシェンドのかかった小太鼓に続いてティンパニがB音でリズムを刻み、その上にトランペットとトロンボーンとチューバによるぶっきらぼうなファンファーレが現れると、木管楽器群が慌てふためくように(パッパラのリズム)高音で金切り声を上げる。クレッシェンドにつぐクレッシェンド、ティンパニはずっとBの音を叩き続け、木管群はどんどん音が高くなって最後にはパニック状態に陥る。(実に見事な情景描写だと思う。) |
|
79 |
トリオ | ここで金管楽器とティンパニはときどきsfffの短い和音の一撃を挟むだけである。にもかかわらず、吹雪のような弦楽器に続いて木管楽器群は右往左往し、だんだんテンションを上げていき、最後にはまたしてもパニックに陥る。 |
|
86 |
再現部 | 拡大した第一主題が威嚇的に響き、クレッシェンドするティンパニ のB音のトレモロがそれを強調する。ついには木管群も拡大した第1主題をいっしょに吹き鳴らす。 ティンパニのB音2回強打に続き、拡大されたファンファーレも木管群を伴って再現する。 |
|
94 |
コーダ | 弦楽器から始まるパッパラのリズムが木管楽器に広がり、小太鼓 に続いて金管が加わり打楽器が増強されて凄い勢いになるが突然終わる。 |
| Copyright (C) 2001 kinton, All Rights Reserved. |