
|
| |||

|
| |||
|
第一楽章概説 |
●旋法と歌と踊りの3つの主題
3つの主題がソナタ形式にそって組み合わされ弓形のドラマを作る。 思索的な暗さと哀歌と皮肉な調子という3つの特徴は、第十番のみならずショスタコーヴィチの音楽の特徴ともいえる。
交響曲第10番第1楽章冒頭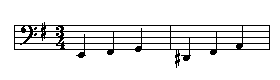 |
mid |
EF#G|D#F#Aと上昇する3つの音2組からなる。直後に総休止を伴い、(ベートーヴェンの第五番同様)はっきりと提示される。チャイコフスキー「悲愴」、ムソルグスキー「ボリス・ゴドノフ」それぞれの冒頭を想起する。 |
全体として大変良く似たモチーフがムーソルグスキの歌曲「太陽なく」第6曲の「河にて」の伴奏に3回出てくる。またリスト「ファウスト交響曲」との影響も指摘されている。
リスト「ファウスト交響曲」冒頭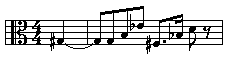 |
mid |
ファウストの哲学的性格を反映しているといわれる。 |
ムソルグスキ「河にて」より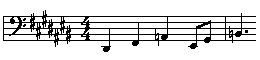 |
mid |
「河にて」は歌曲集「太陽なく」の第6曲。「未知の声が聞こえてくるのだ」に続く3つの疑問文、(この声は)「聞けと命じているのだろうか?」「ここから追い払おうというのか?」「深みへと呼んでいるのか?」の伴奏音型 |
出だしの4小節はマーラーの「原光」のアルトによる歌い出しの部分の引用。(「原光」は「子供の魔法の角笛」による歌曲の1つであり、交響曲第ニ番「復活」の第四楽章。)
交響曲第10番第1楽章第1主題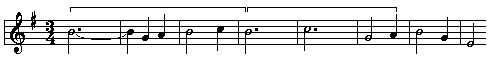 「原光」引用、さらに続く部分も十字架音型。 |
||
マーラー「原光」(交響曲第2番第4楽章)より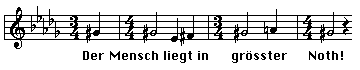 |
mid |
|
| 「子供の魔法の角笛」による歌曲の1つ。アルトによって「人間は窮乏のきわみにある。人間は苦悩のきわみにある。」と歌いだされる部分。十字架音型の旋律であり、記譜も(バッハのように)わざわざシャープとナチュラルをつけてそのことを強調している。第五楽章で「復活」する前の第四楽章で「十字架」に架けられていると思われる。 | ||
ジグザグに下降する形(死を暗示する Dies Irae の変型)の旋律を同音反復で刻む八分音符のリズムが特徴のピチカートの伴奏がついたワルツ。しかし、楽し気でも優雅でもなく、乾いた皮肉な調子に聞こえる。
交響曲第10番第1楽章第2主題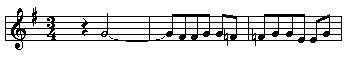 |
mid |
|
第1楽章 Moderato 弓形のソナタ形式 |
全音楽譜出版者の楽譜(4-11-891802-1)での練習番号Nの第m小節めを N.m の形式で示す。
| (約2分半) | 呈示部 |
|
||
|
5 (約4分) |
この部分だけでも一種の弓形をなす。
|
|||
| 17 | ||||
|
29 (約7分) |
展開部 |
非常に訴える力の強い音楽である。
|
||
| 47 | 再現部 | 興奮の頂点で基本動機が再現する。しだいに静まっていく(ここでやっと再現部に達していることに気付く)。しだいに興奮を冷ましながら始めの思索的な気分に戻っていく。呈示部同様コラール(55)に続いてクラリネットの独奏があらわれる(56)が、弦が加わらずクラリネットのみであるため、より虚ろに響く。 | ||
| 57 | 死のワルツはフルートではなく(3度音程の)2本のクラリネットで奏される。 | |||
| 65 | コーダ | 基本動機と哀歌が弱音で奏された後、寂寥感に溢れる2本のピッコロの音色が楽章を締めくくる。(映画「リア王」や「乱」の最後の場面を連想してしまう。戦いの後の空しさを感じる。) |
| Copyright (C) 2000,2001 kinton, All Rights Reserved. |