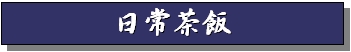
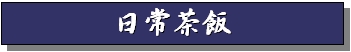
|
月の英語名 英語の九月(September)は七番目の月を意味し、 十月(October)は八番目、十一月(November)は九番目、 そして十二月(December)は十番目の月であることは綴(つづ)りから察しがつく。 月の英語名は、ラテン語に由来する。 特に九月から十二月はラテン語の綴りそのままである。 七月はローマの英雄・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)の誕生月で、 ラテン語ではIulius、英語はJulyである。 そして八月(August)は、初代ローマ皇帝アウグストゥスを記念しての呼称である。 さて、一番目の月に当たる三月(March)は、軍神マルスに語源を持つ。 閏年の二月は、三月が第一月であった時代に二月は最後の月に当たるので、 この月に閏年の日数調整を行なっていた名残である。 一月(January)は、戦いの守り神、ヤヌス神を語源とするといわれている。 ヤヌス神は、前と後を向いた二つの頭を持つ像で描かれる。 古代ローマでは、ヤヌス神殿の出入り口の扉は戦時には開け放たれ、平和の時には閉ざされていたという。 明日から七月である。歳月は勝手に来て勝手に去って行く。 |
|
|
御馳走帖 ・ 後口上 御馳走帖とは、私がいつも美味しいものを食べているということではなくて、 今までに美味しいと思ったものを思い出して書いて並べてみようという趣向である。 勿論、思い出そうとしてもすぐに出てくるとは限らないので、 自然に思い出した時に書こうと思うから、不定期に綴ることになるだろう。 或は新しく食べたものを書いてみようとも思うが、食べ物は出尽くしていると思うからあまり期待できない。 つまり、このページをなるべく長く継続させるために、その様な義理はないが、レパートリーをひとつ増やしてやろうという私の魂胆なのである。 タイトルは、内田百閒の「御馳走帖」(中公文庫)から拝借した。 この随筆集の面白さや味わいについては、既にいろいろな人が書いているので、私の出る幕ではない。 ただし、幾つかお薦めの作品を挙げておきたい。 「饗応」、「百鬼園日暦」、「養生訓」や「一本七勺」など。 「饗応」は僅か3頁程度である。 本屋で立ち読みされることをお薦めする。 出来れば走り読みせずに、一字一句読んでみれば味わいがわかると思う。 北大路魯山人のような美食家の本ではない。 お酒好きで、禁酒も節酒もせずに長生きしたいと願う人には、一読の価値はあるかもしれない。 勿論嘘を云うつもりはないが、真顔で云うつもりもない。 役に立たない話が、百閒先生の味なのである。 何しろ、おからを肴にシャンパンを飲むような人なのだから。 |
|
|
御馳走帖 ・ サクランボ 先日、サクランボを貰(もら)った。 サクランボは桜桃ともいうが、今が旬のくだものである。 山形産の佐藤錦だそうで、たいへん美味しかった。 ただし、その美味しさには季節ものの有難さも含まれている。 近年、くだものの季節感がなくなったという人がいるが、それは心得違いである。 近年どころの話ではない、六十年以上前からなのだ。 高島俊男さんの「お言葉ですが…④」(文春文庫)の中に昭和十五年の、 雪の降る寒い日に新宿を歩いていたら、くだもの屋でスイカを売っていたと、 季節感の喪失を嘆いた随筆の引用がある。 電気冷蔵庫がはじめて発売されたのは戦前だという。 需要は軍や業務用で、値段は土地家屋一軒分に相当したらしく、 世間では知られていなかったようである。 だから、当時すでに季節外れのくだものは可能だったのだ。 佐藤錦のサクランボは、百貨店にもスーパーにも置いてあるが、値段はかなり違う。 百貨店にある綺麗に並んだ手詰め品は、大きさの揃った粒を一粒一粒選び、 詰めるための手間賃が入っているらしく、味に違いはないという。 今の時季にしか出回らないサクランボは、季節を感じさせる御馳走である。 |
|
|
御馳走帖 ・ 薬味 料理にそえる薬味(やくみ)は、脇役のようでいてそうではないところがある。 葱(ネギ)、山葵(ワサビ)、生姜(ショウガ)、唐辛子、芥子(カラシ)、柚(ユズ)、三つ葉、浅葱(アサツキ)、 分葱(ワケギ)、紫蘇(シソ)に胡麻(ゴマ)、まだあるが、それぞれにそえるべき料理がある。 うっかり薬味を切らして、折角の御馳走(ごちそう)が台無しになることがある。 鰻(ウナギ)の蒲焼きには、山椒(サンショウ)がつきものである。 山椒を味わうために鰻を食べているように思えることがある。 鱧(ハモ)落としは、梅肉でいただくのが美味しい。 鱧を骨きりし湯引きにしたあと氷水で絞めたもので、今が旬である。 牛のたたきやローストビーフには、ホースラディッシュ(西洋ワサビ)がよく合う。 最近では、チューブ入りのものが現れて、スーパーで簡単に手に入れることが出来るようになった。 豚のヒレ肉を一口大に切りカツに揚げたものに、ウスターソースをかけても良い。 しかし、矢張り大根おろしをそえて、土佐醤油で食べるのが遥かに美味しい。 近頃は、たこ焼きにソースとマヨネーズをかけるのが流行(はや)っているようだが、 昔ながらのだし醤油で、マヨネーズはつけいない方が矢っ張り旨い。 |
|
|
電池が切れるまで・最終話 昨夜の木曜ドラマ「電池が切れるまで・最終話」はよかった。 骨髄移植の手術を受けた少女・薫が、クリーンルームの中で次第に衰弱し、髪が抜けていく様子を巧(たくみ)に演出していた。 なにより舞台の安曇野(あずみの)の北アルプスの山々を背景にした風景が美しい。 安曇野ならではの道祖神巡りのシーンも良かった。 クリーンルームの中の薫をガラス越しに見守る父親が、 インターフォンを使わずに娘に語りかけるところは印象的だった。 医療ドラマは、医師が治療する過程や患者の容態の変化を丁寧に描くことで、それだけで良いドラマになる。 アメリカのテレビドラマ「ER(緊急救命室)」は、シカゴを舞台にした架空の病院の話である。 監督がふたりいて、ひとりは現役の医師だという。 どうりで、リアリティがあるはずだ。 医師が実際に現場で行うこと言うことを、役者に口移しに演技指導するそうだ。 ところが、私の知り合いのお医者さんは、「ER」を見ると疲れて嫌だと言う。 治療法や薬の処方にばかりに目がいって、次の処置や患者の経過が気になって、 そのうちドラマは先の方に行ってしまい置いてきぼりを食って、ストレスが堪るそうだ。 よっぽど、日本のドラマの方が笑えて面白いと仰る。 そんなことしたら患者さんは死んでしまうよ。思わず言いたくなるドラマが多いとか。 |
|
|
オイチニの薬屋さん 先日、黒澤明の『まあだだよ』を見ていたら、「オイチニの薬は日本一、オイチニの薬を買いなさい、 …」と節をつけた歌に合わせて威勢良く楽しそうに、 オイチニ、オイチニとビアホール内を行進するシーンがある。 この映画のヤマ場の一コマで、名場面のひとつである。 後になって、その「オイチニ、オイチニ」が気に掛ってきた。 聞いた覚えはない。 フレーズに引っ掛かって、聞いた覚えがなければ文字で見たような気もするがはっきりとしない。 どこかで読んだのかもしれない。 昨晩寝る前に、内田百閒の随筆集を何冊か引っ張り出して、頁を捲って探してみた。 映画で丁度その場面を描いた原作である随筆「摩阿陀会」の中にあった。引いてみると、 私の高等小学校時分に、(中略)手風琴がはやり出した。 初めは家庭に這(は)入ったのだが、じきに富山の薬売りや、オイチニ館の行商が、 「そのまた薬の効能は、オイチニ、溜飲、胃病に、腹くだし、オイチニ」と歌って行く合い間の伴奏になって、云々(うんぬん) とあり、薬の行商のことであった。 また、別の随筆「きょうの瀬」からも引いてみる。 その薬屋は、僕は漫然と富山かと思っていたが、そうではなく本舗は大阪だったのかもしれない。 オイチニ館と云うので、そこから全国に薬売りを出して行商させた。 制服制帽に手風琴を持って、歌に合わして鳴らしながら、オイチニ、オイチニと足拍子を踏んで行く。 歌に曰く、 そのまた薬の効能はオイチニそこで僕には新作がある。 神経衰弱房事過度オイチニ、どうかゆっくり御鑑賞を願う。その間(かん)僕はこれにてお祝いの御酒(ごしゅ)を頂戴する。 手風琴とは、今のアコーディオンである。 おそらく薬売りが現れると、子どもたちが、 歌いながらオイチニ、オイチニと足拍子を踏んで後からついてきたのだろう。 オイチニの薬屋さんは、明治大正の頃にはやり、昭和十年過ぎには見なくなったという。 |
|
|
中江有里さんHP NHK「冬のソナタ」が、中年ご婦人を夢中にしているのは聞き知っている。 時々思い出したように見るが、前回見ていなくても話の筋が分るのでいい。 話の展開が単純だからだろう。 それより、役者の口の動きと吹き替えが合っていないので、気になってしまう。 洋画とはかなり違う。口の動かし方が違うようで、 欧米人がパクパクしてる間に、適当な日本語で吹き替えればそれらしく見える。 「千と千尋の神隠し」の英語版の吹き替えは、日本語の音節にあわせて翻訳し苦労したという。 何しろ、"ストライク "は日本語では五音節だが、英語の"strike"は一音節である。 実は別のことを書くつもりでいたのだが、今、女優で脚本家の中江有里さんのHPを見たら、同じようなこと(ただし前半部分)が書かれてあった。 そこで話題を変更する。 中江さんのページは不定期に更新されて、見計らって時々見ている。 一週間ほど前の新聞インタビュー記事で、六年前にタレント事務所から独立したら、 仕事がめっきり減り会社組織などの後ろ盾がないと、世間は冷たいと実感した。 収入も不安定になりスケジュールが空き、何もしないのはもったいないと脚本を勉強した。 2年前に、甲斐あってNHKラジオドラマ脚本賞を受賞したとあった。 そのホームページ、字が小さくて、ちょっと調子が合わないのだが、ご本人の趣向だそうである。 2年前に結婚された時、常連の間で一寸した騒ぎになった。 HPで公表した日付が4月1日で、多くの人がジョークと思ったそうだ。 中江有里さんのHPは http://www.yuri-nakae.com/ |
|
|
台風一過 大型台風6号が去ったら、梅雨まで吹き飛んだようにお天気である。 かねてより観たいと思っていた、黒澤明の最後の映画「まあだだよ」を、 先日の日曜日にとうとう観た。 美しい映像であった。 この事については何れ書こうと思う。  |
|
|
Mozilla 1.7 英語版 タブ切り換え型Webブラウザー Mozilla 1.7 英語版が公開された。 それで今使っている Mozilla 1.6 日本語版と入れ替えてみた。 このタブ式は一度使い出すと便利で手放せない。 またWebページごとに、ポップアップを遮断したり、 Cookie を拒否できる。 新しい機能として、右クリックメニューを使えないように細工されたWebページで、 その細工を無効化できるオプションが追加されたそうだがまだ試していない。 暫く使ってみると、Webページによっては日本語が文字化けする。 設定をいじればどうにかなるのかも知れないが、面倒である。 結局は元の Mozilla 1.6 日本語版に戻して、1.7 日本語版が公開されるのを気長に待つことにした。 |
|
|
桜桃忌 今日は太宰治の命日・桜桃忌(おうとうき)だそうである。 小説「桜桃」では、"子供より親が大事"というせりふで始まり、同じせりふで終わる。 勿論これは虚勢である。 太宰なら十代の終わり頃に、熱心に読んだ覚えがある。 そのうちに飽きてしまって、その後は読み返すことはない。 どれだったか忘れてしまったが、小説の中で高木貞治の「解析概論」が唐突に出てきて驚いたのを覚えている。 そのほかで印象に残っているものに、「ヴィヨンの妻」がある。 フランスの近代詩の先駆者、フランソワ・ヴィヨンの名前から取ったようだが、 内容は関係なかったように記憶する。 ヴィヨンは、泥棒詩人だったそうである。 もともとは、パリ大学に学ぶインテリで、恋愛の三角関係のもつれかで牧師を殺めて、 逃亡生活をすることになる。 盗賊団に加わり、悪事を重ねながら逃亡し潜伏する先々で、詩を書き散らしていたそうだ。 岩波文庫の詩集には、首吊りの挿絵があったと思うので、最期は絞首刑になったようである。 書いているうちに、話がそれてしまった。 |
|
|
蕎麦湯 蕎麦(そば)屋でもりを頼むと、蕎麦湯も出てくる。 その出し方が店によっていろいろと違うので、戸惑うことがある。 一度、蕎麦と一緒に蕎麦湯が土瓶に入って出てきたので、困ってしまった。 蕎麦湯は暑くないといけない。 蕎麦を食した後で、残りのつゆを割って飲んで丁度よい温度になるのがいいのである。 この様にはじめから持って来られると、冷めてしまって美味しくないし、 蕎麦粉の香りが薄れてしまう。 蕎麦が出来る前に、湯飲みで出てくる店があると聞いたことがあるが、そういう店はまだ知らない。 一度行ってみたいと思っている。 蕎麦が出来るまで、焼酎を蕎麦湯で割って飲みながら待つのも美味しそうである。 また、予め器につゆが入れてあり、後で蕎麦湯で割っても割合が調整できなくて困ったこともあった。 蕎麦湯も店によって、サラッとしたものからトロリとしたものまでいろいろある。 サラッとしたのが好みであるが、知らない店では出てくるまでは分らない。 それで今では、はじめての蕎麦屋では、面倒だから夏でもかけを食うようにしている。 |
|
|
漱石の弟子と孫 夏目房之介さんのブログのコメントに、 「房之介先生は百閒に会われたことがおありでしょうか?」という質問が書き込まれていた。 内田百閒は漱石の弟子で、明治・大正・昭和を生きて、71年に没している。 だからアポロ11号の月面着陸を知っている。 百閒は晩年に作品「雨が降ったり」の中で、 アポロ十一号ちゅう物が、お月さまへ飛んで行って、お月さまを引っ掻いたり、くすぐったりしているらしい。いい加減にしておかないと、お月さまが少し軌道をこっちへ、地球の方へ動かしたら、困った事になる。 お月さま、我我文学文章の徒に取っては、詩歌のセンチメントである。 象徴であり、神聖であって、冗談ではない、科学者の勝手放題は迷惑とも何とも。 と書いている。なるほど、漱石の孫の房之介さんが会っていてもおかしくはない。 それに対して、房之介さんは「ないです」と、また「父はドイツ語を内田から習ったんじゃないかな」 という返事をされている。ヴァイオリニストの故・夏目純一氏のことである。 東京フィル交響楽団の財団化に尽力された人である。 夏目房之介の「で?」のURLは http://www.ringolab.com/note/natsume/ |
|
|
携帯が、財布代わりに? NTTドコモは、ソニーの非接触ICカード技術「フェリカ」を搭載したiモード携帯電話で「おサイフケータイ」サービスを始めるという。 携帯をかざすだけで、交通機関の決済や電子マネー、個人認証などのサービスを受けることができるそうだ。 携帯ひとつでコンビニでは買い物が出来ますと、ニュースの解説者は嬉しそうに話している。 どうして、そんなに嬉しいの。 この様な技術サービスは、軽いノリでどんどんと現れてくる。 携帯と財布を共に持ち歩いて不便で仕方のない人ばかりで、その声に答えてのサービスではないようだ。 困ってもいないのに、現れるのは困ったものである。 携帯が他人の手に渡ると、一度に携帯と財布と身分証とが盗まれることになり、矢張り不安である。 リスクは分散するのが、原則だからである。 便利なことだけを言い、不安なことは考えないようなサービスは、もっと見直されていいはずである。 マイクロソフトは、誰でも簡単に操作できるOSを追求した挙げ句、セキュリティホールだらけのOSになった。 それを埋め合わせる為に、金食い虫にもなってしまった。 携帯は元は移動電話である。それがコンピュータになり、 それに感染し悪さするウィルスが現れた。 今のところ大丈夫とは言うけれど、やがてそうではなくなるだろう。 私達は便利さについて、真面目に吟味する時期に来ている。 |
|
Copyright(c) 2004 Yamada, K