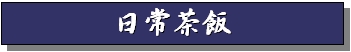
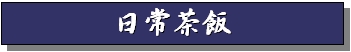
|
どこでもドア 四月の下旬だったと思うが、 川上弘美さんの「椰子・椰子」を読んだら、これが面白いのか、ないのかよくわからなかった。 テレビの小泉今日子・柄本明主演の「センセイの鞄」が結構面白く、 原作は川上弘美さんの小説だというから、近所の本屋に買いに行くと生憎なかったので、 「椰子・椰子」なのである。 川上さんの小説は、内田百閒に通じるものがあるそうだが、それもよくわからなかった。 ただ南伸坊さんの解説が大変面白かった。 私は伸坊さんの顔真似のファンで、あんなに大きな"おにぎり頭"で巧く変装するので、感心することしきりである。 最近のでは、建築家・安藤忠雄さんの「本人だもの」が可笑しかった。 伸坊さんは、川上さんがいっぺんに好きなって、それが百閒をいっぺんで好きになった時と似ているという。それで、「すごく気に入ってしまったので、本をいいかげんにパッと開けて、そこから読んでいくと、おもしろい。いきなりそっちのほうへ入っていける」と、 これを「ドラえもんのどこでもドアのようです」とは言いえて妙で可笑しくなった。 それならわかる。百閒もどこでもドアである。 百閒の本は大概が短い作品で、それらが散らかって収録されているので、どこから読みだしても面白い。 「冥途」、「百鬼園随筆」、「御馳走帖」、「一病息災」、「ノラや」など、どれも文庫で読める。 たびたび百閒物件(ひゃっけん・ぶっけん)で恐縮だが、「百閒の文章は味がありますぜ」 と千三つ屋の顔真似をして推薦する次第である。 |
|
|
議会制民主主義 なるほど、これが議会制民主主義なのかという出来事がふたつあった。 とはいっても数年前の話で、うろ覚えで申し訳ないが、その話を書こうと思う。 ひとつは、イギリスの現・トニー・ブレア政権が行った、 貴族院議員の議席を九割削減したことである。 生まれながらに議席が与えられる貴族の特権は、民主主義に合わないというのが理由であるらしい。 選挙で選ばれてこそ議員だと言いたいのであろう。 当然貴族たちは黙ってはいなかった、議会内で乱闘流血騒ぎもあったという。 それで、残る一割の議席に誰が座るか。 その決め方が面白い。 「議員である必然性」を短い文章に書かせた。 日本でいえば原稿用紙一枚ないしその半分で答えよと言う訳で、「一言で述べよ」と問い質すのが痛快だ。 もうひとつは、カリフォルニア州の何処だったか忘れたが、市議会が決めた法律である。 銀行が手数料を取るのは本業ではないといって、それだけで手数料を禁止したのである。 預けた自分のお金を引き出すのに、時間外だからと取られてしまうあの手数料である。 今では両替するのにも手数料を取り、利息は雀の涙しか払わない。 その僅かな利息はまた税金で引かれてしまう。 こんな銀行は国民の敵である。 だから、汚職を追求するだけの政治は、議会制民主主義とはいえないのである。 |
|
|
特許紛争の三日間 企業紛争の新しい形態を見たというのが感想である。 始まりは、家電大手のシャープが特許を侵害されたとして台湾の東元電機の日本法人を相手取り、 液晶テレビの販売停止を求める仮処分を申し立てたと、10日新聞に載っていた。 はじめは単なる特許侵害の話で、それが事実ならもっともなことだと思っていた。 ところが、怒ったのは小売業界トップのイオンで、シャープとの取引中止に踏み切った。 対象のテレビはイオンがシャープ製の半額以下で独占販売しているという。 翌11日の新聞には、「一方的で、長年の取引の信頼は壊れた」とイオン社長は怒り心頭に発する。 イオンのシャープとの取引額は年間70億円と電機メーカでは高額である。 これに驚いたのがシャープで、取引停止まで踏み込むとは思いもよらず、 「大切な取引先なので、改めて説明したい」と低姿勢である。 しかし、仮処分を取り下げるわけにはいかないだろうし、イオンも強気である。 それが一転して今日(12日)の新聞一面は、イオンはシャープとの取引を再開すると報じている。 たった一日で和解した。 これを空騒ぎと見るのは当たらないだろう。 経営判断が、これまでになく迅速になったということである。 イオンが取引中止を撤回したのには、消費者の声が働いている。 860件の消費者の声が寄せられ、うち6割が批判的な内容だったという。 決断したのは、企業イメージが一層重要になった為である。 イオンは食品の独自ブランド商品の生産履歴管理を厳しく行っていることで知られている。 その基準を、取引企業にも厳しく課してきた。 また、イオンが台湾製液晶テレビを撤去することで、シャープは大きな成果を得た。 特許侵害の安い液晶パネルが流通することで、被害を受けるのは実は日本市場である。 経営のスピード化、声を上げる消費者、ブランドのイメージといった、経営環境の変化の中での椿事は正常な決着を迎えた。リコール隠しの三菱自が旧態依然なのが対照的である。 |
|
|
お言葉ですが…(承前) 高島俊男さんの「お言葉ですが…」には、教わることが多いのだが、 時々たいへん驚いてしまうこともある。 だいぶ前のコラムに、高校の漢文教科書に出てくる「十八史略」は、 子供向けの教科書であって、後世に残す歴史的価値はなく捨てられて、今の中国にはもうない。 とあり、たいへん驚いたことがある。 漢文の教科書には、「史記」などの一流の古典と併せて載っているので、てっきり「十八史略」も同様の歴史書と思っていたから驚いたのである。 本家で滅びたものが、日本ではまだ残っているという変な現象にも驚いた。 「十八史略」が日本に入ってきたのは室町時代の後期だそうで、江戸時代になってから日本刊本が 多く出るようになり、明治以降漢文教科書に多く採用されると、「左伝」や「史記」などの一流の典籍との区別が判らなくなったという。高島さんはこの事を文化輸入国の悲哀と言い、次のように述べている。 「日本は昔から文化の輸入国で、外国から入ってきた書物をたいへんにありがたがる。 書物といってもいろいろで、本国ではおのずから格があり評価があって、一流の古典と三流以下の俗本とが 同列にあつかわれるようなことはないのだが、輸入国ではそれがわからないことがある。」 |
|
|
お言葉ですが… 帰りに本屋に寄って、高島俊男さんの「お言葉ですが…⑤」(文春文庫)を買った。 今日が発売日で、毎年この日が来るのを待っている。 週刊文春の連載コラムで、一年経つと単行本になり、四、五年経つと文庫になるようだ。 文庫で読むので、四、五年前の話になる。 話題は当時の出来事になるが、それは話の取っ掛りであって、 テーマの核心は普遍的な事、歴史の事である。だから、遅れて読んでも構わないし、頗(すこぶ)る面白いのである。 また、文庫では「あとからひとこと」という後日談みたいなものが加わって、これも面白い。 博覧強記の人である。文献の渉猟は徹底していて、本来は真面目くさった難しい話が、 笑いのある読み物に仕立てるところが凄いのである。 高島さんは在野の人らしいのだが、こういう人を碩学というのだろう。 |
|
|
無題 今晩は、セキュリティ・ホール関係のアップデートを2つ行う。 Windows 2000 の脆弱性のパッチを適用。 Direct X 関係のセキュリティ・ホールで、細工が施されたデータを送信されると、特定のアプリケーションを停止させられるというもの。 Windows 98/98SE/Meも影響を受けるそうだが、これらのパッチは未公開という。 また、Internet Explorer(IE)の新しいセキュリティ・ホールは未対応で、それを悪用するWebサイトが既に出現しているそうだ。今までに公開されたIEのパッチをすべて適用していても、そのサイトのページを閲覧するだけで、アドウエアを勝手にインストールされてしまうという。 もう1つは、ウイルスバスター2004の不具合が発見されたらしく、メイン・プログラムをバージョンアップ。 その後で、麦酒(ビール)をゴクゴク。 確か内田百閒に「医者の目を盗んでは麦酒をゴクゴク」と云う句があったと思う。 |
|
|
童謡「赤とんぼ」 好きな童謡についてアンケート調査をすると、ダントツ一位は「赤とんぼ」だという。 詩人・三木露風が、ふるさと兵庫県龍野をうたったものである。 明治の終わりから大正の頃の情景を描いたものだそうだ。 子供のころの郷愁を誘い世代を超えて歌い継がれてきた歌である。 そして、時代の違いを反映してか勘違いされている歌でもある。 一番の「負われて見たのは いつの日か」を「追われて」と誤解していたという人が意外に多いそうだ。 白状すると、私もその一人だった。耳で聞いて覚えたからかもしれない。 「負われて」は、三番の詩のねえや(姐や)に「背負われて」の意味である。 二番もねえや(姐や)に背負われての詩である。 この"ねえや"がまた勘違いされている。 姉ではなく、その家に子守奉公している少女なのだ。 それで、「お里のたよりも 絶えはてた」のお里は、少女の実家ということになる。 赤とんぼ 作詞:三木露風 作曲:山田耕筰 1 夕焼小焼の 赤とんぼ 負われて見たのは いつの日か 2 山の畑の 桑の実を 小かごに摘んだは まぼろしか 3 十五でねえやは 嫁にゆき お里のたよりも 絶えはてた 4 夕焼小焼の 赤とんぼ とまっているよ 竿の先 |
|
|
吉右衛門さんのばあや 土曜日(5日)、日経新聞の「菜食健美」の欄は、歌舞伎の中村吉右衛門さんだったので興味深く読んだ。 吉右衛門は幼少年時代を、家に奉公していたばあやに育てられた。 ばあやは海軍軍人の未亡人で、自分の子供を亡くしていたこともあって、 人生をかけて松本幸四郎、吉右衛門兄弟を育てた。 吉右衛門が稽古に行くのをグズるとピシャリとはたく。 小学校でフランス語を習うようになると、質問に答えられるようにと自分も勉強する。 一日の睡眠時間は四時間にも満たない。滅私奉公で、一生懸命に勤めたとある。 おやっと思ったのが、ばあやの年齢である。計算すると、吉右衛門が少年の頃はまだ四十代である。 それを「ばあや」と呼ぶのは不思議な気がした。 明治・大正時代の人は、今より早く老けて早く死んだと何処かで読んだことがある。 五十歳で死んだ夏目漱石は、すでに翁(おきな)と呼ばれていた。 老成するのが早く四十歳で、初老か老人であった。 吉右衛門は1944年生まれの戦後育ちであるが、当時はまだ明治大正の人の名残があったのだろうか。 吉右衛門が大学生の時に、ばあやは病に倒れる。 舞台の合間に病院に通い、懸命に看病したが、とうとう別れが訪れる。享年五十八。 年齢よりずっと老けて見えたとある。 翌年1966年に播磨屋・二代目中村吉右衛門を襲名。 歌舞伎俳優名鑑・中村吉右衛門のURL http://www.actors.or.jp/meikan/members/actors/a0150_kitiemon.html |
|
|
捜し物 朝から捜し物をしている。今も見つからないから、どうやらまた捜し物に失敗したようだ。 吉行淳之介は、「ないないないアッタの先生」という渾(あだ)名が付いていたという。 すぐに物が行方不明になり、「ないないこの家はものがなくなる」と怒鳴っているうちに 出てくるそうで、それでも出てくればマシなのである。 
|
|
|
スーパーマーケット 大手スーパーには、倒産するか或はしかけて経営再建中のものと、そうでないものとがある。 破綻の原因は、バブル期とその後に本業を忘れて、他のものに手を出したためである。 外食、ホテル、不動産、映画産業などと、 手を出して別の何者かに変われるとでも思ったのであろうか。 近所の馴染(なじ)みのスーパーは、再建中の大手スーパーである。 「お客様のご意見」をお書き下さいという紙が目に付く場所に置いてある。 寄せられた「声」に店長が一々答えて、ボードに張り出してある。 中には意地の悪い客もいる。 『何番レジの茶髪の店員なんて、クビにしろ』、こんな声にも丁寧に答えるので少し気の毒になる。 また、『○○さんには、親切に案内して貰った。有難う。宜しく伝えておくれ』、まるで伝言板である。 それでもその甲斐あってか、店の雰囲気もサービスも良くなっている。 3年程前には、店内を一新した。建物自体は取り替えることは出来ないが、 中央に通路を広くとり売り場の配置を変えた。 外資系の大型店舗の真似をしたのだろう。 おかげで、買い物がしやすくなった。 ところが1,2年経つと、 折角(せっかく)広くとった中央の通路に、ワゴンを置いて商品の小山が出来た。 日が経つに連れワゴンの数も段々と増えて来て、また以前の所狭い売り場に戻りつつある。 どうやら、商品を堆(うずたか)く積まないと気が済まないとみえる。 蛙(かえる)の子は蛙と云うけれど。 |
|
|
リコール隠し 三菱自動車の「リコール隠し」がまた発覚したというので、昨日のニュースの続きかと思ったら、 昨日とは別ものだという。 昨日はパジェロ、ギャラン、ランサーなど17種16万台でほぼ全車種が対象で、 そして今日はまた新たに11万6000台がリコールだそうだ。 三菱車のユーザーは、さぞや苦々しく思っているだろう。 あるいは呆れているかもしれない。 それよりも、三菱グループ企業の出入り業者はどう思っているのだろうか。 業者は、出入りの際に三菱車を強要される。 他社製の車で乗り入れると門番が閉め出すということを以前聞いたことがある。 勿論、他の自動車メーカーでも同様であろうから、慣行に従っているに過ぎないのだろう。 |
|
|
壊れた日本語のサイト 日本語の乱れを嘆いたり、怒ってみる本がある。 読んでみると意外に面白いものがある。例えば、 故・江國滋さんの「日本語八つ当たり」(新潮文庫)がある。 直木賞の江國香織さんの父君である。 何年か前までは、書店の文庫の書棚には親子で並んでいたが、 今では香織さんだけがあり少し寂しく思う。 他にテレビドラマ演出家の久世光彦氏の「ニホンゴキトク」(講談社文庫)も面白い。 当然、"日本語危篤"と読むのだが、"日本ご危篤"と読むものがいるという。 閑話休題(それはさておき)。 言葉の乱れどころでない、検索すると壊れた日本語の文書が出てくる遊びを教わった。 例えば、検索欄に「犬」と入力してエンターキーをたたくと、次のようなものが出てくる。 犬:対話機能がわかりましたか。 つかれた画面。また「脂肪」を検索すると、 12 - ビット脂肪を解釈する方法。マイクロソフト社、技術情報のページのことである。説明にこうある。 「このサポート技術情報は、通常、英語で提供されている文書が機械翻訳システムにより自動翻訳されたものであり、人的な確認・修正が加えられたものではありません。」 よくまあ平気でこんなページを作って恥ずかしくないのかな。 世界一儲かっている会社なのだから、翻訳できる人ぐらい雇えるだろうに。嗤うしかない。 マイクロソフト ヘルプとサポートのURLは http://support.microsoft.com/ |
|
|
夏日 青葉の目にしみる候。ところが一昨日の日曜日と昨日は、初夏どころか真夏日であった。 日曜日は、その暑い最中(さなか)、真っ昼間から四人してビールを飲んでいた。 屋内で涼しく飲んだが、外へ出た途端に暑さに堪えた。 
|
|
|
神々は細部に宿る 土曜日(29日)は朝7時40分頃から例のノンフィクションを読み出して、 8時過ぎに印象を少し書きアップした。 その後は夕食が済んでから読み始めた。 が、どうやらインタビューをそのまま書くダラダラ派だと気づいて斜め読みする。 途中中断しながら、夜11頃ほぼ読み終わる。 日本とアメリカとではノンフィクションの書くスタイルが典型的に違うらしい。 日本人の場合、書き手が一人称で登場し取材の過程をそのまま書いて行くスタイルをよく見る。 これはアメリカのジャーナリズムと対照的である。 古くはベトナム戦争での政策の意思決定の過程を描いたディヴィッド・ハルバースタムの「ベスト&ブライテスト」や、 少し前では、クリントン政権の内幕を描いたボブ・ウッドワードの「大統領執務室」 などでは、綿密な取材を行い小さな事実を積み上げながら、 やがて全体像に及ぼうとするスタイルをとる。 その内容は、当時の政権を揺るがしたほどで、圧倒的な迫力がある。 もちろん日本にも、この様な"神々は細部に宿る"というべき手法で書かれたものもある。 手嶋龍一著「一九九一年日本の敗北」(新潮文庫)はそうで、湾岸戦争での日本の対応、 外務省の失態を描いたものである。 手嶋さんなら、NHKニュースでお馴染みであろう。 長らくNHKワシントン支局長をしておられる。 この2,3年は頻繁に現れる。 先ほど Google で検索すると、手嶋さんのファンページが幾つもある。 テッシーなんだって。アハハ。 |
|
Copyright(c) 2004 Yamada, K