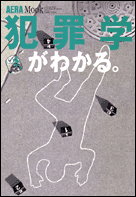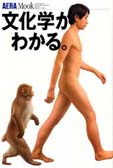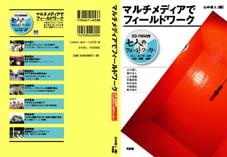山中速人の最近の発表論文・エッセィ・作品(1995年以降)
おことわり 以下の論文・エッセーの版権は、それぞれの発行者に属します。ここで公開しているのは、出版前のオリジナル原稿です。
したがって、出版されたものとは、すこし内容が異なることや未校正による誤字等があります。
- 「メディアがつくったハワイ」『毎日新聞』1995年

- 「観光開発と先住民の町興し」『毎日新聞』1995年
- 「書評:小熊英二『単一民族神話の起源』新曜社」『サンケイ新聞』1995年7月25日書評欄
- 「アミオニ島奇譚」『まほら』95年6月
- Can Tourists and Indigenous
Communities Be Coexisting? : A Case Study on A Hawaiian Indigenous
Community, In Search of Sustainable Development: Japan in
the Circum-Pacific Area. Ibaraki University, 1995
- 「日本語学校訴訟事件と日系新聞」田村紀雄編著『正義は我に在り−在米・日系ジャーナリスト群像』社会評論社、1995年12月
- 「社会学教育と映像利用」『放送教育開発センター研究紀要』1996年
- 「社会問題についてのフィールドワーク−ハワイの民族問題」『フィールドワークを歩く』嵯峨野書院1996年5月
- 「ミャンマーの人々は『ビルマの竪琴』をどう観たか」『少年育成』1996年3月号

- 「ミャンマーの人々は『ビルマの竪琴』をどう観たか(後編)」『少年育成』1996年4月号
「大阪をインターネット自由都市に」『21世紀大阪街づくりフォーラム1996』大阪都市協会1996年4月
- 「ウソとホントの解け合う世界−メディアと擬似現実」『ソシオロジー事始め』有斐閣1996年
- 「観光地イメージの形成−商品としてのハワイ−」『20世紀における諸民族文化の伝統と変容』ミネルヴァ書房1996年
- 「メディアと観光 −ハワイ楽園イメージの形成とメディア−」山下編『観光人類学』
- 「陰謀組織論を超えて−クラン型組織の病理−」『時評』1996年8月
- 「近ごろのハワイ−マクア海岸のホームレスたちから見える世界−」『書斎の窓』1996年11月
- 「アジア稲作社会の映像資料」『出版ニュース』1997年5月
- 「エスニック集団を比較する」苅谷剛彦編『比較社会入門』有斐
 閣、1997年
閣、1997年
- 「書評・吉野耕作著『文化ナショナリズムの社会学』名古屋大学出版局、1997年
- 「ビデオブック(大森康宏・制作)「ジプシー・マヌーシュの生活」評
−映像メディアの進化と人類学的知覚−『民博通信』1997,No.77
- ・「サイバーパンクもひとつの資産」『提言100〜オリンピックと大阪のまちづくり』大阪都市協会、98年5月,
pp.42.
- 「解説 「楽園ハワイ」を超えて」DVD『ハワイ〜虹色のレイ・フラの宇宙』パナソニック・デジタル・コンテンツ、1998年
- 「「フラの宇宙」解説 メッセージとしてのフラを読むために」DVD『ハワイ〜虹色のレイ・フラの宇宙』パナソニック・デジタル・コンテンツ、1998年

- ・「雲南「民族観光」覚え書き〜「雲南民族村」に見る少数民族のイメージ」『アジアを歩く』No.2,
98年10月, pp.28-31.
- 「ハワイ先住民の伝統的生活空間(アフプアア)の再現」−コンピュータ3次元グラフィックスによる仮想空間の構築−『コミュニケーション科学』1999.3
- 研究ノート「日常世界における映像の存在形態をめぐって−カンボジア・ラオス・雲南調査のフィールドノートから−」『コミュニケーション科学』1999.3

- 「ハワイアン」『世界民族辞典』弘文堂1999年
- 『メディア空間の変容と多文化社会』青弓社、99年12月
- 太平洋「探検」とメディア『講座・世界歴史12 遭遇と発見』岩波書店、1999年2月
- 「楽園のもうひとつの姿〜滞在型観光の影で」『まほら』No.19、1999.4
- 「境界集団の力〜民族集団の発展とホスト社会」『書斎の窓』No.483、1999.4
- 「マルチメディア教育事始め〜メディア工房の経験と教訓〜連載第1回:マルチメディアの力」『視聴覚教育』99.6
- 「マルチメディア教育事始め〜メディア工房の経験と教訓〜連載第2回:メディア工房の誕生〜マルチメディア制作の環境と組織を考える」『視聴覚教育』99.7
- オリンピック建設労働に外国人参加の道を開け『街づくりフォーラム99』大阪都市協会1999.6
- 「マルチメディア教育事始め〜メディア工房の経験と教訓〜連載第3回:プロジェクトを組織する」『視聴覚教育』99.8
- 「イメージの中のモンスーン・アジア〜東南アジアを中心に〜」渡部忠世編著『モンスーン・アジアの村を歩く』家の光協会、2000.1
- シンポジウム〜情報とネットワーク社会〜ネットワーク時代の社会・人・縁を語る(広瀬洋子×山中速人×金子郁容×京増弘志)『情報とネットワーク社会2』情報処理教育研修財団機関誌No.93、2000年1月、pp.5-28.
- 「マルチメディア教育事始め〜メディア工房の経験と教訓〜連載第7回:授業への導入〜マルチメディア・レポートの制作指導」『視聴覚教育』99.11
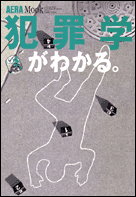
- 「マルチメディア教育事始め〜メディア工房の経験と教訓(連載10回):マルチメディア・レポートの作り方・続 〜生活史調査への応用事例〜」『視聴覚教育』2000.3
- 「マルチメディア教育事始め〜メディア工房の経験と教訓(連載11回・最終回):メディア工房から巣立つ学生たち」『視聴覚教育』2000.3
- 映像と思考の未来〜進化する映像と思考のネットワーク〜『影絵からマルチメディアへの民族学〜進化する映像』千里文化財団(国立民族学博物館・特別展図録)2000.7.18
- 特別対談 山中速人×大森康宏(国立民族学博物館教授)「一億人のリュミエールの時代」『月刊みんぱく』2000.8
- 開発批判からポスト近代観光へ〜ポスト・コロニアルな世界とオルタナティブ・ツーリズム〜『国際交流』2000.10
- ビショップ博物館所蔵のハワイ映像資料の一覧と解説『国立民族学博物館科研報告書』2001.3
- 市民力としての情報メディア〜市民的活動と情報技術〜『ボランティアと市民社会』晃洋書房、2001.4
- 「フィールドワーク教育をめぐる動向と課題〜技法教育へのマルチメディア利用に向けて〜」『中央大学文学部紀要・社会学科』通巻188号、2001年5月、pp.113-160.
- ビデオで犯罪学しませんか『犯罪学がわかる』(AERA
MOOK)NO.70, 2001.6
- 座談会〜情報とネットワーク社会〜市民がネット社会を変えていく(山中速人×奥出直人)『情報とネットワーク社会5』情報処理教育研修助成財団機関誌
No.96, 2001年7月
- アメリカと日本のはざまで〜ハワイ日系人のあゆんだ道〜『季刊民族学』97号 2001.8

- 観光ハワイの誕生〜ワイキキの1世紀〜『季刊民族学』97号 2001.8
- オルタナティブツーリズムとしてのスタディツアー〜その現状と課題〜『開発教育』no.44,
2001.8
- ビデオ案内・まなざしの変遷−フィルムの中の文化論『Aera
Mook・文化学がわかる。』朝日新聞社、2002年3月10日、pp.118-122.
- 『マルチメディアでフィールドワーク』(有斐閣)2002年3月
- メディアとフィールドワークは相性がよいか『書斎の窓』(有斐閣)2002年5月号
- 『オセアニア・ポストコロニアル』(春日直樹編、国際書院、2002年5月20日、「『楽園』幻想の形成と展開」pp.143-192)
- 2002年関西社会学会発表要旨「フィールドワーク教育におけるマルチメディアの活用と教材開発〜印刷教材とCD-ROMを併用するメディアミクス型教材の事例をもとに〜」 および「シナリオ」資料
- ポスト・コロニアルな時代に交錯する視線〜マーシャルローとパレステチナ自主制作ビデオ群〜「裏返しのメディア論」連載1『季刊・民族学』no.101,
2002夏, pp.92-93.
- 「書評 大地にしがみつけ〜ハワイの主権回復を訴える」『サンケイ新聞』Sun,
25 Aug 2002
- 映画が映画を語るとき〜ノスタルジーの向こう側に〜「裏返しのメディア論」連載2『季刊・民族学』no.102,
2002秋
- 日本移民学会報告:デジタル技術を活用した移民史研究における映像史料の収集と公開に関する事例研究〜ハワイ諸島カウアイ島の日系人ライフヒストリー調査の素材をもとに〜(2002年度・京都女子大学)
- 紙芝居からマルチメディアへ〜受け継がれるべき表現と技〜「裏返しのメディア論」連載3『季刊・民族学』no.103,
2003.1
- フィールドワークとしてのライフヒストリー研究の展開と課題−カウアイ島(ハワイ)日系人のライフヒストリー調査プロジェクトを事例として−『Journal
of Policy Studies』No.13, september 2002, pp.67-90.
- 絶滅するメディアをみつめて〜マルチメディアCD-ROMの盛衰〜「裏返しのメディア論」
連載4『季刊民族学』no.104, 2003.4
- メディアが先住者を語るということ〜ラテンアメリカ映画監督ホルヘサンヒネスの主要3作品の日本語ビデオ化完成を期に〜「裏返しのメディア論」連載5『季刊民族学』no.105,
2003.7
- 「映像メディアを使った社会学教育」関西社会学会2003年大会シンポジウム報告、2003年6月、追手門大学
- 立体映像でみるエスノグラフィックな世界〜見せ物からヴァーチャルリアリティへ〜「裏返しのメディア論」連載6『季刊・民族学』106号、2003年10月
- イヌイットたちをめぐる3つの映像がかたる過去、現在、未来〜「極北のナヌーク」から「氷海の伝説」そして小型ビデオカメラが捉える現場へ〜『季刊民族学』107号、2004年初春 pp.76-77
- 裏返しのメディア論8映像メディアは「正統」なるフラを伝承できるか〜『季刊民族学』108号、2004年春
- 『ヨーロッパからみた太平洋』(世界史リブレット・山川出版社)2004年5月
- 神戸新聞 「気鋭の肖像」2004年5月21日
- 「リュミエール映画の興奮はもはや失われたか?〜
くり返される人類と映像との出会いの衝撃」『季刊民族学』109号、2004年夏
- 裏返しのメディア論9「威厳ある一世の父を見つめる悩める二世のまなざし〜移民家族映画にみる世代間葛藤」『季刊民族学』110号
2004年, 秋 pp77-78
- 「スタディーツーリズムとしてのフィールドワーク〜学生・市民が参加するフィールドワークの意義と課題〜」『観光』2004年11月
- 裏返しのメディア論10「ビデオ・ジャーナリストに接近するテレビ番組が語りかけること〜フィールドワーカーはビデオ・ジャーナリズムから何を学ぶか〜」『季刊・民族学』2005新春・111、pp.76-77
- 裏返しのメディア論11「インターネットが伝える「地の民」のことばと歌声」『季刊民族学』112号、2005年春号
- 裏返しのメディア論10「料理は越えられない民族の壁か、異文化を結ぶ感覚のメディアか」『季刊民族学』113号・2005夏
- 「テレビCMにおけるハワイの文化表象の展開〜日本のテレビCMにおけるハワイ・イメージの形成と変容の一側面〜」飯田卓・原和章編『電子メディアを飼いならす〜異文化を橋渡すフィールド研究の視座』せりか書房、2005年
- 「12 カナカ・マオリ/ハワイアン 「先住民」カテゴリーの変遷を軸に」(大林純子と共著)『講座 世界の先住民族 ファースト・ピープルズの現在 第9巻 オセアニア』(監修 綾部恒雄)明石書店、2005年
- 時代の波にのった日本食(ハワイ)「特集:日本料理を食べる人びと」季刊・民族学 114号2005年秋
- エイズとともに生きる家族にむけられたビデオカメラのまなざし〜北タイの感染者家族を記録したドキュメンタリー「YESTERDAY
TODAY TOMORROW」の世界〜『季刊民族学』114 2005年秋
- Learning Fieldwork
with Multimedia: Problems on Education of Field Research Methods
and a Solution using IT. The Institute for Cross-Cultural Studies,
Seoul National University International conference on The Use
of Information Technology in the Research and Education in Social
Sciences (November 21 - 23)
- 裏返しのメディア論12「ネット世界を遊行する芸能民は生まれるのか」『季刊民族学』115号2006年春
- 裏返しのメディア論13「メディアは伝えない」『季刊民族学』116号2006年夏
- 『娘と映画をみて話す 民族問題ってなに?』現代企画室2007年6月
- 書評「カミングアウトレターズ」『読書人』2008年2月29日付9面
- 「ハワイ学からみた米大統領候補オバマ人気の秘密」『JAL機内誌スカイワード』2008年3月
- 書評 「石原俊著『近代日本と小笠原諸島
: 移動民の島々と帝国』」『社会学評論』Vol.59, No.2(20080930) pp. 436-438
- 『映像フィールドワークの発想〜ビデオカメラで考えよう!』七つ森書館、2009.2.1
- 『娘と話すメディアってなに?』現代企画室、2009.1.31
- 「ハワイ州50年 オバマ氏生んだ環境 本土が注目 多文化共生への希望」『北海道新聞』2009年3月25日附9面(文化面)
- 社会調査におけるマルチメディア利用の実践と展望ーフィールドワークにおける映像データの取り扱いをめぐってー『社会学評論』No.237特集,
2009年10月1日
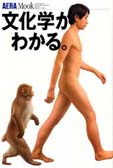
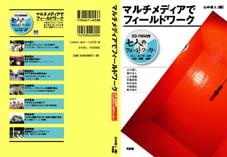





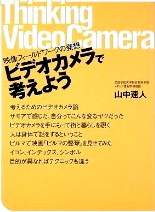
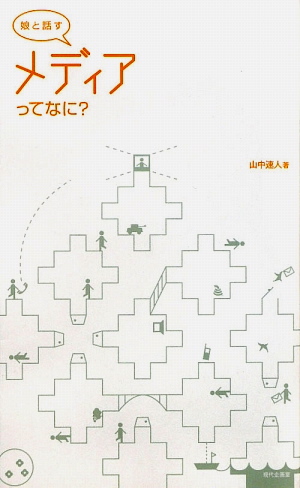


 閣、1997年
閣、1997年


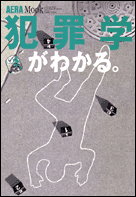



 閣、1997年
閣、1997年