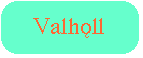北欧神話辞典
あ|い|う|え|お
- アィギル
 <音声クリック。Ægir再建音「エーギル」古北欧語「海」。海神の性格を持つ北欧神話の中の海の巨人。
<音声クリック。Ægir再建音「エーギル」古北欧語「海」。海神の性格を持つ北欧神話の中の海の巨人。
「詩語法」23章では、スノッリはフレールとギミルGymirは、アィギルの別名だと言っています。エッダ詩の神話的挿話の中ではアィギルは頻繁に神々の友だと言われます。『ロキの口論』(と『グリームニルの言葉』45節)では、アィギルは神々を歓待しています。事実、これを枠物語としてこの物語詩全体がはめ込まれている設定になって今s。同様にスノッリ(の「詩語法」1章)では、神々が何度目かにアィギルのもとを訪ねた経緯が、他の神話物語が語られるための枠物語となっています:「かつてアィギルあるいはフレールと呼ばれる男がいた。彼はフレールの島(フレースエイ)と呼ばれる島に住んでいた。彼は大変賢かった。彼はアゥスガルズルまで旅に出て、その旅のことを知っていた神々は、彼を大いに歓迎したが、その多くは単なる幻惑による見せ物であった」
ケニングの中にアィギルに言及する神話が見られます。キリスト教改宗以前のケニングにさえ見られるのです。たとえば、アィギルとフレールの同一人物であることや彼の担う主人役などがあります(エギッル・スカッラグリムスソン「息子達の悲しき喪失」8節)。
中世の全盛期にかかれたとされるノルウェーの前史時代について書かれたテクストには、アィギル/フレールが、フォルニョウトゥルの息子と呼ばれています。スノッリによれば(「詩語法」31章)海の女神ランはアィギルの娘とされますが、同じ「詩語法」58章ではランはアィギルの妻であり、アィギルの9人の娘達の母といわれます。アィギルの9人の娘は「海の波」と考えられていました。ランは網を持っており、それによっておぼれている人間を助けるのです。そして助けられた人間は海の中の彼女の宮殿に行き、そこで暮らすのです。彼らはヘルにもヴァルハラにも行きません。
古北欧語の「アィギル」という単語は「海の巨人」を意味しますが、頻繁に「海」そのものを言及するときにも使われます。ョgirという語はゲルマン祖語の*ahwoやラテン語のaqua「水」と関係すると見られています。もしもそうであるなら、「海の巨人」は「水の男」(ラテン語のAquarius)を意味すると思われます。一方、「海の巨人」と古北欧語æ/ ægiは、まったく別の語である可能性も捨て切れません。
ノルウェーで1967年に建造された快速艇の名前がÆgir と言います。
- アゥス 複数形アィシル
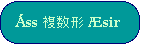 <音声クリック(再建音「アース;(複数)エーシル」;英語・独語アース。日本では基本的に「アース」「アース神族」と呼ばれることが一般
的) 古北欧神話の中で最大神族のメンバーの総称。今ひとつの神族にヴァン(複数ヴァーニル)がいます。北欧神話の中でもっとも重要な神々である、オージン、その息子ソゥルとバルドゥル、またロキはアゥス神族に属します。アゥス神族は戦いと支配の神々であり、一方ヴァン神族は豊饒の神々です。
<音声クリック(再建音「アース;(複数)エーシル」;英語・独語アース。日本では基本的に「アース」「アース神族」と呼ばれることが一般
的) 古北欧神話の中で最大神族のメンバーの総称。今ひとつの神族にヴァン(複数ヴァーニル)がいます。北欧神話の中でもっとも重要な神々である、オージン、その息子ソゥルとバルドゥル、またロキはアゥス神族に属します。アゥス神族は戦いと支配の神々であり、一方ヴァン神族は豊饒の神々です。
大きく意味を捉えると、エッダ神話中の神々は皆アゥスという一般名の中にくくられています。この理由は、ヴァン神族との戦いの後、アゥス神族は婚姻や人質として交わることで、二つの神族は解け合ってしまった、という事実に求められるでしょう。スノッリには、二つの神族を明確に二分しないようにする傾向が見られます。彼が書いたアゥス神族の長いリストには(『詩語法』1章)オゥジン、ソゥル、ニョルズル、フレイル、ティール、ヘイムダッルル、ブラギ、ヴィーザル、ヴァゥリ、ウッルル、ハィニル、フォルセティ、そしてロキの名が記されています。一方、女神としては:、フレイヤ、ゲフュン、イズン、ゲルズル、シギン、フッラ、ナンナがおります。『ギルヴィの惑わし』34章では女神たちの数は増え、エイル、フッラ、フレイヤ、ショプン、ロプン、ヴァゥル、ヴォル、シン、フリーン、スノトゥラそしてグナゥがおります。したがって、アゥシニャル「女のアィシル」もまた、すべての女神を含んでいると考えることもできるのです。
神々は皆、アゥスガルズル(「アゥスたちの宮殿」)に住んでいます。そこへはビルロストあるいはアゥスヴルー(「アゥスたちの橋」)という橋を渡らなければなりません。創世神話の中では、両方の神族が同じ一つの起源から発しています。神族は神話詩にともに登場し、ともにイズンのリンゴによって若さを保ち、ともにラグナロクのすべてを飲み込む終焉に脅かされています。ですから、我々には果
たして、もともとアィシルというのが神々を表す一般名詞で、ヴァンはそこから分かれていったのか、あるいはその反対の過程を経てアゥスというのが神々全般
を指すようになったのか、ということを結論づけるのは不可能です。
エッダ神話の中、特にスノッリの『エッダ』の中では、オゥジンが常に最高神として位 置づけられています。オゥジンも定冠詞付きの「アゥス」と単純に呼ばれることがある一方で、実はソゥルもそう呼ばれることもあるのです。『スキールニルの言葉』の中に登場する「アゥスの中の最高の者」という表現や、誓言の定型文中に現れる「全能のアゥス」という表現がオゥジンを指すのかそれともソゥルを指すのかは、実のところ定かではないのです。しかしながら、古英詩にはルーン詩と呼ばれる詩があり、そこに現れる、aを表すルーンの名前(古英語オース「神(すなわちアース)」、ゲルマン祖語*ansuz)は、(ケンブルという学者は「口」を意味すると解釈していますが)明らかにオゥジンを指しているように思われます。ルーン詩4番を訳して引用します:「オースは、すべての言葉の源(あるいは主人);知識の助け、また知者の慰め;またすべての人にとっての平安また希望」。
この古北欧語アィシル(単数形 「神」)という語は、ゴート語でAnsis(ヨルダネスによってこのように綴られている(Getica 8章、78))、古英語ではesa
(例 esa geschot 「オースに攻撃された>腰痛(椎間板ヘルニア)を起こした」単数形 os)という表現の中に記録されています。ドイツでは人名の中にのみ、この語の名残が認められます(Ansila,
Ansgeir, Anshram)。もっとも英語や北欧語の名前にも見られます。
「神」)という語は、ゴート語でAnsis(ヨルダネスによってこのように綴られている(Getica 8章、78))、古英語ではesa
(例 esa geschot 「オースに攻撃された>腰痛(椎間板ヘルニア)を起こした」単数形 os)という表現の中に記録されています。ドイツでは人名の中にのみ、この語の名残が認められます(Ansila,
Ansgeir, Anshram)。もっとも英語や北欧語の名前にも見られます。
ゲルマン祖語の、またローマ帝国の時代の女神Vih-ansa(「戦いの女神?」)の名前の中にもこの語(ansuz)が明らかに認められます。このように、神々を表す語の基本形はおそらくans-であると思われます。しかしながら、この語の語源はどうなのかというと、「梁、棒」を表す*ansなのか(もしもそうならば、木の神(あるいは磔(はりつけ)の神)に捧げるということの由来がわかる)、それとも古ヒンズー語のasura-(阿修羅<asu「生命力、活力」)に遡るのか、いずれの説にも説得力がありそうで、決定できません。
スカンディナヴィアには多くの土地の名前に As-という接頭辞が見られます(Asperg, Aaslunda(スウェーデン語)、Asarall(ノルウェー語))。しかしこのような地名は一人の神に由来すると言うよりは、神々全体に由来するものと考えられています。
アィシル(アゥス達)がアジアから移住してきたというエウヘメリスティックな説明が、スノッリおよびサクソ・グラマティクスによってなされています。これによれば、アゥスガルズル(アースガルド)もアジアにあり、アィシルという名前も「アジア」という地名に由来するということになりますが、これは中世の学者が考え出した考え方であって、ゲルマン神話には由来してはおりません。名前の似ているものを関係づけることによって、古スカンディナヴィアの系譜を、当時の考え方に従って先史時代と結びつけることで、スカンディナヴィア人を、古典時代、またキリスト教と結びつけることを可能たらしめるための工夫と考えられます。
- アゥスガルズル Ásgarðr
>音声クリック< Asgardr 英語その他の表記:Asgard アースガルドともカナ表記されます。。(古北欧語「アースの神々のすまい;アィシル(神々)の家」の意)。北欧神話の中の神々の砦。神話詩の中で、アゥスガルズルは「ヒュミルの歌(ヒーミルの物語詩)」第7スタンザと「スリュムの歌(スリームルの物語詩)」第18スタンザの中にのみ登場します。スカルド詩の中では10世紀のソルビョルン・ディーサルスカルドの一編の詩だけに出てきます。この名前―元々は固有名詞でなく単なる普通名詞だったでしょううが―はスノッリの著作によく登場します。
スノッリは『ギルヴィの惑わし』でも「詩語法」でも、神々の住居をこの名で呼んでいます。戦死した戦士たちの館であるヴァルホッルはアゥスガルズルの中にあり、同様にオージンが全世界を見渡すフリズスキャゥルフもあり、イザヴォッルルもアゥスガルズルの内側に広がっています。神々は神殿(グラズヘイムル)と女神たちのための広間(ヴィンゴゥルフ)とを建てました。グリームル(=オージン)が挙げた、神々の住まう所も全てアゥスガルズルの中に立っています。
元来は、アゥスガルズルは恐らくはミズガルズルの一部として理解されていて、すなわち、神々は、ウトゥガルズル(すなわち「外界」)とは対比的に、人間世界のすぐそばに住まっていたことになります。一方、スノッリは明らかにアゥスガルズルは空の上にあると考えていたようで、別
名のヒミンビョルク Himinbjorg(「空の都」)がそれを端的に表しています。ビフロストという橋がこの天国のようなアゥスガルズルに続く道なのです。
どこにもそれと明らかに表現しているわけではないけれど、スノッリが『ギルヴィの惑わし』41章の中で述べている大工職人の逸話は、アゥスガルズル建設について語っているように思えます。すなわち神々は堅固な砦をほしがり、ある一人の巨人がそれを18ヶ月で行うと持ちかける話です。その仕事の報酬として、彼はフレイヤを妻にし、太陽と月とを結婚持参金としてつけることを要求します。この偉業に際しては彼の馬スヴァジルファイリ以外に誰も手伝ってはならなかったのですが、この驚くべき馬の助力のおかげで、仕事は見る見るはかどっていき、期限を前にして神々は三日間、集いの席に着かねばならなかったのです。さもなければ、約束に縛られていた神々は彼の要求どおりのものを支払わねばならなくなったでしょう。神々の側としては約束を守る気など最初からなかったのです。ロキが、巨人とこの約束を取り付けたかどで非難を浴び、この難問を解くべく解決策を見つけるように言われます。ロキは姿を牝馬に変え、巨人の馬の気を逸らし、それがために仕事は期限どおりには終わりませんでした。ソゥルはこの巨人を殺し、ロキは八本足の子馬を産み落とします。後にスレイプニルとなる馬です。
スノッリは、アゥスガルズルについて全く異なる見解をもっていて、『ギルヴィの惑わし』の歴史的枠組みの中(2,9章)や、『イングリンガ・サガ』(2,5,9章)の中に記しています。しかしこれはゲルマン神話とは関係がありません。そこではアゥスガルズルはアゥサランド(あるいはアジア人の国)やアゥサヘイムルと呼ばれる国の首都であって、更には『ギルヴィの惑わし』9章では古都アゥスガルズル
(Asgardr inn forni)はトロイと同一視されています。
- アウズムラ >オイズムラを見よ
- アウルゲルミル>オイルゲルミルを見よ
- 『赤毛のエイリークルのサガ』 『ヴィンランド・サガ』を見よ
-
赤毛のエリック=赤毛のエイリークル 『赤毛のエイリークルのサガ』は『ヴィンランド・サガ』を見よ
- アース>アゥスを見よ
- アトラ Atla (古北欧語「論争好きな者」) スールルに登場する女巨人あるいは女トロル。『短い巫女の予言』(ヒンドラの歌37節)では、ヘイムダッルルの九人の母親の一人に挙げられています。
イ
イグドラシル Yggdrasill エッダ神話における、世界樹の名前。「イッグドラシッル」ともカナ表記することは可。しかし、多くの日本語翻訳では「ユグドラシル」と表記されることが多い。中世のアイスランドの写本に見られる綴りのヴァリアントはYggdrasilsが、スノッリの『エッダ』の王室写本に記されているのが見られる。
『巫女の予言』19、47節、「グリームニルの言葉」35、44節によれば、これはトネリコの樹だという。
その根は、全世界の中で、三つの世界に届く。一つは人間の世界に、もう一つは巨人の世界に、そしてもう一つはヘルの世界に(「グリームニルの言葉」31節)。その幹をリスのラタトスクルが上り下りし、一羽の鷲がその枝に留まり、竜であるニズホッグルとその他の蛇たちがその根を囓むという。その蛇たちの名は、ゴーイン、モーイン、グラーフヴィトニル、グラーバクル、グラーウヴォッルズル、オフニル、スヴァフニルである。また四頭の牡鹿が、その枝に茂る葉を囓むという。すなわち、ダーイン、ドヴァリン、ドゥネィル、ドゥラスロール(「グリームニルの言葉」32-35節)。イグドラシルは常緑であり、『巫女の予言』19節によれば、その下にはウルズル(ウルズ)の泉があるという。但し、スノッリによれば、そこにあるのは、ウルズルの泉、ミーミルの泉、フヴェルゲルミルの三つの泉があるという。ラグナロクの前に神々は、イグドラシルの下に集まり、協議をするという(「グリームニルの言葉」29-30節)。また、イグドラシルは、世界の終わりを予感して身を震わせるとも言われている(『巫女の予言』47節)。
さらに、スノッリはイグドラシルについて詳細に描写しており、彼の描写の中にしか見られないような特徴もある(『ギルヴィの惑わし』15章):「このトネリコの樹は全ての樹の中で最も大きく、かつ最高の樹である。その枝々は全世界の上を多い、天の上にまでそびえている。その樹の三つの根は、樹が伸びていくのを支え、非常なる広がりを保っているのである。一つの根はアース神族のところに伸び、もう一本の根は以前はギンヌンガガップにいた霧の巨人族のところへ、三本目はニヴルヘイムルの上まで伸びている。その根の下にはフヴェルゲルミルがある。だが、
- イザヴォッルル
 神話的平野。『巫女の予言』2篇、60篇に出てきます。アースガルズルのそばに広がっていて、神々の居住地の一部をなしています。世界の終末のラグナロクには、神々が新しい世界の中で集まる場所がイザヴォッルルです。イザヴォッルルの意味は、ON
*idi 「壮麗、光輝」という語に関係があると(クログマンの学説以来)考えられてきました。確かに並列する名前(グラィシスヴェッリル Graesisvellir
のように)も存在はしますが、しかし、この説は根拠が不十分です。なぜならイザヴォッルルは確かに時代的に若い造語でして、*idi をはじめとする同族語は文献に残ってはおりません。昔からある試みとしては名詞
idja 「活発さ、行動」との関連を見ることです。するとイザヴォッルルは「行動するための平野」となり、文脈的に無理のないものになります。『巫女の予言』2篇では神々はそこで様々なあらゆることをしていた、と描かれるからです。
神話的平野。『巫女の予言』2篇、60篇に出てきます。アースガルズルのそばに広がっていて、神々の居住地の一部をなしています。世界の終末のラグナロクには、神々が新しい世界の中で集まる場所がイザヴォッルルです。イザヴォッルルの意味は、ON
*idi 「壮麗、光輝」という語に関係があると(クログマンの学説以来)考えられてきました。確かに並列する名前(グラィシスヴェッリル Graesisvellir
のように)も存在はしますが、しかし、この説は根拠が不十分です。なぜならイザヴォッルルは確かに時代的に若い造語でして、*idi をはじめとする同族語は文献に残ってはおりません。昔からある試みとしては名詞
idja 「活発さ、行動」との関連を見ることです。するとイザヴォッルルは「行動するための平野」となり、文脈的に無理のないものになります。『巫女の予言』2篇では神々はそこで様々なあらゆることをしていた、と描かれるからです。
もっとも考えられる可能性は、イザヴォッルルは『巫女の予言』の詩人の創作だと言うことです。この文脈と神々の行いとを鑑みて、この名が最も適切だと思ったのでしょう。
今ひとつの考えられる説は、イザヴォッルルは「続けて新たになる、若返りの平野」という意味だと取ることです。これはiduliga 「続けて」idgnogr
「充分以上に」という語からの類推です。イザヴォッルルはラグナロクの後の新しく作られた世界の象徴だからです。
一方、古参の学者ブッゲはイザヴォッルルはキリスト教的エデンの園の退化したものだとします。(ちょうどウルズルUrdrがヨルダンJordanからの借入なのと同じだと彼は論じ)、古英語時代のイングランド人宣教師を通
じて北ヨーロッパに入ってきた考え方だとします。
- イッグル Yggr 古北欧語「恐ろしき者」の意。カナ表記で「ユッグル」「ユッグ」もあり。英語の影響から「ユグ」とする人もいますが、あまり奨められません。
「高き者の言葉」3節、「グリームニルの言葉」53、54節、「ヴァフスルーズニルの言葉」5節、「ヒーミルの言葉」2節、「ファーヴニルの言葉」43節に見られるオージンの別名。またスカルド詩にも多く見られ、9世紀の詩の中で既に詩人ブラギがオージンのことをこの名前で言及しています。
オージンの別名であるこの古く、また広く普及した名前はいろいろと派生を生みました。例えばイッグドラシルがあります(これは「イッグルの馬」という意味ですが、「スレイプニル」のことを意味するとは思えません。むしろオージンが自らを生け贄として吊り下げた樹のことであり、世界樹を意味するとみなされます)。また、イッギュングルという言葉もありますが(『巫女の予言』28節)、これは字義通りには「オージンの子孫、一族」を指しますが、詩の中ではオージン自身を意味しています。サクソ(『デーン人の事績』5巻)はイッグルをラテン語でウッゲルス(Uggerus)を記し、戦いの結果に影響を及ぼす予見者をそのように呼んでいます。もちろん、これはオージンの多くの役割の一つでもあります。
- イズン
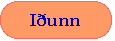 古北欧語で「若返りをもたらす者」の意。北欧神話の中ではあまり多くは言及されていない女神です。彼女は「若返りをもたらす林檎」を筺に入れて守っている、と言われます。>オスロの木彫りの図
古北欧語で「若返りをもたらす者」の意。北欧神話の中ではあまり多くは言及されていない女神です。彼女は「若返りをもたらす林檎」を筺に入れて守っている、と言われます。>オスロの木彫りの図
キリスト教化以前の時代に彼女の名が現れるのはスカルド詩人ショウゾゥルヴルの「ホイストロング(秋の長さ)」(900年頃)という詩の中です。スノッリはこの詩から自分の『エッダ』の「ギルヴィの惑わし」25章を取材しています。「ブラギの妻はイズンという。彼女は筺の中に、神々が歳をとるときに食べなければならない林檎を守っている。これによって神々は再び若返ることが出来るのだ。そのようにして神々はラグナロクまで若いままでいられるのだ」スノッリはまた、シャツィの神話エピソードを詳細にわたって記述しています。すなわち、イズンは林檎と共にロキと巨人シャツィに浚われるのですが、神々はロキを脅して、フレイヤの鷹の羽を使ってイズンを取り戻させるのです。シャツィの留守の時に、ロキはイズンを木の実に姿を変え(スノッリだけの記述)、連れ帰ろうとするのですが、シャツィは後から鷲に姿を変えて追いかけるのです。結末はシャツィは神々によって殺されてしまうのですが。
イズンの誘拐の記述にあたって、スノッリはホイストロング以外の資料も使ったと考えられますが、現存の資料以外には知られていません。
イズンはまた、エッダ詩「ロキの口論」17スタンザの中でも言及されます。ここではイズンは、自分の兄弟を殺した者と寝た、といって非難されます。「ロキの口論」の他の場合と同様に、この非難についての資料は現在不明です。
- イーミル Ymir (古北欧語再建音「ユーミル」)北欧創世神話に登場する太古の巨人。『詩のエッダ』にはイーミルの名が何度も言及されています(『巫女の予言』3節、「ヴァフスルーズニルの言葉」21、28節、「グリームニルの言葉」40節、「ヒンドラの歌」33節)。また、スカルド詩人アルノール・ヤーラスカルド(11世紀)(「イーミルの頭蓋」=「空」)やバル島のスカルド、オルムル(「イーミルの血」=「海」)の詩に見られるケニングからも、イーミルの神話が広まっていることが証拠立てられています。スノッリは『ギルヴィの惑わし』5-8章の中で詳細な説明をしています:エーリヴァーガルの流れが凍ったところから溶けた滴がギンヌンガガップの中で巨大な人の形になり、イーミルが誕生したこと、また太古の雌牛オイズムラの乳によって育てられたこと。イーミルは全ての巨人たちの祖先であること--スノッリはここで彼らのことを「霜の巨人(フリムスルス)たち」と呼んでいます。イーミルの子孫たちはイーミル自身の中から誕生したこと(単性生殖):イーミルが寝ていた時(とスノッリは書いています)、イーミルが汗をかき、その左の脇の下から一組の男女が生まれ、彼の片方の脚は、もう一方の脚との間に一人の息子をもうけたこと。巨人たちはこのイーミルの子どもたちから生まれたこと。最初の神々オージン、ヴィリ、ヴェーの誕生の後、イーミルは殺され、全ての巨人たちはイーミルのあふれ出た血によっておぼれ死んだこと。ただベルゲルミル(と彼の妻?)だけが「ルーズル」と呼ばれるものによって助かるのです(『ギルヴィの惑わし』7章;この「ルーズル」という単語は意味不明であるけれども、文脈から「筏」ではないかと思われている)[訳註:この「ルーズル」と言う語は後にも触れられるように「ヴァフスルーズニルの言葉」35節に出ている解釈困難な語です。スウェーデンの碩学リュドベリはこれを「引き臼」と解釈します。ホランダーは「棺」と解釈しています。どちらの場合も最も賢い巨人ベルゲルミルが命を失ったことを指しています。これは「グロッティの歌」というエッダ詩の一つに見られる「海」のケニングの解釈に関わる重要な単語なのです。「海」は「アムロジの引き臼」というケニングで表されることをスノッリは「詩語法」の中で言及しており、そこに登場するアムロジとは他に記録のない今は失われてしまった一人の巨人の名前であることを示唆していると思われるのです]。
ブールの息子たちすなわちオージン、ヴィリ、ヴェーの三人の神は、イーミルの死骸をギンヌンガガップに運び、そこで彼の体から世界を形作るのでした: イーミルの血は海や全ての水となり、肉は大地に、骨は(岩の)山々に、歯や骨の砕かれたものは岩に、彼の頭蓋は空になります。「グリームニルの言葉」40-41節ではさらに加えて彼の髪の毛からは木々が、彼の脳味噌から雲が、彼のまつげからミズガルズル「中津国」が作られたと語られます。
『巫女の予言』9節では、巨人の名前ブラーインとブリミルは、疑いなくイーミルを意味していると考えられます。それに従えば、ドワーフもまたイーミルから生まれたと考えることができます。スノッリはまた「ヴァフスルーズニルの言葉」に現れるオイルゲルミルの名前をイーミルを意味する名前だとみなしています。
一方「ヴァフスルーズニルの言葉」29節および33節には、スノッリの語る話とは異なる物語が述べられています。ここではイーミルではなくオイルゲルミルが単性生殖を行う巨人であり、その息子はスルズゲルミル、さらに孫がベルゲルミルとして登場します。ベルゲルミルが横たわる「ルーズル」にも言及されますが(「ヴァフスルーズニルの言葉」35節)洪水については言及されません。ド・フリース博士はこの洪水はキリスト教の影響によって挿入されたもので、「ルーズル」は揺りかご、それも巨人族に伝わる揺りかごだと解釈しました。しかしながら「ヴァフスルーズニルの言葉」に従うならば、巨人族の先祖はベルゲルミルではなくオイルゲルミルなのです。
二人の異なる巨人についてのコンセプトが「ヴァフスルーズニルの言葉」の書かれる前に混ざり合ったということは明白で、これはスノッリの過ちということで解決する問題ではないでしょう。異なる巨人の息子を同一人物にすると考えるならば、もちろんそれは元々あった記述のはずはなく、この仮説も合点がいきます。スノッリによれば巨人の祖先はイーミルであり、「ヴァフスルーズニルの言葉」によればオイルゲルミルです。一方で脇の下から生まれた一組の男女がおり、また一方では太古の巨人の両足から生まれた六つの頭を持つ巨人がいるのです。どちらの子孫がどちらの巨人から生まれたのか、という疑問は答えを保留するしかありません。しかし、スノッリがイーミルとオイルゲルミルを同一の巨人とみなしたのは故なきことではないでしょう。しかも、スノッリの資料としては今日の我々以上に豊富だったとは思えないのです。
スノッリの記述のみならず、語源的にもイーミルは単一生殖を行ったと考えることができます。イーミルの名前は語源的にサンスクリット語Yama、ヴェーディック(古)サンスクリット語Yima(どちらも神話的先祖を指します)、ラテン語
geminus、中アイルランド語 gemuin(「双子」)と関連があり、それはインド・ヨーロッパ祖語の*iemo-(「双子、両性具有」)に遡れるからです。同時に、タキトゥスの言う、ゲルマンの三つの種族イングウァエオネース、ヘルミオネース、イスタウァエオネースの祖先トゥイストーも、語源的には両性具有を表します(「数字の二から」)。つまりイーミルの名前にはゲルマン民族本来のものとインド・ヨーロッパ以来のものという両方の宇宙論が潜んでいるわけです。
イーミルの体をばらばらにすることで世界を創造するという創世神話の中には、太古の巨人の体を切り刻むことによって世界が創られたことを表す、生け贄の体をバラバラにすると言う祭儀的な意味合いも含まれると思われます。
ウ
- ヴァーリ Váli
エッダ神話の中でバルドルの復讐を果 たす者。
サクソは彼の役割を果たす者をボウスBousと呼んでいます。エッダ神話とサクソの記述双方に共通
なのは、彼の母親で、リンドゥルあるいはリンダという名前 (RIndr/Rinda) です(「バルドルの夢」11節を参照)。この女性を、オージンは、魔法と欺きとを使うことによって漸く征服できたのです。ヴァーリは、他の場所では唯一『ヒンドラの歌』29節で、バルドルの復讐者として名前が挙げられています。実際、この行為が彼について我々の知る唯一の行動なのです。『巫女の予言』32節以降で言及されるバルドルの復讐者がやはりヴァーリ本人を指しているとするならば、彼は生まれてからたった一日で、その復讐を遂げたことになります。この年齢のことについてはサクソの文献にはなにも記されてはいません。しかしサクソは、ボウスはかなり若かったときから戦争の技に興味を示していた、とだけは記しているのです。サクソに寄れば、ボウスは、ホゼルス(ホズルを見よ)への復讐をはたした後、すぐに殺されると書かれています。しかしながら、『ヴァフスルーズニルの言葉』51節では、ヴァー
リの名前は、ラグナロクの後も生き続ける新世代の神々の一人に数えられています。ロキの息子として、スノッリによって名前が挙げられているアーリ
Ali は、誤読のために、ヴァーリを間違えて新しく加えてしまったようにも思われます。
語源的には、ヴァーリの名前は十分に説明することができていません。ワニロー*Wanilo「小さなヴァン」という解釈は、彼を巡る事実にはまったく基づいてはおりません。とはいえ、ノルデンストレングの唱える「議論をする者」(<*waihalaR)という解釈も、決して真理とは思われないのです。ヴァリという神の名は、ノルウェーの地名ヴァラスキョッルValaskjoll(語源*Valaskialf)という地名に見ることができます。この名前は『グリームニルの言葉』6節において、神々の家の一つとして挙げられる名前と一致します。この地名は、オージンの息子たちの一人に対する崇拝が行われたということの証拠となりうるかもしれませんが、証拠としての重みを十分に担うものとは言い切れないのが実状です。
- ヴァーリ、ロキの息子の Váli
Lokason
スノッリの『エッダ』50章でロキの息子とされています。「今やロキは和解の余地なく捕らえられ、ある洞窟の中に連れて行かれた。それから神々は三つの平らな石を取り、尖った先を打ってそれに穴を開けた。それからロキの息子達、ヴァーリとナーリあるいはナルヴィが捕らえられた。アース達はヴァーリを狼の姿に変え、ヴァーリは自分の弟のナルヴィを引き裂いてしまった。アース達はナルヴィの腸をとって、先の三つの石にロキを結びつけた。」
この記述に関してですが、『ホィクルの書』に編纂された『巫女の予言』34節には次のような記述があるのです。
その後 ヴァーリは [写本: ヴァーラ] 殺しの縄目を 縒るのであった
腸からの枷を非常にきつく綯うのであった
この部分が『巫女の予言』の原詩に存在したか否かはわかりませんが、シグルズル・ノルダルはその可能性は薄いとしています。アーシュラ・ドロンケも『巫女の予言』以外の詩(写本か口承かわかりませんが)から取ってきたのだろうとしています。いずれにせよ、スノッリはこの詩行部分を知っていたと思われ、そこから『ギルヴィの惑わし』の記述に見られるとおり、「ロキの息子」ヴァーリを案出したのだ、と今日の学説では意見が一致しています。スノッリは「殺しの縄目」という語を「ヴァーリが行った殺人からとられた縄目」だと理解したようにも思われます。上述のようにヴァーリが殺したナルヴィの腸からロキの縄目が作られているとスノッリは語っているからです。
しかし、「ロキの口論」後述には、それと似たようなものではありますが、「ロキの息子ナーリの腸から縄目が作られ、ナルヴィは狼になった」としか書かれておらず、ヴァーリへの言及もありません。
ヴァーリは北欧神話では有名であり、オージンの息子にして、バルドルの復讐者、ホズルを殺し、ヴィーザルと共にラグナロクを生き残る者とされます。ロキの縄目との関連を持たされているのは、上述の『ホィクルの書』以外には見られません。しかし、バルドルの復讐を果たした者ですから、ロキを縛ったとしても決して不自然ではありませんし、かえって十分根拠のある役割と言えるでしょう。
ヴァーリという登場人物は、従って、もともとはロキの息子ではなく、『ホィクルの書』から断片的に知ることのできる何らかの伝承をもとに、スノッリが自分で案出したとするのも頷けます。(シグルズル・ノルダル著『巫女の予言』東海大学出版会、1993:
199-200;Ursula Dronke, The Poetic Edda: Mythological Poems. Vol.2.
OUP, 1997: 76, 347-48, 371-72.)
- ヴァルキリア valkyrja <音声をクリック
「ワルキューレ」「ヴァルキリー」「ヴァルキュリア」として有名。その起源は、恐らく戦場で殺された戦士の死体にとりついた悪霊であったと思われます。ヴァルキリア(アイスランド語の複数形
valkyrjur)は、古北欧語 valr (戦場で横たわる死体)+
 (選ぶ)から成り、従って「死体を選ぶ者」という意味になります(古英語にもvælcyrgeという語がありますが、古英語の文献からは北欧の観念との共通理解は伺うことができません。むしろ古英語話者は運命の女神とか魔女として理解していたようです)。ヴァルホッルの観念が、「戦場」から「戦士のための天国」という観念に変わったときに、ヴァルキュリアの観念も変化しました。>ゴトランドの絵画石碑<この北欧ゲルマン人の「ヴァルキリアのイメージ」は「楯の乙女」(アイルランドの女戦士で、戦死した後も、ヴァルホッルにおけるエインヘルヤルのように生き続けるとされた)によって取って代わられてしまいました。ヴァルキリアたちはオージンと密接に関わっていますが、彼女らの役割を、死人選びの悪霊達が担っていたより古い時代でも、オージンとの関係性は確実に緊密だったろうと思われています。
(選ぶ)から成り、従って「死体を選ぶ者」という意味になります(古英語にもvælcyrgeという語がありますが、古英語の文献からは北欧の観念との共通理解は伺うことができません。むしろ古英語話者は運命の女神とか魔女として理解していたようです)。ヴァルホッルの観念が、「戦場」から「戦士のための天国」という観念に変わったときに、ヴァルキュリアの観念も変化しました。>ゴトランドの絵画石碑<この北欧ゲルマン人の「ヴァルキリアのイメージ」は「楯の乙女」(アイルランドの女戦士で、戦死した後も、ヴァルホッルにおけるエインヘルヤルのように生き続けるとされた)によって取って代わられてしまいました。ヴァルキリアたちはオージンと密接に関わっていますが、彼女らの役割を、死人選びの悪霊達が担っていたより古い時代でも、オージンとの関係性は確実に緊密だったろうと思われています。
現在の彼女たちの役割は、戦いに干渉し、戦争当事者達の運命を決定することです。まさに彼女たちはオージンの意志を達成し、戦場で倒れた戦士達をオージンのもとに導く、「超自然的女性戦士」なのです(「ドルルズの歌」より)。このような理由から彼女たちは「オージンの乙女」、「御意(オージンの意志を達成するため)の乙女」と呼ばれます。
この観念の変化の結果、英雄詩の中に彼女らは人気ある地位を得、そこでは悪霊のような性格を大幅に失い、もっと人間っぽい、またそれだからこそ、人間達に恋をするような存在になりました。その例としては「シグルドリーヴァの言葉」のシグルドリーヴァがいます。ヴァルキュリアたちの人数は、9人であったり(「ヒョルヴァルズルの息子ヘルギの歌」36節)、12人だったりします(「ダドルルズの歌」)が、実際のところ制限はなさそうです。「グリームニルの言葉」36節ではヴァルホッルでエインヘルヤルをビールとともに歓待するヴァルキュリアは13人挙げられています:フリスト、ミスト、スケッギョルド、スコーグッル、ヒルドゥル、スルーズル、フロック、ヘルフョートゥル、ゴッル、ゲイロールル(またはゲイロームル、ゲイラホード)、ランドグリーズル、ラドグリーズル、レギンレイヴルです。
「ドルルズの歌」では、さらに加えて、ヒョルトフリムル、サングリーズル、スヴィプッル、グズル、ゴンドゥッルがいます。スールルはさらに加えて、ヘルヤ、ゲイラヴォール、スクルド、ゲイルローンドゥル、ランドグニド、ゲイルスコーグッル、フルンド、ゲイルドリヴル、タングニズル、スヴェイド、ソグン、ヒャルムスリムッル、スリマ、スカルモールドの名前を挙げています。他のヴァルキュリアの名前としては、英雄詩にのみ見られるだけです。シグルン、カラ(「フンディング殺しのヘルギの歌 第二」)、スヴァーヴァ(「ヒョルヴァルズルの息子ヘルギの歌」)、ブリュンヒルドゥル(「グリープススパゥ」)がおります。
これらの表現力豊かな名前は、その戦いを好む性格を表すものがほとんどですが、明らかに起源を古くはもってはおりません。しかも、民間信仰の中からとられた名前と言うよりは、むしろ詩作の過程から生まれたものだと考えることができます。
- ヴァルホッル
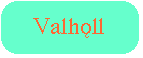 <--音声クリック Valholl
/ Valhalla[ギャラリーへ](日本では「ヴァルハラ」もしくは「ワルハラ」として有名)「死者の館」の意。アゥスガルズルのオゥジンの住まい。闘いで死んだ戦士たちを周りにオゥジンが集めるところ。
<--音声クリック Valholl
/ Valhalla[ギャラリーへ](日本では「ヴァルハラ」もしくは「ワルハラ」として有名)「死者の館」の意。アゥスガルズルのオゥジンの住まい。闘いで死んだ戦士たちを周りにオゥジンが集めるところ。
ヴァルホッルについてのもっとも詳しい記述は、「グリームニルの言葉」(8-10, 18-26節)に、またその後スノッリ(「ギルヴィの惑わし」37-40章)に見られます。ヴァルホッルは、アゥスガルズルのグラズヘイムルと呼ばれるところに存在します。この建物は槍や楯で屋根が葺かれており、ベンチの上には鎧が敷かれています。
ヴァルキュリアたちは、戦死した英雄たち(エインヘルヤル)をこの館、またオージンのもとに案内し、猪「サイフリームニル」の肉(これは調理師オイドゥフリームニルが大釜エルドフリームニルの中で調理したものなのです)を彼らに給仕することになっています。皆だれもが、十分にこの猪から食べるのですが、この猪は自ら常に再生するのです。「エインヘルヤル」
はこの食卓でヘイズルンという山羊の乳房から出る蜜酒を食事と一緒に飲むのです。 この山羊はヴァルホッルの屋根に立って、雄鹿エイクシルニルと同じように
大木「ライラズル」(=イッグドラシル)の葉を噛むのです。
しかしながらオージンは、ワインだけを飲み、自分の飼う二匹のオオカミ「ゲリ」と「フレキ」とを、自分の食べるもので養うのです。
ヴァルホッルに至る一つの門はヴァルグリンドと呼ばれます(おそらく戦死した英雄たちはこの門を通 って入ってくるのです)が、一匹のオオカミがその門の前に寝そべり、またその門の上を一羽の鷲が舞っているのです。
エインヘリヤルは、昼中お互いに戦い合っているのですが、夜になると、倒れたものも生き返り、席を同じくして、酒を飲み交わすのです(『ヴァフスルーズニルの言葉』41節)。このことから、ヴァイキング時代の人々が、天国をどのようなものだと想像していたかがよくわかります。しかしながら、ラグナロクの時にはヴァルホッルの540ある門のそれぞれから800人ずつが行進して出てくるのです。そしてフェンリルやその他の地下の国からの諸力に対抗して、神々の側について戦うのです。
『グリームニルの言葉』に見られる戦士たちの楽園についての詩的イメージは、その詳細の全てだとは言えませんが、間違いなく民間信仰にみられるものに由来しているでしょう。しかしそれでも、そのいくつかの要素は、すでに9-10世紀のスカルド詩に現れているのです:ソルビョルン・ホルンクロヴィ(最盛期900年頃;ノルウェーの詩人)の「鴉の言葉」(楯に覆われた館)、エイヴィンドルの「ハラルド王の言葉」「エイリークル王の言葉」などがあります。
M.オルセン教授の、議論を呼んだ学説は、多くの関心を集めました:常に戦い続ける戦士たちや、ヴァルホッルの540もの門というモチーフは、ローマのコロッセウムに行き、常にグラディエーター(闘士)たちが戦い続けたという記憶によって呼び覚まされたイメージだというのです。たとえまさにこの「記憶」が、北欧神話に現れたヴァルホッルの直接の原点ではないにせよ、この素材を後世の詩作になんらかの土台を与えた可能性はあるでしょう。800人×540の門=432,000人の戦士、という数値は、あるいは地中海世界の影響に遡るのかもしれません。だとすると、なんらのシンボリカルな意味はないことになります。さらには、この数値が本当に正しいのか、また『グリームニルの言葉』は、ゲルマン人の単位
である120という数値を使わなかったかどうか、と言った問の答えは不明というのが現状です。
古北欧語「ヴァルホッル」(ドイツ語Walhallaは1750年H.シュッツェによって初めて使われました)は、valr「戦場で死んだ者」とholl「ホール、館」という語から来ており、少なくとも後期異教時代には、「死人の館」として理解されていました。しかしながら、スウェーデン南部には民間信仰では死人が生きている場所と信じられている山、つまり死者の山、がいくつもあり、それらもValhall「ヴァルハッル」と呼ばれているのです。おそらく「ヴァルハッル」信仰も、塚や山の中での死後の生命の思想に基づいているのだと思われます。13世紀の嵯峨にはこのような例が見られるからです。自分たちの先祖たちと山の中で宴会をしている死者が人間によって目撃されているのです(『ギースリのサガ』11章、『エイルの人々のサガ』11章、『ニャールのサガ』14章)。この場合は、ヴァルホッルの「ホッル」は「館」ではなく、hallr「岩(山)」に由来することになります。
この名前そのものは、上記の考え方よりも古いと言うことはあり得ません。はじめに、死者が累々と横たわる戦場があり、そこから「死の悪霊」(ヴァルキュリア)どもが倒れた英雄たちを死者の神のもとに連れてゆく。この場所の描かれる場所が、山の中であるか、天国の酒飲みの館であるかは、二次的なものにすぎないのです。
- ヴァン Van (「ヴァン神族」複数形ヴァーニル Vanir) ゲルマン民族の神々の中で第二番目の位
置を占める一族。第一位はアィシルが占めるものとなります。
原則としてゲルマン人の神々はアィシルと呼ばれますが、ニョルズル、フレイル、フレイヤのグループは別
の神族に属しています。その神族とはヴァーニル(ヴァン神族) といい、アィシル(アゥス神族)とは常に平和的な関係だけを持ってきたわけではありません。スノッリは「ヴァン戦争」について語ります。その戦争の終わりに、両神族は和解をし、人質交換を行いました。
ヴァーニルとは、豊作、日光、雨や良い風を特に農民が求めるとき、また航海者や漁師たちが良い天候を求めるときに崇拝した豊饒神でした。
ヴァン神族は、アゥス神族からは下品だと見なされる類の魔術を行いました。アゥス親族自身はその魔術をフレイヤを通 じて身近にすることになります。これに加えて、『イングリンガ・サガ』4章でスノッリは、兄と妹の近親相姦がヴァン神族の間では許されていた、と語ります。これもまたアゥス神族とは相容れないものでした。この母権制度的状況はヴァン神族崇拝をしていた人々の間でもともと行われていた状況だったということを示していると考えられています。ヴァン神族への崇拝とアゥス神族への崇拝との間の違いは、社会的な身分の違いに原因があります。ヴァン神族は農耕民の神であり、アゥス神族は戦争志向の貴族たちやその従者たちに崇拝されたのです。
ヴァン神族への信仰ははるか昔にまで遡ることができます。ネルトゥス神は、語源的にニョルズルと同じなのですが、一世紀のローマの歴史家タキトゥスの時代にすでに言及されているのです。青銅器時代の絵画石碑に描かれた豊饒神の姿は確かにヴァン神族を意味しているものと見なされています。念頭に置いておくべき興味深い事項がもう一つあります。それはスカンディナヴィアには、ウッルルを除き、ヴァン神族の名前に基づく地名が多くありますが、ヴァン神族の名にアゥス神族の名前を付け加えた地名もあるのです。ただし、その多くはウッルルの名前を加えたものなのです。
ニョルズルとその子供たちであるフレイル、フレイヤの他にはイングという神がおります。イングはスカンディナヴィアでは後にフレイル神と同一視されますが、この名前もヴァン神族のリストに加えられるべきでありましょう。伝説の王フロージ(=フレイルと見なされている)がかつてはその偉業から当然のごとく神として崇められていた、という仮説があります。しかしながらこの説は疑わしいものです。同様に、ウッルルがヴァン神族の一員であったという説も、証明は難しいのです。ヴァンという語の語源については数多くの仮説がでておりますが、どれも説得力に欠けるもので、未だ定説はないのです。
ヴァン神族戦争。アィシルとヴァーニルの二つの神族の闘いにつけられた名前です。スノッリと『巫女の予言』中の不明瞭な数スタンザでのみ言及されている事件です。スノッリは短い説明を二カ所で行っておりますが(『イングリンガ・サガ』4章と『ギルヴィの惑わし』22章)、また今ひとつほんのさわりを言及しているところもあります(『詩語法』1章):
「始まりは神々がヴァーニルと呼ばれる民と行った戦争であった。しかし両者は和解の会合をもつことで合意し、一つの壺に唾を入れるという形で和解をしようと決めた。神々が立ち去るときになって、彼らはこの和解の印をとり、このことを忘れないように、それからクヴァシルと呼ばれる一人の人間を造った
今ひとつのより詳細な語りは『イングリンガ・サガ』第四章です:「オージンは兵をとり、ヴァーニルとの闘いに向かった。しかしヴァーニルは早くにそのことに気づいており、自分たちの土地をしっかりと守ったので、双方ともに相手をうち負かすことができなかった。双方が互いに相手の土地を荒廃させ、多くの損害を与えた。両者共にこの闘いのありさまに疲弊したとき、彼らは和解の会合を開くことで合意し、調停を結び、人質を交換し合った。ヴァン神族は自分たちの中からもっとも優れた「富めるニョルズル」と彼の息子フレイルを選んだ。しかしアゥス神族はハィニルと呼ばれる男を選び、この者は理想の首長になると言った。ハィニルは体が大きく、見目麗しかった。アゥス神族は大変に賢いミーミルを彼と共に送った。一方ヴァン神族は自分たちの中の最も賢い男を送った。彼の名前はクヴァシルといった」
この他にスノッリは(『ギルヴィの惑わし』22章の中で)ニョルズルとハィニルとがどのように人質になったかを述べ、間接的にヴァン神族戦争に言及しています。
『巫女の予言』21-26節で描かれていることはおそらくヴァン神族戦争のことであろうと思われ、またスノッリもこの詩節を知っていたにも拘わらず、スノッリの物語るこの戦争のエピソードの中身は『巫女の予言』のものからだいぶ逸脱しています。『巫女の予言』の中では人質交換のことについては何も触れられていません。またここではヴァン神族戦争の原因はグッルヴェイグという、スノッリの物語には登場しないヴァン神族の巫女にあるのです。
古い学説では、このヴァン神族戦争についての言及は紀元前二世紀に行われた歴史的事実としての戦争を反映したものだろうと考えられてきました。その頃に、スカンディナヴィア南部から西ヨーロッパにかけて広がっていた巨石文化が発達していたのですが、戦斧文化が北西方向に進んできて、飲み込まれてしまったというのです。これにより、(非インド・ヨーロッパ的?母権的?)巨石文化の勇士(=ヴァン神族)とインド・ヨーロッパ的戦斧文化民族(=繊維陶器(つまり毛皮でなく繊維で造った服を着、石器ではなく火を入れた陶器を用いる)文化=アゥス神族)との融合が起きたというのです。このような歴史的過程は記憶の中に、ヴァン神族の神話として、またアゥス神族とヴァン神族との和平協定として留まったことでしょう。
この学説に異を唱えたデュメジルは、他のインド・ヨーロッパ神話(ローマ伝説やインドの神話)中の関連する神話を示し 、ヴァン神族戦争を、王の従者階級(=アゥス神族?)と(植物の生長を祈る祭儀や魔術を重んじる)農業従事者階級との間に起きた社会的軋轢(あつれき)と解釈しました。二つの社会的階級の間に和平協約が結ばれて初めて--実際、ヴァン神族戦争の主題として強調されているのですが--インド・ヨーロッパ社会の社会的、宗教的な枠組みが生まれることができた、とするのです(デュメジル、ド・フリース)。
- ヴィーザル
 <--音声クリック 古ノルド語「広く治める者?」英語Vidar(「ヴィーダル」とも) アィシルの一人。特にオゥジンの復讐を果
たす者として知られています。>画像へ;ノルウェーのオスロ市庁舎の>木彫り画
<--音声クリック 古ノルド語「広く治める者?」英語Vidar(「ヴィーダル」とも) アィシルの一人。特にオゥジンの復讐を果
たす者として知られています。>画像へ;ノルウェーのオスロ市庁舎の>木彫り画
彼はラグナロクにおいて、フェンリル狼を倒すのです(『巫女の予言』53節、「ヴァフスルーズニルの言葉」53節、「グリームニルの言葉」17節)。スールル(つまりスノッリの『エッダ』の補筆とされている部分)の中には、ヴィーザルがオゥジンの息子という言及しかされていませんが、スノッリ自身の「詩語法」の中に記されているほか(「詩語法」11章)、ヴィーザルはまた女巨人グリーズルの息子とも言っています(「詩語法」18章)。ヴィーザルの住まいは「ヴィーザルスランド」とか「ヴィージ」と呼ばれます(「グリームニルの言葉」17章)。ヴィーザルはまた、ラグナロクの崩壊の後の世代にも属します。それはまるでヴァリ、モゥジ、マグニと同様、彼もまた新しい時代に生きる者とされます。
スノッリはヴィーザルを「寡黙な神」と呼びます。彼は「強い靴」を持っていると言われます。彼はソゥルのなき後、最も強い神と信じられ、神々はあらゆる難題について、彼に頼ることになります(『ギルヴィの惑わし』29章)。靴についての言及が、スノッリによって語られています:「その狼はオゥジンを飲み込み、それが彼の死となった。けれどすぐさまヴィーザルが現れ、狼の下顎に片足を踏み込む。その足に彼がはいている靴は常に集められ続けている素材でできている。その素材とは人々が自分の靴の爪先と踵からちぎりとった皮片からできているのだ。したがって誰であれ神々(アィシル)を助けたいと思う者は、このような皮片を投げ捨てるがよい。それからヴィーザルは片手で狼の上顎をつかみ、その口を引きちぎった。そしてこれがフェンリル狼の死となった」(『ギルヴィの惑わし』51章)。似たような民話的資料がスノッリによっていまひとつ語られています。ナグルファルという船についての言及の中でです(『ギルヴィの惑わし』50章)。
ヴィーザルはスカルド詩の中では言及されていません。したがって、彼のことをエッダ神話詩の中にのみ現れる純然たる文学的登場人物とみなす研究者たちが多くいます(「巫女の予言」「ヴァフスルーズニルの言葉」「グリームニルの言葉」「ロキの口論」)。ノルウェーにときどき現れる地名、ヴィルス(Virsu
<Vidarshof)、ヴィスキョッル(Viskjoel <*Vidarsskjalf)という地名が異教時代の後期にヴィーザルに捧げられた宗教儀式の存在を証拠立てるものであるかどうかは疑問が残っています。いずれにせよヴィーザルは異教時代の古き昔からいる神でないことは確かです。
北イングランドのゴスフォース(Gossforth)、マン島のカークアンドレアス(Kirk
Andreas)に見られる十字架石碑に見られるレリーフ(浮彫画)の解釈には、狼の口を引き裂く男にヴィーザルを見いだそうとするものがあります。しかしながら、これは単なるキリストを描いたものである可能性があるのです。というのも、ヴァイキング時代にキリスト教と異教との融合によって描かれたものであろうからです。ヴィーザルとキリストのイメージが重なり合っているとも言えるでしょう。
『ギルヴィの惑わし』29章は、彼についての紹介の章です。谷口幸男氏の「トールに次いで強い神だ」は誤りで、「トールと同じくらい強い神だ」となるべきでした。原文は:

で、naest は、ドイツ語のam naechsten「〜の次」というよりもアイスランド語の語感「〜に最も近い;〜と等しいほど」の意味に捉える方が良いでしょう。従って、ヴィーザルとソゥルは同じくらい強い、というAnthony
Faulkes の方がBaetkeなどのドイツ語の解釈より正しいと思われます。
また、スノッリに寄れば、彼はトロイ戦争に登場するアエネアスのことで、後にトロイの滅亡を逃れて新しい国(ローマ)を作ったとされます。つまり、トロイ戦争後も生き残った一人として、ヴィーザルはラグナロクを生き残った神々の一人として挙げられているのです。
- ヴィリVili(古北欧語「意志」)ViliとVéはオージンの兄弟です。
この三神は、スノッリの描いた神話によれば、最初の三人の神々だということです(『ギルヴィの惑わし』5章)。この三人は神話的先祖のボルが女巨人ベストラとの間に生まれた息子たちなのです。『イングリンガ・サガ』3章の中では、ヴィリとヴェーは、オージンが放浪している間、アィシルを支配する役を引き受けることになります。二人はまたオージンが帰ってくるまで彼の妻フリッグを共有するのです。『ロキの口論』26節でも、フリッグはヴィリとヴェーとともにオージンを騙したとして、このことに触れれています。オージンはまた、スカルド詩の中でも「ヴィリの兄弟」と呼ばれています(『イングリンガタル』3節)。ボルの息子たちの三神はゲルマン人の祖先に関わる三神の神話と比べることができます。タキトゥスが記すそれは:トゥイストーの息子マンヌスには三人の息子がおり、その名前をとってゲルマン民族は三つに別
れるというのです。インガエヴォーネス、イスタエヴォーネス、そしてヘルミオネースです。ゲルマン人の詩の中に用いられる頭韻は、オージン、ヴィリ、ヴェーの名前の中にも反映されています。この家系が作られて当時では、オージン/ヴォータン
WotanのWによる頭韻が見られるからです。これによっても、三神の名前の起源を古代ゲルマン人の時代に遡ることができるわけです。
【現存する写本について】
グリーンランドに植民移住したアイスランド人の口誦伝承に基づいている『グリーンランド人のサガ』は、1200年頃、アイスランドのスカガフィヨルドで書き残されたと推測されています。このサガは、『フラト島の書』と呼ばれる写本にのみ残されているので、言及される場合は、1387年に書かれたこの写本の、三部に分かれているヴァージョンのことになります。
『赤毛のエイリークルのサガ』の方は、アイスランド南西部のスナィフェッルスネスにて、1264年以降に作られたと推測されています。部分的にトリュッグヴィの息子オーラーヴル王(ノルウェー王として995-1000)のことを称えている文体から、オーラーヴル王のキリスト教政策に重きを置き、誇張している「レイヴルの息子、僧グンラウグルのサガ」の影響を明らかに受けていると見なされています。『赤毛のエイリークルのサガ』は、お互いに関連性の高い二つの写本、『スカールホルトの書』(AM557
四折本)と『ホィクルの書』(AM544 四折本)によって今日まで伝わっています。
スヴェン・B・F・ヤンソン博士は、一文ごとに検証した結果、1334年よりも前にアイスランド生まれのノルウェー人で、法の宣言者も務めたホィクル(エルレンドルの息子;1265-1334)によって書き残された『ホィクルの書』のヴァージョンは、より元の形に近くてあちこち話が飛ぶ『スカールホルトの書』のヴァージョンを、構成を固めて理屈が通るように改訂したものであることを証明しました。
また、『赤毛のエイリークルのサガ』の今日まで伝わるヴァージョンは、ホィクル自身の先祖であり、『赤毛のエイリークルのサガ』の主要人物であるソルフィンヌル・カールスエプニ(=「剛胆なるソルフィンヌル」の意;現代北欧語読み「トルフィン」)の冒険を誇張するように『グリーンランド人のサガ』に手を加えたものであることは確実視されています。学説はいろいろ分かれますが、いずれにせよ、『赤毛のエイリークルのサガ』の作者は、自分が『グリーンランド人のサガ』に大きく依拠していることを隠せるほど、言葉に堪能であった、と思われています。ある意味で、『グリーンランド人のサガ』よりも洗練された文学作品であると言えます。ただし、『赤毛のエイリークルのサガ』は、いわゆる「ヴィンランドの物語』の内容も登場人物達も、ある意図を持って変更させて書かれたものと申せましょう。
ヴィンランドへの航海について、一般的に歴史資料としての、この二つの“ヴィンランド・サガ”を批判的に検証して評価をするだけの外的資料は大いに不足しています。つまり、『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークルのサガ』に書かれている細かい記述を、相互に取り替えたりしながら全体像を描くのが、これまでの学者の一般的な傾向だったので、文学作品としても、歴史資料としても、「ヴィンランドへの航海の物語」はいわば二つのサガのまざりあったもの、となっているのが現状です。二つの作品の関係性は認めつつ、二つのサガは別個の作品であることをはっきりと意識するべきでしょう。これは一般的な「歴史書」でもなければ、「旅行ガイド」を意図して書かれたものでもありません。幾世代にも亘る口誦伝承によって、サガの記述者は、明らかに自分がよく理解できていないものについて書いている箇所もあります。明らかにフィクションの箇所もあり、それらをミックス(あるいは混同)されてしまっていることから、ある学者はヴィンランドの航海そのものの歴史性を過小評価したり、場合によっては認めないこともありました。現代の考古学、特にグリーンランドやカナダ、特にイングスタッド博士によるランス・オー・メドーの発掘によって、基本的なサガの記述の正しさは、現在では認められています。
【あらすじ:ヴィンランドへの航海】
『赤毛のエイリークルのサガ』にはヴィンランドへの三度の航海が記されています。『赤毛のエイリークルのサガ』よりは短いサガではありますが、『グリーンランド人のサガ』(あるいは『フラト島の書』のヴァージョン)では、ヴィンランドへの六度の航海が記されています。六度の航海のうち、最初のものは、ヘルヨールヴルの息子、商人のビャルニが偶然に北アメリカのある場所を発見したことになっています。おそらくは986年のことです。ビャルニは、ノルウェーから家財と共に、家族でアイスランドの西部で冬を越す計画を立てていました。ところが行ってみると、一足違いで、自分の親戚が赤毛のエイリークル達と共にグリーンランドに渡ったというのです。計画を変更したビャルニは、グリーンランドを目指します。ところが大西洋の霧の中に迷ってしまい、数日後にずっと西に陸地があるのを発見します。注意深く陸地と距離をとりながら、ビャルニは陸地に沿って北に向かい、氷河のあるところを目撃します。おそらくボフィン諸島だったと思われます。こんな北まで来てしまい、このままではグリーンランドへの東に向かう航路まで見失ってしまうと思ったビャルニは、そこで反転し、最終的に無事、グリーンランドの南岸に、自分の父ヘルヨールヴルの所領であるヘルヨールフスネスに到着します。ノルウェーへの帰路では、ビャルニは、何故自分の見た土地をもっときちんと探検しなかったのか!と人々から責められます。
二つ目の航海は、赤毛のエイリークルの息子レイヴルによって、西暦1000年頃に行われました。ビャルニが行わなかった探検をしようと決心したレイヴルは、ビャルニの船を買い、西の地を目指します。ビャルニが最後に見た土地まで来ると、レイヴルは南下し始めます。レイヴルが通り過ぎた地名についての言及が見られますが、「ヘッルランド(平たい岩の土地)」、「マルクランド(森の土地)」、「ヴィーンランド(葡萄酒の土地)」もしくは「ヴィンランド(緑の草地)」。そこにブドウの木と森を見つけた彼等は冬を越す為の家を建てます。春、または夏になって、彼等は船に荷を積んで、グリーンランドに戻ります。
三度目の航海は、レイヴルの弟で、レイヴルとともに、冬を越したソルヴァルドルによって行われます。ソルヴァルドルは、スクレーリングル(原住民)の放った矢で殺されてしまいます。彼の仲間達は彼をそこに埋葬し、グリーンランドに戻ります。
四度目の航海が、レイヴルの弟ソルステインによって営まれます。
五度目の航海は、富裕な商人「剛胆なるソルフィンヌル(ソルフィンヌル・カールスエプニ)」によって行われます。五名の女性を含む総勢六十人のクルーと共に、家畜も数頭載せて、ソルフィンヌルは、レイヴルの越冬した家を発見します。彼等はスクレーリングルらから、毛皮を買ったりしますが、やがて二つの民は衝突します。
いずれこの地に植民をしようと思っていた人々は、葡萄の木、葡萄の実、また毛皮などを持ってグリーンランドに戻ってきます。
六度目の航海は、レイヴルの庶子である娘フレイディースが、自分の兄弟ヘルギとフィンボギとともに向かいます。最後にはフレイディースは自分の兄弟も、女も含めたすべてのクルーを殺してしまいます。とはいえ、この最後の航海は歴史的事実かどうかは疑わしいとされています。
『赤毛のエイリークルのサガ』は、カールスエプニ自身に焦点を当てており、航海もずっと少なく語られます。ビャルニは登場せず、レイヴルはへブリーデーズ諸島やノルウェーに航海し(おそらくフィクションでしょう)、ノルウェーではオーラーヴル王に、グリーンランドをキリスト教に改宗させる使命を託されます。その帰りにレイヴル自身が名前も知らない新しい土地を見つけるのです。レイヴルの弟のソルステインは、航海しますが、成果はありませんでした。三度目の航海は、ソルフィンヌル・カールスエプニによる、大がかりなもので、3隻の船と男女合わせて160人の乗組員で構成されました。内紛があり、集団は割れ、スケーリングルらとの抗争はこの植民事業を中止しようという意見を生みます。数年の後、ソルフィンヌルとその妻グズリーズル、「アメリカで最初に生まれた男」スノッリは、グリーンランドに戻ってきます。『赤毛のエイリークルのサガ』では、ソルステインとフレイディースはソルフィンヌルの仲間として巧妙に配置され、フレイディースは暴力的な人物像から英雄的な女傑へと姿を変えています。『グリーンランド人のサガ』で、レイヴルの部下、葡萄を見つけたテュルキルは、『赤毛のエイリークルのサガ』では、異教徒の詩人、気むずかし屋の狩人ソルハッルルに姿を変え、葡萄の見つからないことで嘆きの歌を歌います。『グリーンランド人のサガ』では鯨が食用とされますが、『赤毛のエイリークルのサガ』では鯨には毒があり、キリストの奇跡をとおしてはじめて食用とされます。後には、ソルフィンヌル・カールスエプニとグズリーズルは、アイスランドで重要な家系の先祖となります。
経済的な事情から、「マルクランド」はグリーンランド人にとって、蓄財の資源供給所として、伝説と現実の両方で何世紀にも亘って生き残ります。ヴィンランドの記憶は薄れていき、今ではどこを指すのかはわかりません。もしも葡萄の自生が真実ならば、ニュー・イングランドあたりか、セント・ローレンスあたりになるでしょう。しかし、考古学的な資料に乏しい為、多くの学者にとっては、ニュー・ファウンドランド島が、ヴィンランドの推測地とされています。一方、カナダの北極圏には、北欧人の手製の品が発掘されています。
- ウッル またはウッルル
Ullr はゲルマン神話の中で、北欧の史料にのみ現れる神です。スノッリは、ウッルルはシフの息子であり、ソゥルの養子である(『ギルヴィの惑わし』31章;「詩語法」4章、14章)と言います。その他の資料はケニングからのものです(『ギルヴィの惑わし』31章;「詩語法」14章)。ウッルルは良い射手で、素晴らしいスケーターかつスキーヤーでもあります。彼はハンサムで勇ましい姿をしていて、果 たし合い(フュード)の際に彼を呼ぶことはよいこととされていました。(図版参照)
「グリームニルの言葉」5節によれば、ウッルルの家はイーダリル です。「アトリの詩」30節では、ある誓いがウッルルの指輪にかけて行われています。ウッルルはしばしばスカルド詩の中に名前が挙げられ、とくに「戦士」を表すケニングの中とウッルルの船はくりかえし歌われています。
です。「アトリの詩」30節では、ある誓いがウッルルの指輪にかけて行われています。ウッルルはしばしばスカルド詩の中に名前が挙げられ、とくに「戦士」を表すケニングの中とウッルルの船はくりかえし歌われています。
サクソ・グラマティクスは(『デーン人の事跡』三巻81章)オッレルス(=ウッルル)は骨に乗って海を渡ることができる、といい、サクソはこの能力を魔術によるものと言っています。とはいえ、このことはスノッリの言う、スケートとスキーの名手であることの反映であると考える方がよいでしょう。サクソによれば、このオッレルスはオージンが国を離れている間、アゥス神族(アィシル)の間で摂政となったといいます。ウッルルについての情報は文献資料の中には稀薄ですが、この神の名に基づいた地名が、特にスウェーデンと東ノルウェーに於いて数多いことは、この地域でウッルルへの特別な奉仕が行われていたことを示します。
スウェーデンにおけるウッルル崇拝をサクソが示したことで、オゥジン崇拝の勢力に対してウッルル崇拝は対立していたとする仮説があります。この立証の前に―興味深いことに、ウッルルに基づく地名は、多くの場合、他の神々との関わりが強いのです。ノルウェーではフレイル、スウェーデンではノルズルと(デンマークにはウッルルに基づく地名はありません)。ですから、地名に基づく早急な結論には注意が必要です。実際、ウッルルに基づく地名では、そのすべてがウッルルの崇拝地であったわけではないのです(たとえばノルウェーのウッレロー)。さらには、フレイルやニョルズルとの関係が地名に見られるからといって、ウッルルがヴァン神族の一人で豊饒神の一人であるという結論を引き出すには十分ではありません。ましてウッルルをフレイルと同一視する根拠はありません。
- ウートガルズル Útgarðr 古北欧語で「外の世界、外側の地域」の意。英独仏語 Utgard その影響から「ウトガルド」と仮名表記されることが多い。
北欧の宇宙観によれば、ウートガルズルは、神々と人間の住む世界(それぞれÁsgarðr、Miðgarðrという)の外側に位置し、巨人や化け物の住むところであるといいます。もともとは、ウートガルズルは世界全体を取り囲むものと考えられていましたが、中世の神話物語の中では、ミズガルズルの東にあるとよく語られました。
中世後期になると、旅行が頻繁になって地理的知識や認識が増した結果、巨人や化け物のような危険な生き物の国は、どんどん遠くへと追いやられ、北に向かっていきました。14世紀や15世紀の昔話のサガに葉、巨人やトロルの国を北極海の中に置くものもあります。
スノッリの『エッダ』で語られる、ソールとウートガルザ・ロキの話では、ウートガルズルの重要性はさらに限定され、ウートガルザ・ロキの単なる居城とされます。ソールはそこで力比べをし、負けてしまうのです。
-
ウトガルド>ウートガルズルを見よ。
- ウルヴル・ウッガソン、ウッギの息子ウルヴル Úlfr
Uggason 10世紀のアイスランド詩人。「フースドラゥパ」の作者。彼の人生について我々が知りうるところは、『植民の書』と『ニャールのサガ』に見られる短い言及に限られています。
エ
-
エイル Eir
アィシニヤ(
アゥスの女神)の一人。ここでは、もっとも優れた女医師と言われているものを指します。
『フョルスヴィンスマゥル(
フョルスヴィーズルの言葉)』38節では、エイルは、メングロズに使える女召使いの一人として言及されていますが、
スールルの方では、単なる
ヴァルキュリアの一人としてしか名前が挙げられていません。エイルという名前は「助け手」という意味(古北欧語eir「助け、慈悲」)です。これは癒し手としての女神の名前にはふさわしいものと考えられます。けれどもスールルではアィシニゥル(アゥスの女神たち)の名前のリストには挙げられていないのです。従って、死者を目覚めさせ、その傷を癒すヴァルキュリアたちの力こそ、この名前の意味として考慮すべきであることがわかります。エイルは、そういうわけで、もともとはヴァルキュリアの一人であるということの方が可能性があると言えましょう。
- エインヘルヤル 「一人で戦う者たち」の意。古北欧神話の中では、闘いで倒れた戦士たちを指す用語。死後ヴァルキュリアたちによってヴァルホッルに連れてこられます。
この戦士たちのパラダイスで、彼らは一日を闘いながら過ごしますが、夕暮れには皆ふたたび生き返り(『ヴァフスルーズニルの言葉』41節)、そして山羊ヘイズルンの乳房から流れ出て、ヴァルキュリアたちによって供される蜜酒を飲むのです(『グリームニルの言葉』25, 36節)。毎日、エインヘルヤルは、サイフリームニルという常に回復する猪の肉を食べるのです。その肉は全ての者に十分な肉があります。肉はエルドフリームニルと言う名の大釜で調理されます。調理するのはアンドフリームニルという名前です(『グリームニルの言葉』18)。ラグナロクにはエインヘルヤルは神々の手勢として、フェンリル狼や他の神々人間の敵どもと戦うために出ていくのです(『グリームニルの言葉』23)。
『エッダ』詩群の中では「エインヘルヤル」が言及されるのは『グリームニルの言葉』『ヴァフスルーズニルの言葉』『フンディング殺しのヘルギの歌 1』38節の中だけです。スノッリはそこから知識を得たのです(『ギルヴィの惑わし』37-40章)。10世紀半ばに書かれたスカルド詩『エイリークルの言葉』『ハーコンの言葉』から、異教時代後期にはエインヘリヤルについての考えが広く広まっていたということが証明されるのです。
M.オールセンは、エインヘルヤルについての神話は、グラディエーター(剣闘士)たちが常に戦うローマで作られたという考えを表しました。グラディエーターたちも毎日新たに闘いを行うからです。確かにヴァルホッルのイメージ(しかもそこには540の門がある)の中にローマのコロセウムの影響が全くないとはいうことはできないものの、しかし、ゲルマン兵士の一団にとって楽園の元祖はローマにあるのではありません。永遠に闘い続け、毎日死んだ兵士が蘇るというモチーフはサクソの中(第一書31章)にも見られます。また「ヒャズニンガヴィーグ(ヘディンの戦士たちの闘い)」についての報告もあります。タキトゥスの『ゲルマーニア』43章に言及されているハリイ族は「死人たちの軍隊(feralis
exercitus)」と描かれていますが、エインヘルヤルと比べることができ、語源的にも非常に近いものです。ヘフラー以降、人々はこの死んだ兵士たちの蘇った軍隊を、宗教的な動機付けから作られた兵士の一団として解釈することが多くありました。このような兵士団が、エインヘルヤルやワイルド・ハントという概念を形作ることになったのです。エインヘルヤルの語源について、今ひとつの説もはっきりと納得のいくものがあります:「軍隊に属する者」の意です。
- 『エッダ』Edda
もともとは『スノッリのエッダ』(今日では別名『散文のエッダ』とか『新エッダ』と呼ばれることも多い)を指す書名。
しかしながら、今では古北欧語で書かれた英雄譚および神話を歌う詩歌をも指すようになりました(こちらは今日では『詩のエッダ』または『古エッダ』と呼ばれることも多く、誤用ではあるがいまだに『セームンドのエッダ』と呼ばれることもあります)。しかし、eddaとはアイスランド語で「曾祖母」を意味する語であって、掛詞としての意味ならばともかく、書物のタイトルの第一義としては、はなはだ不可解に思われていました。これについては二十世紀になってから多くの学者たちの様々な意見を出したので、興味のある人は参考になさるがよろしいでしょう。日本語では、谷口幸男著『エッダとサガ』(新潮選書)がいまでももっとも簡便な入門書/紹介文となっています。
もともとはスノッリの書物に付された名前でしたが、中世の写本には、基本的に書名などは付されないのが普通です。ただし、スノッリの『エッダ』の写本中現存する最古の写本である「ウプサラ・エッダ」の始めに、「この本はエッダと呼ばれる」とはっきり記されているので、スノッリの書物は、本当に『エッダ』と呼ばれていたことは分かっています。
- エルフ (英語 elf, elves)神話、あるいは神話の下位に属する伝承に登場する存在とされる。
西ゲルマン語に見られる「エルフ」の概念は、すでに中世初期においてスカンジナヴィアのものとは異なっていた。アングル・サクソン人の間では、伝承の中のエルフというものは、恐らくはケルトの影響からであろうが、独自の発展を見せている。
古英語の中で既に9世紀ないし10世紀の文献に、「エルフ」を指す複数の語彙が存在した。これは地中海世界の神話に存在するエルフと同様の様々な存在に起因すると思われる。すなわちラテン語より古英語に翻訳されたと見るべきであろう。しかし同時に、すでにゲルマン神話の中で十分発達を遂げ、分類別が出来上がっていたと見ることも可能である。男性名詞
ælf / ylf また女性名詞 ælfen / elfen の他に、複合名詞としての bergælfen,
dunælf8en), muntælfen (すべて「山のエルフ」)、landælf, feldælf
(「土地(野)のエルフ」、wæterælfen, sæælfen (「水の精」)、wuduælfen
({森の精」)などがある。
古英語の形容詞 ælfsciene 「エルフのように美しい」は、このエルフという存在の明るい側面を示している。また同様の概念は人名に用いられる場合もそうである:Ælfbeorht
エルフベオルフト、Ælfred アルフレッド。一方、多くの病気の名前(例えば ylfa gesceot 「腰痛、神経痛」)は、エルフという存在が厄災をもたらすものであるという信仰を証拠立ててくれる。
スカンジナヴィアにおいて、中世後期から近代にかけては alfar 、またドワーフも、より一般的な用語である huldufólk の表す概念に集約させられてしまった。同様に、ドイツでは「エルフ」は民間伝承で大きな役割を果たさなかった。一方イングランドではエルフについての伝承が生き残り、ドイツは18世紀になって、これをイングランドから借入することとなった。ドイツ語本来のElbenとかAlbenという語の代わりに、Elfenが今日一般的なのは、恐らくこの英語からの借入に起因するのであろう。
アスクルと共に発見された二本の木の幹の一本から創られました。アスクルの語源は問題ありませんが、エンブラは語源的に不明確です。一つの説は*Elm-laというのが語源であるという説。従ってalmr、英語のelm「ニレ」の樹というものです。今ひとつの説は、ギリシャ語のampelosと同語源のものである、というものです。これは「蔓、ブドウ類」を意味します。
お
- オイズムラ 古北欧語 Auðumla, Auðhumla,
Auðumbla 再建音「アウズムラ」
太古の雌牛。太古の霜が解けた中から生まれた雌牛です。『ギルヴィの惑わし』5章の中で、スノッリはこの雌牛の四つの乳房から乳がどのように流れ、どのように巨人イーミルを養ったかを描きます。一方、オイズムラが神々の高祖であるブーリを、舐めて、塩の氷の中から解放した様子も描かれています。「オイズムラ」の意味は「多くの乳を出す角のない雌牛」です。「オイズルAuðr」は「豊かさ」「フマラ*humala」は「角のない」という意味だからです。タキトゥスもゲルマン民族は角のない家畜を飼っていたと記しています(『ゲルマーニア』5章)。
この聖なる雌牛のイメージは数多くの非ゲルマン民族の宗教にある、大地母神の姿と近い関係があります。エジプトのハトルだけが、雌牛の頭を持つ空の女神です。ヘラ(「雌牛の目」)と特にイシスとは、雌牛のイメージにさかのぼれる性格を持っています。ゲルマン人の地域では、ネルトゥスの名が挙げられるでしょう。タキトゥスに寄れば、宗教行列の中で、ネルトゥスは家畜に引かれる車に乗せられるというのです。ここで、牛の像だけが大地母神の持ち物として明白なものです。
オイズムラの乳房から流れる四筋の乳ですが、エデンの園から流れる四つの川との比較を促すように思われます。しかしながら、よりいっそう可能性のあるのは、スノッリが受けたキリスト教教育の影響であり、この記述が、大地母神の近東の概念との共通
性を証明するものだとは言えないだろうということです。
- オイルゲルミル Aurgelmir 巨人(「ヴァフスルーズニルの言葉」29節以後;「スールル」)。恐らくはイーミルと同一と思われます。というのも「ヴァフスルーズニルの言葉」の中で彼はベルゲルミルの祖父、スルーズゲルミルの父と呼ばれているからです。「オイル」古北欧語のaurr(「濡れた砂、砂礫」)を語源とするという説は信憑性があります。他の巨人の名前にも見られるものです(オイルボザ、オイルグリームニルを参照)。この説から考えるとオイルゲルミルの名は「砂から生まれた吠え猛るもの」という意味になります。
 <音声をクリック オージン(オゥジン、またはオーディン)Óðinn
(OE Woden, OS Woden, 古フランコニア語 Wodan,
OHG Wutan, Wuotan). エッダ神話体系の中で神々の長。最も性格が多岐にわたっています。神々の父、詩の神、死者たちの神、戦いの神、魔術の神、ルーンの神、恍惚の神。ON文献の中に見られる数多くの名前が彼の複雑多岐な性格を物語っています。オージンのイメージ集1
<音声をクリック オージン(オゥジン、またはオーディン)Óðinn
(OE Woden, OS Woden, 古フランコニア語 Wodan,
OHG Wutan, Wuotan). エッダ神話体系の中で神々の長。最も性格が多岐にわたっています。神々の父、詩の神、死者たちの神、戦いの神、魔術の神、ルーンの神、恍惚の神。ON文献の中に見られる数多くの名前が彼の複雑多岐な性格を物語っています。オージンのイメージ集1

- オージン神話:スノッリ(「ギルヴィの惑わし」五章)によれば、オージンとその兄弟ヴィリとヴェーは、はじめに作られた神々です。彼らは巨人たちの息子です(ブル、ベストラ参照)。オージンはフリッグの夫で、彼の息子は、バルドル(母フリッグ)、ソゥル(母ヨルズ)、ヴァリ(母リンドゥル)です。母親がわかっているこの三人はスカルド詩の中に見られますが、その他スノッリはヘイムダッル、ティール、ブラギ、ヴィーザル、ホズルをオージンの息子として名をあげています。
スノッリはまた「オージンは神々の中で最も高貴で最も古い神である。彼は全てのものを統べ治め、他の神々が如何に力が強くとも、彼を子が父に従うように従うのだ」と言っています(「ギルヴィの惑わし」19章)。
彼はアゥスガルズルに住み、フリズスキャゥルフ  <音声をクリック にいて、そこからは全世界を眺めることができるのです。すなわち彼は全知と見なされていて、それゆえ、彼はフョルスヴィズル
<音声をクリック にいて、そこからは全世界を眺めることができるのです。すなわち彼は全知と見なされていて、それゆえ、彼はフョルスヴィズル
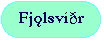 <音声をクリック (勝れて賢い者)と呼ばれるのです。
<音声をクリック (勝れて賢い者)と呼ばれるのです。
オージンを表す特徴は、槍グングニル Gungnirを持つこと、片目が失われていること、縁の広い帽子と外套などです。このようなものから彼であることがわかるのです。(図版参照)彼の登場する場面では、13-4世紀に書かれた『古い時代のサガ』Fornaldarsogur(伝説のサガと呼ばれることもある)から現代に書かれた神話物語にいたるまで、このような姿で現れているのです。もっと古くから伝わるもう一つのオージンの持ち物は、オージンの指輪です。ドロイプニル
Draupnir という名のそれは、9夜ごとに、同じ重さの金の指輪を8個生み出す魔法の指輪です(「詩語法」35章)。オージンの二羽の大ガラスのフギンとムニンも、ゲルマン民族大移動時代の末期からオージンに属するものとして確立していました。二羽のカラスは世界を巡り、朝食に戻ってきて、オージンに様々なニュースを伝えるのです。「それゆえ彼は「カラスどもの神」Hrafnaguðと呼ばれるのだ」(図版5-7)(「ギルヴィの惑わし」38章)。オージンの八本足の馬スレイプニルについてはONの文献のきわめて早い時期に言及が見られます。スノッリによれば、この驚くべき馬は巨人族の牡馬スヴァジファリと(牝馬に化けた)ロキとの間に生まれたと言います。
オージンは、その知恵を、ミーミルの頭から受け取ると言います(『巫女の予言』46、『イングリンガ・サガ』4,7章)が、あるいはミーミルの泉から飲んで得たとも言われます。しかしスノッリによればオージンはそのために片目を犠牲にしなければなりませんでした(「ギルヴィの惑わし」15章)。その神々の長としての立場にも拘わらず、オージンは神話的な冒険談はソゥルほど多くはありません。オージンがその広大な知識を証明する逸話は幾つか残っています。エッダ詩の「ヴァフスルーズニルの言葉」の中でオージンは巨人ヴァフスルーズニルと知識の競い合いをし、勝利しています。「グリームニルの言葉」では、ゲイルロズル王の前で、自分の知識を披露するように言われ、この詩とハルバルのサガの中―そこでもオージンは知識の競い合いをしている―にしか見ることのできない多くのオージンの名前を列挙します。スノッリはまた、おそらくは遙か昔のオージンについての神話を記録しています。それは詩の密酒を盗むために巨人娘グンロズを誘惑しなければならなかった話です。『高き者の言葉』の103-110行に語られるいわゆるオージンの第二の行いはその話に言及しているものと考えられます。一方同じ『高き者の言葉』の96-102行が語るオージン第一の行いは、あるビッリングル(それ以上の情報はえられません)という巨人の娘との冒険について語っています。オージンは恋の冒険との関わりで語られることが多いのですが、これは古典神話の中でゼウスが楽しんでいるのを真似たものかもしれません。いずれにせよ、リンドゥルとの関係では、結局彼女はヴァゥリという息子を身ごもります。ソゥルとの言い合い
(「ハゥルバルズルの歌」)ではソゥルの英雄的行為と自分の恋愛冒険とを比べています。
また、『高き者の言葉』では、彼は「風の吹きすさぶ絞首台」に九日間自分自身を捧げものとして吊さねばならなかったことが語られています。それによって彼はルーンの知恵を得ることができました。
10世紀のスカルド詩の中では、オージンは頻繁に兵士の神、戦死した者たちの神として言及されています。またエインヘルヤルの神とも言われています。エインヘルヤルはオージンがヴァルホッルに集めている兵士で、ラグナロクの時には下界からの戦力に対して闘うとき、自分たちの味方になるのです。(続く)
- オーズレーリル(現代アイスランド語的カナ表記「オーズラィリル」)
 古北欧語での意味は「恍惚へと刺激するもの(ジメックの辞典、その他説)」か? あるいは「詩をもたらすもの(ヘッグスタッドの辞書、その他説)」か? どちらの可能性もあります。
古北欧語での意味は「恍惚へと刺激するもの(ジメックの辞典、その他説)」か? あるいは「詩をもたらすもの(ヘッグスタッドの辞書、その他説)」か? どちらの可能性もあります。
スカルドの蜜酒。しかしながら、スノッリによれば(詩語法第一章)オズレーリルはドワーフのガラルとフャラルが殺したクヴァシルの血を受け、そこから蜜酒を造った大鍋の名前とされています。
スノッリはこの解釈を、『高き者の言葉』140節の意味の不明確な詩節から得ています。けれど、「高き者の言葉」107節や、スカルド詩に見られる多くのケニングから、明らかにこの語の元の意味は蜜酒そのものを意味したと思われます。それは名前の意味からも推測されるような恍惚をもたらす飲み物であったと考えられます。クヴァシルの神話は、スノッリの手が加わったものでさえも、異教時代に遡る宗教儀式の中で、恍惚をもたらす飲み物の重要性を確かめるものです。
この語の意味が二説あるのは、語頭のを「怒りその他の精神的興奮状態」と解釈するか、「詩、詩芸、言葉に関する能力」と解釈するか、によります。オージンの名前に拘わる場合ですら、伝統的な「怒りの神」という解釈もあれば、詩や言葉に拘わる神とする解釈もあるのですから、困りものですね。アイスランド語-英語の辞書では前者に採ることがありますが、後者の説も退けるのは難しいでしょう。「オーズル」の項追記も参照してください。 Óðrの意味を「耳に心地よいもの」とするならば、詩や言葉に拘わる意味となります(ゴート語
vôþis、古英語 wêðe、古高ドイツ語 wuodi「かぐわしい」) 。一方、「怒り、興奮」とするのであれば、恍惚と関わりがあります(古英語
wôd、古高ドイツ語 wuot「怒り」)。
- オーズル Óðr 『エッダ』神話に登場する神。スノッリに依れば(『ギルヴィの惑わし』35章;『詩語法』20章、35章)フレイヤの夫であり、娘フノッスの父親。
オーズルは11世紀のスカルド詩人エイナル・スクーラソンの詩の中のケニングに現れるのみならず、『巫女の予言』25章、「ヒンドラの歌」46、47節に言及されており、後世の思いつきではなく、異教時代に既に存在した神であろうと思われます。フレイヤへの言及の中でスノッリは、オーズルはかつて長い間留守にしていたことがあり、フレイヤは彼の不在を悲しんで涙し、探しに出かけた、と言っています。
このことに関して最も簡単な説明は、オーズルとオージンを同一人物とみなすことでしょう。名前が似ていること(似た例は UllrウッルルとUllinnウッリンがあります)、長い間留守にすること(オージンは放浪します)、オージンがフレイヤと結婚したこと(「グリームニルの歌」14節では妻フリッグではなくフレイヤが死者をオージンと分け合っています)などの記述はこの仮説の裏付けとなります。
しかし、この説への反論ももちろん存在します。フレイヤが、オージンのために涙を流したとか、オージンを探しに出かけたなどといった行動をどうしてとったのか、理由がわかりません。またフノッスが二人の唯一の子供であるという記述もいささか驚きです。美しい娘ということで、彼女の名前をとって「宝飾」のことを古北欧語では「フノッス
hnoss」というのだと言われます。それほど美しい娘がオージンにいたのであれば、やはり美しいバルドルと、オージンの息子&娘として、並び称されてよいのではないか。そうされないのは何故か、といった疑問です。このような不具合から、オーズルについては様々な、まさに多種多様な仮説が試みられました。オーズルのエピソードに(フリュギアの)アッティス神話、さらにオーズルとの名前がアッティスよりも近いとされた「アドニス神話」のモチーフを重ねてみる(ブッゲ、ファルク説)ものや、「アモールとプシケ」のモチーフの反映を見出す(ホランダー説)ものがあり、いずれもスノッリのオーズルとフレイヤのエピソードに似ている神話との繋がりを見出そうというものです。
しかし、もしオーズルとオージンとが同一だというのであれば、スノッリは必ずそのように言及したはずですし、二人を別々に扱うはずもなかったでしょう。しかしまた一方ではオーズル
oðr とオージン Oðinn の名前の類似は非常に大きく、二人を無関係だとするのも難しいように思われます。より古い記録の痕跡を見つけて、二人を関係づけるか、あるいは完全に区別しようという試み(ヘルム、フィリップソン、ド・フリース説)はあるものの、オーズルについての資料が少なすぎるため、どれも信憑性のある説というには至ってはおりません。
[追記] ヤーコプ・グリムは、オーズルの名前の意味について、興味深い考察をしております。クヴァシルの血を入れて蜜酒を造ったとされる大釜の名前は「オーズレーリル」と言われております。古高ドイツ語の
wuodi、古サクソン語の wôthi、古英語 wêðe という語がありますが、香りや音を修飾する形容詞で「甘い(香り、音)」を意味します。さらに、古英語
wôð は「詩、言葉を操る能力」を意味します。古北欧語の óðr がそれらに対応する形であることは明らかで、「詩の才能、言葉を操る能力」を指す名詞だと考えられる、とグリムは言います。従って、フレイヤの夫であるオーズルも「詩、もしくは詩芸」というものの人格化なのかもしれない、と仄めかしています。
(別の箇所では、グリムは、ゴート語の「かぐわしい」という形容詞 vôþis と古北欧語の óðr
との関連について疑いがあることも注記していますが。)
>トップに戻る<