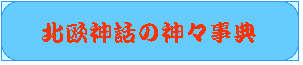
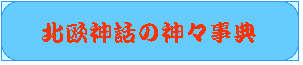
第一メルセブルク呪文(First Merseburg Charm)
第二メルセブルク呪文と異なり、これは「解放の呪文」である。おそらく鎖につながれた囚人を解き放つ呪文であろうと思われる。
呪文の最初の部分は、四長行で、何人もの(ヴァルキュリアのような?)乙女(Idisi)が、囚人たちを鎖から時はなってくれるかを語る。そして、最後の一行では、実際に解き放つ命令が発せられる「insprinc haptbandun, invar vigandun(お前の鎖から飛び上がれ、敵を逃がせ)!」
第二メルセブルク呪文 (Second Merseburg Charm; Der zweite Merseburger Zauberspruch)
OHGの呪文。10世紀の写本の中に記録された呪文。成立はもっと古いものと思われます。呪文の言葉は次のようになっています:
Phol ende Uuodan vuorun zi holza.
du uuart demo Balderes volen sin vuoz birenkit.
thu biguol en Sinthgunt, Sunna era suister;
thu biguol en Friia, Volla ers suister;
thu biguol en Uuodan, so he uuola conda:
sose benrenki, sose bluotrenki, sose lidirenki:
ben zi bena, bluot zi bluoda,
lid zi giden, sose gelimida sin!
フォルとウォーダンは森に行った
バルドルの馬は前足の骨をはずしてしまった
その時シントグントと彼女の妹スンナは歌を歌った
その時フリーアと彼女の妹フォッラは歌を歌った
その時ウォーダンは歌を歌った;彼は大変巧かった
骨をはずすことであれ 血の病であれ 手足がはずすことであれ
骨には骨 血には血 手足に四肢 そのように皆つながりたまえ
ティール(テュール)![]() ゲルマン民族の空、戦、そして会議の神のスカンディナヴィア語の名。
ゲルマン民族の空、戦、そして会議の神のスカンディナヴィア語の名。
理論的に再構築したゲルマン祖語形*Tiwaz (OHG Ziu)。ティールは、ゲルマン民族の神の中で、唯一インド・ヨーロッパ時代から重要と見なされていた神です。古ヒンズー語Dyaus, ギリシャ語 Zeus (ゼウス), ラテン語 Jupiter (ユピテル), 古ヒンズー語 deva, 古アイルランド語 dia, ON
(Tyrの複数形)は、全て語源的に非常に近い関係にあります。
本来の重要な地位に比べると、『エッダ』の中の古北欧神話では彼の地位は重要なものとはなっていません。それでも後期のエッダ詩の中(「ロキの口論」38,40、「ヒュミルの歌」4,35、「シグルドゥリーヴァの言葉」6)やスノッリ自身の著作の中に、彼は何度も言及されていて、神々の中の重要な一人とは言われています。それで、スノッリもティールについて語るべきこととして次のような事柄を報告しています。彼は戦争や決闘の神であり(『ギルヴィの惑わし』24章、「詩語法」9章)、狼フェンリルをひもにつなげるために片手をなくしたこと、またラグナロクには狼ガルムル(=フェンリル?)と闘うことなどが語られます(『ギルヴィの惑わし』50章)。(図版参照)
ティールはまた神々(アイシル)の中に置いて普通とされる関係から一人離れた存在なのです。彼には妻があった記述はありません(ただし「ロキの口論」の中にたわいない言及があるのを除けば)。さらには彼の父が誰かも明らかではありません。「ヒュミルの歌」ではティールは巨人ヒュミルの息子とされています(その理由は神々が巨人から生まれたとされるからか?)。またスノッリは彼をオゥジンの息子と呼んでいます(スノッリによればほとんどの神々は「全ての父」オゥジンの息子と言うことになるからだ)。またティールが戦の神だということについても、せいぜいヒントに毛の生えたような記述しかないのが事実です。一方、彼の名前の複数形
が「神々」を表すことだけでなく、スカルド詩の中では彼の名は、他の神々、なかでもオゥジンのためのケニングに、基礎語彙として使われているという事実など、歴史のある段階で、彼が大変重要な存在だったことを示唆しています。このことは、ティールという名は元来(またヴァイキング時代でさえも)「神」を表す単語だったことの証明となります。
ティールが片腕だという考え方は、スノッリによって、フェンリルを紐につなぐという神話の中で説明されていますが、ノルウェーやアイスランドの古い民話などにも言及されていることがわかっています。従って、この逸話の古さが忍ばれます。非ゲルマン神話の神々にも幾つかの相似が見られます。というのも、アイルランド神話のヌアドゥやインド神話のスールャはともに片腕だからです。違いはティールの場合は契約を守った代償として片腕を亡くすのですが、誓いをたてることで片腕をなくすということは多くの文化圏では偽証の罰として記録されてきました。ですからティールの場合のように正義の神としての存在として片手を失うという神は、他と異なる目立った存在と言えます。デュメジルはローマの伝説の中に、これの類話を見出しており、その中には自分の無実を証明するために片腕を犠牲にする英雄が出てきます。このティールの神話は、宇宙の秩序を安定させるためにはそれに必要なものがあり、結果として腕を失うことさえもあることを告げることで、安定の為にはどのような代償を払ってもよいということを示そうとしたものなのです(ヤン・ド・フリース)
ティールはまた、ルーンの魔法の中で働くことがあります。T を表すルーンは前史時代を終えた後にティールの名を表すようになりました。アングロ・サクソン人にとっては ti、ゴート語では tyzといいます。「シグルドリーヴァの言葉」6節では、ティールのルーンを二度剣に刻むことで、勝利を得ることができると歌っています。民族大移動期にはルーン碑文や腕輪などに T を表すルーンが多く彫られたりしました。これは魔術的な意味で用いられたことがわかります。
ティール信仰が特に行われた地域があることが、たとえばデンマークの地名などからわかっています。Tislund (lundrは「杜」の意味) はいろいろなところで見られます。ノルウェーではそれよりは少なくなりますが、Tysnesなどの地名はそれを表しています。このようなところでは、ティール信仰がデンマークからもたらされたのだと考えられています。また、地名に神の名を戴くようになる時代にはティール信仰は既に弱まっていたという可能性もあり、地名には現れないけれどもティール信仰が盛んだった地域も多くあったことも考えられます。
トール (Tor) : ソゥルを見よ。
「'burir tveggja bræðra' 「二人の兄弟(つまりバルドルとホズ)の息子たち」あるいは'burir bræðra Tveggja'「トヴェッギ(オージン)の兄弟たち(ヴィリとヴェー、またはヘーニルとローズル)の息子たち」。これはまったく不明である(256)」
とあります。この点について、ヒャルマル・ファルクは以下のような解釈を示しています:
「Tveggi (史料 碑文)人名としてはデンマークのルーン碑文にのみ残っている。またそれも恐らくは渾名から来ていると思われる。この語の意味は、元来は「ふたなり」すなわち両性具有であったと思われ、原初巨人のイーミルとの関連がありそうである。もちろんイーミル(=オージン?)は巨人の一族の出であり、空と大地が作られるため、霜の巨人のためにも自らをそこに住まわせたのである。この名前は、タキトゥスの書くとおり、ゲルマン人の間では人間の祖先と考えられていた、土地から生まれ出た神トゥイストーと対応し、この語はドイツ語のzwisterと同じ語であり、「両性具有」を意味した。しかし、歴史時代に北欧に住んだ人々の間まで、この語源的意味が生きていたと言うことはできないだろう。人はオージンの性質の二重性について、例えば、神々しいオージンと人間的なオージン、またその呼び名自体も「ヴァールエイグル(燃える目)」と「ビルエイグル(弱い目)」[や「サンヌル(真実)」と「スヴィパッル(変わりやすい)」「グリームニルの言葉」47]などのように、正反対の意味がついているということも、もちろんすぐに思いつくであろう。同様に、オージンは自分自身に自らを捧げたり(「高き者の言葉」138)、アース神族のためにルーンを彫るアースであると同時に、人間のために人間の魔術師のように振る舞うような二重性を持つのである。(ヒャルマル・ファルク『オーディンのヘイティ』140)」
このファルクの解釈の面白さは、イーミルによって天と地を作ったオージンが、霜の巨人たちが住むための場所も作ったことになるという点でしょう。すなわち、オージンは巨人たちの場所も確保したということになるわけで、だから、スノッリの『エッダ』とは異なり、オージンも巨人族の出であるという理解も生まれたのだと思われます。いずれにせよ、北欧神話のオージンは「両性具有」的な性質はないので、この呼び名は、神としてのオージンと、人間の姿で現れるオージンとの二面性、あるいはオージンの性質に見られる光の面と暗黒の面の二面性に言及しているのかも知れません。オージンはローマ神話のヤヌスのような「二つの顔」を持つ神とは考えなくともよいでしょう。(なお、この項目は「Visindatre―知識の木」掲示板内のVe様の提言により書かれました。謹んで御礼申し上げます)
この種の民俗信仰は、ゲルマン民族のキリスト教改宗後も、その意義や内容をほとんど変えないまま生き残ったので、キリスト教時代からの資料も、ゲルマン民族がこのような生き物に対してどのように考えていたのかについて、充分有益なものを与えてくれる感じがします。神話について言えば、14-15世紀の古ノルド語の伝説的サガは、エッダ詩よりも多くのことを教えてくれます。それというのも、このようなサガの標準装備のものとして、ドワーフは、この種のサガに属する典型的な昔話の要素として、半分は微笑ましいものとして見なされ、また半分では実際に信じられていた存在なのです。
『巫女の予言』や(共通の源から発したと思われる)「一覧詩」(スールル)などはドワーフに関する考えについてさらに多くの情報を与えてくれる大切な資料です。この名前一覧の中に、私たちは100以上のドワーフの名をみることができますが、明らかにこのほとんど全ては時代が下ってからのもので、またかなりのものが名が体を表すようになってもいるのです。
スノッリはドワーフをエルフの亜族とみなしていて、黒アゥルヴル![]() と呼んでいます。『高き者の言葉』(143, 160節)の中では、ドワーフが神々(アィシル)やエルフと並んで数えられています。このことは民俗信仰の反映と思われます。エルフは宗教的儀式の中である種の役割を担っているのに対して、人間たちは、ドワーフのことを単に自分たちの側(がわ)に属する(そしてほとんどの場合助け手として)生き物という認識が見られます。
と呼んでいます。『高き者の言葉』(143, 160節)の中では、ドワーフが神々(アィシル)やエルフと並んで数えられています。このことは民俗信仰の反映と思われます。エルフは宗教的儀式の中である種の役割を担っているのに対して、人間たちは、ドワーフのことを単に自分たちの側(がわ)に属する(そしてほとんどの場合助け手として)生き物という認識が見られます。
資料のテクストに寄れば、ドワーフが特にもともとから小さいと考えられたという記述はありません。この彼らが小さく、醜いものたちとした考え方は、数々のサガの中に初めて描かれた際に出てきます。それ以上に特徴的なのが彼らの知恵です。このことは彼らの何人かの名前に明らかに反映されています。例えば:アルヴィース(多くの智恵)、フョルスヴィズル(大いなる知識)、ラゥズヴィズル(賢い智恵を授ける者)といった名前が挙げられましょう。
彼らはしばしば技術が高いというように言われており、なかでも鍛冶屋としての技術は特別なことです。このことも、彼らの多くの名前に反映されています。例えば、ハナル、ニーラゥズル、ナィヴル、スキルヴィル、ドレイプニル、フャラル、ビヴルなど。ドワーフたちは、神々の持つ宝物のほとんどを造っています;ソールのハンマー「ミョルニル」、シフの黄金の髪、ヘイムダッルの指輪「ドロィプニル」、フレイヤの首飾り「ブリーシンガメン」と彼女の舟「ヒルディスヴィーニ」(「ヒンドラの歌」7節)。フレイルの見事な船「スキーズブラズニル」もまたドワーフたち、特に「イヴァルディの息子たち」と呼ばれるドワーフたちによって造られました。フェンリス狼に付けられた足かせ(グレイプニル)もドワーフの作品です。
11-12世紀のスカルド詩や13-14世紀に書かれたサガ群の中に繰り返し書かれているように、ドワーフは岩の中や山の下に住みます。木霊のことを古北欧語で「ドワーフの言葉」と呼ぶのも、ドワーフたちが山の中に住んでいると信じられていたことの証拠です。比較的後の時代に書かれた「伝説のサガ」の中には、ドワーフを捕まえるには、彼らの岩の前で見張っていろ、と書かれています。また『エッダ』詩「アルヴィースの言葉」には、賢いドワーフのアルヴィースが、岩の家の守りの外にいるとき、太陽の最初の一筋の光を浴びて石に変わってしまう様子を描かれています。さらに、彼らが賢く、また山の中に住んでいるという考え方から、彼らが「鉱夫」であり、様々な財宝を蓄えている、という考えが生まれてきました。この民間信仰は、現代にまで南ドイツで特に長い間保持されてきました。