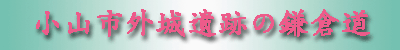 |
|
発掘された小山市の鎌倉道・・・3
|
 |
この外城遺跡で発掘された幅約12メートルの道路は、時代的にはいつ頃に造られ、いつ頃まで使用されたものなのでしょうか。現在の時点でははっきりしていないようですが、14〜16世紀の陶磁器などが出土していることから、この道路も14〜16世紀頃に使用されたものと考えられているようです。この道路は鎌倉時代まで遡れるようですが、その使用最盛期は鎌倉の都としての機能が衰えた後とも考えられるといいます。それにしても中世の道で幅12メートルというのは大変に大きなものです。
左の写真は道路の路面を撮影したもので段差は時期の異なる路面を示しているようです。 |
| 鎌倉の都としての機能が衰えた後の道というのでは果たして鎌倉街道と呼んでいいものなのか悩んでしまいます。この道路跡の場所は大字の外城と神鳥谷の境で、近くには小字名が「鎌倉道」というところもあるようです。今回発見された道路跡の周辺からは地図で示した外城遺跡の第4次と8次の調査で同じような道路遺構が見つかっています。また、南西側の宮内北遺跡でもやはり道路跡が出てきていることから地図の赤太線のような推定ルートが描けそうです。そしてそれらの遺跡の道路遺構から判断して、この道は鎌倉時代から戦国時代頃まで使用されたものであると考えられるようです。
右の写真は道路の硬化面で人が歩いた跡のようなシワも見られます。 |
 |
 |
|
南東側の側溝より幅約12メートルの道跡を見る
|
 |
左の写真は道路跡南西部の硬化面です。道路方向に沿っての幾筋ものわだち状の硬化層は道路補修の跡なのでしょうか? 硬化面を手で触ってみましたが、土というよりも石のように硬く締まった土になっていました。この硬化した道路面から並大抵の通行量でないことが素人ながらも想像できます。この道はある時期には間違いなく幹線道路であったものと思われます。奥州への奥大道(鎌倉街道中道)の可能性は大いに考えられる道路遺構だと思います。
|
| 幅12メートルの道というと古代駅路を想像します。遺跡からは奈良時代の竪穴式住居跡も見つかっていることから見学者の中からは東山道ではないのかという質問も出ていました。現在までの研究から東山道の推定ラインはこの遺跡よりもだいぶ北側を通過しているようなので、その可能性は少ないと思われます。ただ、東山道以外の伝路の可能性は全くないわけではなく、この遺跡から約3キロほど南西には古代寒川郡衙跡と考えられている千駄塚浅間遺跡があると説明資料に見られ、この道路遺構はその方向へ向かっているようなのです。
右の写真は上の写真付近を角度を変えて撮影したものです。写真中央の堀り残された土は発掘前の地表面を表しているのだと思います。 |
| 今回発見された道路遺構は中世の道路跡ではあるようですが、道幅が異常に広いのにも拘わらず、使用最盛期は現在の時点では中世の後半であるようです。これまでに確認された中世道路遺構と比較して、この道路遺構は特殊な分類になるのではないかと思われます。
外城遺跡の付近には地元の人達が鎌倉道と伝えてきている道があります。地図の赤細点線のラインがそのルートになります。従来までの鎌倉街道中道の解説書などには小山市内を通る鎌倉街道はだいたいがこのルートを説明していますが、この遺跡で発見された道路遺構はその従来の伝承ルートより南西の安房神社付近から東側にずれていて、しかも従来説の鎌倉道よりも直線的になっています。 更に外城遺跡の東側(JR東北線沿い)には小山氏関連の館跡としては古い「神鳥谷曲輪跡」があり、その曲輪跡のそばを通る道が一番古い鎌倉街道であるとの伝承も残っているようです。 外城遺跡のある小山市は中世には北関東の小山氏の拠点として居館・城郭ならびに宿が発達していたことが想定され、この付近を通る奥大道(鎌倉街道中道)は度々に変遷していて、北関東の重要拠点を通過する幹線道路は一時期にこの付近のみ広く造られていたことも想像できるのではないでしょうか。ホームページの作者はこの外城遺跡の道路遺構は一応に陸奥へと向かう鎌倉街道中道本道と推定したいと思いますが、中世初期段階(鎌倉時代)の幹線路は或いは別のところに埋もれている可能性も残っています。 |
鷲城跡
 |
 |
 |
||
|
鷲城の土塁跡
|
鷲神社
|
鷲城の遺構
|
 |
鷲城は道路遺構が見つかった外城遺跡内にある小山氏関連の中世城郭です。先に説明させて頂いた小山氏関連の居館・城郭五つの中の一つです。道路遺構が発見された場所から北北西に500メートルほど移動したところに鷲神社があり、この神社のある平坦地は鷲城の中城(本曲輪)にあたります。鷲城は南北約450メートル、東西約280メートルの範囲の中央に大きな東西方向の堀があり。堀の北側が中城でここが城の中心施設があったところといわれます。中城は北側は思川の浸食崖(高さ10〜15メートル)になっていて、思川を見下ろす北東角には櫓台も残されていて、その近くに船場という地名があり船着場があったと考えられています。
左の写真は中城と外城を分ける堀から延長する西側の堀と土塁の遺構です。 |
| 中城に対して中央の堀の南側は外城といい、第二の曲輪になっています。外城は現在の地名にもなっています。鷲城の名前は武蔵太田庄の鷲宮を小山氏がこの地に勧請したことが由来になっているようです。鷲城の築城年代ははっきりしていませんが城跡地から出土している遺物が15世紀を中心としたものが大半で、それ以前に遡る資料が少ないことから14世紀頃の築城と考えられているようです。この城は「軍忠状」などの文献史料に登場していて関東各地に残る多くの中世城郭の中では比較的に、その歴史過程がはっきりしている城なのです。
右の写真は中城にある鷲神社の参道を撮影したものです。参道の入口の鳥居前の南北方向の道は鎌倉道と伝えられています。 |
 |
| 小山義政と鎌倉公方足利氏満の戦い
康暦2年(1380)から永徳2年(1383)におよぶ小山義政の乱において鷲城をめぐる記事が載っています。この乱の切っ掛けは康暦2年に義政が宇都宮基綱を攻め滅ぼしたことから、鎌倉府の足利氏満自身が小山に出陣し義政を攻めるものでした。永徳元年(1381)の攻防戦では義政が鷲城に立て籠もり10ヶ月もの期間、鎌倉府軍と戦いますが、義政は鷲城を開け渡し祇園城に退いて一旦戦いは休止します。その後、義政は家督を子の若犬丸に譲り出家して永賢と号しますが、永徳2年に義政は祇園城を脱出して粕尾(粟野町)山中に立て籠もり再び蜂起し、最後は追いつめられて自害します。 義政の亡き後に若犬丸が至徳3年(1386)に再び挙兵しますが逃走して後に会津で自害します。ここで小山氏の正統は耐えるのですが結城氏より泰朝を迎えて再興するのでした。 さて、3度にわたる小山氏の乱で鎌倉府の足利氏満軍が小山へ向けて侵攻したルートは鎌倉街道中道ではなく、武蔵府中経由の鎌倉街道上道で、途中の比企郡から村岡、永井の渡、新田庄、足利庄、小山という道順であったといいます。何故、このような大回りのルートを選んでいるのかははっきりしていませんが、この時代の古道研究のヒントの手がかりがその中に或いは隠されているかも知れません。 その後の歴史では永享の乱、結城合戦など、ここ小山の地は戦場となることが多く、享徳4年(1455)に足利成氏が古河へ移ってからは小山は地理的に近いということで、古河公方家の内紛に小山氏は巻き込まれることが多かったものと想像がつきます。 |