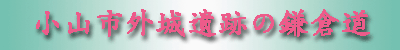 |
|
発掘された小山市の鎌倉道・・・2
|
| ここからは発掘で確認された鎌倉道について見ていきましょう。右の図は現地説明会の配布資料に載っていた道路遺構の断面図を基に新たに作成した図です。この図では4時期の道路の変遷が記されています。当初の道路は両側に大きな側溝を持った幅約12メートルの切り通し状に造られていたことがわかります。 | 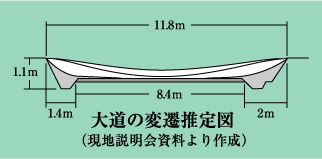 |
 |
道路はその後には側溝が埋められ碗底のような掘割状の道となり、更にその後は数度の改修を受けながら長く利用され、道路の中央部分のみが窪んだ道へと姿を変えていったこことが上図からうかがえます。 左の写真は遺跡調査地から確認された幅12メートル道路の北東端部分で、この北東端箇所は道路建設当初の路面と側溝まで掘り込まれていました。手前の一段高い硬化面は確認された一番新しい道路底面であると思われます。 |
| 右の写真は道路を北に向かって右側(東側)の側溝を撮影したものです。道路建設当初の路面幅は8.4メートルもあり、上の写真でもわかるようにほぼ平な状態で造られていたようです。路面には舗装が施されていたようですが、それが具体的にどのようなものであったのかはわかりませんでした。この遺跡の道路跡には他の道路遺跡などでよく見られる波板状の凹凸や底面のピット列などは見られないようです。 |  |
 |
 |
|
|
上の写真と同じ側溝で南東端部分
|
道路遺構上の地層
|
 |
 |
|
|
道路南西部に見られる土抗
|
道路跡の西に接続していた別の道跡か?
|
|
外城遺跡周辺における史跡と中世の小山氏について 小山氏 寿永2年(1183)に常陸国の志田先生義弘が源頼朝に対して挙兵しました。これに対し小山朝政は野木宮で頼朝側として志田義弘を打ち破り功を得ました。小山氏は鎌倉御家人の中でも屈指の勢力を有し、この地を拠点として以後中世の動乱の中で活躍しますが、天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原北条氏攻略のさいに祇園城の落城と共に小山氏は歴史の表舞台から離れて行ったのです。 小山氏関連の城 小山氏の拠点に築かれた中世都市 更に祇園城の近くには文献などに見られる「天王宿」と呼ばれた宿場が存在していたようです。天王宿の名前は現在の須賀神社の元名で牛頭天王社(祇園社)に由来するといい、天王宿は鎌倉時代まで遡ると考えられています。祇園城の名前も牛頭天王社からきていると見られ、牛頭天王社は藤原秀郷が京都の八坂神社を勧請したという古い伝承もあるようです。 天王宿の墓域 後の時代の「小山評定」跡地 |
 |
|
道路跡を北東側から南西側を撮影
|
| 幅約12メートル道路から東西に延びる二条一体の溝は、幅12メートル道路とは構造が異なる道路跡の可能性が指摘されていて、ある時期にはここが交差点であったとも考えられるそうです。この遺跡地から西へ向かうと中世の小山氏の鷲城へ向かい、反対の東に向かうと行人塚跡地へと進みます。行人塚跡地から東北線に沿ってしばらく北東へ進むと小山氏の館跡と考えられている神鳥谷曲輪があります。
右の写真は幅12メートル道路を横から見たものです。手前のピット列は現在は用途不明のものだそうです。 |
 |
| 後述 上記の幅12メートル道路と交差する二条一体の溝は、その後の報告会によると道跡ではなく、区画溝であったことが確認されたようです。 |