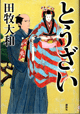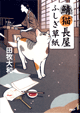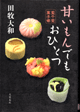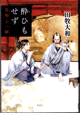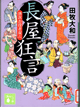| 11. | |
|
●「盗 人」● ★★ |
|
|
|
ピカレスク小説(悪漢小説)と簡単に言ってしまうには、本書主人公の甲斐、凄味があり過ぎます。 ゾクゾクっとするような怜悧な凄味を感じさせる処がこの主人公の魅力。しかも、どこに本心があるのか誰も掴み切れない、という底知れ無さあり。 本書の魅力は、この甲斐というキャラクターの魅力に尽きる、と言って良い作品。 江戸で評判の良い口入屋=えびす屋。ところがその裏の姿は盗賊「幻一味」。頭目は当然ながら主の源右衛門なのですが、実質的に一味を仕切っている裏の頭目は、店では愚鈍な下働きと思われている甲斐に他なりません。 一味の誰も、裏頭目の存在、しかもそれが甲斐であるとはまるで気付いていない、という手の込んだ設定。しかも甲斐は源右衛門が旅先で関わった女に産ませた庶子で、父子であるとは誰も知らず。そして実の父子とはいえ、源右衛門と甲斐はかなり微妙な力関係のバランスの上に乗っている、という風。 そんなえびす屋の面々に加え、歴史上の人物=高野長英が甲斐を超える悪辣なキャラクターとして顔を並べ、さらに盗賊「鬼火」の少年頭領=秀宝が甲斐と張り合うといった、見事な顔ぶれ。 この3人の連環はただものではありません。「三悪人」をはるかに凌駕する凄さあり、と言って間違いないでしょう。 さてその甲斐、江戸市中をどんな風になって吹き抜けるのやら。 本作で田牧さん、新たな段階へ一歩踏み出したという印象です。 螺旋/侘びる椿/葉月の桜/鬼が翳す灯/昔語り−ことのはじめ/梅蛇香/鬼が焚く灯/紅の蓮 |