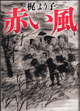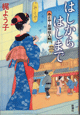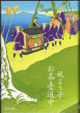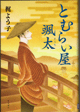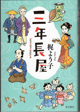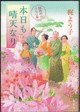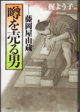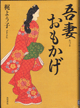| 「赤い風」 ★★☆ | |
|
2021年04月
|
水が出ず、粘土地ということもあって草を採取するしかない“秣場(まぐさば)”として放置されていた武蔵野台地。 その一方、川越藩領内、幕府直轄地、その他が複雑に関わる入会地だったため、農民らの間では長く諍いが絶えなかった。 その川越藩の新たな藩主となったのが、五代将軍綱吉の側用人を務める柳沢保明(後の吉保)。 その保明は、川越藩領をはっきりさせたうえで、武蔵野台地での新田開発を家臣・領民に命じる。民に福をもたらすという信念の下に保明は、その土地を「三富新田」と名付けます。 本作は、その新田開発の労苦を描いた長編ストーリィ。 題名の「赤い風」とは、乾いた土を巻き上げて辺りを赤く染め視界を閉ざす、その土地に吹く春と冬の季節風のこと。 面白いかどうか、少々疑い気分で読み始めた本作でしたが、冒頭からその読み応えにぐっと鷲掴みされました。 そもそも時代小説というと、武家もの、市井ものが殆ど。それらに対して本作や帚木蓬生「水神」は、江戸時代におけるインフラ整備の史実を元にした長編。それらはまさに、日本が発展してきた土台にある史実に他ならず、読みながら感激を覚えます。 そしてその中で、武士と農民、支配者階級と非支配者階級、真剣に取り組む者と自分の儲けしか考えない者といった対立構図、共存構図が様々に描かれます。 そこから最後に浮かび上がってくるのは、人間としての覚悟、価値の様、という気がします。 幾つもの困難、幾つもの対立構図、そしてそれを超えたところにある洞察、信念を描き出す力作時代長編。 土地開拓と人間への興味をかき立て、読み応えもたっぷりです。 是非お薦め! ※なお、「三富新田」、今は埼玉県指定旧跡になっているようです。 1.秣場(まぐさば)/2.国替え/3.三富/4.黒鍬/5.付け火/6.富と福 |