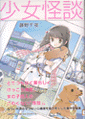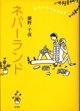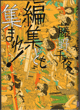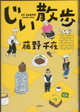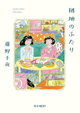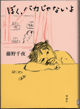|
●「少女怪談」● ★ |
|
|
|
「少女怪談」という題名から、少女が恐ろしい世界にちょっと足を踏み込んでしまう、あるいは少女の持つ怖い部分を描いた短篇かと思ったのですが、それ程怖い、と思うような部分はありませんでした。 しかし、ちょっとした気まぐれから見知らぬ少年の大事な愛犬を黙って連れ回してしまったり、自分をからかった男子高校生に生き霊としてとりついたり、さらには父親と従姉の怪しげな親しさに気付きながらわざと知らんぷりする、誘われるまま謎の屋敷に入り込んでみた挙句大騒ぎしてみたりと、やっぱりそこにはこの年代の少女がもつ特有の危なさ、怖さが覗き見えます。
さらっと短い4篇のみからなるごく薄い短篇集のため、読後感はあまり強く残りません。 一方からみれば小悪魔的な少女の魅力というものなのかもしれませんが、私は体験したことがないので、ピンと来ず。 ペティの行方/青いスクーター/アキちゃんの傘/ミミカの不満 |