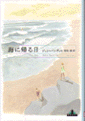| 1. | |
|
●「海に帰る日」● ★★☆ ブッカー賞・フランツ・カフカ賞 |
|
|
2007/09/15
|
60代の老美術史家マックス・モーデンは、少年の頃過ごした海辺の町へ戻ってきます。 彼は最愛の妻アンナを病気で亡くしたばかり。 そのマックスの脳裏には、少年の頃海辺で知り合ったグレース一家とのこと、死病を宣告されたアンナとの最後の日々のことが、渾然一体となって蘇ってくる。 現在と遠い過去、そして近い過去をめぐる老マックスの心中を、まるで時を超えて浮かび上がらせるように書き綴った長編作品。 人生の晩年になると、人は忘れ難い思い出を目の前に蘇らせ、再び味わおうとするものなのでしょうか。 少年マックスがこの海辺で、ミセス・コンスタンス・グレースの豊かな太股や胸の丸みに恋焦がれたこと、次いで彼女の娘クロエとの間に芽生えた恋のこと、そして最後にクロエが双子の弟マイルスと一緒に海に消えた日のこと。 ふとコレット「青い麦」を思い出しました。同じく海辺、年上の女性、幼馴染の少女との恋を描いた名作。 |