
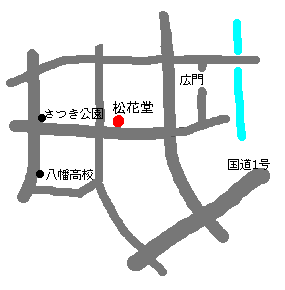 し ょ う か ど う しょいん
し ょ う か ど う しょいん
 松花堂書院
所在地:八幡市八幡女郎花
松花堂庭園の西側にある書院は、もとは男山泉坊の客殿であって、永禄3年(1560)の建築で小早川秀秋が寄進したと伝えられている。また、玄関の車寄せは、桃山城の遺構とも伝えられ、扉についている桐の葉の彫刻は、豊臣秀吉から拝領したといわれている。 |
 目次へ
目次へ

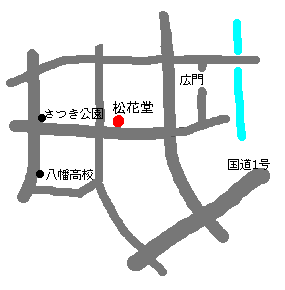 し ょ う か ど う しょいん
し ょ う か ど う しょいん
 松花堂書院
所在地:八幡市八幡女郎花
松花堂庭園の西側にある書院は、もとは男山泉坊の客殿であって、永禄3年(1560)の建築で小早川秀秋が寄進したと伝えられている。また、玄関の車寄せは、桃山城の遺構とも伝えられ、扉についている桐の葉の彫刻は、豊臣秀吉から拝領したといわれている。 |
 目次へ
目次へ