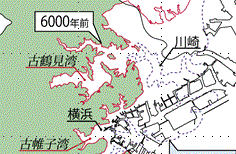大塚・歳勝土遺跡・横浜市歴史
博物館
2015年12月22日(火)、小机城跡・茅ヶ崎城跡に引き続
き歩く訪。全行程は下図の通り。
茅ヶ崎城跡から早渕川を茅ヶ崎橋で渡って大塚・歳勝土遺跡の南側の旧道に出る。これを少し旧中原街道に向かい東に歩く。そこからフォレストパーク四季采の
丘」に上る階段を見つけて登
る。フォレストパークは私有地だが、ここから大塚・歳勝土遺跡まで公開空地を歩ける。
やがて都築民家園なるものがあり、江戸時代中・後期の民家で旧牛久保村で名主をつとめていた長沢家が移築されて建っている。主屋の形式は「ヒロマ型」で、
主屋と馬屋が平行に建てられていて武蔵南部特有の形をしている。
 長沢家
長沢家
歳勝土遺跡(さいかちどいせき)
長沢家の西に環濠集落大塚遺跡に住んだ人びとの墓地である歳勝土遺がある。方形周溝墓とよばれる形をしていて、低い四角形の盛り土と、その四辺を溝で囲ん
でいる。

方形周溝墓
大塚遺跡
約2000年前の弥生時代のムラの跡。外からの敵を防ぐために周囲には濠がめぐらされていた。当時は100人くらいの人々が暮らしていたという。
遺跡内には、竪穴住居7棟をはじめ高床式倉庫、型取り遺構、木橋などが復元してある。
 大塚遺跡
大塚遺跡
横浜市歴史博物館
大塚遺跡から坂を下ったところに横浜市歴史博物館がある。ロビーでかっての紙芝居の実演を見ながら疲れをいやす。
常設展示はつまらなそうなのでパス。特別展のパンフレットをもらう。縄文時代の称名寺貝
塚(BC4,000)や弥生時代の三殿台遺跡(3世紀)につ
いての展示ついてだ。
鶴見川と早渕川は6000年前の縄文海進のころは古鶴見湾となっていた。鶴見川は広く、早渕川は狭い。
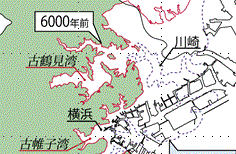
古鶴見湾
早渕川南岸台地には旧石器時代に始まる北川貝塚(BC31,000-BC23,000)があった。検出層位は姶良(あ
いら)Tn(た
んざわ)火山灰(29,000-30,000年前)である。これより下層の3万年前から平安時代までの遺跡が層状に出土する。ちなみに姶
良Tn火山灰の名は丹沢で
初めて見つかったため。
早渕川北岸の南山田には南掘(なんぼり)貝塚があった。セン
ター南駅西側にある早渕川南岸の都築中央公園には境田貝塚、茅ヶ崎公園の水辺には茅ヶ崎貝塚がある。
鶴見川の上流の谷本川東岸には縄文草創期の花見山
遺跡(BC14,000)、三の丸遺跡、二の丸遺跡、旧石器時代の四枚畑(しまいばた)遺
跡(BC19,000)がある。更に
北上すれば古墳時代の市ヶ
尾横穴古墳
群や稲荷前古墳がある。
グリーンランド氷床に閉じ込められた酸素18同位元素比率野尻湖湖底の花粉落葉広葉樹の比率から1.6-1.2万年前に温暖化し石器時代から縄文時代に
入ったとされる。
港北ニュータウン
横浜歴史博物館からニュータウンセンター北駅に向かって歩く。やけにに巨大な立体駐車場があるが、サビがでていてメンテナンス資金不足を想像してしまう。
十分
な収入のあるだけの住民がいないのではないかといぶかる。商店街もさびれている。官製都市開発の失敗のようにも見える。駅前の阪急デパートのみにぎわって
いた。ここでクリスマスカードを購入。
新規造成型ニュータウン造成の例としては千里ニュータウン、多摩ニュータウン、筑波研究学園都市、港北ニュータウンがあるがいずれも高齢化と人口減少でさ
びれてきている。入居時に同じ世代の人ばかりを入居させた為にこのようになった。売りたくとも売れない。千葉ニュータウンなどはバブル崩壊で途中で頓挫し
た結果、団塊の世代問題はない。
December 26, 2015