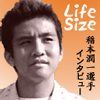稲本潤一選手 スペシャルインタビュー
LIFE SIZE 等身大のプレミア生活 |
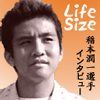 |
| 3/3 |
 |
| 写真提供=ジェブエンターテイメント |
◆3章
イチ、ニイ、サン……。4歳から13歳までの子供たちの人数を確認していると、隣で「本日71人」と、コーチが教えてくれる。
稲本と、同じ齢のチームメイトMFのショーン・デイビス、そして井上氏と私の4人は、練習場から車で15分ほどの所にある警察のグラウンドに立っていた。プレミアでデビューを果たした稲本にとって、今日は2度目のデビューである。「コミュニティ・アクティビティ」、いわば、「地域デビュー」とでも表現すればいいか、フルハムが地域振興、交流を目的に行うさまざまなイベントに、選手が参加する日である。
審判をする者、養護施設を訪問する者など役割分担はそれぞれで、2人は子供のスクールでサインをし、質問に応じることになった。稲本が練習中のグラウンドに入って行くと、子供たちが「イナモトオ!」と声を上げ、コーチが「座りなさい」と何度言っても、興奮状態は収まらなかった。
「凄いね」
声をかけると、隣でショーンが笑う。
「全くだ。僕になんて気が付かないんじゃないか。僕らにとっても嬉しいことだよ。W杯で2得点した選手が加入したことはね」
子供たちからの質問が始まる。
元気よく手をあげた後方の男の子。
「なぜ、アーセナルで出場しなかったの」
ショーン、チーム関係者、誰より本人が、その質問にのけぞって笑い出してしまった。
「そんなあ」日本語でつぶやいてから、「ベンゲル監督に聞いてみてよ」と優しく英語で言った。サッカーを始めたのは、このくらいの年齢だったはずだ。ノートの切れ端にサインをもらおうと、子供たちが2人の前に長い列を作る。メディアへの公開は年4回でも、こうしたボランティア活動は実に頻繁に行う。フルハムユースに将来つながる強化の一貫としても重要な集会なのだ。そういう行事にも、随分と慣れてきたのだとわかったのは、稲本の様子に理由があった。
71人全員、それも子供だけにサインをし写真を撮るなんて、これもなかなか重労働だとふと気がつくと、稲本はサインをしたあとに、子供の頭を優しくなでたり、ホホにそっと手をあてたり必ずスキンシップを入れている。子供たちはサインより、その仕草が楽しみにさえ見える。頭をなでてもらうと首をすくめ、嬉しそう笑い、スキップして列に戻る。
「サッカーを始めたのはこんな年頃かな」
預かっていたミネラルウォーターのボトルを返しながら、私は聞いた。
「ええ、そうですね。あんくらいの時でしょうね。憧れの選手も目標の選手も特別にはいなかったんじゃないかな。しかし、何で起用されなかったか、なんてよう聞かんわ」
コミュニティデビューの出来は上々で、コーチたちは、稲本が英語を「十分に」理解していることがわかった、と言い、付き添いの父母たちは、「なかなかのナイスガイね」と握手を求めていた。
「じゃあまた明日! 僕は広報の車で送ってもらうから。ここで」
ショーンは稲本に向かってそう叫んで、車に乗り込んで行った。最初は簡単ではないが、彼がW杯で見せたパフォーマンスは間違いなく、相手チームのプレッシャーになっているし、そのことがフルハムに与えたプラス要素はとても大きい──それが同じ中盤を任されるショーンの、稲本への見解だった。
サポーターを熱狂させるゴール、静かな環境に守られた練習や、こうして地域で肩の力を抜いて取り組むボランティア活動や交流、自宅で過ごす普通の毎日。どれもこれもがプレミアでの生活であり、すべてのバランスがようやく整い始めた今、ミスをすることやベンチを暖めたまま試合に出ないこと、スランプが襲ってきたり、例えば一時的に故障に苦しんだとしても、リザーブリーグにさえ簡単には出られなかった一年を思う時、恐れるものではないはずだ。
「全然大丈夫だと思う。今わかっているのは、右肩上がりのサッカー人生なんてそうはないってことです。いい時も悪い時もあるけれど、俺は怖くはない。だって去年はスタンドにいたんですよ、ファンと並んで」
結局のところ、それがピッチで目に見えない戦いだとすれば、周囲が、この移籍が失敗だ、パフォーマンスが落ちた、と目に見えるものだけを論評したところで、意味がないのだろう。稲本は、もしかすると、ピッチでアンリやベルカンプと対面する以上のエネルギーと忍耐をもって、初めてベンチに座る自分と向き合っていた。そしてそれが、どこまで強い芯によるものだったのかは、インタビューで明らかになるのではなく、ようやく目に見える形で表ににじみ出てくるに過ぎないのだ。
 |
| 写真提供=ジェブエンターテイメント |
そういえば、ビートルを選んだことに興味があった。かつて私自身が乗っていたのと同じだという郷愁からではない。長い付き合いだったが、今のは洗練されたデザインに変わっている。それでももう少し高級な、海外で成功を収めつつあるサッカー選手にふさわしい、スタイリッシュな車が、何かありそうな気がしたからである。日本ならば、選手は、メルセデスに乗るだろう。そう、ポルシェもある。
「どうでもいいんだけれど、ビートルってどうしてなの?」
「本当のところ、自分でいたいっていうか、嫌なんですよ、今そんな高い車に乗ってしまうんが。もう終わりって感じがして」
「そんなことないでしょう。今の収入だったらほかにもありそうだけど」
「いいえ、上がって行きたいんですよ。一段一段でいい、毎日上がっていく自分に、車はふさわしければそれでいいと思うんです。いい車に乗って頑張ろうっていう選手もいますよね。でも今の自分には、これくらいがちょうどいい」
ロンドンで過ごした2日間、彼の周囲に漂っていたのが、ビートルを今の自分の「等身大」だと楽しめるような、心地良さだとわかるような気がする。一段、一段、決して抜かしたりせずにじっくりと登って行く姿は、確かにあの黒いカブトムシに重なる。次の車は何か、聞いておかなかったことを、少し後悔している。
「ではまた、今度はジーコ監督初の試合で帰国するんでしょうか」
「まあね、呼ばれないことには。でも中盤も厚いよね、もの凄い選手ばっかり。何とかアピールしないとならない」
「守って決めて走れるMFとして?」
「ですね。じゃあ、気をつけて」
握手をする。手入れが行き届き、花が咲き誇る住宅街に消えるビートルを見送った。
ウインドウを開けて、稲本が右手を振った。
(「SPORTS Yeah!」No.050・2002.9.7より再録)
|