第14章 北海の巨王(その1)
デンマークのスウェイン王は、遠路はるばる訪れて来た従兄弟のトステ
ィ卿を暖かく迎えた。
だが、イングランド侵攻と、新王となった兄ハロルドへの復讐を熱っぽく
語るトスティ卿に対して、スウェイン王は物静かに答えた。
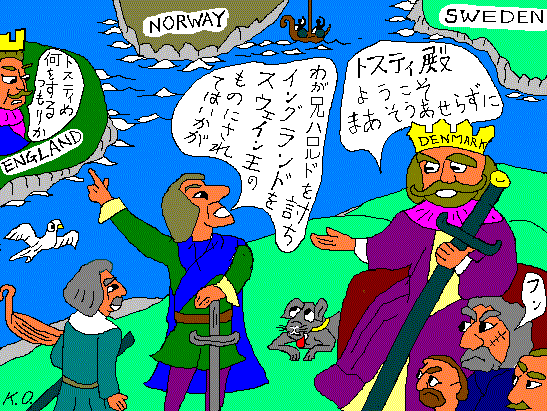
「トスティ卿、貴殿の気持ちは良く判った。しかし、我が輩の器量は、拙
者自身が一番良く知っとるつもりじゃ。どんなに逆立ちしたって、我が
輩には伯父のカヌート大王のような天賦の才はない。
このデンマーク一国を外敵の侵略から守り、国内の諸部族を統治する
ことすら大変な重荷なのだ。
現に、ノルウェー王ハラルド・ハードラダとやっと休戦したが、16年間も
戦ってきた」
「よく承知しております」
「ハラルド・ハードラダの奴はなあ、我が輩がイングランドへ出発すれ
ば明日にでもこのデンマークに攻め入るだろうよ」
「ノルウェー王とは休戦協定を結ばれたのではありませぬか」
「何の、なんの。あの男は平気で約束を破る奴だ。奴にゃひどい目に
あった」
スウェイン王は昔を思い出し、腹立たしげに麦酒を飲んだ。
「かれこれ20年前になるが、奴はロシアのノブゴロドで貰ったエリザ
ベスという別嬪の女房を連れて、スェーデンの我が輩の館に転がり
込んで来よった。
その留守の間に、当時のノルウェーの王マグナスがこのデンマーク
を占領したので、ハードラダと連合してデンマークに戻ったのさ。
ところがこのマグナスはハードラダの甥で一癖も二癖もある奴でな、
叔父になるハードラダと手を握り、ハードラダはコロッと寝返ったのさ。
いきなり両軍がわが幕舎に襲い掛かってきた。あの時は九死に一生
を得て、スェーデンに逃げ帰ったよ。
奴は必ず弱みにつけ込んで、侵略してくる男だ。戦いに憑かれた男
だ。デンマークとスウェーデンを留守にはできぬ」
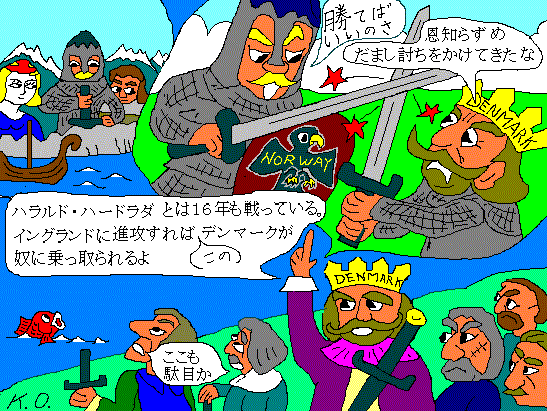
「それよりも、どうだトスティ卿。兄への仕返しは止めて、我が輩の片
腕としてこのデンマークに留まらぬか」
この言葉はトスティ卿には予想外であった。
ヴァイキングといえば誰でも戦を好む輩であろうと期待していたトステ
ィ卿にとっては、諄諄と説得するスウェイン王に、最早何の魅力も感じ
なかった。
一方、スウェイン王は、この思慮浅いトスティ卿を道連れとして、貴重
な一生の成果を反古にするような、危ない賭けに出るつもりは毛頭な
かった。
会議の場はしらけた。顔一面に失望の色を隠そうともしないトスティ卿
の様子を、人生経験豊かなヴァイキングの王は、憐れみを持って見詰
めていた。
もう少しデンマークに滞在をすすめるスウェイン王の申し出を断って、
トスティ卿は直ちに船を出した。
トスティ卿は、このスウェイン王と戦を続けてきたノルウェー王ハラルド・
ハードラダに面会してみようと、船首を急遽北西へ向けた。
<当たって砕けろ。駄目でもともとだ>
今は不敵な面魂の、性根の据わったトスティ卿であった。
「ハラルド・ハードラダは、ヴァキングの中でも最もヴァイキングらしい男
だ」
「身長は7フィート(約2メートル)を超す大男で、金色の髭をぼうぼうと
生している」
「無学文盲であるが、本能的に謀略に長けている」
「戦争が三度の飯より好きという豪傑だそうだ」
寄港する町々での噂を聞けば聞くほど、この豪雄ハラルド・ハードラダ
王を何とか口説かねばならぬと、トスティ卿は心に固く決めていた。
トスティ卿の船は、切り削ったような絶壁と雪を頂く山々の影を映してい
る波静かなオスロー湾の、美しいフィヨルドに投錨した。
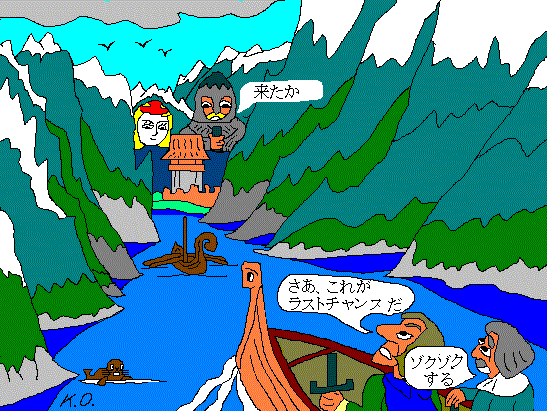
第14章 北海の巨王(その2)
いざないと目次へ戻る
「見よ、あの彗星を」Do You Know NORMAN?へ戻る
ホームページへ戻る