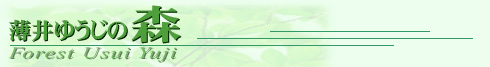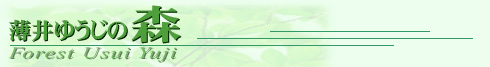|
午後の陽が射している。僕が住んでいる小さな町の大通りは、この時間になるとひっそりとしてしまう。男たちはみな遠い町へ働きに出て夕方まで帰らないし、女たちはすべての家事を済ませて夕方の買物までの時間、家のなかで静かに息を殺しているからだ。
大通りは東から西へまっすぐ延びていて、その両側に必要最小限の店舗が建ち並んでいる。古い雑貨屋と食料品店とコンビニエンスストア。郵便局と小さな銀行、そして夜になると一瞬だけ開く居酒屋。それがすべてだ。ゴーストタウンでないとかろうじてわかるのは、それらの店が静かに息づいていて、たったひとつ大通りのなかほどにある信号機が、気怠そうに点滅しているからだ。
僕はこの町で生まれた。両親が残したこの古い家は大通りに面していて、居酒屋の三軒西隣りにある。僕の仕事部屋の窓から首を出すと、通りの東の端から西の端まで、ぜんぶ見渡すことができる。この季節、僕は窓を大きく開けたまま仕事をする。通りを往来する車の数は少なくて、人通りも、仕事の邪魔になるほど多くはない。新鮮な風だけが静かに窓から入ってくる。僕はこの家とこの仕事部屋を、とても気に入っている。
午後一時二十五分、今日も遠くから足音が聞こえてくる。ハイヒールの音だ。それは大通りの東からゆっくりと近づいてくる。居酒屋の前まで来るといちど立ち止まり、そしてまた歩きはじめる。やがて足音は僕の仕事部屋のすぐわきの歩道を、静かに通り過ぎていく。僕の机は窓ぎわに置いてあるから、彼女は距離にして一メートルも離れていない場所を通過するわけだけれど、なんだかとても遠い、遥か彼方を通り過ぎていくような感じがする。それは、僕が彼女の名前さえ知らないことに関係しているのだろう。僕はそのことが、とても心地よい。
彼女はそのまま西の端まで歩いて行って、こんどは通りの反対側をゆっくりと戻ってくる。骨董品も並べている古い雑貨屋に立ち寄り、すぐに店から出てくる。そしてすこし離れた郵便局に入る。なぜ毎日、郵便局へ行くのか、その理由はわからない。郵便物を出す用事が毎日あるのだろうか。それとも自分宛てに手紙が届いていないか、窓口で確かめているのだろうか。
彼女は間もなく郵便局から出てきて、また東のほうへ歩く。そして町にたったひとつだけある信号機のところで立ち止まる。信号が青であっても必ず、次に信号が青になるまで待ってから横断する。そして東へ。やがて彼女の足音は遠ざかり、町の東端で消える。
そんなことがもう、三年もつづいている。毎日、同じ時間にだ。僕がそのことに気づいてから三年経ったという意味だから、もっと以前から彼女は、そうしているのかもしれない。いずれにしても毎日同じ時間に現れて、決まって同じ店に立ち寄りながら通りをゆっくりと往復するのだ。
名前も知らないし、どこに住んでいるのかもわからない。僕は彼女の顔でさえ、まともに見たことはない。部屋の窓のすぐ近くを通るとき、よほどちゃんと見ようと思うことはあるけれど、目が合ってしまったら、お互いにバツのわるい思いをするような気がして、まともに顔を上げられないのだ。だから通りのむこう側を東のほうへ戻っていくときに、ちらりと横顔を見るだけだ。小さな町のわりには広い通りなので、僕の視力では彼女の正確な顔をたしかめることはできない。ぼんやりと輪郭がわかる程度だ。
彼女は若い。それは遠くからでもわかる。服装とか身のこなし、そしてゆっくりとした歩みだけれどリズムを取りながら歩く姿は、たぶん二十四歳くらいじゃないかなと思う。彼女はいつも、楽しそうに歩く。そして彼女は美人−−だと思う。そう思うことにしている。双眼鏡で顔をたしかめたりする方法もあるけれど、この町ではそんな乱暴なことはできない。町は一見ひっそりとしているみたいだけれど、家々の窓の奥では、通りの様子をうかがう主婦たちの視線が無数に光っているはずだ。いちど通りで小さな交通事故が起きたとき、あっという間に百人以上の女たちが家から走り出てきた。だから双眼鏡で通行人を覗いて見たりしたら、犯罪者扱いされてしまうにちがいない。そういうわけで僕は、彼女が何者かを知らない。いつか声をかけてみたいと思うのだけれど、そのきっかけをつかむ方法さえ知らない。
こつ。こつ。今日も同じ時間にハイヒールの足音が聞こえてくる。僕は窓から視線をはずして仕事に熱中しているふりをする。足音はいちど居酒屋の前でとまり、やがて僕の窓のそばを通る。こつ、こつ。僕は顔を上げたりはしない。 |
|