Ibanez TS10のブレットボードレイアウト
以前アップした「
Ibanez TS10の正しい回路図
」で、
動作確認のためにTS10の回路をブレッドボードで再現しました。
その時のレイアウトを公開します。参考まで。
入力バッファ、出力バッファを含んだレイアウトです。
入力バッファ、出力バッファまで含めないと、TS9,TS080との回路上の違いが無くなってしまいます。
さらには、電子スイッチにあたるjFETを通過させています。
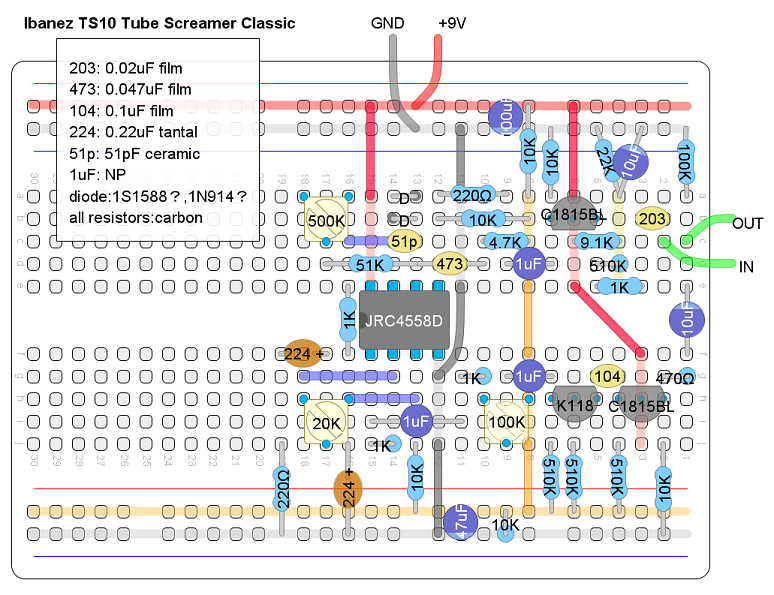
↓回路図
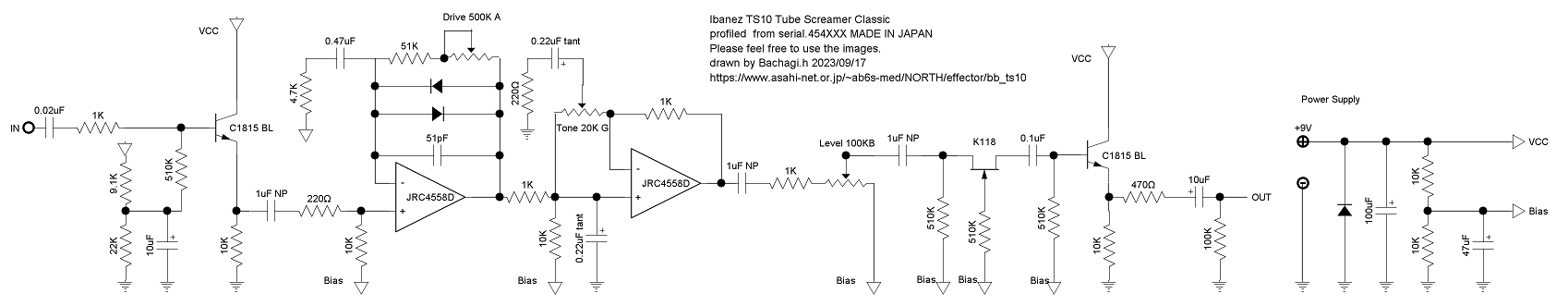
jFET(K118の所)は、スイッチとしては常にON状態固定となっていて、機能的には無意味です。
しかし、jFETは実際に音声信号が通過する箇所であり、何かサウンドに影響するやも知れぬ、
という探究的な意味合いで入れてあります。
実際に構築してみるとこんな感じ
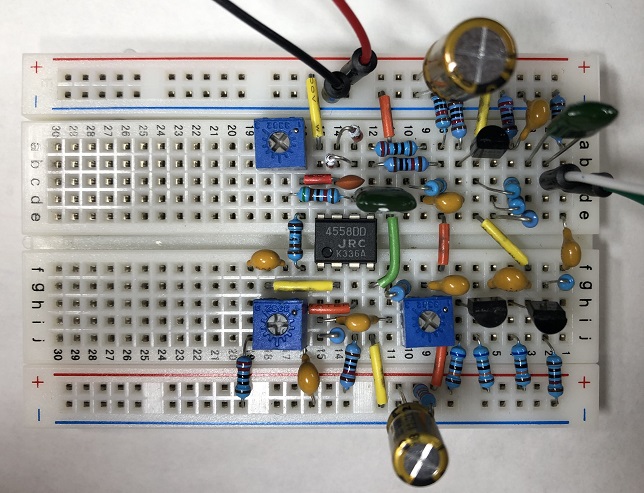
ピンアウトの配列が異なるトランジスタやjFETで代用する場合は、
足に合わせて接続するCやRの挿し位置を変える必要があります。
写真では、各所手持ちのパーツで間に合わせていますが、
基本TSという事もありますし、これで当然のように良い音が出てしまいます。
オペアンプやダイオードを挿し替えて、サウンドの違いを見るのも楽しいです。
コンデンサ容量誤差について
一点、TS系の回路では、トーン段の0.22uFに誤差があると、明るさの印象の違いが目立つようです。
実物のTS10と聞き比べると、割と違いを感じたので、F特を調べてみました。
TONE20K可変抵抗に繋がっている0.22uFを、
手持ちのコンデンサ2種類でどれだけ周波数特性に差が出るか比較したものです
測定条件:Drive=0, Tone=5, Level=10
赤線:フィルムコンデンサ0.22uF(安物)
黒線:積層セラミックコンデンサ0.22uF(安物)
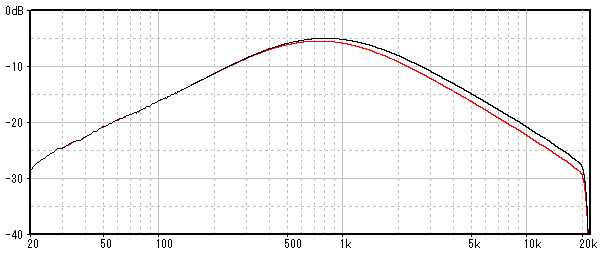
手持ちの2種類でこんなに差がありました。ここまで差があると音として違いが出てきます。
実物のTS102台(JAPANとTAIWAN)を測定してみましたが、上の赤黒の中間くらいの特性で、実物2台どうしは、ほぼぴったりでした。
タンタルの精度が効いてますかね。
0.22uFに、小さいコンデンサを並列で加算して、誤差を補正してF特を実物に合わせてみると、
それだけで出音がかなり似た感じになってきます。
もう1つ、TSはドライブ段から1KHzの抵抗を介して0.22uFでグランドに落としている箇所もあります。
ここは1KHzと0.22uFでLPFを形成するのですが、1KHzってわりと小さい選定で、
オペアンプ自体の出力インピーダンス分(50Ω前後)が、1KHzを加算してLPFのカットオフ周波数が決まるので、
使用するオペアンプによって差が出やすいかも知れません(測定した事は無いですが)。
また、1KHzというのはオペアンプの負荷抵抗としても低いと思うので、
この点でもオペアンプによる音の違いが出やすそうな気がします。
ちなみにBOSSのSD1は、この抵抗が10KΩになっているので、オペアンプ変更による上記の影響は少なそうです。
その他で、容量誤差が周波数特性に影響する箇所は、最初の0.02uFと帰還部の51pですが、
この部分はローエンド、ハイエンドの特性に影響するものの、パーツの誤差程度では聞き分け出来ない程度だと思います。
TS10はミッド寄りのサウンド?
TS10は、TS808やTS9に対して、よりミッドに寄ったサウンドと言われるようです。
しかし、回路的には特にミッドを強調しているような違いはありません。
TS10では入力部のCは0.02uFですが、TS808,TS9では0.027uFとなっています。
ローエンドのカットオフ周波数が違ってくるため、TS10の方がローがカットされる、という事になりますが、
それがいかほどの差になるか、というのは気になる所かと思います。
しかし、実際にはカットオフ周波数はどちらもだいぶ低いので、測定して比較すると、こんなちょっとの違いです。
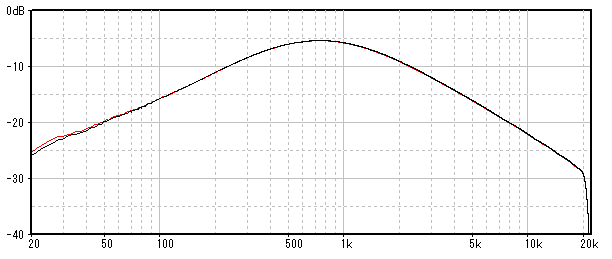
このC(0.2uFまたは0.27uF)と510KでHPFを形成すると考えてシミュレーションしても、20Hzでも1dB未満の差にしかならないようです。
0.02uF,0.027uFの違いのシミュレーション
この程度の違いは、コンデンサや抵抗値の誤差や、測定系の誤差でも出てしまいそうです。
また、ギター自体のインピーダンス(数百Ω)を加味すると、低域さらには落ちづらくなります。
この事から、入力部コンデンサの定数の違いは、ほぼ無視出来る程度かな、と思っています。
また、TS10の特徴であるゲイン段入力部の220Ωを直結にしたり、入力バッファのバイアス源を+4.5Vに変更したりして見ましたが、
F特のカーブとしては、差はありませんでした。この部分はフィルターではないので、まあ当然ですが。
いったい何が世間でいわれる様なTS10のサウンドの印象をもたらすのでしょうかね。。
単に可変抵抗のカーブのずれとか、そんなものかもしれません。