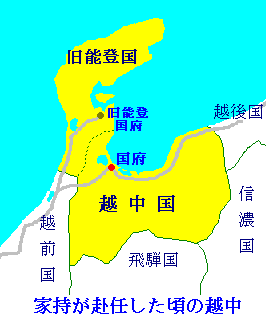
万葉集の巻四には、笠女郎の歌が二十四首もまとめて収められています。万葉全巻を通しても、恋歌の圧巻と言えましょう。その全てが大伴家持に贈った歌ですが、しっとりとした女心を詠んだ歌もあれば、激情に身を委ねた歌もあり、自虐的な歌もあり、と、恋情の種々相を振幅大きく歌い上げています。
巻四はほぼ年代順に歌が並んでいて、排列からすると、笠女郎の歌群は天平年間の始め頃の作となります。家持は十代後半にあたり、笠女郎の年齢もせいぜい二十歳前後とするのが通説となっていました。しかし、この二十四首は短期間に作られたのではなく、何年にもわたって詠まれた歌を、後で一まとめに編集したものと考えるべきです。また、その多くは、成熟した女性の歌としての風格を漂わせています。制作年や年齢については、通説にとらわれずに考えてゆきたいと思います。
笠女郎が家持に贈った巻四の二十四首全てを、順番通りに読んでみましょう。万葉集の並び方がそのまま贈られた順番だとは限りませんが、巻四はかなりきちんと整備された巻なので、歌の順序には充分な注意が払われているはずです。一首一首、敢えて想像を交えながら読み、私なりに彼女の半生を思い描ければよいのですが。
我が形見見つつしのはせ
荒珠 の年の緒長く我も思 はむ(587)
【意訳】さしあげた形見の品、これを見るたびに私のことを想い出してくださいね。たとえ逢えなくとも、何年も何年も、私も貴方のことをお慕いしていますから。
冒頭にいきなり別れの歌が来ます。
「形見」は思い出のよすがとなる品。別れ別れになる恋人同士の間で手渡されるものもこう言いました。衣服など、身につけていた品の場合が多かったようです。
「年の緒ながく」――これから何年も会えない、という傷心が、歌の調子を沈んだものにしているようです。二十代以前の家持が都を遠く離れたのは二度だけ。父に随い大宰府に下向した神亀四年(727)頃と、越中守として任地に赴いた天平十八年(746)です。神亀四年は家持わずか十歳ですから、笠女郎がこの歌を贈ったのは越中守任命時になるはずです。国守の任期は、ふつう五年ほどでした。この年家持は二十九歳。笠女郎もほぼ同世代でしょうが、全体的な歌の印象からは、家持より年下のような気がします。
白鳥の
飛羽 山松の待ちつつそ吾 が恋ひ渡るこの月ごろを(588)
【意訳】白鳥の飛ぶ飛羽山の松ではありませんが、貴方のおいでを待ちながら、私はずっと慕い続けておりました、この何カ月の間というもの。
「飛羽山」の比定地は定説がありません。東大寺近くの山とする説などがありましたが、最近、国語学者の吉田金彦氏が、福井県鯖江市に鳥羽という地名が残り、そのあたりの街道沿いの低山ではないか、と新見を出しました(『秋田城木簡に秘めた万葉集』)。吉田氏は、北陸への旅に出た笠女郎が、実際に飛羽山を見たのではないか、と推察しています。
吉田氏の新著は、これまでの定説に挑む、驚くべき知見に満ちています。特に、笠女郎の越中下向説には納得させられる部分が多かったので、私もさっそく乗せてもらうことにしました(ただ、吉田氏は歌の順序を大幅に入れ替えて解釈しているのですが、私はあくまでも巻四の排列どおりに読んでみるつもりです。従って、氏の解釈とはきわめて異なるものになるでしょう)。
何カ月も待ったけれど、家持が帰京する様子はなく(国司は一年に何度か都へ出向く機会がありました)、待ちきれなくなった彼女は、ついに彼を追って越中へと旅立った、というわけです。
衣手 を打廻 の里に有る我を知らにそ人は待てど来ずける(589)
【意訳】打廻の里にいる私を知らなくて、あの人は、いくら待っても来てくれなかったのだ。
「打廻」は従来ウチミと訓まれることが多かったのですが、所在はやはり不詳でした。吉田氏はこれをウチワと訓み、石川県の河北潟沿岸の土地だろうとしています。私には真偽の程は分かりませんが、氏の仮説に拠った方が、笠女郎の一連の歌のつながりがより納得できるので、ここでも吉田氏の説を借りたいと思います。
越中国府(いまの富山県高岡市)のすぐ近くまで彼女はやって来ていたことになります。しかし、まだ家持はそれを知りません。旅の途次、その都度手紙を贈ったとしても、家持には彼女の現在地を知りようがないのです。
荒玉の年の経ぬれば今しはと
努 よ我が背子我が名告 らすな(590)
【意訳】お逢いしてから何年も経ったからといって、「今はもう」と、私の名を人に洩らすようなことは努々なさらないで下さいね、愛しいあなた。
「我が名告らすな」こういう言い方は、逢瀬を遂げた恋人同士の間で交わされた、決まり文句みたいなものです。遥かな越の地で、とうとう彼女は家持と再会することができたと判ります。しかし、次の歌でも、597番の歌でも、笠女郎が人目を気にする度合いには、いささか尋常ならざるものがあるようです。上記著書で吉田氏は、彼女を家持の「隠(こも)り妻」であったと見なしています。
いずれにせよ、家持との関係は大っぴらにできるようなものではなかったのでしょう。あるいは、これも吉田氏が指摘する通り、越中国府には正妻である坂上大嬢がすでに来ていて、笠女郎は遠慮せざるを得ない立場にあった、ということなのかも知れません。
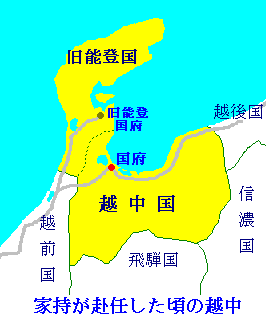 |
我が思ひを人に知るれや
玉匣 開きあけつと夢にし見ゆる(591)
【意訳】あなたへのひそかな想いが他人に知られてしまったのでしょうか、開けてはならぬ玉手箱の蓋を開けてしまった夢を見ました。
玉手箱を開ける夢は、秘密が他人に知られてしまったことの徴と広く信じられていたらしい。露見を恐れつつ、彼女は越中をあとにしたと思えます。
闇の夜に鳴くなる
鶴 の外 のみに聞きつつかあらむ逢ふとはなしに(592)
【意訳】闇夜に鳴く鶴の声を聞くように、遠くからお噂ばかりを聞いて過ごすのでしょうか、お逢いすることもできないまま。
都に帰った彼女は、再び恋人と引き離された哀しみを歌います。「闇の夜に鳴くなる鶴」とは、暗闇の中でお互いの所在が分からなくなった鶴のカップルを言っているのでしょう。鳴き声でそこにいると知ることは出来ても、姿は見えず、逢うことは出来ない、ということです。
君に恋ひ
甚 もすべ無み奈良山の小松が下に立ち嘆くかも(593)
【意訳】あなたへの恋心が募って、もうどうしようもなくなり、奈良山の小松の下に佇んで嘆くばかりです。
奈良山からは、家持の邸のある佐保の里を眺めることができたでしょう。しかし、彼はまだ越中にいました。せめてなにか寄り添うものが欲しいとでもいうように、笠女郎は「小松が下に」佇み、嘆くばかりでした。
この歌は笠女郎の名歌のなかでも、いや万葉集の全恋歌のなかでも、とびきりの秀詠です。やり場のない深い悲しみを歌いながら、まるで一本のか細く清潔な樹木のように、健気で凜とした姿をしています。
我が屋戸の夕陰草の白露の消ぬがにもとな思ほゆるかも(594)
【意訳】庭にある夕陰草の葉に置く白露のように、今にも消えてしまいそうなほど無闇に恋い焦がれているのです。
夕方、家の庭で物思いに耽る女のようすが、ありありと浮びます。「夕陰草」は夕方の光の中にほのかに浮かび上がって見える草の意で、彼女の造語であろうと言われています。なんと情趣ある言葉でしょう。
我が命の
全 けむ限り忘れめやいや日に異 には思ひ益すとも(595)
【意訳】私の命が損なわれない限り、貴方のことを忘れるものですか。たとえ日に日に恋心が増すことはあっても、忘れるなんて。
ここで再び転調です。恋を遂げようとのつよい意志が復活します。彼女はもう一度越中への旅に出ました。続く二首は、彼女が家持のそばにもどったことを暗示しています。
八百日 ゆく浜の真沙 も吾 が恋に豈 に益らじか沖つ嶋守(596)
【意訳】歩き尽くすのに八百日もかかるような長い長い浜―そんな浜の真砂(まさご)を全部合わせたって、私の恋心の果てしなさには敵いますまい。そうでしょう、沖の島の島守さん。
吉田金彦氏が指摘している通り、「八百日ゆく浜」は、越中か能登のどこかの海岸を言っていると思えます。「沖つ島」は、能登半島沖の
越の海の信濃の浜をゆき暮らし長き春日も忘れて思へや(17-4020)
この歌など、笠女郎に応答したような気がしなくもありません。普通、「忘れて思へや」は都の家族のことを言うと解釈されているのですが、遥々都から訪ねてくる旨手紙を寄越した、恋人への思いだったのかも知れません。
空蝉の人目を繁み
石橋 の間近き君に恋ひわたるかも(597)
【意訳】世間の人目がうるさいので、飛石のように間近にいる貴方に逢うことも出来ず、ただ恋い焦がれながら過ごしているのです。

|
再度恋人のそばまでやって来ながら、やはり逢うことはままならない。国守館に住む家持は、常に下僚に取り巻かれ、気ままな行動など許されなかったでしょう。彼女は恋しさに痩せ、死にそうになる、と訴えます。
恋にもそ人は死にする水無瀬河下ゆ
吾 痩す月に日に異 に(598)
【意訳】恋のためにだって人は死んでしまうのです。伏流水のように目には見えず、ひそかに慕う恋心から、私は痩せてゆくのです、日毎に月毎に。
朝霧の
欝 に相見し人故に命死ぬべく恋ひわたるかも(599)
【意訳】朝霧のようにほのかに逢っただけの人のために、私は死にそうなほどの思いで、ずっと恋をし続けるのですねえ。
これはようやく逢瀬を遂げた、

|
伊勢の海の磯もとどろに寄する波かしこき人に恋ひわたるかも(600)
【意訳】伊勢の海の磯に轟々と音立てて寄せる波―そんな身も竦むほどの勿体ないお方に、私はずっと恋し続けているのですねえ。
「かしこき」に恐ろしい意と畏れ多い意と両意を掛けています。「かしこき人」は、越中守という然るべき地位にあった家持を言っています。
吉田氏はこの歌を、家持が伊勢守だった頃(宝亀七年任官、家持五十九歳)に贈った作だろうとしています。これまた魅力的な解釈ですが、私は一連の歌をもう少し時間的に連続したものとして読みたい気持の方が強いので、ここでは、神風の吹く伊勢という畏き土地を比喩として借りたものだろうと考えておきます。
心ゆも
吾 は思はずき山河も隔たらなくにかく恋ひむとは(601)
【意訳】思いもよりませんでした、もう山川を隔てているわけではないのに、これほど恋い焦がれようとは。
家持はようやく帰京したようです。奈良山のそばに住んでいたらしい笠女郎にとって、佐保の邸に落ち着いた家持は、再び近隣の人となりました。彼女はこうなることをずっと願っていたはずです。ところが、「山河を隔て」なくなった今も、やはり恋しさに苛まれる。思いもしなかった、と言うのです。
このように、彼女の願望はつねに現実によって裏切られます。しかし、それが恋する者の宿命でしょう。それでもなお彼女は傷つくことを恐れず、恋の成就を願い続けずにはいません。
この後家持は、因幡守に左遷されるまでの七年ほどを都で過ごすことになります。笠女郎の恋は、時に鎮静し、時に炎を上げます。
夕されば物思ひ益る見し人の
言問 ふすがた面影にして(602)
【意訳】夕暮れになると物思いがいっそう募ります。お会いした方の、話しかける時の姿が、面影に浮かんで来て。
思ふにし死にする物にあらませば
千遍 そ我は死に変らまし(603)
【意訳】もし思うだけで死んでしまうものであるなら、私は千遍も繰り返し死んだことでしょう。
激しい言葉遣いで、家持を責めているのでしょうか。この辺から、笠女郎の歌には一方的な感情が目立ち始めてくるようです。家持にしてみれば、相手の気持に盲目になりがちな彼女の感情は押しつけがましく、しだいに心が離れていったのではないか。彼女の方は、それを頭では分かりながら、心は認めることができない。そんな焦燥に身悶えするような調子が出て来るのです。
剣大刀 身に取り添ふと夢に見つ何のさがそも君に逢はむ為(604)
【意訳】今、剣大刀をしっかり身に添えて寝る夢を見ました。いかなる前兆でしょうか。きっと、あなたに逢えるということでしょう。
天地 の神し理 無くはこそ吾 が思ふ君に逢はず死にせめ(605)
【意訳】もし天地の神々に道理というものが無かったならば、これほど思い焦がれる貴方に逢わぬまま死んでしまう、などということもあろうけれど(神に道理がないはずはないから、きっと貴方にお逢いできると信じています)。
我も思ふ人もな忘れおほなわに浦吹く風の止む時なかれ(606)
【意訳】私はあの人のことを思い続けている、あの人もどうか私のことを忘れないでほしい。(おほなわに、未詳)浦に吹く風の止むときが無いように、二人の思いがずっと続いてほしい。
皆人を寝よとの鐘は打つなれど君をし思へば
寝 ねかてぬかも(607)
【意訳】「皆の者、寝よ」と、亥の刻を告げて打つ鐘の音が響くけれど、貴方のことを思って私は寝るに寝られません。
相思はぬ人を思ふは大寺の餓鬼の
後 へに額つくごとし(608)
【意訳】片思いの相手を頼んでひたすら思い続けるのは、まるで大寺の餓鬼の像を後ろから額づいて拝むようなものだ。
これは特異な表現で名高い歌です。助動詞の「如し」など、あまり女性が用いなかった言葉でした。また「餓鬼」のような音読みの語も、万葉集では非常に珍しい例。
「餓鬼の後へに額づく」とは、まるで甲斐のない片思いを自虐的に表現して鮮やかです。絶望が彼女にこんな言い方をさせたのでしょうか。
やがて、ついに彼女は家持のそばを離れる決心をし、故郷へ帰って行きます。次の二首は、「相別れて後更に来贈る」と左注にあり、離別後、故郷からの音信であったと分かります。
心ゆも
吾 は思はずき又更に吾が故郷に還り来むとは(609)
【意訳】思いもよりませんでした、また再び我が故郷に帰って来ようなどとは。
この故郷は笠氏の故国、吉備でしょうか。あるいは、吉田金彦氏の言う近江国でしょうか。
近くあれば見ずともありしをいや遠に君がいまさばありかつましじ(610)
【意訳】近くに住んでいたからこそ会えなくても我慢できましたが、あなたがいっそう遠いところに居られるようになれば、もう耐えられそうにはありません。
遠く離れれば離れたで、やはり耐え難い。どこへ行っても、恋の苦しみからは逃れられない。歌を見る限りは「恋に生きた」としか言いようのない彼女の、これが最後に残した歌でした。

|
さて、笠女郎の最後の二首に対しては、家持の返した歌が残っています。
今更に妹に逢はめやと思へかもここだく
吾 が胸鬱 せくあるらむ(611)
【意訳】もうこの上あなたに逢えないと思うからだろうか、これほど私の胸が鬱々としているのは。
中々は
黙 もあらましを何すとか相見そめけむ遂げざらまくに(612)
【意訳】こんな中途半端なことになるのだったら、いっそ黙っていればよかった。どんなつもりで逢いはじめたのだろう、思いを遂げることなど出来はしないのに。
笠女郎の贈った歌が二十九首あるのに対し、家持の報和した歌は、この二首があるのみです。しかも家持の歌にはどことなく素っ気ない調子があるとして、二人の恋は女の側の一方的な片思いだった、と見る論者は少なくないようです。
私は決してそうは思いません。彼らの恋が神によって祝福されていた時期も、きっとあったはずです。家持の歌からは、破局を迎えたあとの、何とも言えない沈痛な響きが聞こえてきます。「こんなことになるのだったら、いっそ…」そんな後悔のうちに、笠女郎との恋の残骸のような思い出を眺めているかの如くです。
もちろん、彼女の残した歌は残骸などではありませんでした。後日、家持は笠女郎から贈られた歌を精撰して(何倍もの歌があったのではないかと思えます)、一人の作者の歌群としては例をみない規模を与え、自らの歌はその蔭にひっそり据えるようにして、真情あふれる、一途な、強く美しい彼女の恋歌に敬意を表したのではないか。私にはそう思えてなりません。
| 表紙 | 訓読万葉集 歌枕紀行 千人万首 波流能由伎 |