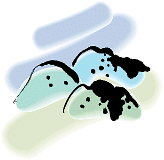
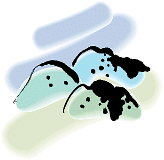 |
←はじめへ 七十一番〜七十五番 題「寄風恋」 →つぎ(勝負集計)へ
〔寄風恋〕風にことよせて恋の心を詠む。『平忠盛集』に先例があり、また『六百番歌合』と『仙洞句題五十首御会』(建仁元年九月)に同題が出題された。古くは『万葉集』巻十の「秋相聞」の部に「寄風」がある。当歌合は宮内卿と定家の傑作を生み、掉尾を飾った。
七十一番 寄風恋
左 勝 宮内卿
きくやいかにうはの空なる風だにも松に音する習ひ有りとは
右 有家朝臣
打ちなびく草葉にもろき露のまも涙ほしあへぬ袖の秋風
右、「袖の秋風」、えんにみえ侍るを、左、心こと葉始終なほよろしく侍るにや。仍てかちとすべし。
○左(宮内卿)
きくやいかにうはの空なる風だにも松に音する習ひ有りとは
【通釈】お聞きかしら。どう?「うわの空」にある風でさえも、かならず松には訪れて、梢を響かせる――そういう習わしがあるということは。(浮気者の風だって、「待つ」者を裏切りはしないのよ。)
【語釈】◇きくやいかに―聞き知っていますか。どうです。「其風の音を聞ことをもかねたり」(美濃の家づと)。◇うはの空なる風だにも―上空を吹く風でさえも。「上の空」はあてにならない男の心を暗示する。◇松に音する―松の梢を響かせる。松に「待つ」を掛け、「待つ女を訪れる」を含意。◇習ひ―習慣。ならわし。風習。しきたり。
【補記】練りに練った題詠歌でありながら、即詠の贈答歌のような軽妙な味わいがある。おおかた湿っぽい新古今時代の恋歌にあって、このカラッとした快活さは珍重されるべきだろう。ことに初句「きくやいかに」の、男を問い詰めるような調子が爽快。近世の註はこの句につき、「女の歌には、殊にいかにぞや」(契沖)、「まことにいかには少しいひ過して聞ゆる也」(宣長)と文句をつけるが、初句切れの威勢よさこそがこの歌の命だろう。宮内卿の才能の一面である機知が遺憾なく発揮された一首。
【他出】「若宮撰歌合」十四番左持、「水無瀬桜宮十五番歌合」十四番左持、「新古今集」1199、「定家十体」199(面白様)。ほかに自讃歌、新三十六人撰、女房三十六人歌合、続歌仙落書など。
●右(有家)
打ちなびく草葉にもろき露のまも涙ほしあへぬ袖の秋風
【通釈】秋風に揺れる草の葉から、もろくも地面に落ちる露――私の袖にも秋風は吹くけれど、ほんの露の間さえ、涙を乾かすことはできない。
【語釈】◇露のまも―「露」に「ほんの少し」の意を掛ける。◇ほしあへぬ―乾しおおせない。
【補記】露を涙になぞらえるのはよくある発想だが、「露の間」に言い掛けて、もろく落ちる露と、乾かない袖の涙と、鮮やかに二つのイメージを重ね合わせた。
【他出】「若宮撰歌合」八番右負、「水無瀬桜宮十五番歌合」八番右負。
■判詞
右、「袖の秋風」、えんにみえ侍るを、左、心こと葉始終なほよろしく侍るにや。仍てかちとすべし。
【通釈】右「袖の秋風」、艶に見えますが、左は、心・詞、始めから終りまで、ずっと結構なのでは。よって勝とすべきです。
▼感想
いずれも巧緻に細工して成功した作だが、面白みを出した宮内卿の歌と、優婉な有家の歌と、趣きは好対照。恋歌を決して得意とはしなかった宮内卿、一世一代の名歌である。
七十二番
左 権中納言
ひとりのみ富士の山風やむごなく恋をなどてかするがなるらん
右 勝 家隆朝臣
いかにせん身はならはしの物とても軒端の松に秋風ぞふく
左、「富士の山風やむごなく恋をするが」など、めづらしくこそ侍るめれ。右、「身はならはしのものとても」といひ、ちかきものよめり。□□□□□□□□□□□□みおよばず侍りけり。いかにも右勝に侍るべし。
●左(公継)
ひとりのみ富士の山風やむごなく恋をなどてかするがなるらん
【通釈】たったひとりで床に臥し、富士の山風のやむ時がないように、どうしてまあ恋しい思いをずっとするものだろう。
【語釈】◇富士―「臥し」を掛ける。◇やむごなく―「ご」は期の呉音。時・期限などの意。◇するが―「する」「駿河」の掛詞。駿河は富士と縁のある語。
【補記】絶えない恋心を富士の煙に喩える例は多いが、山風を用いたのは珍しい。が、それだけの歌。
○右(家隆)
いかにせん身はならはしの物とても軒端の松に秋風ぞふく
【通釈】どうしよう。ひとり寝の寂しさも、身の馴れ次第とはいうものの、軒端の松に秋風が吹くこの頃ときては…。
【語釈】◇身はならはしの物とても―「手枕のすきまの風もさむかりき身はならはしの物にぞありける」(拾遺集)に由来する言い方。寒さとか寂しさとかも、自身の馴れによるものだ、ということ。
【先行歌】寂蓮「仙洞影供歌合」(建仁二年五月)、「新古今集」
里はあれぬむなしき床のあたりまで身はならはしの秋風ぞ吹く
【補記】「先行歌」として挙げた寂蓮の歌は、当歌合のわずか四か月程前に後鳥羽院が鳥羽城南寺において催した歌合での作。俊成はこの歌合に出詠しているが参会はしなかったようで、寂蓮の歌を知らなかったことが判詞から窺われる。「身はならはしの」「秋風ぞふく」の二句が同一、初句切れも同様。この程度の模倣は当時珍しいことではないないが、先行歌が作られてから日にちが浅いこと、しかも作者が亡くなったばかりであることなどを考えれば、家隆の不注意と咎められても仕方あるまい。『明月記』によれば家隆は鳥羽城南寺の歌合に参会しており、寂蓮の歌は知っていたはずである。
【他出】「壬二集」2811。
■判詞
左、「富士の山風やむごなく恋をするが」など、めづらしくこそ侍るめれ。右、「身はならはしのものとても」といひ、ちかきものよめり□□□□□□□□□□□□みおよばず侍りけり。いかにも右勝に侍るべし。
【通釈】左は「富士の山風やむごなく恋をするが」など、珍しく見えるようです。右は「身はならはしのものとても」と言い、最近人が詠んだ(とのことです)。〔脱落〕私は(その歌を)聞き及ばずにおりました。どうあれ右が勝でございましょう。
【校異】親長本「左の歌、ふじの山かぜやむごなくするがなるらん、などめづらしくこそ侍るめれ、右の歌、身はならはしのものとても、といひ、まつ風ぞ吹くなどいへる、よろしく侍るを、ちかくもののよめるよしうけ給はり侍れども、みおよばず侍りけり、いかにも右は勝に侍るべし。」
▼感想
この番の判詞については諸本異同が多く、改判がなされた証とみられる(有吉保氏『日本大学図書館蔵 親長自筆本』解説参照)。方人から家隆の模倣が指摘されたことが窺われるが、俊成はそれを勘案しても家隆の勝とした。作品の出来映えを比較すれば当然であろう。
七十三番
左 勝 親定
わくらばにとひこし比におもなれてさぞあらましの庭の松風
右 前大僧正
いかにせんなぐさむやとてむすぶ庵に猶松風のみねに吹くなり
右の歌、「なほ松風の峯にふくなり」といへる心すがた、いとよろしくは侍れど、左歌、「わくらばに」とおき、「さぞあらましの」など侍るは、又及びがたく侍るべし。仍テ勝ト為。
○左(後鳥羽院)
わくらばにとひこし比におもなれてさぞあらましの庭の松風
【通釈】一頃、あの人はたまさかやって来るのが常だった。それに馴染んでしまって、庭先で待っている私に、やはりふっと立ち寄ってくれないかと期待させるのだ、顔馴染みの松を風が吹き過ぎれば…。
【語釈】◇わくらばに―ふとした偶然で。たまたま。◇おもなれて―面馴れて。馴染みになって。作者が「わくらばにとひこし比」に馴染んで、というだけでなく、松の木も顔なじみになってしまって、という意を含ませている。◇さぞあらましの―そうあってほしい。馴染みの松が風に鳴ると、条件反射のように、恋人がやって来ることを願ってしまうのである。◇庭の松風―庭の松を鳴らして吹く風。松に待つを響かせ、風に男の訪れを暗示する。
【校異】◇さぞあらましの―「ぞ」の右傍に異本参照「も」の書き入れがある。判詞での引用箇所も同様。
【補記】じれったいような婉曲な表現で、諦めと期待の狭間を微妙に揺れながら待つ女心を描いている。「若宮撰歌合」「水無瀬桜宮十五番歌合」に後鳥羽院自ら下した判で勝を付けているのは、この歌と四十一番「里はあれぬ」の二首のみ。院の自信作であったろう。
【他出】「若宮撰歌合」十五番左勝、「水無瀬桜宮十五番歌合」十五番左勝、「後鳥羽院御集」1609。
●右(慈円)
いかにせんなぐさむやとてむすぶ庵に猶松風のみねに吹くなり
【通釈】どうしたものか、気が休まるかと山里に来て、庵を結んで住んでみたが、やはりここでも松風は峯に吹いてあわれ深い音をたて、あの人を待つ思いからは逃れられないのだ。
【校異】親長本は末句「嶺に吹なる」。
【他出】「拾玉集」4960。
■判詞
右の歌、「なほ松風の峯にふくなり」といへる心すがた、いとよろしくは侍れど、左歌、「わくらばに」とおき、「さぞあらましの」など侍るは、又及びがたく侍るべし。仍テ勝ト為。
【通釈】右の歌は「なほ松風の峯にふくなり」と詠んだ心・姿、たいへん結構ではございますが、左の歌の「わくらばに」と置き、「さぞあらましの」などありますのは、やはり及びがたくございましょう。よって勝とします。
▼感想
いずれも「松風」に「待つ」を響かせた二首。慈円の歌は「いかにせん」の初句切れ、「なぐさむやとて」の言い回しなど、上句がやや使い古された感がある。対して後鳥羽院の歌は、耳慣れた語をつなげながらも思い掛けない情趣をあらわし、かそけき心情を歌ってかくも丈高い。神妙な思いを抱かせるほどである。
七十四番
左 左大臣
荻原や余所に聞きこし秋の風もの思ふくれは我が身ひとつに
右 勝 俊成卿女
きえかへり露ぞみだるる下荻の末こす風はとふにつけても
左歌、「よそにききこし秋の風」といひ、「物思ふくれは我が身ひとつに」といへる心、ことによろしくもえんにも覚え侍るを、右歌、「末こす風はとふにつけても」といへる、又よろしくは侍るべし。是は狭衣と申す物語の歌の心に侍るべし。左も劣るべきには侍らねど、右勝の字付け侍りしなり。愚老が面目にも侍るべし。
●左(良経)
荻原や余所(よそ)に聞きこし秋の風もの思ふくれは我が身ひとつに
【通釈】荻原をそよがせて吹く秋風の音――それはあの人の訪れの前兆でこそあれ、「飽きられる」など、他人事と思って聞いていたのに。今やあの人は待っても来ず、物思いに耽る夕暮は、自分ひとりの身にばかり…。
【語釈】◇荻原―荻の生える原。荻の葉は秋風に音をたてるものとして詠まれ、恋人の訪れを暗示することも多い。◇余所に聞きこし―自分とは無縁なものとして聞いてきた。◇秋の風―秋に「飽き」を掛ける。親長本は「秋風の」とする。◇我が身ひとつに―自分ひとりの身にとってばかり辛く感じられる、程の意。
【他出】「秋篠月清集」1449。
○右(俊成卿女)
きえかへり露ぞみだるる下荻の末こす風はとふにつけても
【通釈】下荻の葉末を吹き越して風が訪れるにつけ、露が乱れ散り、繰り返し消えてゆく――。あなたの訪れを下招(お)ぎする私も、あなたの噂を耳にするたび、その下荻のように、打ちひしがれ、息絶えそうになって涙を散らしているのです。
【語釈】◇下荻―物蔭の荻。打ちひしがれた自身を暗喩すると共に、「下招(を)ぎ」(心中ひそかに相手の魂を招き寄せる意)と掛詞になる。◇末こす風―荻の葉末を吹き越す風。下記本歌により、恋人の結婚の噂を暗示する。
【本歌】「狭衣物語」巻三
折れかへりおきふしわぶる下荻の末こす風を人のとへかし
【補記】本歌は、狭衣大将が好きでもない一品の宮と結婚させられるハメになって悩んでいた頃、女二の宮に「困惑している私に、消息くらい尋ねてくれればよいのに」と恨みを述べたもの。俊成女の歌は、「下荻」と「末こす風」の心を本歌に借りつつ、女の立場から詠んだ歌に置き換えた。恋人の結婚の噂に、絶え入りそうになっている女の思いである。
【他出】「若宮撰歌合」十五番右負、「水無瀬桜宮十五番歌合」十五番右負。
■判詞
左歌、「よそにききこし秋の風」といひ、「物思ふくれは我が身ひとつに」といへる心、ことによろしくもえんにも覚え侍るを、右歌、「末こす風はとふにつけても」といへる、又よろしくは侍るべし。是は狭衣と申す物語の歌の心に侍るべし。左も劣るべきには侍らねど、右勝の字付け侍りしなり。愚老が面目にも侍るべし。
【通釈】左歌は「よそにききこし秋の風」と言い、「物思ふくれは我が身ひとつに」と言った情趣、格別結構にも艶にも感じられますが、右歌、「末こす風はとふにつけても」という句もまた結構ではありましょう。これはきっと狭衣と申す物語の歌の心でしょう。左も劣るはずはありませんけれども、右勝との字を付けたのです。私めの名誉でございましょう。
▼感想
俊成の判詞「愚老が面目にも侍るべし」は、自身の名を付して呼ばれた養女俊成卿女が、左大臣の佳詠を抑えて勝となったことを、名誉と言ったものか。勝負は衆議判でついたのであり、持としてもおかしくない好勝負が、自身の娘の勝となったことを、自らの面目を立てる結果と感激しているのであろう。
七十五番
左 定家朝臣
白妙の袖のわかれに露落ちて身にしむいろの秋風ぞふく
右 勝 雅経
今はただこぬ夜あまたの小夜更けてまたじと思ふに松風の声
左歌、「身にしむ色の秋風ぞふく」といへる、よろしからざるにはあらざるべし。右歌、「またじと思ふに松風の声」といへる、まことにをかしかるべし。仍て勝に定まり侍りにけり。
●左(定家)
白妙の袖のわかれに露落ちて身にしむいろの秋風ぞふく
【通釈】差し交わしていた白い袖を引き離して別れる時となり、私の袖に露のような雫が落ちると、そこへ身に沁みるような秋風が吹きつける。色などないはずなのに、こんなにもあわれ深く身に染みとおる風が。
【語釈】◇白妙の―「しろたへ」はもともと栲(たえ)で織りあげた白布を言うが、ここでは単に白い色を指す修飾句。◇白妙の袖のわかれ―白い夜着の袖を差し交わして寝ていた、その袖を離れ離れにして別れる、ということ。後朝(きぬぎぬ)の別れと取るのが王朝和歌の常道であろう。万葉集巻十二に「白妙の袖の別れは惜しけれど思ひ乱れてゆるしつるかも」「白妙の袖の別れを難みして荒津の浜にやどりするかも」など、上代において定型句となっていたことが窺われる。定家はそれを復活させたのである。◇露―秋風の縁で涙を露という。紅涙と解釈し、白と紅の対照に着目する説は採らない。◇身にしむいろ―この「いろ」は、趣き・気色(けしき)、ほどの意だが、初句の「白」が響いて、色彩の意も帯びざるを得ない。本来風は無色透明であるはずだが、これほど「身にしむ」ということは、どんな色だというのか、との心がこもる。下記和泉式部の歌参照。
【参考】作者不明「古今和歌六帖」
吹きくれば身にもしみける秋風を色なき物と思ひけるかな
和泉式部「詞花集」
秋ふくはいかなる色の風なれば身にしむばかりあはれなるらむ
【補記】古来「露」を紅涙の喩えと見る説が多いが、白と紅の対比はこの歌においてはあざとく、興覚めにしか感じられない。参考に挙げた古今六帖詠や和泉式部詠を踏まえた作と見れば、「透明であるはずの風が、別れに際しては、あたかも《色》ある如く、深く身に沁みて(染みて)感じられる」ということであって、「色」はcolorの意に主意があるのではあるまい。
【他出】「若宮撰歌合」十四番右持、「水無瀬桜宮十五番歌合」十四番右持、「新古今集」1336、「拾遺愚草」2550、「定家自歌合」七十九番右勝、「定家八代抄」1067。ほかに「新三十六人撰」など。
○右(雅経)
今はただこぬ夜あまたの小夜更けてまたじと思ふに松風の声
【通釈】あの人が来ない夜が幾晩も重なって、今夜もまた更けてゆき、もう絶対待ってやるものかと思う――その折も折、風に吹かれて松の梢が響きをたてる。すると性懲りもなく「待つ」心が息を吹き返してしまうのだ。
【語釈】◇今はただ―「またじと思ふ」に掛かる。「ただ」は「全く」「ぜったい」程の意。◇松風の声―松に待つを掛ける。風は男の訪れを暗示するので、その声を聞くと待つ気持になってしまう、ということ。
【本歌】柿本人麿「拾遺集」
たのめつつこぬ夜あまたに成りぬればまたじと思ふぞまつにまされる
【補記】詠みふるされた情趣を詞の並べ方の工夫で復活させようとした歌。
【他出】「若宮撰歌合」26(十三番右負)、「水無瀬桜宮十五番歌合」26(十三番右負)、「明日香井和歌集」1111、「新続古今集」1227。
■判詞
左歌、「身にしむ色の秋風ぞふく」といへる、よろしからざるにはあらざるべし。右歌、「またじと思ふに松風の声」といへる、まことにをかしかるべし。仍て勝に定まり侍りにけり。
【通釈】左の歌、「身にしむ色の秋風ぞふく」と詠んだのは、結構でないはずはないでしょう。右の歌、「またじと思ふに松風の声」と詠んだのは、まことに興趣深いでしょう。よって勝に決まったのでした。
▼感想
「よろしからざるにはあらざるべし」の判詞、定家の絶唱には冷淡に過ぎるようにも見えるが、否定の否定は婉曲な肯定でもあろう。雅経の勝となった衆議判の結果を、我が子を擁護してひっくり返すことができるはずもなかった。
なお定家の歌は元久二年(1205)、特別に後鳥羽院の下命があり、新古今集巻十五(恋歌五)の巻頭に置かれることになる。