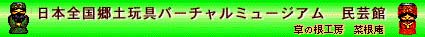
----長崎県篇・第2回----
---- NAGASAKI(2)----

長崎には「古賀人形」のほかに、「長崎焼人形」と長崎人形」があります。
「長崎焼」はふるい伝統があり、市内の大久保さんが、復活製作している人形です。 「長崎人形」は、戦後に土産品として作り始められたものです。 ■長崎焼■ この人形は、明治の中頃、港に近い新地街の住んでいた中国の貿易商人や料理人などの姿をモデルにした土人形です。当時は、あちらの人「阿茶さん」として親しまれいたので、阿茶さん人形とも呼んでいました。 「歴史」:長崎焼の窯元、中原家は、寛文年間(1661〜73)、毛利藩の家老職中原太郎左衛門の代に、高麗焼の陶工・友平を使って、周防国山口吉敷に窯を築き「萩焼」を始めています。その末裔(まつえい)の中原仁平が長崎に移り住み、萩焼の技術を生かして茶器などを製造しました。これが長崎焼の始まりです。 昭和の初期、この中原仁平の妻・ノシが、内職に長崎焼の窯で土人形を焼き始めたのが、「長崎焼人形」の創始となります。戦後もノシさんは人形を作り続け、昭和43年に亡くなりました。 その後、仁平の弟子の久保田はじめが、トンチンカン人形と称した手捻りの土人形などと共に、長崎焼人形も一時復活させましたが、昭和47年に亡くなり、この人形も一時廃絶します。 現在の作者・大久保平さんは、中原ノシの孫で、この人形作りを手伝った記憶もあるそうです。 「全国郷土人形図鑑」(昭和7年刊。足立孔著)に載った写真を見た何人かの収集家から手紙があり、それをきっかけに、大久保さんは勤めのかたわら、昭和63年ころよりこの人形を作り復活させました。 製作者:大久保 平:長崎市愛宕町2-7-5..TEL: 0958-22-4728 ■長崎人形■ この人形は昭和63年から売り始められた新作土人形で、観光都市にふさわしい郷土色のある土産品をという要望から作られました。 実はこの土人形の原型製作、製作指導に当たったのは、佐賀県の「弓野人形」の江口勇三郎さんで、平成3年頃まで長崎に滞在して製作されました。(参照:佐賀県篇(1)) ページ上では少ししか掲載できていませんが、長崎人形は長崎にゆかりのある人物や風俗を土人形にしたもので、阿茶さん・お蝶夫人・じゃがたらお春・天草四郎・阪本竜馬・オランダ漫才・コッコデショ(御輿)など、60種近くが作られています。 製作者:畑 茂「アート・ハタ」:長崎市鍛治屋町1-10..TEL:0958-27-2360 |
| ▼‥[Next] 長崎県篇(3) | ▲‥[Back] 長崎県篇(1) |

|
(1999.8.1掲載)