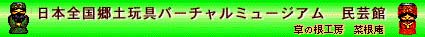
----長崎県篇・第1回----
---- NAGASAKI(1)----
|
■長崎県の郷土玩具ガイド■(掲載されていないもの、廃絶品を含みます)
長崎 古賀人形。長崎焼。長崎人形。長崎ハタ。鯨の潮吹き。 波佐見 舌出し三番叟。 三川内 舌出し三番叟。 平戸 舌出し三番叟。子泣き相撲。鬼洋蝶。 壱岐島 鬼凧。壱岐の八朔雛。 福江市(五島列島・福江島) バラモン凧。日出鶴。 ■施設■ 長崎物産館 長崎市大黒町3-1:交通産業ビル内 TEL: 0958-23-4041 平戸観光資料館 平戸市大久保町2496: TEL: 0950-22-2813 松浦史料博物館 平戸市鏡川町12: TEL: 0950-22-2236 ■参考情報リンク■ 長崎県のホームページ(公式) 長崎県の観光と物産の見どころ |

■古賀人形■
長崎市には新旧とりまぜて土人形がありますが、古い伝統を持っているのが「古賀人形」があり、現在の製作者の小川享さんは小川家18代目です。 古賀人形の特徴は、この土人形にだけしか見られない独創的な型や、独特の色調を持つ彩色であり、人形の種類も100種近く数えられます。 ◇人形の説明◇ 西洋婦人:このバラを持った婦人のモデルは、オランダ商館長ヤン・コック・プロムホフの夫人テルダベルフスマ(当時31才)、幼児はヨハンネス(2才)で、1817年に夫と共に来日。 和蘭陀(オランダ)さん:左手に銃を持った立姿の人形は、長崎出島(でじま)のオランダ館のカピタン(商館長)が猟に行く姿といわれています。 阿茶(あちゃ)さん:あちらの人という意味で、異国の人を指した言葉。中国風の帽子に詰め襟で、裾の長い男が軍鶏(しゃも)を抱いている姿です。 「由来」:古賀人形に添えられている栞によりますと、天文年間(1532〜55)大村藩士であった小川金右衛門が、古賀村で農業を始め、3代目の小三郎の代に、京都の土器師(はじし)常陸之介が日本漫遊の途中に小川家に滞在して、土器製造の秘法を教えました。小三郎は農業のかたわら副業として神仏用の土器を作り、晩年には小さな人形をも作り始めました。 天和年間(1681〜4)6代目、喜左衛門の代には土器製造の師範として肥後国に招かれ、同地の人形の状況を視察、古賀人形の発展につくしました。 その頃より、オランダ、中国などとの貿易が盛んとなり、九州の諸大名は「長崎詰め」を置くようになります。その折り、長崎港への街道筋にあたる古賀村の「小川家」は休憩所となり、帰りの武士は土産に「古賀人形」を求めたといいます。 文化年間(1804〜18)小川金兵衛時代より、三月の雛祭り用の人形を作り、販路を大いに拡張しました。明治42年頃には一族三家で製造していましたが、その後、今の小川家1軒となりました。 製作者:小川 享:長崎市中里町古賀1533..TEL: 0958-38-3869 |
▼‥[Next] 長崎県篇(2)

|
(1999.7.25掲載)