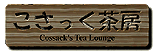■鯖の道とは・・・。
かつて、若狭人と都人が交易をしていました。若狭湾で取れた鯖をはじめ様々な海産物に塩をひとふりし、1〜2日かけて十八里離れた都へ運びました。人々が交易に行き来したこの道は、海の幸だけでなく、お互いの文化も運んでいきました。そして、いつしかその道は「鯖の道」と名づけられていました・・・。
 鯖街道とも言われている「鯖の道」。皆さんはどんなイメージをお持ちですか?若狭の海で獲れた新鮮な鯖は一塩ふりかけられ、大急ぎで京まで運ばれました。着いた頃にはちょうど良い塩梅になっていて、都人たちに大変喜ばれました。その鯖を運んだ道が「鯖の道」であると・・・。たしかにこれはよく耳にする有名なお話。おおむね当たっているし、事実だと思います。かくいう私も最初はそう思っていました。でも、よくよく調べてみると、その事実のなかに更に肉づけされた「本当の真実」があったのです。 鯖街道とも言われている「鯖の道」。皆さんはどんなイメージをお持ちですか?若狭の海で獲れた新鮮な鯖は一塩ふりかけられ、大急ぎで京まで運ばれました。着いた頃にはちょうど良い塩梅になっていて、都人たちに大変喜ばれました。その鯖を運んだ道が「鯖の道」であると・・・。たしかにこれはよく耳にする有名なお話。おおむね当たっているし、事実だと思います。かくいう私も最初はそう思っていました。でも、よくよく調べてみると、その事実のなかに更に肉づけされた「本当の真実」があったのです。
じゃあ、「鯖の道」とはいったい何でしょう・・・?実はこれを一言で言うのは大変難しいのです。なぜなら、この「鯖の道」は東海道や中山道などのように、道や宿場が整備された街道とは性格が全く異なっているからです。あえて「鯖の道」を一言でいうと、この文章の冒頭の段落の部分と言っておきましょう。世間でイメージされている「鯖の道」とは実際はかなりギャップがあるのではないかと私は思っています。実際の「鯖の道」は我々が思っているそれとははるかに地味な存在であり、生活に密着した地道だったのです。と同時に、若狭と京の発展に貢献した「文化の道」でもあったのです。人々の食と文化と心を運んだロマンの道それが「鯖の道」だったのです。
■京の台所を支えた「鯖の道」
京都の人たちは葵祭りや祇園祭りの時にご馳走として鯖ずしを作って食す風習があります。それに使用されていたのが若狭で獲れた鯖だと言われています。世間一般 でもこの鯖が「鯖の道」を使って運ばれ、「鯖を運んだ道」であるという認識が強いです。そして、実際鯖が運ばれたのも事実です。しかし、それは真実ではありません。実は「鯖の道」を使って運ばれたのは「鯖」だけではなかったという事なのです。
小浜を含む若狭地方は古くから海産物の宝庫として発展し、朝廷に海産物を上納した重要な「御食国(みけつくに)」のひとつだったという記録が残っています。つまり、「鯖の道」を使って運ばれたのは鯖だけではなく、色々な海産物がはこばれたのです。「鯖」はその言わば代表選手に過ぎなかった訳です。そして、海産物だけでなく、塩も運ばれたという記録も残っています。
海産物を運ばれたという証拠として、京都の台所である錦市場にその名残を見ることができます。あるお店では「若狭一汐もの」として塩鯖をはじめとした若狭かれいや小鯛が並んでいるところを見ることができます。また、京都の有名料亭では若狭の海産物を高級食材として重宝がられています。大げさかも知れませんが、「鯖の道」は京の台所を支える重要な役割を担っていたのでした。
■鯖の道ネットワーク
 鯖の道はいったい、どこからどこまでなのでしょうか?東海道の場合ですと、東京の日本橋から京都の五條大橋までと起点と終点やルートまで明確に定まっております。しかし「鯖の道」の場合、実は特定のひとつの道はないのです。鯖を含めた若狭の海産物は色々なルートを使って運ばれており、「これが鯖の道だ!」とそれのみと決めることが難しいのです。おまけに、その出発点も小浜とは限らず、また、到達点も京都とは限らないのです。 鯖の道はいったい、どこからどこまでなのでしょうか?東海道の場合ですと、東京の日本橋から京都の五條大橋までと起点と終点やルートまで明確に定まっております。しかし「鯖の道」の場合、実は特定のひとつの道はないのです。鯖を含めた若狭の海産物は色々なルートを使って運ばれており、「これが鯖の道だ!」とそれのみと決めることが難しいのです。おまけに、その出発点も小浜とは限らず、また、到達点も京都とは限らないのです。
小浜より京都へに至る鯖の道に限って言えば、大きく分けて5つのルートがあると言われています。まず「鯖の道」として有名なのは福井県小浜市から遠敷郡上中町熊川を経て、滋賀県高島郡朽木村、京都市の大原を抜けて出町柳までの道のり。「若狭街道」としてもその名を知られています。それ以外にも「周山街道」「小浜街道」「根来・針畑越え」「西近江道(琵琶湖湖畔の道)」などがあります。これら5つのルートが分岐、合流し、また別 の近道や峠越えなども含めると網の目のように「鯖の道」が存在するのです。
■「鯖の道」は文化の道
 また、「鯖の道」は食材を運んだだけではありません。大陸から伝えられた文化を都に、都の文化を若狭に伝えた「文化の道」でもあったのです。大陸からの仏教文化、祇園祭りや六斎念仏、壬生狂言などたくさんの文化が発信され、取り入れられ、根づいていったのです。 また、「鯖の道」は食材を運んだだけではありません。大陸から伝えられた文化を都に、都の文化を若狭に伝えた「文化の道」でもあったのです。大陸からの仏教文化、祇園祭りや六斎念仏、壬生狂言などたくさんの文化が発信され、取り入れられ、根づいていったのです。
また、室町時代には南蛮船から象もたらされ、都まで運ばれたり、戦国時代に越前の朝倉氏を攻めていた徳川家康が撤退する時に通 った道であったという記録も残されています。
このように、「鯖の道」は文化を伝え、継承し、根づかせていった舞台であったと言ってもいいでしょう。
■概論まとめ
以上のように「鯖の道」について概論を述べましたが、簡単にいうと以下の特長があるということが解ります。
- 「鯖の道」は若狭から京へ海産物を運んだ道
- 「鯖の道」は文化交流も果たした
- 「鯖の道」のルートは様々
このように、「鯖の道」は多岐にわたり、色々な側面を持っています。我々の生活に密着し、豊かな食と文化を提供しました。また、歴史的にみても重要な役割を担ったのです。そして、それは決して表に出ることはなく、地味な存在であったのです。
そんな優秀なバイプレーヤーであった「鯖の道」にスポットを当て、実際の写 真とともに紹介したいと思います。
|
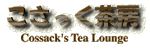
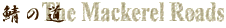

 鯖街道とも言われている「鯖の道」。皆さんはどんなイメージをお持ちですか?若狭の海で獲れた新鮮な鯖は一塩ふりかけられ、大急ぎで京まで運ばれました。着いた頃にはちょうど良い塩梅になっていて、都人たちに大変喜ばれました。その鯖を運んだ道が「鯖の道」であると・・・。たしかにこれはよく耳にする有名なお話。おおむね当たっているし、事実だと思います。かくいう私も最初はそう思っていました。でも、よくよく調べてみると、その事実のなかに更に肉づけされた「本当の真実」があったのです。
鯖街道とも言われている「鯖の道」。皆さんはどんなイメージをお持ちですか?若狭の海で獲れた新鮮な鯖は一塩ふりかけられ、大急ぎで京まで運ばれました。着いた頃にはちょうど良い塩梅になっていて、都人たちに大変喜ばれました。その鯖を運んだ道が「鯖の道」であると・・・。たしかにこれはよく耳にする有名なお話。おおむね当たっているし、事実だと思います。かくいう私も最初はそう思っていました。でも、よくよく調べてみると、その事実のなかに更に肉づけされた「本当の真実」があったのです。 鯖の道はいったい、どこからどこまでなのでしょうか?東海道の場合ですと、東京の日本橋から京都の五條大橋までと起点と終点やルートまで明確に定まっております。しかし「鯖の道」の場合、実は特定のひとつの道はないのです。鯖を含めた若狭の海産物は色々なルートを使って運ばれており、「これが鯖の道だ!」とそれのみと決めることが難しいのです。おまけに、その出発点も小浜とは限らず、また、到達点も京都とは限らないのです。
鯖の道はいったい、どこからどこまでなのでしょうか?東海道の場合ですと、東京の日本橋から京都の五條大橋までと起点と終点やルートまで明確に定まっております。しかし「鯖の道」の場合、実は特定のひとつの道はないのです。鯖を含めた若狭の海産物は色々なルートを使って運ばれており、「これが鯖の道だ!」とそれのみと決めることが難しいのです。おまけに、その出発点も小浜とは限らず、また、到達点も京都とは限らないのです。 また、「鯖の道」は食材を運んだだけではありません。大陸から伝えられた文化を都に、都の文化を若狭に伝えた「文化の道」でもあったのです。大陸からの仏教文化、祇園祭りや六斎念仏、壬生狂言などたくさんの文化が発信され、取り入れられ、根づいていったのです。
また、「鯖の道」は食材を運んだだけではありません。大陸から伝えられた文化を都に、都の文化を若狭に伝えた「文化の道」でもあったのです。大陸からの仏教文化、祇園祭りや六斎念仏、壬生狂言などたくさんの文化が発信され、取り入れられ、根づいていったのです。