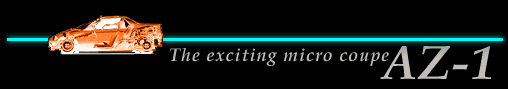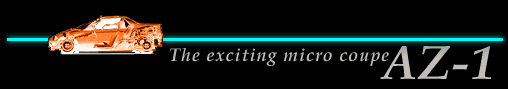
マツダの新しいブランドシンボル
それにしても単調すぎて不細工である。新しいブランドシンボルのニュースを見たとき目を疑った。このシンボルが適用された恐らく最初の大規模案件が、MAZDA TRANS AOYAMAだと思われる。

これ、どこかで見たと思ったら、ICONICに使われていたのとよく似ている。

が、100%同じではなく、矢印部分が切れていない。

ここがICONICのように切れていたら、まだ単調ではなくなると思う。なお、このシンボルは車両には適用されず従来の立体カモメマークが使われるとのこと。そりゃそうだ。不細工すぎる。
なぜこのようなデザインになったのか、隠れた経緯を深掘りしていく。
報道によると、小型デジタル媒体での視認性を向上させるためだそうだ。言い方を変えると、従来のシンボルを縮小すると、デザインが潰れて視認性が悪くなるとのこと。

ということなので、縮小してみた。まあ確かに従来シンボルよりも視認性は高いかな。
視認性の向上を目的にするとはいうが、そもそも従来のシンボルが設定されたとき白黒2階調カモメマークを大々的に設定していなかったことが問題だった。実は、ステッカー製の2階調カモメマークがボンゴの一部グレードのリアゲートに貼り付けられていた。しかしスクラムなど他車に展開されることなく、乗用車と同様のプラスチック製立体カモメマークが多用され、2階調の設定は「無かったこと」同然となった。
そのため、公式2階調の設定を知らないサードパーティーが2階調カモメマークを勝手にデザインし、多種多様の非公認バージョンが氾濫することとなった。下の写真はその一例である。

マツダがコントロールできない状態で、非公認のブランドシンボルが市場に氾濫しているのは問題である。長年見て見ぬふりをしてきた問題を、「視認性の向上という表向きの理由」をつけてこの機に解決しようとしたのが本当なのではないかと邪推する。というのも、視認性向上を目的とした平面的なデザインは、他の業界では相当前に流行したので、これを理由とするにはタイミングがあまりに遅すぎるためだ。
なお、既に出回っている2階調カモメマークとは異なるデザインにする必要があるため(サードパーティーのデザインを、マツダが盗用したという形になるのを避けるため)、サードパーティーすら採用しなかった一番不細工なデザインを選択せざるを得なかったのだと、さらに邪推する。