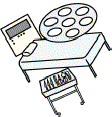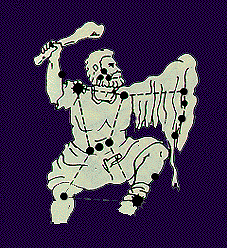![]()
普 遍 時 間
第一章
病室の壁には、一辺が二メートルの大きな絵が掛かっていた。印象派の巨
匠、モネの『睡蓮』である。が、むろん、本物ではない。この病室の宿主である、
牧村俊の手による模写絵である。絵は、ただ、睡蓮池に、溢れるばかりの陽光
が描いてある。しかしそれは、すごいまでに、睡蓮の形が色彩と光の中に溶け
込んでいる。そしてそこに、全てが渾然一体となった、一瞬の“今”が表現され
ている。その一瞬の“今”が、キャンバスの上で、永遠にくり返されているのだ。
牧村俊は、今朝もまた、どれほどの時間、その睡蓮池の上を漂っていただろ
うか。あらゆる概念の厚みも重みも消え失せた、その一瞬の“今”の上を。こ
の、モネの創り出した“今”の上に、彼は禅的な“空”を見つめていたのである。
「やあ、」と、一人の患者が、開けっ放しになっているドアから、ベッドの上の牧
村に声をかけて通り過ぎた。
「やあ、」と、牧村も答える。
それから牧村は、灰皿の中の吸いさしのタバコに火をつけた。が、二口三口
吸うと、また丁寧に火をもみつぶした。
しばらくして、その開いているドアをコンコンとたたき、看護婦が一人入って
きた。いかにも忙しいらしく、ボールペンをあちこちのポケットにはさみ、脇にプ
ラスチックのケースとバインダーを抱えている。
彼女は、ベッドの上の牧村に微笑を投げると、素早く部屋の中をぐるりと見回
した。獲物を追う、女刑事か女探偵の目だった。それから、彼女はぼんやりと
深呼吸し、ドサリと脇に抱えていたものを丸テーブルの上に置いた。
病院では働きざかりの、中堅どころの看護婦である。つるりとした卵型の顔
は、まず美人といっていいのかも知れない。が、それ以上に、成熟した女の知
性のようなものを感じさせた。そうしたものが、いったい女のどこで形成されてく
るかは知らないが。
「これは、北野女史・・・」牧村は、やつれた頬をほころばせ、からかうように言っ
た。「ここで何か捜し物ですか?」
「ええ、ちょいとね」彼女は、顔をとりすませた。が、今までネズミでも追いかけ
ていたのか、髪と帽子がいくぶん乱れている。
「この部屋に、ネズミが逃げ込んだとでも?」
「いえ、もしそうだとすれば、もっと大きなネズミですわね。そうそう、牧村さん、
ビデオが入力されてきてますよ」
「どこから?」牧村は、リクライニングになっているベッドの上で、頭の後ろに手
をさしこんだ。
「宇宙開発機構から。弟さんでしたわね」
「ああ・・・学が、いったい何を言ってきたのかな・・・」
牧村は、ラックからキーボードの載ったアーム式のテーブルを引いた。そし
て、ユニット式の書棚の真ん中に収めてある、INSの端末機を操作した。これ
はパソコンと繋がっていて、テレビのスクリーンに表示するようになっている。メ
ッセージを映し出すと、項目のトップに来ていた。
「ところで・・・ねえ、牧村さん、」北野看護婦は、ノートに何かを書込みながら、
ちらりと牧村を見た。「今朝早くに、少し散歩なされたんですの?」
「いや、」牧村は、スクリーンの表示を消した。「何で、また?」
「チャンと知ってますよ」彼女は顔を上げて、まっすぐに牧村を見た。「ここは病
院です」
「もちろん、病院ですがね」
「みんな、お見通しなんですよ」彼女は、決めつけた。
牧村は笑った。髪を指ですき上げた。すっかりやつれきってはいても、まだ男
としての威厳は保っている。
「ふうん、隠しカメラでもあるんですかね」
「さあ、どうかしらね」彼女は、採血の準備を始めながら言った。
「ところで、スキャナー(核磁気共鳴スキャナー)の方はどうでしたか?」牧村
は、話をそらした。
「ええ、なんとかね。でも、朝早くにあんな所まで散歩なさるようですと、もうタバ
コは一本もさしあげられませんわ」
「ふむ、なるほど、それも悪くない脅しですね。それで、このおれを、どうしても生
かし続けておきたいわけですか?」
「ええ。弟さんのためにもね、」彼女は、ボールペンをポケットにさしこんだ。そし
て、やや首をかしげて牧村を眺めた。「つぎは、トレーサーをやるそうですよ」
「NMR(核磁気共鳴)トレーサーを?」
「ええ、」彼女は、唇を閉じてうなずいた。
「どうしてです?ATPでもトレースするんですかね?」
「さあ、」彼女は、首をふった。髪が、サラリと流れた。
「とにかく、牧村さんが協力して下さればですけどね。みんなご存知ですの?」
「自分の体のことは、だいたい分りますよ」
「そう、」彼女は、口もとをくずした。「私たちが、病院の中のことが分るようにで
すね」
「そういうことですね」
「そう・・・」彼女は、制服の腰に手を当てた。「鋭いのね」
「知ってるはずですがね」
「ええ、」彼女はうなずいた。
「痩せても枯れても、男でしてね」
「それも、知ってますよ」
牧村は、笑って首を横にふった。
「体のつくりが男だと言ってるんじゃあない。男とは、心の中にある」
「ふうん・・・そうなの。で、トレーサーは、受けて下さるんですの?」
「条件がある」
「大変な患者さんね」彼女は、眉をつりあげて見せた。
「で、それは、いったい何?」
「接吻でどうかね?まけておくよ」
「そう、そういうことね」彼女は、笑ってうなずいた。「いいですよ。そのうちにね」
「他にも、御用の節は、何なりと、」
「それじゃあ、腕を出して。採血しますよ」
正午少し前、牧村は、トレーニング・ジャージ姿で病室を出た。三階から二階
まで、エレベーターで降りた。老婆が一緒に乗り合わせた。が、老婆は、牧村を
ジロジロ見ただけで、何も言わなかった。牧村も何も言わず、天井を見ていた。
エレベーターを降りると、牧村はホールの方へ歩いた。老婆もヒョコヒョコとつい
てきた。ここまで来ると、駅の待合室のように人が多かった。牧村は、新聞スタ
ンドで新聞を一部買い、ふらりと食堂に入った。石鹸で丁寧に手を洗っている
と、誰かが声をかけた。眺めると、レントゲン技師の朝倉だった。窓の近くのテ
ーブルで、カレーライスのスプーンを振り上げていた。
牧村は、笑ってうなずいた。ペーパー・タオルで手を拭いた。それから、骸骨
がトレーニング・ジャージを着ているような体で、ゆっくりとそっちへ足を運んだ。
「やあ。めずらしいですね、牧村さん」
「おれは、鳩時計のように正確さ」牧村は、朝倉の横の椅子を引いた。「めずら
しいのは、朝倉さんの方じゃないですかね」
「ハッハ、そうかな」朝倉は、色白のぽっちゃりとした丸顔をくずした。
「いつも不思議に思うんだが、」牧村は、一息ついて言った。「朝倉さんを見て
いると、いつも七福神を思い出す」
「じゃ、きみはいったい何だい。まるで・・・」朝倉は、そう言ってちょっいと考え
た。「君の方がむしろ不思議じゃないかね。考えてみれば、益々そうだよ。まる
で、貧乏神が、」
「ハッハッハ、分った。そのぐらいにしといてくれ。こっちは病人なんだ」
「言い出したのは、君の方だ」
「分ったよ」牧村は、テーブルの上に両手をついて、ゆっくりと椅子に腰を下ろし
た。「ただ、朝倉さんの健康そうな体が、うらやましかっただけさ」
「ふむ、そうか。じゃあ、やめよう」
牧村は、給仕の一人に手を上げた。目顔で合図を送った。給仕は、分った、
と指を立てた。牧村は、今は好きな物を食べるというわけにはいかない身分だ
った。献立は、とっくに彼の胃袋とは何の関係もない連中が決めてあった。そ
れがコンピューターに入力されてあり、後はただ運んできてもらうだけである。
「火星探査隊の出発も、いよいよ大詰ですね」朝倉は、スプーンを使いながら言
った。
「ああ・・・」
牧村は、新聞を脇へやった。そして、奥の広い壁面の半分以上を占めてい
る、高品位コスモビジョンの映像を眺めた。火星の、赤茶けたザラザラした砂漠
のような大地が、大写しで映っている。ゆっくりと流れていく大地。その火星の
空は、夕焼けのように淡いピンク色に染っている。まるで、自分も火星の大地
の上にいるような迫力があった。国連が、二年前に、無人貨物船を火星軌道に
送り込んでいる。そこから、火星に降りている無限軌道の探検車の映像を中継
しているのだ。左下に出ているマークは、この中継が、リアルタイムで処理され
ていることを示している。つまり、地球までの電波の所要時間と、コンピュータ
ーによる画像処理の時間を差し引いた、ほとんど現在の火星の姿である。
映像は、つぎに、火星をはるか上空からとらえた。赤道上空約二十万キロ
の、無人貨物船のカメラからだ。その高空から眺める火星の姿は、まるで赤々
と燃えているようだった。
給仕の佐川が、片手でワゴンを押しながら、牧村の横に来た。牧村の前に、
ステンレスの盆を置いた。それから、オシボリを一つ渡した。
「ありがとう」
「みんな食べてもらいますよ、牧村さん」
「残したことがあったかな?」
「ええ、」佐川は、ムッツリと口をつぐんだ。それから、食堂の中を見回し、付け
加えた。「とにかく、そういうお達しなのです」
「分ったよ。ここへも来れなくなったらおしまいだからな」
佐川は、何も言わなかった。
牧村も、昼食にとりかかった。佐川は、牧村の傍らに立っていた。ワゴンに
片手をかけ、ポーカー・フェイスで壁面のコスモビジョンを見ている。
「昨日のレースは、とったのかい?」牧村は、佐川に聞いた。競輪の話だった。
「落としましたね。最後のレースで、何とか戻しましたが、」
「かたいんだな」
「今日も買いますか?」
「うむ。ま、後で考えてみるさ」
牧村は、味噌汁の椀を取り上げた。そして、コスモビジョンの女性の声に耳を
傾けた。
“・・・なお、この太陽系第四惑星は、毎秒24キロメートルの速度で動き、 約
687日の周期で太陽のまわりを回っています。したがって、地球に最も 接近す
るのが、二年二ヶ月に一度。自転は、約24時間37分。自転軸は、 火星軌道
面に対し、約66度傾斜。赤道における半径は、3397キロメー トル。質量は、
地球を1とした場合、0.11。密度は、3.92。表面気圧は、地球の1013ヘク
トパスカルに対し、7.7ヘクトパスカル。脱出 速度は、地球の・・・”
「こんな所に基地を作ったって、」朝倉が言った。「住みたくはないものだな」
「南極にだって、住んでいるじゃないですか」
「しかし、この地球を出て行くのは、バカ者さ。それが分かっていないね。この
生命圏を、離れるべきではないよ」
映像はやがて、日本の衛星軌道基地“穂高”にかわった。“穂高”の窓から、
地球の青い海洋と、ちぎれた真綿の様な白い雲を見下ろした。それが、コスモ
ビジョンの横八メートルの画面いっぱいに広がった。こうして見下ろす地球は、
宇宙に浮かぶ、巨大な青い水玉のようだった。
「この地球を、核戦争で失いたくはないものだな」牧村は言った。「仮に、人類
が滅亡しても・・・」
「うむ・・・」朝倉も、ゆっくりとうなづいた。
カメラが、スッ、と後退していく。そして、今度は、ソ連邦宇宙実験基地副司
令官ガレエフ大佐と、その一行の姿が映った。マイクを前にして、一行はニュー
ス・レポーターたちと歓談している。
ガレエフ大佐の太い眉毛、フサフサした黒髪、のどかな黒い瞳は、いかにも
北の国のスラブ人らしい印象を与えている。が、ガレエフ大佐ともう一人だけ
は、ソ連軍の軍服ではなかった。火星探査隊の、宇宙飛行スーツ姿だった。腕
と胸に、国連火星探査隊のエンブレムが縫いつけられている。このガレエフ大
佐が、火星探査船フォボス号の船長として、惑星間航行に関する全責任を負っ
ていた。そして、もう一隻の方のダイモス号の船長は、米空軍のバーソロミュー
大佐である。バーソロミュー大佐の方は、火星探査及び火星基地建設に関し、
全責任を負っていた。
「むろん、ウォッカを持って行かれるんでしょう、大佐」ニュース・レポー ターの誰
かが、英語で聞いた。
「もちろん・・・ウォッカも持っていく」ガレエフ大佐は、副官やまわりに 笑いかけ
ながら、よく通る声で、まずロシヤ語で答えた。それから、英語で 付け加えた。
「そして・・・サケも、バーボンも、スコッチも、ワインも。 だが、少々・・・」
みんなの笑い声が広がる。
「長い航海になりますが、ガレエフ大佐、その間、ずいぶんと退屈されると 思
いますが、」
「オーケイ・・・我々には、非常に多くの任務と、期待がかけられている。 天文
観測、通信、そして惑星間航行に関する、工学、医学、航法等の、膨大な諸問
題・・・太陽系開発は、今まさに、ここから始まる。我々は、地球を遠く離れた宇
宙空間での一日一日を、貴重な歴史資料として残して行くことになるだろ
う・・・」ガレエフ大佐は、小さくうなずきながら話し、同じように自分の取り巻きた
ちにうなずき、そして大きくうなずいて、言葉を結んだ。
拍手が沸き起こった。
「これが、いかなる形であれ、」と、ニュース・レポーターの一人が、拍手の中で
言った。「太陽系文明史に刻まれる、第一節であることは間違いない でしょう」
「ありがとう、諸君!ありがとう!」大佐は立ち上がって、演出効果満点に 手を
振りかざした。
「最後に、もう一言、大佐。今回の火星探査が、十六名という大構成になっ た
点について、」
「オーケイ・・・探査船が二隻になったことは、きわめて心強い。我々は、 万一
の事故で一隻が航行不能に陥っても、残る一隻で十分地球へ帰還できる保証
を得た。我々は、必ずや、この太陽系大航海時代の第一歩を、人類の頭上に、
国連の頭上に、持ち帰ることが出来るでしょう!」
まわりから、拍手と喚声が沸き起こった。
高品位コスモビジョンを見ている食堂の中でも、拍手があがった。
「そういえば、牧村さんの弟さんは、“穂高”に居るんでしたね」朝倉が、牧村の
方に顔を向けた。
「ああ。あの宇宙船建造組だ。もう宇宙滞在時間が、六百日を越えているはず
だ」
「すると、いずれは、火星や小惑星あたりへすっとんでいくんですかねえ、」
「ああ。それが、アレの夢だった・・・」
牧村は、大きな口を開け、里芋の煮っころがしを口の中に入れ、ハシを抜き
取った。それを、もぐもぐとやった。それから、それをのみ下しながら言った。
「ま、アレとは、同じ墓に入れるとは思えんな」
「スペース・オペラの世界か・・・人類もこの銀河系で、いよいよ宇宙文明にまで
達した種族として数えられるわけか」
「有史以来、わずか七千年あまりでな」
「いや、」朝倉は、カレーライスの皿を脇へかたづけ、コップの水を取り上げて言
った。「人類が、蒸気機関を発明したのは、わずか二、三百年前のことでした。
全ては、そこからです」
「うむ」
「ということは・・・我々の銀河系でも、宇宙文明にまで達した種族が、予想以上
に多いんじゃないかと思う」
「宇宙文明論か。しかし、ネコやアヒルが、いつ宇宙へ出かけていくかね?」
「しかし、現に、こうして我々人間がいるじゃないか」
「ああ、」
「君は人間というものを、特殊に、あまりかいかぶりすぎてやしないかね、」
「ふーむ・・・」
朝倉は行ってしまった。牧村は、最後にヨーグルトを食べながら、食堂に入っ
てくる人々を眺めた。それから新聞を開き、写真と見出しを拾っていった。気に
入ったものは、さっと読んだ。
フランスのマルセイユ港で、また兵器を満載した二千トン級の密輸船が摘発
されていた。さらに香港でも、機関銃と弾薬を積んだジャンクが二隻おさえられ
ていた。最近、再びこうした武器の闇ルートの摘発事件が、新聞をにぎわすよ
うになっている。各国の兵器産業や、その闇市場が、巻き返しに出ているとい
われている。が、国際世論を背景に、締めつけはさらに強くなる雲行だった。
二面には、国際世論調査の特報が載っていた。国連は、太陽系開発計画の
第一段階として、火星・アステロイド開発計画で、大きなポイントを上げているこ
とが書かれていた。そして、さらに、一連の世界軍縮会議の成功で、徐々に力
を付けつつあるのが趨勢とある。が、むろんこれは、混乱を深める世界情勢の
中での、希望的観測が多分に含まれていた。いずれにせよ、もはや国連によ
る再構成しか、世界平和への道はなかった。
牧村も、むろん、この国連路線を支持していた。牧村は新聞をたたみ、ゆっく
りと立ち上がった。こっちを見ている佐川に、手で合図を送った。佐川も、小さく
手を上げた。牧村は、新聞を屑かごに放り込み、食堂を出た。それから、ミル
ク・スタンドや、ブックセンターや、クリーニング取扱所を眺め、ホールの真ん中
にある明りの入ったショウ・アイランドを眺めた。そのアイランドにある案内坂
に、病院での文化祭のポスターが張られていた。医学的な専門分野の発表か
ら、患者たちの手芸、書画、短歌や俳句、ビデオ等にいたるまで、さまざまな募
集を始めている。
牧村は、エレベーターを使い、五階の屋上まであがった。屋上には、気持ち
のいい秋風が吹きわたっていた。かなりの人出だった。ベンチがあり、ススキ
の株植えがあり、隅の方に卓球台が二つあった。ずっと向こうの端の方には、
ロケットの形をしたアドバルーンが上がっていた。そこに、今週の健康標語のた
れ幕が下がっている。
この新病棟の東側には、一段低い旧病棟が二棟並んでいる。その一号棟の
屋上に、ペイントで描かれた、ヘリポートのマークが見える。そして一号棟の向
こうには、寄田の市街地が一望できた。秋の日射しを浴びて、その一群のビル
が白くかすんでいた。こうして見る限り、日本は豊で平和な国だった。
牧村は、かすかな頭痛を感じながら、南側の鉄柵の方へ歩いた。そこから
は、音無川の渓谷が一望できた。まるで秋のうれいをひめたような樹林が、鬱
蒼として下っている。その底に、音無川の川原が、所々白く見えた。その川に
そって県道が一本登っているのだが、樹林の中にかくれていた。音無川は、今
は落ちアユの観光ヤナのシーズンである。
「よう、牧村!」
「ん・・・ああ、」牧村は、滝本がやってくるのを眺めた。
「今日は、いい天気だな・・・」
「うむ、」滝本は、ドン、と牧村の肩に手を置いた。乱暴なヤツだった。
滝本はそれから、鉄柵にドスンとよりかかった。浴衣姿で、ぼさぼさの髪を秋
風になぶらせ、ニヤニヤ笑っている。
「しかし、ずい分とまあやつれたじゃねえか」
「ま、そのうちに、全部なくなっちまいそうだな」
「ハアッハッハッハッハッ、とにかくだ、食わんことには話にならんぜよ」
「分ってるさ」
「ふむ・・・」滝本は、頭をかきながら目を細め、渓谷の方に顔を向けた。
滝本は、何に関しても、めんどう見のいい男だった。が、その話しぶりや、雰
囲気ほどには、神経の太い男でもなかった。それに何かがあると、真面目な顔
で、すぐにコケてしまう男だった。が、そうしたところが、男どもの間では、なか
なか人気があった。
「ところで、牧村」滝本が言った。「ジープをちょっと貸してくれんか」
「ああ。いいぞ。どこへ行くんだ?」
「ちょいと、みんなで競輪場へな。今日が最終日だ」
「そうか・・・今日が最終日か、」
「おめえは、一緒には行けまい」
「ああ。おれはいい。ジープの鍵は、おそらく北野が持ってるだろう」
「北野って、あの看護婦のかい?」
「ああ、」
牧村も、鉄柵に背中をもたせかけた。頭が、またひどく重くなってきた。牧村
は、額に手を当て、大きく息をした。
「じゃあ、なにかい、取り上げられちまったのかい?」
「まさか、おれが?ちょっと貸しただけさ」牧村は、額に手を押し当てながら笑っ
た。「ま、返してくれねえがな」
「どうして?」
「知るか。色々と理由をつけてな。看護婦連中が、便利に使ってるようだな」
「チエッ、そんな話しってあるかい!」
「連中を、敵に回した方が得策だと思うか?」牧村は、笑いながら聞き返した。
滝本は、浴衣の胸に手を突っ込み、胸毛の上をぼりぼりかいた。
「まあな。おめえじゃあ、腕力でも勝ち目はねえ。追いかけることもできねえな。
それにしても、情ねえ話しだぜえ」
「タバコを持ってるだろう?」
「ああ、」
滝本は、たもとからタバコの箱を出した。箱の隅をたたき、一本うかせた。牧
村が、それを抜いて口にくわえると、ライターで火をつけた。
「北野か・・・おりゃあ、あの看護婦は苦手だぜ」
「使うんだったら、取り返すんだな」牧村は、タバコの煙を吐きながら、滝本を眺
めた。
「よーし、分ったァ、森本にやらせてみるか。取り返しといてやるぜ」
「うむ」
病室に戻ると、丸テーブルの上に手紙が一通置いてあった。牧村はそれを
取り上げ、裏をひっくり返してみた。差出人は、久保洋一となっていた。九年
前、科学実験用原子炉“富楼那”で、一緒に放射線被曝した仲間の一人であ
る。その五人の仲間のうち、一人はすでに他界していた。また、軽度の被曝で
すんだ一人は、再び社会の渦にたち返っている。現在、なお病床にあるのは三
人だったが、もう最近では、互いに連絡をとりあうことも無くなっていたのだ。
が、この今の時期に、わざわざ手紙が来たということに、牧村は人の世の、奇
妙な“符号”のようなものを感じた。
これが、いわゆる、人間の“絆”というものか・・・牧村は、心の中でつぶやい
た。それとも、久保の方も、すでに死期が迫っているのだろうか・・・
が、こうやって、一人、また一人と、やがてみんなこの世の舞台から下りてい
くわけだった。さまざまな事故や、災害や、犯罪の被害者が、常にそうやって忘
れられてきたようにだ。あるいは、さまざまな加害者の側が、そうやって同じ時
の流れの中で、心の傷を癒してきたようにだ。
牧村は、しかし、こうした時空座標をめぐりめぐる、経歴や歴史という真実が
好きだった。そこに刻印される真実の結晶と、風が吹きわたるように流れてい
く、人間の影と香りが好きだった。そして自分もまた、その非情な真理の歯車
に噛み合わされ、この世の外に送り出されていくことに、感動も覚えていた。
牧村は、手紙を手にして、ぼんやりとたたずんでいた。それから、ドサリ、とリ
クライニングになっているベッドの上に腰を下ろした。このごろはもう、ほんの少
し動いただけで、体がひどく疲れた。自分の体が、しだいに意志の通わない、
ただの肉と骨の塊になっていくのが分るのだ。
そうやっていると、しだいにまた頭が重くなり、体も重く、ひどく気分が悪くなっ
た。そして、長い間忘れていた、悲しみという感情が顔をのぞかせた。牧村は、
それを不思議なもののように眺めた。そうしたものは、どうやら肉体の中に、頑
強にしみこんでいるものだと知った。さらに眺めていると、まるで思いもかけな
いことだったが、自分の人生に対する悔恨の情が、胸をしめつけ始めた。
牧村は、そうしたものは、とうの昔に、自らの心のうちで処理できたものと思
っていた。今さら欲望も、過去の事象に対する悔恨も無いはずだった。が、ま
だ、存在する肉体そのものの中に、明らかに残っていたのである。
牧村は、ベッドに腰を下ろし、壁の『睡蓮』を眺めた。その大きな絵の額の横
には、もう一つ小さいアルミフレームのパネルがあった。そこには、詩が入って
いた。牧村は、その詩を一週間ごとに入れ替えていたが、今は『正法眼蔵』の
“有時”の一節が入っている。牧村は、それをさっと読み下した。それから、ゆっ
くりと立っていき、ロッカーの中から、かなり以前に入れたことのある『一夜賢者
の偈(げ)』を選び出した。そしてそれを、“有時”の一節の上に、重ねてパネルに
入れた。
この『一夜賢者の偈』という詩には、かって、今のように悩んだ頃の思い出が
あったからである。もっとも、牧村自身、以前の彼ではなかった。今はこの詩
も、懐かしい思い出として掲げたのである。自分自身の歩んできた、真実の結
晶世界の道しるべとして・・・
牧村は、久保洋一から来た手紙を拾い上げた。そもそもの原因は、この手
紙にあった。牧村は、ため息をつき、バルコニーの方を眺めた。それから、弟か
らも電子メールが届いているのを思い出した。結局、気の重い久保からの手紙
よりも、弟の電子メールの方を先に見ることにした。牧村は、手を伸ばし、パソ
コンのキイボードをたたいた。メッセージのトップに入っている、弟からのメール
を呼出し、スクリーンに表示した。
スクリーンに、派手な宇宙開発機構のマークが出た。それから、立体的に回
転していく国連のマークが出た。つぎに、衛星軌道基地“穂高”のプラントの全
景が映り、その上に重なって、弟の顔が透けて映ってきた。弟は、国連のサテ
ライト・スーツ姿で、髪をテカテカにし、はつらつとしていた。
「ヤア、兄さん、元気でやってますか?そっちは、もう秋ですね。しかし、宇宙空
間は、相変わらずの真冬です。もっとも、北半球の黄葉前線の南下は、ここか
らも見えます。ところで、音無川の渓谷が黄葉を始める頃には、ぼくの組も地球
へ降ります。火星探査船の最終ライン、38万キロ上空の月軌道離脱は、おそ
らく地上で見ることになるでしょう。」
「兄さん、宇宙からの土産は、何がいいですか?ここの名産の、インターフェロ
ンにしますか?それとも、宇宙合金の置物がいいですか?最近では、宇宙キ
ャンデーも人気とか。では、兄さん、近々・・・」
牧村は、電子メールをファイルし、パソコンをオフにした。それから、ペーパ
ー・ナイフを取った。そして、ため息をつきながら、久保の手紙を開封した。久保
の手紙は、相変わらずの身の回りのことだった。そうしたことを、事細かに書い
てきた。そして最後に、久保はいつもそうするのだが、短歌が二首並べて書い
てあった。
第二章 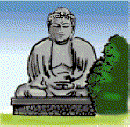
その日の午後もおそく、牧村はベッドの上で目を覚ました。彼は、目を覚まし
たまま、暗くなってきた天井を静かに見つめていた。部屋の中に、秋の夕暮れ
の、静かな濃密な時間が流れていく。
しばらくして、牧村はゆっくりとバルコニーの方に顔を向けた。遠く、渓谷の向
こうの尾根の空が、赤々と夕焼けに染りだしている。牧村は、そこを眺めなが
ら、何も考えないでいた。ただ、その、すさまじい真理の姿だけを見つめてい
た。・・・菩提樹の木の下で、悟りを得た後の釈迦の一生は、静坐と、托鉢と、
説法と、そして夢を見ない深い眠りのくり返しだったという。牧村は、この夢で
はない、目に映っている真実の結晶の姿を・・・あらゆる言葉の薮を払い除け
た、目に映っているナマの概念そのものを見つめていた。
この、秋の夕暮、風にかすかにざわめくケヤキの梢、それを埋める空間時
間。すべて、牧村自身の姿だった。歴史、未来、無限に広がる空間と“今”・・・
何者とも知れない、この存在世界の意味の流れ・・・自我の認識・・・みな、一枚
の、彼自身の“命”の風景だった。
カチャ、とドアの切れる音がした。人の気配が、部屋に入った。牧村は、それ
が北野看護婦だと分った。が、それが彼女だと分っても、どういう経路でそれ
が彼女だと分ったのかは分らなかった。ただ、なんとはなしに分ったのである。
日常の中に頻繁にあるこうした類の問題は、牧村自身、かなり長い期間考えて
きたことだった。
直観、認識、確信・・・そうしたものの閉鎖系としての人間社会・・・そうした意
味世界の全体を、“今”という走査線によってトレースしていく、超媒体の
“命”・・・
牧村はしかし、“今”の走査線をはるかに飛び越えて、自分自身の未来を自
覚したこともあった。牧村は、このことは誰にも話したことはなかったし、これか
らももう話すことはないだろうが、彼は自分が放射線被曝というような異常な人
生を歩むことは、あの事故よりもかなり以前から分っていたのである。むろん、
それが、科学実験用原子炉“富楼那”による放射線被曝とまでは分らなかった
が。
しかし、牧村は、こうした奇妙な経歴を重ねつつ、“命”や“人生”というもの
の意味が、すこしづつ分りかけていたのである。それはまさに、この“分る”とい
うことのために自分は生まれ、あの原子炉での放射線被曝という大事故にも
出会ったのではあるまいかと。また、そこに、“人間”の明らかな閉鎖系要素が
見えるのではあるまいかと。そうした人格的時空構造についても、彼は考えた
かったのである。が、彼には、すでにその猶予はありそうもなかった。しかし、
いずれにせよ、彼がこの被曝という運命をあまり悲観的に考えたことがないの
も、この予定されたコースを、おぼろげながらも、あらかじめ知り得ていたから
である。
牧村は、夕映えを眺めながら、ふと記憶の中にとどめていた、ある短歌を心
の中でつぶやいた。
暗きより
暗き道にぞ入りぬべし
はるかに照せ
山の端の月
この、無明の世界を歌った歌である。御仏の教えを山の端の月にたとえ、人
生のこの暗く細い山道を、どこまでも照していってほしいという願いが込められ
ている。これを歌った歌人の心境が、奈辺にあったかは、古典に親しんだこと
のない牧村には分らなかった。しかし、牧村は、ずっと昔からこの歌が好きだっ
た。
いつしか、部屋の中の物音も絶えていた。北野看護婦の気配も、どこかに消
えてしまっている。牧村は、細い深呼吸をし、ゆっくりと体をそり返した。
北野は、ドアの方の、『睡蓮』の絵の掛かっている壁の前にたたずんでい
た。束ねた後髪を止めているヘアピンがにぶく光り、すらりとした白衣が、かす
かに夕映えの色を映していた。しかし、北野が見ているのは、『睡蓮』の模写絵
ではなかった。その横の、パネルに入った詩の方だった。さっき牧村が入れ替
えた、『一夜賢者の偈(げ)』と題されている詩である。それは、こう書き綴ってあ
る。
過ぎ去れりを追うことなかれ
いまだ来たらざるを願うことなかれ
過去、そはすでに捨てられたり
未来、そはいまだ至らざるなり
されば、ただ現在するところのものを
そのところにおいて、よく観察すべし
揺るぐことなく、動ずることなく
そを見きわめ、そを実践すべし
ただ今日、まさになすべきことを、熱心になせ
たれか明日、死のあることを知らんや
まことに、かの死の大軍と
遇わずということはあることなし
よくかくのごとくみきわめたる者は
心をこめ、昼夜おこたることなく実践せん
かくのごときを一夜賢者といい
また、心しずまれる者というなり
「釈迦がまだ、あのヒマラヤの山麓に実在していた時代だ・・・」牧村は、北野
看護婦に、ぼそりと話しかけた。「その頃、巷で語られていた、読み人知らずの
偈(げ)だ・・・」
「お釈迦様の詩ではないのね・・・」北野は、沈んだひきしまった顔を、牧村の方
に向けた。夕映えが、彼女の頬をほの赤く染めた。
「ああ。しかし、気に入られていたようだ。あの頃・・・摩掲陀国の都は王舎城と
いった。その近くに、温泉精舎というのがあった。いわゆる、温泉が湧いていた
んだろう・・・」
彼女は、何も言わず、知的な顔をひきしめ、牧村の言葉を待っていた。
「釈迦が、その温泉精舎に居留していた時、三弥提という名の比丘(びく)が、釈
迦にこの偈(げ)の解説を願い出たと書かれてある・・・」
北野は、小さくうなずいた。そして、横顔を見せながら、パネルの詩の意味を
見つめていた。
「それで、お釈迦様は、なんて解説されたんですの?」
「まあ、それは、そんなに単純なものじゃあない。煩瑣(はんさ)哲学のような薮の
中に入ってしまうようだ。だから、その詩はその詩として、作者の意図したとお
りに受け取っておけばいい」
彼女は、黙ってうなずいた。
「当時の彼等の思想の斬新さは、今でも目を洗われるようなものばかりだ」
彼女は、牧村を眺めた。
「どうしてなのかしら?」
「多分、科学ではなく、人間学だからだろう」
「そう・・・」
「もちろん、仏教は、宗教だが・・・」
「生きるってことは、ねえ、牧村さん・・・やっぱり、悲しいことかしら?」
「さあな・・・君はどう思う?」
「病院という所は・・・」北野は、歩いてきて、牧村の肩に指を立てた。「どっちに
しても、楽しい人達が集まっている所ではありませんわ」
「君が、そんなことを言うとはな、」
「ええ、」彼女は、顔を落とした。「ただ、時々、そんな気持ちになることがありま
すわ」
「それはそうだ。しかし、おれはこう思う・・・自分も、この奇妙な世界の旅人だっ
た。そして、君も、他の大勢の友達も、みんな旅人だった。ただ、それだけのこ
とだと、」
「そうね・・・」
「“月日は百代の過客にして、行きかう人もまた旅人なり”という、」
「芭蕉の『奥の細道』ね、」
「ああ、」
「そうね、」北野は、はずんだ、晴々とした声に切換えて言った。「そういうふう
に考えると、いいですわね」
北野が出ていった後、牧村は夕食の時間まで、ぼんやりと過ごした。窓の外
の夕焼けが、しだいに灰色の夕闇の中に溶け込んでいく。
「オイ、いるかァ!」ドアの所で、誰かが声をかけた。廊下の明りを背に、長身
の男が突っ立っている。
「ああ、いる。入れ、」牧村は、暗いベッドの上で言った。
「おれだ。おれだよ。アユを食うか?」笑いを含んだ、脇坂の声がとんできた。
「ああ。食うとも。なんだい、今日も行ったのかい?」
「うむ。じゃ、二匹やろう。すぐに焼いてやる」脇坂は、影絵のように手を振り上
げ、姿を消した。
さあ、今日もアユが食えるな、と牧村は思った。それほどアユが好きというわ
けではないが、かって川を歩いた頃の郷愁があった。脇坂は、病院の事務員
だったが、三年ほど前までは、牧村をよく釣に誘ったものだった。
牧村は、脇坂の声を聞くと、なんとなく愉快な気分になった。この世の中は、
考えてみれば、すべてがマンガじみていた。すぐにコケるヤツ、女房をほったら
かして釣ばかりしているヤツ、真面目すぎて、それが少しもきまらないヤツ。こ
の病院の中だけでも、実にいろんなヤツがいた。そして、いいヤツも悪いヤツ
も、出世ばかりたくらんでいるヤツも、いずれはみんな死んでいくのが愉快だっ
た。悲劇も喜劇も、美しいものも醜いものも、みんな時間に押し流され、跡形も
残さないわけだった。
牧村は、しかし、その“死”というものについては、それほど深く考えたことが
なかった。『チベットの死者の書』の巻頭の句に、こう書かれてある。
“死ぬことを学べ。そして汝は、生きることを学ぶだろう。
死を学ばなかった者は、生きることを何も学ばないだろう”
が、牧村は、さしてそうはしなかったわけである。しかし、『チベットの死者の
書』に書かれているような、死の瞬間だけが、“死”の全てではないだろうと、牧
村は思っていた。“死”の大いなる海、“死”の大いなる河、そして“死”の、無限
に広がる時空があるはずだと思っていた。
そうした“死”について、最近牧村の印象に残っているのは、今年の春の出
来事だった。あれは多分、彼岸を幾らか過ぎた頃だったろう。病院から寄田市
街の方へ下る近道の途中に、杉やアカシヤの木立にうずまった、二、三百坪ほ
どの墓地があった。いつもひっそりとしている、陰気な墓地だった。が、今年の
春に限っては、やけににぎやかだったものだ。まだ真新しい白木の棺か輿か
が、墓石の立つ林の中の方々にあった。この地方の風習で、いまだに土葬に
するものらしかったが、数えると十五、六個もあった。牧村は、ジープからそれ
らを眺めながら、ひとりほくそ笑んだものだった。
誰かは知らないが、どこそこのうるさい婆あさんもいただろうと思った。それ
に、どこそこの気難しい爺さんもいただろうと思った。そうした人々が、みんなア
タフタ、バタクサしながら、結局はそこへ納まさってしまったのがおかしかった。
そして、古くさびた墓石の前にもっともらしく祭られ、それこそ生真面目な顔をし
て眠っている。墓地の中に担ぎ込まれてしまえば、文句もなく、平和であり、全
てが平等で静かな風景になる。そして、夜には、大きく伸びた杉やアカシヤの
木立の間から、星空がのぞく。そして星空は、死者に宇宙の静かな運行を伝え
ていくだろう。永遠に永遠を重ね、さらにこの宇宙の終わり、この意味世界の消
え果てるまで、死者に静かな死の時が流れていく。牧村は、この墓地に葬られ
るのも、悪くはないと思ったものだった。
それから、もう一つ、牧村が今でも時折思い出すのは、三、四年前に琵琶湖
へ旅行した時に見た、大きな鯉の死骸の風景である。あれは確か、十二月の
中旬だったろう。カラリと晴れ上がった冬空の下で、琵琶湖の湖面がのどかに
さざ波をたてていた。そして、そのさざ波の中に、巨大な鯉の死骸が浮かんで
いるのを見た。その鯉のあまりもの大きさに、牧村は友人二人と共に、船着場
の棧橋の先まで降りていってみたものである。鯉は頭の先から尾鰭の先まで、
1メートル半はらくにあった。それが腐乱し、全体がビヤ樽のようにふくれ上が
り、彼等はその姿に強く心を打たれた。
彼等は、長い間その大鯉の死骸の風景を眺めていたものだった。すると大
鯉は、冬の冷たい北風に流されて、しだいに棧橋の方に近づいてきた。が、や
がて、左手に広がるヨシ原の方へ漂っていった。そしてヨシ原にたどり着くと、
大鯉はそこで、プカリ、プカリ、と打ち寄せる波にのどかに揺られていた。それ
からしばらく見ていると、大鯉は少しづつ、広いヨシ原の中にのみこまれていっ
た。
牧村は、その大鯉の、大いなる死の風景の感動が、今も忘れられなかった。
その死の風景には、何故か甘い憧れがあった。牧村自身、すでに長い闘病生
活にあり、そうした肉体に対する自己の所有という次元を、越えたかったので
ある。そして、彼も、この不可思議な幻想世界の大海原を、あの大鯉のように、
悠々と漂ってみたかったのである。
開け放しになっているドアに、ゴン、と靴で蹴飛ばしたようなノックがあった。
それから、わざとらしい咳払いがした。パッ、と天井に明りが灯った。やや小太
りの若い看護婦が、顔をほころばせながら、もそもそと食事のワゴンを引っ張っ
て入ってきた。
「どうですか?痛みはないでいかあ?」
「ああ、」牧村は、肩で大きく息をした。「痛みはないよ。今夜の御相伴は、尾崎
さんか、」
「そうですよう。ブドウ、食べますか?今日、家から送ってきたんです」
「うむ、」牧村は、リクライニングになっているベッドの背を、電動でもう少し起こ
した。「ほう、こいつはうまそうなブドウだ。尾崎さんの田舎は、どこだったか
な?」
「勝沼ですよ。毎年聞くんですね、もう、」
「ああ、そうだった。本場だったな」
「甘いですよう、」彼女は、カゴに自分で盛りつけてきたブドウを、一粒もいで口
に入れた。「うまいですよう」
「うむ、」牧村も、その黒い大粒のブドウを、指先でひねってもいだ。
牧村が、そのブドウを口に含んでいる間、彼女はベッドの上に回転式のテー
ブルをセットした。その上に、ワゴンの盆を置いた。温かい御飯と味噌汁、ガラ
ス皿の野菜サラダ、そして脇坂の釣ってきたアユの塩焼があった。それから、
大きな房が三つ積み上げられている、ブドウのカゴだ。二尾のこんがりと焼か
れたアユは、笹の枕の上に頭を揃え、牧村に食べてもらおうと誘惑していた。
脇坂の心づくしの料理だ。
「たくさん食べて下さいね。テレビ、見ますかあ?」
「うむ、君が見たけりゃ、」
彼女は、テレビはつけなかった。ベッドのかたわらで、無造作に盆の上から
ブドウをもぎ取り、口に入れていた。
「今頃が、一番いい季節ですね」彼女は、ブドウを食べながら、クルリと軽くひと
回りして言った。
「ああ・・・」
牧村は、そっとハシを下ろした。そして、闇に埋まったバルコニーの方に目を
やった。遠く、かすかに、尾根の崚線の黒いシルエットが見える。牧村は、ぼん
やりとそこを見ていた。それから、ゆっくりとアユをひとかけらくずし、口に入れ
た。
「どうなんだ、まだ恋人は見つからんのか?」
「ええ、まだ」彼女は笑いこぼし、口もとを押さえた。
「ふむ、」牧村も笑った。「よくある話しさ」
「どういう意味ですかあ、それ、」
「君の人生は、まだまだ長いということだ」牧村は、苦笑して言った。
「うーん、」彼女は上を向き、ブドウを二つ口に放り込んだ。
「さて、そろそろニュースの時間だな。テレビのスイッチを入れてくれないか」
「はーい、」彼女は、パソコンの方へ行き、キイボードをたたいた。
テレビは、世界軍縮会議の模様を中継していた。今は、第五回目の会期中
で、北京で開催されている。この会期中に、第一次火星探査隊の出発がある
わけである。その時、軍縮ムードは最高潮に達すると言われている。会議のテ
ーマも、全核兵器の国連による査察、及び管理の問題に入ってきている。また
最近では、国連総会でも、しきりと二十一世紀の地球文明の、新しいシナリオ
作りの演説が行われている。武装国家乱立の軍事対立的な文明構造から、新
たな、より自覚的な文明構造への脱却が叫ばれている。しかも、現実は、南北
東西間の生活水準技術水準の格差の増大、地球規模での長期的な異常気
象、危機的な食料問題と飢餓、さらに地球の砂漠化の進行等で、事態は一刻
の猶予もないところまできている。豊な日本にいては分らないが、すでにパニッ
ク的な軍の暴走か、民衆の爆発かの、レッド・ゾーンに入っているのである。地
球と地球文明そのものが、まさに疲れ果てている。そして、唯一の希望の光り
が、国連主導による、火星・アステロイド(小惑星帯)開発計画の順調な進行で
ある。
「どうして、すぐに全面凍結できないんですか?」尾崎は、怒ったように牧村に
聞いた。「だって、みんな賛成してるんでしょう。核戦争なんかやったら、地球は
おしまいなんでしょう?」
「反対してる人間は、一人もいまいな・・・しかし、無くならん・・・ま、核爆弾なん
てものは、最初から作るべきじゃなかったんだろうな。こいつは、使えない兵器
だ。作ったとしても、広島と長崎で、やめておくべきだった」
「でも、」彼女は、頬をふくらませた。「全員が軍縮に賛成してるんなら、どうして
決まらないんですかあ?」
「それが、そもそもの出発点だった」
牧村は、味噌汁の椀を口へ運んだ。味噌汁は、だいぶ冷めていた。
「もったいないのかしら、」
「まさかな、」牧村は、椀を置いて言った。「しかし、大丈夫だ。いずれは凍結す
るさ。そしたら、段階的に、国家というワクなどは取り払っていけばいい。そし
て、誰もが平等で、自由に生きていける社会を作っていけばいい」
「そうすれば、戦争はなくなるんですかあ?」
「まあ、今のような形での紛争や、世界戦略はなくなるな。世界政府ができて、
世界中がちょうど、日本の都道府県や市町村のように統治されれば。そうなれ
ば、今までの莫大な軍事力が、中に浮く計算になる。最終的には、その溢れ出
したエネルギーが、海洋開発や太陽系開発へ向けられていくことになるんだろ
うな」
「ふうん・・・」
「まあ、いずれにしても、やらなきゃならんだろう。科学的クライシスの社会的ポ
テンシャルが、どんどん高まっているのは確かだ」
「むずかしいんですね、」
「そうかも知れんな・・・」
牧村は、なんの飾り気もないこの娘と話をしていると、心がなごんだ。
「あ、そうそう、牧村さん。明日、お友達がお見舞に来るそうですよ。オフィスの
方に電話が回されてきました」
「いなかったのか?」
「ええ。昼食の時、」
「誰からだい?」
「ええと・・・」彼女は、乳房でパンと張った胸のポケットから、二つに折った紙切
れを取り出した。「椎名さんです。男のひとでした」
「ああ、椎名茂か。おれの幼なじみだよ」
「なら、たくさん食べて、元気になってくださいよう」
「ああ。そうしよう」
が、牧村は、さして食欲がわかなかった。しかし、それでも、のろのろとハシ
を動かした。弟から電子メールがあり、久保洋一から手紙が来、こんどは椎名
茂が会いに来るときた。
牧村は、深いため息をついた。窓の外の、闇を眺めた。遠くの方、病院の庭
園の木立の中で、下から登ってくる車のヘッドライトが動いた。
「ねえ、牧村さん、いいですかあ?」
「ああ、何だ、」
「人間が、あと百年も二百年も、千年も、生き続けていくと思いますう?」
「うむ。まあ、そうなるだろう。千年昔といえば、奈良か平安時代だ。なら、これ
から千年先や二千年先の時代も、当然あると考えられるだろう」
「そっかあ・・・」
「ただ、今からそうした時代を予測するのは難しい。目に見えない、予測できな
い技術開発や、新しい理念が生まれてくるからだ。たとえば、ナポレオンの時
代に、原子爆弾なんか、想像も出来なかったろう。相対性理論なんかも、まる
で見えなかった。しかし、そうしたものが、時代を大きく変えていく」
「じゃ、想像できないんですか?」
「可能なことは、現在の延長線で考えるということだ」
「ふうん、」
それから、彼女はまた来ると言って出ていった。牧村は、脇坂の心づくしの
アユをきれいにたいらげると、ハシを置いた。彼女が、一房残していったブドウ
に手を伸ばした。一粒もぎ取り、口に入れた。そして、テーブルを、脇の方へ回
転させた。
牧村は、テレビの音を消した。音が消えると、部屋の中がさっぱりとした。あ
とは牧村の感覚に、能動的に押し入ってくるものは何もなかった。『睡蓮』の視
覚的な“今”と、『一夜賢者の偈』の認識的な“今”と、開け放されている窓の外
の宵闇と・・・全てが、彼自身の世界に還った。
二次元のスクリーンの上では、ただ色彩と形態的図形イメージだけが、時間
の関数として静かに流れて行く。そこに、人間が不安定要素として関与しなけ
れば、価値関数の描くストーリイの広がりも、感情のうねりも、決定加重値と共
に起こる緊迫感も生まれてこない。変数が、ただ、限りなく流れていくのみであ
る。その二次元のスクリーンの姿は、この三次元宇宙、この意味世界そのもの
に関しても言えることだった。
やがて牧村は、大きな自分のため息を聞きながら、再び窓の外の闇を眺め
た。そして、その中に、“今”という走査線が作用する、永遠の過去の深淵と、
永遠の未来の関数を見ていた。そこではもはや、“時”は一次元のベクトルで
はなく、無限の“今”、永遠の“今”であり、認識の香る“普遍時間”の全体世界
だった。
しばらくすると、尾崎看護婦が、栗の小枝を持って入ってきた。緑色の大きな
栗のイガが、可愛いリボンのように二つ付いていた。それを彼女は、花台の上
にある生花に加えた。それは昨日、北野が活けていったものだった。草月流と
かだが、この追加を北野が何というだろうか。
「もう、その栗は、食べられそうだな」牧村は言った。
「ええ、あと一週間ほどだって言ってました」
「そうかあ・・・もう、そんな季節だな、」
尾崎は、夕食の盆をワゴンに移し、出ていった。
牧村は、ベッドから下り、バルコニーへ出てみた。バルコニーには、プランタ
ーに植えたコスモスの花が咲いていた。牧村は、部屋の明りに映えるコスモス
の花を眺めた。それから、渓谷の方の暗闇と、空を見上げた。月はなく、星が
二つ輝いていた。
牧村は、部屋に戻った。そして、書棚の上の段から、美術全集を二巻抜出し
た。浮世絵の巻だ。それを、丸テーブルの上に置いた。それから、肩で大きく息
をし、椅子を引き寄せ、スタンドの明りを灯した。夕食の後の時間は、いつも本
を読むことにしていたが、最近は写真や美術全集ばかり眺めていた。
牧村は、静かな慣れた手付きで、まず広重の『東海道五拾三次』のあたりを
開いた。牧村は、版画による、広重の素朴な東海道のストーリイが好きだっ
た。また、そこに描かれている、ミレーの農村風景の様な、素朴な人間の姿が
好きだった。しかし、牧村が、この連作の風景画が好きなのは、もう一つ理由
があった。それは、人間のトレースする体験の普遍性を、この東海道の連作の
中で発見していたからである。
牧村にとっては、江戸時代の真実の全ては、この広重の版画の風景の中に
実現していた・・・江戸の時代を今も生きていく人々、権力と民衆、人間の哀し
さ、海浜の雄大さ、夕暮れのわびしさ、時間の美しさ・・・これらは彼にとって、
この東海道の素朴な連作の中に結晶化していた。その、人間における歴史と
いうもののなつかしさが、そして過去という土壌の静かなぬくもりが、彼の心の
中で限りない情熱をもって溢れ始めていたのである。そして、その一枚の時間
風景の中に入っていくと、そこに住む、静的な豊な人々と巡り合うことが出来
た。そうした中を、彼はしだいに深く、遠く、過去の歴史の人々と巡り合い始め
ていたのである。
牧村は、この世界における“命”という超媒体が、いよいよ昇華する今になっ
て、どうやら世界の“意味”というものが、理解できかけていたのである。むろ
ん、論理的にではない。ただ、さまざまな事象からくる、実感としてである。山
の美しさの意味、空の深さの意味、海の広さの意味が、そしてそれらの限りな
い完璧さと、閉鎖系・人格系としての、“人間原理”の無矛盾が、である。
第三章
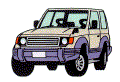


翌朝早く、牧村は塩崎医師と北野看護婦にともなわれ、脊椎腰部の三次元
NMR(核磁気共鳴)データを見せてもらった。十分ほどですんだ。二人のNMR
技師の他に、放射線障害の権威である仁科博士が招かれていた。仁科博士
は、すでに十数回にわたって牧村を診察していた。グレーのスーツの似合う、
銀髪の紳士である。
「それで・・・ええと、こっちは?」仁科博士は、パーカーのボールペンの尻で、
白黒画像の方を指した。
「陽子密度の比較です。上のカラーは、パルス列を変えてあります」若いNMR
技師が説明した。
「うむ・・・」
「次のは、さっきのと同じで、画像面を三センチほど動かしてあります」
「では、回してみてくれないかね・・・ああ、それでいい。うむ、うむ、うむと・・・あ
りがとう、よく分った・・・特に異常はないようだが、」仁科博士は、背広の内ポ
ケットにボールペンをさした。
「すると、」塩崎医師が、ずんぐりとした体を揺らして、そっと聞いた。
牧村は、無表情に塩崎医師を眺めた。塩崎医師は、赤ら顔で黒縁の眼鏡を
かけ、タワシのように濃いアゴ髭を生やしていた。牧村は、それから仁科博士
の方に目を移した。
「うむ、」仁科博士は、かすかに、だが深い意味を込め、うなずいた。
「では、牧村君には、引き取ってもらっていいですかな」
「どうぞ。では・・・牧村君、また会いましょう」
「はい」
「うむ。お大事に、」
北野看護婦が、牧村を病室まで送ってきた。
「さあ、すぐに朝食を運びますわ」
「今日は、これからまだ検査はあるのかい?」
「特に、予定はないはずですよ。どうして?」
「友達が見舞に来るんだ」
彼女は、納得し、微笑んだ。
「そう、椎名さんね」
「ああ」
朝食の後、ひと息ついていると、早々と椎名茂が姿を見せた。連日の牧畜
作業で、ナメシ革のように黒く日焼けしていた。そして、汗と陽光で鍛えた笑顔
に、白い愛嬌のある八重歯をのぞかせた。
「オーイ、なんだ、それはァ!」茂は、牧場で話すような地声で言った。
「オウ、」
茂は、両手に下げてきたビニール袋と雑嚢を、ドスン、とドアに立てかけた。
「まあ、えらく痩せたじゃねえかよう!」
「ああ。今年は、夏バテしちまってな、」牧村は、ベッドから脚を下ろした。
「いけんなあ・・・」
「今年は暑かったろう」
「まあな、」茂は、荷物をドアの所から、書棚の前まで運んだ。「まあ、この暑さ
で、少しは稲の方も盛返すと思ったんだがなあ」
「そういえば、冷害がでてるんだったな」
茂は、黙ってうなずいた。
「とにかく、こっちも大変さァ・・・」
茂は、ベッドのそばに椅子をもってきた。
「何時ごろ出てきたんだ?」
「まだ、暗かったなあ。おかげで、高速道路はずっとすいてたぜ」
「で、みんなは、相変わらずか?」
「ああ。あいかわらずさァ。観光開発をおっぱじめるとかでな。あのバカ共が、
大騒ぎだぜ」茂は、額をたたいて首を振った。
「まだ言ってるのか」
「ああ。黒井沢の方には、だいいち見る所なんて、何もありゃあしねえだろうが
ァ。それじゃ、テニス・コートを作れ、温泉をひっぱれ、牧場を開放しろときた。そ
んな金が、いったいどこにあるってんだい」
「猫も杓子も、観光の時代か、」
「ふざけてるぜェ、まったく」
牧村は、今度は半年ぶりに茂に会うわけだった。が、この半年の間に、茂は
ずいぶん変ったように見えた。元来の陽気な顔に、時々暗い影を感じさせるも
のがあった。それが、年を取るということか、と牧村は思った。人間は、こうし
た、日常的な年の取り方をするべきだった。しかし、すでに牧村には、それは
かなわぬ道でもあった。
「ああ、そうだ・・・」茂は、タバコの箱を丸テーブルの上に放り出した。「そうい
やァ、七月の末に、中村章一が死んだぜ」
「何だって?」
「あいつ、死んだよ」
「おいおい、本当か?」
茂は、真面目な顔でうなずいた。
「仲が良かったんだろう?」
「ああ。クラスが一緒だったからな。しかし、いったい、何で死んだ?」
「地獄谷の源泉よ。あそこの工事でだ。七月の末に、土砂崩れがあった。その
後だ。ありゃあ、すごい集中豪雨が来てなあ。そいつァ、すごいもんだったぜ
ェ」
「そうかあ・・・先に行ったか・・・」
「黒井沢じゃあ、二ヵ所で土砂崩れがあった。それに、五郎岩から鉄砲水が走
った」
「五郎岩からか?」
「ああ」
「あのあたりから、鉄砲水が走るかなあ?」
「そりゃあ、すごいもんさ。洪水じゃあないんだ。鉄砲水だぜ」
「うーむ。じゃあ、地獄谷もメチャメチャだったのか?」
「いや、あそこはそれほどでもなかった。分水嶺の方は、どうってこたあねえ」
茂は、目でハエを追って、天井を見上げた。
「べつに、川があるわけじゃねえからな」
「うむ、」
牧村は、今朝、北野看護婦から一本もらった、貴重なタバコに火をつけた。
「しかし、中村が、おれより先に死ぬとはなあ、」
「まあ、分らんもんさあ。おれも、三日ばかり捜索に狩り出された。現場に、ザイ
ルやネットを張ってよう。カラビナで体を結んでよう。しかし、ダメだったなあ。そ
んなに広い場所じゃあねえんだが・・・まるで、神隠しにあったように見つからね
えんだ」
牧村は、グッ、と手を握りしめた。
「かわいそうによ・・・それによ、温泉組合の連中は、源泉に死体があっちゃま
ずいって言うんだ」
「そうだなあ・・・」
牧村は、頂上の噴火口から数百メートル下にある、もうもうと湯気の沸き立っ
ている地獄谷の風景を思い出した。年中、硫黄の臭気が立ち込めているところ
だった。そして、コンクリートの土止めや、鉄柱や金網が、幾重にも張り巡らさ
れている。が、それでも、一年中、大なり小なりの土砂崩れのある所だった。牧
村は、その地獄谷での、友人の一枚の死の風景を理解した。
「子供の写真を持ってきたぞ」茂は、タバコを口にくわえながら、腰を浮かし、ビ
ニール袋を引き寄せた。その端の方から、ぶ厚くふくれ上がった封筒を引き抜
いた。
牧村は、それを受け取った。
「ここに入っているのは、シイタケと、庭の木でとれたリンゴと、ハシバミと、あと
は何があったかな?そっちは、新米とジャガイモだ。あとで開けてみてくれ」
「ああ。いつもすまんな」
牧村は、封筒を逆さにした。二、三十枚はありそうな写真を、左手の中に落
とした。
「ほう・・・でかくなったなあ。これが、あの下の女の子か」
「ああ。京子だ。まあ、仔牛を育てるみてえなわけにはいかねえがな」
「うむ、」牧村は、写真を見ながら、写真の中の女の子に微笑んだ。
茂は、言葉とは裏腹に、沈んだ顔をしていた。額に、これまで見たこともな
い、深く暗いシワが刻まれている。
「どうかしたのか?」
「いーや、どうもしやしねえ。みんな元気さあ」
「まだ、虫のつく年でもあるまい」
「ああ」茂は笑って、重そうに首を振った。「虫だったら、消毒するさ。そいつァ得
意だ」
「うむ、」
「義弘の方も、来年は中学だ。京子は、五年生になる。それは、小学校のプー
ルだ。裏の畑の方に、新しいのを作ったのさ」
「ふむ。しかし、ちょっと見ない間に、ずいぶんと大きくなったなあ」
「最近じゃ、すっかり色気づいちまってよ」
「ふむ・・・」牧村は、口をすぼめて笑った。「胸が少しふくらんできてるな」
茂も、笑って写真をのぞきこんだ。
「しかし、京子は、その胸を病んでるんだ」
「病気か?」
「いや、生まれつきなんだ。心臓の弁が、ちょっと奇形とかでな」
「そんなことは、初めて聞くぞ」
「ああ、つい最近分ったんだ」
牧村は、うなづきながら、しみ入るような目で写真を見つめた。
「手術すれば、治るんだろうな?」
「ああ。治るそうだ。しかし、手術は、何年か先になるらしい」
「ふむ・・・まあ、大丈夫だろう。医学の進歩は、めざましいからな」
茂は、黙って額をなで上げた。
十一時頃、牧村は茂に、下の渓谷までこっそりと連れ出してもらった。車で、
県道を五分ほど登った。そこにドライブイン食堂があり、下の音無川にはヤナ
場があった。牧村は、そのドライブインの親父とは、数年来の親しい仲だった。
アユ釣に関しては、県下では並ぶ者の無いと言われている名人である。
そのドライブインの広い駐車場も、今日は車でほとんど埋まっていた。観光
バスやマイクロバスまで止っている。が、牧村が車から降り立つと、すぐに親父
が勝手口から出てきた。困ったような笑顔を浮かべていた。薄くなったゴマ塩の
頭髪をなでつけ、下駄をカラカラ鳴らして歩いてきた。ひと夏の道楽で浅黒く日
焼けした顔に、黒く透けたような銀歯が光っている。
「はっは、牧村さん・・・」親父が、頭を撫でつけながら言った。「あんまり、看護
婦さんを困らせちゃいけませんなあ。今、電話がありましたよ」
「誰か、こっちへ来るって言ってましたか?」
「いや、わしが預るって言っておきましたがね、」
「そうだろうと思ってました」
「かなわんですなあ、牧村さんには、」
「こっちは、ぼくの幼なじみで、」牧村は、茂の方を見た。
「ああ、前にお会いしましたな。椎名さんでしたかな?」
「ええ、久しぶりです」茂は、親父よりもさらに日焼けした顔をほころばせ、八重
歯を見せた。「今年も、えらい繁盛で」
「おかげさまでな。さ、どうぞ、」
彼等は、駐車場の端から川原の方へ下った。ケヤキ林の黒土が、牧村にな
つかしい大地の臭いを思い出させた。そして、林の中には秋の香りが漂ってい
た。うっそうとしたケヤキの梢がサラサラと風に揺れ、まだあおいモミジの葉
が、秋の陽光に光った。牧村は、そこから来るこぼれ日に、なつかしい青春を
眺めた。
その、きれいに手入れされた林が切れると、ドライブイン食堂の表側の方
に、広々とした川原の景色が開けてくる。秋の日射しの中で、この川の豊な水
量が、キラキラと水脈を作って反射した。その流れの端の方に、青竹で作った
ヤナ簀(す)が仕掛けてあった。何十人もの観光客たちが、そのヤナ簀の上にあ
がったり、膝まで流れの中に入ったり、手前の広い川原で遊んだりしていた。
牧村たちは、斜に切り開かれている砂利道に入っていった。食堂の軽自動
車が一台、川原に入っているのが見えた。上流の方を眺めると、中州のように
残っている小さな島が一つあった。島には柳の木が一本と、ブッシュがおい茂
っていた。対岸は、こんもりとしたクリ林だった。ようやく、クリのイガが色づき始
めていた。川原から、そのクリ林へのぼっている崖は、藤ヅルが広く密生して
いた。
ヤナの横の方では、店のハッピを着た数人の土地の女たちが働いていた。
大きく広げた炭火のまわりで、川から上げられたピチピチとはねるアユに、小気
味よく竹串が突き刺されていく。また、それを、炭火のまわりに立てたり、抜き
上げたりしている。焼き上がったアユは、観光客の土産物に包まれたりしてい
たが、ほとんどはカゴにのせられ、上の食堂へ運び上げられている。
今年も変ることのない、観光ヤナの風景だった。人はうつろい、時代は流れ
去っていくが、文化としての観光ヤナは残っていく。“月日は百代の過客にし
て、行きかう人もまた旅人なり(芭蕉の“奥の細道”の一節)”・・・牧村は、そのことの意
味と概念とを眺めながら、ぼんやりと川原の縁に立っていた。
・・・人間の普遍的体験、か・・・牧村は、心の中でポツリとつぶやいた。
・・・人々の流れと、時間の美しさ・・・時が移り、季節がめぐり、ヤナの風景が
くり返されていく・・・
・・・その、めぐりめぐる“今”は、永遠に連なる“今”の連続であり、この“命”の
中において実現していく・・・時空構造における永遠と無限の影を、認識によっ
て走査しつつ・・・
牧村は、親父と茂が、並んでヤナの方へ歩いていくのを、ぼんやりと見てい
た。そして、静かに、深呼吸をした。そうしていると、彼の脳裏に、ふと広重の
『東海道五拾三次』の連作が浮かんだ。牧村は、その連作の中に、このヤナ場
の風景をも眺めた。
広重の描いた東海道も、むろん一枚一枚の“今”である。そして、『睡蓮』も、
このヤナ場の風景も“今”である。そうした、あらゆる時代のひと連なりの“今”
が、人間の普遍的体験として、“命”の中を流れていく。“命”が、“命”の中を流
れ、歴史の大河が、歴史の大河の中を流れていく。
「牧村さん、わしはちょいと失礼しますよ」親父が、川原を歩いてきて言った。片
手に、焼き上がったアユを入れた竹カゴを下げていた。「テーブルは、何処にし
ますかな?」
「ああ・・・中段がいいですね」
「はっは、そうでしたな。牧村さんは、あそこが好きでしたな」
親父は、分ったと言うように手を振った。そして、竹カゴを片手に下げ、のん
びりと上の方へ登っていった。
牧村は、ヤナのそばにいる茂の方へ歩いた。そこで観光客たちに加わり、の
どかな落ちアユの漁を眺めた。炭火のまわりで焼かれている何十本ものアユ
が、川原いっぱいに香ばしいかおりを流していた。
牧村は、焼いているそばへ行き、よさそうなのを二本上げてもらった。
「まあまあ、牧村さんも好きですねえ」女が、串をそろえ、牧村に渡しながら言っ
た。
牧村は、アユ漁解禁の時から、しばしば病院に届けてもらっていたのであ
る。
「おれは、これで命を支えてきたようなもんだ」牧村は、一本を茂に渡した。そし
て、札を一枚出した。
「いいですよ、牧村さん」
「そこまで言われちゃ、」串に刺したアユに、塩をぬっている女が言った。「お代
はもらえないわねえ」
牧村は、串をさしあげて礼を言った。
「ほんとに、精力を付けて下さいね」別の女が言った。
「おばさんたちも、相変わらず元気なことですね」
「お世辞を言わなくてもいいですよ」
「あたしらは、健康が第一ですよ」
牧村は、熱い焼たてのアユを、フーッ、と吹いた。
「まったく、」牧村は、息をついて言った。「その体力が、うらやましいですね」
「あたしらは、それだけが取柄です」炭火の向こう側の、小柄な女が言った。
「なるほど、」牧村は、フーッ、フーッ、とアユを吹いた。
「いやですよ、牧村さん、」串を渡してよこした女が、クッ、クッ、と笑いながら言
った。「そんな言葉だけ、まともに受け取っちゃあ。ねえ、」
「ひどいわねえ」
「そんなこと、ないですよう」
まわりで仕事をしている女たちが、みんな笑った。
牧村と茂は、川原をぶらつき、熱いアユを、フー、フー、と吹きながらかじっ
た。それから、川原より一段高い所の、雨ざらしのテーブルが五つある所まで
登った。そこは端の方に、料理を準備する数寄屋作りの小屋が一軒あった。女
が一人、そこに入っていた。テーブルでは、二組の客が食事をとっていた。
そこから、さらに斜面を十五メートルほども登って行くと、同じようなテーブル
が、もう五つあった。ここが、中段である。この川原では、一番景色のいい場所
だった。牧村たちは、端の方の、空いているテーブルに腰を下ろした。ここの小
屋の中では、二人の女が働いていた。
タバコを吹かしながら、二人で話し込んでいると、若い方の女が盆を持って
やってきた。茶を入れてくれた。それから、野草を活けた花器を運んできて、テ
ーブルの端に置いた。
「クリは、もう出てるのかい?」牧村は、女に聞いた。
「ええ。早稲はもうボツボツですよ」
「そうか・・・早いものだな、」
しばらくすると、親父が脇道の方から、ミニ・カーに乗って入ってきた。後に飯
の櫃や、ステンレスの汁の容器を積んでいた。それを小屋の中に入れると、親
父は牧村たちのテーブルの準備にかかった。三人分の飯と、キノコ汁と、漬物
と、果物の盛り合わせが出た。最後に、焼き上がったアユを川原から上げてき
た。アユは、青竹のまだ臭うような新品のザルに、二十尾前後がきれいに飾っ
て盛り上げられていた。
「こいつは、たっぷりだなあ」牧村は、焼たてのアユの芳香に、グッ、と生ツバを
のんだ。こんな食欲は、全く久しぶりだった。
茂は、日焼けした額にうっすらと汗をにじませ、ぼんやりとテーブルが作られ
ていくのを眺めている。クリのイガや、アケビや、フジの実がいっぱいに並べら
れ、ススキの穂や萩が置かれ、テーブルがしだいに賑やかに、きれいに飾り上
げられていく。
「芸のない料理ですがな、」親父は言った。「しかし、本当に味わうには、これが
一番でしょう」
「こりゃあ、豪勢だなあ」茂が言った。「ずいぶんと、風流になるもんだァ」
「しかし、今年のアユは、カタがいまひとつですなあ」親父は、盛り上げられてい
るアユを、指でつまんで少しくずした。
牧村は、秋空の下で、久しぶりに食事がうまかった。天を突くように伸びるケ
ヤキの枝を、思うぞんぶん眺め、ヤナを眺め、トンビが一羽、川原の空で弧を描
いているのを眺めた。そして、今年の漁期のさまざまな話を聞きながら、新鮮な
アユをさらに三尾もたいらげた。
食事を終え、しばらくくつろいだ後、牧村は茂と一緒にもう一度川原へ下り
た。今度は、川上の方へ歩いてみた。
「いつも川原に来ると、」牧村は、茂をふりかえて言った。「子供の頃を思い出す
なあ」
「とにかく、子供の頃が一番よかったぜ」
牧村は、唇を結んでうなずいた。
「大人になりゃあ、心配事が増えるだけだ。心配したって、どうにもなるわけじゃ
ねえのによう」
「そうしたもんさ」
牧村は、それから、心を込め、砂利を一歩一歩踏みしめて歩いた。その、石
と石がこすれる、乾いた硬い音を聞いた。そして、その音が、宇宙の深淵へ響
きわたっていく、“命”の感触をかみしめた。体の衰えた牧村の目には、間近に
見る清流は、ゆらゆらと立体的に深く澄みわたり、宇宙そのものの姿を見せて
いた。
牧村は、砂利に足をとられないようにして、ゆっくりと膝を折った。清流の中
に、そっと手をつけてみた。水は、ひんやりと冷たかった。そして、限りなく豊だ
った。それから、膝の上に両手を立てて腰を伸ばそうとした時、牧村は思わず
体がふらついた。頭がぼうっとした。
茂が、肩を支えた。
「おい、大丈夫か、俊!」
「ああ・・・」牧村は、深く息を吸い込んだ。「今度は、いつ来られる?」
「今度か・・・そうだなあ・・・」茂は、髪を手ですきながら、清流を眺めた。「まあ、
十二月の初め頃か・・・いや、おそらく、それどころじゃねえだろうな」
茂は、単純で陽気な顔を、しんみりと曇らせた。
「おい・・・そんなにひどいのか?」
「ああ、」茂は、砂利を蹴飛ばした。「ま、借金を増やすために、牧場をやってる
ようなもんだな」
「二、三百万なら、なんとかなるぞ」
「うん・・・ま、その時は頼む。しかし、前の分も、まだ返してないしなあ、」
「そりゃあ、いい。おれが死んだら、どっちみち全部やるようになってるんだ」
「おい、ほんとか?」
「ああ。他に誰にやる?」
「学さんにやればいいだろう」
「あいつは心配いらんさ。宇宙開発機構がついてる。ああ、そうだ、宇宙開発
機構の株も幾らか持ってる。国債もあった。そうだな、国債は、下の女の子の
ために、残しておいてやってくれ」
「分った・・・しかしよ、俊、おれたちの年まわりは、どうもみんな因果な運命だっ
たんじゃねえか?」
「はっは、そう思い込んでるだけさ。第一、おまえが、一体どうしたっていうん
だ?」
茂は、首を振った。八重歯をこぼした。
牧村は、手に持っていた小石を、清流の中にポチャンと投込んだ。
茂も、小石を幾つか拾い上げた。それを、対岸のフジづるの密生しているあ
たりまで投げた。子供の頃は、川原で、こうやってわけもなく石を投げて遊んだ
ものだった。牧村は、茂の投げた小石が、一つ一つゆるい弧を描いて沈んでい
くのを見ていた。
その後、彼等はヤナの方へもどり、土産物のアユを包んでもらった。それか
ら、ゆっくりと食堂の方へ登った。親父が、売店の中にいた。土産物の他に、釣
道具も売っている。その売店と反対側の壁には、このドライブインの風景画が
二枚掛かっていた。いずれも、三年ほど前に、牧村が描いた大作だった。が、
今はその当時とは、店のかまえもだいぶかわっている。季節は、盛夏と晩秋の
頃である。今見ても、両方とも、よく描けている。この絵には、現実以上の郷愁
を感じさせるものがあった。牧村は、自分のなつかしい絵を眺めた後、奥の居
間で少し休ませてもらった。
その午後、しばらくすると、病院からまた電話があった。牧村は、今度は自
分で出た。そして、すぐに帰ると答えた。
外へ出ると、西の尾根の空が、にわかに暗くなっていた。風も出ていた。厚
い雨雲が、すでに渓谷の青空をほとんどかくしていた。客も、川原からどんどん
上がってきている。その客で、しだいにテラスと食堂の中がごった返し始めてい
た。
牧村たちは、ツツジの植込のあるところまで出ていって、川原の方を見下ろ
した。川原はすでに薄暗く、今にも降り出しそうだった。女たちが、川の中に入
って、ヤナ簀(す)を片ずけている。
親父が、牧村たちを見つけ、下駄を鳴らして歩いてきた。
「こりゃあ、ひと荒れ来そうだなあ、」親父は銀歯を見せ、雲の流れを見上げな
がら言った。
「そうですね、」牧村も、ザワザワと騒ぎだしたケヤキ林を見上げて言った。
渓谷全体が、嵐を予感させる重苦しい風景になりつつあった。
牧村が、茂の車に乗込むと、親父が外側からドアをしめた。牧村は、シート
にぐったりと体を沈めた。そして、明るく笑って見せた。
「色々と、お世話になりました」牧村は言った。
「なに、また何時でも来て下さいよ」
「ええ。それじゃあ、」
親父は、手を振った。
彼等は、急いで県道を下った。樹林の中を這うように、濃いガスが急速に下
ってきている。
「もうじき、」牧村は、ガスにかすんでいく県道を見つめながら言った。「火星探
査船が、プラットホームを離れるな・・・」
「ああ・・・」茂は、ハンドルの上で両腕を休めながら言った。
「これで、いよいよ、太陽系開発時代の幕が開くわけだ」
「しかし、おれは、くだらんとおもうがな」
「そうかも知れんさ。しかし、核ミサイルで、チェスをやってるよりはましだ。“道
連れ戦略”だの、“核の手づまり”だのと、程度の低いケンカ哲学で、バカをやっ
てるよりはな」
茂は、苦笑し、滑り落ちてくるガスを見上げた。そして、フォグランプのスイッ
チを入れながら、ポツリと言った。
「まあ、やってくれりゃいいさあ・・・」
「とにかく、人類にはもう地球は狭すぎる・・・」
牧村は、ガスに埋まる沢の風景を見つめ、胸に湧いてくるかすかな甘い哀し
みを感じた。
「核戦争が、純粋な意味で、科学的クライシスと言えるかどうかは知らん」牧村
は、腹の上で手を組んで言った。「しかし、人類の文明が、もうこの地球だけで
は狭すぎることは確かだ。仮に人類が、太陽系にもっと広く散っていれば、少な
くとも、絶滅するというような危機の確率は減少する・・・たとえ、ハルマゲドンが
あっても、」
「そういうもんかな・・・」
「ああ・・・まあ、仮に遺伝子工学をひとつとってみても、これを兵器として使え
ば、核兵器をはるかに上回るものになるだろうな」
「おれには、そういう話はよく分らんがな・・・」
牧村は、窓を少し開け、新鮮な空気を入れた。胸が、重苦しくなってきてい
た。
「火星探査船がプラットホームを離れるのは、七時四十五分だったな、」
「ああ。おれは高速道路だ。ラジオで聞くさ」
「おれは、ひと眠りしよう・・・えらく疲れた・・・」
「それにしても、ひでえガスだなあ・・・」
車は、県道から病院の方へ登る道に入った。そこを登って行くと、しだいにガ
スが薄くなり、樹林の梢で風がザワザワと鳴った。フロントガラスに、ピシッ、と
大粒の雨が当たった。それからたちまち、バシャバシャッ、と車の屋根をたたき
始めた。
「さあ、着いたぞ」
「帰りは大丈夫か?」
「ああ。高速を飛ばせば、すぐに抜けちまうさ」
新病棟の玄関に、数人の看護婦が立っていた。まだ昼休みの時間で、ザア
ザアと降り出してきた雨を見ていた。牧村は、その中に婦長の姿を見つけた。
彼女は、玄関の方へ回って行く、牧村たちの車を眺めていた。肩の肉がもりあ
がっていて、ひどく威張って立っていた。彼女は、たいがいイライラセカセカし、
その上ガッカリしたような顔をしている女だった。それでも、折あるごとに、牧村
をとっちめてやろうと狙っていた。
茂は、屋根の奥まで車を突っ込んで止めた。
「大丈夫ですの!」すぐに、北野看護婦が、車のドアを開けて聞いた。牧村の
手をつかんだ。
「ああ。アユを四匹食べたぜ、」牧村は、彼女に笑いかけた。
彼女は、唇をすぼめ、首を振って見せた。
「ほんとうに・・・」婦長が、ここぞとばかりに、険しい声で牧村に言った。「何て
人なんでしょう!」
「やあ、婦長さん、こんにちは。もう、昼食は食べたんですか?」牧村は、北野
の肩につかまって、二、三歩あるきながら言った。
「知りませんよ!そんなことは!」
「おや、婦長さん、ストッキングがほつれてますよ、」
「え?」
牧村は、クッ、クッ、と笑った。
北野が、牧村の腰骨を突ついた。
「はっは、冗談ですよ、婦長さん」
「もう!ほんとうに!何て人なんでしょう!」
婦長は、あやうくカンカンに怒って、どこかへ行きかけるところだった。が、今
日はそれでも、何とか牧村に詰問するために、両足で踏みとどまっていた。
「いったい、どういうつもりなんですか、牧村さん!」
「外出のことですか、それとも、ストッキングの、」
看護婦たちが、クスクス笑い出した。
「おい、それじゃあ、俊、」茂が、後で頭を掻きながら言った。「おれはこれで帰
るぜ。ひどい降りになってきたからなあ」
牧村は、北野につかまりながら体を回し、茂を眺めた。
「色々世話になったな。楽しかったよ」
「ああ。うまいアユを食わせてもらった」
牧村は、茂の手を握った。北野が、両手で牧村の腰を支えた。
「それじゃあ、看護婦さん、」茂が、頭を下げた。「俊を、よろしく頼みます」
「ええ、」北野がうなずいた。「また、いらっしゃって下さいね。気をつけて運転な
さって、」
「ああ、大丈夫です。それじゃあ、俊、元気でなあ」
「ああ。絵は後で送ってやるよ。他にも、送るものがあるかも知れんから」
「分ったァ」
茂は、車に乗込んだ。バン、とドアを閉め、窓から片手を振った。それから、
手を引っ込め、激しい雨の中へ走り出していった。
第四章
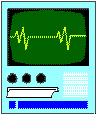
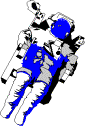
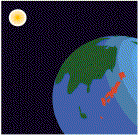
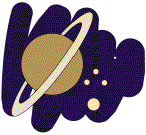
茂を見送った後、牧村は看護婦たちと一緒にエレベーターに乗った。婦長
は、エレベーターには乗らず、何処かへ行ってしまった。牧村は、むろん、婦長
とも仲良くしたかったのである。が、彼女はあまりにも真面目で、あまりにも責
任感が強く、あまりにも忙しかったのだ。
牧村は、エレベーターに入ると、すぐ壁にもたれかかった。看護婦たちが、牧
村を支えながら、にぎやかに話しかけた。が、牧村は、胸が苦しく、ひどく気分
が悪かった。それに、だいぶ息苦しくなってきていた。北野が、牧村の額をなで
上げた。他の看護婦たちも、すぐに気付いた。が、三階で扉が開いた時、牧村
はグニャリと全身から力が抜けた。彼女たちの腕の中に、そのまま崩れかかっ
た。
そこから、牧村は、担架で病室まで運ばれた。ベッドの上に寝かされると、よ
うやく少し楽になった。すぐに注射が射たれ、点滴が始められた。そうしている
と、部屋の中に男の声がし、あたりが騒々しくなってきた。集中監視システムが
運び込まれ、電極が体に張り付けられ、酸素テントが立てられていくのが、消
えていく意識の中でぼんやりと分った。
牧村が、意識を取り戻したのは、それから数時間たってからだった。体が、
まるで何かに押さえつけられているように重かった。体に力が入らず、手を動
かすことも、まぶたを押し上げることもできなかった。それで牧村は、ただぼん
やりとしていた。そして、意識の作り出す、漆黒の闇を見ていた。その無限の
中で、自分の静かな存在感を見ていた。
そうやっていると、牧村は、自分がしだいに若くなっていくような感じがした。
はつらつとした、青年期の頃に・・・それからさらに、生まれたての新品の赤ん
坊のように・・・そして、さらに遡って、人間原理が静かに波動を始めた頃・・・こ
れからいよいよ、直径数百億光年の、物理空間へ落下していく時のように・・・
が、意識は再び、死にかけた自分の肉体の上に帰った。この、肉体を所有
する世界・・・それゆえに苦があり、またその苦ゆえに、苦楽の波動と、深い認
識の刻印される世界・・・その膨大な意味世界を走査してきた、超媒体である
“命”が、今ようやくその自らの終わりを認識していた。
それから牧村の意識は、何故か、赤道上空五百キロメートルの宇宙空間に
あった。そして、遠くから、出発間際の火星探査船のプラットホームを見てい
た。巨大な弧を描く壮観な地球の朝焼けの上を、銀色に光る数個のひとかたま
りの構造物が、音もなく流れていく。すぐ上には、真空中にギラギラと光る裸の
太陽があった。
牧村は、秒速八キロメートルで流れていくそれらの構造物に、なんなく近づい
た。角張った、ひときわ大きなプラットホームに、すでに惑星間飛行体が完成し
ている。また、近くには、巨大な太陽発電パネルを張り出した、居住用構造物
や組立工場が浮かんでいる。そして、シャトルやレスキュー艇やスペース・タグ
等が、それぞれのポジションで、光りを点滅させながら浮かんでいる。
それから、ふと牧村に、弟の顔が見えてきた。弟は、大きなナンバーの入っ
た、白い宇宙服を着ていた。仲間と、スペース・タグに乗込んでいる。牧村は、
こんな弟の姿を見るのは初めてだった。
弟は、白い宇宙服のヘルメットの中で、ゆっくりと牧村の正面に顔を向けた。
が、その目は、深宇宙の星屑を眺めているように無表情だった。それから、何
かを感知し、捜している目になった。
牧村は、その目の前の弟を、ひどく冷静に見つめていた。自らが生まれ出
た、この宇宙における弟という“絆”の、裸の概念だけを眺めていた。その裸の
概念に、かすかなぬくもりと、愛情を込めて・・・
その頃、牧村の病室には、塩崎医師の他に、看護婦が二人いた。北野看護
婦と、尾崎看護婦である。が、その三人とも、集中監視システムは見ていなか
った。警報ブザーがオフのまま、INSのスクリーンに目を奪われていた。
スクリーンには、巨大な宇宙船用プラットホームと、全長二百二十八メートル
の火星探査船、フォボス号とダイモス号が映されていた。二隻の宇宙船は、す
でに固定アンカーを全て外され、ゆっくりと、プラットホームの両翼から離れよう
としていた。三人は、その瞬間を、かたずをのんで見守っていたのである。探査
船は、これから試験飛行があり、燃料や物資の積み込みがあり、さらに最終出
発ポイントである月軌道までくだる。が、この進宙式が、事実上の船出であるこ
とにかわりはなかった。
探査船は、後部に四つの球形の燃料タンクをつけた、ユニット式の裸の構造
体である。そして、その居住ユニットの側面には、大きな国連マークがくっきりと
描かれていた。
二隻は、やがて補助推進エンジンを使い、秒速〇.五メートルという宇宙遊
泳の速度で、ゆっくりとプラットホームを離れた。そして、徐々に、まるで赤ん坊
が膝の上から這い出すように、かすかな加速が加えられていく。
数分たつと、プラットホームのカメラにも、宇宙船の全景が入った。そして、さ
らにどんどん小さくなっていく。二隻の火星探査船にたくした人類の夢が、核兵
器廃絶の平和への願いが、奈落のような深宇宙の虚無へゆっくりと沈んでい
く・・・
これが、脱地球圏時代の始まりであり、太陽系大航海時代の始まりになる。
「おい、まだ意識はもどらんのか?」塩崎医師が、スチールの椅子の上で、ず
んぐりとした肩を回して聞いた。
「ええ、」北野看護婦が、酸素テントの中を眺め、気のない返事をした。
「このぶんじゃ、トレーサーも中止ということか、」
「牧村さん、探査船の出航を、あんなに楽しみにしてらっしゃったのに、」
「うむ・・・まあ、それもしょうがあるまい。川原なんぞ歩きおって、」塩崎医師
は、濃いあご髭をジャリジャリとこすった。「おい、コーヒーでも飲むか、」
「ええ、はい。あの、尾崎さん、」
「はあい、入れてきまあーす」
彼女は、帽子のてっぺんをポンとおさえ、ドアの方へ歩いた。そして、チラリと
集中監視システムを眺めた。
「あれ、」彼女は、ふと立ち止まった。
何か、ヘンだった。首を傾げよく眺めると、脳波計も心電計も波が消えてい
た。
「何だ、どうした?」塩崎医師が聞いた。
外は、また雨が強くなってきていた。
〔 完 〕