〔巻1/原・万葉集〕 <吉野への脱出/壬申の乱・・・ 大王から天皇へ>
 天武・持統朝
天武・持統朝 ![]()





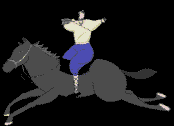


| Menu/文 芸/短 歌/万葉集/天武・持統朝 |
〔巻1/原・万葉集〕 <吉野への脱出/壬申の乱・・・ 大王から天皇へ> |
| トップページ/Hot Spot/Menu/最新のアップロード 女流歌人: 里中 響子 |
| No.15 | 【巻1(25)】 天武天皇 み吉野の 耳我の峰に 時なくそ・・・ | 2011.11.14 |
| No.16 | 〔1〕 吉野への脱出風景 | 2011.11.20 |
| No.17 |
〔2〕
壬申の乱・・・②
|
2011.12. 3 |
| No.18 | <吉野から・・・伊賀・伊勢への脱出> | 2011.12. 3 |
| No.19 | <美濃から2方向・・・数万づつの軍勢を送り出す> | 2011.12. 3 |
参考文献 Wikipedia
・・・ 万葉集 (・・・インターネット・サイト・・・) その他
|
|
1(25)】 天武天皇/ み吉野の 耳我の峰に 時なくそ 雪は降りける ・・・ (長歌) ( 壬申の乱・・・吉野への思い ) *************************************************************
時なくそ 雪は降りける 間(ま)なくそ 雨は零(ふ)りける その雪の 時なきが如(ごと) その雨の 間なきが如 隈(くま)もおちず 思ひつつぞ来(こ)し その山道を
【現代語訳/大意・・・巻1(21)】 吉野の耳我の峰には 時知れず雪が降るという 絶え間なく雨が降るという... その雪や雨が絶え間ないように...道を曲がるたびに... 物思いを重ねながら...
その山道を辿ってきたことだ... *************************************************************
「この長歌は...」響子が言った。「“天武天皇”の、吉野への思い詠まれたものと言われて います... “天智天皇”の皇位継承をめぐって...長年約束されていた太政大臣/大皇弟・・・東宮 /皇太子/大海人皇子が外されて...大友皇子への布石が進む中で、大海人皇子は辛く も、も吉野へ脱出しました。剃髪して、妃/鸕野讚良/“後の持統天皇”ともども、都を落ちて 行ったわけですね。 歌は...近江京を去り...奈良/吉野に隠遁する道中を回想し、詠んだものといわれま す。天皇の支配力/軍勢は強大であり、追手がかかっているやもしれず、きらびやかな都を 離れての逃避行です。 しかも、1日で、嶋宮(/近江京からの最初の宿泊地・・・旧都の天皇家の離宮。蘇我馬子の邸宅跡。後 に草壁皇子の東宮・・・奈良県/高市郡/明日香村/島ノ庄)から、吉野への脱出をはかったわけです から、よほど事態が緊迫していたのでしょう。嶋宮に、追討の部隊が迫っていたのかも知れ ませんね。
“雪や雨の絶え間ないように・・・道を曲がるたびに・・・物思いを重ねながら・・・” ...吉野 の険しい山道を進んだわけです。 もはや...帰る都/戻る道はなく...反旗を翻し、近江朝廷に勝利する...覇道の道し かありません。また大海人皇子は、頭の片隅でこの日のあることを折り込み、後の世の大構 想を描いていたのかも知れませんね。 でも...大化の改新の端緒となった、“乙巳の変”(いっしのへん)のようなクーデターではな く...本格的に国軍と激突するようなクーデターでは...本来、ほとんど勝ち目はありませ ん。それでも、周囲の支援も多く、社会的不満の高まりがあり、地方豪族を糾合できたわけ です。 そして、たちまち...数万の軍勢を不破(岐阜県/不破郡/関ヶ原町)に結集し...2方面か ら近江朝廷に挑んだわけです。これに勝利することができたのは、大海人皇子の武将として の抜群の統率力と、ズバ抜けたカリスマ性でしょうか。
ええと...耳我の峰とは、吉野/金峯山のことでしょうか...この峯に、絶え間なく降ると いわれる雪や雨のように...曲がり角ごとに、絶え間なく物思いをしながら、山道を超えて来 たわけですね...“筆舌に尽くしがたい・・・雪の中の逃避行”...だったようです。 とりあえず、虎口(ここう)を脱出し...1日にして吉野へ逃げたわけですが...その間は、 まさに、様々な思いが駆け巡ったと思われます。 そして、一方、この状況を...“虎に・・・翼をつけて放てり”...ということだったわけで すね。やがて、近江朝廷に反旗を翻すわけですから、周辺状況も非常に複雑だったと思いま す。万葉の時代は、おおらかで、穏やかなだけではなく、こうした濃密な血縁の中での壮絶 な抗争/粛清もあったわけですね...
その時の、“天武天皇”の吉野への深い想いが...この長歌に詠まれているわけです」
|
|
〔1〕
吉野への脱出風景
「ええ...」支折が、顎を上げ、目を細めた。 唇をかるく結び...≪航空宇宙基地・赤い稲妻/シンクタンク・赤い彗星ビル3 F≫の窓から、紅葉の始まった草原を眺めた。長野県/≪軽井沢・基地≫から引き揚 げてきて、1週間になる。関東平野/西部丘陵も、いよいよ秋が深まる様相だった。 “・・・額田王(ぬかたのおおきみ)の言う通り・・・”...支折が、心の中でつぶやく...“・・・ 憂いを帯びた秋の陽の光...紅葉し始めた灌木に散る優しい陽光が...時の無い、 永遠の存在をしのばせている...・・・” 支折が口に手をやり、眼前する...“存在の・・・結晶風景”...を見つめつつ、小さ な息をついた。響子とマチコを振り返り、口元に微笑を漂わせ、静かにうなづいた。うな づきは、特に意味はなかった。ただ、全ての存在を、己が肯定したものだった。 「さあ...」支折が、両手の指を組んだ。「では、始めましょうか...」 「そうですね...」響子が、口をすぼめた。「帰って来たのが、嬉しそうですね、支折さ ん、」 「存在しているのが...」支折が、言い直した。「嬉しいのですわ...また、草原の散 歩に出られます...秋の山道を歩けますわ...去年の、栗拾いを思い出します」 「うん...」マチコが、深くうなづいた。「アケビは、もう駄目よね。口が開くと、鳥がきれ いに食べてしまうから、」 「ホホ...」響子が楽しそうに、窓の鰯雲を眺めた。「そうですね...」
「さあ...」支折が両手を組み、モニターに目を落とした。「ええと... ここは<壬申の乱>となりますので...<壬申の乱・・・①>に引き続き、私まと めておきました。吉野への脱出/逃避行の様子は...【巻1-(25)】...で“天武天 皇”も、『万葉集』に残しています。そこから、当時の状況が生々しく偲ばれます。
吉野の耳我の山に...時知れず雪が降っている...
絶え間なく、雨が降っている...雪が定めなく降るように...
雨が絶え間なく降るように...道を曲がるごとに...
絶えず物思いに沈みながら...その山道を超えて来た...
元・皇太子/大海人皇子(おおあまのみこ)の一行の...飛鳥/嶋宮(/天皇家の離宮・・・蘇 我馬子の邸宅跡/後に草壁皇子の東宮・・・奈良県/高市郡/明日香村/島ノ庄)からの...吉野/宮滝 /天皇家の離宮への脱出/逃避行を...後の“第40代/天武天皇”が懐かしみ、詠 んでいるわけです。 私は...不勉強のそしりを、甘んじて受けるつもりですが...“第38代/天智天皇” は琵琶湖のほとり...近江/大津宮に遷都していたわけですね。大海人皇子の、吉 野への脱出/逃避行は...飛鳥/嶋宮が起点になっているのでしょうか? それまでは...近江朝廷の厳しい監視下にあったわけですが、逃げようとはしてい ないわけですね。ところが、嶋宮で妃や皇子たちと合流すると、間髪を入れず、翌早朝 には、冷たい氷雨の中を、飛鳥川沿いに、吉野への脱出を謀(はか)っているわけです。
このことを、軍事戦略担当の大川慶三郎さんに伺ってみたのですが...この敏速 さは、宮廷での緩慢な所作ではなく、“優れた・・・軍事戦略的・行動”、とのことでした。 この少し前あたりから、大海人皇子の、“将帥・・・戦略/戦術/カリスマ性”、が光って いるそうです。 また、こうも言っていました...同じような才能を発揮した人物に、〔平安時代・末 期〕の源義経(みなもとのよしつね)がいるが...彼は、奥州/平泉で弁慶ともども、非業の 最期を遂げた。しかし大海人皇子は、最後まで生き抜き、稀代の英雄となった、そうで す。当然...歴史上の影響力というものは、抜群となるわけです。 その1つが...群雄の中の旗頭である大王から、〔超越した存在/最初の天皇〕、 となったということです」 「ええと...」響子が言った。「最初に天皇を名のったのは... 誰かというのは、諸説あるようですが、最近は“天武天皇”とする説が有力ということ ですね?」 「はい...」支折が、うなづいた。「...つまり、それほどの力をもったとしても、自然と うなづけるということです、」
「はい...」
「ええ...」支折が、髪に手を当て、モニターをのぞいた。「嶋宮からの、脱出に話を戻 します... 飛鳥/嶋宮の近くには、飛鳥川が流れています。おそらく、夜明け前から準備し、周 囲を偵察していた事でしょう。そして、空の白んだ氷雨の中を、人目を避け、飛鳥川を 遡上し...“稲淵(いなふち)”...“栢森(かやのもり)”...と進んで行ったようです。 そこから、さらに登って行くと...現在の明日香村と、吉野町の境にある、“芋ケ峠 (いもがとうげ)”に達します。この“芋ケ峠”の前後あたりが、【巻1-(25)】に詠まれてい るような、つづら折れの道になり、急勾配になっているようです。 歌に詠まれている“耳我(みみが)の山”は、どの山かは判明しないそうですが、“み吉 野の・・・”、と詠まれていることから、“芋ケ峠”を越えて、その先にある山と言われてい ます。
ええ...<壬申の乱・・・①>...でも触れていますが、671年/9月初旬頃、風 邪をこじらせた“天智天皇”は、病床に伏していました...病状は、いっこうに快方には 向かわず、臨終の床となるわけです。 この時点では...太政大臣は実弟/大海人皇子から...子息/大友皇子に差し 替えられています。この最終的な人事が行われた時、大海人皇子は譲位を諦(あきら)め たと思われます。 そしてこの時点で、東宮/皇太子の宮殿をも、離れていたのでしょうか。浅学を晒(さ ら)していますが、おいおいと確認して行きたいと思います。 あ...大海人(おおあま)という、特徴的な名前ですが...これは、皇子が少年時代を 過ごした、尾張/海部評(あまこおり)に由来しているそうです。そこから飛鳥京に入ったの は、13歳の時だったそうです。 “武人気質(ぶじんかたぎ)”に育った大海人皇子は、中大兄皇子のもとで大変貌し、有 能な片腕として成長し、実績を重ねて行きます。そして、大皇弟/東宮・大皇弟(/中臣 鎌足=藤原鎌足に、大織冠を授けた折)とも呼ばれ、人々に慕われていたようです。 “天智天皇”は、そのご褒美ということでもあったのでしょうか。鸕野讚良(うののさらら/ “持統天皇”)の他にも、何人かの自らの娘/皇女を、実弟(父母が同じ)/大海人皇子に与え ています。 姉・妹と...何人も重複して、身近な人間に嫁いでいる様子から...当時の宮廷の、 おおらかな生活感がうかがえると思います。でも、譲位は...大海人皇子ではなく、子 息/大友皇子に固めた“天智天皇”は...今度は、大海人皇子のその抜群の能力を 恐れたわけです。
さあ...また、話を戻しますが...“天智天皇”は、臨終の枕頭に大海人皇子を召し 出し、例の“譲位の話”を切り出します。もし、譲位を受けたら、“謀反の意あり”として、 ただちに首を落とす手筈(てはず)となっていた様です。 私たちの感覚から言えば、“情として・・・本当に、そんなことができるのか?”、と思 いますが、“皇位をめぐる身内の抗争”は、すでに幾度となくくり返されて来ているわけ です。“おおらかな・・・万葉時代”ですが、皇位をめぐるこうした、“恐さ”もあったわけ ですね。 さあ、大海人皇子の方も...それを察していて、大津宮の近くの自分の屋形を引き 払う準備をし、“天皇の呼び出し”を待っていた様子です。言葉も用意してありました。 そして、召し出しを受け...天皇の枕頭で、“とんでもございません・・・”...言い、 “直ちに出家し・・・吉野の宮滝にこもって・・・仏道の修行を重ねつつ・・・陛下の御病気 の快復を祈りたい”...と、身の振り方も申し出ます。“天智天皇”はこれを許可します。 まさに“天智天皇”は、近江朝廷において、絶対権力をもっていた様子がうかがわれ ます。前にも言いましたが、“天智天皇”もまた、自分の片腕として歩んできた実弟が、 可愛くないはずはありません。そうした、“甘さ”と“非情”の優柔不断が、妙な展開を招 いてしまったわけです。
一方、大海人皇子の方は必死です。機を失せず、宮廷内/仏殿で剃髪をし、そそく さと退出したと思われます。そして翌日...一足先に、妃/鸕野讃良(うののさらら/天智天 皇の娘/持統天皇)、草壁皇子(くさかべのみこ)、忍壁皇子(おさかべのみこ)たちを...舎人(とねり: 天皇や皇族の身辺で御用を勤めた者)や女官(にょかん: 朝廷につかえる女性の官人の総称/・・・雑事を行う下級女 官は女儒/にょじゅ、めのわらわ)を付けて、吉野(/その途上の、飛鳥の嶋宮)に先発させたようです。 残った大海人皇子の方は...出家した身に武器や武具の類は必要なく、それらを キッチリと宮廷の武器庫に納める仕事があります。これは覚悟のほどを示すためにも、 大事な仕事になります。 それから...吉野で隠遁するとなれば、山越えもあり多少の準備も必要になります。 その下工作と、親しい知人への、当たり障りのない、別れの挨拶もあります。そうした全 てが、厳しい朝廷の監視下で行われたわけですね。よほどの胆力(たんりょく)が必要にな ります。 ええと...逆の立場から見れば...剃髪し、武装解除を進めている屋形を、朝廷側 が襲う理由は、何もありません...武装解除は、大いに結構なことです。それから、都 落ちして行くわけで...ただ見ていればいいわけです。 でも...この辺りは...息詰まるような緊張感の中で...粛々と進行したものと思 います。
2日後・・・10月19日/早朝・・・ 大海人皇子は...兄/“天智天皇”と、最後となる別れの挨拶をした後...輿(こし) に乗り...50人余りでしょうか...厳選した舎人・女官と共に、大津宮から宇治の方 向に、出発したと思われます。そして旧都/飛鳥を通り、その南側の山を越え、吉野に 入るわけですね。 宇治橋あたりまでは...見送りの近江朝廷の重臣たちも、付いて来たのでしょうか。 そこで...ピリピリした監視下から離れ...いよいよ都落ちです。でも、この辺りから、 さらに油断ができなくなります。何処に、伏兵を忍ばせているかも分かりません。 そうした危険を避けるために...おそらく一行は、見送りが離れた先で、ひそかに 準備しておいた馬に乗り換え、約50キロ南方の飛鳥/嶋宮(しまのみや)をめざし、奈良 盆地を疾駆(しっく)したと思われます。 大和の地は、熟知している土地です。でも、ここはまだ、近江朝廷にとっても裏庭の 中です...ともかく、早朝に近江/大津京を発ち、夕方遅くには飛鳥/嶋宮に入り、首 を長くして待ち焦(こ)がれていた、妃/鸕野讃良や皇子たちとも合流したようです。 ひとまずは、安堵(あんど)の再会といったところでしょうか。でも、虎口(ここう: 虎の口・・・非 常に危険な所)を脱出するには、吉野まで逃れ、ようやく、“後ろを振り返ることができる”、 といった状況でしょうか。嶋宮/離宮は、ある程度の防御はできても、危険な状況に変 わりはありません。
翌日・・・10月20日/早朝・・・ 大海人皇子の一行(/推定100名前後)は...早々に嶋宮を発ち吉野を目指します。前 夜から降り出した、冷たい氷雨は、みぞれまじりの雪に変わったようです。決死の脱出 であり、1刻を争う緊迫した危機が、身近に迫っていた様子です。武人/大海人皇子な らではの決断であり、行動力ですね。 氷雨の降る、薄闇の中...一行は、身を潜めるように...飛鳥川を遡り...“稲淵 (いなふち)”...“栢森(かやのもり)”...と進んで行ったようです。“芋ケ峠(いもがといげ/標高 500m)”では、本降りの雪になった様子です。 その...冷たい雪の吹き付ける山道を...濡れそぼって黙々と歩き...屈曲をくり 返し...追手も警戒しなければなりません...また、吉野にたどり着いたとしても、先 の当ても定かでない...都落ちの逃避行です。 大海人皇子の心は...この天候のように鉛色で、重く沈んでいたのでしょうか。それ でも、その日のうちには、吉野の離宮にたどり着いたようです。古代の山道は険しく、女 ・子供を伴った逃避行は...“生涯・・・忘れえぬもの”...となったようですね。 【巻1-(25)】...はその吉野への、山越えの逃避行を...しみじみと偲び、長歌 に詠まれ...『万葉集』に編纂されたものです...」
いう地ですが... ここは、“初代/神武天皇”の通ったコースですよね...それは、後で確かめる機会 があるかと思いますが...この地も、“様々に・・・いわくのある地”です。そしてまた、 “天武天皇”と“持統天皇”にとっても...“思い込みの深い地”に、なるわけですね。 さあ...吉野/宮滝に到着して...まず大海人皇子のやるべき仕事は、離宮の防 備を固めることでした。これは武人として、十分な心得があったと思われます。なにより も、追手の有無...周囲の偵察...そして、土地の人間を味方にすることも、防御/ 情報収集において、最重要になります。 大海人皇子は...舎人(とねり)たちに、周囲に居住する山人/国栖族(くずぞく: 吉野川 上流に住んでいた先住民族)、吉野・宇陀(うだ)の豪族たちと、親しく付きあい、懐柔し、味方に 引き入れるように指示します。 さらに、東国の地方豪族の兵力を結集させるべく、隠密裏に工作を開始するわけで すね。有能な舎人を騎馬で動かし...伊賀・伊勢・尾張・美濃の豪族たちに...軍団 を編成するように促すわけです。尾張は、大海人皇子が少年時代を過ごした土地でも あったわけでね。 律令体制の整いつつあったこの時代...近江朝廷は、その律令体制を使うことがで きたわけです。それで、吉野も監視できたのでしょうか。浅学のため、こうした事情まで は分かりませんが、ともかく吉野も、しだいに強力な近江朝廷の監視が敷かれて行っ たと思われます。 大海人皇子の一行は...100人程度で吉野に入り...半数は帰しているようです。 これは、離宮の収容規模のためでしょうか。でも、残った舎人や女官たちの中にも... 脅し・すかし・血脈などで...近江朝廷に通じる者も出て来たのかも知れませんね。 “虎に翼をつけて放った者(中国の故事)”...の動静は、常に掌握しておかなければな らないわけです。その意味では、土地者も、油断はできません。したがって、真の味方 を結集して行くことが、重要になります。 こうした所でも...大海人皇子の、将帥(しょうすい)としての実績と、才能と、強烈なカ リスマ性が発揮されるわけです...」
令制度で、締め付けられて来たからかしら?」 「うーん...」支折が、唇を結んだ。「それも、あると思います... それと...唐・新羅(とう・しらぎ)の連合軍に、“白村江の戦い(/663年)”で大敗し... 国防にかかわる膨大な出費や、徴用や兵役が、重い負担になっていたからでしょう。そ れらは全て、都の人々や、地方豪族などへの、重い負担になっていたわけです。 ええ、667年には...対馬(/長崎県)に金田城...讃岐(/香川県)に屋島城...さら に、お膝元の大和(/奈良県)と河内(/大阪府の南東部)をわける生駒連山にも、高安城を建 設し、外国と戦争に備えていました。最前線の西国の離島から、畿内(きない: 都に近い地) まで、臨戦態勢を高めていたようです。 また同年...都の防衛をより一層高めるために...海岸線から遠い、琵琶湖・湖畔 の近江/大津に遷都を敢行(かんこう: 無理を承知で、思い切って行うこと)します。さすがに、これ は、都の人々も地方豪族も疲れ果ててしまい、大いに反対したそうです。 でも、“天智天皇”は強行したわけです。こうした諸々のことで、不満が鬱積(うっせき)し ていたわけですね。うーん...そこへ持って来て、またまた、皇位継承をめぐる血縁の 中の争い事です。都の人々も、さすがに、ウンザリしていたのではないでしょうか、」 「そうかあ...」マチコが、コクリとうなづいた。「大海人皇子は...それらを緩和すると 約束し...ゴタゴタを終わらせると、宣言したわけかしら?」 「多分...」支折が、うなづいた。「世の中の空気も、変わると思ったのでしょう....」 「でもさあ...外国の軍隊が、攻め込んでくる危険はなかったのかしら?」 「<壬申の乱>は、672年ですから... 遷都から、5年ほどたつわけですね...ともかく大海人皇子は、近江朝廷とは別の 政策を約束し、地方豪族を糾合をして行ったのだと思います。 大川慶三郎さんも言っていました...皇位の正当性の主張しただけでは、わずか 8ヶ月間で、数万の軍勢を結集することは不可能だそうです。当時の兵は、豪族や庶 民/農民ですから、皇位の正当性などでは、分かりずらいわけです。 したがって...急激な改革や、租税の負担は、緩和・軽減すると約束したのでしょう。 つまり...皇位の正当性は、実力勝負/兵力の激突で決まることになったわけです。 〔平安時代・後期〕には、平清盛(たいらのきよもり)などが現れて、武家社会の台頭が始 まります。でも、時代ははるか以前...〔奈良時代〕の『万葉集』の編纂が始まる以前 の...防人が、西国の海岸線を固めていた時代です。 「うーん...」マチコが言った。「でも...8ヶ月間で、数万の軍勢を招集するとは、すご いカリスマ性ですよね...」
「そうですね...」響子もうなづき、口に指を押し当てた。 「ええと...」支折が、モニターから顔を上げた。「吉野が、“いわくのある地”、と言っ たのは...」 「はい...」響子が、腕組みをした。 「これは... 古人大兄皇子(ふるひとのおおえのみこ)の一件があったからです...古人大兄皇子は、 “第34代/舒明天皇(/・・・【巻1(2)の長歌】・・・の作者)”の第1皇子で...母は、蘇我馬子 (そがのうまこ)の娘/蘇我法提郎女(そがのほほてのいらつめ)です。そして...娘/倭姫王(や まとひめのおおきみ)は、“天智天皇”の皇后です。 さあ...その古人大兄皇子ですが...古人皇子/古人大市皇子/吉野太子とも 呼称されたわけですが...もともと、中大兄皇子や中臣鎌足らの、“乙巳の変(いっしの へん)”の標的の1人とも言われた...重要人物です。 ところが、考えてみれば...中大兄皇子は、后(きさき/・・・后は第1位、妃は第2位)の親/ 岳父を、クーデターの標的にしているわけですね。当然、妃(/後の皇后)としては、ビック リ仰天です。こんなことが、当時の権力中枢では、まかり通っていたわけですね。よくも、 別れてしまわなかったとも言えるわけですが...どうなのでしょうか...」 「うーん...」マチコが、頭を横に沈めた。「皇后/倭姫王(やまとひめのおおきみ)は、それで 納得していたのかしら...」 「ともかく...」支折が言った。「先を見てみましょう... “乙巳の変”の後...“第35代/皇極天皇(・・・第37代/斉明天皇でもある・・・)”の退位を 受け...古人大兄皇子が即位することを勧められるわけです。でも、こうした事情もあ り...辞退し、出家して...吉野宮滝の離宮へ隠退するわけです。 つまり、ここが...大海人皇子の追従する道となるわけです。同じようなことが、2度 あると言いますが...まさにこのことですね、」 「うん!」マチコがうなづて、納得した。「そういうものよね...」 「それで...さらに、話の続きがあるわけです... この古人大兄皇子に、真偽は不明ですが...“謀反(むほん)の企てあり”...という 密告があります。そして、645年9月12日、この吉野において...中大兄皇子によっ て、“攻め滅ぼされる”...わけです。 そもそも...“皇極天皇”が退位し、古人大兄皇子は出家しているわけです。“何を もって・・・謀反”、なのか、よく分かりませんが、旧勢力の巻き返しでもあったのでしょう か。ともかく、山に囲まれた檻(おり)の中の様な吉野は、わずかな兵力で攻略されたと 言われます。
つまり...“天智天皇”には...“大海人は恐いが・・・古人大兄皇子と同じ・・・あの 吉野に入るというのであれば”...という想念があったと思われます。 また、大海人皇子にしてみれば...“出家し・・・あの吉野に隠退しますので...謀 反の意思は皆無です”...というメッセージを発したわけです。ここは、大海人皇子が、 1枚上手だったということですね。吉野という地理を逆手(さかて)に取り、油断させたわけ です」 「そこから...駆け引きが始まっていたわけかあ...」マチコが、宙を見た。 「そうですね... 大海人皇子は...兄/中大兄皇子を超える軍略家だったわけです...カリスマ性 もあり...中大兄皇子はそれを、誰よりも恐れていたわけです。それゆえに、太政大 臣の地位を解き、あえてそこに、大友皇子を据えたりもしたわけです...」 「うん...」マチコが、コクコクと、2度うなづいた。 「ええと... 吉野ですが...そこは山桜で有名な吉野山ではありません。その北の吉野川ほと りで...吉野宮滝の大王家/天皇家の離宮です。私は、訪れたことはないのですが、 離宮があったほどですから、吉野川の渓谷の美しい所だったと思われます。おそらく、 今でも、地形は変わっていないと思います。 出家して隠棲(いんせい: 俗世間を離れて静かに住むこと)するには、古人大兄皇子(ふるひとのおお えのみこ)も好んだように、格好の地だったようです。また、謀反の意思はありませんとい う、強いメッセージもあったわけですから、好都合でした。 ところが...大海人皇子の...優れた戦略眼で俯瞰(ふかん: 高い所から、見下ろして眺める こと)した時...吉野は、“山に囲まれた檻(おり)の中”と見るよりも、伊勢と、紀伊とを結 ぶ、戦略的要衝(ようしょう: 軍事・交通・産業の上で、大切な地点)/交通の要衝、と見えたわけで すね。 ここをうまく使えば、近江朝廷の触手をかいくぐり、味方の本拠地となる美濃との往 来も、可能だったわけです。また、いざという時は、熊野の山中に逃げ込むこともできた わけです」 「そうかあ...」マチコが、コーヒー・カップを取り上げ、ゆっくりと傾けた。
「近江朝廷では...」支折も、コーヒー・カップを取り上げた。「...“天智天皇”の... 崩御が、さし迫っていました。 そして、吉野では...大海人皇子が、近江朝廷に対する戦の準備を開始しているわ けです。信頼のできる精鋭20人余の舎人を機動的に使い、隠密裏に軍勢の動員を促 す、指令を発していったようです。 ここでは、簡単に言い切ってしまいますが...権力側/近江朝廷との、しのぎを削る 戦いであり...当然、容易なことではなく...熾烈な攻防もあったと思われます...」 「うーん...」マチコが言った。「“天智天皇”の、実弟/大海人皇子の名は、天下に知 れ渡っていたわけよね、」 「そうですね... 皇位の継承で、身内の粛清をくり返し...多額の戦費...膨大な築城...兵役に 苦しめられて来た、“天智天皇”の後に...大海人皇子が立つと言います。天下の情 勢は、大きく動いたと思われます...」 「ふーん...」マチコが、腕組みをした。 「でも...こうしたことは... 吉野で隠棲すると決まった時から、天皇の周囲では薄々と予想されていたことです。 だから...都落ちの時もピリピリとし...嶋宮からは、逃避行のような山越えになった わけです...まさに、“虎に翼をつけて放てり”...という状況になったのです...」 「それでも...」響子が、後ろ髪のバレッタに手をかけた。「...“あの吉野・・・”...だ ったわけですね?」 「そうですね...」支折が、うなづいた。「私は... <壬申の乱・・・①>で、“鴻門の会”(こうもんのかい: 紀元前206年、楚の項羽と漢の劉邦が、秦 の都/咸陽の郊外で会見した故事。楚漢の攻防の端緒となった。この宴席で劉邦を取り逃がした項羽は、結局、劉 邦に滅ぼされることになり・・・漢王朝が到来した)を、彷彿(ほうふつ)とさせると言いました...」
「はい...」響子が言った。
「それから...」マチコが言った。「どうなったのかしら?」 「大海人皇子が... 吉野に脱出した年...671年12月3日...“天智天皇が崩御(/46歳)”しています。 この頃には、大海人皇子の“挙兵の工作”も耳に入っていて...“如何(いかん)ともしが たい状況”...になりつつあったのでしょうか。 内大臣/中臣鎌足(藤原鎌足)が存命なら...この事態も、あるいは、回避されていた のかも知れません。でも、この重鎮は...2年前/669年に、すでにこの世を去ってい ます。 “天智天皇”は...己(おのれ)が健在なら、大海人皇子を抑えられるのだが...と思 いつつ...“自らが蒔(ま)いた種であり・・・心の残る崩御”...と、なったのではないで しょうか...」 「そうですね...」響子が、冷めかけたコーヒーに、スッと手を伸ばした。
〔2〕 壬申の乱・・・②
東国における軍勢・結集のメドを受け...大海人皇子(おおあまのみこ)がわずかな人数 で、吉野を脱出したのが...672年(天武天皇・元年)6月24日...です。 ええと...これからは、大海人皇子の子息/皇子が多く出て来るので...ここから は大海人皇子を、単に大海人(おおあま)と呼ぶことにしますので、よろしくお願いします」 「はい、」響子が、うなづいた。 「さあ...」支折が、残っていたコーヒーを飲み干した。「この時点から... 古代/日本における最大の内乱...<壬申の乱>(じんしんのらん)...が始まります。 新しい律令体制下の軍勢と、急激な改革に反対する、大海人の糾合した地方豪族軍 勢との戦です。でも元々は、皇位継承をめぐる権力闘争だったわけですよね。 これは...俯瞰(ふかん: 高い所から見下ろし、眺めること)して見渡せば...大海人・側が、近 江朝/律令体制・側から...地方豪族と律令組織を、どれだけ離反させることができ るかがカギでした。 ええ...時間経過を追って...乱の推移を...詳しく見てみましょう...」 「はい、」響子が、小さくうなづいた。「お願いします、」
<吉野から・・・伊賀・伊勢への脱出> a1
「大海人は...」支折が、背中を伸ばした。「吉野を脱出し... 伊賀から伊勢を経由して、美濃(みの/現在の岐阜県南部)まで逃(のが)れています。吉野・ 脱出と同時に、軍勢・結集の号令をかけ、たった数日で数万の軍を動かすというのは、 非常にダイナミック(力強く生き生きと躍動するさま)です。 近江朝の不穏な動きを見て、先手を打った様ですね。このあたりは、優れた将帥(しょ うすい)としての独特の嗅覚であり、武人としての、素早い決断と行動力です。こうした大 冒険というのは、誰でもできるものではなく、大海人にそれが降りかかったわけです。 『日本書紀』によれば...大海人に共に吉野を脱出したのは、妃/鸕野讃良(うのの さらら)、草壁皇子(くさかべのみこ)、忍壁皇子(おしかべのみこ)を含め、20人ほどだったようで す。女官は10人ほどで、少人数での機動性を要する、脱出劇だったようです、」 響子が、うなづいた。 「でも... 確かな足取りで、東国/美濃にある、大海人の所有する邑(むら、ゆう)を目指したよう です。この邑/“湯沐邑(とうもくゆう、ゆのむら)”というのは...古代中国と日本の〔飛鳥時 代~平安時代〕までの、一部の皇族に与えられた、領地のことをさします。 日本におけるの“湯沐邑の制度”は、当時の唐からではなく、古代/漢の制度をまね たようです。都を離れた地にあり、直属の軍勢(まだ、武士階級というものはなく・・・農民が武装した軍 勢)もあって...大海人の命令で、密かに戦の準備を整えていたようですね」 「ええと...」響子が、指を唇に当てた。「後の、律令制の“湯沐邑”は... いわゆる領地のような統治権はなくて、収入源だけですね。つまり、お財布だけ。で も、この頃の“湯沐邑”と、大海人との関係をみると、統治権もあったのでしょうか。緊密 な人間関係も見えますし、舎人(とねり/護衛・雑用に従事した下級官人)なども、邑の出身者たち もいたのでしょうか?」 「うーん...そうですね... 古代中国にも、邑(むら)はあったわけですが...国によって、時代によっても、制度は 異なるようです。邑の人間が、都へ出た時は、土地の貢物(みつぎもの)を持って行くことな どもあったのでしょう。また、御用を聞いたりなどもして、“人間的な絆(きずな)”もできたと 思われます。 そのような都に通じた人物を通し...屋形の使用人などにも入れてもらえたかと思 います。特に、大海人は大皇弟として、大きな力をもっていたわけですね。武人気質の 大海人もまた、武勇に優れた人物を、周囲に置くことを好んだかと思われます、」 「カリスマ性による、吸引力もありますね..」響子が、目を細めた。「制度とは別に、人 が集まったということですね...」 「うーん...そうでだと思います... 大皇弟ととして、相応の軍事力も持っていたわけです。古代や中世の軍の編成につ いては、私は詳しくはないのですが、有力者や、貴族や、豪族などが、そうした人々や 農民などを、保有していたのでしょうか。人材を、常に求めていたのかも知れません」 「はい...」響子が、うなづいた。「そのあたりも、研究が必要ですね」
「そうですね...」
護衛に...地元の山人/国栖(くず)族、吉野・宇陀(うだ/莬田(うだ))の豪族など、50人 ほどが周囲を固めたようです。わずか50人ですが、山人や地元の猛者(もさ)たちです。 獣道(けものみち)まで知る人々で、機動的に動ける人数ということでしょうか。当時の緊張 感が、ヒシヒシと伝わって来るようです... 再度の脱出になるわけですが、今回は、薄暗い氷雨の中の脱出ではありません。季 節は陽光の輝く6月です...現在の新暦/太陽暦ですと、7月~8月でしょうか。兵力 動員のメドもつき、頼りになる味方兵力の、護衛も受けているわけです。 でも...脱出ということは...相当な包囲の中を、抜け出るということです。ただ、そ こを抜ければ、緊張した中にも、草花や風景を見る余裕もあったと思われます。都や、 離宮の周辺にいて、本当の意味での外に出ることのなかった、妃や皇子や女官たちに とっては、暗雲の晴れた、別天地の光景だったのかも知れませんね...」 「うん...」マチコが、うなづいた。「でも、さあ...美濃/岐阜県南部まで歩くのはさ あ、けっこう大変よね...古代の山道だし...」 「うーん...そうですね... でも、吉野からの脱出はともかく...後は、馬なども使ったのではないでしょうか。味 方の勢力下にはいれば...軍勢の動く緊張感の真只中にあっても...それは、味方 の軍勢です。 一行にとっては...広々とした空の下で...初めての、楽しい旅だったのではない でしょうか?」 「美濃の、“湯沐邑(とうもくゆう、ゆのむら)”からは...」響子が言った。「迎えなどは、来たの でしょうか?」 「あ、来ています...」支折が、モニター目を移した。「ええと...そのあたりを、もう少 し詳しく説明しましょうか。調べてあります、」 「お願いします...」響子が、ニッとほほ笑んだ。 「はい...」支折が、微笑した。
「ええと... 672年(天武天皇・元年)/6月22日...大海人は挙兵を決意します。美濃に、舎人(とね り/下級官人)/村国男依(むらくにのおより/美濃の豪族出身)らの使者を派遣し... 2日後/6月24日...には自らも吉野を脱出し、後を追います。武人として周到な、 実行力のある、ダイナミックな動きです。 村国男依という人は...<壬申の乱>...では琵琶湖/近江への直進の軍勢の 諸将の筆頭として...連戦連勝し、最大の戦功を打ち立てています。詳しいことは分 からないのですが、美濃では、村国氏や尾張氏などの地方豪族が、味方に付いていた ようですね。その村国氏の出身かと思います」 「はい...」響子がうなずき、ボールペンでメモをとった。 「大海人は、まず美濃に使者を出したわけです... 安八磨郡(あはちまのこおり/“評(こおり)”を、『日本書紀』は“郡(こおり)”と書き改めています。現在の岐阜県 /安八郡 = 安八町、神戸町、輪之内町)の、自分の“湯沐邑(とうもくゆう、ゆのむら)”/湯沐令(ゆのうな がし/湯沐邑の管理者)/多品治(おおのほんじ)に対し、ただちに挙兵し、不破道(ふわどう/“不破の 関(せき)” = 岐阜県/不破郡/関ヶ原町にあった関所。東山道/信濃方面を押さえる要地。美濃/“不破の関”、越 前/“愛発(あらち)の関”、伊勢/“鈴鹿の関”は、“古代の3関”)を封鎖するように、命じます。これは、 電光石火の、戦略上の最初の仕事です。 これ受け...美濃では、25日までに兵/3000を動員し...不破道の封鎖を完了 しています。これにより、海人は東海道(/三河、遠江(とおとうみ)方面)と東山道(/信濃方面)の 諸豪族から、兵力を募(つの)ることが可能となります。そして逆に、近江朝の連絡路を遮 断することができました。 ここが戦略上の、重要な分岐点になります。またこの地は、実は後々も“戦略的な地” として有名となる、“関ヶ原の合戦場”(1600年10月21日/美濃国/不破郡/関ヶ原・・・岐阜県/不破 郡/関ヶ原町)の地ですね。 ええ...“日本で最大の合戦となる・・・関ヶ原の地(豊臣方/石田光成と、徳川方/徳川家 康が・・・双方合計で20万の大軍が激突・・・わずか半日で決着した戦場)”...ですね。でも、それ以前の 古代においても、すでに戦略的な土地だったわけです。 大海人には、そうした大きな戦略図が見えていたわけです。何よりも、まず不破道を 封鎖し、戦略的な仕切りをしたわけです。この、“先見性・戦略性”の、“有無・優劣”が、 時代を動かして行くわけです。 うーん...うした天性の能力が、何度となく大海人の危機を救って来ているわけです ね。武人気質ではあっても...“単純/直情型”ではなく...“謙虚さ・客観的視点”と を合わせ持ち...さらに“慎重さ・・・大胆さ”を、兼備していたようです。 つまり、こうしたことの総合評価が...“虎に・・・翼をつけて放てり”...という恐怖 となっていたのでしょうか、」 「はい...!」響子が、ゆっくりと、強くうなづいた。「《危機管理センター》の担当者とし て、しっかりと承っておきますわ!」 マチコが、響子を見て、うなづいた。
「ええと...」支折が、モニターのデータを眺めた。「...この美濃兵/3000を... “湯沐邑(とうもくゆう、ゆのむら)”の兵力とみる説と...美濃/全体の兵力とみる説があ るそうです。当時の人口から、どうかということですね。でも、ともかく、安八磨郡の“湯 沐邑”が、最初に挙兵したことは確かなようです」 「うん...」マチコが、宙を見てうなづいた。 「『日本書紀』/巻28/“壬申紀”は...」支折が言った。「<天武天皇・元年(672年) の・・・1年間の様子>...を克明に記しています。 それによると...6月24日...大海人は吉野を脱出し、伊勢に向かう途中の“莬田 ・郡家(うだ・ぐんけ/・・・莬田(うだ)は、現在の奈良県北東部の宇陀。郡家(ぐんけ)は郡司の役所)”の近くで、 湯沐の米を運ぶ、伊勢国の駄馬50匹を目撃しているようです。 馬の背に米俵を振り分けて載せ、50頭ほどが連なっていたのでしょうか。当時の物 資輸送の風景が偲ばれます。“湯沐邑”の米は、そんな風にして、都へ運ばれていた わけですね。伊勢国/“湯沐邑”は、誰のものかは...浅学のため、分かりません」 「このあたりは...」マチコが言った。「宇陀(うだ)ですよね。宇陀の地方豪族が味方に 付いていても、安全ではなかったのかしら?」 「うーん...近江朝の勢力も入り、渾然としていたのでしょうか... ともかく、吉野から80キロほど先の、伊賀国/積殖山口(つみえやまぐち/伊賀国/阿拝郡/ 柘植(つげ)郷=現在の伊賀市/柘植)まで行けば、安全圏だったようですね。でも、そこまでは、 用心していたようです。 一行は、大和の宇陀/(うだ/莬田)を通り...米を運ぶ馬/50頭を目撃し...名張を 越えて...伊賀盆地に入ったようです。このあたりまでくれば、まずは、一安心だった のでしょうか...味方の軍勢が集まって来たということもありますが...」 「うーん...」マチコが、大きくうなづいた。「伊賀・甲賀の...忍者の里よね、」 「ホホ...そうですね...でも、それはもっと後のことです」 「うん、」マチコが、唇をつまんだ。 「ええと...それから...“別の・・・参考文献”では... 6月25日に...伊賀国・評督(ひょうとく、こおりのかみ = 郡守)が...正規兵/500を率い て、大海人に合流しています。それから、積殖山口(つみえやまぐち)に到着し...近江を 脱出してきた、大海人の長子/高市皇子(たけちのみこ)とも、合流しています。 さらにそこで...兵500を動員している、紀阿閉麻呂(きのあへまろ)に迎えられたようで す。彼は、倭(やまと)国守/紀麻呂岐の子ですね。大海人の挙兵の号令で、一挙に軍勢 が集結してきたわけです。非常に、心強かったと思います...」 「うーん...」マチコが、髪を押さえた。「すごいわよね...」 響子が、うなづいた。 「この、正規兵というのは... 何をもって、正規兵かは良く分かりませんが...おそらく、武装/装備ではないかと 思います。源平合戦の時代や戦国時代のような、鎧兜(よろいかぶと)の武者ではないので しょうが、相応の武装や兵站(へいたん)を備えていたのでしょうか。 軍勢の動く所では、水・食料などは非常に重要になりますし、弓矢などの補給も、必 要になります。つまり、その人数分の生活が、大移動するようなものです」 「うーん...」響子が言った。「古代においては、大変だったでしょうね...」
近江に通ずる倉歴道(くらふのみち: 近江国/甲賀郡/蔵部)の守備に残しています。それか ら...大海人は、兵/800余を率いて、加太越(かぶとごえ)から鈴鹿山脈を越えて... 伊勢国/鈴鹿評(“評(こおり)”は、『日本書紀』は“郡(こおり)”と書き改めています)に入ったようです。 ここで...美濃の“湯沐邑(とうもくゆう、ゆのむら)”/湯沐令(ゆのうながし)/多品治(おおのほ んじ)が、美濃から大海人に送ってよこした、兵/数百と合流している様子です。これは、 直属の兵であり、これも心強かったと思います。
ええ、そして、“鈴鹿・郡家”では...国司守(伊勢守/・・・朝廷から派遣されている官吏・・・守(か み)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)などの、最上位)の三宅石床(みやけのいわとこ/壬申の乱の功臣)、そ れから、介(すけ/次官/・・・太守は任国へ赴任しない遥任だったため、実務上の最高位になることも多かった)の 三輪子首(みわのこびと/壬申の乱の折、大和への増援軍の指揮官の1人)が、正規兵/1000をそろ え、大海人の一行を迎えたようです。 さらに、湯沐令の田中足麻呂(たなかのたりまろ)、同じく高田新家(たかたのにいのみ)が参じ たようですね。大海人の勢力は、この地でも急速に膨れ上がって行ったようです。
「あの、支折さん...」響子が言った。「高市皇子(たけちのみこ/天武天皇の第1皇子、持統天皇時 代の、大半の太政大臣を務める・・・母は胸形尼子娘)の...近江からの脱出は、どんな様子だった のでしょうか?」
「ええと...そうですね... 6月24日...行動を起こした大海人は...大分恵尺(おおきだのえさか)を使者として、 都にいる高市皇子と大津皇子(おおつのみこ)に挙兵の事を告げ、伊勢で会うよう命じてい ます。 2人の皇子は、別行動をとって都を脱出しています。共に捉えられるのを恐れたから でしょう。この脱出劇に付いては、フィクション(小説)の世界に任せることにします。 ともかく...高市皇子は、鹿深(かふか: 滋賀県/甲賀市/水口町/鹿深)を越えて、6月25日 に...積殖山口(つみえやまぐち/三重県/伊賀市/柘植)で、父に追いつき、合流しています。 鹿深は甲賀...積殖は伊賀の柘植(つげ)ですね...ともかく、長子/高市皇子の合 流は、大きな意味があったようです。高市皇子は、全軍を掌握し、<壬申の乱>では 大活躍をするわけです。 この時、高市皇子につき従っていた者は...民大火(たみのおおひ/渡来人系)、赤染徳足 (あかそめのとこたり)、大蔵広隅(おおくらのひろすみ)、坂上国麻呂(さかのうえのくにまろ)、古市黒麻 呂(ふるいちのくろまろ)、竹田大徳(たけだのだいとく)、胆香瓦安倍(いかごのあへ)だと記されていま す...大津皇子の方も、遅れて“鈴鹿の関”に着き、こっちも無事合流しています」 「はい、」響子が言った。
「ええと...6月26日... 大海人の軍勢は...“伊勢国/朝明郡/郡家”の手前で...村国男依(むらくにのおよ り/美濃への使者に発った舎人)に出会ったようです。彼は...“美濃兵/3000で・・・不破道 を封鎖した”...と報告に来たようです。 大海人は...“郡家”に着いてから、高市皇子を不破に派遣します。そして、軍事を 監督させ、東海道と東山道に、兵の動員を促す使者を送ります。こうした動員令では、 遅れることは、“二心(ふたごころ)あり”、と疑われることになりますよね... 6月27日...高市皇子は不破から...“桑名・郡家”にいる大海人に使者を送り、 “御所から遠くにあっては・・・政治を行うのに不便です・・・近い所にいて欲しい”、と要 請しています。大海人はその要請に従い、4キロほどの距離にある野上に移ることにし たようです。 同/6月27日...不破に配置した伏兵が、西から来た敵の使者を捕らえています。 高市皇子は和蹔(わざみ)から野上まで出向き...父/大海人を野上に出迎えます。そ して、敵の使者を捉えたことを報告しています」 「はい...」響子が言った。「うーん...だいたいの様子は分かりました...」
<美濃から2方向・・・数万づつの軍勢を送り出す> a2 |