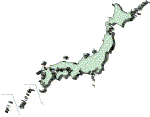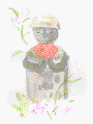「ええ、星野支折です...猛暑の日が続いています...ご機嫌はいかがでしょう
か...」
支折は、目を細め、窓の外の陽射の風景に目を投げた。外気はすでに35度を超え
ている。その中で、時折、強い風が吹いていた。風は涼風というよりも、熱風が吹き抜
けている様相だった。
「ええと...」支折は、作業テーブルのノートパソコンに目を戻した。「...難しい課題
ですが...いよいよ“新・民主主義の時代”をスタートさせる事になりました...」
支折は、首をかしげ、腕組みをした。それから、作業テーブルについた、津田・編集長
と、政治部・担当の青木の方を見た。
「ええ...
津田・編集長と、青木さんと、私の3人で...ここしばらく...“新時代の民主主義
社会の展望”を考察してきました。そして、そのキーワードは、
【情報公開】と【国民参
加型・評価システム】の2つではないかという考えに到達しました...
このことは、これまでも何度か触れて来ています。ええ、さて、ここでは...具体的
に、どのようにして、そこに到達するかを考察して行きます...編集長、青木さん、よ
ろしくお願いします」
「うむ、」津田が、外の猛暑を見ながら、重々しくうなづいた。「まず...一番大事なこ
とを、1つ言わせてもらう。それは、この国は、“国民が動かなければ、何も変わらな
い!”ということだ。一言でいえば、これが全てだな、」
「そうですね、」青木が、首をかしげた。「逆に、“国民全体が動けば!”、この国は、ど
うにでも変るということです」
「はい...
道は、様々あるのだと思います。でも、“到達する所”は、1つだと考えています。そ
れは、“透明性の高い、国民参加型の民主主義社会”だと思います。また、そこに
至る改革で“主役”を演じるのは...今、編集長と青木さんが言われたように、まさ
に、“国民主権”の原理によって動く、私たち“国民自身”なのだということです...」
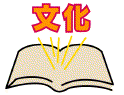

 <星野 支折>
<星野 支折>
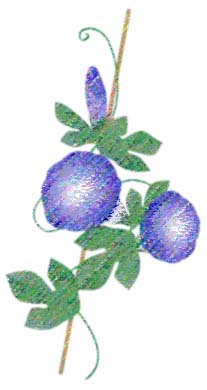
「ええ、さて...」支折は、ノートパソコンのキイを、軽く叩いた。「いま、民主主義社会
の閉塞感は、世界規模で拡大しています...それぞれ事情は異なり、グローバル化
の弊害もあり、簡単に解決できるものではありません。
でも、これを打破する1つの共通項は、これまでの間接・民主主義から、新しい形
態の直接・民主主義へ、その比重を少しづつずらして行くことにあるのではないでしょ
うか...私たちは、一応、そのような結論に到達しています...」
津田が、黙ってうなづいた。
「ええ...そのバックボーンとして、」と、支折が続けた。「インターネット社会・高度情
報化社会の急速な拡充があります。こうした情報化時代の爆発の中で、市民や国民
が、より直接的に社会全体のシステムに参入していく事...これが、“民主主義社会
の第2ステージ”を切り開いて行くものと、私たちは期待しています...」

 <編集長/津田 真>
<編集長/津田 真>
「はい、」津田が、うなづき、支折の言葉を引き取った。「現在、日本は大混乱の真只中
にあります。しかし、それゆえに、この閉塞的な世界情勢の中で、“民主主義社会の
第2ステージ”を切り開いて行く、“1つの実験場”になり得る可能性があります。い
や、その役割が非常に濃厚だと、あえて宣言しておきましょう...
私たちの、数世代前の先祖は、徳川・幕藩体制の“封建社会”から“明治維新”を
引き起こし、一気に“近代社会”に脱皮しました。極東アジアの、その最果ての小さな
鎖国の島国から、世界で唯一、西欧文明の列強へ参入して行ったのです。その鮮や
かな国家大改造は、今でも世界中の国々が絶賛するものです。また、現在の日本が、
世界の先進国でいられるのも、この“明治維新”の大きな遺産が背景にあることを、決
して忘れてはいけません...」
「はい!」支折が、うなづいた。
「そして...平成の現在...まさに、日本の国は、再びその“維新”による大革命を
必要としています。しかし、今度は、下級武士階級による革命ではなく、“国民主権の
原理”による、民主主義革命になるということです...
今、政治は、完全に国民の信頼を失っていますが...議会制民主主義における
“政治舞台”での革命と、“国民参加型・評価システム”等の構築による、“文化・情報
舞台”での革命が必須となっています」
「はい、」支折が、コクリと、深くうなづいた。「政治が、国民の信頼を失い、“世襲”や
“様々な特権”の上で胡座(あぐら)をかき、国家ビジョンを示す能力さえ欠いています。
ええ、青木さん...このことについて、一言お願いします」
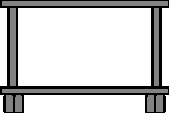

 <青木 昌一>
<青木 昌一>
「そうですね...」青木が、眼鏡の縁に手をかけ、プラズマ・スクリーンの方を見上げ
た。「いずれにしても、ここしばらくは、“国民が政治をリード”していく必要があります。
とても、政治が、国民や国家をリードしていける状態ではありません...」
「はい」支折も、スクリーンの方を見た。
「現在、日本の政治は、“単なる国民のお荷物”としか、言い様がありません。ともかく、
現在の政治家は、出来の悪い“厄介者のセガレ”のようにヨタッています。仕事にも勉
強にも実が入らず、ただ“飲んだくれ”て、“大ボラ”をふき、“犯罪発生率”だけが異常
に高い集団です...まあ、私も、こんなことは言いたくはないわけですが、あえて言
わせてもらいます」
「分りますわ、」
「いずれにしても、政治を、シャン、とさせるには、スパッ、と“世襲”を諦めさせることで
しょう...これは、これまで国民が、“世襲”や“政治一家”みたいなことを許していた
から、こんなことになったわけです。
まあ、ついでに言っておきますが、官僚の“天下り”も、キチッ、と禁止することです
ね。議員の“世襲”も、官僚の“天下り”も、キチッ、と禁止すること。ここが、日本の新
時代のスタートになるのではないでしょうか」
「はい!もう、いくらなんでも...“天下り”や“世襲”の時代ではないということです
ね?」
「そうです。とても、“先進国の風景ではない!”ですね...」
「はい!」
「政治家や官僚は、コンプライアンス(法令順守)はもちろんのことですが、それよりもさら
に高い社会規範の手本を、国民に示して欲しいですね。“犯罪スレスレのライン”を浮
き沈みしているのでは、とても国民の代表とは言えないわけです」
「はい!」
「ええと...」支折が言った。「繰り返しになりますが...
司法、立法、行政、そして文化・マスメディアの全てにおいて、“国民の直接参加の
比重を高めて行くこと”...これが、“新時代の基本戦略”になるわけですね?」
「そうだな...」津田が言った。「現在、司法は“裁判員制度”の創設で、まさに具体的
に国民参加のシステムが動き出そうとしている。そして、行政での課題は、よく言わ
れる所の、“情報公開”と、“民間との人事交流”だろう...
立法府の政治の課題は、一言でいえば、“国民主権による政治全体の管理”という
ことだと思う。そのあたりの不備が、この国の政治全体を堕落させてしまった。今回の
参議院選挙後も、相変わらず、選ばれる側の議員や政党が、再び選挙制度のことをア
レコレと議論し始めているようだからねえ...
しかし、これは、議員を選出する側の、“国民主権に属する権利”なのです。まあ、
国民の側も、今後は、この“主権を守るシステム”しっかりとを構築し、“国民主権によ
る政治全体の管理”を徹底して行かないといけない」
「はい」
「さて...次に問題になるのが、4番目の、文化・マスメディアを、どうするかということ
だ...ここに、いかに民意を反映させて行くか...いかに、直接・民主主義のエキス
を移植していくか...それが、つまり、“国民参加型・評価システム”の組織作りにな
る。
むろん、名称や組織形態はどうでもいい。ともかく、インターネット社会・高度情報
化社会の中で、国民が直接文化に参入していくシステムを、早急に構築して行く必要
があるわけです...もはや、マスメディアに頼れる状況ではなくなってきている...」
「うーん...そうですよね。..
高度情報化社会の中で、マスメディアは“情報の双方向性”をうたいながら、実際
にやっていることは、“情報の一方的な押し付け”の傾向になって来ています。それか
ら、定番になったスポーツニュースや芸能ニュースのために、国民にとって非常に大事
なニュースが捨てられていますよね...
権威があると思っていたNHKニュースでも、最近は話題性の方が重視されてい
て、がっかりさせられることがありますわ...」
「うむ、その通りだ」
「どうしたらいいのでしょうか?」
「まあ...
だから、我々は...1つの“国民的な新しい文化活動”として、“国民参加型・評
価システム”を創出していけないかと考えて来たわけです。これは、既存のマスメディ
アとは、別のステージに構築されることになります。
今、国民が強く望んでいるのは、まさに“国民の思い!”を、いかに文化や政治に
反映させて行くかです。ところが、政治にも、マスメディアにも、それを実現しようという
誠意がほとんど感じられないわけです。
そこで、国民自ら、高度情報化社会の中で、それを新たな文化活動として、“ルネッ
サンス(文芸復興)”をやろうというわけです。ともかく、まず、“この方向で動く”という、
“戦略を起動”して行かなければなりません」
「はい、」
「いずれにしても...何らかの形で、“国民の想いを社会に反映させるシステム”
が必要です。それを、インターネット社会・高度情報化社会の中で、如何に実現してい
くか...その試みの1つが、“国民参加型・評価システム”なのです」
「うーん...」支折は、プラズマ・スクリーンを見つめた。「いずれにしても、国民の声を
反映させる、何らかのシステムが必要ですよね、」
「そう...
きめ細かく、国民全体に開かれた、“信頼性の高い窓口”...そして、“ガラス張
りの集計センター”...それを“社会に反映していくガラス張りの推進組織”が必
要です。
いずれにしても、“この3つ”を作らなければ、“国民による、国民のための、国民の文
化”は実現しないわけです...テレビ文化は、国民から乖離してしまっています。新
聞も、全幅の信頼がおける時代ではなくなったわけです。そこで、情報爆発の時代の
波に乗って、“国民的な新しい文化活動”を創出して行こうというわけです」
「はい...」
「現在の日本の“マスコミ文化”は、何と言うか...国民不在です...誰に向かって
放送しているのか分らない...だから、何をやっても、国民はますます白けて来るわ
けです」
「はい、」

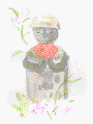
「さて...」津田が言った。「“維新”を起動できるかどうか...カギはこの“国民参加
型・評価システム”にかかっています...政治、行政、マスメディアが膠着状態の今、
“国民参加型・評価システム”のようなものを、如何に創出していくか...私は、ここ
に、日本の命運もかかってきていると思っています」
「はい、」
「“国民参加型・評価システム”が...地方レベルから火が付き...小さな無数の評
価グループを、地方の“評価・NPO”がまとめ上げ...それを地方文化に反映して行
く...これは、おそらく、うまく行くのではないでしょうか。これもまた、“地方から”、とい
うことになるわけですが、」
「はい」
「その“地方の火”が、やがて全国的に燎原の火のごとく、動き出して来るものと思い
ます...そして、そのソフトを全国統一的なものにすれば、ネットワークはたちまち出
来上がります」
「はい」
「むろん、形としては簡単でも、実際に構築していくのは、ラクではないはずです。膨大
な知恵と時間と労力が必要になります。しかし、それが、それそのものが、私たちの文
化となり、血や肉になって行くわけです。
いずれにしても、国民全体が動き、知恵を絞り、試行錯誤を重ねていくことになると
思います。また、短期・長期的にも、大きな雇用の創出につながって行くと思います。
国の形や、文化の形態が大きく変っていくわけであり、“新生・日本”が胎動して行くこ
とになります。
そして、これが成功すれば、あの“明治維新”にも匹敵する、“維新”が展開して行く
はずです...まず、全国で、独立独歩でいいわけですが、“国民・市民参加型の評価
システム”を立ち上げて行って欲しいと思います。それが、スタートになります!」
「はい...ええ、よろしくお願いします!」
![]() 新・民主主義の時代
新・民主主義の時代