<大乗仏教と小乗仏教>
仏教とは、仏の教えであり、私たちが自ら悟りを開いて仏/仏陀の心境
を体得する教えです。しかし、そうなるためには出家し、非常に厳しい修行
をしなければなりません。しかも、そうしたからといって、全ての出家者が悟
りを得られるというものでもありません。つまり、仏教は比類のない素晴らし
い“智慧の道”を説く宗教ですが、それは同時に非常に難解なものでもあっ
たのです。
さらにまた、大多数の出家することの出来ない人々、あるいは苦行に耐
えて悟りを得る能力のない人々は、一体どうすればいいのかという問題も
出てきました。つまり原始仏教では、超エリートの出家者集団の中からしか、
悟りに至る人は出てこなかったのです。しかし、釈尊の仏法がいかに素晴
らしい究極の教えでも、これでは大衆はついていけません。また、全員が出
家したのでは、社会が成り立ちません。
さて...釈尊の入滅後、400年から500年を経た頃、大衆を同時に救
済するという考え方から、“大乗仏教”が興ってきます。この大乗仏教を説
く人々は、それまでの出家主義の仏教を、小乗仏教と呼んで非難しはじめ
たのです。大乗とは、“大きな乗り物”、“すぐれた乗り物”という意味であ
り、小乗とは、“小さな乗り物”の意味です。
一方、小乗仏教の側は、自分たちの方が、釈尊の教えに忠実だと主張
しました。そして、自らを小乗仏教などとは呼ばず、“上座部仏教”と規定
し、その主張を譲りませんでした。こちらの主張も、理にかなっているように
思います。
大乗仏教は、シルクロードをへて中国に渡り、日本に到達しています。
一方、小乗仏教は、タイ、カンボジア、ビルマ等の東南アジアで拡大しまし
た。
私のように、出家者でもなく、たった一人で仏道を独学している者には、自力本願の
上座部仏教/原始仏教の方に親近感を覚えます。ただし、出家者でない身であってみ
れば、宗教的信仰心というものが極めて希薄であり、寺も神社も一緒に拝んでいます。
むろん、時の熟成を待てば、身も固まってくると思いますが。
この大乗仏教と小乗仏教の違いは、“釈尊”の捉え方にもあらわれてき
ます。小乗仏教では、原始仏教における“人間・釈尊”をそのまま捉えてい
ます。しかし、大乗仏教では、仏陀を超越的な存在に据え、釈尊はその化
身と考えます。いずれにしても、大乗仏教は出家できない在野の信者を中
心に結成されてきた仏教であり、弱者をも一緒に救済して行くものです。
ところで、禅宗の初祖・菩提ダルマは、海路で南方中国に入りました。イ
ンドを出発して3年余りの苦しい航海の後、梁(りょう)の国の広州に到着して
います。西暦520年9月21日と伝えられています。そして、南方中国から
北方中国へのぼり、魏(ぎ)の国に至っています。ダルマはそこの嵩山(すうざ
ん)の少林寺にとどまり、終日壁に向かって座禅していたといわれます。こ
れが“壁観バラモン”と呼ばれ、“9年面壁”といわれます。この間、禅宗の
2祖・慧可を得ているわけです。 <無門関・第41則/達磨安心>
 胡 子 無 鬚 (
こすむしゅ )
胡 子 無 鬚 (
こすむしゅ ) 
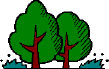
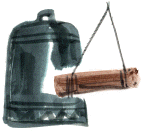



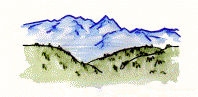

![]()

