<1> 公案 
ある時、1人の僧が趙州(じょうしゅう)和尚(おしょう)に問うた。
「犬には仏性(ぶっしょう)が有るでしょうか、それとも無いでしょうか...」
「無...」と趙州は答えた。
非常に短い公案です。したがってこれだけ言われても、普通には何のことか分かり
ません。そこでまず、趙州和尚と仏性について説明します。それから、肝腎なこの公
案の「無」について説明します。
本来、公案は説明などせず、師から与えられた公案で大疑問の深淵の中に追い
込まれるのがその命なのです。そして、その心地のきわまった中から、座禅を中心と
した修行によって、体験的に大疑問を打ち破るのが“悟り”への道です。つまり、知的
解釈や思想的な説明はむしろ邪魔者であり、公案の本来の目的を失わせるもので
す。
しかし、現代の情報化社会では、考案のもつ大疑問の答えが、あっさりと書籍や
雑誌の中で説明されていたりします。したがって、その気が無くても、ついうっかりと
目に入ってくるような時代です。
また一方、こうした情報化社会だからこそ、私のような門外漢が“無門関”と出会
うことも出来ました。そして、私のような独学の輩には、とにもかくにも、知的解釈も
哲学的思想も含め、一度読み下さなければ禅の世界に近づくことも出来ません。
が、そうなると、公案の意味あいも必然的に本来のものとは違ったものになるわけ
です。しかし、さらに考えてみれば、ここでも “大道無門 千差路有り”
ということでしょ
うか。私たちにその気があるならば、大道の門はいつでも開いているということです。
<五祖下の暗号密令>
五祖山の法演禅師以後、宋の時代の臨済宗において、いわゆる看話禅(公案禅)が
形成されました。その時、最も有力な公案として活用されたのが、この“趙州の無字”の
公案だったのです。“無門関”を編集した無門慧開禅師は、法演禅師から六代目に当た
ります。
<趙州和尚> ......(
778年〜897年 )
この公安に出てくる趙州和尚は、北方中国は趙州の観音院に住した人物です。時代
は唐の末期。まさに禅文化の最盛期の禅界の重鎮です。齢120歳まで生きたといわ
れ、これほど長く生きたということも、特筆すべきことです。しかも、“無門関”の第1則に
取り上げられたほどの人物です。
趙州禅師57歳の時、師の南泉禅師が遷化しています。また武帝の仏教大弾圧の時
(845年)は67歳。一緒に観音院で活躍した臨済義玄(りんざいぎげん)の遷化は、88歳の
時。仰山禅師(ぎょうざんぜんじ)の遷化は、112歳の時。まさに、中国における禅文化の隆
盛を見届けた人物です。
<仏性>
この“無門関・第1則”は、仏性に関する問答です。
「一切衆生皆仏性有り」 (いっさいしゅうじょう みな ぶっしょうあり)
これは、一切衆生が本来持っている、仏となるべき性質のことを言っています。
この“仏性”という概念は、かなり深い意味合いを持つようです。しかしここでは、参考
文献にあるように、「生きとし生けるものは、ことごとく仏性を有する」ということでご理解
下さい。
私は仏性とは、生き物だけではなく、この現象界全てに共通する“真理の輝き”という
ほどの意味に解釈していました。したがって、大草原のススキのホンのかすかなひと揺
れにも、雨滴が木の葉から落ちるその永遠の一瞬にも、ことごとく仏性の輝きが有るも
のと理解しています....
いずれ、様々な意見に出会うと思いますので、今後とも少しずつ勉強して行きます。
<2> 無門の評語 /...口語訳

この“無門関/第1則”は、無門禅師自身が透過して大悟に至った公案といわれ
ます。そのため、彼自身がこの公案に対し、非常に詳しく評語を加えています。
禅を学ぶには、修行者は祖師の設けた関門を通らなければならない。妙悟を得る
には、分別心を尽くしきらなければならない。祖師の関を通らず、分別心を断ち切るこ
とのできない者は、草木に宿る正体のない化物のようである。
さあ言ってみよ、祖師の関とは何か。ただこの「無」字...これが禅の究極の一関
である。故にこれを「禅の門なき関門」と名付ける。この関門を透過する者は、親しく
趙州に相見えるばかりでなく、過去の代々の祖師たちと手に手をとり面々相対し、彼
等と1つ眼で見、1つ耳で聞くことができるであろう。なんとすばらしいことではないか。
この関を透過しようとする者はないか。360の骨節と、84000の毛孔をあげて、
自己の全身を1個の大疑団として、ただこの無字になりきれ。昼も夜もひたすら参究
せよ。虚無の無や、有無二元の無だなどと誤解してはならない。それは真赤に熱し
た鉄の丸を呑み込んだようなものである。吐き出そうにも吐き出すことはできない。
これまで積み重ねてきた二元的知識分別を払い尽くし、さらに参究を続けよ。やが
てその修行の機が熟する時、(内だ外だというような)一切の対立はおのずから一枚
となるであろう。この時、彼はすばらしい夢を見た唖子のようなもので、ただ自分が身
をもって知っているだけである。突如として関を打ち破れば、天を驚かし、地を振動さ
せるであろう。
それはちょうど、関羽将軍の太刀を自分の手に奪い取ったようなものである。仏に
会えば仏を殺し、祖師に会えば祖師を殺すものとなろう。生死の際にのぞんで真に
自由自在、どこにどう生まれようと、解脱無碍(げだつむげ)の真の生を楽しむであろう。
さて、そこでどのように努力したらよいのか。自己の気力の全てを尽くして、ただ
「無」になりきれ。なりきり続けてやむことなく、ためらうことがなければ、見よ、灯明に
火がともれば、暗黒はたちまち光明となる。
<3> 公案の説明

非常に短い公案ですが、まずこれが何を言っているのか解説してみます。
ある時、1人の僧が趙州(じょうしゅう)和尚に問うた。
「犬には仏性が有るでしょうか、それとも無いでしょうか。」
「無」と趙州は答えた。
この短い会話そのものは、あえて説明する必要はないと思います。また、趙州和
尚についても、仏性についても、いちおう解説しました。では次に進んで、この僧が
趙州和尚に問いただした意図は何なのでしょうか...ここから禅問答に入ります。
この僧は、実は犬に仏性が有るか無いかは百も承知で尋ねているのです。むろ
ん、大禅匠である趙州和尚も、“生きとし生けるものは、ことごとく仏性を有する”こと
は知り尽しています。では、何故あえてこんなことを質問したのでしょうか...
ここで考えてください...この質問は、小学生が先生に質問をしているのではない
ということです。これは禅問答なのだということです。つまり、禅者として、相手の器
量を推し量るための会話なのです。当然、聞かれた方も、小学校の先生のような回
答をしていたのでは話にもなりません。したがって、禅者としてその質問の真意を理
解し、自分の禅の境涯を端的に示さなければなりません。これが禅問答なのです。
両者の、火の吹くような会話が展開する理由も、ここにあるのです。
<芭蕉と仏頂和尚の禅門答> .....(俳句コーナーへジャンプ)
芭蕉の禅の師である仏頂和尚が
「如何なるか青苔未生前(せいたいみしょうぜん)春雨未来前の仏法 」
と、問うたのも、実は禅問答なのです。そして、芭蕉は、こう答えているのです。
「蛙飛びこむ水の音」
そしてその後、この下の句に、 「古池や」
という上の句を付け、
古池や蛙飛びこむ水の音
という、日本の文学史上に残る名句が出来あがっています。しかし、何故こ
の句が優れているかというと、禅問答として、芭蕉の深い禅的な境涯が示さ
れているからなのです。
さて、では“無門関第1則”で、この僧の放った、
「犬には仏性が有るでしょうか、それとも無いでしょうか」
という質問の意図はなんだったのでしょうか...有るか無いかといわれれば、犬も
生き物ですから、当然仏性は有ります。しかし、“有る”と答えたのでは、小学校の先
生の答えになってしまいます。では、“無い”と答えたらどうでしょうか...これも当然
間違っています。第一、犬には仏性は有るのです。
ということは、“有る”と言ってもダメ、“無い”と言ってもダメだということです。では
どう答えればいいのでしょうか。実は、このように追い詰めて、答えに窮するように
もっていくのが禅問答なのです。そして、そのことによって、互いに研鑚を積むので
す。さあ、この僧は、趙州和尚に対し、“有る”と言っても許さない、“無い”と言っても
許さないと迫っています。
しかし、さすがに趙州和尚です。間髪を入れずに、「無」
と答えています。ただし、
“無”という答えはもともと許されないはずです。では何故趙州和尚は、「無」と答えて
許され、“無門関”の公案第1番目になるほどの歴史的な大手本となったのでしょう
か。
さあ...この趙州和尚の「無」こそが、この公案の命であり、この公案の全てなの
です。また、無門禅師自身も、苦労研鑚して透過し、ついに大悟に至った公案でもあ
ります。さらにまた、この“趙州狗子”(/“趙州の無字”ともいいます)は、その当時から今に
至るまで、最も愛された有名な公案の1つなのです。むろん、誰であろうと、この「無」
を極めれば、“悟り”に至ることができます。
さて、では小学校の先生の“無”と、趙州和尚の「無」は違うのでしょうか...はっ
きりと言って、この2つの無はまるで違います。小学校の先生の“無”は、有無の無
です。有るとか無いとかといった次元の意味です。ところが、大禅匠である趙州和
尚の答えられた「無」は、有無というような二元論的な無ではないのです。無門禅師
も評語の中でこう言っています。
虚無の無や、有無二元の無だなどと誤解してはならない。
これは...有無を越えた無、自他を超えた無、時を越えた無であり、あらゆる意味
で、二元論的意味の世界を越えた無なのです...
“心を空っぽにして、無になりきれ”、とは、この「無」を体現せよということです。そ
して、体現したまま、恐れることなく、一歩も引くなということです。
あるいは、“ 「無」字になりきれ ”
といいます。この時、自分も「無」字、他人も「無」
字、この世のありとあらゆるものを「無」字と観じていくわけです。そしてそれに成り
切っていくと、超越が起こります。「無」字が「無」字を見つめている、世界が世界を見
つめているという風景になります...そして、一歩も引くな、恐れることなく突き進め
といいます。
これが公案三昧です。座禅を中心とした修行で、この公案を透過し、“見性”(悟り)
に至るのが看話禅(かんなぜん)、つまり公案禅です。この公案禅の出現により、禅の修
業が公式化し、システム化され、より大衆に受け入れられやすくなったといわれます。
“無門関”は、その最初の公案集です。
さあ、この「無」について、もう少し考察してみます。無門禅師はこう言っています。
これまで積み重ねてきた二元的知識分別を払い尽くし、さらに参究を続けよ。やが
てその修行の機が熟する時、(内だ外だというような)一切の対立はおのずから一枚
となるであろう。この時、彼はすばらしい夢を見た唖子のようなもので、ただ自分が身
をもって知っているだけである。
この傍線部分は、原文に近い文語調で言うと、格調高く、こうなります。
自然に、 内外打成一片
(ないげだじょういっぺん)ならば...
この“内外打成一片”が、つまり、「無」の姿です。内もなく外もなく、一切の二元論
的対立を超越し、“一片”となった姿です。 さあ、“内外打成一片”を体現してみてく
ださい。
また、無門禅師は、こうも言っているわけです。
さあ言ってみよ、祖師の関とは何か。ただこの「無」字...これが禅の究極の一関
である。故にこれを「禅の門なき関門」と名付ける。
結局、この「無」が、「禅の門なき関門」の究極の1つだということです。そして、1つ
の公案を透過すれば、全ての公案を透過するといいます。また、その“見性/悟り”
の時の様子は...
この時、彼はすばらしい夢を見た唖子のようなもので、ただ自分が身をもって知っ
ているだけである。<PP>
...といいます。つまり、自分は身をもって知っているが、唖子のように、言葉で
言うことができないということです。さすがにここは“悟り”の領域ですから、自ら身を
もって体験するほかありません。
(1999.7.9)
<4> 趙州の
“無”
の考察 
さて、禅は実戦であり宗教であって、禅の思想的研究は、別のものとよく言われま
す。しかし、寺で修行できるのはごく一握りの超エリートであって、ほとんどは私のよ
うに在野の人間だと思います。こうした在野の人間が禅の世界に入っていくとなる
と、やはり禅の関係書物を読み、禅の思想的背景を勉強して行かなければなりませ
ん。
つまり、一般人の私たちは、禅の師匠に1つの公案を提示され、それに数年間も
命がけで取り組むというような修行は、とうてい出来ないのです。もっとも、現代の情
報化社会の中にあっては、禅寺においてさえ、あの公案時代のような大らかな修行
は、とうてい望めないのかも知れません。
いずれにしても、私は寺のことは何も知りません。また、座禅もあまりやった事が
ないのです。しかし、座禅は是非お勧めします。たとえ15分でも30分でも、また1
週間に1度でもいいですから、ぜひコツコツと積み重ねて行くべきです。なぜなら、禅
の修業は座禅が全てではありませんが、あくまでも座禅がその中心となるものだか
らです。確かに、六祖・慧能のように、米つきをして禅定に入り、悟りを開いた人もい
ます。しかし、この慧能とて、暇を見つけては座禅をしていたはずです。
しかし、一方、座禅が全てではないというのは、別の文化的な明るさと、ある種の
希望を与えてくれます。現代社会の中では、座禅を出来るような環境にある人は、そ
う多くはないと思えるからです。こうしたごく一般的な人でも、禅や禅文化と接した
時、身構える必要もないわけですから...
( ...当然のことですが、私もぜひ座禅をモノにしたかったのです。しかし、実はこの座禅の独学と
いうのは、うまく行きませんでした。生活や環境、私自身の問題など色々あったわけですが、ともかく
縁を結べませんでした。そこで、1週間でも10日でもいいですから、ぜひどこかの座禅会で、その基
礎を学ぶ機会を得たいと考えています...)
(
座禅に関しては、他の専門書をお読みください。座禅会に直接参加するのも、いいと思います)
さあ、ここでの仕事...「無」...の考察に入ります
自他を超えた「無」、主体と客体を越えた「無」、「内外打成一片(ないげだじょういっぺん)の自己」
とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。ここでは、“無門関”やその他の専門書
の教えとは別に、21世紀初頭の現代文明風に、独自の視点から考察してみます。
私たちは普通、なにがしかを認識する場合、まず“自己”という軸点となる主体を
置き、そこから自己以外の客体を観察するという手法を取ります。そして、自己を中
心に、友人や社会や国家、あるいは大自然や宇宙というものを認識します。つまり、
こうやって“自己”というものを確立しておき、そこから他を認識するというのが普通の
思考形式なのです。
ところが、“趙州の無字”では、この主体と客体という思考形式を越えた所に、
「無」の本質があるといいます。そこでまず、この“自己”、つまり主体とはなんなのか
の考察から入りたいと思います。
私たちはある範囲(とりあえず、時空間的な領域や、組織集団等の抽象的な領域...)を主体として
認識しますが、その最小の範囲を形成する境界は、自己の人体の皮膚表面というこ
とでしょうか。確かに、日常的な慣習としては、このあたりが境界になっていると思い
ます。そこで私たちは、まずこの境界から内側を自己として認識します。そして、その
外側を客体とか、自己に対する他者として認識するわけです。
しかし、ここでよく考えてみてください。この人体の皮膚表面という境界は、果たし
て本当に境界なのでしょうか。真に、厳密な意味で、自己と他者を分断している境界
面なのでしょうか。
まず、ご存知のように、人体の皮膚表面は呼吸をしています。これは分子レベルで
は、相当に激しく周囲の空気と相互作用をしていることを意味します。また、太陽の
輻射熱がジリジリと皮膚の温度を上昇させ、紫外線は皮膚ガンを作ります。これも、
皮膚と太陽との相互作用なのです。こうしてみてくると、この絶対的とも思える人体
の皮膚表面という境界面も、実はかなり曖昧なものだということが分かってきます。
(
これは、人体が環境や生態系、あるいは生命圏というものの中に、深く織り込まれているというこ
とです。そしてここは、まさに1点を押せば布模様全体が揺らぐ、切れ目も断層もないリアリティーの
世界だということです...)
また、外なる境界面とは別に、内なる境界面というものもあるわけです。例えば、
いまラーメンを一杯食べて胃の中に落ち着いたが、このラーメンはいったい自分の一
部と言えるのだろうか、とか...あるいは、風邪のウイルスが体内で増殖し、全身が
発熱しているが、この良からぬお邪魔ムシは、やはり自己の一部と言えるのだろう
か、とか...こう見てくると、内なる境界という風景も、きわめて曖昧なことが分かっ
てきます。
すると、厳密な意味で、“自己”と呼べるものなどいったい何処にあるのでしょう
か。そこで、それではDNA最高モードの人間の脳は、間違いなく“自己”のはずだと
言う人がいるかもしれません。しかし、このDNA最高モードの脳も、実は酸素や血液
がその外部から常時供給され、人体全体と密接に相互作用している存在なのです。
そして、その人体は、生態系や地球生命圏と深く相互作用をしているというわけで
す。こうみてくると、厳密に“自己”と呼べるものなどは、この世の何処にも存在しない
ということが分かってきます。
<関連 >
/ 私の “心” は、いったい何処にあるのか?
禅宗の初祖・菩提達磨(ぼだいだるま)と2祖・慧可(えか)の話です。
ところで、“自己”という概念はそもそも、この世界を自己と他者の2つに分断した
上で、一人称の部分系を指すものです。しかし、この野暮で本能的でもある単純な作
業を、甘く見てはいけません。この世界を分断する意識の圧力は、まさに細胞分裂よ
うに、この世界全体を際限もなく部分に分解して行く力を持っているのです。しかし、
この発達心理学的な進化は、あくまでも影であって、真の姿ではありません。また、
禅の悟りの風景とは、むしろ生まれたばかりの赤ん坊の、自己と宇宙が未分化な状
態の意識に近いのです。
<関連>/
発達心理学における原初の“我”
この世界を際限なく分断してきた流れは、裏を返せば言葉による概念や名詞の分
類と、それに名前をはめ込んできた、人類文明の歴史でもあるのです。またこれが、
人類文明が独自に形成してきた、言語的空間の進展なのです。こうした観点から眺
めると、人間はこの言語的空間、つまり文明的空間に居住しているという側面を持つ
のです。例えば、“アメリカ”と言った時、それは瞬時に膨大な情報量が準備されま
す。そのイメージは時空間的なものから歴史に至るまで、相当な領域と深度に及び
ます。しかし、この文明空間を離れて“アメリカ”と言ったのであれば、それは単に五
感によって直接的なアメリカ大陸の大地を指すだけです。つまり、人類の持つ文明空
間とは、これほどの威力のものであり、これが人類を太陽系の惑星空間へと押し出
したのです。
<この文明空間のコントロールは、その巨大さゆえに、今後十分な監視と微妙な注
意が必要となってきました。これがさらに惑星空間へと拡大する前に、文明空間自
身の崩壊か、地球生命圏の崩壊が起こる可能性が出てきたからです。>
さあ、上記のように、“自己”という部分系が厳密には成立しないように、そもそも
この宇宙にも、独立した部分というものは成立しないし、存在しないのです。これは、
数学的にも証明されています...<ベルの定理>。
<ベルの定理>
この定理は、局所的な隠された変数の存在は、量子力学の確率的予測
と数学的に両立できない事を証明しています。量子の世界では、因果律が
崩壊しているという言葉をよく耳にします。これは、現象には原因があり、結
果があるという一般的な常識が崩れているということです。そして、この事は
何を意味するかというと、局所原因の原理が間違っているということです。つ
まり、この世界の中に、独立した部分というものは成立しないということで
す。しかし、こういうことになると、光速度を越える情報交換の可能性も出てく
ると言われます...
したがって、このように考えてくれば、禅的な深い境涯に至らなくとも、“自己”とい
う部分系などは本来成立しないものであり、それゆえに他者などというものも存在し
ないということが分かります。つまりこれが、この主体と客体を超えた風景が、この世
界のリアリティーそのものの姿だということです。
さて、もう一度確認してみましょう。今、この我々の眼前に展開している世界...
このリアリティーの風景には、切れ目がありません。首を回せば、球形に、継ぎ目の
ない生の世界が展開しています。通常私たちは、このリアリティーの風景というもの
は、あまりにも身近すぎて、ほとんど考える事がありません。私たちはこのリアリティ
ーというものを、折に触れ、じっくりと観察してみる必要があります。
まず、テレビや絵画や映画には、枠や切れ目というものがあります。しかし、リアリ
ティーにはそうしたものがありません。“切れ目”や、完全に独立した“部分”や“断
層”というものがまるで無い世界なのです。それがあるように見えるのは、言語によっ
て名前が付けられているからです。私たちは名前によって川と大地を分け、海と山を
分け、水と魚を分けているだけなのです。それらは本来互いに影響しあっている、不
可分な風景であり、不可分な世界なのです。
それゆえに、“この世界は唯心、ただひとつの心”と言われるのです。また、私が
この世界を“真実の結晶世界”と呼ぶわけもここにあります。したがって、あえて
“「無」になれ”などと言われなくとも、元々この世界のリアリティーは、2元論を超越し
た「無」であり、部分や継ぎ目の無い“単一の結晶世界”なのです。
このことを知っておいて、さあ、「趙州無字」の禅的な世界に入っていきます。
(1999.7.21)
<Tea time
>
「山を眺めながら、お茶を一杯どうぞ...」
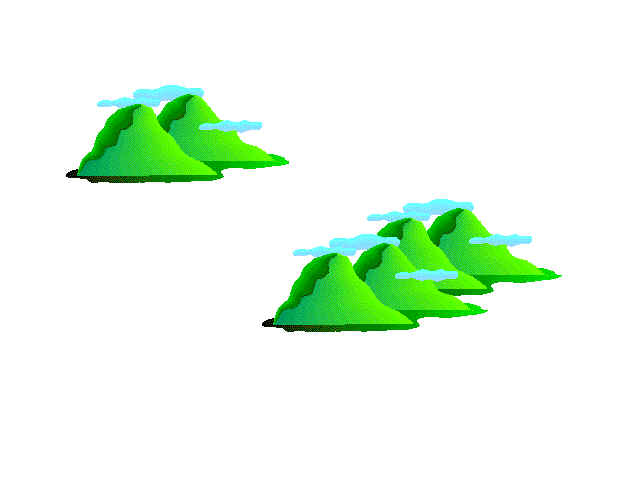  
<担当:高杉光一より、お茶のサービス >
お茶を飲みながら...
「...うーむ...
人生における最大の関心事とは何でしょうか...それを、私たちは“価
値”あるものとして、終生追い求めて行くわけです...しかし、いったい価
値あるものとは、どのようなものなのでしょうか...」
「豊さ、愛、正義、宗教心、美、そして探求心...どの地域のどのような社
会集団であれ、こうした価値観というものはほぼ共通しているのではない
でしょうか...さて、ここでもう少し突っ込んで、これらの価値観や目的性
というものを考えてみましょう...」
「そもそも“豊さ”とは、その対極に“貧しさ”という概念があります。“愛”と
いう概念もまた、“憎しみ”という対になる概念の一端です。同様に、“正
義”の反対には“悪”があり、“美”の対極には“醜”があります...一体こ
れはどうなっているのでしょうか。
これは、実は不可分であるリアリティーを、私たちが言語で境界線を引く
ことによって発生してくる概念なのです...その境界線を何処に引く
か...これこそまさに、無限に拡大して行く可能性を秘めています。」
「...私たちの思考形式、言葉による概念の世界は、このリアリティーを無
限に分断する事によって成立しています。右といえば左があり、上といえ
ば下があります。また、東西、南北、大小、長短、強弱、賢愚、苦楽...
私たちの言語世界は、こうした相対立する概念の単位が構成する、膨大
なホログラムのように見えます。」
「...繰り返しますが、私たちは本来不可分であるリアリティーを、言語に
よって境界線を引いているのです。そして、益々深化していくその両極端
の一端にのみ、価値を見出そうとしているのです。
社会も個人も、“より深い”豊かさを求め、“より深い”愛情を求め、“より
深い”正義を求め、“より深い”美を求めています。しかし、表裏一体の関
係にある概念の一方のみを求めるということは、本来不可能なことです。
私たちは、その影、つまり裏の部分が必ず付いてくるという事に、もっと注
意を払うべきです...」
<学校では、豊さ、愛、正義、美、探求心等を教え込もうとしています。しかし、この陰陽
のうちの“陽”のみを寄せ集める事など、本当に出来るのでしょうか...うーむ...もし
これらの全てが本当に実現するとしたら、そこには“無気力”が同居しているのではない
でしょうか...>
「...こうした二元論的関係は、しばしば波に喩えられる事があります。例
えば、豊かさの頂点に立つ人は、その対極にあるどん底の人を知ってこ
そ、自らの豊かさを認識できるのです。また、深い愛情で結ばれたカップル
は、深い振幅の波の頂点にいるのだということに気づくべきです。それは
いつまでも続くものではなく、やがてそれに相応した深い谷底に沈んで行く
のだと言うことを知るべきです。もっとも、これも人生の妙味というものでし
ょうが...」
「...さて...禅では、この二元対立的な概念を超越し、リアリティーを直
接掴み取るところに、“無門の関”があるといいます...貧しさをにらみな
がら豊かさを求め、憎悪や差別を片隅に住まわせながら愛情を求め、悪の
影を踏みながら正義を叫ぶのは、本来矛盾しているということなのです。そ
れは決して実現する事のない命題であり、私たちは絶えず敗北しつつ、適
当なところで折れ合って生きているのです。
しかし、この二元論的対立を超越し、“無門の関”を越えれば、この迷い
から脱する事が出来るのです。」
<第1則/趙州狗子>...終り
|
 趙 州 狗 子(
じょうしゅうくし)
趙 州 狗 子(
じょうしゅうくし) ![]()

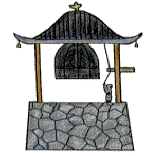


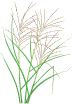
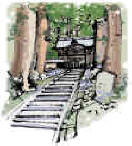


![]()
![]()


