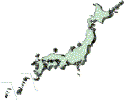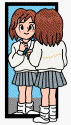「すっかり春らしくなりましたね...」茜が、茶碗と皿を押しやり、ノートパソコンに目を移
した。「ええ、では、始めましょうか...
これは...高杉・塾長の言葉ですが...私たちの社会を構成するシステムは、“存
在の器”と、“目的追及組織”とに大別されます...この2つシステムは、目的も性質も
大きく異なるものです...
これらが、“混同”され、経済原理で統一的に運営されている所に、社会の様々な矛
盾や弊害が生まれています...つまりこれが、東西冷戦構造時代以降の...勝利をお
さめた側の、資本主義/自由主義/経済至上主義...の、社会モデルという事になり
ます...
ええ...この社会モデルは、“市場万能主義”という側面を持ちます...ある意味で
は、野生のような...非常に“弱肉強食性の強いシステム”です...でも、それがあま
り強くなり過ぎると、私たちは何のために文明社会を形成しているのか、社会を形成して
いる意味が、分からなくなってしまいます。
私たちは、支配され、奴隷のように奉仕するために、社会を形成しているわけではあり
ません。主権者である国民は、平等に、心豊かに暮らしていくために、社会を形成してい
るのです...」
茜は、風に目を細め、2階の窓から草原を眺めた。草原は淡い緑の沸き立っていた。
青木が、茜の横顔を見た。茜が、その視線を受けながら、ノートパソコンに目を落とした。
「“存在の器”とは...」茜が続けた。「家族や教育の場...それから、地域社会や国
家が代表的なものです...
こうした“器自体”は、何かを“追及するシステム”ではありません。そこに“存在”し、
心豊かに暮らしていくための、“生活基盤/社会基盤”です。この基盤システムが、安定
していて豊かであることが、豊かな文化を育みます。そこが、私たちの理想郷なのだと思
います。
したがって、この“存在の器”では...経済原理や様々な理屈を超えて、穏やかな愛
情で包まれ、“人間的エキス=社会慣習法的システム”で、万事処理されているのがい
いのだと思います。“人間的不文律/慣習法”こそ、社会構成のエキスなのですわ。
特に...野性を離脱して、文明社会を構成している人類社会では、この人間的エキス
/社会構成エキスがとても重要になります...ところが現在の日本では、この“慣習法”
が、故意に破壊されつつあります。
“慣習法が破壊した社会や文化”は、非常に不快なものですわ。テレビを見ていても、
イライラすることが多いですね。街路の花は首をちょん切られ...公園の水鳥は不当な
虐待を受け...後期高齢者保険は、老人は切り捨てると言わんばかりです...こうした
状況は、さらなる治安の悪化を予感させます...
日本の社会は、治安が非常に悪くなってきていますわ...これは、社会上流域でモラ
ルハザードが拡大し、“慣習法”が故意に破壊されていることが原因と思われます。政
治・行政・マスメディアの責任は、非常に大きいという事ですね」
「そうだと思います」菊地がうなづいた。
「私たちは...
“生活基盤/社会基盤”を豊かにするために、文明を発祥させ、農耕や工業を展開
し、あるいは幾多の戦争や革命を経験してきました。その全ては、この“存在の器”を、
豊かに保持することが、共通の大目的でした。
一方...もう1つの、“目的追及組織”というのは...“存在の器”の中で構成する、
軍事組織、政党組織、行政組織、研究組織、経済組織群などに、典型的に見られます。
これは、“物事を目的にそって完遂”するための、ハイ・テクノロジー組織です。つまり、
“文明社会の利器/文明社会の高度な道具”と言えますね。
現在、膨大な市民を吸収している...労働環境/企業組織群も...資本主義経済
下では、やはり、利潤追及型の“目的追及組織”だと言えますね。こうした組織は、目的
追及のための、高機能/目的達成型システムなのです...」
「はい...」菊地が、頭を傾げた。
「ええ...
現在、これらが、ゴチャマゼに...“経済原理で統一的に運用”されている所に、民主
主義社会が大混乱に陥っている原因があるようです。このために、“文明社会の高度な
道具”/“目的追及組織”が、逆に“存在の器”を支配している状況になっています。こ
れは、民主主義社会として、正しい姿ではありませんわ...
それから、もう1つ付け加えると...民主主義社会における、“組織の私物化”という
現象です...こちらの方が、むしろ弊害が大きいかも知れませんね。政治・行政・マスメ
ディアという、社会上流域での“社会公器の私物化”は、この国を建国以来の大混乱に
陥れていますわ。
その人たちは...ハイ・テクノロジー組織/“文明社会の高度な道具”/“目的追及
組織”を、自らの“存在の器”にししようとしています。そこを既得権を囲い込み、巧妙に
“社会公器を私物化”しはじめました。このことが、“慣習法”を破壊し、身分差別社会を
創出する方向へ流れています。
それで、一体...当の彼等に...果たして得るものがあるのでしょうか...?」
「まさに、そう思いますね、」菊地が腕を組み、椅子の背に体を引いた。
「くり返しますが...
原始・共産主義社会=“存在の器”の中で機能する、“目的追及組織”は...ちょう
ど、“文明の利器/便利な機械”のようなものですわ...ところが、そうした組織が、支
配階級のように権力を振るい始めたという事ですね...
組織というものは、命令系統/指示系統が明確ですわ。そのために、必然的に力を
持ち、支配力を拡大する傾向を持ちます。この種の力が、いよいよ増大し、モラルハザー
ドを突破力として、基本的人権を凌駕しつつあるという事です...これは、放置しておけ
る問題ではありませんわ」
「確かに!」菊地がうなづいた。
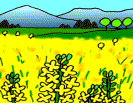


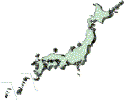

「本来...」茜が言った。「“目的追及・機能”は、社会を豊かにしていくためのシステム
/・・・機能です...
また...その“社会システムの生み出した富/・・・社会的果実”は、“存在の器”の
中で、主権者に平等に分配されるはずのものです。でも、現在の日本の実態は、全レベ
ルにおいて、“目的追及組織”が“組織・権力”を持ち...それを“既得権化/特権階級
化”し...“寡占化(かせんか)/独占化”しています。
そのことが、そもそも社会に、壮大なモラルハザードを展開する原因となっています。
国家上流域の、政治・行政・マスメディアが特にひどいですね...そして、国家中流域
/企業組織群で、“大企業が富を寡占化”しています...これも、ひどいものですわ。
くり返しますが、“社会システムの生み出した富/・・・社会的果実”は、主権者/国民
に、“正しく=平等”に再配分されなければなりません...それが、デタラメになっていま
すわ...
“社会貢献/努力/勤勉/勇気/まごころ/優しさ/”といった“社会慣習法的・価
値観”が、故意に破壊されて来ています...これでは、国民は夢が持てません。確実な
将来地図をもち、それに向かって勤勉な努力をすることができません」
「そうですね、」菊地が言った。
「社会奉仕もせず、労働もしない人々が...
富裕階級/資産階級となっているのは、“存在の器”として、正しい姿ではありません
わ。システムがそうなっているとはいえ、“慣習法”に反し、大きな弊害となっています。こ
れは、国民主権の民主主義国家としては、非常に問題のある姿です。
法律的に、それが許容されているというのであれば...私たちは、その法律や“社会
的慣習”を、変えて行かなければならないという事です...“ライブドアの株売買の事件”
で、そうした事が一時問題になりましたわね...
私たち主権者/国民は、そうした事を正していく権利と、民主主義的な力があるとい
う事ですわ。主権者/国民は、その権利と力を、今こそ発動しなければなりません...」
「ええと...」菊地が、口に手を当てた。「整理すれば、そういう事になりますね...
様々な“目的追及組織”が...国民主権とは別の所で...“組織・権力”として機能
しているという事だと思います。行政組織が、その代表的なものですね。公務員というの
は、事実上、非常に優遇されています。“天下り構造”に見られるように、“組織・権力”と
して機能しているという事です。
本来、“目的追及組織”は、“存在の器”のための、奉仕システムでした。それがい
つの間にか、逆に、事実上の支配組織になってしまっています。国家上流域での、“社
会的慣習法”の崩壊が、こうした傾向に拍車をかけています。
これは、“国家OS(基本ソフト)のバージョンアップ”が必要だという事ですね。また、それ
を未然に防ぐためにも、“国家OSの定期バージョンアップ”が必要だという事ですね。
それを受け入れられないのであれば、官僚になる資格がないという事でしょう。そういう
人は、何か他の仕事をすればいいわけです」
「はい...」茜がうなづいた。「そうですね...
東西冷戦構造が終結し、資本主義体制が勝利をおさめ...世界システムを、資本主
義/自由主義/経済至上主義が席巻しています。
こうした世界構造の中で、“存在の器”と“目的追及組織”は、経済のもとで、統一的
に処理されています。まさに混在・混同して運営されていますわ。厚生行政が、その典
型となっています。まさに、滅茶苦茶で、それが顕在化しています。
ともかく、“経済至上主義”のもとで...経済力が“1つの権力”として...その力を増
大させています。これが、日本国家/【日本国憲法】における...基本的人権を侵害す
る所まで増大して来ています。
これは、“文明の折り返し”の中で、解消して行かなければならない課題です。“経済
至上主義”のもとでは、“地球温暖化の危機”は乗り越えられませんわ。そうである以上
は、できるだけ早く、緩やかに舵を切り始めることが、良策だと思います。
それを政治に期待できない以上は、国民が覚醒し、行動に移すことが必要になって来
ました」
「うーむ...」菊地が、手を組んだ。「そうですね...そうした大局的展望はともかく...
“経済至上主義”というものは、まさに民主主義を凌駕(りょうが)していますね...日本
の実情は、“経済至上主義”が、基本的人権を凌駕しています。経済が民主主義を凌駕
し、“強大な権力”を持ち始めているようですね。
こうした権力は、憲法に謳われているものでもなく...正当な民主主義的手続きを経
たものでもありません...しかし、事実上、国家上流域の政治・行政・マスメディアの中
枢にも...こうした“経済・権力”が、ガン細胞のように浸潤(しんじゅん)しているのは確かで
しょう。それが、社会を大きく歪めています」
「はい!」茜が、強くうなづいた。「国民は、“自由”という象徴的な言葉に酔ってきました
わ。その裏で、“経済・権力”が、民主主義国家に、ガンのように浸潤しているのに気付
きませんでした。
日本では、政治においても、行政においても、経団連/財界のような組織が、強力な
“経済・権力”として介入していますわ。政府のもとに、経済財政諮問会議があったり、公
共放送・NHKに経営委員を送り込んだり...その一方で、国民の人権はないがしろに
されていますわ。
最近、ようやく消費者・担当部局の話が持ち上がっていますが、あまりはかばかしく
ありませんね。自民党・長期政権の下で、権力の側が国民の側に立つという、考えその
ものが無かったからですわ」
「まあ...国民の“命と生活”を預かる厚生労働行政を見ても、あのありさまですね、」
「はい...ええ...
菊地さんのおっしゃるように...そうしたあらゆる矛盾を押さえ、緩やかに国民を納得
させてきたのは、“伝統的・慣習法の機能”によるものだと思います。“世間様”に対す遠
慮/配慮と、その了解を求める“慣習法”が、古来から日本の文化の中に存在して来ま
した...それが、日本的な社会構成のエキスだったのですわ。
ところが、その“社会的慣習法”まで破壊された所に、現在の日本の、未曾有の危機
があります。“社会秩序の基盤/文化的なエキス”まで抜き取ってしまった所に、社会上
流域の、真の愚かさ/邪悪の巨大さが反映されていますわ...」
「まさに、茜さんの言う通りですね、」菊地が、大きくうなづいた。
「“各個/・・・自分だけ”が...“清濁を併せのむことを許されている”...と思ってきた
結果ですわ...そんな事を公言していた政治家もいましたが...そんなバカな事は、
本来成立しないわけです...
国家上流域が、全レベルで、そんなバカげた哲学を持ってしまったわけですわ。政治・
行政・マスメディアに、非常に大きな責任があります。“世襲政治”、“天下り行政”、“公
共放送・マスメディアの私物化”に、国家が未曾有の大混乱に陥った原因があります。
何度も、くり返して言って来ていることですが、それを反省している様子はありません
ね。いつまで、こうしたバカなことを続けて行くつもりなのでしょうか...?」
「そうですね...
国民が、その壁をぶち破って行くしかありませんね。物価高と労働格差で、いよいよ生
活ができなくなってきています...“世襲政治”、“天下り行政”、“公共放送・マスメディ
アの私物化”を、全てやめさせていく所に、〔21世紀・維新改革〕があります。その先
に、日本の明るい未来がありますね」
「はい!
そのためにも、〔人間の巣〕を展開していく、【日本版・ニューデール政策】を推進し
たいですね!」
<当たり前のようになった・・・
組織・権力/経済・権力 の暴走!>



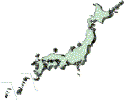

「まあ...」青木が、初めて口を開いた。「話を戻しますが...
確かに...“経済・権力”というのは存在しますねえ...大企業/経団連などを中核
とした財界は、この国で膨大な権力を持っています。また、そうした大企業による“富の
寡占”が、まさに構造化しています。これは、まぎれもない事実でしょう...
国民は、そうした“経済・権力の暴走”の下で、とうとう食えなくなる所まで、弾圧されて
います...まあ、こういう言い方をすると、様々な異論もあると思いますが、これは1つ
の客観的事実です。個人の能力や努力を超えた所で、“富の寡占”が構造化していま
す。
“組織・権力/経済・権力”等を有していれば、政治や行政は接見もしますし、耳を傾
けたりもするわけです。しかし、庶民/市民/国民の側は、その窓口さえないわけです
ねえ。全国各地で、市民と行政組織の対立は、構造化している状況です。このこと自体
が、民主主義社会としては、非常に歪んだものです...」
「はい...」茜が、唇を引き結んだ。
「日本は、国民主権の、民主主義国家です...
そのことは、【日本国憲法】に謳われています。しかし、資本主義とか経済主義とか、
あるいは、“組織・権力/経済・権力”とかは、憲法には何も記述はないわけです。“経
済・主権”などという言葉も、むろん存在しないわけです。ところが、それに従う政治家が
いて、それにつながる官僚が存在します。
自民党・長期政権下で構造化し...現在の福田・政権においても...行政全体が、
経済を中心に動いていますねえ。人権や民主主義などは、“しょうがない(福田首相が使った言
葉)”という一言で、片隅に追いやられています。これで、果たして、国民主権の国家なの
でしょうか...」
「そうですね...」菊地が言った。「現実には...
“組織・権力/経済・権力”が事実上、“日本を支配”しています...まるで、主権者/
国民の上に、“経済・権力”が存在しているようですね...非常に微妙な問題を内包して
いますが、少し引いて眺めれば...大企業/財界が日本を牛耳っている構図は、火を
見るよりも明らかですね、」
「まあ...実質的に、そうでしょう...
“富を独占”しているわけですからねえ。民主主義国家の中で、この国の主権者/国
民はどこへ追いやられてしまったのでしょうか。茜さんの言うように、ルールがそれを許し
ているというのなら、私たちはそのルールを変えていく必要がありますねえ...」
「でも...」茜が言った。「国民も、ようやく、この異常な事態に気付き始めましたわ...
これほどの、“富の寡占/富の片寄りはおかしいと”...社会システムの生み出した
果実は、財界で独占していいものではありませんわ。それは、国民みんなのものです。
むろん、それなりの努力した部分は認めます。でも、独占していいものではありません。
国民は、実質的に、生活ができなくなっていますわ」
「政治家は...」青木が言った。「民主主義の代議員というよりは...
まさに、利益代表のようになっていますねえ...行政は、民主主義の行政組織とい
うよりも、単なる利益配分/利益再配分の組織のようになっています。こうした状況は、
すでに国民は、“組織・権力/経済・権力”の支配下にあって久しいという事です...
それが、いかにも“当たり前”のようになっている所に...国民の側の民度の低さもあ
るわけです...これは茜さんが言うように、“公共放送・NHK”の責任が、非常に大きい
でしょう。まさに、“民主主義の牙城”を、権力側に明け渡していたのですからねえ...
“運営委員会”が“経営委員会”に変えられているのが、何よりの証拠でしょう。そし
て、国民とのリンクが切られた場所に、財界人が送り込まれていますねえ。この“公共放
送・NHK”は、前にも指摘していることですが、“日本国家のミニチュア版”になってい
るという事です。
“公共放送・NHK”は、モラルハザード国家の“バロメーター”になっていて、その全
てが投影されているという事ですか...」
「はい...非常に精密な“バロメーター”になっていますわ...トヨタ方式を移植すると
かしていますが...この方式では、経済効率は追求できますが、もっと大きな民主主義
社会の健全化や、“地球温暖化”の時代は、乗り越えられませんわ...」
「国家全体が...“公共放送・NHK”のように、“経済・権力”に乗っ取られ...まさに、
その“経営委員会”のように、国家が経営されているという事でしょう...トヨタ方式で。
それがいかにも“当たり前”のようになっていますねえ。しかし、この“存在の器”はそ
うしたものではなく、国民の“生活基盤”なのだという事ですねえ...」
「はい!」茜がうなづいた。
「今問題になっている...」菊地が言った。「厚生労働省や国土交通省や財務省も、国
民の方を向いているというよりも、まるで“富の支配の舵取り”をしているようですね。そ
れを当然の事のようにやっていますね、」
「うーん...」茜が、首を振った。「だから...
“地球温暖化対策”などでも、経済原理を超えた大改革が打ち出せないのですわ。国
民のことを第1に考えているとは、言い難いものがあります...“経済・権力”に、構造的
に支配されているから、既得権の殻を打ち破る大改革が打ち出せないのですわ」
「豊かな国民生活とは...」菊地が言った。「イコール、富の配分のように考えられて来
たわけですね...しかし、そうではない事が、喫緊の課題として顕在化してきています。
富のバラマキが、政治であり、行政であるかのように行われてきましたが、それがいよ
いよ行き詰まって来ましたね。国民が、まさに、食えなくなってきています」
「はい!」茜が、強くうなづいた。「物質主義/経済至上主義/“経済主権の政策”の下
で...まさに、“心の豊かさ”も失われて来ましたわ...
そうした中で...“社会的慣習法”の破壊も、公然と進められているわけですね。それ
で、日本の文化全体、日本の社会全体が、非常にシラケたものになって来ています。マ
スメディアの流す文化全体が...1部をのぞいてですが...非常に気分のイラダツもの
になって来ています。こうした事が、様々な犯罪として、顕在化して来ていますわ...」
「そして...」青木が、宙を見上げた。「そうした中で...
国民に、愛国心や、国際的競争心を強要していますねえ...自らが、モラルハザード
社会を創出しておきながら、文部行政の中に、愛国心を盛り込んでいるのは、政治・行
政の茶番ででしょう...案の定、国家体制が、まさに空中分解しようとしています...」
「はい!」茜が、コクリとうなづいた。