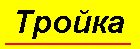
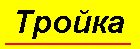
 |  | 
|
| パッケージ | トップ画面 | ストルガツキイ兄弟の紹介 |
↑クリックで拡大
| ||
同誌に掲載された「ストラーニク'99」レポートに書ききれなかった部分をここでフォローしておく。
●分類しろ!――サブジャンル分けの試み
堀浩樹氏が書いているとおり、ロシアのSFはかなり多様化している。作家はそれぞれの姿勢で創作を続けるだけなので何の問題もないのだが、困るのは出版社や書店である。売り方や並べ方がわからなくなってしまうのだ。そこでSFをサブジャンルに分類する試みが始まっている。 例を挙げてみると、遍歴者賞ジャンル部門は、と分けているが、一九九八年に出版された「二十世紀ロシアファンタスチカ作家事典」では、ファンタスチカにはサブジャンルとして、
- ヒーロー物
- 歴史改変
- ファンタジー
- ホラー
があると紹介されている。また、SF専門出版社テラファンタスチカが経営しているオンライン書店では、
- 歴史改変
- サイバーパンク
- ターボリアリズム
- ファンタジー
と分類している。 だが、そんな試みが行われている一方で、作家は表現したい題材にあわせて自由に手法を組み合わせてしまうので、「歴史改変ホラー文学的科学小説」という作品も実際に存在する。作家達が自分の課題を突き詰め、表現を磨くほど、出版社や書店、資料家や評論家は困ることになるわけである。だが、これは作家の創作意欲や向上心が旺盛であることの証なので、読者にとってすれば大いに結構なことだといえる。
- 文学的ファンタスチカ
- 科学的ファンタスチカ
- 歴史改変
- ファンタジー
- ホラー
- 娯楽作品
数百年にわたる「呪い」を背負った旧家の当主となってしまった美少女の苦悩と、迷信に取り憑かれた人々の混乱、偶然訪れた学者が遭遇する奇怪な事件を描いた作品。紋切り型にジャンルを当てはめると、ダーク・ファンタジーのように始まり、ホラーかと思わせ、サスペンスミステリーで終わるとでも言えるだろうか。
伝説の収集に訪れた学者が、雨宿りのために泊まった城には、若い女性の当主ナジェージダが住んでいた。そこは何者かの走り回る音がいつも聞こえているという、幽霊屋敷のような場所であった。そしてその当日、全裸の当主が白い羽の中で、何らかのまじないを受けているところを目撃するなど、どう考えても尋常な雰囲気ではない。執事から聞いた伝説によると、数百年前に城の先祖が暗殺したスタフ王の呪いによって、関係者は全員変死してきたのだと言う。そして小人、女、スタフ王の幽霊として目撃されるのだとも言う。
呪いに心を奪われ、ナジェージダや叔母が次第に半狂乱になっていくなか、ついに人が殺されはじめる。そして学者もついにスタフ王の部隊を目撃するのだが……。
総じてたいへん完成度が高い作品だと言えるだろう。過剰なまでのドラマ性・幻想性、そして非常に凝った画面の構図や美術は、少女漫画的ですらある。また、効果音や音楽の使い方が上手く、よけいに効果を盛り上げている。
この作品をダリオ・アルジェントの作品と比較すると怒られるかもしれないが、オカルト的な題材、美術・構図・音楽の様式美、奇怪な小道具、唐突な演出、猟奇的な事件、事件の渦中でいたぶられる美少女など、作風に多くの共通点が感じられた。
少女漫画やダリオ・アルジェントなどを持ち出すと誤解されるかもしれないが、私にとっては褒め言葉である。
(1999.3.13) (大野典宏)
さすがに特撮などは古いと言わざるを得ないし、同時期のアメリカ映画や日本映画と比べると技術的にも遅れている。だが、それが本作品の価値を貶めることにはならない。
単に金星に行き、命からがら帰ってくるだけという単純な話なのだが、異星人の存在・文明の起源に関する考察などを真っ正面から扱い、テーマ的にもストーリー的にも非常にまじめでしっかりした映画である。SF映画史の中で決して無視できない作品だと思うので、機会があればご覧になることを強くお勧めする。
面白かったのは、本作品に登場するアメリカ製ロボット「ジョン」である。このロボットは敬語で話さなければ言うことを聞いてくれない。また、宇宙服のヘルメットを平気で剥がしたり、溶岩の中に人間を放り込もうとしてしまうロボットなのである。アシモフの三原則がしみ込んでしまった身としては、非常に違和感を感じてしまう存在だ。ジョンは本作品の中でギャグの部分を担当するのと同時に、トラブルメーカーなのである。
だが、本作品の中で採用している行動ルールで考えてみると、ジョンの行動には何の矛盾も無いのだ。ルールは次の二つ。
SFマガジン1999年4月号の記事で本作品を少し紹介したが、そのアフターフォロー。
このビデオ、困ったことにR指定である。税関の審査がどうなっているのか全くわかっていないうえ、何らかのトラブルが起こった際、私には責任の取りようがないので、「買えない」と書いてしまった。だが、実は購入できてしまっていたわけだし、事実と違う記述をしてしまったことに変わりはないので、この点に関してはお詫びして訂正するしかない。だが、そう書くに至った事情はご理解いただきたい。
とはいえ、実際に観てみたが、なぜR指定になったのか、まるっきりわからない。
記事では本作品の簡単なあらすじを紹介したが、実を言うと、ストーリーの途中までしか紹介していない。今後この映画が公開されないという保証はないので、ネタバレを避けるために途中で止めてしまったのだ。だが、本作品では後半こそが重要なので困ってしまう。
主人公はその後、良心とルールの狭間に追い込まれ、「新しい世界での生活」に絡め取られてゆく。そして皮肉かつ衝撃的なラストシーンが……。題名にある「Friend」とはいったい誰のことなのか、それがわかったとき、観ている者は、主人公が背負った業を実感することになるだろう。
と、書いてみたが、何ともはや……である。
そこで、その後のあらすじを別ファイルとして用意したので、ネタバレでも良いという方は、そちらをご覧いただきたい。反則といえば反則なのだが、こうでもしないと説明できない。
個人的には高い点を付けられる作品だと思うだけに、あえてこのような形で紹介することにした。
(1999.3.7) (大野典宏)
チャペックのSF戯曲である。名前を変えながら、時代と場所のあちらこちらに登場するオペラ歌手の秘密を巡る「喜劇」。ネタを割っても怒られないと思うが(だってカバーに書いてあるんだもん)、不老不死、具体的には「人間の適正な寿命」がテーマになっている。
人間には寿命があるという現実をどう捉えるのか、もし不老不死が実現されたら、といった「不老不死テーマ」の作品は少なからず書かれているが、残念なことに、これらは私にとってあまりピンとくる題材ではない。そもそも考察する意味があまり無いと思うのだ。個人的にはあってもかまわないし、無くてもかまわない。確かに身近な人が危険な状態になったときには延命治療をお願いすることになるのだろうし、誰もが長く生きていてほしいとは思う。とはいえ、それと「不老不死」を望むこととは一致しない。したがって、「人間は長寿であるほど良い」、「人間には寿命があるべき」というどちらの意見に対しても積極的に支持する気はない。
ただ、gooで「不老不死」と入力すると千件以上も引っかかるところを見ても、一般的に広く関心を持たれている話題なのだということはわかる。長寿を望む人、さらには不死を渇望する人がいる以上、その研究がなされるのはたいへん良いことだと思う。そして、もし「寿命があるべきだ」と信じる人と意見が対立することがあったとしても、思う存分意見を交わせばいいだけの話だ。ただし、これはすでに「信心」の問題なので、議論したところで結論がでることはないと思うが。
さて、本書の序文を読めばチャペックが「寿命派」の意見を持っていることがわかる。そしてこの主張は、当然、作品の中にも強く現れる。死を望みながら、それを得ることができない主人公の様は「悲劇」でしかない。また、それと同時に、不老不死の必然性を必死で唱える人々の様は、強くデフォルメされ、明らかに「喜劇」として描かれる。「長寿派」の見方からすれば、このようなチャペックの態度は不公平に見えるのかもしれないが。
で、私は先に書いたように、このような主張には関心が無いので、喜劇は喜劇として、悲劇は悲劇として単純に楽しむことができた。
(1999.2.9) (大野典宏)
えらいことになっている……。どうしよう(^^;)。
コンセプチュアリズムやソッツアートとしての読み方や位置づけに関しては、本書の解説や阿部軍治著「ソ連邦崩壊と文学」(彩流社)などを参照していただいたほうがいいだろう。また、こういった文脈で語ると、インタビュー中で作者本人が『(外国での評価が高いことに対して)ある種の素材としての研究しているのです』と語っている通り、作品が「素材」という違った意味になってしまうようなので、避けたいという気持ちもある。たとえ作者が、そのような研究であれば認められているのも『分かる』とし、話そのものについて語られることを拒否するような態度でいようが、読者としては知ったこっちゃない。作者の背景を全部無視し、書かれている内容のみで判断する、つまり本書の場合には、特異なエロ・グロ・シュール作品として評価するのもアリだろう。
さて、本書に収録された作品を、エロ・グロ・シュール作品として読んでも、非常に高い評価を与えることができる。
本書を読んでいる最中、その現実感が全く感じられない描写や、徹底した表現から、筒井康隆のスラップスティック作品やピーター・ジャクソンの映画を思い出していた。本書の読書体験は、観た人ならわかると思うが、ジャクソンの作品『ブレインデッド』の後半部分、観ている者の感覚が次第に麻痺して行く体験に近いものがある。あれこそは映像のハードドラッグだ。そういう意味では、「言葉は麻薬」という帯の表現は非常に言い得ている。
解説によると、作者は『パルプフィクション』が好きだということだが、これは本書を言い表すのにピッタリの表現である。まさに文で書いたタランティーノ作品。ストーリーの無さ、薄っぺらい登場人物、意味の無い会話、決してウェットにならない視点、それでありながら受け手に与えるインパクトを計算しつくしている点など、多くの点で非常に似通っている。本書に最も近いタランティーノ作品を挙げるとすれば、『パルプフィクション』よりも『フロム・ダスク・ティル・ドーン』(脚本・出演)だろうか。『フロム〜』で意味もなく続けられる大量殺戮スプラッターシーンと、本書で脈絡も意味も無く発生するエログロバイオレンスとの間に大きな違いはない。
というわけで、喩えとして挙げた、筒井康隆のスラップスティック、タランティーノやピーター・ジャクソン作品が好きな人は絶対に楽しめる……と思う(自信はないけど)。
(1999.2.7) (大野典宏)
ロシア東欧SF関連ニュースで紹介されている「ダーシェンカ展」に行った。
展示されている写真や文章のほとんどは本に掲載されているものばかりだが、チャペックの珍しい写真や資料、イラストの下書きなども(一部)展示されていた。「猫好き」ばかりがもてはやされるなかにあって、「犬好き」が趣味を満喫できる時間だったと言える。
ただ、「グッズ販売がある」と知った時点でわかっていたことだが、これはチャペックという作家と「ダーシェンカ」という作品を詳しく紹介するための展示会ではなかった。あまり広くも無い会場の半分が「ダーシェンカ」グッズの販売場になっているということからもわかるように、商品を売るための展示会だ。「チャペック没後60周年」は単なる理由でしかないのだろう。
別にこれが悪いと言っているわけではない。私も売られていたカードを何枚か購入したし、どういう形にしろチャペックの名前が広く知れ渡ることはファンとして嬉しい限りだ。チャペックが犬に対する愛情を込めて「ダーシェンカ」を作った以上、「可愛い」という評価は正当なものだし、それが現在において商品として十分に通用するということであれば、それはチャペックの才能に対する大きな評価である。
これをきっかけに「R.U.R.」や「山椒魚戦争」に興味を持つ人が増えれば万々歳なのだが、「ダーシェンカ」だけがチャペックであると誤解されるようなことがあるとしたら、それはあまりにも勿体ない話だ。
(1998.10.4) (大野典宏)
本書は、ロシアの科学者・作家に広い影響を与えたコスミズム−−宇宙主義の中心的な人物であり、ロケットの祖であるツィオルコフスキイが師事したニコライ・フョードロフの生涯と思想、影響などをわかりやすく紹介した本である。昨年出版された同じ著者による「ロシアの宇宙精神」(せりか書房)は、コスミズムの概論と論文が収録された総合的な入門書と言えるものだったが、残念ながらわかりやすいとは言えなかった。しかし、本書の翻訳は読みやすく、内容の理解に専念できる。目次を見る限りはツィオルコフスキイの文章などが収録された「ロシアの宇宙精神」のほうがお買い得なのだが、理解するためには本書の方が適している。
コスミズムは多くの作家に影響を与え、特にプラトーノフやドストエフスキイといった作家たちに大きな影響を与えているという。恥ずかしい話だが、昨年「ロシアの宇宙精神」(せりか書房)が出版されるまで、ロシアにこのようなオカルト思想が存在したことすら知らなかった。
だが、よくよく考えてみると、SF作品の中に肯定的/否定的にかかわらず、似たような考え方が見え隠れてしている。もともとコスミズムは宗教的な要素の強いオカルト哲学だが、宇宙開発に関する思想でもあるため、SFに与えている影響は少なくないはずである。事実、「ロシアの宇宙精神」が出版された後、ロシアのSF作家数人に意見を求めてみたのだが、皆それぞれに肯定・否定が混じりあった複雑な返答が戻ってきた。
コスミズムがSF作品に大きく影響している発想を荒っぽくまとめると次のようになる。
1.空間的限界の克服−−地球的な束縛を解消するための宇宙への移住
2.時間的限界の克服−−不死の達成と復活の実現
空間的な限界の克服とは、宇宙開発や惑星移住に直結する発想である。だが、話はそれだけに留まらず、宇宙での活動、そして不死性を実現するために、器官の拡張−−手足の人工的な延長とも言える「道具の使用」にとどまらず、人間そのものの変容を唱えている。前者については何の問題も感じないが、後者については個人的な意見を述べさせてもらうなら、到底受け入れられる発想ではない。
話は変わるが、かつてロシアのSFファンから「宇宙移住のための人体改造案」について話し合いたいという申し入れを受けたことがある。その時には馬鹿なことを言っているとしか思えなかったため、その旨を正直に伝えたのだが、今から思い返してみると、これはコスミズムの影響を受けた発想そのものであり、ロシア人の中にコスミズムの発想が深く根付いていることの証左でもあったのだ。その前提をわかった上で、コスミズムについて議論するのであれば無駄な話にはならなかったのかもしれないと後悔し、自分の不明を恥じている次第である。
十九世紀の当時からすれば「未来哲学」として非常に先進的かつ過激な思想として、他を牽引するだけの魅力はあったのだろうし、それだけでも存在意義は十分にあっただろうと思う。だが、私の価値観からすれば、かなりバカげた考え方としか言えないし、今の時点でこのようなことを唱える人がいたとしたら「妄言」の一言で片づけてしまうだろう。
しかし、ロシアSFの理解には必須だと思われるし、人によって肯定的にせよ否定的にせよ、ロシア人の根元的な思想のある部分を担っていることが明白である以上、避けては通れない課題であることだけは事実である。
そういう意味では、ロシアのSFファンとコスミズムについて語り合えなかったことは後悔しているが、そのSFファンが本当に議論したがっていた「肉体改造」について、議論に参加することなどは永久にありえないだろうという確信は今でもある。
(1998.9.25) (大野典宏)