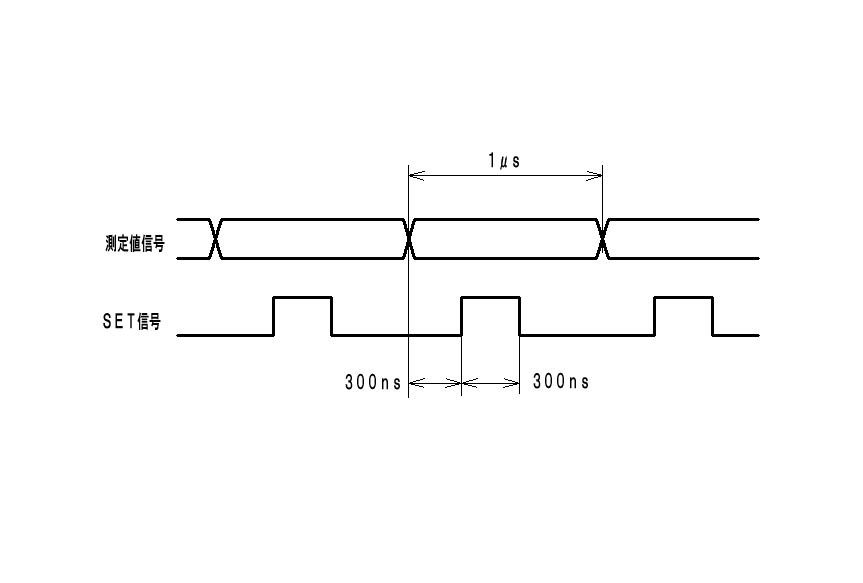
HV400
”リアルタイムでの測定量デジタル出力”
機能詳細
測定中であれば、リアルタイムでの測定量をデジタル出力します。
デジタル出力端子より、1μs間隔で出力されます。
HV400のフロントパネル上のデジタル出力端子は40ビットで次のような構成です。
| コネクタ出力端子番号 | 信号名 | データ内容 |
| 1 | SIG[31] | 変位量または速度32ビットの最上位ビット(=第32ビット、MSB) |
| 2−31 | SIG[30]−SIG[1] | 変位量または速度32ビットの第31ビットから第2ビットまで |
| 32 | SIG[0] | 変位量または速度32ビットの最下位ビット(=第1ビット、LSB) |
| 33 | HVS | 変位量(=1)、速度(=0)指定信号 |
| 34 | PVS[2] | 信号の小数点位置を3ビットで表現する際の最上位の第3ビット、MSB |
| 35 | PVS[1] | 信号の小数点位置を3ビットで表現する際の第2ビット |
| 36 | PVS[0] | 信号の小数点位置を3ビットで表現する際の最下位の第1ビット、LSB |
| 37 | ENA | 出力ON(=1),OFF(=0)指定信号 |
| 38 | SET | データ出力の出力開始信号、0.3μs信号幅 |
| 39 | GND | グラウンド |
| 40 | GND | グラウンド |
この信号を読み出すことの出来る、PC及びPC接続ボードをご利用ください。。
<変位量の場合>
変位量を出力します。32ビットをnmを基準に、整数部と小数部に分けます。それを、(整数部ビット数+小数部ビット数)と表現します。
例えば、(24+8)、は整数部24ビット、小数部8ビットです。したがって、上限値があり、分解可能値があります。
上限値を超えた場合、または下限値を下回った測定値は正しく表示されません。
| 倍率 | 整数部、小数部ビット数 | 上限値(絶対値) | 分解可能値 | [nm]以下を表現するビット数 | PVS[2..0」表示 |
| S1 | (28+4) | 268mm | 0.0625nm | 4 | B”000” |
| S2 | (26+6) | 67mm | 0.0156nm | 6 | B”001” |
| S3 | (24+8) | 16.8mm | 0.00391nm | 8 | B”010” |
| S4 | (22+10) | 4.194mm | 0.000977nm | 10 | B”011” |
注意;分解可能値を小さくして意味がない、とご指摘を受けるかもしれませんので、説明させていただきます。
たっったひとつのデータを用いる場合には、確かに意味はありません。しかしながら、複数の点の平均を用いる場合、これらの要素が影響します。例えば、1ms間のデータの平均を求める場合、1000個の平均となります。210=1024、からお分かりかと思いますが、小数部ビットが平均値を変更させる力を有します。そこで、小数部ビットを大きくとっている次第です。
<速度の場合>
速度値を出力します。変位量と同様に、整数部と小数部で表現します。単位は、μm/s、です。
| 倍率 | 整数部、小数部ビット数 | 上限値(絶対値) | 分解可能値 | [nm]以下を表現するビット数 | PVS[2..0」表示 |
| V1 | (28+4) | 268m/s | 0.0625μm/s | 4 | B”000” |
| V2 | (26+6) | 67m/s | 0.0156μm/s | 6 | B”001” |
| V3 | (24+8) | 16.8m/s | 0.0039μm/s | 8 | B”010” |
| V4 | (22+10) | 4.194m/s | 0.000977μm/s | 10 | B”011” |
測定値信号とSET信号の時間的関係は下図のようになります。LVTTL(3.3V)信号です。
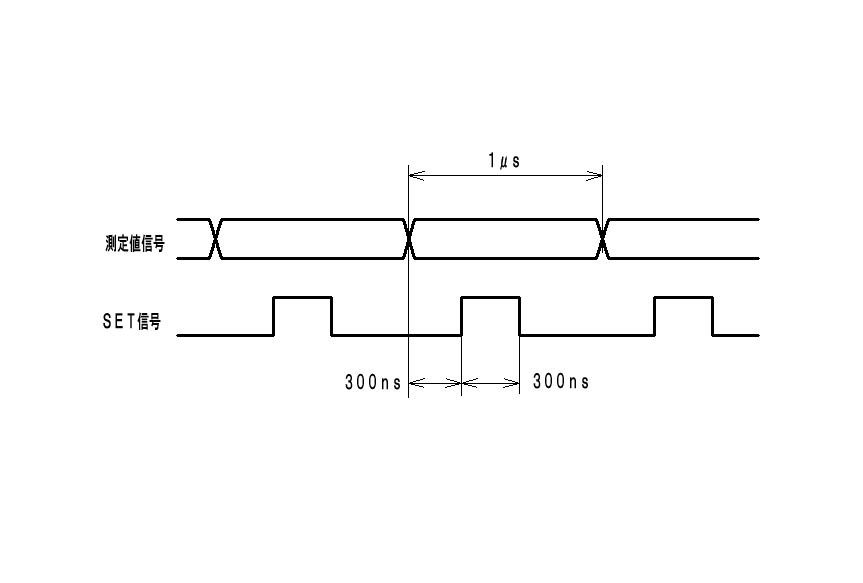
”光で物理量を高精度に計測”
お問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。
株式会社フォトンプローブ 代表取締役 理学博士 平野雅夫
TEL 048−538−3993 本社
電子メール photonprobe@asahinet.jp
注意;2020年5月より、本社を移転しています。
旧本社の電話番号は使用できません