
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 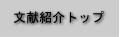     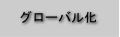
  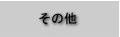
モダニティの社会学
今村仁司(1994)『近代性の構造』 講談社選書メチエ
近代における人々の世界観をとても分かりやすく解説しています。近代に特有な時間概念や機会論的な世界像などを理解するのに非常に便利でしょう。また、そうした抽象的な議論にとどまらず、(私にとっては)斬新なナショナリズム論が展開されており、非常に面白く読めました。また、哲学の世界では常識なのかもしれませんが、ヒューマニズムに対する批判なども新鮮でした。いろいろな思想家の思想が紹介されており、知的好奇心を刺激してくれる本です。 (1997年)
ヴェーバー・マックス、大塚久雄訳(1920=1989)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
岩波文庫
社会学の名著中の名著。通称『プロ倫』として親しまれ、社会学を本格的に学ぼうとするならば、必ず誰もが読む一冊でしょう。が…、これが意外としんどい。プロテスタントの宗派や教義を詳細に論じている箇所なんかは読んでいても結構つらいものがあります。とはいえ、いかにプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神とが親和性を有していたのかについての説明はやはりエキサイティングであり、「鉄の檻」としての資本主義など著名なフレーズも数多く登場します。ただし、『プロ倫』の解釈については結構難しいところもあるらしく、あんまり細かいこと書くと怒られそうなので、ここらへんで止めときます。(1997年)
鹿島茂(1991)『デパートを発明した夫婦』講談社現代新書
一般に「消費社会」とは、「必要性」に基づかない消費によって経済が動いている社会のことを言います。たとえば、衣服の最も重要な機能は、寒さから体を守ることです。けれども、現代では「暖かさ」や「動きやすさ」といった機能面だけで衣服を選ぶ人はあまりいません。そこでは、その服が流行にマッチしているかが重要なファクターとなるわけです。
実際、もし仮に、人びとが機能面だけで毎日着る服を選ぶのであれば、季節ごとに数着あれば何年ももってしまいます。しかし、流行というものが存在するがゆえに、人びとはまだまだ着ることができる服を捨てて、新しい服を買うことになります。いわば、流行のおかげで資本主義を回転させる大量消費が実現されているのです。
以上は消費社会論のありふれた解説ですが、人びとはそうした消費社会の論理にいきなり馴染んだわけではありません。それどころか、資本主義の力点が「生産」から「消費」に移っていく過程で、消費の仕方というものを教え込まれる必要がありました。そのための教育の場として、重要な役割を果たしたのがデパートなのです。
本書は、世界最初のデパートであるフランスの<ボン・マルシェ>を生み出したブシコー夫妻の生い立ちから経営戦略までを描いた著作です。この著作では、消費社会の基本的な論理から、経営戦略、従業員の管理や福利厚生までが論じられ、ブシコー夫妻がどのように現代的なデパートの原型を築きあげていったのかが論じられています。そして、この著作で興味深かったのが、次の一節です(p.106)。
「…<ボン・マルシェ>の年間大売出し暦は、ある意味で典型的な教育的配慮に基づいていた。すなわち、たとえば夏物だったら、そのシーズンの流行を実際の時期よりも数ヶ月早く教育を開始し、それに答えられる生徒には真っ先に流行の最先端の商品を売ってやる。…反応の鈍い生徒もいるから、こうした生徒には、徐々にレベルを下げていって、最後にはどんな愚鈍な生徒にも、全員に流行の品がいきわたるようにしてやる。」
流行に敏感でその最先端にいることにお金を惜しまない層には、高い価格で商品を売りつける。他方、そこまでお金を支払う余裕がないものの、流行からは取り残されたくない層のためにバーゲンが実施される。要するに、バーゲンとは、消費社会の学校の「落ちこぼれ」のための「救済措置」として始まったというのです。もちろん、バーゲン価格では採算が取れなかったとしても、流行から遅れたものを在庫として持っておくよりはましだという経営判断もそこにはあるわけです。
つねづね、デパートの暦というのは、実際の暦となんであんなにずれているのだろうと昔から疑問に思っていたのですが、その疑問も氷解しました。
これ以外についても、消費社会の論理を考えるうえで非常に参考になる著作だと思いますので、興味のある方は是非読んでみてください。
ギデンズ・アンソニー、松尾精文ほか訳(1990=1993)『近代とはいかなる時代か?』而立書房
近代を可能にしたものとは一体なにか、近代の特性とは何か。これらの問いと中心にして、近代という時代の姿を社会学の観点から解き明かしているのが本書です。著者であるギデンズは現代イギリスを代表する世界的な社会学者です。ギデンズは現代をポスト・モダンではなく、近代の延長線上にあるハイパーモダンの時代であると位置づけ、その展望について考察を加えています。実は一回目に読んだ時にはさっぱり理解出来なかったのですが、二回目に読んだときには、かなり理解することができました(それでも、わからないところがあるのですが)。全体としては非常に興味深い著作で、現代社会学を語るには欠かせない一冊と言えるのではないでしょうか。(1997年)
ギデンズ・アンソニー、松尾精文・松川昭子訳(1992=1995)『親密性の変容』而立書房
国民国家やグローバリゼーションなど社会のマクロ的な側面に関する著作の多いギデンズとしては珍しい、性愛やセクシュアリティなどミクロな側面を扱った著作。とはいえ、ギデンズのモダニティというモチーフは一貫していて、脱伝統化がすすむ近代社会において人間関係がどのような変化を遂げてきたのかを論じています。また、そのような新しい人間関係が社会のよりマクロなレベルでの民主化に結びつきうるのだという主張にも、ギデンズの大局的な視点を見ることができるように思います。ところで、ギデンズはこの著作で、現代の結婚関係が、富や権力を目的とするのではなく、結びつきを維持することそれ自体を目的として形成・維持されるようになっている(純粋な関係性)と論じています。言わば、結婚の脱手段化あるいは目的化という事態を指すわけですが、これはこのページの別のところで紹介している大平健さんの『純愛時代』の問題意識と関係するのかなぁ、などと思いました。(2004年2月)
佐藤俊樹(1993)『近代・組織・資本主義』 ミネルヴァ書房
西洋における「近代」と、日本における「近代」。この二つの「近代」のあり方をヴェーバーの理論を足がかりに論じた、大変に刺激的な著作です。佐藤さんはまず、ヴェーバーの理論に対する独自の再解釈を行ったうえで、組織の合理性と個人の合理性との分離、近代的自我の成立、西洋における「自由」および「公共性」と日本におけるそれらの相違などのテーマについて議論を展開していきます。本書は1993年に出版されたのですが、その後のオウム事件の発生や日本的経営の崩壊などについて参考になる見解がすでに提示されており、本書の有用性を裏付けていると言うことができるのではないでしょうか。(2002年12月)
田口富久治(1994)『近代の今日的位相』
平凡社
アンソニー・ギデンズの理論を軸として、近代とは何か、それは今日にあってどのような状況にあるのかを論じている本です。ギデンズの入門書、と言いたいところなのですが、内容は決して平易ではなく、ギデンズの入門としては、ギデンズ自身の『社会学(改訂新版)』(而立書房、1993)の方がよいでしょう(原書では、第3版が出ているようですが)。注意しておかなくてはならないのは、この『近代の今日的位相』とギデンズの著作の邦訳とは、若干、ギデンズ用語の訳が異なるところです。例えば、「再帰性(reflexivity)」が「反省性」となっていることが挙げられます。この著作は、ギデンズの理論が社会学・哲学・政治学においてどのような位置にあるのかを知るのによいのではないでしょうか。(1997年)
富永健一(1996)『近代化の理論』 講談社学術文庫
近代とはいかなる時代であったのか。社会学の永遠のテーマであるこの課題に、著者は社会変動論的な観点からアプローチしています。西欧のみならず、日本や中国などの近代化にも触れた力作。また、歴史的な事象にとどまらず、情報化やポスト・モダンといった現代的な概念もわかりやすく整理されています。内容構成に筋が通って、文章も分かりやすく、さすがに日本社会学の大御所の風格を漂わせています。ちなみに、私はこの本でパーソンズのAGIL図式の概略を理解した(つもりです)。ところで、パーソンズの本って、入門書も含めてなんであんなに難しいのでしょうか…。 (1997年)
バーガー・ピーター、園田稔訳(1967=1979)『聖なる天蓋』 新曜社
現象学的社会学の観点から宗教のメカニズムについて論じた本です。バーガーの本は基本的に読みやすいと思うのですが、本書も例外ではありません。宗教というものがいかに人間の認知構造を規定してゆき、またそれによって宗教が再生産されてゆく過程が明確に理解できます。バーガーは近代を世俗化の過程として論じてゆくわけですが、近年のカルト宗教の流行、あるいは原理主義の台頭などの現象を見るのにも本書の枠組みは大いに役立つことと思われます。さらに言えば、ナショナリズムなんてのも一種の世俗宗教なわけで、こうした極めて近代的な現象の理解にも有用なのではないでしょうか(バーガーの趣旨からは外れることになりますが…)。(1998年)
バーガー・ピーターほか、高山真知子他訳(1973=1977)『故郷喪失者たち』新曜社
近代人の意識と、伝統的な社会に暮らす人々の意識とは何が異なるのか。「意識の複数化」という観点から、近代人の意識の特質を明らかにしてゆきます。単純化して言えば、伝統的な社会に暮らす人々の生き方が一つであったのにたいし、近代人の生き方は様々であり、絶対的に優れた生き方が存在しえないがゆえに、近代人のアイデンティティは常に不安定となっている、というところでしょうか。こうして書くとあまり面白くないと思われるかもしれませんが、特に中盤から後半にかけては非常に刺激的な分析がなされています。お勧めの一冊です。(1997年)
ハーバーマス・ユルゲン、細谷貞雄・山田正行訳(1990=1994)『公共性の構造転換 第2版』 未来社
近年のメディア研究においては、「公共圏」に関する議論がさかんに行われいますが、その出発点とも言えるのがこの著作です。正直、あまりにも頻繁に目にするため、僕としては「公共圏」という言葉を聞くだけで「またか」と思ってしまうほどだったのですが、実際にこの著作を読んでみると、思っていたよりもずっと楽しく読むことができました。近代初期における「市民的公共圏」の成立と、その変容、そして再封建化の進行が、様々な分野の研究を土台として論じられています。特に、第6章以降のジャーナリズムや広報に関する議論は、マス・メディアの発展過程に興味を持っている人であれば、必読と言ってもいいでしょう。もちろん、この第2版の「序言」ではハーバーマス自身がこの研究の問題点を認めており、また『公共圏とコミュニケーション』でも論じられているように、多くの研究者がハーバーマスの見解を批判しています。しかし、それらの批判を踏まえたうえでなお、読んで損のない著作と言えるのではないでしょうか。(2003年5月)
ハーバーマス・ユルゲン、川上倫逸ほか訳(1981=1985)『コミュニケイション的行為の理論(上)』未来社
ハーバーマスによる大著の前半3分の1の翻訳です。全部読んでからだと内容を忘れてしまいそうなので、とりあえず上巻の感想をば。上巻の前半部分では、合理性という概念の検討が行われ、後半ではヴェーバーによる合理化に関する議論の批判的なレビューが行われています。まぁ、細かい話はしませんが(と言うか、できない)、一言で言えば、非常に難解です・・・。後半についても、ヴェーバーの研究についての知識をかなり持っていないと理解は難しいのではないでしょうか。合理性だけでも何種類もの類型が出てくるので、それらをきちんと把握していないと、混乱するばかりです。
無理やりにまとめてしまうと、ハーバーマスは、普遍的なコミュニケーション的合理性というものが重要であって、ヴェーバーの合理性に関する研究にはそれに対する視点が欠けている・・・と言いたいのでしょう、多分。そうそう、ごく最近、未来社から新装版が出ている様子。箱入りのバージョンで上巻と中巻を持っている僕は少々危機感を覚えています。箱入りの下巻が売り切れになるまえに入手しなければ。(2003年8月)
ブルデュー・ピエール、原山哲訳(1977=1993)『資本主義のハビトゥス』 藤原書店
ブルデューの初期の作品で、彼の著作としては極めて読みやすい部類に属すると思われる著作です。本書では、資本主義に特有のハビトゥスを途上国(アルジェリア)の人々が身につける困難性について分析がなされています。ハビトゥスとは、正確さを犠牲にして言えば、構造によって規定される価値意識や行動様式と言えるでしょうか????(うぁー、すごく問題ありそう)
例えば、資本主義的な社会に生きてゆくためには、特有の時間感覚を身につけなくてはならないのですが、そうした感覚は馴染みのない人々にとってはなかなか身につけられないものなのです。また、本書の最後の部分では、後年の文化的再生産の概念が紹介されており、文化的再生産の理論の基礎を学ぶのにも良いのではないでしょうか。 (1997年)
フロム・エーリッヒ、日高六郎訳(1941=1951)『自由からの逃走』 東京創元社
ナチズムを可能にした心理とは何か?筆者は本書において、近代社会における「自由」の困難さについて論じ、いかに人々がナチズムに惹かれていったのかを心理学的な観点から分析しています。ナチズム研究の古典中の古典であり、100刷を越えているという超ロングセラーでもあります。「自由」であることの難しさ、怖さ、そして素晴らしさを知る上では必読の文献と言ってよいでしょう。正直、読む前はあんまり期待していなかったのですが、かなり面白く読めました。フロム自身はアイデンティティという言葉をあまり使っていないようですが、アイデンティティ論としても読み直せる本ではないでしょうか。(2000年7月)
ベック・ウルリッヒほか、松尾精文ほか訳(1994=1997)『再帰的近代化』而立書房
近代を可能にした要因としてアンソニー・ギデンズが重視する「再帰性」概念を軸に、ギデンズを含む三人の筆者が政治、伝統、美的原理について論じます。ベックは政治がもはや政治家や官僚に限定される現象ではなく、社会のあらゆるところに見られるようになったということを、ギデンズは伝統が失われていく時代にあって人はいかに生きるかを論じています。ラッシュは…よく分かりません。あまりに難解で、理解出来ませんでした!(情けなや)私個人としては、やっぱり、ギデンズの論文が面白かったですね。ところで、この本で変わっているのが、三人の論文の後に、相互に批判しあう論文を載せているところです。特に、ギデンズのラッシュに対する批判は強烈です。これは、結構、面白い試みだと思います。共著だと、その著者の間で見解が違うことがよくありますから、そこらへんがハッキリして良いのではないでしょうか。(1997年)
|

