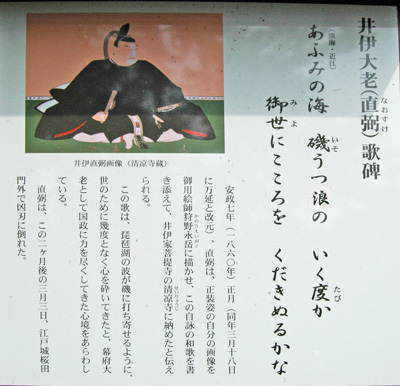|
|||||||||||||||||
| 2009年4月5日 | |||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
日本の木造建築は、法隆寺の建物群を見ても分かるように、その耐久力はすばらしいものがある。 少々害虫の被害にあってもその部分を修復すればさらに寿命は延び、人々の目を楽しませてくれる。 彦根城もその一つである。 彦根城は、江戸時代初期、現在の滋賀県彦根市金亀町にある彦根山に、鎮西を担う井伊氏の拠点として置かれた平山城(標高50m)である。山は「金亀山(こんきやま)」との異名を持つため、城は金亀城(こんきじょう)ともいう。 多くの大老を輩出した譜代大名である井伊氏14代の居城であった。 明治時代初期に馬鹿な役人が廃城令を出したが廃止を免れ、天守が現存する。 天守と附櫓(つけやぐら)及び多聞櫓(たもんやぐら)の2棟が国宝に指定されるほか、安土桃山時代から江戸時代の櫓・門など5棟が現存し、国の重要文化財に指定されている。中でも馬屋は重要文化財指定物件として全国的に稀少である。一説では、大隈重信の上奏により1878年(明治11年)に建物が保存されることとなったのだという。 国宝に指定されている城は5つあるが、この彦根城はその中でも遺構をよく残している。 城があるのでたくさんの観光客がくるが、彦根は街並みを昔の雰囲気で整備している。 ちょっと素材が新しいので物足りない感じは否めないが、コンクリ作りの四角な建物が並ぶよりはるかにいい。 ●二の丸佐和口多聞櫓(さわぐちたもんやぐら) 入口に向かって左側は、佐和山城から移築されたものという。 ●天秤櫓(てんびんやぐら) 羽柴秀吉の長浜城大手門を移築したといわれる。廊下橋を中心に左右対称に櫓が並び立つ姿が、天秤に似ていることからこの名が付いた。この櫓の形は彦根城だけといわれ、国指定の重要文化財。 ●太鼓門櫓(たいこもんやぐら) 本丸表口を固める勇壮な迫力を感じさせる楼門で、城中合図の太鼓を置いたことからこの名が付いた。釘跡が残っているのは、彦根寺楼門が移築されたためと伝えられているが、佐和山城か長浜城の城門を移築したものという説もある。 いずれにしても釘跡は移築前の建物の痕跡と見られている。国指定の重要文化財。 ●天守 牛蒡積(ごぼうずみ)みと呼ばれる石垣は自然石を使い、重心が内下に向くように作られ、外見は粗雑だが強固な造りという。その上に三重の天守が立っていて、規模は小さいが、屋根の曲線の調和が美しく荘厳な雰囲気がある。花頭(かとう)窓が配列されているのも特長の一つで国宝。 ●三重櫓 西の丸は、文庫が立ち並んでいたところだが、今は桜の木が植えれている。春には桜祭が行われ、花見の宴の客でにぎわう。国指定の重要文化財。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||
|
この日は青春18切符で彦根に来た。青春18切符での遠出はここ彦根あたりがちょうどいい。 城をみて、帰りに京都駅で食事をする余裕がある。 琵琶湖周辺の街は、様々な取り組みをして街の活性化につなげている。どこかの県も見習いたい。 少し盛りは過ぎていたが、それでも桜が人々の目を楽しませていた。あちこちで花見の宴が楽しそうであった。 驚いたのは、池の中を大きな雷魚が悠然と泳いでいたことである。たくさんの人がいても動じる感じはなかった。 博物館前が騒がしいと思ったら、彦根のゆるキャラの彦にゃんがやってきて愛嬌を振りまいていた。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <彦根城> 別名:金亀城 城郭構造:連郭式平山城 天守構造:複合式望楼型 3重3階地下1階(1604年築) 築城主:井伊直継 築城年:1622年(元和8年) 主な城主:井伊氏 廃城年:1874年(明治7年) 遺構:現存天守、 櫓、門、塀、馬屋 石垣、土塁、堀 <国 宝> 天守 付櫓及び多聞櫓 彦根屏風 <重要文化財> 太鼓門及び続櫓 天秤櫓 西の丸三重櫓及び続櫓 二の丸佐和口多聞櫓 馬屋 我宿蒔絵硯箱 (ウキペディアより) ▲ページトップへ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||