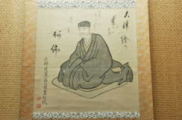義仲寺はJR膳所駅・京阪電鉄膳所駅にほど近いお寺である。 行く前から、その名前からして木曽義仲と由来がある寺だろうと思っていた。  やはり思った通りであった。 義仲寺の名は、平家討伐の兵を挙げて都に入り、帰りに源頼朝軍に追われて粟津(あわづ)の地で壮烈な最期を遂げた木曽義仲(きそよしなか)(1154-84)をここに葬ったことに由来しているという。 ここで討ち死にしたとは知らなかった。 源義仲(木曾義仲)の死後、愛妾であった巴御前が墓所近くに草庵を結び、「われは名も無き女性」と称し、日々供養したことにはじまるとも伝えられる。 戦国時代に荒廃したが、天文22年(1553年)頃、近江守・佐々木六角氏によって室町時代末期に再興したといわれている。 江戸時代中期までは木曽義仲を葬ったという小さな塚だったが、周辺の美しい景観をこよなく愛した松尾芭蕉が度々訪れ、のちに芭蕉が大阪で亡くなったときは、生前の遺言によってここに墓が立てられたと言われている。 今は普通の街中の寺となってしまっているが、目の肥えた芭蕉をして美しい景観ということは当時は湖が近くてきれいなところだったのだろうと想像した。 境内には、芭蕉の辞世の句である「旅に病て夢は枯野をかけめぐる」など数多くの句碑が立ち、芭蕉の足跡を忍んで多くの人が訪れるという。 拝観受付の隣に小さな史料館があり、芭蕉や義仲に関する遺物が展示されていた。 このほか、本堂の朝日堂(ちょうじつどう)・翁堂(おきなどう)・無名庵(むみょうあん)・文庫などがあり、境内全域が国の史  跡に指定されている。翁堂には芭蕉の坐像があり、中央に芭蕉、左右に弟子の俳人、丈艸と去来の像が安置されている。 そして天井には伊藤若冲の描いた天井画が15面ある。 跡に指定されている。翁堂には芭蕉の坐像があり、中央に芭蕉、左右に弟子の俳人、丈艸と去来の像が安置されている。 そして天井には伊藤若冲の描いた天井画が15面ある。無名庵で句会も盛んに行われた。 大坂で亡くなった芭蕉だが、「骸(から)は木曽塚に送るべし」との遺志により義仲墓の横に葬られたという。 又玄(ゆうげん)の句「木曽殿と背中合わせの寒さかな」が有名。 その後、再び荒廃したが、京都の俳僧蝶夢が数十年の歳月をかけて中興した。 昭和期には、敗戦後に再び荒廃壊滅の危機に瀕するが1965年(昭和40年)に再興され単立の寺院となった。再建に尽力した三浦義一氏と文芸評論家保田與重郎氏の墓所でもある。 境内にはいろんな花が咲いていた。
|
||||||||||||||||||||||||||