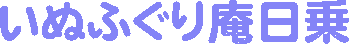
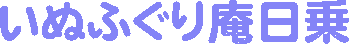
朝、とある大きな図書館で少し調べもの。やはりこの図書館の案内板はわかりにくい。1階の一般書と2階の一般書の関係はどうなっているのだろうな、などということが普通の利用者にわかるのかな。何の予備知識もないひと、を前提にしてない気がする。司書が使ってわかりにくい、というのではまずい。かなりましにはなってきたけれども。特に2階。今回はレファレンス探検隊のコメンテイター関連のあれこれを調べるために出かけたのだが、自然科学と人文科学とにまたがる調べものとなり、人文科学の図書の場所はだいたい把握しているのだが、階全体ではどういう書架配置になっているのかの見通しがついていなかったため、2階全図のようなものがないかと探したのだが見つからない。どこかにあったのだろうか。毎日働いているひとは当然わかっているのだが、たまにゆくひとはわからない。1階がわかっているひとは2階がわからないし、2階の参考資料を使いにいってそこの把握ができても、次に一般書を探しにゆくともうわからない。これでは困る。
グランパス対大分トリニータを観にゆく。瑞穂陸上競技場。0対3。金正友と本田がとても良かった。大分は汚いところのあるチームであったが、審判が取らない(取れない)ので見ていてストレスがたまった。しかし強いことも確かである。
友達の荻窪圭がwinnyについて書いている。私も同感である。開発者が逮捕されたとき、ならばコピー機や写真機を作った人も犯罪者だし、携帯電話で写真が撮れるようにした人などは極悪人だ、と私は感じたのだったな、と思い出した。我が国民は全部ひとのせいにするのが好きで、皆が動くように動いていれば安心ができ、いけないことかも知れないと心のどこかで思っていても、みんながしているんだからいいや、と悪いことでもしちゃうのであるから、物理的にできないように働きかける方法はきっと正しいのではあろうが、物事を考えない人たちがそれで増えてゆくのである。
我が国から遠く離れた国の住民の多くが我が国はアメリカに良い感情を抱いていない、と考えているらしい。原爆を落とされて無辜の市民を空襲であれだけ殺されているのに数十年でアメリカに対する恨みがすっかりなくなっている国の存在を信じられる人は多くない気がするのだが、あるのだから不思議である。平和ボケという言葉があるが、そもそもボケている国民なのである。第二次世界大戦が起きたのは軍部など一部の人たちが悪くて巻き込まれた国民は被害者である、との意識が強かった。自分たちで止めることは到底無理な話であった、という話はよく聞く。確かに拷問を受けたりなんだりしてまで戦争を止めようというのは大変な事柄で、私もしないような気がする。でも、イタリアではファシズムへの抵抗運動があったのだよな。それで命を落とした人は今も称えられてい。自国が為そうとすることに反対した国民が命がけで戦った歴史があるのである。大きな流れを疑う国とそうでない国との差はどこで生じるのだろう。winnyを使ったために情報を流出させてしまった人よりもwinnyを作った人がいけない、winnyが存在するのがいけないとばかり言っている状況から様々なあれこれを思う私である。楽して違法コピーをしよう、と考える性根の卑しさについて目を向ける人があまりに少ない気がする。
異動の内示が出た。4月から図書館に戻ることとなった。3年間続けた「いぬふぐり庵日乗」を今月いっぱいで終え、「図書館員日記」を再開する。
新しいドメインhttp://www.inufuguri.jp/を取得したので4月からはこちらに移ろうと思う。
PSE法、中古家電製品については販売を結局経済産業省が認めることとなった。まずはめでたいのだけれど、5年前、一体何がしたかったのであろうか。官報をこまめに確認してゆかないとどんな法律が通ってゆくかわかったものではない昨今である。
作曲家の宮川泰さんが亡くなった。ピーナッツの『ふりむかないで』や『恋のバカンス』、『銀色の道』などで知られたひと。黛敏郎の『題名のない音楽会』で年末に紅白歌合戦のパロディのような番組を放送していた頃、その審査員をつとめていて、このひとがやたらと面白かった記憶がある。息子さんの作曲家、彬良さんも個性的で、ああさすがに親子だなあ、と、教育テレビを楽しく観ていたりする私である。ご冥福をお祈りします。
金融会社のテレビCM自粛は変な気がする。そもそもCMというのは何もしなくても売れるわけではないものを売ったりするために莫大なお金をかけて流しているわけで、その合間に番組を放送しているのだから、青少年に害毒を流す類のものでなければ放送すれば良いのではあるまいか。金融会社でお金を借りることができるのは法的には分別がついている人たちである。借りるか借りないかは、商品を買うか買わないかと同様本人の意思による。さまざまな過保護が国民をだめにしているのではないだろうか。それよりも問題にすべきは、宗教団体が出している雑誌の広告を大新聞に載せたり公共交通機関の車内に吊ったりしていることではなかろうか。ものすさまじい勢いで日陰にあったあれこれが日向に出てきていて、それで構わない、と多くの人が思っているのか何も考えていないのか、とんでもなく変梃な状況になっている我が国。
グランパス対鹿島アントラーズ戦を豊田スタジアムへ観にゆく。豊田ではアントラーズに強いグランパス。後半3分、金正友が退場になったあとからかなりスリリングな試合展開となった。スコアレスドローに終わったが、今後に期待ができるような気分になった私。しかし、このところ出かけると雨降りになることが多いのはなぜであろう。
スタジアムへ出かける車のなかのラジオから『夜空ノムコウ』が流れていた。「このままどこまでも日々は続いていくのかな」というところがなんだか怖かったのであった。帰りにはラジオからユニコーンの名曲『素晴らしい日々』が流れていた。
京都に出かけたのだから、と北野天満宮にゆく。牛だらけで楽しい。梅が香っていた。30年ぶりに金閣寺にも行った。金色がきれいになっていて驚く。くすんだ色だった記憶が鮮明に蘇る。30年などあっという間のような気がする。
生方則孝さん達のライブが京都アンデパンダンであったのを観にゆく。生方さんはグランドチェロという六弦のチェロと、コルグのシンセサイザーとテルミン、冷水ひとみさんが1オクターブを43に分けた微分音オルガン、市橋若菜さんがオンド・マルトノ、という編成のトリオ。平均律でない音楽。ほとんどがオリジナル曲。脳味噌がどこかへ飛んでいって泳いで帰ってくるかのような不思議な心地よさ、美しさ。緊張と緩和が繰り返されるとても素晴らしいライブだった。演奏終了後、生方さんに、「トリップしそうな気持ち良い音楽ですね」と言うと、「演奏しているのは地獄。この音がずっと頭のなかで鳴っているの。微分音に慣れてしまうと、平均律の音楽が汚く聴こえてくる」とのこと。おっかない世界である。オンド・マルトノという楽器、名前と音は知っていたが、なんとも大時代でかっこいい電子鍵盤楽器であった。
朝の6時から名古屋テレビで放送されていた『テレメンタリー2006「海にすわる-沖縄・辺野古 反基地600日の闘い-」』を観る。一旦、日本国は諦めて撤退しているのだなあ。アメリカのいいなりの政権であることがよくわかる。アメリカは1966年からキャンプ・シュワブをつくろうとしていたのか。アメリカ領であったその頃と違い、今ならば日本のお金(税金であるが)で基地をつくってもらえるわけで、さぞやたのしかろうなあ。こうした番組はゴールデンタイムに流すべきなのではあるまいか。ここ数年、テレビ、新聞が怪しいのだが、変な時間帯には志のある番組を放送したりしているようである。観るひとがあまりいないのが難だが。
『シリアナ』を観る。ジョージ・クルーニーがアカデミー助演男優賞をとった映画であり、アメリカの暗部を描いた作品とのことで興味を持った私。めまぐるしく画面が変わり、展開がわかりにくかったり、必然性のない話や、それは無理ではなかろうか、といった事柄があったりしたが、面白い映画であった。アメリカはしかし、世界各地に進駐したくてしかたがない国であるなあ。
木村元彦の『オシムの言葉』が面白かったので、三部作の第一部『誇り』と第二部『悪者見参』も読んだ。ストイコビッチのプレーに魅せられた著者が、旧ユーゴスラビアのサッカーをめぐるあれこれを取材し、構成した作品。私はあの国のあれこれをちっとも知らなかったのだな、としみじみ思った。名著である。
国会図書館が出している『カレント・アウエアネス』によると>公共サービスの市場化テストが法制化されるとのこと。これって大きく報道されていたっけ。官民競争入札、という方法が取り入れられるそうな。文化施設への影響も当然あるが、税金の徴収や、住民票、戸籍謄抄本の発行も民間企業でできないかも検討するそうな。個人情報保護法があるから大丈夫、と大勢が考えるのかな。住基ネットワーク、民間業者による住民票発行、税金徴収という動きは大丈夫か。すでに住民票や戸籍謄抄本の発行をNPOに委託している小さな町があったりするようだけれども、本来公印の取扱は公務員が行うことになっているわけで、電子認証であるから赤いハンコではないけれど、受け渡しはともかく、発行についての委託は現在時点では法的にまずいし、これが緩くなってくれば、いくら契約をしていたとしても、だらだらゆるゆるになるのではないか、と危惧するのは私が公務員であるからなのであろうか。一応、普通の公務員は、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、という感覚がいっぱい身体に貼りついている。税金を頂戴して仕事をしているのであるから、並の神経の公務員はそんなふうである。例外的な事件があちこちで起きていて、そちらばかりが報道されているので、公務員はろくでなしばかりのように思われているし、実際にそんな公務員もいたりはするが、大半は何かをするとき内なる規制が働く人種なのである。そうした、公僕であるからまずいことはしないぞ、との感覚が元々ない人たちが企業のためこっそりとバレないように、といろいろできるのであればあれこれしちゃう可能性の検討、なんてことはこの法案が通ってゆくときにされないのであろうな。気づけば国民は丸裸にされてしまうかもしれない。アメリカのお犬さま達の作る法律によって、治安維持法なんて敷かなくても巧妙に国民を囲い込んだりできるようになってお国にとって安泰な状況が簡単にできそうな気がしてしまうのは私の深読みであろうか。おっかない事態が目の前にやってきているのではあるまいか。
ウディ・アレンの『僕のニューヨーク・ライフ』を観る。ストーリーにゆるいところがあって、なんとなく私にとっては今ひとつではあったが、ウディ・アレンらしい作品。アダムス・ファミリーのクリスティーナ・リッチはとても良い女優になったな、としみじみ思った。ジェイソン・ビッグスが客に向かって話すときの感じが良かった。ダニー・デピートは随分太った。ウディ・アレンはもしかすると、ユダヤ人とナチの話を撮ろうとしているのではなかろうか、とふと感じたのは私だけであろうか。
良い天気の開幕戦。セレッソになんとか勝った。古賀のヘディングシュートも見事だったし、玉田から杉本恵太へのパスからシュートも美しかったし、豊田陽平はディフェンスをうまくかわした綺麗なシュートであった。ディフェンスに課題はあるが、去年とは見違えるようなチームになりそうな予感。
久世光彦が亡くなった。この人の名前をはじめて意識したのは『時間ですよ』。女風呂のシーンが男の子たちの間で話題となり、毎週楽しみに観た。沢田研二が三億円犯人を演じた『悪魔のようなあいつ』も久世さんの演出で、コメディのひとだと思っていた私は驚いたのだった。沢田研二主演といえば、2001年に久世さん演出の『いつかヴァスコ・ダ・ガマのように』を名古屋に観にいったとき、うしろのほうに久世さんが腕組みをしていて、実にかっこよかった。
仕事場近くの喫茶店へ昼ご飯を食べにゆき、雑誌「ブルータス」を読んでいたら、久世さんのエッセイが載っていて、そこに私の好きななかにし礼の詞について書かれていた。これが彼の文を読んだ最初。美しい文章と鋭い目を持ったひとであるな、と感じた私。のちに函入のきれいな本『昭和幻燈館』(晶文社)となった。『一九三四年冬-乱歩』には圧倒された。ことに、この小説のなかで、乱歩が書いた小説として書かれた『梔子姫』は乱歩以上に乱歩。当時勤務していた館の図書館だよりですぐにとりあげた記憶がある。幾人かの友達にこれはすぐに読むべきだ、と騒いでいた私。久世さんの『卑弥呼』のなかに川上さんが描かれていますよ、と川上弘美さんにお話しし、『一九三四年冬-乱歩』の話をしばらくしたこともあった。最近では週刊新潮での森繁久彌さんの大遺言書を楽しみにしていたのだけれども。ご冥福をお祈りいたします。
藤枝市まで電車とバスで三時間ほどかけて、ジュビロ磐田対グランパスのプレシーズンマッチを観にゆく。大雨。良い席のチケットを買えたと喜んでいたのだが、前のほうは屋根がない。弁当を買って、通路にビニールを敷いて食べる。乞食の気持ちが少しわかる。ゴミをどこに捨てるのかを尋ねると持ち帰ってほしいとのこと。席においておくと水浸しになるのだが、なんとかするほかない。デイパックを背負ったまま、ポンチョを着、席に座ると、長さが足りず、尻に水がしみ込む。デイパックは膝の上に置き、そこにポンチョをかけることにする。雨降りのサッカー場ではやたらと仕事が増える。試合はサッカーとは思えぬものとなった。パスを出す。選手が走る。ボールが止まる。選手だけが走っている。実にシュールな光景。開幕に向けての調整の意味もある試合だが、これでは無理。それよりも怪我が怖い。ジュビロの西選手は足を捻っていた。中村直志からのパスに杉本恵太がゴールを決めた。前半が終わると雨はさらにひどくなっていた。あと45分だな、と思っていると、マッチコミッショナー等が協議をしているのでしばらくお待ちくださいとの放送。やがて選手が出てきて頭をさげていた。中止であった。寒く冷たい一日となった。
『ウォーク・ザ・ライン』を観る。ホアキン・フェニックスの出る映画はどうしてもリヴァー・フェニックスを思い出してしまうのだけれど、この映画は兄弟の話でもあって、重なってしまって変な感じだった。それにしてもジョニー・キャッシュの歌を見事にコピーしていた。リース・ウイザースプーンのジューン・カーターも良かった。ぞくり、とするシーンもあり、映画的な映画であった。しかし、私はどうもこの作品、好きではないのであった。お父さんが苦手なのか、キリスト教的倫理観が駄目なのか。多分そのあたりが原因なのでした。
生方さんのブログを読んでいたら電気用品安全法(ここは2ちゃんねるによるまとめ)の改正について書かれてていた。国民のほとんどが知らないぞ、これ。電化製品の中古品の売買ができなくなるのであった。 使い捨てを助長する法律だな。困ったことを考えるひとがありますな。なぜパソコンは例外なのだろう。不思議だな。LDプレーヤーが毀れたら中古品を買う予定でいるのだけれども、買えなくなっちゃうではないか。こそこそと国民に影響のある謎の法律ができている昨今の我が国。官報や省庁のページを毎日チェックせねばならないのであろうか。
首を寝違えた。夜になっても痛い。
昼休に川辺を散歩したら、オオイヌノフグリが咲いていた。たんぽぽも。春である。川では石亀の子が三匹浮いたり沈んだり。
『博士の愛した数式』を観る。原作では淡々と描かれていたところをくっきりさせてしまったのは失敗だったのではあるまいか、と私は思った。映像はきれいで、深津も良かったが、80分はかなりどこまでも長い時間であったりするのかな、と感じたり。小説もリアリティが薄かったが、映画ではもっと薄くなってしまっていた。おとぎ話だからしかたがないのかもしれないが。どうもファンタジーが苦手な私である。
バレンタインデーにまつわるあれこれを思い出す。
青山真治監督の『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』を観る。筋に無理がある気がした。映像はあいかわらず鋭いし、『ユリイカ』以来の宮崎あおいも良い。筒井さんの存在感がしっかり映っていた。戸田昌宏は邦画にかなり沢山出ているひとだが、この探偵役はとてもかっこ良かった。でも、変なところがいっぱいだった。宮崎あおいは大事な孫のはずなのになあ、とか、そういうところでのおかしさ。
出産へのプレッシャーが厳しすぎて、お加減が悪くなりはしないか、と心配になるのは私だけであろうか。男尊女卑反対運動論者の声があまり出てこないのが不思議。革新の党が男女同権の意味合いから彼に賛成する発言をしたらどうなってゆくのか、と想像すると少しわくわくするのだが、黙っているのは作戦か。しかし、今週の週刊文春に書かれていた電気をつけろ発言は事実なのであろうか。あろうなあ。ほとんど幼稚園児である。そんなひとがお参りして騒ぎを起こしているということか。やれやれ。
と、念のために調べたら賛成しているのですな。首相が法制改革で、あの党と論を同じうした例はあるのかな。
『有頂天ホテル』を観る。贅沢に役者を使った作品。今までの三谷幸喜監督のなかでは一番良かった。でもなんとなくまだまだ良くなったのではあるまいか、と欲張りな気持ちになった私。角野卓造が可笑しい。原田三枝子は脂っけが抜けて渋みが出てきている。若い頃のぎらぎらした雰囲気が苦手だった私。
『フライト・プラン』を観る。それは無理だろ、という話であった。予告編で良いところが出つくしているのではあるまいか、との予感が当たってしまった。
『図書館界』に名古屋市中村図書館の木村さんが書いている文の内容がよかった。昔、作られていて、今は継続されていない郷土資料のレファレンスツール作製についての話。カードからエクセルに入力しなおし、途絶えていた期間の分も収録しなおした、とのこと。カードや冊子でつくっていたレファレンスツールの多くが、インターネット時代になって、無駄、というか、使えない資料になってしまっているのだが、探せば使えるものも少しはあるはずである。温故知新という言葉をひさしぶりに思い出した。ただ、レファレンスツールは作って満足してしまうケースが多々あるので、いかに活用するか、ツールの存在を市内各館の司書に認識してもらうか、あることを忘れぬようにしてゆくか、といったあたりに注意せねばなるまい。古い図書館日誌を見ていると、過去にはこんな面白い仕事をしたのか、と発見する場合がしばしばあるにはある。たいていはほとんど役に立たなかったりはするが、昼休などに読んで、先人の足跡をたどるのも悪くないものである。
俳句の師、小澤實が句集『瞬間』で讀賣文学賞を受賞とのこと。日本で最も位が高い文学の賞。アサヒネットの闇汁句会、風羅坊句会で一緒に遊んでいただき、その後師事した私。偉ぶらないシャレのきいた人。彼は存在そのものが俳人である。とてもめでたい。
『オリバー・ツイスト』を観る。ポランスキーの映像の美しいことといったらない。バーニー・クラークは実に見事であった。ベン・キングズレーよりも映えていた。今年は良い映画の多い年なのかもしれません。
『疾走』を観る。SABU監督は『幸福の鐘』以来。途中までは大傑作。韓英恵が素晴らしい。柄本佑も見事。この人は両親より上手いのではないかな。豊川悦司の神父様も良かったし、私の好きな中谷美紀が渋くかっこいい役。それにしても平泉成はどれだけの映画に出ているのであろう。観る邦画全部に出ているような気がしてくる。はっとしたり、どきりとしたりするところが多い映画。それが私にとって良い映画なのだな、と改めて思った。後半の展開とラストは原作がきっとそうなのだろうけれど(未読なのでした)、私の好みではなかった。しかし、あとから効いてくる作品。
堀江の逮捕。ライブドアってどんな会社なのだろ、と球団買収のときにWebをあれこれしていたら、知人というか変人のコモエスタ坂本がこんなことを書いていて、ふうむ、なるほど、鋭いな、と思ったのだった。 なにしてるんだかよくわかんない会社。こないだみっけたところは、 ここ。アクセスが殺到しているサイトとのこと。マザーズへの上場時点でなんとかできたんじゃなかろうか、と思えるが、それについてマスコミは全く言わないなあ。きっと何かいろいろな事情があるのでしょうな。規制緩和とか官から民へ、というのが、どこかからどこかへお金が流れて都合がいいから、というような話からはじまっているのではなかろうか、といったあたりから疑ってゆくべきなのだろうけれども。
『プライドと偏見』を観る。映画らしい映画であった。微妙な心の動きを見事にとらえている。景色も美しい。今月は観たい映画が山のようにあって困る。
F本さんから、「メールはご覧になりましたか」との電話。そういえば最近スパム・ブロックであれこれ切ったな、と思い出す。aolもhotmailもyahooも片っ端から切っている。一応、切られたメールのタイトル一覧を確認し、例外処理をしてはいるのだけれども、見落としたようであった。その旨を言い、謝ると、「三通出したのですが」と言われる。スパムブロックのサイトへ行き、見てみると確かに三通あった。ううむ。私から返事がない、というひとがいましたら、そんなような理由ですので、違うメールアドレス、例えば携帯電話メールからでも(って、docomoは切っちゃったな)ご連絡ください。多分誰からもメールをいただいていないと思うのだけれども。F本さん、ごめんなさい。
『秘密のかけら』を観る。コメディアンの二人組がいたホテルでの殺人をめぐるストーリー。陰気な話であったが、映像はよかった。
清水崇監督の『輪廻』を観る。『呪怨』を観ても笑ってしまう私が観て、少しぞっとしたのだから、恐がりのひとはおしっこを漏らすかもしれません。優香が良い芝居をしています。杉本哲太が良いのは当然。ショックとサスペンスを見事に駆使した作品。『呪怨』はリアリティがなかったのだけれど、『輪廻』はなんとなくありそうな感じがするのと、辻褄が合ってるように思える箇所があるので余計に怖いのだろうな。ラストが秀逸。怖いもの好きのひとにはお勧めです。
昼に『ある子供』を観る。パルムドール受賞の随分と話題になっているベルギー映画。しかし、私の好みではなかった。映像感覚はとても良く、暴力のシーンはとても痛そうだった。
カフェ・デュフィというところでサエキけんぞうのライブとトークショウ。セルジュ・ゲーンズブールやミシェル・ポルナレフらの曲に直訳の詩をつけて歌うという活動を最近はしているとのこと。ミシェル・ポルナレフについて、「シェリーに口づけ」を聴いてあんな感じを期待してアルバムを買うとがっかりします、と語っていたのに爆笑。中学の頃、アルバムを買ったら陰気な曲ばかりで辟易した記憶がまざまざと蘇ってきたのであった。狂ったような振り付けで包丁を振り回しながら歌う曲もあって、変梃で良かった。1部がライブ、2部は、2日に観にいった『アイドルたち』についてのトークで、名古屋シネマテークの人とやりとりをしていたのだが、その人が若いため、微妙なズレがあって可笑しかった。『アイドルたち』のファッションについて尋ねられたサエキけんぞうが、「腐ったGSみたい」と言ったのに吹き出してしまったが、ウケていたのは私ともう一人の年輩のひとくらいで、若い人たちにはそのニュアンスが伝わらなかったようである。グループサウンズをテレビでリアルタイムで観ているのは私あたりが最年少の世代なのであるな、と歳を感じたりもしたのであった。シルビー・バルタンとジョニー・アリディ夫妻の曲『トワ・エ・モア』をかけるとき、DJに「なんて曲だっけ」と尋ね、「『トワ・エ・モア』ね、ある日突然」とサエキけんぞうが言ったのに吹いてしまったのだったが、これもほとんど誰も反応していなかった。セルジュと寺山が死についての詩人という点で共通しているとのことで、寺山修司作詞、シャデラックスの『孤独よおまえは』を歌ったのだが、その後、寺山夫人だった九條今日子からサエキけんぞうが聞いた話として、『上海異人館』の海外公演のオーディションにジェーン・バーキンが来た、と言った時、「おおお」と思わず声を発した人数もとても少なかった。セルジュ・ゲーンズブールとジェーン・バーキンは以前、結婚していて、間に生まれたのがシャルロット・ゲーンズブールである、ということを知る人があまりいなかったようだったのだ。また、名古屋という土地のわからなさについて語った話で、90年代初頭に名古屋でブライアン・フェリーのコンサートがあったときの客が100人ほどだったのに対し、エルヴィス・コステロのコンサートには1500人来たとのこと。私はまるで知らずにいたので、かなり驚いたのだったが(普通の土地ではこの数の差はあり得ないだろ、と誰もが思うのではあるまいか)、客席の反応は皆無に近かった。ううむ。マニアックな話題ではなく、今日はかなり有名な人たちについて語ってくれているな、と私は感じていたのだったが、客層が若かったせいか、盛り上がりが今ひとつでサエキ氏にはなんとなく気の毒だなと感じていた私。しかし、終わり近くにクロード・フランソワの映像を少し流していて、変わったツイストや横にいるダンサーの不思議な動きに場内は笑いの渦と化し、めでたしめでたしであった。最後にクロード・フランソワの曲に直訳の詩をつけた歌を歌い、おしまい。とても充実した楽しい2時間であった。
昼休に本屋へゆくと「文學界」2月号表紙に小林信彦の『うらなり』とある。20年ほど前にエッセイで、うらなりの目から見た坊ちゃんについて書こうと考えたことがある、といった内容のことを小林信彦は書いていて笑った記憶がある私は、つい最近友人とそのことを話題にしたばかりであったので驚いた。帰宅後読む。設定がうまく、その後のうらなりにリアリティがあり、とても面白かった。
「文學界」には筒井康隆の連載『巨船ベラス・レトラス』もあり、著作権にまつわる事件について出版社の実名を挙げて書かれている。あの本はそういう本であったのか、と吃驚仰天。筒井さんは大変な被害に遭っている。
あけましておめでとうございます。
朝、『ロード・オブ・ウオー』を観る。ニコラス・ケイジでなければこの役は難しかろうと思われるほど上手く、ぴたりとはまっていた。兵器販売業のひとの実話に基づいた映画。アメリカでの配給会社は『華氏911』と同じカナダの会社だそうで、日本でもあまり上映館が多くないのでした。ブッシュにとってあまり都合の良くない映画。多くの人が観たほうが良いと思われる映画だと思うのでした。
晩、名古屋シネマテークに『アイドルたち』を観にゆく。主に服を観るつもりで行ったのではあったけれど、出来の良くない映画。服はポール・スミスみたいなのがあったりして面白かったし(影響を受けているのかな)、歌のなかに『ロッキー・ホラー・ショー』の『タイム・ワープ』みたいなところがあったりしたり(多分無関係な気はするけれども)、また、作られた偶像としてのアイドルを暴き茶化す、といった感じの内容は当時としては新しかったのだろうな、という気はしました。今の目から見てしまうとかなりつらいものがありましたが。
アップルストア栄で、アサヒネット時代からの友人ウブカタノリタカ(生方則孝)さんのライブ。集客をしていなかったらしく、大変お客さんが少なかった。4日のアップルストア渋谷では満員だったというのに、情けないぞ、名古屋、といった気分になった私。生方さんが88年に出した『内容のない音楽会』は、遊び心いっぱいのアルバムで、発売前には取材申し込みが沢山きていたのだが、発売時期が昭和天皇の容態が悪くなった時期と重なったため、笑いのあるもの、ということで、取材がすべてキャンセルとなり、PRもできなかったという不幸な事態となったのだが、音楽業界のひとたちの間では話題となり、4000枚ほどの売り上げがあったとのこと。奥田民夫はこのアルバムのなかの歌をすべて歌えるとか。そのなかから「軍艦行進曲」、「パンクのモーツアルト」を少しと、「戦場の盆踊り」を全部聴かせてくれたのであった。はじめは再来月あたりに出るニューアルバムのなかから、「てぃんさぐぬ花」とモスラが最後に空へ飛んでゆくシーンで流れるきれいな曲を演奏してくれたのだが、このアルバムはほとんどシンセサイザーとテルミンだけしか使っていないのでした。とてもあたたかくてやわらかい音楽たち。今後もライブがあるそうなので、興味のあるかたはどうぞ。
リチャード・プライヤーが死んだ。アーサー・ヒラー監督の『大陸横断超特急』は大好きだ。こんな面白い映画はめったにない。ジーン・ワイルダーとのやりとりが最高。シカゴ駅に列車のオブジェがあるとかいう話を聞いたような気がする。名古屋で二週間で打ち切られた『見ざる聞かざる目撃者』も面白かった。目が見えない役のリチャード・プライヤーと耳が聞こえない役のジーン・ワイルダーが殺人事件に遭遇してしまう、というとてつもない設定。私を心から笑わせてくれた偉大な役者の冥福を祈る。
とある雑誌に出した論文の初校を直す。締切間際に書いたため、意味の通らぬ箇所があったり、文章が変梃だったり。申し訳なく思いつつ、かなり手を入れたのであった。Tさん、ごめんなさい。
某大学図書館の友人が、ATTTのTさん、というか名古屋の某図書館のTさんと図書館のあれこれについて語りたいとのことで、連絡をとり、三人でタイ料理屋さんで会食。ここには以前、豚の耳の揚げ物があり、昼間からよく食べたものであったが、一年ほど前になくなってしまった。いつか飲んでみようと思っていたコブラスープもメニューから消えている。淋しいことである。
解決しようと思えばなんということもなく片づくであろう問題があったりするわけだが、そのことを問題と捉えていない、あるいは、問題が発生しているところに対して、「問題が起きてるよ」と言わないと問題そのものの存在が把握できていない、なんて話はきっと全国津々浦々にあるのだろうな、などということをこの会談が終わって感じた私。笑いの趣味が近い人たちと力を抜いたやりとりをするのは楽しいものである。そして何かが解決してゆきそうでもある。めでたしめでたし。
千葉のフクダ電子アリーナにジェフ千葉対グランパスの試合を観にゆく。グランパスの最終戦であるが、それよりもオシム監督のジェフが優勝するのではあるまいか、とのかすかな期待を抱いて出かけたりもしたのであった。グランパスの次にジェフが好きな私なのである。アウエイではこんなにグランパスファンが応援しているのか、と驚いた私。瑞穂や豊田でしか観たことがなく、アウエイチームの応援は気合いが入っているのにグランパスファンはあまり覇気がないのかな、と思っていたのだが、遠くまで出かけていって声援するひとたちはとても力が入っているのであった。鴨川が一点入れたときにははしゃぎそうになってしまったが、まわりは全員ジェフサポーターであり、私も今日はにわかサポーターとして来ているのだ、と気をとりなおしたり。結果はジェフがロスタイムに逆転。しかしガンバが優勝。帰りに、アサヒネットのパソコン通信時代の古い友人夫妻と特急列車に一緒に乗る。「やっぱり特急に乗りたいよね」「そうだよね、特急だよね」などと男二人で語るのを妻のひとはやや冷たいまなざしで眺めていたりしたのであった。なかなか良い一日だった。
『イン・ハー・シューズ』を観る。トニー・コレット、キャメロン・ディアスが見事に姉妹を演じているのであった。監督は『L.A.コンフィデンシャル』のカーティス・ハンソン。シャーリー・マクレーンは、『奥様は魔女』であまり良くなかったので、名優も駄目になるものなのかな、などと思っていたのだけれど、この映画ではさすがシャーリー・マクレーンといった感じであった。でも、この人のもっているかわいらしさのようなものがもう少し出る演出があっても良かったのではなかろうか、などと贅沢なことを思ったり。
二兎社の『歌わせたい男たち』を観る。春日井市出身の戸田恵子、名古屋出身の近藤芳正が出ているせいか、名古屋弁でのやりとりが途中に幾度か入る。「外人」を「ぎゃあじん」という名古屋のひとはそれほど多くない気がするが、いないこともないのでなんだか可笑しい。しかし、このバージョン、名古屋以外でも演じられているのであろうか。通じるのかな。とても良い芝居であった。君が代を卒業式で歌わせたい校長、若い教員、と不起立の教員、新任の音楽講師、保険の先生の五人しか登場人物はいないのだが、実に深みのある、そして、押しつけがましくない物語であった。
朝、『イン・ハー・シューズ』を観に行こう、と新聞の映画欄で時間を確かめて出かけたところ、『イントゥ・ザ・サン』の時間であった。スティーブン・セガール主演のアクション映画。ま、これも観たかった気もするな、と観る。いやはやひどい映画であった。どうして彼らがそれを知ったのか、とか、どういう組織なのだろ、とか、築地の魚市場であんなことを、とか、変なところがいっぱいの日本を舞台にした作品。スティーブン・セガールが彫師に話したりする日本語もすさまじく、これはこれで一見の価値があるかもしれない。
グランパスのホームでの最終戦は対新潟。どちらもぱっとしないまま、フリーキックで一点取った新潟が勝った。気が抜けたような試合であった。来シーズンはなんとかしてもらいたいものである。
友達が「たんすにジュゴンプロジェクト」という活動をはじめたとのこと。彼女はアサヒネットに「KYサンゴ」という衝撃的なハンドルネームで登場したひと。朝日新聞に載ったサンゴ礁に「KY」といたずら書きをされたという記事が新聞社と関わりのあるカメラマンの仕業であった、という大きな事件からそれほど間がない頃のこと。過激なひとかと思ったらとても穏やかで細やかなひとであった。まだお会いしたことはないのだけれども、ゆるゆると10年以上のおつきあい。彼女のブログを読んでいたら、佐藤義美の『王さまの子どもになってあげる』という本について書かれていた。このお話は知っている。子どもの頃に好きだった。調べたらほるぷ出版の『日本児童文学大系第27』に入っているとのこと。読み返してみようと思う。
図書館と指定管理者制度についてのあれこれは、別の項目を立て改めて書くことにする。
『ALWAYS 三丁目の夕日』を観る。西岸良平のマンガ『三丁目の夕日』を初めて読んだのは中学のときだったと思う。単行本を何冊か持ってもいる。しかし、どうも絵柄を好きになれず、話は良いのにな、と生意気に感じていたりした私。このマンガ、まだ連載が続いていたのですね。ロールの終わりに「ビッグコミック・オリジナル連載中」とあって驚いた。三十年くらいになるのかな。随分昔に読んだきりの原作だったのに、細かいところをかなり覚えていた。十代に読んだものについての記憶というのは面白いものだ。吉岡秀隆が上手いことは彼が子どもの頃からわかっていたけれど、今回の役での演技は素晴らしかった。ピエール瀧の氷屋の存在感がすごかった。夏に大きな氷を鋸で切って運んで、と大変な作業を何年もしてきたのに、電気冷蔵庫のせいで、突然仕事が減ったりなくなったりするのだろうな、とひとごとでないような気分になったり。短篇をつなげた作品で、元の話を皆知ってしまっているにも関わらず、なんだかじんときた映画。合成映像の箇所が多いのに実によくできている。随分客も入っていたが、あまりに昭和三十年前半を忠実に再現しているためか、出てくるモノなどについて話をする年寄夫婦などがいたのには参った。
寒い中単車で豊田にグランパス対ガンバ大阪戦を観にゆく。2対1。勝てるとは思っていなかったので、とてもうれしかった。審判があぶなそうなひとなので大丈夫かな、とどきどきしていたが、指導があったのであろうか、それほどカードは多くなかった。鴨川がどうなってゆくのか楽しみだ。私のなかでの今日のMVPは攻守に貢献した角田。
仕事がばたばたであった。このところ卒業論文の調べものでやってくる学生が多い。熱心なのだけれど、『雑誌記事索引』の存在を知らなかったりする。幾度か図書館員日記にも書いているが、大学における図書館教育は重要であると思う。
仕事が終わったあとでレファレンス探検隊へ行く。あやしげな医療関連図書を公共図書館におくべきか否か、といった論があったのだが、これはなかなか難しい問題であろうと思う。しかし、公共図書館にあるレベルの本で大きななにかが解決するとかしないといったことはないだろうし、インチキな、ガンが治りました体験談の本を読んで、それを試みて損をした人がいたとか、家庭の医学あたりを読んで自分は余命幾ばくもないと勘違いしたひとが自殺しちゃったとして、それが図書館の責任であるのか、と言えば違うだろうと思う私。大人であれば様々なことを自分で判断すべきだと私は考える。児童についてはここではおいておく。図書館にうそが書かれた本ややたらと古い医学知識が書かれた本(大江健三郎の『われらの時代』の避妊法なんてどうなんだろ)があるからと言って、借りて読んだひとの責任ではなく、蔵書にして貸し出している図書館のせいになったら大変なことではなかろうか。医学に限らず、どんなジャンルの本にも誤りがあったり、読み手の側によって不思議な力が作用するわけで、医学のジャンルだけは生き死にに関わるので、なるべく完璧な蔵書構成にすべきである、なんて無理な気がする。小説読んで自殺しちゃうひとなんて昔からいっぱいいるのだし。はじめから100%めちゃめちゃな本であれば避けるべきだろうけれども。もし信頼のおける医学知識を利用者が得たいのであれば、公共図書館でなく別の専門機関(なければ作ってもらうよう、それを真に必要とする人々がどこかに働きかければ良い。しかし、ひとは死ぬときは死ぬのだけれども)を頼るべきであろう。医学関連図書についての考え方はつきつめてゆくと、死生観の問題にゆきつくのではなかろうか。あるジャンルについて特別な知識を持った司書が、それを使いにきたすべての利用者に誤りのないよう接することができる市町村図書館なんて多分100年経ってもできやしないので、公共図書館における医学領域図書選書論についてはほどほどのところで止したほうが良い、と私は思ったのであった。思い込んじゃっているひとに、それは間違っていますよ、と司書が言えるのか、という問題もある。あるときそれが正しくなる場合だってあるのである。時代、地域により本当であったことは嘘に変わるのだし(ついこないだまで胃には何もいないことになっていたぞ)、ほかのジャンルの本にも嘘がいっぱい書かれているし(海王星と冥王星の位置はいつ変わったのだっけ)。誤っていることを正すのは悪いことではないけれど、完璧にできないのだから、何をそこでなすべきか、止しておくべきかを判断してゆかねばならないのである。マニュアル化や標準化の困難な事柄を果てまで追いかけていっては一生を誤るかもしれない。
『スクラップ・ヘブン』を観る。栗山千明とオダギリジョーを観たいがためであった。映像はきれいだったが、私の好みではなかった。いらだたしい感じはよく伝わるのだけれども。
『TAKESHIS'』を観る。フェリーニの『8 1/2』系列の映画。花束のなかの芋虫、頑固おやじのラーメン屋、拳銃、麻雀、ヤクザ達、岸本加代子、デブ二人、がぐるぐるしていて、いかにも映画的な映画でコミカル。私は好きだが、好き嫌いがはっきりわかれそうな作品。ボブ・フォッシーの『オール・ザット・ジャズ』やウディ・アレンの『スターダスト・メモリー』を好きなのと同じような感じ。紫色のタクシーの運転手になったシーンが特に良かった。美輪明宏の使い方のうまさ。京野ことみが雰囲気があって良いし、寺島進、大杉漣は良いに決まっている。しかしこの映画、暴力や死や性の描写がかなりあるけれど年齢制限をしなくて良いのだろうか。
『ミラクル・バナナ』を観る。はじめのほうは面白いのだが、なんというか説教臭い感じになったり、わくわくする感じが薄れてきて残念であった。オープニングのアニメーションでどんな話なのかがすぐにわかってしまうのも考え物。もっとずっとよくなりそうな話だっただけに残念。映像はきれいだった。
グランパス対清水エスパルス。ディフェンスが変。攻め手も欠いている。しかし川崎戦と違い、点を取られたあと、取り返してやろう、との気概が感じられて良かった。川崎戦と言えば、浦和レッズと川崎フロンターレの試合の審判は随分ひどかったようだ。Fマリノス対グランパスの時、古賀正紘がわけのわからぬファールでPKにされたときの審判。まだ割と若い人のようであるが、審判がこんなに目立ってはいけないと思う。Jリーグは審判のレベルをあげてゆかないと客が離れてゆくことであろう。
琉球新報や沖縄タイムスを時折読む。本当に沖縄は日本に返還されたのかな、と考え込んでしまう記事がしばしばある。様々なことに無関心でいたり、知らずにいたりするうち、いろいろとひどいことになってゆくのであろうな。ところでジュゴンは大丈夫なのだろうか。
拝む関連の事柄についてどうも醒めてしまうのは、信じる性質が私に全くないからなのだ、と気づくのでした。一応お通夜に数珠持って出かけたりはするけれど。お盆に集まったり、お墓に参ったりもかれこれ二十年ほどしていないのでした。厭な奴が死んだら命日に墓に小便をかけにいってやろうかな、と考えたりはしますが。お参りを選挙公約にしたり、詣でたかどうかで揉めたりということが全然謎。お国の為に亡くなった人を茶化すつもりはありませんが、やはりこれは宗教の関連行事ではないのかなと思えてなりません。首相が公人として出かけるのはどうかなという気がします。お伊勢さんもまずいわけだな。あそこは景色が良くて好きだけれども。って生まれてから二回しか行ったことはないが。ううむ。公人は大変ですな。
実名を出しているひとに匿名で批判をしたことに対して実名の人が憤るのは当然のように思えるのですが、そうでもない世の中になってきたようです。
そんなわけで表紙に、「むずかしい質問をする場合はご記名ください」と書きました。ひとにものを尋ねるのにフルネームを書かないというのは育ち方の問題ではないか(うっかり忘れたということもあるだろうけれどもさ)、と私は感じるのだけれど、もしかして最近では普通のことになったのでしょうか。
育ちと言えば、ちかごろの教諭のひどさには目を覆いたくなるようなものがあります。遠足に子ども達を連れてやってくるのですが、図書室はぐぢゃぐぢゃにしてゆくわ、大騒ぎしていても叱らないわ、というのがごく普通になっております。先日は外にトイレがあるのに(気づかなかったかもしれないが)、透明なビニール袋に吐瀉物が入ったものを、吐いた当人であろうと思われる小学生を連れて館内にやって来て、トイレで片づけたのでした。ほかの客がいるのが目に入っていないのだろうな。もっとひどい事例もあったりしますが、汚い話が好きなひとばかりではないでしょうから、この辺で。しかし、子供をまともに叱れない友達みたいな先生ばかりになって大丈夫なのであろうか。結局自分が痛い目に遭いたくないから子供に迎合しているだけのこと。そういうところを子供はしっかり見て計算して先生を軽く見ている、というあたりに気づいていないのか、気づいていても面倒だから適当に過ごしているかであろうな。親もそう。良い子がいっぱいの世の中になってゆく予感がします。
『シン・シティ』を観る。アメリカン・コミックがそのまま映画になった感じ。って、そのまんまですが、それ以外の感想を持てなかったのでした。
しかしなんでそんなにお参りしたいのでしょうな、靖國神社。神道が好きならばお伊勢さんではいけないのかな。って、そういう問題ではないのであろうな。A級戦犯の分祀が簡単ではないのならば、首相でいるうちに参ってはいけない気がするが。あるいは、「頭のなかでA級戦犯をわけて参っているのだ」と、コメントしたら近隣諸国は許してくれないだろうか。無理か。自分家の庭に戦没者の祠かなんか建ててそこを地味にお参りしてはどうか。目立たないから駄目か。
『切ってはいけません!日本人が知らない包茎の真実』(石川英二著、新潮社、1000円)を読みはじめる。目から鱗がぼろぼろ落ちる。包皮の問題に関心のあるひとにとっては必読の書。
国勢調査の調査票を提出。ふう。これで今月末締切の論文に集中できる。しかし、書こうと思っていたことが論文として書けるのかが疑問に思えてきている。
与党はし放題である。弱者はより虐げられ、強者は大笑いをするシステムが徐々に作り上げられてゆくわけだが、わかりやすい報道がなされぬためか、ずるずると進む。知らずにいるのは幸せなことである。
『さよならCOLOR』を観る。きれいな映画になる寸前でいろいろ毀れる感じが厭だった。ことに竹中直人のバレエシーンが謎。笑えないし、竹中直人監督作品は『無能の人』しか観ていないのだが、どうも生理的に私と合わない気がする。原田知世を観にいったので十分に満足したのではあったが。段田安則はいい加減なひとを演ずるとどうしてしっくりするのだろうか。実に良かった。
日本対ウクライナ戦。審判に泣かされた試合ではあった。シェフチェンコは出ないし、二線級の選手がいっぱいのウクライナ相手であったわけだが、ううむ。ジーコのままで大丈夫なのであろうか。
スパムメールがひどい日は100通くらいくる。アサヒネットにスパムブロックというのがあるので、頭に「info」とつくのなどを拒否設定した。例外は通るようにすれば良いのである。しかし、まだまだ多い。今日は思い切って、hotmail、Yahoo、msnメールなどをみんな拒否設定した。例外を通せば良いのである。どのみち、どんな標題のスパムメールが来たのかは確認しているのだし、hotmailなどで送ってくる友人はほとんどいない。というか、最近はほとんど誰からもメールが来なくて、九割五分以上スパムなのだ。
休みであった。朝と晩、順調に調査票を配る。
昼に『容疑者室井慎次』を観る。室井の恋愛の話は良かったが、田中麗奈ってこんなに訛っていたっけ、と変なことが気になる。八嶋智人演ずる弁護士がどうして訴訟を起こしたのかがいまひとつわからなかったりしてすっきりしない映画であった。話の盛り上がりなどは良いのだけれど、おしまいのあたり、休職中じゃなかったっけ、とか、様々な疑問がわいてきてしまって困った。
仕事場近くの花を見にくるひとのための駐車場整理と、童話賞の応募作品整理とでばたばたの金土日のあとの休み。国勢調査員の仕事をする。調査票配布に朝早くからまわったのだが、留守宅が多い。帰宅したのち、やけくそのように、あおなみ線に乗り、TOHOシネマズベイシティに『銀河ヒッチハイクガイド』を観にゆく。この映画、上映館が極端に少ないのだが、観ると頭がすっきりする、良い意味で莫迦莫迦しい作品である。最初にイルカが出てくるので、別のスクリーンに入ってしまったか、と外に出て店員に訊いてしまった。あおなみ線はさすがに赤字だけのことはあり、がらがらであった。観終えたあと、今池のナゴヤシネマテークに行き、『ノミ・ソングス』を観る。クラウス・ノミのドキュメント。若くしてエイズで死んだ有名人であったのだな、と思い出した。急にファルセットになる歌い方にどきどきしたものであった。悲しい作品。
雨が降っているなか、仕事が終わってから単車に乗ってグランパス対セレッソ大阪戦を瑞穂に観にゆく。前半終了間際に中村直志が見事にフリーキックを決め1対1。これで勝つことでありましょう、などとハーフタイムに某図書館のTさんとやりとりをしたりもしたのだけれど、後半に2点とられておしまい。ネルシーニョ監督とルイゾンがいなくなったわけだが、ううむ。うかうかしているとJ1残留が危ないではないか。
朝、手と膝と腰に灸を据えてもらう。すっかり爺である。手は腱鞘炎、膝は数年前単車で二度転んでぶつけた後遺症、腰は26歳のとき、ぎっくり腰になってからずっと悪い。
午後、『サマータイムマシンブルース』を観にゆく。本広克行監督で上野樹里が出ているからであったが、あまりと言えばあまりに莫迦莫迦しい映画であった。私にはあまり笑えなかった。
夕方からレファレンス探検隊。熱気のようなものがこの集まりから減ってきているのが気になった。私のような年寄が横槍を入れることとも関係しているのかもしれない。
瑞穂にグランパス対レイソル戦を観にゆく。4対0の快勝。ルイゾンが良いし、杉本恵太が素晴らしい。ずっとこんな試合をしてくれれば優勝も夢ではないのだが。
一昨日までとある欧州の国へ出かけていました。欧州へは生まれてはじめて。レンタカーを借りたのも生まれてはじめてでした。大韓航空を利用したのでしたが、機内で感じたのは、韓国のひとたちは日本人を好いていない、ということ。帰りの飛行機は九割方韓国人でしたが、そのことが皮膚感覚でひしひしと伝わってきて落ち着きませんでした。隣席は空いていて、その隣に80歳くらいの女のひとがいたのですが、露骨に厭な顔をされました。アテンダントとのやりとりを聞いていて安心したのか、お手拭きを落としたことに私が気づかずにいると、「It is yours」と英語で私に言い、私がきょとんとしていると、「落とされましたよ、あなたのです」と言い直してくれました。それほどまでに子供の頃習わされた日本語を話したくない彼女。日本は彼女に対して何をしたのでしょうね。国と国との間では1965年に話がついているわけで、お金の問題は向こうの国でなんとかすべき、との説に私は傾く者です。全てそれで済んだというのはどうかな、とも感じますが。でも、ともかく国民と国民との間の溝は決して埋まっていやしないのだ、と思うのでした。その溝を深く広くしたひとが一番上にいて、彼を支持するひとたちが一杯居る。近隣の国のひとたちからは、アジアの国々をないがしろにし、ただただ自分たちが負けた米国とだけ仲良くしようとしている国なのだ、と思われていますな、きっと。負かされた、とても沢山の人たちを殺された国に無条件降伏をしたのだから、とただただ尻尾を振ってついてゆき、すぐ隣の国はどうでもいいや、と思ってるのって私はとても変な気がするのだけれども。あの人が首相で大丈夫なのかな。隣国との溝だけでなく、国内での貧富の差もひどいことになってゆくのではないかと思う私。日本の持ちものが安価でアメリカの手に落ちて、ああ良かった良かったと思っているような、自分の人気のためには北朝鮮に貢ぎ物をするような、そんなひとだということが多くのひとたちにわかっているとは思えない感じなのが厭だな。と、何も考えずに過ごして帰ってくる飛行機のなかでぼんやり思ったのでした。ただ威勢がよくかっこよさそうだ、ってだけでついていっちゃう癖があるのが我が国なのだからしょうがないのかもしれないのだけれども。
ノーラ・エフロン監督、ニコール・キッドマン主演の「奥さまは魔女」を観る。なんともかわいらしく懐かしい映画であった。さすがによくできた脚本。シャーリー・マクレーンが可笑しいし、魔女のお父さん役のマイケル・ケインには爆笑しそうであったが、映画館が静かだったので笑いをこらえた私。
『リンダリンダリンダ』を観る。田舎の景色がきれいで、少女達がかわいくて、痛かったりおかしかったりして、私はこの映画、好きでした。
グランパス対浦和レッズ。あああ。楢崎は前節の失点のせいではじめはどうなるか、と思ったのですが、PKを止めたので自信がついた感じでした。ルイゾンは謎のFWだな。シュートを打つか前に出さないといけないところで、はるか後ろにボールを戻していました。あああ。
『妖怪大戦争』を観る。映画館に子どもがいっぱいいて、途中で出たり入ったりしてうるさい。夏休みだからしかたがないのではあるが、親がついてくるなり、なんとかならぬものか。途中で叱ったが敵のほうが数が多く如何ともしがたかった。神木くんは実に良い。菅原文太のじいちゃんがとてもじいちゃんらしくて、時の流れを感じたりした。忌野清志郎の演じる妖怪が良かった。堂々とした娯楽作。豊川悦司の加藤保憲もいかにも加藤だった。
一昨日書いた米軍施設について、新聞、テレビで報道があったよ、と幾人かが教えてくれた。毎日新聞は幾度かとりあげていたとのこと。見落としていました。_●_
しかし、これ、全紙がトップニュースにするような問題ではないのかな。どうせならば首相官邸や国会議事堂の隣で実弾演習をしたら面白いと思うが。
今の首相が進みたいように進んできたこの四年。マスコミの罪は大きいのではなかろうか。しかし、このままずっと進むのであろうな。
友達のホームページを久しぶりに読んでいたらおっかないことが書かれていた。
「沖縄の米軍キャンプ地で、対ゲリラ戦を想定して実弾演習をしているんですが、今度新しく建てた演習場は、住宅地から200メートルしか離れていない場所なんです」
これと郵政民営化とどっちが我が国にとって重要なのかな。報道されない事柄はないことになってしまうのであった。恐ろしい国である。
『亀は意外と速く泳ぐ』を観る。上野樹里と蒼井優が目的であった。とてつもなくばかばかしい(←褒め言葉)映画だった。あの亀はしかし、いかにもアカミミガメにあれこれしました、という感じでいただけませんでした。上野樹里は大女優になる予感。
しかし、なんだろうな郵政民営化。民営化自体に賛成反対、ということではなく、法案に無理がある、とか、もう少し考えた方がよいのではないか、という理由で反対したひともいるだろうに、こないだの国会で反対したから、とすべて公認しない、という方向は正しいとは思えないのだけれど、それについてマスコミはあまり言及しない。いよいよヒトラーみたいなひとに政治をまかせる国となってゆくのであろうか。はて。
なごやレファレンス探検隊のキャンプが昨日今日とあった。いつもとてつもなく飲む人たちがさほど飲まず、いつも酔っぱらうひとは酔っぱらい、関ヶ原ウオーランドは不思議であり、ATTTはおさんどんユニットとしても働き、と、ま、ぼちぼちな感じで過ぎていったのでした。
友達の生方則孝さんが著作権関連の訴訟を起こすとのこと。彼はキーボードプレイヤーとして米米クラブのレコーディングに参加したり、シンセサイザーの音を作ったり、変態だったりするひとなのだが、「三井のリハウス」のサウンドロゴを作ったことでも知られている。今度の訴訟はサウンドロゴには著作権がない、と主張する住友生命を相手にまわしてのもの。体力のいる大変なことであるが、音楽業界やマスコミの著作権に対する認識が変化する可能性がある、と思われる重要な裁判となる気がする。
今度の日月となごやレファレンス探検隊のキャンプ。ギターの練習をする毎日。ほかにもあれこれしたいこと、しなくてはならぬことなどがあり、ばたばたな日々。我が家の蝉はにぎやか。
最近、どこか遠方へゆくと雨か霧か雷である。泳ぐ予定であったが、泳げずに帰る。
名古屋の某図書館のTさんとのユニットATTT(あたたた)が再活動。というほど大袈裟な話ではなく、なごやレファレンス探検隊でキャンプにゆくので、そのときの余興に何曲か歌うことになったのであった。Tさんと曲目の選定と練習。こんなやりとりをする。
「この曲はまだ新しいよね」、「76年ですね」、「なんだ、こないだだ」、「そうですね、ほんの29年前」、「とんでもない会話をしてないか」、「そんな気もしますね。そうか、どうせこれくらい前の曲ならば誰も知らない」、「ならば何を演奏してもいいんだ」、「気楽ですね」
そんなふうにテキトーに曲を決め、なんとなくあれこれが決定。
夕方から瑞穂にゆく。ジュビロ磐田戦、快勝。ジーコが見に来ていたとのこと。川口よりも楢崎のほうが良いとは思わないのかな。中村直志も良いときはとても良いし、中谷もミスをしなければとても良い選手。そして杉本恵太はやはり魅力的なのであった。
「それは急ぐんですか」と、これを急がなくてほかの何を急ぐのか、というような事柄について尋ねられた。日々、物事を考えていないか、危うそうな話を避けて通ってきたか。人間はいずれ死ぬわけだからどうやって一生を終えてもたいした差はないのかもしれないが、私と関わる他人を情けない気分にさせるような過ごし方はしたくないな、としみじみ感じた。
実相寺昭雄監督の「姑獲鳥の夏」を観にゆく。あの長い小説を実相寺監督がどのように映像化するのかが楽しみだったが、ダイジェスト版みたいになってしまった観は否めない。キャスティングは私の目からは京極堂以外はとてもぴったりしていた。田中麗奈の服は昭和二十七年にはあり得ないが。宮迫博之の木場修太郎はもしかして関西弁を話すのだろうか、とどきどきしていたのだが、見事な東京言葉だった。原田知世がとてもこわかった。
伊東四朗一座『芸人誕生物語』を池袋サンシャイン劇場へ観にゆく。去年の『熱海迷宮殺人事件』は異常なほど面白かったが、今年は少しパワーダウンした感じだった。去年のはラサール石井がすごすぎたから仕方がないのだけれども。しかし伊東四朗は出てくるだけで空気が変わってしまう恐ろしい役者である、としみじみ思った。軽さを感じさせることができる役者は沢山いない。日替わりで特別ゲストが出ているとのことで、今日の回はベッキーだった。アドリブが多く、もう少しで設定さえも変わってしまうほどの状況をほかの役者たちに作られていたが、見事な反射神経でこなしていたのに驚いた。脇が甘いところはあったが。春風亭昇太は前座のときに一度、二つ目の頃に一度、真打になってから一度観ただけだが、芝居でも噺のときと同じ感じで独特であった。冒頭、ドラを叩きながら歌ってせり上がってくる伊東四朗が最高。その後、新しい歌を古い歌にかえてしまうギャグはすばらしかった。良いものを観ることができた。パンフレットのおしまいに小林信彦、伊東四朗、三宅裕司の対談が載っているので喜んだが、話題があまりに古すぎ、三宅裕司が入れないほど。小林さんは話し始めると止まらない、という噂を聞いたことがあるが、走ってしまったのであろうか。一番新しい話題がのり平と八波むと志では私も物心ついていない。シミキンを知ってるひとがこのパンフレットを読むうち何人いるだろうか。
中村文則の「土の中の子供」を読んで一番気になったのは、この作者、「ヒキガエル」と「ウシガエル」の区別がついているのかなという点であった。私は多分小説の良い読み手ではないと自分で思う。
うっかりと知らずにいたのだが、船橋市立図書館の司書が新しい歴史教科書をつくる会の書籍を思想・表現に関わる理由で廃棄していたことに対し、市への訴訟が起きていたとのこと。その司書は懲戒処分を受けたのだそうだが、当然である。言語道断。最高裁ではどんな判決が出るのであろうか。個人の恣意で選書を行ってはならぬことは「図書館員の倫理綱領」の第4にもしっかり書かれている。指定管理者制度になったとき、特定の思想、宗教等に関わる管理者がこっそり図書館に入り込んだら怖いだろうな、などと思うのはこの点がおかされる可能性を思うからなのである。しかしびっくりしたなあ。図書館関連雑誌を斜め読みにしかしていないからこういう重要な事件を見逃している私を反省。
郵政民営化法案を無理矢理通そうとする首相の姿は民主的なのだろうか。問題があれこれあろうがなかろうが、何が何でも早く決めてしまいたい、だって俺がそうしたいのだから、というふうにしか見えないが気のせいかな。脅迫して法案を通すのって良くあることだったのだろうか。表に出てきたのは過去に記憶がないのだが、この程度の報道で済んでいっていいのかな。
イギリスでのテロが日本でも起こる可能性がある、と、本気でどれくらいに日本人が考えているのであろうか。それはどうして起こるのかを考えているひとはどれくらいいるのかな。原因をつくった人たちが確かにいて、もしかするとテロを避けられるかもしれない方策もいくつかある感じもするのだけれど、多くの人がそんなことはどうでも良いと思っている国に私は住んでいるのだよなあ、となんだかうれしくなってくる昨今である。滅びてもしょうがないのではあるまいか。
学芸員実習の大学生が3人くる。学芸員になりたいという人もいるのだが、司書よりも難しいし、指定管理者制度の波がやってくるわけで、精進して目指しなさい、などと安易に言えない。公立の文化施設に働くと不安になるよ、と言わなければならない状況はいつまで続くのだろうな。専門的な知識を持ち、資格を取り、そこに就きたいと考える若者に失望しか与えられない国に未来はあるのかな。文化についての考えのなさはなんとかならないものであろうか。
対鹿島アントラーズ戦。3対0の快勝。本山が前半にイエローカードを二枚受けていたのだが、どちらもかなり悪質なファールに見えた。98年のワールドユースの頃にはとても良い選手だ、と思っていたのだけれど、最近の彼を好きになれない私であった。杉本恵太のアシストのシーンを間近で見たのだが、とても落ち着いて豊田陽平にパスを出していた。楽しみな選手である。
対横浜・F・マリノス戦。1対1の引分。なかなか見どころのある試合だった。FWで入団した新人杉本恵太がDFとして右サイドバックで出ていたのだが、とても良かった。左は中谷、渡辺とも致命的なパスミスをする選手。攻撃はとても良いのだけれども守備が安定していないのは困るのであった。
グランパス対大宮アルディージャ。藤田と中山悟志が加わったのだったが、今ひとつ噛み合わず。私の好きな角田が久々に逆上していた。パープルサンガにいた頃はよく見た光景だったが。とても良い選手なのだが右サイドバックというのは彼に合っているのだろうか。このチームはしかしぼちぼちと良くなってゆくのではないかという気がする。
仕事場のいろいろなところにがたが来つつある。修繕費があまりないので、自分たちでなんとかしようと、今日はドライバーと金槌でのハツり作業を二時間ほどしたが、目的を達することができなかった。たまには肉体労働も良いが握力がなくなっているのであった。暑い日だった。
久しぶりに東京へ行く。朝、古本屋と新刊本屋を回る。ついつい沢山買ってしまう。
所属する句誌「澤」の五周年記念大会に出席。土日勤務であるため、なかなか出られずにいたので四年ぶりであった。小澤實先生が三冊の本を出され、句会の会場で販売されていたのを全部購入。そこへ先生がいらして、「通信句会の特選の短冊です」とくださった短冊の包みには「いぬふぐり君 種馬」と書かれている。はて、と開けてみると、先生の「種馬の尻照る秋となりにけり」という句。私が種馬というわけではなかったのだった。参加者の九割ほどが私より年上。みなさん、私よりずっとお元気であった。句会のあとの祝賀会では懐かしいひとと話したりしているうちにすぐに時間が過ぎた。背の高い閨秀作家Kさんに我が家の「ノラ」のことを尋ねられた。スピーチは小林恭二さん、真鍋呉夫さん。二次会では高橋睦郎さん。古くから面識のある新聞記者の方が、どうして「澤」の大会にはこれほどいろいろなひとが集まるのでしょうか、と話していたので、ほかの句誌ではそうではないのですか、と尋ねると、こんなに賑やかではありません、とのこと。小澤實さんは俳句の世界で何かをするのではないか、と期待されているので多くのひとが集まるのではないか、と言っておられたのでした。
トルシエを懐かしく思い出す日がくるとは。99年のワールドユースは実に面白かったなあ。今年も夜中に起きて4試合とも観たのだったが、ううむ。つまんなかったわけではないけれども。本田選手が初戦前半しか出なかったのが大きな不満のひとつではある。梶山は確かに良い選手だが、本田だって良い選手である。調子が悪かったのかな。大熊監督はばてている選手が幾人かいる中で、元気そうな選手をかえたのではなかったろうか。水野は守備でも健闘していたと思うが。ま、結果論だけれども。それにしても悔しい負け方であった。
ブログに移行をしようか、と思い立ち、リンクもしたが気が変わった。どうも性格に合っていない感じなのだ。そこに書いたのが今日の分と13日の分。以下に。
夏である。しかしあの首相は首相になる前からずっとお参りしていたのかな。そこのところがどうも気になる。東京裁判の正当性について云々する人たちはしっかりとアメリカが日本に対して行った悪逆無道についても発言してもらいたいと思う。無辜の市民がどれだけ殺されたのであろうか。ソ連が持っていったところは正しかったのであろうか。そのあたりもしっかりはっきりさせてはどうか。アメリカべったりのまま、東京裁判でA級戦犯になったひとが悪かったわけじゃない、あとから首相になったひとだっているんだから、などと言うのはどうかと思う。ま、いろいろなひとが首相になる国ではある。暑い。
アメリカのメーン州で17歳以下の子どもが借りている本のタイトルを親に教えるという話がしばらく前の「カレントアウェアネス」に載っていた。これはなかなか危険な話だと思う。家族に読書を制限されて殺害し、自殺した同い年のひとがいた記憶がある私である。
ウディ・アレンの新作『さよなら、さよならハリウッド』を観る。ハリウッド・エンディングという原題にふさわしいとても幸せな終わり方の映画だった。観ているあいだずっとうれしかったのだった。『マンハッタン』からずっと観ているわけで、思えばもう25年にもなる。
ワールドユース予選、日本対オランダを観る。1-2で破れた。終わりの五分ほどで家長、カレン、森本のシュートが入らなくて惜しかった。みどころいっぱいの好試合であった。オランダは前半めちゃめちゃ強くて、このままだと0-10くらいになりはしないかとはらはらしたが、よく守った。この年代は良い選手が多いので5年後のワールドカップが楽しみ。
『フレンチなしあわせのみつけ方』を観る。シャルロットがだいぶ歳をとったなという感じがした。煙草が肌に良くないのではあるまいか。中年の男にとってなんだか生々しい映画であった。田舎の風景が美しい。ベンツのEクラスで走るのはさぞかし気持ちいいことであろう。ジョニー・デップを見ると京都の友人Hさんに似てるな、と思う私であった。終わり方が好きな映画。
『ミリオンダラー・ベイビー』を観る。近所の映画館は最終回が1000円なのがうれしい。この映画、私の好きな映画評論を書くひとがことごとく褒めていたので、かなり期待していったのだが、私には合わなかった。イーストウッドの演出も演技もいいし、ヒラリー・スワンクはなるほどオスカーだな、と思ったけれど、ううむ。
シドニー・ポラック監督の『ザ・インタープリター』を観る。ニコール・キッドマンがとにかく良い。ショーン・ペンはさらにうまくなっている。敵と味方がわけわかんなくなる、なかなか面白い映画だった。
ペドロ・アルモドヴァルの『バッド・エデュケーション』を観る。それにしてもこの邦題、なんとかならぬのか。アルモドヴァルらしい映画であった。あるいは自伝的な物語だったのか。ありそうな話なのだけれど、アルモドヴァルが撮ると世界がアルモドヴァルのものになるのだった。色遣いが相変わらず独特で、そのあたりでも好き嫌いが別れるかもしれない。『オール・アバウト・マイ・マザー』、『トーク・トゥ・ハー』あたりではじめてアルモドヴァルを観たひとにとってはどうなのだろう。私はこの映画、好きでした。
『オペレッタ狸御殿』を小さいスクリーンの映画館で観た。大きいところで観ないといけない映画。しかし82歳でこんなめちゃめちゃな映画を撮る鈴木清順に驚く。清順ファンかオダギリジョーのファンでないと怒り出すかもしれないような映画ではあった。平幹二朗の演じる悪役だけでも私には観る価値があるのだが。由紀さおりは若い頃からテレビでコメディエンヌを演じてきたが、映画では本格的なデビューではないだろうか。過去に何かに出ていたかな。わけのわからない迫力のある演技であった。
グランパス対アントラーズ戦。マルケスのラストゲーム。前半4分にコーナーキックからマルケスが美しいヘディングシュート。川島がファインセーブを幾度か。危ない場面もあったし、決めたいところを決められなかったのもあったけれど、1対0で勝てたのはなによりだった。去年の私はマルケスを見るためだけにスタジアムへ通っていたようなもの。ブラジルでの活躍を祈る。
ムーンライダーズのライブに行く。来年で30年になるのか。しかし全然ヒット曲なしでここまできているのはとても偉いな、としみじみ思う。かしぶち哲郎さんが体調不良ということでカーネーションの矢部浩志が叩いていた。いつかは誰かが欠けるのだろうな。『Who's gonna die first』。こないだ慶一さんを観たのは去年の9月。高田渡とのジョイントだった。こないだムーンライダーズが名古屋に来たのは一昨年の12月。相変わらず元気なおじさんたちだった。
メール友達の影響で図書館関連の論文を今年も書こうか、という気になっている私。しかし、書きたいのが先行論文があまりない分野なのが大変そうではある。
民間委託や指定管理の図書館のことについて、ふと思ったのだが、プライヴァシー保護は万全なのだろうか。いや、契約でそのあたりは当然無事なはずではあるのだが、素人でなくても延滞督促や予約の電話の際、家族などにタイトルを告げてしまうことがままあるのだから何が起きても不思議はない。乱暴な場合は延滞利用者一覧を貼り出したり、タイトルまでそれに載せちゃったりして。公共図書館で働く人は是非一度してみたいに違いないことだったりはするが。また、同じ管理者が入ってる館同士で市をまたいでオンラインしちゃったり、個人データを流すと金になるからこっそり業者に流すとか、その辺まで自治体はチェックできるのだろうか。お金の流れだけを追っていればわかるかな。少し疑問。そもそも専門職がいない自治体ではじめちゃったら、そんなことまるで考えてもいない可能性もあるよな、と想像したのだった。個人情報が重要である、くらいの認識はあるだろうけれども、思想信条の自由についての概念が希薄な我が国において、そのあたりをまともに考えない自治体の一つや二つや十や二十あってもおかしくはない気がしちゃう私である。杞憂だろうか。
豊田スタジアムにグランパス対ヴィッセルを観にゆく途中、昼ご飯を食べようと下車。駅の構内でフォークギターを弾いて歌っている高校生くらいの男の子たちがいた。よくよく聴いていると銀杏BOYZの『もしも君が泣くならば』だった。アンプラグドで演奏するとまるで違う曲だ。峯田和伸の曲は耳に残りやすくきれいなものが多いと思う。昔の歌謡曲のような、と書くとファンに怒られるかな。私にとっては懐かしい感じのする曲たちである。
ひどい試合であった。マルケスのJリーグラストゲームとは思えぬほど。本田がいないと別のチームのようだ。
『交渉人真下正義』を観る。軽快な展開が心地よい。寺島進、國村隼、金田龍之介。強烈な印象の役者がいっぱい。君塚良一はとてつもない数の映画を観てきているひとなので、マニアックな箇所がいろいろあるのだが、あまりに有名な映画を踏まえているための弊害もあった気がする。おしまいも少しすっきりしなかった。しかし、立派な娯楽作である。観ていてわくわくするのがなにより。
この日記を読んでいて、間違ったことを書いていたことに気づく。4月12日(火)の、
>1945年と2005年の同じ場所の写真が並んでいる展示もあったが、どう観ても2005年のほうがいい。
これは「1945年のほうが」である。正反対のことを書いてしまっていたので訂正します。
『阿修羅城の瞳』を観にゆく。目的は宮沢りえである。滝田洋二郎らしい映画であった。外連味たっぷりの派手な映画。渡部篤郎の悪役が良かった。
夏になごやレファレンス探検隊の人たちと関ヶ原へツアーへゆくので、その打ち合わせ会に仕事が終わってから出かけた。相変わらずすさまじい飲み方の女のひと2人に加えさらに大酒のみの女のひと1人。F本さんはとある事件により糾弾されていたが、それも仕方あるまい、と、私も一緒になって糾弾していた。少し気の毒ではあったが、みんな酔ってもいたし、多分本人のせいなのでしかたがない。関ヶ原ウオーランドへは行ったことがない気がする。鍾乳洞は行ったようなおぼろげな記憶。
とある図書館の方から、『一図書館員から見た日本』第二回『プライヴァシーの問題』のなかに「トラックに乗って来た利用者が図書館の本をみんな借りていったらどうするのか」というのをくだらない質問としているが、現実に貸出冊数を無制限にしている図書館で、百の単位の本を借り、まとめてブックポストに返すひとが存在するとのご指摘を頂戴した。絶対そんなひとはいないかのように私は書いていましたが、図書館には実に様々なひとがやってくるわけで、想像力が足りませんでした。いずれこの文章は書き改めようと思います。ごめんなさい_●_
グランパス対大分トリニータを仕事を終えたあと観にゆく。主力選手がかなり欠けていて、若手選手が沢山出ていた。攻めて出ていこうにも守備が不安だったのであろう。おしまいは惜しいところもあったが、引き分けならば、ま、良かったのではないか、と帰宅後気分が落ち着いた私。観てる間はフラストレーションが溜まったのだった。
ハナレグミを観にゆく。客層は30前後のひとがほとんど。8割以上が女のひとであった。大沢誉志幸の『そして僕は途方に暮れる』やはっぴいえんどの『春らんまん』を演奏したのには驚いた。はじめのアンコールでの『明日へゆけ』、『さよならCOLOR』へと繋がっていったところにはぞくぞくしたのだった。ゆったりとした余裕のある良いライブだった。
末井昭さんの日記ページを読んだら、銀杏BOYZのおっかけをしているとのこと。4月17日の安城でのライブにも来ていたそうだ。気づかなかった私。以前、一度お会いしたことがあるのだが、多分覚えておられないだろう。オープニングアクトの加藤君は銀杏BOYZがオーディションして決めたのだそうだ。しかし、「鶴舞線よ空を飛んであの娘の胸に突きさされ」はまずかろう。あの曲にチェックが入っていなかっただけなのかもしれない。良い歌もあったし。
メーラーが不調となり、あれこれしながら本を読んで一日が過ぎる。
原田知世が結婚。『時をかける少女』から20年か。20年前、友達と紀尾井町の角川ビルに行ったとき、「きっとここを知世ちゃんは歩いたんだ。舐めておこうか」と友達は言ったのだった。時は早く流れている気がする。
グランパス対ヴェルディ。ピッチサイド見学ツアーに当選したのだった。楢崎、川島を間近で見る。試合のはじまる15分前まで練習をピッチサイドで見学したのだった。ボールの動く速さが客席で見ているのとは違う。胸でのトラップは痛そうだ。森本も間近で見た。後半になぜか主審がアクシデントで交代。この審判がすさまじかった。どうして出したのかわからないイエローカードが3枚。謎のPKまで与えてしまう。ラインを割ってもコーナーキックにならなかったり、きれいに足の間を抜けてラインを切っても敵方のスローインになったり。沢山ひどい審判を見てきたが、今回は最悪だった。これで負けでもしたら暴動が起きたことだろう。しかし、なんとか5対4で勝利。
仕事で万博へゆく。
映画『真夜中の弥次さん喜多さん』を観る。原作が原作なのだが、映画はもっと映画だった。と、これではなんだかわからない。万人向けとは決して言えない映画。私はかなり好き。宮藤官九郎は偉いと思ったのだった。荒川良々が出ているとそれだけで幸せな気分になる私ではある。それにしても濃い役者ばかりよくもこれだけ集めたものだ。
私が題を設定したネット句会で投句をし忘れる。二度め。皆、怒っているに決まっている。気がないわけでもないのにいろいろなことを忘れる昨今の私。病気かもしれない。
家人にひきずられて万博にゆく。12日と違って人が多く、よれよれになった一日であった。日立館はなかなかよかった。
銀杏BOYZのライブを「安城夢・希望」というライブハウス(私の感覚ではロックの関係の場所につけることを考えられない名前ではある)に観にいった。Webにある地図では駅から数分で着きそうなのだが、歩いて30分ほどかかる。大人しそうな若者達が静かに話しているのが不思議。「あの、こんなことお願いするの、変なんですけれど」と躊躇しながら十代の男の子が近づいてくる。「100円いただけませんか。1900円しか持っていなくてTシャツが買えないです。すごく悔しい」と言うので100円あげると喜んでTシャツを買いに行った。客層が若いのである。しかし世の中は変わったな、と思ったのがオープニング・アクト。加藤亮二君という17歳の鳴海高校の生徒がとても緊張して、上手いとはお世辞にも言えない歌を歌っていたのだが、声援が暖かい。はじめの歌は友部正人の『中央線』の歌詞をそのまま使っている箇所があって頭を抱えたくなった私。オープニング・アクトはひどく野次られたものだった。「ひっこめ」「早く終われ」「つまんねえぞ」などと言われながらの演奏はつらかろうな、と思ったものだった。今はそういう世の中ではなく、優しさに満ちているようである。あるいは銀杏BOYZのファンたちだけがそうなのかもしれないが。驚いたのは次に現れたブレックファーストへの客席の反応。バンドメンバーでなく、ついている人かなにかがダイブしたのに客は怒りもせず、縦ノリをしていた。前のほうで、「ああ前座だからぼんやり観ていればいいや」と思っていた私は思わず眼鏡を落としそうになったのだった。野次らないのだ、とはわかっていたものの、知らないバンドの演奏がはじまった途端ノるのはどうなのだろう。好き嫌いなく何でも喜んで迎える人たちに私はついてゆけそうもない。音を聴いて良いと思ってノりはじめたのではなく、はじめっから盛り上がるのは変。私は脇に避けて醒めた目で見ていた。あまり好きな音楽ではなかったのだった。銀杏BOYZの演奏がはじまったのは8時20分。上半身裸の峯田和伸はスターのオーラが出ていた。『銀河鉄道の夜』を静かに歌いはじめたのだが、客席はとてつもない状態。サビのところでは、客席からステージ方向へ向けてのダイブがはじまる。おいおい一曲めだぜ、と思っていたのだが、その状態は二時間続いたのだった。リズムセクションがしっかりしていて、演奏はとても良かった。アンコールでは峯田が客席に降りて客が輪をつくり、その真ん中で『なんとなく僕たちは大人になるんだ』を峯田が客と一緒に歌ったのだった。MCで「援助交際でもなんでもしてていいんだ。したくなくなったらやめればいいんだ」と言っていたのを今ふと思い出して、『人間』の歌詞に「戦争反対って言ってりゃいいんだろ」とあるのに違和感を抱いた記憶が蘇ってきた。何に対しても寛大、なのかな。全てに対して嫌悪感がないのではないか、と思う。それはしかし、いろいろなこと、ものに引きずられてゆくことにつながりはしないか。リリカルでとても良い詞とメロディアスな曲、幸せな時間、空間にいられたのはうれしかったのだけれど、一日経っていろいろと考えてしまった私である。
仕事場の会は無事に終わった。人数は少なかったが充実した内容であり、参加者が皆熱心で良い会になった。
高田渡の死。最後に観たのは去年の9月。76年にラジオで新譜「FISH ON」についての話をしていた高田渡を聴いてああ、これなら私もギターを弾けるかもしれない、と思ったのだった。遡ってアルバムをみんな買った。酒の飲み過ぎで体を壊していた彼は90年代半ばに復活。中学の頃、私は『自衛隊に入ろう』が大好きだったな。今の時代にぴったりするんじゃなかろうか、この歌。しかし、「男の中の男」が減っている、かな。最後に歌ったのは『生活の柄』だったとのこと。山之口獏という詩人を知ったのは高田渡の歌から。渡さん、ゆっくり眠ってくださいな。
藤田湘子が亡くなった。昼休に『鷹』同人のTさんについて思い出していたので妙なシンクロニシティに驚く。私は昔、鷹新人俳句スクールネット校に入ったのだった。湘子氏とも一度お会いしている。私の師小澤實は彼の弟子だったが、考えが合わず鷹から抜け、元々小澤實に俳句を教えてもらうつもりで鷹新人スクールに入った私は小澤實のつくった『澤』へとうつった。その際、『鷹』の同人で小澤實の弟子のようであった幾人かは『澤』にゆき、幾人かは様々な事情で『鷹』に残った。Tさんと小澤實の関係は見事なまでに師弟であった。あああれが師弟というものだな、私はあんな関係を持つことはできないな、と感じたのだった。しかしTさんは『鷹』に残った。さぞや苦しい選択であったろう。世の中には苦しい選択がいくつもあるのだよな、なんてことを考えていたのだった。湘子の冥福を祈る。
くらくらと日の燃え落ちし春の雁 藤田湘子
仕事場で行う会への参加申込者がとても少ない。昨日までで一人。鶴舞中央図書館のTさんが申し込んでくれた。もう一人電話があり、今のところ三人。なんとか成り立ちそうではある。内容はかなり面白いのだけれど、タイトルが硬かったのかも知れない。
グランパス対FC東京を寒い中観にゆく。楢崎がPKを防いだとき背中がぞくぞくした。しかし、グランパスの守備は安定していない感じ。主審の柏原丈二はやたらと野次られていた。ま、しかたがないが。Jリーグの一番の課題は審判の水準をあげることではあるまいか。マルケスのきれいなシュートで得た一点を守りきってホーム初勝利。ともあれ勝ってうれしい。
万国博覧会に出かける。雨降りの平日だが、そこそこひとはいた。マンモスラボ、日本館、トヨタ館、カナダ館、JR東海館(超電導ラボは観なかった)、大地の塔などを観た。日本館のナノ・バブルというのが気味悪かった。淡水魚と海水魚を一緒のところに住まわせることができるそうで鯉と鯛が同じ水槽にいた。1945年と2005年の同じ場所の写真が並んでいる展示もあったが、どう観ても2005年のほうがいい←(誤り。1945年のほうがいいに決まっているのにこう書いてしまいました。5月9日に訂正)。環境をテーマにしているのであれば、この100年の間に、どれくらいヒトが住み難くなっていて、それに貢献したのは誰か、今ヒトの環境悪化はどの分野で進んでいるか、などという展示があっても良い気がする。トイレの水がセンサーで出たのにはびっくり。水栓をひねったままだと水が出っぱなしになって資源を浪費するから、と、電気を使うとの思想であろうか。「人類の進歩と調和」なんてテーマを信じていられた70年、子供の私は幸せだったな、としみじみ思った。
BS2の「名探偵モンク2」、邦訳タイトルのせいでトリックが早くからわかってしまった。今日の回はあまり良いできではなかったが。ミステリがわかっていない人がタイトルをつけているのだろうか。NHKに苦情のメールを出す。
名演会館へ『天井棧敷の人々』を観にゆく。館のひとに尋ねてみると名古屋ではミリオン座(今のハートランドがあったところに名画座があったのだった)での上映以来であろうとのこと。81年、19歳の私は一部と二部に別れて上映されたこの映画を観にいったのだった。終わってはじめて翌週二部があると知ったのではなかっただろうか。その待ち遠しかったこと。80年、キネマ旬報の日本公開外国映画史上ベストワンであることは知っていて、しかし、35年も前の映画だよな、と少し軽い気持ちで観ていてうちのめされた。24年ぶりに観て、私はどこをどう観ていたのかな、と自分に驚いた。そしてその年月の重みについても考えたのだった。こういうのが良い映画なのであろう。版権の関係で日本の映画館での上映は今回でおしまいかもしれないとのことなので、観るのならばいまのうちです。
岡田史子の死を知り驚く。67年にデビューし、数年で活動を停止。70年代半ばには伝説の漫画家だった彼女の単行本が朝日ソノラマからはじめて出たのは76年の『ガラス玉』。私が知ったのはそんな時期。独自の、ほかの誰も真似られない世界を持ったマンガを描いたひとでした。ご冥福をいのります。
しばらく前に読んだ『国家の罠』(佐藤優著、新潮社)がとても面白かった。鈴木宗男の運転手と書かれていた著者が日本の運転免許証を持っていない不思議。書かれていない事柄も多いのだろうが、報道とあまりにかけはなれた話に少なからず驚いた。とても論理的、理知的な構成であり、下手なミステリよりわくわくどきどきさせられる本。いくつかの偶然が歴史の必然に結びつくのだな、とそんなことを改めて思った。
このところめっきり酒に弱くなっている。駅から家までどのようにして帰ってきたのか記憶がない。どこかの国会議員のような事件を起こしたりせぬよう気をつけねば。
春なのでノラが深夜に暴れる。もう10歳なのだが。
晩に「サイドウエイズ」を観る。40くらいの男二人のロードムービー。見境なく女に手を出そうとするジャックと離婚して二年になるのに妻を思ってほかの女とつきあわないマイケル。彼ら二人と魅力的な女二人。不思議な友情、それぞれの行く先。ジャックは翌日に立ち直れる性格、マイケルはずっとひきずる性分。私は、ジャックのようだったら良いだろうな、と普段ならば思う質だが、あれはあれでつらそうだ、とこの映画を観て感じたのだった。大笑いする箇所もあり、景色もきれいで、苦みがあって、真っ暗なところがあって、光が差しているとても良い映画。微妙な、描き出しにくい気持ちの動きが画面にあらわれているのが見事。
年度のおしまい。仕事はばたばた。3月9日に書いた国立国語研究所に、仕事の関連の質問で昨日電話をした。今日、実に懇切丁寧な返事をいただいた。一般のひとからの質問にも答えてくださるとのこと。電話で尋ねると折り返し電話をしてもらえるのである。質問の量が気になるところ。
『クライシス・オブ・アメリカ』を観る。陰気な映画。『羊たちの沈黙』のジョナサン・デミ監督なので期待していたのだが、おしまいのあたり必然性のない展開があったり、あいつはそれでどうなったのかな、との疑問があったりしてすっきりしなかった。
いつも行くスーパーマーケットの魚屋の魚が良くなくて高かったので、違うスーパーマーケットへ行く。小鰺が20円、20センチほどのセイゴが80円と安い。カタクチイワシとコウナゴを買う。カタクチイワシはトマトソース煮にし、コウナゴは釘煮にした。しかし20円の鰺は100匹売っても2000円。それは売り上げであって利益ではないわけで、お金儲けは実に大変であるな、としみじみ感じたのだった。それに比べて公務員。世間から叱られてもしかたがない人は確かにいそうですな。私も叱られぬよう、仕事に励まねば。
『ナショナル・トレジャー』を観る。なかなかよくできた娯楽作。おしまいがあっさりしすぎている感じもするが。
『ロングエンゲージメント』を観る。なんとなくどことなく物足りない気分になった。
4連休である。昨日今日と山陰地方へ車で旅行。腰の調子はよくなってきた。島根県の荒神谷遺跡にびっくり。10月に博物館ができるとのことだが、そんなことは知らず、出雲大社へ行った帰りに、聞いたことがある遺跡だな、と寄ってみたのだった。358本もの青銅剣が一箇所で出土したところ。それまで日本中で出た剣の数を抜いてしまった。いったいここはなんだったのであろう。二日とも雨。宍道湖の夕日を見たかったのだが、見事なまでに霞んでいた。
朝、腰が痛くなかったので、名古屋シネマテークに『トニー滝谷』を観にゆく。宮沢りえとイッセイ尾形を観たいがためである。村上春樹の『レキシントンの幽霊』のなかに入っている原作は傑作だ、と一昨日読み返して改めて思った。珍しく書庫から簡単に出てきてくれたのだった。どのように映像化するのだろうか、とかなり興味がわいた。「とても自然にとても優美に服をまとっていた」女。これはほんとうにそういうひとでないと演じられないのかもしれないな、という気がしてしまった。市川準は服を好きなのだろうか。過去に私はこの登場人物に似たひとと会ったことがある。
いくつかの言葉やストーリーが原作に足されていて、そのどれもが原作の持つ美しさに欠けていた。宮沢りえもイッセイ尾形も映画のなかの役者としては素晴らしかったが、原作を読んだときに感じたようななにかを残念ながら私はまったく感じることができなかった。
映画を観たあとで、瑞穂陸上競技場へ行った。グランパスの守りはどうにも不安。攻めは去年よりずっと重厚になっているのだけれども。痛い負け方だった。
腰痛がなかなか治らない。映画の観過ぎであろうか。
大学図書館に勤めていらっしゃる方の論文を読む。実のところそれほど期待せずに読みはじめたところ、かなり面白かった。進んでゆこうとの意図がそこにあったからだと思う。論文を提出するための論文が世には多くある気がする。そうではなく、すぐ先の未来に繋げようとしている姿勢がある論文だったので刺激になった。私は最近未来を思わなくなっているな、と反省。
久しぶりに古い友達と長電話をする。最近毎月の通話料は100円前後。今月分は10倍くらいになりそうだ。携帯電話は私に要りそうもない。しかし、メールチェックというのは中毒性が高いと思う。どこでも携帯電話のメールをがさごそしている若者やおばさんおっさんを見かけると、パソコンのメールが来てるかどうかが気になってしかたがなかった15年ほど前を思い出す。人間のために良いことなのだろうか、と考える私もパソコンメールの来る来ないは今も気になることがらである。
先日お会いしたMさんからメールをいただいた。アメリカの図書館についてのエッセイも読ませてもらった。示唆に富んでいて、私にはたいへん参考になった。
ノラの写真をいくつか載せてみることにする。
レファレンス探検隊。おもしろい問題、調査過程。クイック・レファレンスは「為せばなる為さねばならぬなにごとも」のあとに続く言葉と誰の言葉か、という問題。これ、実際に受けた記憶がおぼろげにある。「為せばなるナセルはアラブの大統領」というのが子どもの頃流行ったのを思い出したが、若い人たちにナセルが通じないな、と考え、人前で言うのを控えた。「ガッツポーズの語源」という問題に対する回答が私には疑問だった。ガッツ石松の勝利のポーズを新聞記者がそう書いたとのことだが、ボクシングを熱心に観ていた私がテレビでその言葉を聞いた記憶がないのだ。もしかすると本当なのかもしれないのだが。試合翌日のスポーツ新聞が保存されている図書館はしかし愛知県内にあるのだろうか。一般紙かもしれない。大変な作業ではある。大学の附属図書館勤務のM氏が国立国語研究所で言葉を集めているので、ここが出している文献を調べるべきだ、との指摘。中小公立図書館からは出てきにくい考え方。国立国語研究所は問い合わせたら教えてくれるのだろうか。どなたがご存知であればお知らせください。メールはこちらまで。
レファレンス探検隊が終わったあと宴会。県図書館の横断検索名称募集の発表の際モリゾーとキッコロの着ぐるみを着たおふたりもいた。臨時職員や嘱託として図書館で働きながら正職員になろうと励んでいたひとが三人職に就けたとのこと。新潟県立、大阪府立、横浜市立。4年半かかったひと3年かかったひと、と大変である。図書館にはなかなか就職できないのだが、図書館でいやいや働いているひとが沢山いるのは、やはりどう考えても変である。図書館法ができて55年経っているというのに我が国では図書館がまともにできている状態ではなく、またこれから先には指定管理者制度の導入も多くの自治体で検討されることとなる。身分がどうなってゆくのか先が見えないというのに、そこで働きたいから、と図書館の世界に身を投じる若者たち。涙が出そうな話である。今図書館にいる司書がしっかりせねばなるまい、と強く思うのであった。
午前、仕事。午後、『ライフ・イズ・コメディ』を観にゆく。ピーター・セラーズの伝記映画。このところ伝記映画がとても多いのではなかろうか。ジェフリー・ラッシュ演じるピーター・セラーズが見事だった。顔立ちや体型は似ていないのだが、観ているうちにピーター・セラーズに見えてくる。『博士の異常な愛情』の車椅子に乗った博士の演技のまま食事をするシーンが最高だった。私の好みの映画。
猫の写真をHPに沢山載せてほしい、との要望がメールであった。このごろはテキストデータばかりをエディタで書いているので、画像をどうやって載っけていたのかを思い出せない私。もうしばらくお待ちください。
Jリーグ開幕である。瑞穂にゆく。ひどい結果であった。怪しげなファールで得たPKで先制し、後半5分、本田からのセンタリングを古賀正紘が見事に決めたヘディングシュートを見たとき、時間が早すぎるかもな、と感じたのであったが、そのいやな予感があたってしまった。2対1になったあとどうするつもりなのかがまるでわからなかったのが引き分けにされた原因であろう。キープならキープ、攻めるなら攻める、とはっきりすべき。もっとも気になるのはディフェンダーが相手を手で引っ張ったり、乗っかかったりしているところ。マークは完全にずれちゃっていたりもしたし。攻撃は良い感じなのだが、これからどうなってゆくのであろうか、グランパス。
休みなので前売を買ってある『ライフ・イズ・コメディ』を観にゆこうとして、映画の日であることを思い出した。先月も映画の日に前売で観たのだった。ひとは学習するものである。そこで、『またの日の知華』をシネマテークに観にいった。これがまるで私のシュミにあわなかった。なんというか生理的にだめ。『ゆきゆきて神軍』の原一男監督なので期待していたのだったが。帰りにちくさ正文館で数冊本を買う。
『ビヨンド・ザ・シー』を観る。ケヴィン・スペイシーがボビー・ダーリンを演じる映画。サンドラ・ディを口説くシーンがとても良かった。『ビヨンド・ザ・シー』って『ラ・メール』だったのですな。筒井康隆さんの『朝のガスパール』でリクエストする夫人が出てくる箇所があったな、と曲を聴いていて古いことを思い出した。ケヴィン・スペイシーの歌のうまさにおどろいた。
紀要の校正をする。新仮名になる前に死んでいる作家なので、元はすべて旧仮名に決まっているのだが、戦後、別のひとの手によってはじめて発表された作品や書簡があり、それらの原稿が紛失したため、全集収録の際には新仮名になっているものがあったり、作家本人の仮名づかいの誤りを全集掲載のとき、「ママ」と振っていないものがあったりして引用されている文章が正しいのかどうかを確認するだけで頭が痛くなってくる。そもそも作家本人が間違えていすぎるのも問題なのだが、なぜこんなに誤りがあるのだろう。かなり有名な作品で生前出版されたもののなかに「ほんたう」が「ほんとう」と誤植されているケースもある。これはそのまま全集に引かれ、「ママ」となっていない。何の註釈もつけずに論文に引用すると、どの時点での誤りかが簡単にはわからなくなっているのだった。また、いくつもの作品を引いた場合、旧仮名と新仮名と本人の誤りと戦前の誤植とが渾然一体となり、読んでいて吐きそうになる。誰かなんとかしてくれえ、と叫び出したくなるような作業であった。60年前の国語改革がいけないのである。なんだか去年もこんなことを書いていた記憶。
明後日から三月だというのに寒い。単車で走っていると手先の感覚がばかになってくる。
朝、愛知県図書館に行き、雑誌記事の閲覧と複写。午後、名古屋大学附属図書館でのワークショップ。「国立国会図書館の資料保存とIFLA/PACアジア地域センターの活動」。国立国会図書館の那須さんのお話はとてもわかりやすかった。酸性紙で作られた資料の脱酸処理の作業はもう少し進んでいるような気がしていたのだが、まだこれからといった感じ。国の財産を守ってゆかねばとの姿勢を強く感じた。媒体変換を進めている資料の著作権処理について質問をしたところ、電子媒体化についてすべて一冊ずつ処理を行っているとの答え。気が遠くなるような仕事。予算が潤沢にあれば、中小図書館も地域資料などについて脱酸処理やマイクロフィルム化、電子媒体化をしてゆくべきなのだが、恐らくどこの市町もそうした状況にない。かなり憂うべき問題だよな、としみじみ考えたりもした私である。
また鍼を打ってもらった。からだのあちこちぼろぼろな感じ。
『不機嫌なジーン』は微妙なやりとりの演出がとても良い。諫早干拓に対する怒りを柔らかく表現しているのに好感を持ってみている。私の好きな故野呂邦暢が守ろうとしてきた干潟。
プレシーズンマッチ、グランパス対大連実徳は見応えのある試合だった。星陵高校から入った本田、流通経済大学から入った杉本、そして北朝鮮代表アルビレックス新潟から安英学、皆良い動きをしていた。得点を挙げた渡邊圭二は去年も出てはいたが、今日はとっても良かった。本田は三本コーナーキックを蹴ったがとてもきれいに曲がる良いボールだった。大連実徳は細かくオフサイドを取ってくるチームで、見事なまでに引っかかっていた。線審はさぞかし大変だったことであろう。グランパスの4バックはまだまだ。古賀、角田、増川、皆相手を押したり引っ張ったり乗っかかったり、と反則ばかり。元々古賀はそういうのが得意だったが、反則を極力せずに相手を抑えることから心がけねばディフェンスは不安なままなのではなかろうか、と思う私は素人なのかな。トーレスはあんまり反則しなかったけど、立派なディフェンスをしていたもの。ともあれ若手に期待できそうな今年のグランパスであった。雨が降っていて寒い日だった。
録画してあった13日放送『ミューズの楽譜』大貫妙子の回を観る。ラジオのトーク番組には時折出ているが、テレビは多分はじめて。ジョニ・ミッチェルの『サークル・ゲーム』を歌っていたのには驚いた。ラジオの番組で、新しい音楽、今までにない音楽を作ろうとしていない若いミュージシャンに対してのいらだちを語っていたことがあったが、このひとは本当はとても怒りっぽいのだと思う。川平慈英が、収録後、「緊張したぁ」と言っていた。大貫妙子は30年以上も音楽と真摯に取り組んできて、ああした姿勢になったのだな、と感じて、私の来し方について少し考えたりもしたのであった。
腰痛である。鍼を打ってもらう。
スーパーで鰯が安かったので、買ってきて鰯団子を作る。あたり鉢であたっていたらまた腰が痛くなってきた。養生せねば、と思う43歳の私。
仕事場に見学にくる小学生たちの様子が学校によってまるで違う。今日午後来た学校はひどかった。図書室で水筒からお茶を出して飲み出したり、通路にかばんをおいたり。通路がふさがると困るでしょ、と注意すると、「あ、そうか」と素直に聞き、ほかの子ども達にも、「ここに置いたらいけないよ」と言って回るくらいの良い子。この学校はどうやら先生がいけないようであった。
福島で「おはようございます」とあいさつをした小学生が若い男に「うるさい」と殴られる事件が起きた。腹だたしい。昨日の寝屋川の事件も理不尽でうんざりするが。アメリカを真似て進んで来た我が国はアメリカと同じような国になってゆくことであろう。
昨晩、急に腰痛になった。朝、多少楽になったが、近所の鍼灸院に行った。根の深いところから出ている痛みなので無理をせぬように、と言われてしまった。手の甲と脇腹に鍼を打たれたのにはびっくり。痛いのは腰なのに、と思ったのだが、痛みが軽くなる不思議。
夕方から『レイ』を観る。名画。映画は映像と音声でできているのだな、などととても当たり前のことを改めて思った。ジェイミー・フォックスはレイ・チャールズにしか見えなかった。うちの近所では今週で打ち切り。三週間しかかからないということである。アカデミー賞で候補になっているのになあ。それにしても伝記映画が多い。アメリカには絵になる人が多いのがうらやましい。日本のミュージシャンだと誰の伝記映画を作れるかななどと考える私。江戸アケミかな。
三連休、ずっと映画を観てしまった。今日は『恍惚』。ファニー・アルダンとド・パルデューとエマニュエル・ベナール。アルダンとド・パルデューはトリュフォーの『隣の女』の恋人同士なわけで、あれから20年。エマニュエル・ベアールは『8人の女たち』の小間使い。痛ましい役でした。静かでエロティックで人間らしくて良い映画。
『ステップフォード・ワイフ』を観る。ニコール・キッドマン目当に決まっている。筋に無理があり、ラスト近くの肝心な箇所もどうだかな、といった感じではあったが、面白かった。とにかくニコール・キッドマンが良い。ベット・ミドラーはすっかり太ったおばさんと化していた。
しばらく前に名古屋にできたアップルストアに行く。最近あまりパソコン屋さんに行かず、情報も拾っていなかったのだが、Macって機種が減ったのかな。突拍子もないデザインのものがあまりなくなったのか、私が慣れてしまったのか。初代iMacのまま、買い替える気もない私なので、そんな風に思えたのかもしれないが。ipodが人気のようで、若い娘さんが、「ああ欲しいっ」と身をよじっていたりして面白かった。1000曲も入れて持ち歩ければ幸せだろうな。私はヘッドホンとかイヤホンの類が体質的に合わないので無理だけれども。
『北の零年』を観た。『きょうのできごと』の行定勲監督だし、石田ゆり子が出てるし、なんだか人気があるみたいだし、と出かけたのだが、百姓にリアリティがなくて、筋に無理があって、歴史的にもどうかなってところもあって、私には駄目だった。香川照之の尻を映画で見たのはこれで三度目。ほかの二作は『美しい夏キリシマ』と『ホテル・ビーナス』だったかな。見事な役者。渡辺謙も石橋蓮司も香川と比較すると影が薄くみえてしまった。
NHK教育の『トップランナー』にハナレグミが出たので観た。話をするときの声は歌よりも細いけれど、印象に強く残る。名前の由来を知らずにいたのだが、目が離れているからだったりして、などと以前テキトーなことを喋っていたのが当たっていたのに驚いた。トークのときに持っていたのがK・ヤイリのギターだったのだろうか。
私がいま働いている文学関係の施設は本の貸し出しをしていない。しかし、資料の提供も主な仕事であるので著作権法31条の範囲内での複写は可能であろう、と念のため文化庁に問うた上でしているのではあるが、ほんっとこの法律厄介。というか30条の附則のからみで整合性がとれていないからなのだが。図書館で働いていたとき、著作権法の説明を毎日のように利用者にしていたのだったな、と改めて思い出してうんざり。図書館だけで複写が可能なんだよ、よかったねって感じではじまった法律がコピー機の普及によってコンビニエンスストアならばできるのに、なぜか図書館だとコピーができない、といったふうに変わっちゃった、そんな感じの法律。と、それはさておき。閉館時間近くに、女子高生が閲覧室で資料を書き写していたので、コピーもできますよ、と声をかけると、「マジすか?」と訊かれた。図書館と違って研究者や学校の先生といった人とのやりとりが多い職場なので、久しぶりにこうした言葉を耳にし、一瞬「マジ須賀小六」などとつまらぬ駄洒落が頭に浮かんだりもしたのだが、気を取り直し、コピーが必要な箇所を確認すると、31条の規定にあてはまるかどうかが微妙。作品解説がいくつか載っていて、そのうちの一つ、ということなので、解説すべてをひとかたまりにして一著作と解釈しちゃえば半分未満なので可能だが、一つの作品解説を一著作と考えると著作すべてとなってしまい不可。でも、多分どこの図書館でもそんな風に悩まないだろうな、と思い、複写を許可。ね、こんなことで悩まないでしょ、全国の図書館員よ。でも、一件ずつ、こうやって検討すべき、というのが著作権法の精神であろうし、それは正しい、と私は考えるのだけれど、文化庁っていうか、国はそんなこと求めてないよね、公貸権を最近主張しはじめた権利者はどうなのか。他の国ではすでにシステムもできていたりするわけだけれども。なんというか国全体の文化についての考えがないっていうか、そんなことをずっと感じている私。
立春。日がかなり長くなってきているな、と仕事が終わって外に出て感じる。しかしまだまだ寒い。仕事場のひとがインフルエンザでひとり倒れたりもしている。
愛知県図書館では図書館探検ツアーという企画があるそうだ。あそこのなかは広くて謎に満ちているので近隣の図書館好きの人は出かけてみてはどうだろう。
10ヶ月ぶりにステレオアンプが修理からかえってきた。部品がないので電気屋のおじさんが苦労たとのこと。その間借りていたアンプもなかなか悪くない、と思っていたが、妻よりもつきあいの長いアンプはやはり私の好みの音であった、と改めてしみじみ感じたのであった。直らなかったら真空管アンプに買い替えようか、とかあれこれ考えたりもしたのだが、直って良かった。
猫のノラは変わった鳴き方をするようになった。にゃにゃにゃにゃにゃおーん、などと難しいことを言う。でも言ってる意味はよくわからない。
雪が積もっていた。これくらいならば大きな道の雪は溶けているだろう、とチェーンも巻かず、車検中の代車で出かけたところ時折滑った。道に横になっている車が3台いて通れなくなっている場所があったので引き返して違う道を走ったりしながらなんとか職場に着いた。明日は立春。
『イブラヒムおじさんとコーランの花』を観る。お客さんがとても多いので、大人気の映画なのかな、と思ったのだったが、今日は映画の日だった。私は1500円の前売を買っていたので損をしてしまった。う。オマー・シャリフが上手いのはわかりきっているが、主役の男の子も娼婦のひとたちもとても良かった。きれいな映像。でも、私の好きな映画ではなかった。
『パッチギ』を観る。傑作。上映館が少なく、上映回数も多くないようなので、早めに観ておかないと終わってしまう危険あり。しかし、気になった箇所がいくつか。『スワンの涙』は私が小学一年生のおしまいの方に流行った記憶があるので(その前に流行った『ガールフレンド』のレコードは持っている。従姉がGS気違いだったので、わけもわからず赤松愛だの野口ヒデトだのといった名前を覚えさせられたりもしたのだった。物心つかぬ頃からGSを聴かされていた私)確かめたところ発売は1968年12月5日。1968年の春か秋の話なので曲が合わない、と感じてしまった私は細かい性格ではある。赤松愛を真似てマッシュルームカットにしたのに、カーナビーツのアイ高野の歌を持ってきたのはどうか、と感じたのは私だけであろうか。と、これもとても細かい話。もひとつ。モハメド・アリの徴兵忌避の話題が出たのだが、この時期、日本での彼の名前はカシアス・クレイ。モハメド・アリではない。カシアス・クレイがモハメド・アリに変わっちゃったときびっくりした記憶が私より上の世代にはあるはずだが。江戸時代の考証について細かな点をつつくおじさんが昔いて、ああそんなこと別にどうだっていいじゃん、と子どもの頃には思っていたものだが、自分が息をしているときの映画となると、変なことにひっかかってしまいますな。と、小さな瑕疵を惜しい、と思えるのはとてもできが良い映画だからなのでした。今年一本だけ観る、というひとはこれを観るべきです。
ハナレグミの新譜『帰ってから歌いたくなってもいいようにと思ったのだ』を仕事の帰りに買ったのだった。自宅録音とのことで、なつかしくあたたかい感じの音。ハナレグミの声は幾度か聴いていると癖になるのであった。ジャケットにK・ヤイリって書かれているけれど、写真がなさそう。実は我が家のギターもK・ヤイリなので気になる。くるりの『男の子と女の子』のカヴァーがとっても良い間合いで歌われていて、気に入ってしまった。ペダルスティールギターなどで参加している高田漣の名を見ると、あの漣くんが大きくなったのだなあ、と70年代半ばにフォーク少年だった私はしみじみ思ってしまったり。漣くんの名は中川五郎の『飛行機事故で死にたくない』に歌われていたりもしたっけ。このハナレグミのアルバムで一番好きなのは『明日へゆけ』かな。
クラブには高校生は入れないんだっけ、とクラブのHPを読んで思うのであった。身分証チェックをしてるというのは世間に向けた広報かな。それよりもここ10年くらい、ライブに行ってコワいのはクスリをしてる人たち。私に関わりのないところであれこれしてくれていれば良いのだけれど、ふらふらとぶつかったり、ヘンな目つきで睨まれたり、奇声をあげるべきでないところで叫んだりされると鬱陶しいのであった。おまわりさんがライブハウスやクラブに潜むようになったらヤだなあ。って、そういうことは起きてきているのであろうか。
先週はいろいろなことがあったのに、日記を書かずにいた。火曜には『ターミナル』を観た。おしまいの15分くらいがなんとかなっていれば傑作だったろうに、いくらなんでもそれはないんじゃないの、と観終えて思ったのだった。水曜に金沢へ行ってきた。はじめての町。朝早いバスに乗り、夕方帰ってきた。日帰りをするには少し遠かった。目的は泉鏡花記念館の生田コレクション展。きれいな初版本がずらりとならんでいるのかな、と想像していたら、後藤宙外宛書簡と葉書が主な展示物だった。でも、ほかの展示室には本もたくさんあったし、なかなか良い展示がされていた。周遊バスの一日周遊券というのを使い、兼六園、室生犀星記念館、近代文学館をまわった。雪が降ったりやんだりの寒い日だった。
会場と時間を間違えてライブに行った。着いたときには見事に終わっていた。そんな経験をしてひとは大人になってゆくのであろうか。って、私はもう充分に大人だが。
ようやくこたつを出した。
猫のノラは人間がこたつ布団をめくってやらないと入らなくなった。歳とともに段々わがままになってゆく。
タワーレコードで銀杏ボーイズのCDを二枚買ったらクリアファイルをもらえた。江口寿史のイラストがうれしい。そいえば私の名前が『すすめ!パイレーツ』のはじめの単行本(ジャンプコミックス)に載ってる話はここに書いたっけ。と、古いことを少し自慢してみたりして。銀杏ボーイズは『アイデン&ティティ』で主役をしてた峯田和伸がいるバンド。過激とかわいらしさが一緒になってるのは珍しい。
蜷川幸雄演出『ロミオとジュリエット』を観にゆく。藤原竜也はますます良くなってきた。これからどう進んでゆくのかわくわくする。。鈴木杏はときどきセリフが早くなったりしたが、声が大きくて動きがよくて観ていてうれしかった。とてもしっかりとした見事な芝居だった。
「新潮」2月号、車谷長吉の『凡庸な私小説作家廃業宣言』には驚いた。あの、斎藤愼爾について書かれた箇所にも驚いたけれども。次はどんな作品を読ませてもらえるのであろうか。絲山秋子の『愛なんかいらねー』を読んで、「自由」なんて言葉を久しぶりに思い出した。
『ボン・ヴォヤージュ』を観る。イザベラ・アジャーニはこの映画を撮ったとき48歳。若い頃とほとんど変わっていないのが怖い。やや太ったが。ド・パルデュー、ヴィルジニー・ルドワイヤン、イヴァン・アタルと豪華なキャスト。新人のグレゴリ・デランジェールもとても良かった。話は無茶なところや淡白な箇所もあったが、私は好き。イザベラ・アジャーニとヴィルジニー・ルドワイヤンが出るってだけで観にゆくわけだけれども。
新潮別冊「名短篇」に廣津和郎の『崖』が載っていて、和郎の柳浪が知多半島の師崎で療養していたことを知り、気になって和郎の自伝『年月のあしおと』を読みはじめる。「泉鏡花と雨蛙」の章が面白い。読みかけの本が沢山あるのに、ほかの本に手を出してしまう癖をなんとかしてゆきたい今年の私である。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。
今年の読み初めは三島由紀夫の『小説とは何か』。読みたいなと思っていながら機会がなかったこの本の初版を古本屋さんで暮れに100円で入手したのだった。名著。このところ難解で厚い本を読み初めに選ぶだめ、なかなか読み進めず泣きそうな一月になることが続いたのだが、短くて充実した良い本に出会うことができた。良い一年になりそうな予感。
観初めは『五線譜のラブレター』。さすがに今日は空いていた。名演会館ではぜんざいをふるまっていた。映画館で初めて見る光景。コール・ポーターの伝記映画。彼のナンバーをエルヴィス・コステロ、シェリル・クロウ、アラニス・モリセット、ナタリー・コールらが歌うのはとても良かったけれども、音が出た瞬間に背中がぞくりとくるところが私にはなかったのが残念。
『バッド・サンタ』は良かった。次はこうなるのかな、との予想を超えてゆく展開が楽しい。汚い言葉だらけだけれども。ビリー・ボブ・ソーントンは『シンプル・プラン』のお兄さん役で初めて見て、なんてうまいんだろう、と思ったのだけれど、今回のアル中のサンタさん役も見事。
私は渋滞が大嫌いなので、できるだけ巻き込まれぬようにしているし、単車で行けるときはできるだけ単車に乗っているのだが、今日はしっかり巻き込まれた。イヴだったのだった。
先日、『僕の彼女を紹介します』を観た。前半はとても良かったのだけれども、後半はいまひとつ。
黄斑部変性の疑いが出て以来買おうと思っていた黄色いレンズの眼鏡を購入。前にかけていたフレームにレンズだけ入れてもらった。この眼鏡でパソコンを観るととても楽な気がする。
大きな仕事が終わったので、平穏。せねばならぬことは沢山あるのだが。
日本対ドイツ戦、完敗。観ていて厭だったのはベンチでの大久保が笑っていたところ。1点差でチームが負けている状態で何の話をしていたのかは知らないが、そういうことで良いのだろうか。負けたあと、悔しそうにしている選手より、にこやかな選手のほうが多かったのはどういうわけだろうか。楢崎はめちゃめちゃ悔しそうだったけれども。果たして日本はワールドカップに出られるのか。出たとして、どこまで進めるのか。心配である。
愛知県勤労会館にエルヴィス・コステロを観にゆく。はじめからほとんどの客が立っていた。50歳のイギリス人はとても元気。西洋人と戦争しても勝てるはずがないのだよな、とわけのわからないことをふと思う。でかい声、良い歌。隣の隣の席にいたひとがその後ろの親爺に言いがかりをつけられていた。「前の人もその前の人も坐っているのだから坐れ」と。渋々坐っていて気の毒だったので、これからアンコール、という時に、空いていた隣の席を勧めた。不自由なルールを勝手に押しつける人はロックなど聴くべきではない、と思う。坐って観たければ一番前の席を確保すべきだし、自分のルールを強要するのであれば、前の前の前の席のひとにもその前のひとにもさらに前のひとにもずっと文句を言ってゆくべき。「助かりました。もう少しで台無しになってしまうところでした」とお礼を言われた。時間を作ってお金をかけて何年かに一度のイヴェントにやってきて、わけのわからぬ他人のルールの強制で不愉快にさせられたのではたまらないものなあ。どこにでもくだらないひとはいる。そんなつまらぬ事件など吹き飛ぶとても良いライブであった。
愛知県勤労会館に矢野顕子を観にゆく。再来年で30年になるそうだ。『ジャパニーズ・ガール』が出てから28年も経っているのか、とびっくり。落ち着いた良いコンサートだった。
愛知県図書館が横断検索の愛称をWebで募集しているので応募。
小林信彦の『袋小路の休日』が講談社文芸文庫に入っているのをしばらく前に買った。単行本も中公文庫も持っているのだが、年譜が最新になっているのと著者から読者へという文章が載っているのと坪内祐三の解説がついているのでつい買ってしまった。菊池信義の装丁が美しい。この文庫、値段が高く、いつ無くなっちゃうかな、とはじめのころには心配していたのだが、長く続いていてうれしい。講談社は偉い。
少し前に観た『お父さんのバックドロップ』は良い映画だった。涙腺がゆるい最近の私は少し泣いてしまったのであった。
今日は『スカイキャプテン』を観た。昔ながらのアメリカ娯楽映画といった感じ。ラジオ・シティ・ホールで『オズの魔法使い』がかかっているシーンが良かった。
夜、なごやレファレンス探検隊。私がテキトーにつくった問題を調べてもらったのに対し、解説をする。こんな問題。
きれいとは言い難い作業着を着、日焼した60歳くらいのおじさんがやってきた。
「わしんとこへなんとかクラブのヤツがやってきてよ。わしの土地になにやらをどうのと言うんじゃ。ちょうど腹がすいとって機嫌が悪かったから、『きゃあってけ』って追っ払ってやったんじゃ。んでも、落ち着いて考えたらむこうは紳士だったし、わりいことしちゃったかな、と思うんだけど、持ってきた名刺もやぶいちゃったしどうしたらええかな、にいちゃん」
「何をしにいらしたんでしょうね」
「わしのじしょに、なにか建てたいとかって言っとったぞ」
「クラブの名前はわかりませんか」
「「ロ」がついたな。「ラ」だったかな。それがどんなもんかがわかるといいが」
このあと、何を尋ね、会話がどう展開し、最後にどのような答えを利用者に与えるか、がポイント。よくない調べ方としては、思いつきそうなクラブ名に拘泥してしまい、幅を狭めてしまう仕方。五人の回答者はとても上手に対処していて、私が解説するまでもない感じであり、すぐに済んでしまった。司会者のF本さんに、「え、もう」と言われ、時計を見るとあまり時間が経っていず、四方山話でお茶を濁した。ほかのふたりの発表者はとても真面目で綿密に調べており、資料もふんだんに用意していた。初めての試練とは言え、少し反省。次回は名誉回復せねば。
会が終わった後の食事会での話題は重く苦しいものが多かった。PFI図書館の話、指定管理者制度のことなど。委託をされた図書館では直営の際、検討し、引き継ぎをしておいた動線を無視した配架になっている、と、以前その館でアルバイトをしていた人が言っていた。PFI図書館での、利用者と職員のやりとりを聞いていたら、「にったじろう、というひとはいません」と職員が言っていたとのこと。本屋さんの関係の会社が運営しているのだけれども。別の職員が出てきたので安心したら、「新しいひとですよね」と言った、という。ま、しかし、直営の図書館でも、「こうだろはんの、『ろはん』ってどういう字ですか」と言われた友人がいるので、PFIとか指定管理化による問題とも言い切れないが、自治体はいったいなにをつくろうとしているのだろうな。魚の名前を知らない魚屋とか、自社の車の性能を知らずに売ってる販売店とか、「今日の日替ランチはなんですか」と訊くと、「さあ」と答えて動こうともしない店員を使ってる食べ物屋とかさ、そういうところに多くの人が行きたいのだろうか。扱っているものについての知識を沢山もつ人が働いていないケースがこのところ多いけれども、今の世はそれでいいってことになっているのかな。それは働いていることにならないのではなかろうか。金をもらっちゃまずいひとがそこになんとなく居るって話なのだが、賃金安いんだからしょうがないじゃん、それで大勢のひともいいって思ってるんだし、っていう風に済んでゆくのだろうか。かもね。司書を敵視するかのようなメールを時々行政のひとからいただいたりするけれど、やっかみが入ってるんじゃないか、と思われる時も実はある。専門的な知識って言ったって大したことないじゃないか。長く勤めていれば本の名前なんて覚えられるに決まっている、などと書いた人もいた。本って結構沢山あるし、書いてる人もいっぱいあるのだが。10万冊以上の蔵書のある館であれば、所蔵するのすべての本のタイトル、著者名を覚えられるひとはいまい。でも、なるべく沢山覚えよう、と意識していなければ覚えられるものではない。また、過去何十年かのベストセラーのタイトル、とか、有名な賞を取った小説とかは覚える気で覚えるのである。それが世間的に何の役に立つか、と問われたら、多分ほとんど役に立たないんだけれども、図書館の中では、図書館にやってきて質問をするひとに対してはかなり為になっている。市民のうち、図書館に何人が来て、そのうち何人が質問をするのか、そんなことのために税金を使っていいのか、と言われてしまう日がやってきているのだが、そこでお金を削ると、ひいては地域や国の中身を削っちゃうのかもしれない、と私は感じる。苦労して身につけた知識、技術が生かせない状況になる職種は過去にも沢山あった。司書はしかし、まだまだ使えるはずである。司書は、どう利用できるか、なにができるか、いかに使ってもらえるようにするか、をしっかり考えて日々過ごすべきであろう。もう、すでに存在を否定する流れがやってきているのだから。
アルビレックス対ドリームチームをテレビで観る。被災した地域の子ども達は喜んで観ただろうか。前の日からうれしくて眠れなかったと言っていた子がいた。得点がなかったのが残念。それにしても新潟はこれからいよいよ寒いだろうな。
ぼんやりしていると、いろいろなことに慣れている。私の勤め先にはあちこちの小学校から見学者が来るのだが、建物の中を走ったり、大きな声で話したり、展示物に触れたりといったことが日常茶飯事になっている。そうではない学校もたまにあるが。先生は疲れているのか、ロビーで腰掛け、先生同士で話をしていたりする。児童に注意をする気など頭っからない先生もいる。図書館の見学も、「自由行動の時間を設けたい」とか「働いている人に質問をしたい」との希望があったりしたが、利用者がいる時には断ったり、時間の制限をしていたのだが、今の勤務先ではそういう質問もされず、勝手に自由時間となり、すさまじい状況になっている。まじめに調べものをしている子どもも中にはいるが、考えてみれば、大きな平仮名しか書けない年齢の子どもが壁に紙をあててあれこれ書かせるってこと自体、無理がありはしないか。私が小学生のときの社会見学は先生の後ろを金魚のうんこのようにくっついてゆき、そこを引き上げ、バスのなかで何かを書いたのではなかったか。或いは翌日の学校で作文を書いたり。小学生の見学の日にたまたまやってきてしまった一般客は不幸である。文化施設を自由見学することよりも、ほかの人に迷惑をかけないように行動することを学んだほうが良い、と考えるのは私だけだろうか。ある作家について知らずとも大したことにはならないが、大勢で公共施設にどかどかと来て騒いだって別に構うことはない、という感覚が身についてしまうのは大したことのように思う。小学校の先生はきっと疲れているはずだ。幼児をほったらかしにする親が育てた子どもの世話をしているのだから。ところで、こうした子ども達はこれから先どうなってゆくのか。学級崩壊という言葉さえ聞かなくなってきたのは、それが普通になってしまったからであり、いずれ国ごと崩壊したってしょうがないや、だって家庭教育がめちゃめちゃなのだから、と教育現場で諦められてしまっていたりしてね。お金があり余るほどあったとしたら、国を捨てて、よそで住みたいな、なんて、友達とたまに会うと淋しい話をしたりする。
気がつけば最後に日記を書いてから2週間ほど経っている。時の流れは恐ろしい。
先週、「ハウルの動く城」を観た。お城の動きがかわいくて面白い。キャラクターも個性的で魅力的。でも、失敗作ですな。いろいろな『なぜ』が残ってしまう。脈絡がおかしかったりもする。けれども宮崎駿は失敗作でさえ見事な出来映え。
近所に変梃なオーディオ関連の店がある、と出かけてみたら通信販売専門の、かなりマニアックなところであることが判明。思えば通信販売とか卸しの店が我が家のそばには多いようである。それらしい展示がしてないからヘンだな、と思って入ってみてはじめてわかる。インターネットで調べるとかなり有名な店。今年中の予約が一杯とのことで年明けに試聴にゆくことにした。何かを買うかどうかは聴いてみないとわからない。
帰宅後、ハル・ベリー見たさに「キャット・ウーマン」を観に出かける。客が私を含め五人しかいなかった。筋に無茶な箇所があるが、ハル・ベリーとシャロン・ストーンがとても良かった。
このところオーディオが気になりだした。20年ぶりのことなので、何がなにやらさっぱりわからないところから少しずつ調べている。パワーアンプが毀れ、CDLDプレーヤーが毀れかけており、借り物のアンプで聴いているのだが、振動の影響を受けぬようにと隣の部屋に置いてあるあれこれを普段の部屋に持ってきて20年前に買ったスピーカケーブルにかえたりなどしていた。今日、思い切ってCDプレーヤーを買った。いやはや値段だけのことはある。よく聴いているCDから今まで出ていなかった音がいっぱい出てきてうれしい。しかし結線どころか電源コンセントも簡単に差せないような汚い部屋をなんとかせねば、不思議な体勢で作業をすることとなる。どこから片づければ良いかわからぬ部屋と化しているな、としみじみ思った。
昨日『笑の大学』、今日『父と暮らせば』を観る。どちらも元々舞台の作品。どちらも戦争を扱った映画。『笑の大学』は良い映画だった。『父と暮らせば』は傑作。多くの人が観るべき。せりふのある役者は3人しかいないのに多くの人の声が聞こえる。宮沢りえの上手さに驚く。図書館員の役。いろいろな国の人が観ると良いのだが。
ハ・ジンの『狂気』を読む。評をいくつか読んで期待していたのだが、途中までは私にとってそれほどおもしろくなかった。おしまいに近づいて段々すごいことになってきて止まらなくなってくる。読み終えて、おお、とため息が出た。これはビルドゥングス・ロマンなのかな。
ひとと、ひと以外のおおきなものとの関わり方についてのものばかりに接しているこの頃である。しかし、そろそろ真剣にいろいろなことを考えてゆかねばらならないのだよな、と思う。
11月になったのに暑い。
天災は恐ろしい。突然来るのだから困る。それまで当然だと思っていた暮らしがすべて毀れてしまう。
先日、久しぶりに朝のJRに乗ったら、床に女子高生が坐っていた。男子高生は数年前から坐っていたが、女子高生は初めてみた。椅子はがらがらなのに不思議。念入りに化粧をしている。まるで夜の商売の人の出勤前であるが、彼女らは電車のなかで化粧しないだろう。いろいろこまかなところで、ヘンな状況になっているのに、新聞、テレビは何も報じない。愛知県地方だけの現象なのかな。「親の顔が見たい」ってのは死語になっているのであろうか。あろうな。いまから五年後十年後がとても怖い。そんなとき、図書館がどうのと考えたり語ったりすることに果たして意味はあるのか、などとふと思う。
こんな事件があったことを、とある司書のひとがメールで教えてくださった。図書館員は命の危険を感じる場合がしばしばある。酔っぱらい、ホームレス、刃物を持ったひと、精神を病んだひとは突然やってくる。逆上させてはならないひとを逆上させてしまうケースもあったりする。いかにそうしたひとと接するかも図書館員の腕ではある。柔らかく、時には毅然と応対し、なんとか暴れずにいてもらうようにする。でも酔っぱらいには話が通じないこともしばしば。寝込んじゃうひとなんてのもいる。幸い吐かれたことはなかったけれども。かなり難しいし、無理な場合もしばしば。帰ってくれたか、とほっとしていたら、家に刃物を取りに帰って刺しにやってくるってのはやだな。応対がどうこうじゃないような気がする。酒気帯びの方は一切入館禁止、としている図書館ってあるのだろうか。私が働いていた図書館は日曜の朝から飲んだお父さんたちがいっぱいやってきていたが。
グランパス対ジェフはひどい試合。シャツ一枚で出かけたらとても寒かった。二点目を取られてから、もう真剣に試合をする気がなくなってる感じがとても厭だった。
朝、「恋の門」を観る。面白いようないきすぎのような。松田龍平はとても良かったけれども、私はそれほど好きと言い切れない映画であった。
今年は颱風が多すぎる。真横に降る雨が雨戸とサッシを越えて部屋のなかに少し入った。
今週はBS2でトリュフォーの特集をしていてうれしい。
「平凡パンチ1964」(赤木洋一著、平凡社新書)は面白かった。バブルの時期、マガジンハウスの冬のボーナスの額がものすごかった記憶があるが、平凡出版の時代も不思議な会社だったのだなとわかる。タクシーチケットの使われ方の話が恐ろしい。平凡パンチが高田賢三、金子功らとこんなに早くから関わっていたとは知らなかった。「ヒッチコックマガジン」に影響を受けたという話を読んだことがあったが、そうではなかったのであろうか。個人的には著者が中原弓彦に会うくだりが興味深かった。時代の空気がよく伝わる一冊。
昔は失言で辞任した大臣がいたが、今はそうしたことがなくなったらしい。謝罪もせず、撤回もせず、済んでゆく。言葉の値打ちが下がっているのか、国民の感覚が鈍くなったのか。自分ちにヘリコプターが落ちてきて、屋根が少ししか崩れなかったとして、「パイロットの運転が上手くて助かった」と感じるひとばかりではあるまいに。よその事件だと考えているうちに、すぐ目の前にいろんなことがやってくるのではあるまいか。日本の主権を侵害されたのである。北朝鮮に侵害されると腹を立て、アメリカに侵害されても平気だという感覚はどうなのだろ。
また颱風がやってくる。
BS1で流れている香港のテレビ番組をぼんやり見ていたら、日本の憲法改正について討論をしていた。他国の人から日本がどのように思われているのかがわかって興味深かった。かなり誤解されている気もするが、されてもしょうがない気もする。
最近よく「日米同盟」という言葉を見たり聞いたりするが、そんな同盟あったんだっけ。どうも時代についてゆけなくなっている私である。
童話賞の一次審査が昨日終わった。ふう。
いがらしみきおの「SINK」をWebで読む。最終回だった。生まれてから読んだなかでいちばん怖いマンガだな、と単行本を読んで思ったが、終わってみると今の世の中のほうがずっと怖い気がする。日常の奇妙な違和感を見事に形にした作品。いがらしみきおは天才だ、と改めて感じた。。
目の検査。「瞳孔を開く目薬をさしますね。五時間くらいものが見えにくくなります」と言われる。検査結果は黄斑部変性はあるけれど、ドライなので、すぐに進んだりといったことはないとのこと。一安心。病院の外に出ると光がまぶしく、帰宅後本を読もうとしても厳しく、しかたがないので昼寝をして過ごしたのであった。目を大事にせねばと改めて思った。
ナビスコカップ準決勝。グランパスは浦和レッズに見事に破れた。田中達也はどうして代表に召集されていなかったのであろうか。ジーコがいかんと思う。山田も永井も都築も代表に選んでおいてくれたらグランパスも勝てたかもしれないのになあ。と、ひとのせいにする私。颱風の日だったらもしかしたら、って、普通じゃ勝てないということか。ううむ。
大雨警報と暴風警報が出たため休館。以前は開館していたけれど、来館したため事故に遭う人がいるといけないとの配慮から最近、そうした自治体が増えているのであった。確かに颱風の日に出歩くのは危ない。職員は普段の仕事をし、颱風がおさまってから建物内外の被害状況を見にゆく。幸い大きな被害はなかった。被害に遭った地域の方々、お見舞い申しあげます。
貫禄というものについてふと考える。一昨日お会いしたYさんは私より一学年下なのにとても堂々としている。35歳のMさんは私より落ち着いて見える。ま、しかし、ATTTのTさんは45歳で、偉い人だけれど落ち着いて見えないので安心。ふうむ。
『新潮』11月号、坪内祐三の『福田章二論』が面白かった。「(つづく)」となっていたのが残念だが。高校生の頃、『喪失』を読んだ時間を思い出す。
なごやレファレンス探検隊に出席。日間賀島でデビューしたフォークデュオATTT(あたたた)のTさんが作詞作曲をした「レファレンス探検隊の歌」をご自身で弾き語り。私にも要請があったのだが、ギターを持って歩くのが億劫だったので断ったのだった。きれいなメロディラインの良い歌。
私が見事にしくじった調べものにしっかりと答えを出している若者達がいた。コンピュータを使わずに調べよう、と決めたところまではともかく、雑誌記事索引は使うべきだったかなと反省。
名古屋の図書館に勤めるYさんの短い講演があった。レファレンスの記録を4冊印刷製本した際のエピソードなど。その冊子を目にしたとき、よくまとめているな、感心した覚えがあった。この人とはどこかで会った気がするな、と感じていたのだが、まるで思い出せない。あとで尋ねたら、一昨年、県のレファレンス講習講師を彼もしていて、打ち上げで話をしたとのこと。たった2年前なのにほぼ忘れている。以前から男の人と会った記憶を頭からはじいてしまう傾向があったが、それがますます進んでいるのかもしれない。ATTTのTさんに、「最近物忘れはどうですか」と尋ねると、「ひどい」、と答えていらした。物忘れを悪化させないようにするにはどうしたら良いのであろうか。
なごやレファレンス探検隊のあとの宴会で、珍しく図書館の話をしていた私。Yさんがいらしたので真面目なふりをしようとしていた、ということもあるが、先日いただいたメールにかなり衝撃を受けていたのであろう。
終電に乗り遅れタクシーで帰宅。運転手が女のひとで、日本で徴兵制が敷かれるかも、などといった話題になったところ、「私は断じて阻止します。もしそれで罪になり、牢に入れられたとしても戦争には行かせません」と力説していた。大きな力が動いているかのような気がしてしまう昨今であるが、多くのひとが、それは厭だから絶対そうはならぬようにする、という意志が強く働けば方向は片側だけに傾くってわけでもないのだよな、などと思う。兵隊が沢山要る状況を作ろうとしているかのようなこの頃なのだけれども、それが止まる感じがしていないのだけれども、息子を、家族を戦争にとられたくない、と思うひとはもちろん普通に大勢いるのだ、と当たり前のことに気づいた私であった。
行政職から図書館へ無理矢理異動させられた経験のある方からメールをいただいた。その図書館には司書もいて、司書が一般行政職を敵視し、司書が不当な差別を受けているといった内容の不満を始終述べていたらしい。司書職制度が敷かれていたのが毀れ、一般行政職も司書と同じ内容の仕事をするようになっていたとのこと。彼のメールの内容を六掛けくらいと思って読んでもそこの司書は悪すぎるように感じた。しかし、それが日本全国の図書館の普通の姿であると思い込まれては困る。図書館関連の雑誌に司書職制についての記事が載ったとき、一般行政職すべてが司書にとって敵であるかのように書かれた場合もしばしばあった。私のHPに私はそうは書いていないつもりであったが、そのように読まれたようである。司書の専門性についてわかろうとしない一般行政職もいるし、わかってくれるひともある。一般行政職すべてを敵だと考える司書も多分いるだろう。メールには数年図書館で働いたが、司書に専門性があるように思えなかったとも書かれていた。それはその図書館の司書の責任であろう。質と量の充実した図書館の仕事を専門性の高いヴェテランの司書が日常的に行っている横で数年働けば、異動が頻繁に行われる一般職にこの仕事は難しい、と感じられるはずである。そう思わせなければ専門職ではない。高い専門性を持つ司書がその図書館において必要かどうかを彼がどのように判断するのかは司書の責任ではないだろうが、少なくとも司書は調べもののプロであり、利用者の役に立つ場面もしばしばあるのだな、と感じさせなくてはならないはずである。一般行政職のひとの話すべてを否定し、それは司書の仕事ではない、などと傲慢なことを言っているばかりであれば、司書など要らぬ、と感じて役所に戻ってゆく人が増え、その町における司書職制度復活はあり得なくなる。敵視するばかりでなく、理解を求めようとはせねばなるまい。
司書の専門性は本を読まない人、調べものをしない人にとっては一切何の役にも立たない。言い換えれば、多くの人には、ほぼ無価値無意味な専門性である。司書はそのことを自覚する必要があると私は思う。司書なんてちっとも偉くないのだ。どんな本のどこに何が書かれているか、とか、ある作家の著作に何があり、書架のどこに並んでいるかを知っていたって、ほとんど意味はないのである。その無意味に近い存在にも図書館においては価値があるのだ、とわかってもらわねばならない。欧米やアジアの一部の国では図書館ができた途端、司書の重要性に人々が気づき、高い地位にいるわけだが、日本ではそうはならず、いまもそのまま、いや、50年前より専門職としての司書の位置は多分下がっているのである。自分たちで下げた一面もあるはずだ。我が国の図書館活動は今さらこの時点から「本を読む人、調べものをする人にとって司書はどうやら必要らしい」と多くの人に感じさせるところからはじまるのであろう。これまでの図書館の運動はどこか間違っていたのだと思う。身内だけに向けてあれこれ言ったり、狭いところに敵を作ったりしていただけで、大きな世界に対して誤解されたまま動いてきていたのでなかろうか。国の「文化」についての認識の問題も大きいが、今後図書館をどのようにし、そのために何から手をつけるべきかを図書館に関わる人々は広い視点からしっかり捉え直さねばなるまいな、などと今更ながら思った私であった。
グランパス対FC東京戦を豊田スタジアムに観にゆく。ピッチが悪すぎる。普通にドリブルしていて転ぶ選手が幾人もいる。岡田正義さんは何とかした方がよいと思う。もう歳なのかも。Jリーグは審判をどうにかしないと未来がない気がする。グランパス、攻めきれず、守りきれず。1対1。第二ステージの優勝は絶望的。
山田風太郎の「同日同刻」を読む。原子爆弾を落とされた日について日本人は忘れすぎていないかと思う。山本夏彦が原爆被害の写真を小型飛行機でニューヨークなどにまいてはどうか、と幾度か書いていたが、あの爆弾の凄まじさを全世界に知らせる必要は今なおあると私は感じる。いずれどこかでまた使われるであろう今。私に何かできるかを考えねば。
人間ドックで黄斑部変性の疑い、というのが出た。眼の検査はおまけみたいなもの、となんとなく思っていたので驚いた。再来週検査を受けることにした。普通に見えているので、なんということはなかろう、と調べずにいたのだが、調べたらかなり怖い病。手術を受けると、ものが二重に見える場合がある、との箇所を読んだときは、「ほお、おっぱいが四つに見えるわけだな」などとテキトーなことを考えていたのだが、失明の率が高いとも書かれているのであった。とっても小さい字を読むとき、片目にして読まないと読めなくなっていて、老眼がはじまったのかな、と思っていたのだが、ううむなんだか深刻な気分になりつつある私。ともあれ検査を待たねば。
研修。面白いのだが、午後、少し睡魔に襲われたりしてきつかった。歳なのだな、と思う。
愛知県のとある図書館で利用者のメールアドレスが流出した事件が数日前に起きたとのこと。あちこちの団体、会社等からメールアドレスは流出していて、私も一度被害にあったが、図書館からってのは困る。どのメールアドレスの人が図書館にメールアドレスを登録しているのかが、ほかの図書館利用者にわかってしまうのはかなり怖い。いろいろと想像すると段々怖くなってくる怖さ。BCCではなくCCに入れてしまったというわかりやすいミス。あってはならないことである。
「アイ・ロボット」を観る。よくできた映画。ロボットたちがかわいい。
このところ、知り合いからのメールや、ふつうのひとからのメールがほとんどこない。「セックスフレンドを募集されていましたが、もう締め切りましたか?まだでしたら、ぜひなってみたいと思っているのです」なんてのが来たが、募集をした記憶はない。
来館者多し。
内閣を替えないって話で首相になったはずのあのひとはテキトーで嘘つきだと私は感じているが、多くの人はそう思っていないのであろうか。郵政民営化がこのまま進んじゃってほんとうに大丈夫なのかなあ。全国各地から郵便物が消印から三日ほどの差で無事に届いているのを大したものだと思うけれど、これは民営化になっても変わらないのであろうか。はて。
応募作整理の仕事が終わった。ふう。
子どもの頃、芸能人の書いた本を読むのが好きだった。恥ずかしいのでこっそり買ったものであった。大抵はゴーストライターが書いているな、と子どもにもわかる文章であったが、なかには「蒼い時」のような本もあった。増田惠子の「あこがれ」を読んだ。「スター誕生」で地味な格好で歌っていた彼女らがピンクレディとなって現れた時の衝撃といったらなかった。好きとか嫌いといった話ではなく、あれは現象であった。大林宣彦の「ふたり」での演技などで増田惠子はとても気になっている。ピンクレディの頃、私はミーのファンであったが。いやはやこれは大した本である。下手なビルドゥングスロマンなど足下にも及ばない。なにせ事実なのである。おそらくは本人が書いている。まっすぐな文章で、読みやすく、身体の中に届いてくるかのよう。良い本である。
元々は休みの日だったのだが、出勤。応募作整理のため。「二文字変更したいのですが」という電話がある。無理。締切までに完成原稿を送るべきである。2000点を超えていて、応募票と作品をばらばらにもしているわけで、物理的にも難しい。締切を過ぎてから速達で送ってくるひともいる。謎の行為である。
呆れすぎた事柄というのは忘れてしまうのだな、と今思い出した。電車の中の世界が最近異様である。高校生が床に坐っている。女子高生が足をひらいてパンツ丸出しで坐っている。老人がいても席を譲らないひとがいっぱいいる。携帯電話でのメールチェックをしているひとがいっぱいいる。声高に電話をしてるひともいる。高校生が品のない会話を大きな声で交わしている。念入りに化粧をする女子高生がいる。靴を履いたままの幼児が椅子に立っているのを笑顔で見てる親、祖父母がいる。いや、全員がそういうわけではないのだが、段々増えている気がするのが怖い。悪貨は良貨を駆逐する。
昨日、本屋で見たことのない格好で立ち読みをしている小学生を目撃。注意しようとしたら母親と一緒に帰っていってしまった。母親は何事もないような顔をしていた。平積みの本の上に全体重をかけ、ページをしっかり折り曲げながら読んでいたのだった。そいえば最近本屋でいろいろ見る。付録のついた本の付録をばらばらにしている幼児。絵本のページのど真ん中をばきんばきんと折って読んでる幼児。平積みの本を両手でばんばんと落としている幼児。思えば図書館でももっとひどいものなあ。大抵母親ははるかかなた遠くにいる。私が書店員であれば必ず買わせてやるはずだが、見て見ぬふりをしている場合が多いようだ。本屋さんは返本すれば良いとの感覚なのだろうな。休みの日にまで疲れたくないので、大抵私も注意しないようになったが、こんなのが当たり前になってゆくのは実に怖いと思うぞ。紙は貴重である、本は大事なものである、活字の載っている紙を粗末にするな、といった教えをしている家はどれくらいあるのであろうか。
金井美恵子のエッセイ「目白雑録」をほんの少しずつ読んでいたのだが、姉の言葉として「デブの中学生がキャンプに行って戦争ごっこしてウルシにかぶれたって顔してる防衛庁長官」と書かれていて笑った。
利用者がとても多い。駐車場整理係をする。暑い。
ノラに取り分けた鰯の丸干が床にあるのに、ひとが食べているのを欲しがって、食卓へ上ろうとするので食事を中断し、ノラをのける。食卓の上で食事をしたがる猫は多いのだろうか。
仕事場の学芸員が先日、指定管理者制度について調べていた際、「これはとんでもない制度ですね」といろいろ話していたのだが、ほんと、実に恐ろしい制度であると思う。極端な話、公立の美術館の美術品が指定管理者のものになっちゃって、テキトーに売られちゃったりどこかに行ってしまったってしょうがない、といったかんじの制度だったりする。も少し調べて根気があったら、まとめたいと思う。
昨日が締切の童話賞。応募作が続々届く。めまいがするほどの量である。
仕事が終わってから大須まで出かけ、少年王者舘の「こくう物語」を観にゆく。受付に杉浦君がいた。大学に入って初めてできた友達が彼である。漫画研究会で一緒だったのだった。「芝居、やらない」と誘われたこともあったな、などと思い出す。彼が中退したあと会ったのは三度目。一昨年も同じ話をしなかったか、と歳をとるといろんなことを忘れている。彼の名がチラシにあったので出るのか、と楽しみにしていたのだが、ダブルキャストとのことで残念。芝居の原作は鈴木翁二。70年代末から80年代はじめにガロを買っていた私にとってはとても懐かしい世界。原作をとても膨らませて、映像をきれいに処理し、パターンとなってきているがかわいらしい踊りがあって、淋しいような悲しいような、でも前向きな気持ちになる良い芝居であった。名古屋で20日まで。そのあと大阪、東京公演もある。
今日も暑い。
山上たつひこの『喜劇新思想大系 完全版』読了。15歳のときに読んだときの衝撃がぼんやり蘇る。しかし「幼女」が「バンドウイルカのメス」になっていたり、「クソ男」が「糞ころがし」になっているのは失敗だと思う。作者が手を入れたようだが。青林堂の版と秋田書房の版を持っているのにきれいな装丁だったのと「完全版」の文字に負けて7350円出して買ってしまった私であった。どうかしているような気がしないでもない。若い頃幾度も繰り返し読んだせいでセリフをかなり覚えているから変わっているのがすぐわかってしまうあたりが少し情けない。いい歳をして読む漫画ではないよな、と思いながら読むのが良いのかもしれない。
暑い日が続く。
『スウィング・ガールズ』を観る。矢口史靖監督の映画作品はすべて観ている私。土手から少年が自転車で転がるシーンあたりがいかにも矢口印といった感じであった。無茶なところも無茶とわかっていて撮っているのが良い。勢いのある、観ると元気になれる作品。上野樹里が良いのは当然だが(私の中では)、ドラムを叩いていた豊島由佳梨がとても存在感があって良かった。
鈴木慶一と高田渡を観に今池のTOKUZOへ行く。開場三十分前に着いてしまい、早すぎたかな、と思ったのだが、行列ができていた。こんなにお客さんの多いTOKUZO、私ははじめて。 鈴木慶一はエピフォンのギターの弾き語り。エフェクターをいろいろ使っていて音がきれいだった。『Modern Lovers』ではじまり、『グルーピーに気をつけろ』、『大人は判ってくれない』。『夢が見れる機械がほしい』は21世紀になってしみじみ聴くと違う曲みたい。有頂天が歌った『君はガンなのだ』には背筋がぞくぞく。15年ほど前、頻繁に聴いていた曲だったな、と思い出したり。『国民の煙草しんせい』には「結婚式で歌う歌ですが」とMC。キンクスの曲を、と言って『ユー・リアリー・ガット・ミー』のイントロを弾き、「嘘です」と止したり。それで日本語の詞をつけた『ビクトリア』。ビートニクスの『大切な言葉は一つ「まだ君が好き」』に痛みを感じてしまうのだが、『白と黒』はもっと痛かった。この曲、というか『SUZUKI白書』というアルバムを家ではあまり聴かないようにしているのだけれども。『月にハートを返してもらいに』では携帯電話を取りだして音をマイクに拾わせてたのが面白かった。『酔いどれダンスミュージック』でおしまい。ほかに三木鶏郎さんの「吟遊詩人の歌」、まだなにか演ったような、とこのところ記憶力が落ちている私。
高田渡は、「鈴木さんは元気だね。私は五曲しか歌わない」と言って登場したけれど、かなり歌い(『スキンシップブルース』、『コーヒーブルース』、『あきらめ節』などなどこの頃にはすっかり酔っていた私)、坂庭省吾の遺品だというオートハープで『埴生の宿』ともう一曲弾き、ラストは『生活の柄』を鈴木慶一とデュエット。アンコールに短い曲を高田渡一人で歌い、その後、映画『タカダワタル的』のダイジェスト版を上映するとのことだったが、それは観ずに帰宅。とても良いライブ。充実した一日。
暑い。
童話賞への応募作品を整理。いっぱいあって頭がくらくらしてくる。原稿の規定を守ってなくてマイペースな字数にしている作品や、枚数を気にせず沢山書いているのなどがある。電話で字数ならば足りているが、枚数だと越えるがいけないか、と謎の問い合わせがあったりする。字数の規定はないのだが。問い合わせ、と言えば、受賞後についての話を延々と尋ねる人がたまいる。受賞してからにしてくれ、と言いたいが、我慢する。孫の自慢、ペットの自慢、感想文などいろいろあって楽しそうなのだが、応募作品をじっくり読んでいる時間がないのが残念。学生の宿題で無理矢理書かせて、先生が確認せずに送ってくるのはどうかと思う。タイトルだけからでもいろいろなことがわかるのだが。
夜中に地震。寝ていた私はとてつもなくおおきなナマズがどこか近くににいるのでは、などとわけのわからぬことを寝ぼけた頭でふと考えた。
車のタイヤの一部が切れてぴろぴろしているので、そろそろ替えねば、とタイヤ屋さんへゆく。以前替えたときは一本が完全に毀れてしまっていて、すぐにも替える必要があったため、元のとは違うサイズに替えたはず、と話し、いろいろ調べてもらった。かなり高さの違うタイヤに替わっていたので、速度メーターに表示されている速度と実際の速さに差があったはず、と言われて驚いた。車検はぎりぎり通る変更であったようだけれども。
「誰も知らない」を観る。はじまって一時間くらいで胸がつまりそうになる。柳楽くんがとてもいい。
二度の地震。二度目は熟睡していたのだが、震度4なのでさすがに起きた。今年は過去に見たことのないほどの蜻蛉が近所で飛んでいて、地震でも起きねば良いが、と話していたばかり。大雨と地震が重なると外に出るのも大変。それほどひどくなくてとりあえずは良かった。
しばらく前に、私のHPからこんな匿名メールが来た。「死ねーーーーFUCK!!!!」。恨まれる覚えがあちこちにあるから、そのうちの誰であろうか、と考えたりもし、やがて忘れた。ふと思いついてヘッダからたどっていったところ、宗教系の中高一貫の学校からだった。中高生か先生であろうか。匿名は厭だな、と改めて思った。
童話賞の締切が近づいているため、仕事がばたばた。とりあえず今日までに来た分の整理は済んだ。あと二週間くらいは何が何やらわからぬような状況となろう。
土砂降りのなか、サッカー観戦。グランパス対アントラーズ。雷が鳴っていたりもした。今まで観たなかで一番の雨。神がかりのような勝利。実力もついてきている。ナビスコカップ、優勝できると良いが。
箸を持てぬ若者が増えているのだな、と気づいたのは昼に中華料理屋で凄まじい箸の持ち方の若い娘さんを目撃したためであった。主に薬指で箸を動かしていた。はて、これは珍しい、とあちこちの席を見回すと、10人ほどいた若人のうち正しく持てている人が皆無。私は中学くらいに直したので、偉そうなことは言えないのではあるが。直すのは結構簡単。魚の身を取ったり、豆を取ったりするのが楽になるし、見た目がきれいでもあるので、直すと良いように思う。25歳の頃直した知人もいるので、それほど難しくはないはず。
水曜日に休みをとって「ネコのミヌース」を名古屋シネマテークに観に行った。映画の日であることをすっかり忘れていた。かなりの人出であった。猫好き必見のかわいらしい映画。猫の口が動くCGが少し不気味だったが。
とある万博の会合に出席。ふうむ、といった感じ。しかし中日新聞購読圏外ではあまり話題になっていないどころか行われることさえほとんど知られていないという事実を主催のひとたちはどれくらい把握しているのであろうか、などと素朴な疑問を感じる私。愛知県人、名古屋人の多くは近場のひと以外にひとが居ることをしばしば忘れている気がする。万国に向けて、より以前の日本中に向けて、といったあたりで躓いているのでなければ良いのだけれども。身内の好評だけでめでたしめでたし、とならぬことを祈る。と、まるで部外者のようなことを書く私(ほぼ部外者なのですが)。
指定管理者制度を活用した図書館が沢山できてきたりすると、その管理者に特定の思想信条の団体がいっぱいなっちゃう場合があるよな、と、とある事柄から考える。それを狙って法ができていたりはしないだろうな、などとコワイことを思ってコワくなる。
暑い。台風のせいで湿気がひどいのであった。「華氏911」を観る。この映画で新しく知った話はそれほどなかったのだが、戦争がいかにばかばかしいかを改めて思った。あれを支持する我が国の愚かしさも。マイケル・ムーア監督の突撃ルポの箇所が少なかったのが残念。アフガニスタン攻撃の前の西部劇風のところが好き。
農夫の背青葉青葉の合い間から 田辺一教
すっとん教さんこと田辺一教さんの命日が過ぎた。なんということのない風景がありがたいのだ、とこの歳になるとわかる気がするのだけれど、彼は20代でいろいろな真理に気づいていたのであろうな。鋭いひとと鋭くないひとの差の激しさは神様のいたずらか。やわらかいやさしい視点の句。それは彼の在り方でもあったな。ああいうひとに私はなろうと思っても決してなれないのである。せめて長く生きねば、などと考える。
暦の上では夏が終わり、秋となった。単車で走ると秋らしい風が吹くことがある。
「文學界」9月号清水良典氏の『吉行淳之介原論』が面白い。清水さんらが編集した「高校生のための文章読本」に『暗室メモ』を掲載したことによるあれこれの推理がスリリング。「高校生のための文章読本」は一生に1冊のつもりで当時小牧工業高校の先生だった4人(梅田卓夫、清水良典服部左右一、松川由博)が授業の副読本を作ろうとし、良い文章と思われる文章を持ち寄った、と清水氏から聞いたことがある。ベストセラー、ロングセラーとなるなど、まるで予想もしていなかったそうで、それは吉行も同様だったはず。多くの人に発表するつもりがなかったと思われる『暗室メモ』を見られたのをどう感じたかは気になるところである。講談社文芸文庫の『暗室』をゆっくり読み、インターネット古書店で購入した『猫背の文学散歩』の見返しにある『暗室メモ』をじっくり眺める。そのようにして本が増えてゆき、部屋が大変なことになってゆくのであった。
気がつけば13日の金曜日。長い間日記を書いていないことに気づく。「スパイダーマン2」を観て以来映画を観ていない。先月28、29、30と松本へ出かけた。一昨年だったか林檎の生っているのを見たことがない、と話したり、メールに書いたところ、「えっ、見たことないんですか」と幾人かに言われたのがとても悔しくてどうしても見たくなったのだった。ひとりで高速道路を長く走ったのは生まれてはじめての経験。悪くないものであるな、とこの歳にして思う。行く先々で雨。行くときは晴れていても着くと雨だったりする。ともあれ林檎の生っているところは無事見てきたのだった。
3月のなごやレファレンス探検隊で思いついた「日間賀島たこしゃぶツアー」がついに実現。幹事の打ち合わせがはじめにあったのが5月4日。8月8、9に行ってきたのだった。参加者13名。TさんとのギターユニットATTT(あたたた)、デビュー。Tさんが譜面台を持ってゆく、というのでしかたなく私も譜面台を購入。関係者以外のひとも通る海辺の夕方、飲んでいないのに立って歌うのは勇気が必要であった。たこ、えび、しゃこなど豪華な食事。風が強くて花火はできなかったが、ひとりの死者も出ず、まずまずのツアーであった。
世間はお盆休み、仕事場はなかなか混む。
土曜日に伊東四朗一座を本多劇場を観にゆく。生で元気なうちに伊東四朗を観ておかねば、と思ったのだった。とてつもなく面白い芝居であった。芝居のはじまる前、不思議なパソコンライターOさん夫妻と会う。Oさんとは10年ぶりくらい。フットサルをし、自転車に乗っているとのことで、随分締まっていた。私は水泳をやめてからぶくぶくになってきている。愛知県出身のOさんに万博について訊かれる。私もまったく興味がないのだが、来年開かれるのはどうやら間違いないこと、キャラクターはモリゾウとキッコロという名前であることなどを話す。「え、なにそのモリゾウとキッコロって」と問われる。「そんなのがいるのだよ。緑色と黄緑色の」などと答える。Oさんは万博について多少興味を持ってるマスコミ関係者なのだが、東京で普通に生活していると情報をあまり得られない、ほんとうにあるのかどうかさえわからない、と言っていた。東海地方以外に知られていない万国博覧会は果たしてどうなるのであろうか。
昨日、「スパイダーマン2」を観る。傑作である。映画館で観ないといけない映画。
名古屋市の某図書館のTさんが家に来たのはなごやレファレンス探検隊のツアーでの余興の練習、というかギターを合わせて弾いてみよう、ということなのであった。思えば誰かと音を合わせるのは20年ぶりくらい。昔とった狐塚、などと言いながら、あれこれした。猫のノラは暑かったこともあっておとなしくしていた。
ヤマザキナビスコカップ、ガンバ大阪戦を瑞穂で観た。後半二十分くらいでほとんどの選手がばてていた。マルケスと川島のおかげでなんとか引き分けた、といった試合であった。これで決勝進出。しかしこのチーム、第二ステージもあまり期待できないような気がする。
ともあれ自民党は負けたみたいだ。
仕事場近くは自然にめぐまれている。今日はオニヤンマを見た。あいかわらず速く飛んでいる。こいつはなかなか捕まえられなかったな、と思い出す。最近のセミは子どもにいじめられていないせいか手で捕まえられるが、オニヤンマは手網でも無理だろうな。
休み。「下妻物語」を今池まで観にゆく。もっと長い間多くの館で上映するかと思っていたら、はやくに終わっちゃっていたので遠くまで行かねばならなかった。良い映画だった。土屋アンナ最高っ。観終えて、ジャスコの関係で上映が打ち切られたのかなと邪推。
やたら暑い。映画館を出たら頭がぱーになりそうな日射しだった。
千種からJRで一駅の図書館にゆき、締切を過ぎてしまったレファレンス探検隊の問題を調べる。二階の表示がかなりわかりにくい。本を持ち、空いている席に坐り、別の本を探しにゆき、帰ってくると、「すみません。この席、私の番号の席なのですが」と言われ、その席に番号札が必要であったことに気づく。うかつであったが、番号札についての表示がもう少しあっても良いのではなかろうか。ならば番号札をと思いカウンターに行くが、長いカウンターのどこでもらっていいのかがすぐにはわからず、訊くのも大儀なので、番号札が要らない席に坐る。知り合いが幾人もいる図書館なので、ま、しょうがないか、と思うのだが、知り合いがひとりもいない図書館であったらすでに逆上していたかもしれない。どこにどんな本があるのかも実にわかりにくい。またがった分類の資料を探す際、動線が悪いのはともかく、どこに行けば良いのかの見当がつかないのだ。せめてNDCの頭一桁が遠くからでも見えるようになっていたら良いのだが。広いスペースをあちこちうろうろし、ああ、ここではなかった、と全くの逆方向へ歩かされるのは楽しいことではない。一応、書架の地図のようなものを眺め、目星をつけてから動いたつもりなのではあるが。調べ物をつづけるうち、この館はもしかすると利用者を拒絶しているのではあるまいか、といった気分になってくる。すぐにできないことも多々あるだろうけれども、すぐにもできることが沢山あると思うのでご一考願いたい。一応図書館のプロである私でさえこんな感覚にとらわれたのであるから、かなり慣れないと迷子になる人ばかりだと思う。調べる手だての予想がついても、どこに本があるかわかんないって実にフラストレーションがたまるものである。そして結局問題を調べきれなかった。ああくやしい。F本さんに回答を渡し、館を出ると猛暑。
長谷邦夫の「漫画に愛を叫んだ男たち」を読んでいたら悲しくなった。ギャグマンガの神様赤塚不二夫のブレーンだった人。彼の全盛時から目に生彩がなくなってくるところまでの内幕が描かれている。登場人物も多彩。長谷さんは冷静な目を持つ人だなと改めて思った。
ロブ・ライナー監督の「あなたにも書ける恋愛小説」が良かった。ケイト・ハドソン最高。しかし「スタンド・バイ・ミー」、「恋人たちの予感」の監督の作品がなぜ名古屋では単館で二週間だけの上映なのだろうな。しかも朝と夜一回ずつ。ま、上映されただけましか。
図書館雑誌の特集は指定管理者制度である。先日、とある町のとある施設に関わるひとと話をしていたら、「これからの文化施設はみんな指定管理者による運営になりますよ」と話していた。その施設の中身について聞いていたら、頭がくらくらしてきたのだが、我が国における文化施設は、とりあえず建物が建っていさえすれば良い、といった風なので、それでも問題ないかのように済んでいってしまうのであろうな。物事の質を問わないひとが多いのである。雰囲気に呑まれやすいから、史実などどうでもよく、吉良が悪玉、赤穂浪士が善玉、と本気で思ってしまう。痛みをともなう改革を掲げた首相がいつまで経っても改革をせず、痛みばかりが残っていても、はじめの雰囲気に呑まれたままで、本質を捉えることができないひとがかなりいてここまで来たのも、国民性のような気がしてならない。文化は国の重大事なのだが、経済原理だけが重要視され、本来税金で行わねばならない事柄をせぬようになってゆく。図書館なんて儲かるわけのない施設。税金をかけなければ質が落ちるであろうことは必然。質を気にせず、安いお金で運営しようと考えるということはつまり文化施設などないがしろにすれば良いって話ではないのだろうか。良い国ができるわけである。
良いものもあるし、悪いものもある。というだけの規準になったら楽だろうな、と考えていたことがあった。いわゆるジャンル不要論である。しかしmixiで不快に感じたのは若者達の好みの無秩序。この作家を好きならば、この作家を好きというべきではない、とか、プログレが好きならウエストコースを好きと言うな、といった感覚が私のなかに間違いなくあるのだ。そんなの全然関係なく、大衆文学の代表のような作家を好きと言い、片方ではカルトなマンガ家を好きと言う若者を私は不思議に思う。数年前の文學界での川上弘美さんと長嶋有さんの対談を思い出した。美内すずえの「ガラスの仮面」の話題で長嶋さんが川上さんに「どうしてこの作品を読んでいるんですか」といったようなことを尋ね、川上さんは「スタンダードだから」と答えた。少女マンガをある程度読んだひとで「ガラスの仮面」をまったく読んでいないひとがいるはずないのにおかしな質問をするな、と感じた私。川上さんは1958年生まれ、長嶋さんは1972年生まれ。60年代末あたりからあとに生まれたひとは、古いものを追いかけねばならないわけで、それがメジャーであったかマイナーであったかがわからないのだ。読んでいて当然、というものが最近ではなくなっているのかもしれない。10年ほど前からメジャーとマイナーの境目が曖昧になっているが、20年前には確固としたものがあった。しかし若者は、「高野文子って元々有名なマンガ家ですよね」とか「森田童子は活動していたときにも売れていたんですよね」などと質問する。私が高校生のとき、高野文子を知っている友だちはいなかった。森田童子を知っていた友だちは同じ高校でひとり、大学に進んでひとり。10年ほど前、森田童子のリバイバルヒットには複雑な思いを抱いた。若者にとってはそんなのどうでもいいんだよな、と思う。でも私はなんとなく納得できない。歴史感覚の欠如を感じると言ってもいいかもしれない。でも、発表当時の反響について考えなければその作品に触れてはならない、なんて誰にも言えやしないのだが。100年前の小説についてだったらそんなことを全然思わないのだし。私は何にいらだっているのであろうか。mixiにはコミュニティというのがあって、好みのところに帰属し、同好の士とやりとりをする。なかに変なコミュニティがある。新書好き、とか新潮文庫好きといったところ。新書を全部好きなのか、新潮文庫ならば全部好きなのか、と問いたくなる私はひねくれているのであろう。なにかをとても嫌い、という人間が減ってきているのかもしれない。とある古い芸人を好きだというひとたちが集まっているところでは決定的に誤った文章が書かれていた。嫌味のない芸風が好きだ、と。おそ松くんのイヤミのモデルになった芸人なのだが。「ここが好きだ」と発言して、その「ここ」が間違っていても良いのだろうか。私はそうした文章を目にしたくない。面白いところも多々あったmixiだが、つまんないところをついつい読んでしまったり、アラをさがしまわったりする性格の私には向いていなかった。
最近の言論のおかしさは、以前であれば言わなかった層がいろいろ発言をするところから起きていはしないか、と乱暴なことを思う。根拠のない、思考のあとのない投書をあちこちで目にする。インターネットが影響しているのかもしれない。とある新聞にしばらく前、郵便物の宛名にマンションの号室を入れなかったら、表に宛所不明のスタンプが押されていたので、書き直して出すことができなくなった、といった意見が載っていた。普通、宛名を誤った場合、書き直して切手を貼りなおして出すことになるはずであり、とりあげるべき意見ではないと思われるのだが、新聞に載っちゃっていた。わけのわかんない論をマスコミはしっかりと取捨選択すべきではないのだろうか。いよいよ箍が完全にはずれた国になりつつある。
12日の土曜日、ホームゲームでグランパスが勝ったのは久しぶり。ヤだったのは試合前、「ようこそ世界のトヨタへ」「まだあるだろ」「剥げ剥げの三菱のマーク」をグランパスサポーターが掲げたこと。確かにレッズのスポンサーである三菱自動車の事件は許されないが、選手がいけないわけでも、レッズサポーターがいけないわけでも、また、末端の三菱自動車社員がいけないのでもない。スタンドですべき行為だったかどうか。酒井友之選手はグランパスにいたときには見せたことがないようなプレーをしていた。移籍は彼にとってよかったのであろう。
今週は火曜に京都へ友だちのバンドチルドレンクーデターのライブを観にゆき、水曜日に名古屋レファレンス探検隊があり、土曜はサッカーとばたばたしていた。
レファレンス探検隊の人たちはとても真面目。課題をとことんまで調べてくる。しかし、今回の問題のなかに、とことんまで調べては果てしない調べものとなる種類のものが混ざっていたので、それについて少し説明。几帳面さと適当さがレファレンスには必要なのだと思う。
ソーシャルネットワーキングサイトmixiを退会することにした。世代間の差、といったようなことを思う。しかし、若者のなかには骨のある人もいるのだ、と知ったのは良いことだった。幾人か友だちもできた。「私を会員にするようなクラブには入りたくない」と、最近本気でしみじみ思うようになってきている。
拙い文章で罵られるのと、少ない語彙の話し言葉で罵られるのとでは前者のほうがはるかに痛みが激しい。佐世保の事件で加害者が書いた言葉は日本語とは思えないほど汚い。その彼女がひとを殺すに至った言葉はどうだったのだろう。チャットは瞬発力を必要とする言葉のやりとりである。日本語能力が備わっていない子どもたちにできることではない。多分何の勉強にもならないし、何かが上達するということもない。キー入力が速くなるくらい。子どもにパソコンを使ってさせていいこと、悪いことを、使わせる大人がしっかり考えないと無意味に傷だらけになる子どもが世の中に満ち溢れることになるのではないか。傷はさらに大きな傷を生む。言葉をうまく使えない子どもにチャットをさせるのは、のこぎりを使ったことのない子どもにいきなりチェーンソーを持たせるようなものだ。或いはパソコンに触るのは高校生になってから、と決めちゃってもいいのかもしれない。ネットワークコミュニケーションって、大人になってからすることだと思う。
今週の週刊文春の小林信彦「本音を申せば」に快哉を叫ぶ。しかし支持者っていったい誰なんだろう。
通っちゃいましたな、輸入盤CD規制法案。輸入盤を買うひとは全国民の1割くらいなのかな。少数のひとは切り捨てられる国。スポンサーには楯突かないマスコミ。でも、このパターンでいろいろ法案が通っているし、これからもきっとおんなじ。多くの人に知らされていない危ないかも知れない意図を持った、あるいはあとから考えるとどうにでも使えそうな法案がぼおっと通って言っちゃって、新しい法律ができたことさえ知らないひとだらけ。マスコミが報じないことは、ないのと同じなのが我が国。インターネットで、知られていない情報が流れるけれど、大マスコミで取り上げられない程度の情報、ということで、それほど重視されなかったりする。自分の頭で思考する習慣を持たないひとたちが多い、のだろうな。はじまった当初、インターネットは武器になる、と言った友達がいたけれど、自立、自覚したひとたちが沢山いてこその武器。ひとがかわらず、システムがかわってもあまりなにもかわらない、と思う。悪いことは増えるけれども。
ぼちぼち5月も終わりである。暑い日であった。衣替をせねば、と思うのだが、ときおり冷えたりもする。
最近はペットボトルをもってくる人が多い。展示の前で飲んでた人もいたりする。「立ったまま食べたり飲むのははしたない」などと子どもの頃に言われたりしたものだが、いつの間にかそうではなくなった。しかし、文化施設のなかで持参の飲み物を立って飲む必然性ってあるのだろうか。子どもだけでなく大人もそんな風。図書館の閲覧スペースで飲んでる客もいたっけ。どこでなにをしてもいいという風潮、私は気持ち悪いんですけれども、もう止まりませんな。
グランパス、見事に負ける。マルケスがいないと駄目な感じ。パナディッチも早く戻ってこないかな。
気がつけばアクセスカウンタが50000を越えている。HPをつくってから1年くらいあとにくっつけてもらったから6年半ほど。5人のひとが訪れているとして1万回。日に4回くらい来ないといけないから、きっともう少し沢山のひとがきてくださっているのであろう。お越しくださった方々に感謝。
膝に水がたまり、月曜日に抜いてもらう。針がささるときとてつもなく痛かった。火曜からずっと腰と右手にお灸をしてもらっている。すっかりぢぢいである。
拉致被害者の家族への批判がかなりあるとの報道だが、批判してるひとの多くは匿名なのではなかろうか。インターネットの世界もそうだが、自分が誰であるかを名乗らず、よくよく考えもせず、いい加減なことを言ったりしたりしてる人たちのことなどほったらかしておけば良いと思う。それをマスコミが言説の数に入れるからおかしなことになるのではあるまいか。今回のは泥棒に追い銭外交だと思うけれども。ところで年金の目糞鼻糞合戦はどうなったのであろう。我が国の国民はいろんなことをすぐに忘れるのが偉いところである。
名古屋シネマテークでフェリーニの「青春群像」と「甘い生活」を観る。歳をとってから観なおすと違う映画になっている。甘い生活のマルチェロはあそこからどう生きてゆくのだろうなあ。
mixiはいまだによくわからない。ただ、若者の嗜好みたいなものが読みとれて面白い。日本って自国の文化的基盤をないがしろにしてるんじゃないか、という気がする。「何か」についての距離感が定まっていない人が多いようなのだ。うまく言えないけれど。例えばイギリスでは日常会話にシェークスピアのセリフが使われたりするそうだが、いまの日本では共通の教養といったものが存在しない。それは例えばアニメーションのセリフであっても良い訳で(ほんとはもっとずっと古いもののほうがいいだろうけれども)、その「何か」までのそれぞれの距離によって人の持つ「文化」を推し量ることができるようになっていると良いのではないかと思う。己の「何か」に対するスタンスを磨くことによってほかの文化についての目ができてゆく、といったことがあるのではないか、という気がする。と、書いていて本人がよくわからない話で申し訳ない。つまり、好きとか嫌いとかは別として知ってなきゃまずいんじゃないのってことを知らずにいて平気なのに、かなりつまんないものを好きだということだけを強調するひとが以前よりさらに増えてる感じがして、それは国の歪みに繋がっていきはしないか、誰もが知ってる基礎教養みたいなものがないからまずいんじゃないか、と、そんな話。
コイズミ叩きがあそこからはじまるとは思っていませんでした。もっと早くに叩くところはあっただろうに。官房長官が変わったからかなあ。大逆転を狙っての訪朝だったはずではあるけど、帰ってきた子どもさん達にマスコミが長くカメラを向けることができないわけで、うまくいかなければ、自分のまずいところへ向いちゃう、といったあたりを読めなかったのでしょうな。それでもいままでならばうまくいったかのように報道されてた気がするけれども。マスコミが彼に嫌気がさしてきているとかってよりも、マスコミはなんとなくテキトーに記事作ってんじゃないか、流されてゆくままに流れていってるんじゃないか、と思えちゃったりもする。人さらいにあったひとたちのご家族の心情を彼が真剣に考えていなかったであろうことはまず間違いないわけで叩かれてもしかたないのだが。
と、テレビをぼんやり観た感じで書いたのだけれど、新聞だと内閣支持率はあんまり変わってないし、訪朝の評価も高いんだ。ううむ。
私が定期的に読んでる数少ないWeb日記に フジテレビのオフィシャルサイトのことが書かれているのだけれど、このサイト、それだけじゃなく「木島則夫」が「小島則夫」になっていたり、1980~1999のところでは自局番組のヒットした主題歌の記述が違っていたりもする。大マスコミがこういうところで間違っちゃいけない。
これはあれだな。100個宝石を盗んだことがはっきりわかってるドロボウに「返せ」と言って、「よしわかった盗んだのは10個だから返してやろう」と言われ、「ほかにも盗んだはずだが」、と他人事のように尋ね、「すぐにはわからないが、調べておいてやろう」と答えをもらったことに喜び「よろしく頼む。ならば1000万ドルあげしよう」と約束したってな話。しかしそういうバカを支持するひとがいっぱいいるんだからしょうがない。
おたふく風邪は一昨日治った。仕事場のひとたちのなかには罹患したことがないひとがいて、恐れ戦いていたのであった。私は小学生のとき左っかわが膨れたことがあったのですが、抗体がうまくできていなかったらしい。ほっぺたが腫れただけで熱もなかったのだけれど、「ひとにうつるので出歩かないように」とお医者さんに言われていた私。
ぼちぼちと童話賞の仕事をする。
友だちの間で評判になっている「スクール・オブ・ロック」を観る。ご都合主義の脳天気映画だが、確かに元気が出る作品。
ソーシャルネットワーキングサイトmixiには若いひとたちが多いようだ。自分の半裸写真をトップページに使っている女のひとがいたりもする。世の中は変わったのだな、としみじみ思う。60年代末から80年くらいまでのことに興味を持つ若いひとがかなりいるのにも驚く。考えてみれば80年前後の生まれなのだから、それほど不思議でもないのだが。さして良い時代でもなかったが、ここ10年くらいと比べたらずっとずっとましだったのだな、と今更ながらに思う。どうしてこういうことになっちゃったのでしょうな
おたふく風邪に罹った(T_T)。
「キル・ビル2」を観る。1ほどの迫力はなかったが、楽しめた。アメリカで日本のマンガやテレビドラマなどにどれくらいの人が関心を持っているのだろうか。
しばらく前に「コールド・マウンテン」を観た。ニコール・キッドマンが目当てであることは言うまでもない。もっと甘い映画かと思ったら反戦映画であった。戦争は厭だな、としみじみ思った。人物造型が良くって面白かった。レニー・ゼルヴィガーはすげえや、と思った。もちろんニコール・キッドマンは素晴らしいにきまっている。
名古屋レファレンス探検隊の若い人たちととある打ち合わせ。そののちにF本さんから来たメールを読んで、そういえば彼は10代の頃から図書館員になりたくて、司書資格の取れる大学に入ろうとして誤って司書教諭資格しか取れない大学に入った、とか、そんなよな話をしていたことがあったな、と思い出す。大学の頃から図書館関係の人と交流があったようなのだ。数年前からようやく図書館関係の人と接するようになった私とは気合いの入り方が違うな、としみじみ思った。F本さんほどの熱意ではないにしろ、10代から図書館員を目指している人たちは沢山いるはずである。彼らが図書館で働けるような状況をつくってゆかなくてはいけない、と強く思う。経済効率ばかり重視している世ではあるが、まず未来を見据えて文化の基盤をしっかりと築くべきではないのか、我が国は。
昨日今日と混んだ。天気が悪かったせいもあるのだろうか。調べもののため、覚え書き、聞き書きの類をいくつか読む。隠したいだろうな、と思われることを別のひとが語ってたりして面白い。
イラク人への米兵の虐待。にんげんをにんげんと思っていたら戦争なんてしていられないのだろうな、と改めて思う。もしかすると元々アメリカ人にはそういうひとが多いのかもしれないが。第二次大戦中に日本もおなじようなことをしている。ヒトは毀れた生き物だとよくわかってしまってヤな感じ。毀れたヒトが起こした戦争に尻尾を振ってついていっているヒトの支持率が五割を越えている国。
久々に風邪をひいた。歳をとると徐々にではなく、突如として風邪がやってくるのかもしれない。ぼおっとしてるうちに、おおおお、がたがたといった感じになった今回。丸一日寝ていたらなんとかなったようだ。世間はゴールデンウイークだが、今日の来館者はそれほど多くなかった。
図書館における同一本大量購入の問題が取り沙汰されてしばらくになる。一つの館で何百冊も買ってるところがあるのはどうか、と思う。利用者の数だけは増えることとなろうが。発行後半年経ってから貸し出せ、という作家がいるが、半年経つと買えなくなったり買いづらくなる本が世の中に結構あったりするということをご存知ないのだろうか。出版し、取次に全部出した時点で版元品切とし、売れなければそのまま。返本が来た時点で在庫となるという方式の出版社の本は店頭在庫をつかまえるほかない。どの本屋にその本があるか、を一冊一冊探す手間をかけるのも図書館の仕事ではあろうが、それだけの人的余裕がなかったりするのも現状。発行後すぐに購入し、それから半年間開架に出さずに置いておくスペースもない。本の流通は昔と今とではまるで異なっているのだ。半年どころか発売後一ヶ月で品切ですってスリップが返ってくるのである。いろいろと簡単ではない話が多い問題ではある。
児童文学者と友だちだった現在86歳のひとの話を先日聞いた。補聴器はしていないし、話の時期が多少混乱するが、記憶もしっかりしている。尋ねる中身は6、70年前のこと。意地悪な私が知りたいのは、その児童文学者の厭な面。児童文学者についてのおぼえ書きがあるのだが、彼は唯一良くない面について語っていた。いいところと悪いところがあるのが人間なのだが、早く死んでしまい、あとから有名になった人を悪く言うひとは極めて少ない。それが児童文学のひとだからなおさら。世間に向けてはよい話だけをしていればいいが、研究をする人は悪いところも知るべきだと思う。児童文学者についてだけでなく、戦争の話も出た。市の有力者と彼の父親が懇意にしていたので徴兵検査の際、第二乙種にしてもらったのだそうだ。甲種、第一乙種、第二乙種の順で兵隊に取られるのが常。丙種不合格は身体に障碍がある人。第二乙種は相当身体の悪いひと。普通は戦争に取られない。徴兵忌避のため検査のとき醤油を飲んでふらふらになり、なんとか乙種にしてもらうひとの話が本などに出てくる。第二乙種にさえ終戦間際には徴兵があったそうだが、大抵は出征せずにすんだ。ところが彼は早くに召集された。左翼のひとが出入りする喫茶店を親戚が経営しており、そこによく行ったため共産主義者だと疑われたからだ、とあとから知ったとのこと。当時は政府に反抗的なひとは早く兵隊に取られ、過酷な外地や最前線に送られた。こんな人がアサヒネットにいた。学生のとき、軍人が話している途中で何人かの生徒が笑い、「今笑った者、立て」と言われ正直に立ったのがその人ひとり。すぐ最前線へ行かされ、生きて帰ってこられたの者がほとんどいないなかで過ごしたとのこと。「また日本もその頃と同じようになりますよ」と86歳のひとは言っていた。私もそんな気がしている。ただ、その頃と今との違いは選挙で政治家を選ぶことができる点。
毎日新聞25日の朝刊にファルージャで家族が殺された少年の話が載っていた。足が不自由で反米の運動などできない父親が表に出ていった途端、米兵に射殺され、母も弟も撃たれて死亡。アメリカの正義はこんなものである。戦争を終わらせるため、と称して59年前、日本各地で無辜の市民を焼き払った国だ。そしてそれを今でも正しかった、と多くのアメリカ人は言い張っている。本当にそうか。その正義を支持する被害国だった国の人たちもイラクでの殺人に荷担している自覚だけは持つべきだと思う。
「エレファント」を観た。静かな美しい映画。ガス・ヴァン・サントはこの映画で何を言いたかったのだろうか。何かが私の中に残ったのだけれど、それが何だかよくわからないのが気になる作品。
ソーシャルネットワーキングサイトmixiというところへ招待された。半開きのような場所、とのことだったので、あちこち訪ねてみると、行くさきざきに足あとが残ることが判明。見ず知らずのひとのところへ出かけるわけで、少し怖かったりもするが、考えてみたら誰と会うときもはじめははじめてなのだ。誰かの紹介がないと入れないので、友だちの友だちの友だちの友だちの・・・、といった関係で成り立っているのだが、友だちの友だちくらいにならないと見られない自己紹介文があったりしてなんだか不思議な世界。若者も多く、ゆるゆるした感じでもある。これからどうなってゆくのか、なにができるのかわからないけれど、しばらく遊んでみようと思う。
書こうと考えていたのにすっかり忘れてた話があった。海外CD輸入盤規制法案のこと。村井康司さんの日記を読んでいて思い出したのだった。すっかりボケ気味の私。こんなサイトやこんなサイトもありますが、まだ多くの人が知らずにいるのではなかろうか。私は4月10日の朝日新聞土曜日版(というのかな)に山形浩生さんのコラムで知り、びっくり。外国で売られている日本のミュージシャンの音楽CDが安価なので逆輸入を禁止するって話は幾度も報道されていたが、日本盤が出ている洋楽CD(いわゆる輸入盤)も輸入できなくなる可能性があるとのこと。これ、もしかして音楽会社があれこれしていたりはしないだろうか。だって報道されなさすぎ。知的財産権をめぐっての中山教授と福田官房長官とのやりとりもすごいな。こんなめちゃめちゃな話をマスコミが突っつかないでいるのはなにかあるのかやる気がないのかなんだろ。危なすぎないか我が国の文化をめぐる状況。文化だけじゃないけどさ。
日本って世界のなかでどれくらいなんだろうか。って曖昧なことを最近よく考える。例えば日本の公共図書館の内情について多くの日本人が知らないってことを私は知っている。日本の公共図書館について考えている人は世界規模で考えたらほとんどいないだろうなと思う。日本の自衛隊の中身について詳しく知っている人もかなり少ない。日本の自衛隊がイラクに行った話を知ってる世界の人は何人いるのだろう。アメリカ人の中ではどれくらいなのだろう。そこで何をしているのかを知ってる人の数は。あまり誰も日本に感心を持っていないんじゃなかろうか。幾人かの政治家とか、学者とか、マニアくらい。国際貢献って大騒ぎしてるけれど、誰も知らない村のなかだけで騒いでる村おこしみたいなものだったりするんじゃなかろうか、なんてふっと考える私。多くの欧米人にとって我が国は極東の小さな国。何をしてるかなんて誰もそんなに気にしてないんじゃないだろうか。アメリカの政治家にいいところを見せるって以外、今回の派兵に意味はあるのかな。あとは多くの人がマスコミに踊らされてるだけだったりして。日本の首相の名前を世界で何人が知ってるだろ。あの人はこのまま突き進んで有名になりたいのかな。
横山光輝さんが亡くなった。子供の頃、テレビマンガ「鉄人28号」、「魔法使いサリー」、実写版「仮面の忍者赤影」をどれほど好きだったろう。「水滸伝」、「三国志」の面白さを彼のマンガで知った人は多いはず。月刊少年マガジンが早く発売されないかな、とわくわくしていた時期がある。「時の行者」を楽しみにしていたのだ。彼には主流のグループのようなところから少し距離を置いた感じがあり、そこがなんだかかっこ良かった。ご冥福をお祈りします。
仕事はこのところマスコミの取材が多い。小さい施設なので広報担当はなく、関わりのある職員が対応するのである。ことのなりゆきで、もしかすると来週私の顔が国営放送でオンエアされるかもしれないらしい。子供の頃はテレビに出たかったが、42にもなると照れる。偶然のできごとでの出演なのでなおさらである。生きているといろいろなことが起きるものである。
ベトナム戦争のときって殺された人たちの映像をよく見た気がするのだけれど、今回の戦争ではあまり見ません。亡くなっている人の数が違うことは確かだけれど、規制されてるのかな。人が沢山死んでいるのだからマスコミは知らせるべきではないのだろうか。こんな感じで人々が死んでいるのだ、と戦争が好きなこの国の人たちに見せてあげるのが親切というものだろう。コードにしばられてしなくちゃならないはずの報道を忘れちゃってるのか、すでにできないのか。我が国の首相は戦地に出かける気で出かけて亡くなったアメリカの民間人と、住んでいるところが戦場になって逆恨みのように爆撃されて亡くなったイラクの民間人とではどうやらアメリカの民間人のほうが大事らしい。週刊文春の発売を止められた事件、案外いしいひさいちと高橋春男のマンガを気に入らない人のしわざだったりして。などとふと思う。次は朝日新聞夕刊のしりあがり寿が狙われているかもしれない。
憲法改正に賛成の人が多いようだが、1条についてなのかな。21条をいじりたい人もいるのだろうなあ。護憲派の私である。
なんかヤな感じ。人質が殺されても自衛隊を撤収すべきでない、との意見の人たちのこと。この事件、たまたまイラクで起きたけれど、スペインと同様の事件が起きても同じことを言っているのだろうか、とか、その被害者のなかに自分の身内がいてもそれは変わらないのかな、とかあれこれ思う。そういうところまで考えた上での発言ならば偉いな、と思うけれども。自分は安全なところにいて、まったくの他人事として回答をしていたり、ものを書いたりしてる人が間違いなくいる、と、ひねくれた私は思っちゃうのであった。この戦争が長びいて、兵隊さんが足りなくなって本人や子供が徴兵される、なんてなことになっても出兵は正しい、とか、テロに屈するつもりはない、たとえ私や家族がテロリストに殺されることがあるとしても、と今現在思ってる人の数を知りたい。多分そこまでの覚悟の上に語っている人は少なかろうと感じてしまうのである。私は殺されたくないし、危ないところに行きたくないし、はじめた人たちが正気かどうかはっきりしない戦争の一端に荷担しているのかと思うと憂鬱になる。この時期、あの危ない場所にどうあっても行かねばならない、と考えて出かけた人たちの気持ちは私には想像もつかないのだけれど、行くからいけない、生焼きにされてもしょうがない、だなんて言っちゃう人たちについてはもっとわからない。人質事件の報道のすぐあとに私が知らない新人タレントの一日署長のニュースを流す感覚も全然わからない。解放されるらしいってことになったら盛り上がってるけれど、根拠があるかないかわからない話で、本当に解放されたら、それで「よかったよかった」でおしまいにしちゃおうって考えてるんじゃないかって思っちゃう私が厭だ。そんな風にいろいろなことを思いながらも名古屋グランパス対柏レイソルをしっかり観てきたりもしました。自分と直接関係ないことって、本当はどうだっていいんだよね。ただ、関係なさそうな話が突然近づいてくるんじゃないかって想像しちゃうからそれが困る。でも自衛隊、することあんまりなくって危ないんなら帰ってくればいいのに、どうしていつまでもいなくちゃいけないんでしょうな。ま、アメリカには嫌われちゃうだろうけれども。そういう面白い国が世界に一つくらいあったっていいと私は思うが。
新年度である。キツネの糞らしきものが雑木林にあるとの連絡があり、見に出かける。どうも去年からキツネと縁がある私。てんこもりになっている糞の写真を撮り、糞を採集。キツネの糞には独特のにおいがあるというので嗅いでみる。木の実のようなにおいだが、糞なので当然くさい。なんとなく懐かしい香りでもあった。館にもどり、Webで少し調べる。キツネの糞は先端が尖っているとのこと。おお、尖っているぞ、と写真をしげしげと見る。念のためタヌキの糞について検索。タヌキにはため糞という習性があるが、キツネにはない。ん。とてもたくさんの糞が同じ場所にあったわけで、これはもしやタヌキ。タヌキならばいくらでもいるのであった。動物にくわしい先生にメールで質問しておいた。町のなかに異世界のような雑木林。そのなかに入ることができただけで幸せだった。
年度はじめはあれこれあってばたばた。
人事異動は私にはなかった。ま、一年なので大抵ないわけだが。名古屋市や愛知県はどうなったのであろうなあ。
「イノセンス」を観る。私の好きな映画ではないかもしれない、と思っていたのだが、好きな映画だった。観るたび新しい発見のありそうな作品。観るときの気分によって違う映画になるのではないか、という感じがした。
「花とアリス」がすぐに終わってしまいそうなので観てきた。人気のある女優が出てるのになぜだろうか、と行ってみたらがらがら。岩井俊二らしい映像のきれいな作品だった。鈴木杏と蒼井優も良かったし、私の好きな木村多江もいい感じだった。
六本木ヒルズの痛ましい事故。ロープで通せんぼしてあって、いかにも危なそうなあそこにどうして小さい子が入ってしまったのかもしかし気になる。突然走り込んじゃったのだろうか。森ビル側にももちろん問題はあるが、小さい子がいる人たちはいろいろなことに用心していないとまずいのではないか、とも思う。そうした視点が全然出てこないのは世の中が昔とはまるで変わっちゃったからだろうか。亡くなった子についていた人たちはそのときどうしていたのか、といった話を知りたいのは私だけだろうか。
20日にグランパスがジュビロに負けた。確かにグランパスのあれこれも良くなかった。しかし一番気になったのが主審のジャッジ。Jリーグは審判の水準を上げないと客が離れてしまうのではなかろうか
週刊文春の発禁にはびっくり。自分のことではないから、と無責任な感想を書いてしまえば、あれくらいの記事は今まで週刊誌にいくらでも載っていた。私人のプライヴァシー侵害であることは確かであろうし、それを良いとも考えていないが、この時期になぜこうした事件が起きるのだろう。検閲に結びついてゆかねば良いが。週刊文春を購入していた図書館の対応はいろいろ。71万部流通したのであるから、と通常通りの閲覧にするところ、該当の記事だけホチキスで綴じるところ、雑誌ごと禁閲覧にするところ。今後こうしたことが増えるのではなかろうか、と考えると気が重くなる。今はすでに平穏な時ではなかったりして。
「ホテル・ビーナス」を観た。中谷美紀目当てで出かけたのだが、なんだかなあ、といった感じの映画であった。香川照之は「美しい夏キリシマ」でも後ろ姿の裸を見せていたが、この映画でもなぜか尻を見せていた。存在感のある良い役者である。しかしこれだけ役者が揃っているのに、ううむ。
「ドッグヴィル」を観る。ニコール・キッドマンを見たいがためである。見事であった。映画は少し長すぎる気がした。
「1980」と「赤目四十八瀧心中未遂」の2本をシネマスコーレでかわりばんこに上映しているのを2本観る。まったく色合いの違う映画。ケラリーノ・サンドロビッチは有頂天の頃から気になる人であった。「心の旅」のカヴァーを聴き、驚いてELLに観にゆき、ファンクラブに入ったりもした。彼はコメディ映画のマニアで小学生の頃に小林信彦と文通したり、フィルム屋さんでハナ肇と知り合ったり、とまっすぐに喜劇の道を進んできた人。彼のはじめて撮る映画なので期待して観たのだが、期待以上に面白かった。ラスト近くともさかりえがテレビを観ているところを家族がうれしそうに眺めるシーンは私には気味が悪かったけれども。1980年には「未来」ってものがまだあったな、としみじみ思った。プラスチックス、YMOを私はあまり気にしていなかったけれど、今聴くとその頃の感じが蘇ってくるのが不思議。
「赤目四十八瀧心中未遂」は原作にかなり忠実な作品。でも、言葉のイントネーションのこととか、子供の晋平をもう少し使っても良かったんじゃないか、とか、山根はあれで良かったのかな、とそのあたりが少し気になった。とにかく美しい映画。シネマスコーレに平日の昼間あれだけ客が入ったのをはじめて見た。プロデューサー荒戸源次郎には過去いい映画を見せてもらっている。監督としても一流。次作が楽しみ。
レファレンス探検隊の宴会のあとでさらにF本さんは飲み続け、路上で午前五時、見ず知らずに人に起こされたそうな。長生きをしてもらいたいと思う。
「ミトン」を名古屋シネマテークで先週観た。「チェブラーシカ」で知られるチェコのロマン・カチャーノフ監督の短篇。毛糸のミトンが犬になるお話。昨日、名古屋レファレンス探検隊があったのだが、会のあとの宴会(出席者十人)でこの映画を観た人が私を含めて三人もいたことが判明。ううむ。
名古屋レファレンス探検隊は今回も面白かった。私の当たった問題は正解者なしであったが、出題者はたどりついていた。レファレンスの際、先入観を持ってはいけない、という大原則をつい忘れていた。ほかの二問もよくできていた、というか、利用者からの問いなのだが、へんてこな質問が図書館にはやってくるのであるな、と改めて思った。それにしても皆若い。長く生きているだけあって私にもアドバイスできることがあって幸せである。宴会では80年生まれの人がいた。いまの中学一年生は90年生まれだそうだ。そのうち私は前世紀の遺物となるのであろうなあ、と考えると少し嬉しい。F本さんは腹話術の人形ともちゃんを膝に乗せていた。宴会場でのネタは面白かったが早くも私は少し飽きてきた(^^;)。もっと勿体をつけて出し惜しみした方が良いのではなかろうか。ぼおっとしていたらコメンテーターを頼まれていた。名古屋レファレンス探検隊、存続の危機とのことなので、喜んで引き受ける。Tさんに「マイナー好きなんですね」と言われた。古いフォークソングの話をしていたときのこと。私はときどきそう思われるのだけれども、当時はメジャーなものを聴き尽くしてからマイナーなものを聴いていたのでした。今はメジャーなものをあまり熱心に聴かなくなっちゃっていますが。宴会では飲みすぎるほど飲んだのでしたが、まるで水を飲むように冷酒を飲んでいる化け物のような女のひとが斜め向かいの席にいたので、ついつい釣られたせい。
週刊文春に学校大崩壊という記事があった。嘘だろう、と思えないのは図書館にくるひどい親子の例を目の当たりにしているからである。
森達也の「下山事件」を読む。彼の「放送禁止歌」を読んだときの衝撃を思い出す。自らの思い込みをこれだけ封じている人がいることに安心する。自分の目で見、耳で聞いたことさえ疑う姿勢がこれからは重要になろう。
日曜日にグランパス対エスパルスのプレシーズンマッチを観た。後半、守備ががたがたであった。隣の人がかなりのグランパスファンで、去年は日産が優勝したわけだから、TOYOTAのロゴが入ったユニフォームを着たチームが優勝しないわけにはいかない、と話していた。
昨日からアテネ五輪アジア最終予選がはじまった。サッカー狂いの人たちにとっては慌ただしい季節である。
先週末から軽い腰痛になり、鍼灸院に行く。その治療でうぎゃぎゃぎゃ、と叫んだりした私であるが、ぼちぼちと良くなってきている。
仕事は主に図書整理。単調である。
とある雑誌に投稿しようとして規定を見たところフロッピーディスクも送らねばならないとのこと。こないだまで使っていた外付FDDはOSをバージョンアップしたら使えなくなっちゃったので、古いMacを引っ張りだしてきて、自分宛のメールを送って読もうとしたら、アサヒネットのアクセスポイント変更とかのあれこれが違っていて、設定をし直したのであった。しかし、どうもうまくいかず、いらいらしてきたので思い切って外付FDDを買った私。掲載されると良いが(^^;)。
もうじき名古屋グランパスのプレシーズンマッチがはじまる。わくわくする季節である。
司書になるため、勉強以外に今しておいた方がいいというようなことはないか、との質問メールをいただいた。13日に中学生に答えた内容くらいしか思いつかない。司書に向いてる人としては、本と人が好きである、ってこともよく挙げられているが、図書館で働くうち、少しずつ人を嫌いになる場合が多いようではある。ルールを守らない人が世の中に多いのがわかってくるから。なるまで、よりもなってからが大変というのも確か。大変だと思わない人もかなりいるが。大学4年間で何をすべきか。何をすべきか、と焦るために4年間がある、との答え方もあるかもしれない。私が何をしていたのか良く思い出せないが、あまり内容があったようにも思えないので偉そうに言えないのでもある。本屋と古本屋には良く出かけたが、公立図書館にはほとんど行かなかったな。と、あまり良い答えが浮かばない私。
民営化になる図書館がいくつかあるようだ。内容に目を向けず経済効率を上げることを狙うのであれば、図書館の民営化は確かに良いことであろう。司書としては戦々兢々である。正規職員の司書がなぜ必要か、を説明できるようにしておかねばならないし、毎日そのように過ごさねばならないのは当然だ。だが、例えば図書館を使わない人、これから先も多分一生使わない人が図書館の人件費を安くすることだけを狙った場合、司書が戦うのは大変なこととなるだろうな、と厭な想像をする。私は司書の専門性について、以前ひとにこんな説明をしたことがある。「森鴎外の『普請中』(題はあくまで例である)はありますか」と問われたとき、自館の蔵書を電算で検索するのは素人、文学綜覧シリーズを引き、開架か閉架にある鴎外全集か選集の棚にすぐ行くのが中堅司書、「しばらくお待ちください」と言って何も引かず該当の全集の巻を持ってくるのがヴェテラン。素人の場合、電算を叩いて、「ありませんね」と客を帰してしまうことだってあり得る、と。しかし、「客を帰したっていいじゃないか」と言われたとしたら司書の価値は無くなってしまうのである。プライヴァシー保護のため正規職員が必要、との回答もできるが、契約で漏らさぬようにすれば良いと言われたらどうするか。素人に選書をまかしておいていいわけがない、と答えるとしても、「どんな本でも並んでいればいいのだ。流行ってるよく借りられそうな本を複数冊買っておけばいい。いずれ本棚はいっぱいになってみんな市民に差し上げることになるのだから」と言われたらどうするのか。また、民間委託はされていず、司書がいるのに内容がそんな風になっている館は多々ある。以前はレファレンスツールを引かねばわからなかった事柄がインターネットでかなりわかるようにもなってきている。高度な専門性を持つ司書がいる館も多くあるし、意識の高い司書も沢山いる。しかし、図書館の内容を気にせず、人件費を安くし、開館時間を長くすることだけを目的とされたらひとたまりもあるまい、と考えると暗澹たる気持ちになる。恐らく世の中の半分くらいの人は本や視聴覚資料と無縁であろう。本屋に今現在沢山置いてある本かリサイクル古書店に沢山ある本などがあれば構わないと考える図書館利用者が半分以上かもしれない。調べものや小さな本屋やリサイクル古書店にない本のために来館する人は全人口の何割であろう。彼らにとって図書館はなくてはならない場所である。しかし、そのためだけの図書館とはなれない。逆に彼らは切り捨てられる可能性がある。司書がいる図書館でも切り捨てているかもしれない。料理の本やガイドブック、ベストセラー、パソコンソフトのマニュアル本がメインとなっている図書館であれば、もしかすると正規職員の司書は要らないかもしれない、などと私も考える。図書館員の倫理綱領第1に「図書館員は、社会の期待と利用者の要求を基本的なよりどころとして職務を遂行する」とある。実に曖昧な話ではある。昔ながらの本らしい本よりもHow toもののために図書館に来る人がかなり多くなっている。それも社会の期待、利用者の要求であろう。第12に「図書館員は、読者の立場に立って出版文化の発展に寄与するようつとめる」とある。出版文化は20年前と大きく変わった。世の中もかなり変わった。20年前にはお金だけがすべてじゃない、と多くの人が見栄を張って言っていたし、本気で思ってもいた。今やお金がほとんどすべてである。出版文化の発展とはよく売れる本が沢山出ることだったりはしないだろうな。読者の立場というのはどんな読者なのだろうか、と考え込んでしまう。少数の人が大事である、と言うのは簡単である。しかし少数意見は大抵黙殺されるのが我が国の傾向である。マイノリティへの風当たりの恐怖については中島義道の「うるさい日本の私」を読んでみてはいかがか。彼はやや特殊かもしれないが。
図書館でいくら本を貸しても決してお金はもうからないが、長時間開館したり、人件費を安くすれば、それを実績として偉くなる人はお金持ちになれる(かもしれない)。図書館はなぜ必要なのか、正規職員の司書がなぜ必要なのかを理解してもらうのははなはだ困難である。児童サービスの充実の話をするという手ももちろんある。しかしわかってくれる人を相手にするのではなく、わかろうとしたくない人を相手にせねばならない事態が起きる可能性を考えねばならない気がするのである。我が国の貧しくなる文化状況のなか、正規職員の司書が生き残るのはこれからますます大変なこととなろう。本を読まない人に司書の仕事を説明したことがある人には、これが杞憂でないことがわかって眩暈がしたりして。なるべくこういうことを考えないように日々を過ごすのが司書として生きるこつかもしれない。文部科学省を巻き込んで日本人の文化の底上げを狙う、とか、それくらいおっきな話を考えてゆかないと駄目なのであろうなあ。とにかく文化はあんまりお金にはならない。「それをしないとどれだけの人が困るんだ」との質問に対する答は図書館にはない。図書館がなくても困らない人はいっぱいいるのだから。博物館がなくても、文学館がなくても、美術館がなくても。だから中身なんてどうでもいいって人がいっぱいいたって何の不思議もないのである。
土曜日に名演小劇場で「美しい夏キリシマ」を観る。柄本佑が良い。戦争はやだなと改めて思う。宮崎に行ってみたくなる。日本の映画史に残る映画だろうな。
月曜に名古屋シネマテークで中平康の特集を観る。「月曜日のユカ」、「牛乳屋フランキー」、「狂った果実」の三本。「牛乳屋フランキー」はパロディが多く、同時代に観ていたらさぞかし面白かっただろうな、と思った。フランキー堺のコメディアンとしての評価が40代の私にはよくわからないのだが、この作品と「幕末太陽傳」を観ると納得する。「幕末太陽傳」の監督川島雄三のフィルム保存のために映画会社が持っているマスターポジからのニュープリントを行っている人たちがいる。川島雄三ほどの監督であれば本来国がすべき仕事のような気がしないでもないが、我が国ではしかたがないのであろうな。ニュープリントの「新東京行進曲」(1953年)を木曜に名古屋シネマテークで観た。面白い。ややこしい人物関係をしっかりと整理していて一時間半ほどにまとめる手腕の確かさ。ユーモアとペーソスなどという使い古された言葉を思い浮かべた。主演は1959年33歳で交通事故死した高橋貞二。いかにも好青年といった役者。古き良き時代の日本。
最近の仕事は図書整理と紀要の校正。旧仮名遣の文章の引用があるのだが、書いた本人が仮名遣を間違っている箇所がかなりあって大変。それにしても戦後の国語改革は問題だらけなのだよな。正字旧仮名が続いていたとしたら、別の国であった可能性もあるのではないか、と時折思う。高校のとき、福田恆存の「私の國語教室」(現在は文春文庫)を読んで、「え?」と思い、「漢字と日本人」(文春新書)を読んで愕然としたりもしました。ところで乱歩や谷崎のえっちな作品を読むとき、旧字旧仮名のほうが新字新仮名よりずっとえっちだと感じるのは私だけでしょうか。三倍はえっちだな。新字体のせいで毒も薄くなっちゃったのではないかな。
ちくさ正文館になぜか「風車が記憶する」(木靴舎)があったので購入。「高校生のための文章読本」(筑摩書房、1986)の著者、梅田卓夫、清水良典、故・松川由博、服部左右一の4人が1984年に出した私家版。きれいな版画の表紙。彼らは当時愛知県立小牧工業高校の国語教師。「国語表現」という新しい課目の教科書がまるで使えないものばかりであったため、サブテキストとして「高校生のための文章読本」を4人で集まって作ったのだった。「高校生のための文章読本」について、「一世一代の本を作ろうと考えていました」と清水さんから聞いたことがある。高橋源一郎らが書評でとりあげ、シリーズ化され、ロングセラーになるなどとは予想もしていなかったとのこと。そんな彼らの今から20年前の小説、詩、戯曲の本が新刊本屋にある不思議。
気がつけば13日の金曜日である。仕事場では図書整理をぼちぼちとしている。
月曜日に田中麗奈主演の「ドラッグストアガール」を観た。田中麗奈を観たくていったので、とりあえず良かった。ところどころ笑えたが、構成に無理があったりはした。
中学生から調べ学習(総合というらしい)で職業調べのためとのことでアンケートメールがきた。こんな回答をしておいた。
>1,この仕事を選んだ理由
本を好きだから。お金儲けを目的にしていない、あってもなくてもいい仕事だから。
>2,喜びや苦労
お客さんが探していた本、調べていた事柄がわかった瞬間の喜んだ顔を見たとき、この仕事に就いて良かったなと思います。苦労は世の中には悪い人が多いのだ(期限に本を返してくれない、本を切り抜くなど)と毎日気づかされること。
>3,(司書という仕事について)どんな人に向いているか、適性・能力・体力など
本が好きな人。調べものの好きな人。真理について疑い深い人。整理整頓が好きな人。歩くのが好きな人(図書館は広い)。
>4,今、やらなければならない(必要な、身につけておかなければならない) こと
とにかく沢山本を読むこと。本屋さんや古本屋さんに習慣的に行くこと。
しかし私は整理整頓が嫌いであったりする。司書は本と人をつなぐ仕事であるのだな、と改めて感じた。案外そんなことを司書は忘れているものだ。
休みだったのでSABU監督の「幸福の鐘」を観る。寺島進の顔がいい。ブラックユーモアをところどころに漂わせたおとぎ話のような映画。セリフをあれだけなくしているのにしっかりと見せる監督の手腕に驚いた。映像の美しいことといったら。
とあるサイトで「貸本マンガ史研究」という雑誌に桜井昌一さんが特集されていたことを知り、慌てて版元に注文メールを出したところ品切。在庫のありそうなところを教えてもらい、なんとか入手。あまり知られていないが、マンガの世界に彼の果たした役割はかなり大きい。水木しげるのマンガに出てくる歯の出たキャラクターのモデルが彼である。辰巳ヨシヒロは彼の実弟。
本屋さんに行くとついつい沢山の本を買ってしまう。という病がかれこれ二十五年ほど続いている。部屋をなんとかしないといけない状態がまたやってきたのだが、今までで一番なんともならない感じになってきているのであった。
暦の上では春である。小澤實氏の連載万太郎の一句がうれしい。
友人が知らせてくれたアサヒドットコムの四元康祐氏の連載も良い感じ。春と詩歌は良く似合う。
先日、名古屋シネマテークで「パリ・ルーブル美術館の秘密」を観た。ナレーションなしの一時間二十五分、断片ばかりの映像はかなりつらかったが、面白かった。文化大国フランスの底の深さを感じることのできる映画であった。
しばらく前から歯と顎と頬が痛いので歯医者へ行く。私の話を聞き、歯茎の具合を見た後、「悪くなさそうですね。多分、原因は歯ぎしりです」と言われる。レントゲンを見ても悪いところはなく、やはり歯ぎしりのせいらしい。寝ている間に歯ぎしりをしてるなんてなんだかやだな。私が歯ぎしりの音を生まれてはじめて聞いたのは大学のサークルでの合宿。ギリギリギリギリと謎の音が聞こえたのだった。「あれはなんの音だ」と友達に問うと、「K先輩の歯ぎしり」とのこと。前に友達はK先輩の下宿で泊まったそうで、「いびきと寝言と歯ぎしりと寝屁に悩まされた」と語っていた。そういえばK先輩の紹介で食堂のアルバイトをしはじめた奴がベソをかきながら、「先輩、あの店、おかまがくるじゃないですか。どうして教えてくれなかったんですか」と抗議をしたところ、「ん。お前、訊かんかったやろ」とK先輩は答えたのであった。ま、普通、「先輩、その店おかまは来ませんか?」と質問しませんわな。私はその先輩以外の歯ぎしりを聞いたことがないのだった。
ぼおっとしてるとすぐに十日ほど経ってしまう。連句アニメーション「冬の日」を昨日観た。35人の作家が芭蕉が名古屋の野水宅で参加した連句それぞれをアニメーションにした作品。最後にそれぞれの作家が制作意図について語っている。
一月ほどまえに入手したばかりの資料がレファレンスに役立つ。こういうとき、なんとなく幸せな気分になる。
イラクに大量破壊兵器がなかった、とデビッド・ケイ調査団長が言い、パウエル国務長官も保有問題は未解決と言ったそうな。このあたりを我が国のマスコミはトップ記事にする気はもはやないのであろうな。変梃な戦争に荷担している、のである。ぶちこわしておいて復興もないものだ。似たようなことを過去にされたのではなかったのか、我が国は。
なごやレファレンス探検隊に出席。自己紹介のあとクイックレファレンス。ここ数年くらいの日本人の海外渡航者行き先別人数をどう調べるか、というのが問題。2001年EDカードの廃止に伴い、今はわからないとの話が面白い。統計関連の調べもので肝心なのは実はそこなのだ。どこか(誰か)が数を拾って記録していない事柄についての統計は存在しない。と、当たり前なのだが、それを捉えた上でないと調べられないことを知っておくと、「調べようがありません」と答えることも可能。ただ、はっきり「統計はありません」と言い切れる場合はとても少ないのだが。S田さんはコミックマーケットで買ってきた岩波書店の児童書一覧や、読み聞かせについての本などを持ってきてくれた。コミケではそういうものも売っているのか、と驚く。「やおいは買ってきませんでした」と語っていたが、参加者からはあまり反応がなかった。もしかして「やおい」という言葉はあまり知られていないのかもしれないな、と思った私であった。コミケとかコミカ(確かコミックカーニバルと言ったのではなかったか)には大学生の頃先輩に誘われたが、怖そうなので行かず、そのまま今まで一度も行ったことがない。今後もきっと行かないだろう。「犬小屋の作り方」なる問題が出ていたが、私の勤務先では年に数件、この質問を受ける。閉架にある古い日曜大工の本などを出していた記憶。新しい本にはあまり載っていないのだな、と再確認。「ウィリアム・アーサー・ワードという人のことばについて」が面白かった。結局この人がどんな人かよくわからない。さまざまな資料が挙げられているが、同じ名の人がいたり、新聞記事にはっきりとわかる誤りがあったり、イギリス人なのかアメリカ人なのかも謎のまま。そのことばを書いたか言ったかしたのがどのウィリアム・アーサー・ワードなのかが判然としないという結末。私が調べた問題は「食べ物の陰陽について」。出した答に大失敗箇所があって回答集に目を通したとき愕然としたが、そこを詫びたりしつつ、易占関連のレファレンスで気をつけねばならないことなどを話したのだった。
F本さんは腹話術の人形「ともちゃん」を持ってきていた。腹話術の講座を受けたそうで、人形はレンタルしてもらっていたのだが、情が移ってしまい、9万円で購入。確かに見ようによってはかわいい人形である。レファレンス探検隊が終わってからの新年会ではF本さんと「ともちゃん」とでおめでたい藝を演じてくれた。彼の人生はこれからどうなってゆくのであろうか。
新年会ではすぐに酔っぱらってしまった私であった。前厄のひとがいたり、酉年のひとがいたりしたようである。ある図書館の臨時職員だったひとが名古屋市の司書区分に合格し、来年から名古屋市のどこかの図書館で働くとのこと。「入ってからが大変だよ」などと話す。ともあれめでたい話である。
連休も今日で終わり。評判の「ミスティック・リバー」を観る。映像が美しい。ショーン・ペンがすばらしい。ティム・ロビンスもケビン・ベーコンもマトリックスのモーフィアスさんもいいけれど、ショーン・ペンのすごみを感じた。重い深い映画だった。ショー・ペンってまだオスカーとってなかったのですな。なんだかとっくに受けてたように思ってたけれども。多分、私の今年の洋画ベスト5に入るであろう作品。
「アイデン&ティティ」を観る。原作はガロに連載されていたとき読んでたのだが、カエルのマンガを描いたりしてたみうらじゅんがヘンテコなものを描いてる、という印象が強く、シリアスなのか冗談なのかがよくわからなかったところがあった私。まとめて読み返していたらまた違ったのかもしれないけれど。映画は音が出るのが強い。まだ観てないひとは観た方が良いと思います。田口トモロヲの映像感覚もすばらしい。久々に興奮した映画。
週刊現代今週号のイラク派兵50の疑惑が面白かった。ああそうだろうなあ、と思われる箇所がいくつか。大新聞も気づいているはずなのにそこまで踏み込めないのはなぜだろう。なんとなくそういう雰囲気になって、ああそうかな、とぼんやりたくさんの人がそう思っているうちにおかしなことになってゆく。過去にもこの国はそんな時期があったのではなかったっけ。第二次大戦経験者が歳をとり、死んじゃったり元気がなくなったりしたとき軍隊をしっかりさせよう、と実はとうの昔に決めていた、なんてことがあったりして。良いことじゃない、と思っていても雰囲気に抗えなかった、と言った人がさきの戦争のあとには沢山いたのではなかったろうか。ヤな感じ。
おや。なんかへんなメールが来るな、と思っていたら、私、ぼけていました。今月4日の日記が飛んじゃっていたのですね。書いたのに。ただの私のミスでした。その次が7日の記述だから4日に私が書いたことが規制されたのかと思われてしまったのですが、全然そんなことはなく、私のだらだらとしたマスコミ観察でなんとなく感じたことを書いたのでした。ご心配をかけた方、すみませんでした。_●_
ま、飛んでしまったものはしかたがないので、4日の日記は元々なかったことにします。
メールと言えば、アドレスが書かれていない方からの質問がありましたが、返事のしようがないのでした。「図書館の自由に関する宣言」の1979年改訂はなぜ行われたのか、との問い。もしかして、大学生の宿題だったりはしませんか、と疑り深い私は思うのですが、010に分類されている本のなかに図書館の自由についてのものがありますので、一度お探しください。Webのサーチエンジンで、「図書館の自由」で引いても出てきます。返事のいるメールにはアドレスを書いてくださいな。
JR高島屋の第一回大古本市に出かけた。初日の9日に休める予定だったのだが、最終日の今日まで休みがとれなかったのだった。デパートの古書展に来たのは何年ぶりだろう。古書会館の古書展には時折出かけるのだが。第一回についつい惹かれてしまったわけだが、掘出物、と思われる文学書の初版が何冊も残っていたりする。買おうかと悩んだ本もあったが、部屋がいっぱいいっぱいの状態なのでそれは止し、映画関連の本を買う。集める気で集めていた作家の本が集まってしまうと、また別の作家の本を集め、といった循環が無くなってしまった今の私は古本にときめかなくなっているな、と感じた。
高校サッカーは国見対筑陽。後半16分までは1対0。しかし平山が2点目を入れてから試合が崩れてしまった。前半終わり間際のゴールが決まっていたらどうなっていたかわからなかった試合。国見は攻撃面ばかりが注目されるが、守りもとてもかたいチームであった。初出場で決勝まできた筑陽は超攻撃的なチームで楽しいサッカーであった。桑原が良い。コンサドーレ札幌に行くそうだが、今後が楽しみ。
鏡開きである。しかし、私はうっかりと日を勘違いしていて、すでに食べてしまっていたのであった。食べたと言えば、今年に入って五日で二キロ太り、戻らない。さてどうしよう。
F本さんからの年賀状にはお名前のスタンプのよこに「フニャモト」とルビが振られていた。
エクセルを使って細かい表を作っているここ三日間。老眼になるときっと大変だろうな、と思う。
ビッグコミックを暮れに久々に買った。二十年ぶりくらいか。山上たつひこの「中春こまわり君」を読むためである。昨日、後編を読む。五十六歳の人がこれを描いたのか、と思うとかなりの衝撃。私は何カ所かで笑ったのだった。懐かしさももちろんあるが。楽屋落ちが多いのは「喜劇新思想大系」からなのだが、これを批判する人が幾人かいるようである。サンコミックスで出た「光る風」をまとめて読んでから狂い、「人類戦記」を読みたくてCOMを集めた高校生の頃のことをふと思い出す。なぜか「まんがジャイアンツ」という雑誌までマニアの人から買ったりもした。その関係で文通していた人が幾人かいて、何年か前、部屋を整理していたら、そのなかに赤田祐一という名前を見つけた。この人とは喧嘩別れのようになったのではなかったか、と記憶している。原因は私にあるはずだ。インターネットなんて想像もしていなかった二十五年ほど前の話。なんてことも思い出したり。
わずかに残っていた童話賞の仕事が終わった。明日からは溜まった仕事に本格的にとりかかるのである。
「新潮」2月号、四方田犬彦と坪内祐三の対談が面白い。68年に私は小学校に上がり、72年には切手マニアの小学五年生であったのでかすかな記憶があるわけだが、それ以降に生まれた人たちにとってはどうなのだろう。すが(糸偏に圭)秀実についての箇所もあり、ツツイスト関連の方必読(かな)。
グランパスの補強はなかなか大したものではある。大野は好きな選手。楢崎が海外でプレーするとなれば、川島を獲得したのは手柄。角田は荒いところもあるけれど、将来の日本を背負ってたつディフェンダー。問題は右サイド。石川直宏は来ないかな。って、来ないか。開幕が待ち遠しい。
言論統制ってはじまってませんか。ま、朝鮮戦争あたりから少しずつ不自由になり、風流夢譚事件以降自主規制が強くはなったわけだし、意識を変えるのではなく、言葉だけを狩るなんてこともあったりしたわけだけれど、ここへ来ていよいよマスコミは書いちゃいけないんじゃないか、といった事柄が増えてくるのではなかろうか、と思っちゃう疑り深い私。当然のことだが、図書館員も無関係ではないぞ。「図書館の自由に関する宣言」を今一度しっかりと読んでおく時期かもしれませんな。言論弾圧と図書館の自由についての話を昔、仕事場で若い職員にしたところ、「図書館って危険を伴う可能性のある職場だったんですね」と言われたことがあるが、実はどうやらそうなのである。ま、知ってて入った人がほとんどであろうとは思うが。
そういえば店の開くのが早い。スーパーマーケットはどこも1日から開いている。そしてなぜか混んでいる。働いている人達は大変である。ま、別にどうでも良いと言えば良いのだが、正月が正月らしくない気がするのは私だけか。二十年前には4日からの営業が多かったわけで、保存のきくおせち料理に意味もあったのだが、そろそろおせち料理は滅びるのであろうなあ。暮れにウラジロを探した。鏡餅も探した。橙も。どうやらパックに入った餅の上にプラスチックの橙らしきものが載っているのが主流になってきているらしい。日本の危機ではなかろうか。鏡餅を飾らなくとも、おせち料理を食べずとも、注連縄飾りを玄関につけなくとも年は明けるのだけれども。クリスマスのほうが位が高くなってきたのであろうか。
年賀状を35通出したが、1日に来たのは15通だった。どんどん友達が減っている。10年前には70通ほどのやりとりがあったが。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨晩早く寝て、真夜中にひとりで単車に乗って初詣。三時に近かったのでほとんど人がいなくて平和。近所の寺では読経の声が聞こえていた。お坊さんは大変だなあ、と思う。
ようやく部屋にこたつを出すことができた。出した途端、猫のノラが入った。年賀状も出した。年の瀬である。
グランパスの酒井友之選手はレッズへ移籍。私が一番好きなJリーガーなのだが残念。ネルシーニョ監督の戦術と合わなかったのかなあ。ベルデニック監督時代にはずっと先発だったが、最近は先発からはずれていたのであった。レッズで活躍できると良いな。才能だけは間違いなくあるわけで、欲のなさが問題なのであろう。新しく来るのは清水商業のGK河野、アントラーズのDF秋田、MFにベガルタ仙台の岩本輝、愛媛FCから18歳の西川。MFの競争は今年も激しそうだ。
村上ポンタ秀一の「自暴自伝」が良かった。日本の音楽を好きな人の必読書といった感じ。
なごやレファレンス探検隊の回答&コメント集が届く。名古屋市のF本さんがいぬふぐり庵日乗をパスティーシュにしている。「水虫のガク(7歳♂)が夜中にまだ暴れている(T_T)」などと書いたりしている。なかなか上手だが、悔しいのでここでF本さんの本当の名字を明かしてやることにする。フニャ本さんというのが正体だ。というのは嘘だが。
メリー、クリスマス。って、もう過ぎましたが。年賀状をまだ書いていません。なんとかせねば。年の瀬ですな。
先日、ムーンライダーズを観にいったら、会場で図書館によくいらしていた五十歳くらいのお客さんとばったり。「ずっと来てるの?」「ええ、まあ。長いんですか?」「いや、最近知ったの」などと短い会話を交わしたのであった。ムーンライダーズを好きになり始めるのに年齢は関係ないのだな、と思った私。図書館のヘビーユーザーには柔軟な精神を持った人が多い気がする。意固地な人ももちろんいるが。
先週、報告書を作り送ったので、これでほぼすべての童話賞関連の仕事が終わった。
何日か前、「蛇イチゴ」をつみきみほ目当てに観た。宮迫博之がとても良かったのに驚いた。映像がきれいで、話の展開が面白くて、終わり方もすっきりとした良い映画だった。
小川美潮のユニット「シンシュンのミ」をTOKUZOで観た。生の小川美潮を観るのは初めてだったのだが、あのちっちゃな体からどうしてああいう声が出るのだろう、と不思議に思った。聴いてる間、幸せな感じであった。
「ブルース・オールマイティ」を観た。昔のアメリカ映画みたいだった。古き良き時代のアメリカ。ジム・キャリーのわがままな感じが良かった。
いよいよ派兵。いくつかのテレビ番組で批判的なコメントを見るが、どうして3月とか選挙前に大きな声を挙げなかったのかな、と思う。
童話賞作品集の発送作業。
寒くなってきた。風がびゅんびゅんとゆらす竹藪へ昼休に出かける。そこに狐が葬られている。なんということもない竹藪なのだが、厳かな気分になるのである。もうじきなくなってしまうとのことなので時折出かける私である。時代から取り残されたかのような空間。
サダム・フセインが捕まった。状況はどうなるのだろうな。ニューヨーク市民がインタビューを受け、すぐにすべてが解決するかのように答えていたりするが、そんなはずはないのではなかろうか。異なる宗教を持つ異なる民族間の争い。目的は石油。簡単に終わらないくらいすでにこじれている。戦争も自衛隊派遣もフセイン拘束も結局みんな今のところ他人事。自分とは関係なさそうだな、と思っているうちに真横まで戦争はやってくるのであろう。
土曜の朝、ワールドユースの日本対ブラジル戦を観る。彼らの今後の成長が楽しみである。トヨタカップ。ボカ・ジュニアーズはしたたか。ああいう試合を生で観たら楽しいだろうな。
三連休も今日でおしまい。名古屋シネマテークでオタール・イオセリアーニ監督の「月曜日に乾杯」を観る。去年のベルリン国際映画祭で監督省と国際批評家連盟賞をとっている作品であり、予告を観て良さそうだったので期待していったのだが、私の好みではなかった。映像は確かにきれいなのだけれども。キアロスタミ監督の「10話」も観ようかなと思ったけれど、腰痛の予感があったので止した。パルコのとある店で女ものの傘を買う。小ぶりでなかなか良いデザインなので欲しいが、高いし、どうしたものか、としばらく悩んでいたのだが、思い切って買うことにした。盗まれぬように気をつけねば。一月ほど前に病院で盗られたのであった。もしかしたら間違えて持っていったのかもしれないが、そろそろ日に灼けて変色してきてはいたのだが、かなり高かった傘なので悔しかったのだった。二年ほど使ったのだった。その前に持っていた傘は熱海で新幹線を降りるとき忘れてきた。それは中国製の安い傘だったのだが、デザインが気に入っていたのだった。と、傘について思い出しはじめるといろいろな記憶が蘇ってくるのは面白い。
「ラストサムライ」を観る。渡辺謙はやはりうまい。馬がいかにも外国の馬であったし、「村」に天皇の側近だった男がいたり、侍に天皇がものを尋ねたり、と謎めいたところはあるが、外国人がつくったにしてはなかなかしっかりとできていた。吉野からどこまで馬に乗っていったのだろうなあ。途中で富士山が見えたけれど。フジヤマが見える、ワハハ、と、ムーンライダーズのコンサートをこないだ観たばかりなので頭のなかに一瞬「トンピクレンっ子」のフレーズが流れた私であった。小雪の子供役のひとりが肘をついてご飯を食べていたが、あれがかなり気になる私は歳なのだろうか。アラ探しに熱中してしまう癖を治したい私ではある。「ボブ」の役の福本清三もとても良かった。
表彰式、無事終わる。ふう。
イラクで亡くなった二人の葬儀。どこが危険でどこが安全なのかと問われて「私にわかるわけがないじゃないですか」と発言した首相が泣いている。泣けばいいってものかな、と嫌味なことを考えてしまうのは私だけだろうか。これからもっと沢山の人が死ぬかもしれないが、そのたびに泣くつもりなのだろうか。
大学生から司書、学芸員になるには、といった質問があり、名古屋市と愛知県の司書にも尋ねてみた。しっかりとした司書から冷静で論理的で実体験に基づいた回答を得る。なんとなく幸せである。
真夜中に起きて、ワールドユースの試合を観ている。谷澤と今野、茂木が良いな。川島も素晴らしい。平山もとても期待できるFW。筑波大に進学希望とのこと。卒業したらグランパスに入ってほしいものである。グランパスの山口慶はコロンビア戦に先発したのだけれど、後半に替えられてしまったのであった。どこまで勝てるかが楽しみなチームである。
お巡りさんが常識では考えにくいことをしていたので、逆上した私はクレームをつけたのであった。なかにはどこでなにをしてもいい、と考えている人がいるのではないか、と一瞬疑ってしまう。
表彰式の準備、着々と進む。
くど(かまど)の表面に塗ってある黒いものはなにか、との問い合わせ。館とは少し離れた場所にある市の管理する建物のなかにある展示物。わからない。問い合わせた人は個人でくどをつくっているとのこと。あちこちに尋ねてみると、とてつもなく詳しい学芸員がいたりして面白い。しかし、それについてはすぐにははっきりせず、のちほど博識な人から連絡があることになっている。世の中にはいろいろな人がいて、世界は豊かなのだな、と感じる。
土曜日は休みだったのでテレビでFマリノス対ジュビロとアントラーズ対レッズを交互に観ていた。丁度シュートシーンを見逃したりして慌ただしかったのだったが、どちらの試合のロスタイムでの得点も観たのであった。劇的。昨日の早朝、というか一昨日の深夜、ワールドユースを観る。99年のワールドユースに熱中したことを思い出す。あの時の酒井友之選手は良かったなあ。あれでファンになったのだったが、とても遠い昔のことのような気がする。
「フォーン・ブース」を観る。なんだかなあ、といった終わり方。私の好みではない。このところ、本も映画もハズレが多い。そういうめぐりになっているのかもしれない。
報道管制がまだ敷かれてはいないのだなあ、となんとなく安心する。しかしほかの国の死者についての報道が少なくはないか。イラクに派兵をするとどれくらい良いことがあるのかを明確に語った人はいたのだろうか。悪いことが沢山あるようなのに、良い点をしっかり話してくれなくては困るはずなのだが、そのあたりが曖昧なまま、ただなんとなく派兵せねばまずいかのような雰囲気になっていたのはどうしてなのだろう。戦争に荷担しないと世界の仲間はずれになるような気がする、というのは湾岸戦争のあとにぼんやりそんな風に思えるようになっちゃったのであろうなあ。別に行かなくったって大したことはないと思うが。確かにイラクは悲惨な状況であり、なんとかなると良いと思うし、奥という人の報告は正義感に溢れたものであると感じるのだけれども、元々は誰のせいでここまでのことになっちゃったのか、その国に味方をした状態のまま、目の前のことをなんとかすればすべてが解決するのか、といった洞察があったのかな、と亡くなった人には申し訳ないが、そんなことを考えたりする嫌味な性格の私である。正義は人を殺す、という山本夏彦の言葉を思ったり。ところでこれから先、イラクにどかどか自衛隊が沢山行かなくちゃいけなくなって、アメリカも行っちゃってて、その隙にどこかの国が日本を攻めてきたらどうなるんだろうかな、なんて変なことを考えてみたりするのは私だけだろうか。
遙か遠くから来館した学生さん。一時間ほどかけて文学散歩コースを歩いたとのこと。以前にもいらしたそうな。オペラの役づくりの参考のためだというので、いろいろと資料を提供。若く熱心な人がいるとほっとする私は歳をとったのだな、としみじみ思ったり。
童話賞表彰式が近づいてきている。どうやら司会もすることになっているらしい。向いていない私である。
レファレンス探検隊の宿題を昨日投函。答え方によって質問者の読書傾向が変わるかも知れないなどと想像すると楽しい問題であった。
名古屋シネマテークで「くたばれハリウッド」を観る。原作と違うところがあったりする。どこまでが本当かわからぬあたりが面白さなのかもしれない。おしまいのダスティン・ホフマンが良い。ちくさ正文館で「東京人12月号」を買う。志ん生、馬生、志ん朝の特集。小朝の話がとても良い。
友達のお父さんから葉書。友達の死を告げている。一度も会ったことはない友達。車椅子の生活をしていたひと。アサヒネットでは以前、今現在アクセスしているひとのIDを知ることができた。IDからそのひとのプロフィールがわかる。ユニークで上手いプロフィールが書かれていた。筒井康隆さんのファンなのに筒井さん関連の会議室に書いていないひと。それどころか会議室にまるで書いていない。いわゆるROM。私はそのひとにメールを送り、書込をしてはいかがですか、と勧めたりもしたが、結局書くことはなかった。手紙のやりとりもときどきあった。うちの飼い猫ノラの写真を送るとそのひとの飼い犬の写真が返ってきたり。彼女には婚約者がいたのだが、病死し、彼らが一緒にゆこうとしていた土地について調べているのだけれど、わからないだろうかとのメールがきた。調べものの好きな私はインターネットで探したりして、メールで返事をした。彼女はずいぶん喜んでいる様子であった。姿形をまるで知らないし、声も一度電話で聞いたきり。でもどんなひとなのかをなんだかよく知っている。そんな不思議な友達が幾人かいる私である。突然の訃報に驚いた。今頃は婚約者と仲良くしているだろうか。
昨日のグランパス対レッズ戦は4対1と快勝。しかし優勝の可能性はゼロになった。来シーズンが楽しみ。
なごやレファレンス探検隊の次回分の問題を調べている。楽しい。ある程度資料の見通しがつき、利用者にどのような道筋で話をするかを考えたりする。
森田芳光監督の「阿修羅のごとく」を観る。NHKで昭和54年に放送した同作を観ている人にはつらかったのではないだろうか。はじめのほうで、「ななじゅう」「よんじゅう」とせりふが出てきた段階で、これはよくないな、と感じてしまった私。今から二十数年前であれば、「しちじゅう」「しじゅう」であったはず。「ジョギング」という言葉は当時普通に使われていたかな、とか、細かなことが気になる。和田勉演出はずっとどきどきわくわくだったのだが、この映画版はずるずるゆるゆるに思えてしまった。うまい役者があれだけ揃っているのにみな下手に見えてしまう。仲代達也など嫌味が漂ってしまった。佐分利信はああではなかった、などと思ってしまってはもういけない。大竹しのぶ、三津五郎、桃井かおりのからむシーンは良かったけれども。なんだかがっかり。リメイクがオリジナルよりも良いケースは稀だとは思っていたが、森田芳光が敢えて撮ったのだから、と期待して観にいった私が愚かであった。
休み。服のバーゲンに出かける。知人が勤めていた有名ブランドの服の縫製をしている会社のバーゲンなので、以前は客が少なく、とてつもなく安く平和な感じだったのだが、ここ二三年は戦場のようになっている。仕事着、普段着を年に二回のこのバーゲンの服で済ませている私。今年起きた異変にはしかし驚いた。春もそういえばいたな、と思い出したのだが、子供が多いのである。靴を履いた子供を背負ったおとうさん。「ここどこここどこ」と叫びながら走り回るお子さま。私はぶらさげてある服に鼻水やよだれや泥がついたりはしないだろうか、と心配になった。預けるのは難しいのだろうけれど、服も欲しいのだろうけれども、服屋さんの下のほうは埃っぽく子供にも良くないし、なんというかしつけが終わっていない年頃の子供を連れてきちゃいけないところといいところの区別が、もうこの頃まったくなくなってしまいましたな。これが段々と当たり前になってゆくのだろうなあ。そういえば、こないだコム・デ・ギャルソンでぶらさげてあるコートにもぐる子供を叱るでもない母親を目撃したなあ。十数万円のコートの裏地に鼻水はついていないか、と不安になるのは私だけであろうか。当然だが、子供が悪いのではなく親の問題である。
某図書館に雑誌の閲覧、複写のためにゆく。自分が図書館で働いていない時期によその図書館を純粋に客として眺めるのは就職してからはじめての経験。昼の人出が少ない時間にいったこともあったためかいろいろと気になった点があった。まず、誰に尋ねればいいかがはっきりしないこと。カウンターの中での仕事が忙しいのか、カウンターに近づく私にすぐに気がついてくれる職員がいなかった。「こんにちは」とこちらから知った人に声をかけてからやりとりがはじまる。私の勤めていた館ではひどいときにはもっとひどく、カウンターで発注などの仕事をしていたりして、どちらかというと利用者に接するより、そちらに熱心だったりして、利用者をないがしろにしていた。客がこなければ仕事がない、という基本を図書館員はついつい忘れがちなのである。カウンターの職員はすぐ客が尋ねることのできるような姿勢でいないといけないのであった。と、自分のことはいくらでも棚におけるというのは気楽なものであるなあ。それとサインがわかりづらい。どこがなにをするところなのかが見づらい。「1番に」と言われてもそこから1番がどこにあるのかがわからないのはつらい。それから、待たせていい利用者と待たせてはいけない利用者をしっかりと分けたほうがいいように思った。閉架資料を出してもらっている間は少しくらい待っても良いのである。私の勤務先では待つ場所がなかったので待たせてはいけない利用者となってしまっていたが、ここは広いのであった。ただ、どこで待っていてください、とは言いづらい作りではある。ほんとうは「どこそこでお待ちください。お呼びしますから」と案内してもらうと安心だったのだが、そういうスペースはなさそうであった。どこでどうしていればいいのか、とはじめての利用者はとまどうことであろう。時間のかかりそうな利用者と時間のかからない利用者とを切り分けることも必要ではないか、と思った。忙しい、職員のいない時間帯でのことなのでしかたのないところもあるが、なにがなにやらよくわからぬまま、お使いでやってきたお年寄は慌ただしく処理をされてしまって、もしやあとから不平を抱いていはしないだろうか、さらに投書マニアだったとしたらどうなることであろうか、と他人事ながら不安になった。 すんなりわかってくれない、もしかすると淋しいかもしれない利用者を柔らかく、そして手早く扱うことができる箇所があると良いのだが。ずらりと人が並んでしまっているときに感じる威圧感というか脅迫されているかのような気分でいる職員。そんなことはおかまいなしに自分の話を長々としようとする利用者。そこで早く処理をしてしまおう、と考えるのは人の常なのだが、「恐れ入ります、こちらのカウンターでお話を伺いますので」と利用者に動いてもらって自分はそこから逃げる、という方策をとれると良い。正規の、水準の高い職員があれだけ並んでいるのに、なんというかもったいない状態のように感じた私であった。人手不足の場合、ごく普通の貸出返却業務については臨時職員や若い職員にまかせてしまい、そこからはみでた仕事をヴェテランが受ける、といった格好にできるのではないかと思ったのであった。カウンターが短く、その人しかいないっていう状態であればともかく長いカウンターだもの。簡単ではないと思うけれども。などと好き勝手に感じたままを書いたけれども気を悪くしないでね。
ノラは寒くなっても朝早くから暴れる(T_T)。
部屋の掃除をする。かなり久しぶり。本だらけでどうにもしようがなく、とりあえず廊下に少しずつ本を出し、あいたところに掃除機をかけ、本を動かし、掃除機をかけ、とよくわからぬ作業。雑然と積んであった本を真っ直ぐに積みなおし(当然分類などするはずもない)、歩けるスペースができた。そろそろ本気でなんとかせねばなあ。
昨日の余韻にひたっていた私であった。ピチブーは偉い。楢崎のミスのあと、楢崎コールがF・マリノスサポーターから起きたときには悔しくて腸が煮えくりかえりそうになっていましたが、最後はしょぼんとしていた彼らを気の毒に思いました。これで優勝の目が残りました。レッズが2試合負けないといけないあたりが少し大変ですが、1試合は直接対決なので可能性はあるな。大分に負けたりはしないだろうな、と少しびくびく。酒井くんはベンチにもいませんでした。どうしちゃったのだろ。グランパスのMFは競争が激しい。海本幸治郎が3点目を見事にアシストしたのであの位置にはしばらく定着するだろうし。 しかし来年のグランパスのカレンダーに載ってないのはヘンだと思うぞ。ピチブー・ウェズレイのハットトリックはたいしたものでしたが、すごかったのはマルケス。松田に出た2枚のイエローカードはどちらもマルケスに対するファールでした。
日本国民はいつまで高枕で寝ていられるのであろうなあ。と、なんだかわからぬひとりごとをつぶやいてみたくなる。
なごやレファレンス探検隊。いろいろなことを思う。面白かったのがF本さんが出したクイックレファレンス問題。「チャールズ・ディケンズの書いた『ブラムストーカー』か『判事の家』を読みたい」。何を使ってどう調べるかというのが出題なのだが、「電算を使って、それぞれの言葉でOPACで探す」という答えばかりが出てくる。ブラム・ストーカーが『ドラキュラ』の作者であること、メアリー・シェリーが『フランケンシュタイン』の作者であること、くらいは数年働いた司書であれば知っていたほうが良いと思う私である。まず、『ブラムストーカー』という本の存在が怪しい、と疑うところからはじめるのがこのレファレンスでは重要。『判事の家』だけを探せば良くなりそう。それと、なにでこの本を知ったか、原タイトルはわからないか、などということも尋ねると良い気がする。日外アソシエーツの『文学綜覧シリーズ』がなかった時代、インターネットがなかった時代を経ているのと経ていないのとではもしかすると図書館員の在り方が違ってしまっているのではないか、と妙な違和感を覚えた。『判事の家』を東京都立図書館のページや国会図書館のNDLOPACで引けばどの本に収録されているかがわかるというのが答えだが、それは結果であり、その前にいくつか疑うべきこと、利用者から聞き出しておくべきことがあるのだ。だが、それを聞き出さずとも答えが出てしまうあたりが今の時代の司書の難しさかもしれない。回答集のなかに藤原正彦の名が出てきて、藤原ていの次男と書かれていた。藤原ていよりも新田次郎の息子と紹介されていることが多い。それは新田次郎のほうが有名だから。藤原正彦のエッセイにも息子が東大に受かったことを喜んだ新田次郎が飲みにつれてゆくところが書かれている。問題だな、と感じたのは藤原正彦の名前を知らない司書が幾人かいたこと。作品を読んでいなくてもNHK教育テレビに講座を持ち、日本エッセイストクラブ賞を受賞しているほどの数学者の名前は知っていなくてはいけない気がする。「藤原正彦の本ありますか」との問いに、「しばらくお待ちください」と答え、電算で調べれば所蔵がわかるわけだが、電算を叩かずに、「ああ、あの新田次郎の息子さんの数学者ですね。はい、こちらに」と案内することができたとしたら利用者からの図書館への信用は上がるはずである。そうしたことの積み重ねが司書にとって重要なのではないか、と私は思う。司書にとって大事な心がけは固有名詞を沢山覚える気で覚えることだ。それは一生かかっても終わらないのである。と、苦言を呈したが、この集まりは若さと活気に満ちていてとても良いものである。40を過ぎた私にも、世の中まだまだ捨てたものではないな、と力が湧いてくる気がする。S田さんが「『WEB本の雑誌』がやっているような、こういうブックガイドの仕事、本来司書の仕事のはずなんだよねえ」と回答集に書いているのは競輪についての小説がないかとの問題についてのこと。小説の中身をジャンルに分け、そこに該当する作品の一覧を作るのは確かに司書の仕事。ジャンルを抜き出し、沢山の図書館に尋ねて集めてまとめればできないでもない気がするが、本を読んでいない司書や、役所から嫌々飛ばされてきた司書の多い現状では難しいかもしれない。また整理するのが膨大な量にもなる。「全国の司書たちがこういうものを作りました」なんて言えるものができると素敵だと思うが。F本さんの「読書案内とレファレンスの違いについて」の質問も良かった。児童サービスには読書案内があるが、大人に対してはない、と思っている人が多かったのは大きな図書館の司書がほとんどだったからではないか。とくに小説について、「次は何を読もうかと悩んでいる」とか「こういうミステリを読んで面白かったけれど、ほかにそういうのはないか」といった質問はしばしばあった。うまく答えられていたかどうかに自信がないのと、この頃ボケ気味で忘れていたため、昨日の場では報告しなかったが、確かにそういう仕事をしていた。利用者との距離(近づきすぎず、遠くなりすぎずといった微妙な)、信頼関係の深さによってそうした質問ははじめて出てくる。司書に営業は必要なのだと私は考える。どういうのを次に読もうか、と訊かれ、答えるのは実に難しいのではあるが、司書らしいといえばこれ以上司書らしい人間らしい仕事はないかも知れない。頻繁にそんな質問をしていた利用者たちは皆死んでしまったなあ。彼らに対して少しは何かができたのではないか、それは私が司書であるからだ、とそんな気がする。
仕事で大変な間違いがあり、申し訳ないこととなってしまっていた。大変であった。
私が愛読している数少ないページに書かれていることに愕然とする。日本はここまで来ているのか。来ているのであるな。日本語がわからない人と接しているのではないか、と感じることは時折あったが、本当にわからない日本人がかなりいるのではなかろうかと思えてくる。この国に果たして未来はあるのか。ところでこのページ、たまたま存在を知っただけで、どんな会社なのか、社長がどういう人なのか、まるで何も知らない私。乱暴な言葉や私にはまったくわからぬことがらが書かれていたりもする日記なのだけれど、感じ方が似ている人であるな、と読んでほっとするのである。彼女の斉藤孝批判は正鵠を射ていると思う。本を三色ボールペンでえどくるな、と私も店頭で憤ったのである(註:えどくるは三河弁で落書きをするの意)。
明日はレファレンス探検隊。楽しみ。
図書館における複本の購入がしばらく前から問題になっている。ところで、読む本が画一的になっている、なんてことまで図書館のせいにされているのはおかしくないか。同じ本を読みたい人が多いから図書館はしかたなく複本を買うのである。図書館が買うから同じ本が読まれるのではない。極端に沢山の複本がある館は別にしてベストセラーは本棚にはないのだ。いつも貸し出されているか予約の連絡をしたのち、カウンターの内側に置いてある。図書館の本棚に沢山並ぶ本を見て皆がそれを借りてゆく、と考えている人がいるとしたらそれは誤りだ。昨今のマスコミの報道のほうが画一的ではなかろうか。
「キル・ビル」を観る。死を軽く、重く扱えるのは映画の特権。すべてを笑い飛ばすことができるのは力であろう。好き嫌いが別れる映画。R15は妥当かな。観ちゃいけない大人ってのもかなりいるような気がする昨今の我が国ではある。この映画のカルチュア・ギャップを笑えるのは日本人だけ。タランティーノはよほど日本を好きなのだろうな。死んだ友人は彼と顔立ちがよく似ていた。映画好きだったけれど、タランティーノは観てたのかな。
飼い猫のノラ(8歳♀)が夜中にまだ暴れている。早く寒くならないものか。
約6年ぶりにデジタルカメラを買い替える。500万画素。近々どこかにノラの写真でも載せようと思う。1センチの接写ができるとのことなので、ノラの耳のなかの写真などもどうであろう。って、それではなんの写真かわかりませんな。なにかリクエストがありましたら、お気軽にメールしてください。
館内展示の案内をする。三度目。短歌の会の方たち。三分の一ほどのところで突然ふしぎな音がする。「きゃあ」「ああ、倒れられたわ」「救急車」。男の人が倒れ、意識不明となっていた。すぐに救急車を呼ぶ。意識はすぐに戻り、顔色もよくなってきていた。図書館では何年かに一度救急車を呼んでいたが、ここでは開館以来はじめてだとのこと。幸い一時的な軽い症状とあとで聞く。「呼吸をしていないようだったら気道の確保と人工呼吸をしておいてください」と救急隊の人に電話で言われたが、三年ほど前に受けた講習をかなり忘れてしまっている私は焦ったのであった。復習しておかねば。
入選者から念書などが返送されてきている。喜んでいる様子を手紙で伝えてきてくれる人もいてなんとなくうれしくなる。
数日前、アメリカからのAIR MAILで童話賞への応募作品が届く。締切をとうに過ぎているのになあ、と消印を見ると締切に間に合っている。封筒を見るとJAPANではなく誤ってJAMAICAに送られていたとのこと。一月半もかかっては困ってしまう。手紙で来年度にまわします、と詫びる。JAPANとJAMAICAではJAしか合ってないではないか。アメリカの郵便屋さんには泣かされる。
童話賞の入選内定者に送る文書などを作成。ひとりずつ微妙に違うのを何種類か作るという細やかな神経を使わねばならない私に向かない作業なので、なんとなく頭髪が薄くなってくるような気がする。
利用者との接触がそれほど多くない仕事場にいると、図書館の現場のどこがどう楽しく苦しいのかがわかる。図書館では毎日、何が起きるかが見当もつかないのだ。突然不思議なレファレンスがきたり。いつも違う仕事をしている感じ。それは本の一冊一冊すべてが違うからなのである。一人として同じ人間がいないように。案外図書館員はそんなあたりまえのことを忘れているのである。
昨日のグランパス対ヴィッセル神戸戦の衝撃からまだ立ち直っていない。しばらくは駄目かもしれない。今ステージのホームゲームをすべて観ているのだが、なんとなく優勝できるのではあるまいか、という気がしていた私。どうして公式戦初出場の深津を使ったのであろうなあ、とか、酒井選手は控えにもいなかったけれど海本兄もいなかったけれど、そんなに調子が良くなかったのかな、とかいろいろ考え込んでしまう。GK本田がぽんとボールをはずませた瞬間にすべてが終わってしまったような試合であった。なんという失点。
笠智衆への批判を山本夏彦が書いたところ、かなりの抗議文が届いたという話があるが、実は私も笠智衆になじめないのであった。先日BSで小津のはじめてのトーキー作品「一人息子」を観ていて改めてそう思った。寅さん映画を小学生のときに観、御前様とは九州の人のことを言うのかな、と思い込んだ記憶が蘇ってきたり。
若い人から時々メールをいただくと元気になる。と、書くとすっかり歳をとったような気がする。二十年前に深刻に考えて込んでたことのうち、どれだけを覚えているだろうか、と落ち着いて思い出してみようとすると、その時期の自分に戻ったような感覚がやってきてすぐに去る。
ぼんやりしていると一週間があっという間である。土日の仕事場は混んだ。児童書の古書を注文した。児童文学の世界はなかなか大変そうであるな、と研究書や概説書をぱらぱらと斜めに読んで思う。私には向いてない気がする世界。しかし仕事なので、そうも言っていられない。図書室の長椅子の上を靴を履いて歩く幼児。親が隣に坐っているので注意。
先日の大学生より、大学院を修了してからのほうが図書館、博物館に就職しやすいかとの質問。知人にも確認した上で回答をする。どこを出ても就職は難しい、というのが答え。就職したからといって一生働いていられるかどうかもわからぬ我が国の情勢。明るい返事をしたいものなのだが。
休日、M坂屋の上の階にあるイタリア料理店ですさまじいものを目撃。なかなか立派な店のランチタイム、食事を終え、カプチーノをぼんやりと飲みながら、遠くの席に目をやると若いきれいな娘さんが二人、一心不乱に化粧をしていた。列車のなかでの化粧は、もはやあちこちで見るようになったが(私はもちろん嫌いだ。例えば男が列車のなかで鼻毛の手入れをしてたら大抵の人が気持ち悪いと思うはずだが、それとどのくらい差があるというのか)、飲食店であんなに激しく顔を塗りたくっているのを見たのははじめてである。店の人は注意しないようだ。気づいたのが食事中でなく、また、席が近くなくて良かった。私は禁煙席、彼女らは喫煙席だったから一緒になることはなかったのであるな。気管支が弱くて10年ほど吸っていた煙草を26のときにやめた私。知らぬ間にもしかすると席の上に靴を履いたまま立ったり、食べ物屋で化粧したりというのは常識になったのかもしれないぞ、と感じる。カウンターの上に赤ん坊を乗せる人と乗せない人とどっちが多いだろ、と考えると、もうあれは注意をしても駄目だな、という気がしてくる。常識は変更されたのかもしれない。歩きながら一人で大きな声で喋るのは以前は病気の人か酔っぱらいだけだったが、今は町中に溢れている。携帯電話とは恐ろしい発明である。気にしない人、慣れてしまう人の勝ちである。携帯電話といえば、先日車を車検に出したとき、連絡先の携帯電話番号欄を記入せずにおいたら、「ここもよろしければご記入ください」と言われ、「いえ、持っていないんです」と答えると、「主義ですか」とにこりと笑った。いまや携帯電話を持たぬのは主義かもしれないな、と思った。世の中は恐ろしい速さで変わっているのに、もはや誰もそのことを口にしなくなっている。言う暇もないのかもしれない。
児童文学賞の第二次審査会があった。用意しておかねばならないものをすっかり用意し忘れていた。審査員の先生にお願いすることがらの内容を間違えた。帰りに駅までお送りする際、元々スイッチが入っていた公用車のラジオのスイッチを消し忘れたまま走っていたことに館まで戻ってきて気づく。緊張していたのであろうな、と翌日思い当たる。ただの粗忽者ではあるのだが。
仕事場での一年で一番慌ただしい週が終わり、平穏になったかと思いきや、パソコンが不調。私がさわると調子がおかしくなるような気がする。
先日の大学生よりメールをいただく。司書として働きたい人が世の中にはとても沢山いるのだよなあ、と改めて思う。しかし実際に図書館で働いている人のうち、どれだけそのことを認識しているのであろうか。図書館員のうち司書資格を持っている人は、働きたくても働けない人のことを思ってできる限りの仕事をしよう、などと考えるようにしてみてはどうだろう。図書館にいやいや飛ばされて本庁に戻りたい、と思っている人が何割いるのであろうなあ。不条理な状態である、と私は思う。
アレルギー性鼻炎と風邪に襲われている。ノラ(♀8歳)は真夜中に暴れる。
ややばたばたとした日々。童話賞の一次審査終了。利用者の多い季節。
大学生と大学の先生が来館。説明をしていたのだが、伏線を張った箇所のあとに続く話をふたつもしそこねていたことに気づく。朝飲んだ鼻炎の薬のせいかもしれないが、ぼけてきている可能性もある。司書になりたいと希望する学生からの質問を受けた。答えるのが大変難しい問題であるので、ざっと答えた後、このページをご覧ください、と言っておく。このホームページももう少しなんとかせねばなあ、と思う。
さしてなにごともない日々が続いている。23日にはグランパスが首位に立った。明日勝てばまだ首位であるが、ヴェルディはなかなか強い。
故山本夏彦の長男、山本伊吾の「夏彦の影法師」は手帳五十冊から抜いて編集した本。とてつもない量、質の作業。十八歳にしてすでに山本夏彦は山本夏彦であったのだな、と驚く。「年を歴た鰐の話」も買う。昭和二十二年の四刷を実は私は持っている。たいそう高かったが欲しくて買ったのだ。もったいないので、三ヶ月ほど眺めているだけで、本文を読まずにいた。読んでびっくり。落丁だったのである。表題作が途中で終わってしまっている。購入してから間が空いたので返本は無理であろうと思ったのと、落丁でも持っていたいのとで、今も我が家にある。全文を読めたのは「小説新潮」に載ったときだった。しかし残念ながら挿絵が異なっていた。ようやく読むことができた私であった。
13日のグランパス対ジュビロ磐田戦はなんとか引き分け。豊田スタジアムはピッチコンディションがいまひとつ。しかし不思議なのが客のマナー。やや前のめりになって見ていて、ゴールが決まらずため息をついて背もたれに戻ったら背中に変な感触。後ろを振り返ると、後ろに坐っていた中年の女のひとが私の背もたれに足を乗せていた。ハーフタイムにはその隣にいた夫らしきひとが、トイレにでも出かけた私の横の席の背もたれに足を。しかし彼らは靴を脱いでいたからまだまし。少し離れたところでは靴を履いた人が前の背もたれに足を。こういうことを気にする人間が損をする世の中なのはわかっているが、気になるのだからしかたがない。気にならない人が今後ますます増えてゆくことであろう。
大曽根で物騒な事件。二十年くらい行ったことのない町だが、19号線沿いのあんなところでひどい事件である。ガソリンを撒くのが流行ったら厭だな。亡くなった方たちのご冥福をお祈りします。
「図書館雑誌」9月号が届く。公共貸与権について最近熱心に書いている人がいる。図書館での図書の貸出について、国家が著作者に補償金を払うというシステムが確立している国が欧州にいくつもあるので、それに倣うべきであるとの主張。正しいと思う。コピー機会社の子息である彼は複写についても文化国家に倣うべきだ、と言うかな。と、意地の悪いことをふと考える。著作権に関して我が国は感覚的にとても遅れているのは間違いない。ただ、公貸権について、暫定的に国ではなく地方自治体に補償金を払うようにすべきだ、などと主張して蔵書数を減らしてしまうことになるのはまずい。この国の「しばらくの間」は数十年だったりするわけだし。
ばたばたの童話賞の仕事がひとまず終了。ほっとする。第一次審査の先生によりわけた応募作を配り終えて帰ってくると、応募作が郵送されてきている。「よろしくお願いします」などと書かれているが消印が締切をはるかに過ぎているし、お願いのされようがない。ここを読んでいらしたら来年の応募期間にまた出してくださいな。
映画を観てから少年王者舘の芝居を観にゆく。私の友達が幾人か旗揚にかかわっていた劇団。もう20年近くも前のこと。今では熱狂的なファンのいるカルトな存在。「それいゆ」は再演とのことだが初演を観ていない私。とても良くできた見事な芝居だった。12日まで大須の七ツ寺共同スタジオ、その後17日から21日まで東京の中野ザ・ポケット、27、28日は大阪の一心寺シアター倶楽部で公演。行けるひとは行ってみてはいかがでしょう。
どかどかと童話賞応募作品が集まってくる。作業をしている部屋は普段あまり使っていないのだが、ガラスから入る光の加減か、霊みたいなものが時折動く気がする。なにかいたりして。ま、悪いことをしなければ別になんということもないが。
グランパスは快勝。しかし酒井君が出ていないのが残念。前の日、日刊スポーツに写真が載っていたのにな。
就職活動中の学生さんから時折メールをいただく。日本の図書館における司書の地位についてのお話が多い。なかに、「私が変えてゆく」といった感じの力強いものもあり、日本も捨てたものではないな、と思う。しかし図書館に司書として就職することが簡単ではないのだから(だって司書を使ってないところがいっぱいなんだもん)問題はなかなか解決しない。。
300作以上応募作が届く童話賞。整理で頭がくらくらする。腱鞘炎がまた痛くなってきたりもする。この仕事場での司書は今が一年で一番ばたばたするときらしい。
7時45分頃、家が揺れた。地震ではないな、と思ったのはしばらく前にも爆発事故が近所であったからであった。やはり爆発事故。一生に二度も爆発で家が揺れるのは珍しいことかもしれない。
昨日、名古屋シネマテークで四本の映画を観たせいか一日目がしょぼしょぼ。童話賞応募原稿の整理で一日が過ぎてゆく。締切が近いせいか恐ろしい分量が届く。失格原稿もある。なぜか横書だったり、はるかに枚数を超えていたり。応募者は全国津々浦々。パリやタイやアメリカからも届いている。
30日のサッカーは厭な負け方。しかし私の好きな酒井友之選手はユースから所属していたジェフ市原戦だったためかとても元気で良いプレーをしていた。ずっとああいう動きができれば代表に選ばれることであろう。
アサヒネットの友達上田早夕里さんが第四回小松左京賞を受賞。電話で少し話をする。パスカル文学賞が終わってから八年間いろいろな賞への投稿を続けていらしたとのこと。知り合いがみんな偉くなってゆくなあ、とぼんやりしている私であるが、彼らは水の下で足を動かしているのであった。彼女の夫は筒井マニアで、早川ポケミスの函だけに平気で1万円出したりするひとである。受賞作は11月に出版されるとのことなので、「お会いしたときにサインをしてくださいね」と頼んでおいた私であった。
友達の森青花さんが新刊「さよなら」(角川書店、1500円)を贈ってくださった。きれいな装丁のかわいらしい本。デビュー作「BH85」について私は、「タイトルが良くないよね。同じくらいの年月が経った小説のなかからどれを閉架にしまうか、と悩んだとき、まっさきにしまいたくなるタイトルだものなあ」と失礼なことを言ったりしたのだけれど、今回の本のタイトルはシンプルで素敵。この小説を彼女が執筆なさっているとき私は、「そうだ、私がタイトルを考えてあげよう。どんなお話なの?」と尋ね、「95歳のおじいさんが冒険をする話なの」と聞き、「よおし、わかった。『おじいさんのぼうけん』がいいんじゃないかな」などとテキトーなことを言っていた。
先週清水良典氏が新刊「自分づくりの文章術」(ちくま新書)を贈ってくださった。十年ほど前、図書館で文化講座の講師をお願いしていらいのおつきあい。といってもお会いしたのはそのときだけなのですが。彼の書評はとてもスリリングで面白く、何を読もうかと悩んでいるときの指針となるのでした。
童話賞への応募、続々。横書きのひとがいたり、枚数規定をはるかにオーヴァーしているひとがいたり、孫の絵日記を送ってきたりするひとがいたり、となかなかわくわくする。
23日の対FC東京戦は見事な逆転勝ち。グランパスは2点差をはねかえしたことが過去にあっただろうか。27日のアントラーズ戦では私の好きな酒井友之選手が活躍。しかし厭な負け方をしてしまった。ナビスコカップはこれで敗退。明後日のジェフ戦はどうなるだろう。と、サッカーきちがいと化している私であった。
デ・パルマの「ファム・ファタール」を観る。悪女ものは好きである。私も悪女に翻弄されてみたかったなあ、などとふと思う。「殺しのドレス」でぞくぞくして以来、デ・パルマの作品はほぼ観ているが、これはなかなか私の好みであった。好き嫌いが別れる映画だとは思う。
一昨日は仕事場の入り口にカマキリのおおきなのが、昨日は謎の虫が建物のわきに。調べてみるとマイマイカブリの幼虫。青光りのする少し気味の悪い虫であった。成虫は子供の頃見た記憶があるが、幼虫ははじめて。田園地帯なのでいろいろな生き物にめぐまれている。帰りにはアキアカネが飛んでいる。
日本図書館協会のメールマガジンを読んでいたら、TBSラジオのアクセスという番組のなかにバトルトークというコーナーがあって、そこで図書館の席貸しの問題についての意見が交わされたとのこと。
これを読んで私はいろいろと考え込んでしまった。図書館でなにができるかを知ってる人は少ないのだな。受験勉強をする若者は国の宝だというのは本当だろうか。受験地獄批判というのはどこへいったのか。教養主義はほぼ絶滅したのだろうか。利用する人が少ない施設が無くても良いのならば文化施設は皆いらないな。美術館や博物館はもっといらない。国の文化水準は上がらないだろうな。その論だと福祉施設はいるのかな。インターネットで全ての事柄が調べられるかのように思っているひとはきっとコンピュータによって本が無くなるなんて話やコンピュータの出現で労働が少なくなったり紙の使用が減ったりって話を真に受けたひとなのだろうな。多数は少数に勝る、と思っているひとの多さはなんなのだろう。戦後58年かかって多数決が浸透した国。税金でつくられた施設は、一生そこを使わない人をも含めた多数意見に左右されるものなのか。皆がそこで小便をしたい、と言ったら面白かろうな、などとつまらぬことを思ったり。
「図書館」と名のつく建物は沢山できたのだけれど、中身はばらばら。専任の司書がいず、テキトーに選書して、参考図書があまりなく、調べものにやってきたひとにまともに受け答えができないような館であれば、受験勉強や資格試験の勉強のために持ち込んだ資料のみを使って席を占有する人がいくら来ても困りはしない。館内でしか使えないような資料(たとえば古くからの新聞、幾年にもわたる統計類など)を利用する一般の人が多い場合、席のみを長時間使う利用者だらけだったらどこを使うのか。まじめにテーマを選んで調べ学習にやってきた小中学生(かなり難しいことをテーマにしてくる子供たちも多いのである)に応対した職員が開架閉架から提供した十冊以上の資料を閲覧するとしたら場所が必要だ。静かに受験勉強をするとてもまじめな学生ばかりであったとしても席が埋まっちゃっていたとき、図書館員は困るのである。図書館の資料を使いに来たひとも困るのである。棲み分けなどと簡単に言うが、なまやさしいことではない。社会人席、閲覧専用席が空いているならば使って良いではないか、という論理にまともに対していたら、そこを使いたいひとが来たときに、空いていたからと使う人ですべての席が埋まっていた場合、沢山居るひとのうち誰に席を譲ってもらうのか、全員か、善意の幾人かか。「あなたは早くからいたからそこを空けてください」と言う為には席を使うひとをすべて管理する必要がある。そのための労力があるような図書館は多くはない。それどころか司書が少ない、正職員が少ない図書館が沢山あるのだ。空いているからどうぞ使ってください。今日は閲覧利用者がきっときませんから、と言える人はエスパーだ。使うひとが来たら私は席をあける、と言うひとはいるだろう。図書館の資料を使いたいけど、席が埋まっててるから帰ろうと考える潜在的な利用者のことについては考えがおよんでいない。図書館を使うひとは気の弱い人が多い。多分それは少数者であることを自覚しているからではなかろうか。棲み分けができている館は運がいいか、職員が努力をしているか、歴史があるのである。昨年度まで私が勤務していた館は紆余曲折を経て、棲み分けができていた。ほんの少しのことで棲み分け不能となる。持ち込み学習利用者が膨大な数となった場合、制御ができなくなるのだ。あるいは整理にとてつもない人を割かねばならなくなる。さして多くない席数なのに持ち込み学習を認めていて、棲み分けもしていない館は調べものに来た人に対応できていないか、とても来る人が少ないかのどちらかであろう。図書館の使い方を知らない人が多いのはしかし、図書館の責任ではある。調べものに対応できない図書館の多さは国の問題でもあり、民の問題でもある。だけど持ち込み学習ってどこでもできるじゃん。これが勉強だから良いことのように感じるだけなのだ、と私は思う。静かに瞑想にふけるから閲覧席を使いたいというが多いという話であれば、ほかですれば良いのではないか、という結論にならないだろうか。夏涼しく、冬温かい場所を学習館として作れば良いのかもしれないけれど、それならば学校がある。図書館という場所でしかできないことがあるのだ、ということを図書館が態度で主張しなければならないのではあるまいか。それには我が国の公共図書館の状態が貧弱すぎるのが問題なのだが。多くの人はそれで構わないと思ってもいるのだろう。民主主義国家は大変である。
主力選手を欠いたナイジェリアと海外移籍組も召集した日本代表のサッカー。勝ててなによりであった。
脳内出血で死んだ友人の命日。もう五年になる。31歳。よい人であった。こんな句を詠んでいた。
酒をつげ来世を虎に決めるかな
砂粒をひとつ焦がして花火落つ
韮畑茄子畑出て葱畑
天道虫降る林道を父と行く
真実を語る女や保夜を食う
ネルシーニョ監督は大胆だ。しかし私としては酒井と藤本をスタメンからはずしてほしくないと思うのであった。酒井は才能があるのに目立たないのだよなあ。あの準優勝をしたワールドユースでの活躍で彼のファンになった私であるが、欲の無さというか淡白な感じが実に歯がゆい。
以前は8月になると戦争関連のテレビ番組ばかり放送していてうんざりしたものだったが、気がつけばそうした番組は絶滅寸前になっている。昨晩のNHK特集は良かった。日本が委任統治していたサイパン島(国際連盟が認めていた)をアメリカが攻めてきたカラー映像にはぞっとした。民間人が住んでいるのである。ばたばた死ぬ人。数十年前からアメリカは同じようなことをしてきたのである。美しい首里、那覇を焼き払う米軍の映像。人が死ぬ映像。日本がいいことをしたわけはない。しかし、民間人でもなんでもかんでも虐殺して良いということは絶対ない。今日の核の番組もついつい観てしまった。多くのアメリカ人は原子爆弾を広島に落とさなければあの戦争は終わらず、内戦となり、アメリカ人が沢山死んだはずである、と今でも思い込んでいるのだな。
大停電。お盆で休みの企業が多くて幸いだったな、とニュースを観てすぐに思ったが、アメリカにはお盆はなかったのであった。しかし150年前にはなかったはずだが、今ではないと生きていけない電気っていったいなんなのだろうなあ、とふと思う。
利用者多し。しかし、質問がそれほどあるわけでもなく、平穏な日々。童話賞への応募は続々。職業欄に「求職中」とか「難病療養中」とあったりする。「無職」だときまりわるいのであろう。来年から職業欄はなくそうかと思う。
ネルシーニョグランパスは1対5でスタート。どうなってゆくことであろうか。
企画展には沢山の来館者。しかし生原稿ってあまり真剣に見る人がいないのであった。古本好き、生原稿好きな私としては不思議な気がするけれど、古本好きの人がそもそも世の中に多くはないものなあ。
油蝉の季節から熊蝉の季節となったのだが、急に寒くなってきた。お米は大丈夫だろうか。
「茄子 アンダルシアの夏」は黒田硫黄の原作に忠実。しかしアニメーションとしてはどうだったのだろうか。自転車レースの絵は面白かったのではあるが。「ユリイカ」今月号は黒田硫黄の特集。ここにも書いている四方田犬彦の「ハイスクール1968」第二回(「新潮」)。35年経たないと書けなかったのだな、と思うとその時代のことはわからなくとも、ずきずきする。ハイティーンの男の話ってなんだか困る。
「図書館雑誌」が届く。図書館を高級シティホテルのような雰囲気に云々と書かれている文章が気になる。以前、名古屋のとある高級ホテルのロビーにホームレスの方々やノミ屋さん達がたむろしていたことがある。入り口やインテリアを変えて今はそうした人たちがいなくなったが、雰囲気をなんとかするだけではなんともならないことはある、と私は考える。多くの人間を思い通りに動かすのは簡単ではない、と私は思う。雰囲気なんてある時から少しずつ違ってゆくものなのだし。システムを変えないと仕事がしづらいから、法律を片っ端から変えてる国に住んでいるになあ。学生はやがて卒業し、注意してまわった人間はいずれいなくなる。そのときにどうなるかを見越してシステムは考えられるべきであろう。良い雰囲気がずっと保たれるような世になれば言うことはないが。
ベルデニックはどうして解任されるのであろうか。選手やフロントとどのように揉めたのかがとても気になる。ウェズレイと仲が良くないことは彼のコメントで気づいていたが、ほかの選手とはどうだったのだろう。基礎的なところが固まり、これからかな、と思っていたのに残念。とても堅い守りからががが、と攻めてゆくことがあったり、いきなり攻めていったり、点が入らないとディフェンダーをがんがん上げていったり、前線へのつなぎがファンタジックだったり、と私は彼の方法をかなり好きだったのでしたが。ブラジル人監督ネルシーニョと今のグランパスは果たして合うのだろうか。ま、しかし、基盤はしっかりしてきたように思う。これからも観てゆく私である。
アーティストにはいろいろな人がいる。児童図書関連の人を私はおっかないのではなかろうか、とずっと思い込んでいた。多分それは筒井康隆さんのエッセイの影響。今の仕事場で二人の児童文学者と電話で話し、先日はサイン会で絵本画家の人と接して、温厚な人もいるのであるな、と感じた私。しかしとてつもなくエキセントリックな人がいたりはしないだろうか。それはそれで見てみたい気がするので、私は実のところ少しがっかりしているのかもしれない。
我が家の回りは夏になると蝉だらけ。洗濯機の回る音さえ聞こえぬほどの蝉の声。猫が暴れ、蝉が大声で鳴く朝。平和である。
ペドロ・アルモドヴァルの「トーク・トゥ・ハー」は良かった。未見の人は観たほうが良いと思います。でも、アルモドヴァルは毒々しいほど派手で馬鹿馬鹿しい作品はもう撮らないのかなあ。
ぼおっとしているうちに7月が終わってしまった。
先日のレファレンス探検隊二次会で話題になった(と言ってもTさんと私の中年男二人の間ではじまった話であったが)岡田史子の「オデッセイ1966~2003」(飛鳥新社)が先月発売されていたことを知ってびっくり。萩尾望都や山岸涼子に影響を与えた漫画家なのでした。私は高校生のとき、雑誌「COM」を古本屋で集めていて知ったのだったか、漫画評論誌「ぱふ」で知ったのだったか。67年デビューの漫画家なので、リアルタイムでは知りませんでした。この本、解説を音楽家の青島広志さんが書いています。NHKFMの夕方の番組で童謡の解説などをしていた「ブルーアイランド青島」さんが岡田史子とこんな縁があったとは全然知りませんでした。うらやましい中学生時代を送っていたのだなあ。「新潮」8月号、四方田犬彦の「ハイスクール1968」にも岡田史子について触れた箇所があってなんだかシンクロニシティを感じたのでした。四方田さんはNTT出版から出た二冊の岡田史子の本に関わっているわけだし、1968年の話ならばその名が出てきてもなんの不思議もないのだが。
こないだの日曜日はいろいろな企画があってとってもばたばた。腰の調子がいまひとつなので立ち通しの仕事はなかなかきつかった。
私の勤務先の企画展、なかなか良いのでお時間のある方は是非お越しください。と、この展示に私は関わっていないので宣伝するのである。
一昨日はレファレンス探検隊であった。気がついたけれど、なんとなく言わずにいたことがひとつ。出された問題のうち、図書での回答が困難なのが一題あったのだけれど、それは以前であれば該当企業に電話で確認して答えたであろうと思われ、しかもそれが一番迅速で間違いがない方法なのだ。今ではホームページですぐに見ることができるのであるから、この場合はホームページで見て、利用者に示して答えるのが正解。さらに図書で探す必要はない、と私には思われた。基本的には複数の図書資料の提供をすべきであるが、場合によってはそうしなくてもよいのだ、ということを指摘すべきであったな、とあとから思った私であった。みなさん、とても真面目なので、かえって袋小路にはまりこむことがあるやもしれない。衝撃を受けたのが70年の万博についてのレファレンス問題に絡んでのこと。万博を見た参加者、というか、70年以前の生まれの人間がそのなかに三人しかいなかったってこと。なんとなく私のなかではいつまでも日本人の共通の話題であろうなと思っていたのであった。もう33年も前なんだな。
二次会ではそのショックもあってやや飲みすぎ、降りる駅を間違えたりしたが、なんとか帰った。 そこで帰り際に尋ねられたこと。カッティングの上手な日本人(外国人でも良かったんだっけ?→質問をしたひと)ギタリストについて。酔っていてひとりも思い浮かばなかった私はアサヒネットで数年間「音種」という会議室を運営していたことがある。帰宅後考えたのだけれど、あんまり思いつかない。ビブラストーン、メンズ5にいた岡田陽助、パンタ&ハル、パラシュートにいた今剛。ほかに誰がいるかなあ。お心当たりの方はご一報ください。
暑い日々がはじまりました。夏休みもそろそろ。
朝、自動車で通勤途上、動物の死骸を目にする。犬、猫、牛蛙、ときにイタチ、野うさぎ、去年は狸を見たが、今日見たのはそのどれでもない。最初、犬かと思ったが、通り過ぎたあとで、キツネではないか、との疑念が頭を擡げてくる。キツネと関わりのある文学者の記念館に勤めているせいかもしれない、きっと気のせいであろう、と思いつつも、どうも気になり、職場に着いてから隣町の郷土資料館に電話をし、「犬かも知れないけれど」と断った上でキツネらしき死骸があった旨を告げる。確認しに行ってもらったらやはりキツネ。我が町では戦後発見事例がないのであった。私の勤務先の市では目撃事例があり、近隣の市町では生きたキツネを写真に撮ったりビデオに撮ったりもしているのだが、我が家の近くにいるとわかり少し驚いた私。せっかくなので昼はきつねうどんを食べた。
童話賞応募作は続々とやってくる。不思議なのもいっぱい。世の中には様々なひとがいるなあ、とうれしくなる。
地球を支えている象の足をのこぎりで切りはじめている人がいるのに、気づいている人が少ないってな感じで日が過ぎていってはいないだろうか、などと、山上たつひこの「地球防衛軍」という変な漫画をふと思い出したりする昨今。
ダイソーシュッパンというところから昨日、文学者の写真の著作権についての問い合わせ。「大創出版」という会社があって、たしかダイソーという会社と関係があるのではなかろうか、と話し、念のため尋ねてもらうとやはりそう。100円で200ページほどの文庫本を出すのだそうである。文学者の作品を多くの人に知ってもらうのはうれしいことだけれど、100円か、となんとなく複雑な気分になる。
論文を収集しているのだが、なかには不思議なものがある。昭和初期に教師として通っていた学校までの交通手段についての論文はどの汽車に乗っていたのかを想像して書いているのだが、資料としてあげられているのが明治大正の時刻表。果たしてこの論文、意味はあるのであろうか。
童話賞は続々と集まってきている。今日届いたのには原稿を色画用紙ではさんである裏表紙にあたる位置にプリクラの写真が貼ってあった。確かに美人ではあるのだけれど、童話賞に顔は無関係である。いろんなひとがいて面白い。
「え、こんなところに一行の記述が。あ、ここにも一行の記述が」と大発見関連で文学者の日記に記載があるのを臨時職員が差出人の関係する団体の名を見つけてくれたのであった。しかしその団体の会誌は今のところ見つかっていないし、構成メンバーもいつからいつまで存在したのかもわからないのであった。
童話賞の応募作品がぼちぼちと集まってきている。原稿用紙に書いたのをコピーしたあと、余白をちょんぎっちゃったついでに文字まで切っちゃったのとか、枚数規定の倍ほどの量のとか、修正液でいっぱい消してあるの、とか、ワープロ原稿なのに文字を無理矢理加筆したのなどがある。一般の部は七枚。書き直さない主義の人もいるみたいである。
腱鞘炎、治らず。思えば十年以上痛かったものなあ。
伝聞というのは恐ろしいものだな、としみじみ思ったのがGさんの調べてくださったことがら。先日から書いている大発見とはとある文学者に宛てての葉書が古書の間から見つかった事件。差出人と文学者との関係がまったくわかっていず、調べていたのであった。この差出人の親戚の方にお尋ねしたところ、横浜正金銀行に勤めていたけれど、じきに退職をし、しばらく仕事をしていなかった時期があるのであるいはその頃、文学をしていたのではないかとのお話。ずっと銀行に勤めていたとの説もあったのだけれど、直接交際があったわけではないとは言え三親等の方のお話のほうが多分正しいと判断。その線でキャプションを書いたのだけれど、Gさんを経由して調べてもらった結果、横浜正金銀行が東京銀行になってからもまだ勤務していらっしゃったと判明。朝、キャプションを変更。それにしてもGさんの調査能力はものすごい。
新聞の影響は大したもので差出人のお兄さんのお孫さんが来館。よくここまで調べることができましたね、と感心されることしきり。市内在住のKさんからの聴き取りとGさんのおかげ。けれどもまだ文学者と差出人との関係ははっきりせぬまま。七十年以上も前のことを文献資料がない状態で調べるのは恐らくかなり難しいと思われる。ここまでしかわからない可能性もかなりあるなあ、とやや諦め気味の私。
早いものでもう6月。四十を過ぎてから時の流れをとても早く感じる。
みつたさんにこのページの色などを直していただいた。お会いしたことのない謎の親切なひと。お会いしたことがない、と言えば、今回の大発見に関わる調べもので調べているひとが慶應義塾に関わりがある、と判る。アサヒネットには慶應義塾の歴史にとても詳しい方がいらっしゃるな、と思い出し、調査をお願いした。Gさん。電脳筒井線の頃から十年以上通信でのやりとりはしているのだが、お会いしたことがない。メールで調査をご依頼してから24時間経っていないうちに、かなりのことがわかり、仕事場の学芸員に話したところ、「一体どんなお知り合いなんですか。これだけのことがすぐにわかるなんて」と仰天していた。世の中にはものすごいひとがいるなあ、と改めて今頃思ったりした私。そういえば私が筒井康隆さんのファンクラブ会議室のモデレーターをしていた際、「筒井さんの臨終の言葉トトカルチョ」(略して【臨トト】)を思いつき実行。筒井さんは臨終に際してなんとおっしゃるだろうかをみんなで考えようというとんでもない企画。怒られたらどうしようか、と真夏に涼しい思いをしながらはじめたのであったが、真っ先に反応してくださったのがGさん。お答えは「今度は、ほんとうの断筆じゃ」。
大発見を記者発表したところ、早速取材に来てくださり、三つの新聞の地方版に大きく載せてもらった。突然、展示することも決まり、少しばたばた。
謎の大発見関連の調べものが多少進んでいる。いろいろな推理をすると楽しい。調べものが好きであることは図書館員としての必須条件かもしれないな、などとふと思ったり。
団体に属するのを好かない私であるが図書館関連団体に入ろう、と思い立つ。とある著作権関連の論文を読んでいて、あまりにも現状を把握していないぞ、との疑問が生じ、しかしほったらかしておけば良いか、と思っていながら、どうも私の中ですっきりしないので反論を書きたくなっている。それを発表する(載せてくれるかどうかは知らないし、そもそもまだ書いてもいないけれども)には団体の会員にならねばならないのであった。一つだけ入るのも癪なので二つ入ろうかと思う。
風邪をひく。
イーヴォ、イーヴォ、と良い試合を見にいったのであった。って、ファーストステージのホームゲームを今のところ全部見ているのだが。ベルデニック監督はヴァスティッチを退団させたくなかったようである。パスの精度やポストプレーに不安があるのは確かだが、なんとなく日本的なところのある雰囲気の良い選手。シュートが決まった瞬間、鳥肌がぞわぞわと立った。
中国のひとから、その後連絡がない。お心当たりの方はご一報を。
鶴舞中央図書館のTさんからメールをいただく。なかなかむずかしい内容のご質問。Tさんとは一昨年の著作権関連のワーキンググループで知り合ったのでした。
中小公共図書館関連等のご質問がございましたら、お気軽にメールでどうぞ。
大発見があったりしている。いろいろな古本屋さんや図書館に尋ねてみているのですが、わからないことだらけで、発表までにはもう少し時間がかかることであろう。
坪内祐三の「一九七二」を読んでいる。坪内祐三の疑り深さがいいな、と思う。
数日前の新聞に去年私がレファレンス研修の講師をした際の受講者の名前を発見。とても熱心に、小さな図書館で充実したレファレンスを行ってゆくにはどんなことをしてゆけばよいかを考えていた人。しかし、その人は犯罪の容疑者として逮捕された。ヒトは複雑なものです。
いよいよコンピュータが不調。マウスを本体に繋いだままだと起動しなくなっちゃう。起動したあとマウスを繋いでポインタが動くことが稀。かわいがっている初代iMac。マウスを替えるとなんとかなるのかなあ。と、悩む昨今の私であった。
そろそろ何かしないと読者のみなさまから見はなされると思い、この日記をはじめることにした。
タイトルは俳号「いぬふぐり」にちなみ「いぬふぐり庵日乗」とすることに決定。
さて、最近の私が何をしているかというと、とある文学関係の博物館のようなところの仕事に就いているのである。そこでは創作童話賞の募集、関連資料の整理などをしている。
中国の人から質問状のように読めるメールをいただいたのだが、文字コードのなにかのせいか、ところどころしかわからず。お心当たりの方はまた連絡してください。
仕事だけでなく、あれこれとテキトーなことをぼちぼちと書いてゆこうと思います。
昨日、なごやレファレンス探検隊に出かけた。熱心な若手図書館員を見ているだけで元気がでてくる。懇親会では無人島に持ってゆく一冊の本、一枚のレコードが話題になった。私はその場の 勢いで「広辞苑を持ってゆくかな」などと言ったが、本当は違う本を持ってゆくことであろう。ローザルクセンブルグの「ぷりぷり」かセカンドを持ってゆくという珍しい人に会った。そういえば、私のつとめていた図書館で「ぷりぷり」を貸し出していたな、などと話しはじめたら、多くの人がその場を去る。少し地味な話題であったのかもしれない。ローザルクセンブルグの故どんとのファンという人には会ったことがあり、友達が彼のソロになってからの作品(「波」は名曲だと思う)をコピーしていたりするのではあるが、ギタリストの玉城宏志のファンに会ったのははじめて。ローザルクセンブルグを聴いた時、気になったのはどんとの声と強烈な歌詞。ジャケットは無意味に派手だし、これは頻繁に聴くアルバムじゃないな、とそれほど聴かなかったのだった。歌詞がどうも好きになれなかったし。玉城さんのカッティングギターが素敵、と言われても全然思いだせなかった私。そこで今日十五年ぶりくらいで「ぷりぷり」を聴く。なるほど素敵。
児童書の書誌ってすごい。初刷には函がついていて、どこかの刷りで函がなくなり、その後カヴァーがついたり、カヴァーが変わったりしてるのに、どこにも版が変わった記述がなかったりする。こないださわっていた本はタイトルが英語から日本語になり、ISBNコードも変わっているのに奥付を見ると同じ本の刷り違いってことになってる。おおおい。ある作家の著作を網羅的に集めてゆく場合、こういうのはとても困ると思う。
とりあえず今日はこの辺で。ご質問、ご感想などがございましたら、お気軽にメールしてください。iMac不調のため返事が遅くなるやも知れませんが。