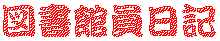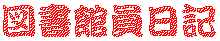
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 9月30日(火)
気がつけば明日から10月である。としょかんだよりをつくらねばならない。と、慌ててつくる。
朝はブックポストに本が沢山。風邪気味な私はなんだかくたびれたのであった。
- 9月27日(土)
第4土曜日である。利用者多し。だが、夏休みのようにレファレンスが多くないので、大したことはない。登録者多し。さしたる事件もなし。
- 9月26日(金)
館内整理日。議題がそれほどなく、会議は1時間ほどで終わる。ぼろぼろになり、除籍した本を清掃事務所に運ぶ。普段、時間がなくてできない箇所等の書架整理をする。
- 9月25日(木)
このごろ、本にもたれる子供が多い、と思っていたら、大の大人が床に座り、本の一杯入った棚に持たれて雑誌を読んでいたのをみつけた。世も末であるな、と思う。マナー以前の問題のような気もするが、実害もあるのである。棚の奥に当たっている表紙の部分が曲がってしまうのだ。当然注意したのであった。
受付のローテーションを組む。
かれこれ一週間ほど風邪気味の私である。
- 9月24日(水)
新刊マーク(電算の書誌データ)が送られて来ないし、見計らい本も来ない。どうなっておるんじゃぁ、と電話で尋ねる。見計らい本は夕方に来たが、マークは謎のまま。今週の予定が狂うかもしれない。ううむ。
大学生の宿題、ぎりぎりになってからありそうもない資料をたずねてやってくる学生が年々増えている。テーマを自分で決めるといった調べものでも、調べられそうもないことを考えてやってきたりする。それと似たようなので、このような調べものならば、資料がないこともないが、などと、どうして公共図書館が大学生の宿題にそこまで教えてやらねばならないのか、と思いつつも資料を出したりするのであった。
今日もまた登録者多し。
- 9月23日(火)
他市町村からの登録者が市内の登録者よりも多かった。約30人。遠い町から来ている人もいる。なぜだ。
雑誌記事の検索(雑誌記事索引CD-ROM)、新聞記事の検索(オンラインデータベース)の請求があると、それだけで一時間くらい取られてしまう。役所の幹部に言うと、きっと、「ならばそのサービスをやめればいい」と言うであろうなぁ。新しい情報を調べるために、雑誌、新聞の記事検索は図書館では必須なのであるが、していない館の方が多いという恐ろしい現状がなんとかならないといけないのだが。しかし、検索ツールはあっても、元の雑誌や新聞の地方版、本社版がなかったりするわけで、これを県の図書館や大学図書館へ複写依頼をするとなると、大変な仕事の量になってしまうわけで、記事のありかだけを教えて、あとは県の図書館あたりに調べに行ってください、と答えることになるのである。雑誌が電子媒体になる時代がくると、図書館の仕事は増えることになろうなぁ。それとも利用者が自宅から調べるようになるのだろうか。調べきれない分を図書館でなんとかすることになるのだとすれば、司書の力量が問われることになるわけだが、そうした危機感を持っている司書がどれほどいるのであろうか、などと考えはじめるときりがないのであった。
- 9月21日(日)
さすがに日曜日である。貸出4016冊、返却3651冊。貸出が350冊も多い。ということは、利用者が増えているのである。登録者も20人を越えている。
- 9月20日(土)
長期延滞利用者に電話をかける。返却期限から一年以上過ぎている人ばかりなのであるが、さすがにそういう人たちであるから、やりとりが狂っていて面白い。「本がない場合にはどうすればいいんですか」「なくされたのであれば、弁償していただきますが、本はありませんか」「おもちゃ箱を探せば出てくると思います」と、主婦。あるなら早く返しにきなさい。もちろん督促は今回がはじめてであるはずはなく、幾度も葉書を送り、電話をかけているのである。ひどい人になると、今頃になって、借りた覚えがない、などと言い出したりもする。世の中には悪い人も沢山いるのである。
朝、昼と比較的空いていたのだが、夕方からばたばたと混む。急に混むと体力がついてゆかない昨今である。
- 9月19日(金)
カウンターのローテーションを組む。
今日もまた登録者多し。来年どうなっちゃうんだろうか、と心配になってくる。
- 9月18日(木)
このところ郷土資料の利用が多い。ほとんどが貴重書にあたるため、閉架にしまってあるのだが、閉架に資料があることが知られてきたのであろう。
父親が小学生の子供さんと来館。郷土関係の宿題なのだが、児童向けの資料など皆無。親が資料を見て、子供に説明せねばできない宿題を出す教師の感覚がよくわからない。このごろ、こうした宿題が時折ある。宿題を出す前に自分で一度は調べてみたのであろうか。教師はそれほど気楽な商売ではないはずだが。
- 9月17日(水)
思ったほどブックポストへの返却はなかった。が、利用者が多い。夏休みが終わったというのに登録者がずっと多いのは何故だ。
新刊図書の見計らい作業。
- 9月15日(月)
登録者多し。夏休みからずっと登録者が多い。予約、リクエストも随分増えている。どうなってゆくことであろうか。
飴をなめている子供、ガムを噛んでいる子供、缶ジュースを持ち込んでいる中学生がいるので注意する。飴、ガムの幼児は口の中に手を突っ込み、その手で本を触ったりするのである。本はべたべたになる。ま、何も食べてなくても口に手を入れた手で本を触っていたり、鼻をほじった手で本を触っていたりもするのであるが。などと書くと図書館の絵本はまるで汚いようであるが、確かにあまりきれいではない。
- 9月12日(金)
来週のカウンターローテーションを組む。夏休みが終わって、受付に出る人数が減ったので、昼食を二交代で取れるようになった。組むのが楽。
比較的利用者の少ない日だなぁ、と思っていたのだが、夕方からかなり混む。登録者が15名。登録者が増えるということは、それに伴うほかの仕事が全部増えるということである。うれしい悲鳴ではあるのだが。
- 9月11日(木)
夏休みが終わったというのに学生の調べものが結構あった。
市報に載せる図書を選ぶ。
冊子目録を一種類印刷屋さんに頼んで作ることになっているのだが、フロッピーで出稿するとして、テキストデータ出力がどのようにできるのかがよくわからないので電算会社に尋ねる。項目ごとのカンマ切りのプログラムを作ってもらうか、通信ソフトを使ってのログ保存からの加工をすればなんとかなることがわかる。印刷会社に、どちらの形がいいかを尋ねるとどちらでも構わないとのこと。目録作成自体は私の担当ではないのだが、電算担当ということで、なぜだか仕事が増える昨今である。
新刊書の見計らい。
洋書絵本の見計らいに毎年来る外国の人が今年も来館。事前に連絡がなかったので児童書担当がばたばたする。
しかし最近、慌ただしい時には電話に出ることさえ、時間が惜しい、というか、話している時間がない。細かな内容の事柄についてはFAXでの連絡に切り替えてもらうようにしている。メールでやりとりができるようになれば、その方がいいだろう。時間の空きがあるときに返事をすればよい方法に慣れると時間を限定される電話が鬱陶しくなるのであった。余裕があれば、なんということはないのだろうが。
- 9月7日(日)
さすがに日曜日である。貸出冊数4651冊、返却冊数4756冊。返却が少しだが増えている。棚がきつくなってくる。が、調べものは少し減った。
- 9月6日(土)
土曜日だというのにそれほど混まないなぁ、などと1時くらいまで呑気にしていたのが間違いであった。その後、ずっとばたばた。かえり際までばたばたであった。
新刊書の発注業務も行う。
- 9月4日(木)
ローテーション表を組み、新刊案内用の図書を選び、図書入力をした。
ようやく普通の平日並になってきたなぁ、と思っていたら、大学生のレファレンスにてんやわんや。大学の図書館が休みとかで、J-BISCや雑誌記事索引や学術雑誌総合目録といったCD-ROMを駆使して、書誌情報を提供する。J-BISC以外は利用者に開放していない、というかLANにしていないので、事務室に入ってもらってあれこれせねばならないのであるが、いずれにしても使い方の説明をするよりも、情報を出してしまった方が早いわけで、しかし、こうした利用者がすごく増えたらどうなるのであろうなぁ。職員が増えなければどうにもならないのであるが。サービスをどこまでにするか、などと役所の管理者側によく言われるが、資料提供、という一点においてはすべて繋がっている仕事なのである。見つけやすいか見つけにくいか、点数が多いか少ないか、相互複写、相互借受になるか、自館資料複写、自館資料貸出になるかの差だけなのだけれども、他館から借りてまで貸す必要はない、とか他館に複写の依頼をしなくてもいい、などといった話になったりする。その他館がめちゃめちゃ遠い場所にあったりした場合には、利用者がそこまで行くしかなくなるわけだし、市外の利用を認めていない公立図書館や、在学生以外の利用を認めていない大学図書館だってあるわけだが、こういった事をしっかりと理解している、あるいは説明して理解してくれる自治体の管理者が実は多くないのである。また、これは自治体の管理者だけでなく、他の町では図書館のなかでも理解していない職員がいたりもするのだ。別に図書館で働きたくて働いているわけではなく、役所から飛ばされて嫌々働いている、などという市町村立図書館が結構あったりするのであった。そうしたことがどれだけ図書館の発展というか、国民の文化にとって有害なことであるか。恐ろしい話だと思う私である。これについてはいずれ、「一図書館員から見た日本」に書く予定でいる(思えば長らく書いていないのでした。_●_)
- 9月3日(水)
ようやく普通の平日並になったかなぁ、と思っていたら、帰り際、ひどくばたばたする。登録がどかどか、複写がどわどわ、貸出窓口に人が並ぶといった状態。
夏休みが終わったせいか、未就学児童を連れた親が目立つ。「建物のなかで口笛を吹いてはいけないよ」と注意をしてもきかない子供。下段の絵本がずらっと並んでいる上に乗っかって、高い位置の絵本を見ようとする子供と近くにいて注意しない母親。絵本コーナーでは出しっぱなしにした絵本を踏んづけて走り回る子供。すぐそばに両親。こうした呆れ果てた人たちを注意するととても体力を消耗する。それにしても10年、15年先、この国はどういう国になるのかな、と考えてしまう。貸出返却業務というのはある程度の信頼関係がないとできないのだが、今よりもさらに悪い状況になっているとすると、なかなか大変なことになるであろうなぁ、とも思う。
- 9月2日(火)
9月である。夏休みが終わってほっとし、カウンターローテーションも図書に2人、視聴覚に1人にして組んである。利用者は減る予定であった。が、しかし、貸出冊数2142冊、返却冊数3465冊。予備的にローテーションに入れてあった職員は出ずっぱり、返却図書は帰りまでに片づかなかったのであった。ずっとこうではあるまいなぁ。
冷房が不調。暑い日であった。
- 8月29日(金)
最後の追い込みのせいか、小学生が閲覧席でさんすうの宿題をしていたりする。せっかく勉強しにきてもらったのに申し訳ないんだけれど、この席は百科事典とか図鑑などの図書館の本を使った調べものの為の席だから、もし、調べものの宿題があれば使ってもらっても構わないんだけれど、家でもできる宿題だったら、ここは使わないでくださいね。あなたたちのクラスの子が全部来ちゃうとそれだけでこの席はすぐいっぱいになっちゃうでしょ、と、説明して納得してもらう。きっとお母さんか誰かに、「図書館に行って勉強してきなさい」とでも言われたのであろうなぁ。
登録者、紛失届の再発行、今日も多し。
先月購入したばかりの写真の多い焼き物の本のページがくっついて開けなくなっているのを発見。どうしようもない状態である。風呂で読んだのであろうか、などと話していたのだが、これは水ではありませんよ、と女子職員が言うので、以前にあったような欲情した変態のしわざ(図書館員日記11月26日をご参照ください)ではなかろうな、と恐くなる。焼き物フェチというのがいるのだろうか。ま、精液でくっついたと決まったわけでもないが、変態には困ったものである。
- 8月28日(木)
登録者の多い一日であった。23人。紛失届の再発行も20件ほど。しかし夏休みもそろそろ終わりである。
それにしても親が子供の宿題の手伝いに来るというケースが多い。毎年のことではあるが。小学生ならばともかく、中学生、高校生の子供に頼まれて本を借りに来たり、コピーをしにくる親というのは一体なんだろうか。本も書名がわかっていてくるわけではなく、「○○についての本」という尋ね方で、ご本人が探しているのかと思って、資料を出すと、「これでは息子には難しすぎる」などと言う。ひどいのになるといくつかあるテーマの中のどれかについてのレポートを書く宿題をプリントのまま持ってきて、母親が、「この中のどれでもいいんですけれど」などと言う。どれを選ぶかも宿題のうちではないのか。良い子が育つことであろう。
- 8月27日(水)
宿題の追い込みの子、多し。同じ参考資料を使わないとできない調べものだったりすると大変。空くまで待ってもらうか、閉架にある少し古い資料を見てもらわないといけない。閲覧席はずっと満席だった。
来月号の「としょかんだより」を作る。
図書の見計らいをする。ばたばたであった。
- 8月26日(火)
朝、ブックポストへの返却本が約1000冊。出勤している受付要員8人。全然片づかないまま一日が終わった。
登録者、再発行の人、貸出券をなくした人、相変わらず多し。夏休みの宿題の追い込みの中高生が多くて、百科事典の奪い合いのような状況。
- 8月24日(日)
とにかく入館者が多かった。約2000人。夏休みの宿題の調べものの学生が沢山。
夏休みには、久々に来たという人が多い。貸出券の更新業務をしていないので、三年前、五年前に作った貸出券をそのまま使える。貸出券を以前に作ったのになくしてしまった人や、子供の頃に家族が作ったのだろうけれども記憶にない中学生などがわさわさとやってくる。そういう人には紛失届を出してもらうのだが、家を探すと貸出券が見つかるというケースが多いので、すぐには再発行をせずに、その日は紛失届を貸出券のかわりにして貸し出し、一週間後に再発行をしている。この仕事がめちゃめちゃ多い。今日だけで20件ほどあったと思う。また、三年前まで家族の貸出券での貸し出しを認めていたため、家族の券で借りようとする人が多い。「ご自身の貸出券しか使えなくなりました。もしまだ登録しておられないようでしたら、すぐに貸出券を作りますので登録をしてください。ご自身の券を忘れてこられたのでしたら、この用紙にご記入くだされば、貸し出しをいたします。なくされたのでしたら、紛失届にご記入ください」といったようなことを貸出窓口で言わねばならないのであるが、この数も実に多く、ばたばたなのであった。ま、十年もすれば本人の貸出券を持ってこないと貸し出しができない、という概念にみんなが慣れてくれると思うが。まだまだ家族の貸出券の利用可能という館が多い。私の勤務先も三年前まではそうであった。しかしやはりそれではプライヴァシー保護の概念が一般に浸透しない。図書館の夜明けはなんだかずいぶん遠いような気がする。
- 8月23日(土)
貸出冊数4449冊。返却冊数4113冊。新規登録者31名。夏休みも終わりに近づいているというのにばたばた。閲覧席も完全な満席になってしまって、閉架資料の閲覧者が来たら、事務室で読んでもらうしかないなぁ、などと思っていたら、少し空いたりしたのでした。
パンフレットが机の上にたまってしまっていたので、選定発注業務をする。なんにしても出版点数が多すぎると思う。少し油断しているとパンフレットが100枚以上机の上にのっかっていたりするのであった。
- 8月22日(金)
館内整理日。あれこれ日頃気になっている細かなことについて改善策などを決める。CD-ROMやON-LINE検索についての簡単な講習会を開く。私が講師なのでテキトーなものなのであるが、毎日ばたばたしていて新しく買ったCD-ROMがどのコンピュータに入っているのか、どれがLANで使えて、どれがスタンドアローンなのかといったようなこともわからずにいる職員がいるわけで、まとめての説明を開いておく必要があったのでした。資料があることを知っているのと知らずにいるのとではそれだけで大きな差があります。調べものを調べおわるまでの時間がまるで違ってくるのでした。念のため、J-BISC(国立国会図書館所蔵図書目録)のNDC(日本十進分類法)を使った検索も説明。このごろはマークの分類を参考にした分類作業をしているせいか若い職員がNDCについての認識をあまり持っていないというか、誰も使ったことがないことが判明。J-BISCならばNDCの細目や細々目からも引けるので、相関索引を使ってNDCから検索すれば、書名に単語が含まれていなくても検索が可能であることを話したのでした。普段検索につかっているシステムについても、若い職員が知らずにいるいくつかのことがあることもわかりました。やはり、簡単な研修であってもしないよりはした方が良いなと感じたのでした。ま、自己研修をしていてくれれば、しなくても済む、ということも少し思ったのですけれども。
来週のカウンターローテーション組み。毎週のことだけれども面倒。職員があと三人くらい増えると随分楽に組めるんだけど。
今日が館内整理日で休館であることを知ってか知らずかブックポストへの返却が1000冊を越す。
- 8月21日(木)
寄贈本を蔵書にするか否かの判断をする。このところ、寄贈本も多いので大変である。個人からの蔵書寄贈は郷土資料以外、受け付けていないのだが、会社の社史や、著者からの寄贈などあれこれとある。
明日の館内整理日に行う電子ツールによるレファレンスについてのレジュメを作る。こうした仕事をばたばたのカウンター業務の合間にするのはやはりなかなか気疲れがするのであった。
- 8月19日(火)
朝、ブックポストへの返却は約780冊。11時までになんとか書架に収める。汗だくである。
新刊図書の見計らい、長期延滞利用者への督促電話。一昨年から返していず、頻繁に督促しているにもかかわらず、今頃になって借りた覚えがないという人や、しれっと、「もうありません」という人など、長期延滞をしている人は個性的な人が多い。
今日も慌ただしい一日であった。
- 8月17日(日)
昨日、新聞を探していたOLの知人という人が引き続き記事を探すとのことで、昨日も出したのだが、その年については中日新聞縮刷版(地方版の保存が必要なので、新聞そのものを保存するようにしたため、ある年度だけしか購入していなかった)と索引があるので、まずはそれでお調べになられてはどうでしょうか、と勧める。「窃盗、事故などの項目に別れていて、どこの警察署で取り扱ったかもわかるようになっていますので」とそこまで言うと、「調べているのは○○署で扱っているはずなのだが」とのこと。「昨日の方は××署の扱いだとおっしゃって、そこだけを調べておられたようですが。その記事の載った縮刷版を出して欲しいとのことで、出した覚えがあります」というと、「場所は確かに××だが、扱った署は○○だから、勘違いしていたな、きっと」とのことで、昨日出した年の分と、それ以降の三年分をまとめて閉架から出す。昨日出した分に見つかった。それ以降からはじめると、地方版にしかないと考え、また頭から最後まで繰って、見つけられずに終わってしまうところだった。調べものはひとつ間違えると大変なことになるのである。
今日も当然、利用者が多かったのであった。夏休みも終わりが近づき、調べものの学生がぞろぞろ。夏休みが終わるまであと二週間である。
- 8月16日(土)
新聞の利用者が多い一日だった。マイクロフィルムで読んでいると酔ってしまう、保健室はないのぉ、気持ち悪いよぉと言うOLがいた。どうやら2年分の新聞のなかから目的の小さな記事を探すらしい。地方版に載ったものなので、indexもなく、全部見るしかない。原則的には古い新聞はマイクロフィルムで読んでもらっているのだが、新聞そのものもあるので、そちらで読んでもらうことにする。目的箇所の日にちがある程度しぼられていないと、マイクロフィルムはつらいのである。新聞はしかし重たい。
しばらく前に読んだ本の題名も著者名も出版社名もわからないのだが、今、棚を見たらない。わからないか、との質問。題名のかけらでもわかっていれば、なんとかなるのだが、大きさくらいしかわからないので特定は無理。また読む可能性のある本は書名か著者名を覚えておいて欲しいと思うのであった。
- 8月15日(金)
貸出2684冊、返却2055冊。随分楽だったような気がするのだが、かなりの利用者である。登録者も20人を越えている。
カウンターに出ている合間をぬって、来週のローテーションを組み、郵送されてくる見計らい図書を購入するかどうかを判断し、取次から送られてきた図書の見計らいをする。その間にもカウンターが混んでくると、出てゆかないといけない。やはりばたばたした一日であったことには変わりがないのだなぁ、と落ちついて考えるとそんな気がする。
- 8月14日(木)
朝、中学生が体験学習に来る。書架整理と廃棄する新聞の整理。おとなしく、まじめな生徒であった。帰る少し前に図書館についての説明をする。図書館というと、かたいむずかしいまじめな、といったイメージがあるかもしれないけれども、面白い本もあるし、とんでもない本もあるし、こんな本があっていいのかなといった本もあるので、探してみてください、とか、音楽CDのCD-ROMもあるから、ある曲を聴きたいけれど、どのアルバムに入っているかわからないといったときには訊いてもらえば、探しますといった話をしたのだが、反応が今一つ。もしかすると勉強が忙しくて、あまり本を読んだり、CDを聴く時間がないのかな、と訊くとうなずかれてしまう。中学生は忙しいようだ。
貸出返却とも3000冊ほど。なんとなく楽だったような気がするから慣れとは恐ろしいものだ。普通の平日の4倍ほどだというのに。
- 8月13日(水)
朝、ブックポストの本の返却処理。2200冊ほど返っていた。日曜日に残った分と合わせて4000冊。尋常な量ではない。私は11時まで書架整理をしたのち、11時から昼休みを取り、12時からカウンター業務に出て、13時ちょっと過ぎに主査とともに役所へ行き、OA検討委員会に出席する。ふと気がついたら、組合交渉の時、かなりあれこれ私が質問した元の職員課長や、行革関連の質問をした部長や課長がいて、これはもしかしてあれこれ根に持たれているかなぁ、などと少し思ったりしたが、さして影響はなかったと思われる。今回は郵便番号が7桁になるのに伴うプログラム修正費用と、平成6年にリース切れになったマイクロフィルムリーダーの買い換えと枚数が入り切らなくなったCD-ROMサーバー機の増設についてであったのだが、財政状況が厳しいこともあって、郵便番号のプログラム修正以外は通らなかった。リースが切れてから3年経ってるのですが、壊れたらどうしましょうか。「また、その時に考える」といった寂しいやりとりや、CD-ROM自体がどんなものかを今一つわかっておられれない人がいらしたりして、なかなか楽しい会であった。CD-ROMサーバーには現在J-BISC(国立国会図書館の図書データ)とHY-SFY(音楽出版社の出している音楽CDのCD-ROM)と判例体系CD-ROMを入れているのだが、当初13枚だったので、7枚入るCD-ROMサーバーを2台導入したのだが、J-BISCの昭和1・2期版が増え、カレント版も増えた為、全部のCD-ROMがサーバー機に入りきらず、判例体系の公法編が抜いてあり、もし要望があれば、J-BISCの一枚と差し替えようと思っているのだが、今のところ、要望はないのであった。J-BISCは分類からの検索、件名からの検索、利用者が書名や著者を間違えて覚えてきたときなどに大変役立っており、日に合計200回ほどの利用をしているのだが、判例体系は月似1、2度ほどしか使わないので今のところは困ってはいないが、CD-ROMという媒体自体が出続けていることなどを説明。すると、待ちかまえていたかのように、「ほかの図書館はそのJ-BISCというのを使って利用者の調べ物をしているのか。そういうサービスまでしているから、よその町の利用者がわざわざ来るのではないのか。その為、市民が受付で待たねばならないことになるのではないのか。サービスのしすぎではないのか。趣味で訊いてくるような人間の便をはかる必要があるのか」となにやら譫言のようなことを言っていた課長がいたが、彼は図書館の利用者でもなし、行革では市民サービスの拡充がうたってあるわけだし、その文をおりこんだうちのひとりでもあり、暑さのせいでどうかしたのだろうと思った私は笑って無視することにした。ま、でも、本を探したことのない人が世の中には多いわけで、それと図書館が流行っているのが気に入らない、図書館の職員が生意気なのが気に入らない、司書が専門職なのが気に入らないというのが結びつくとヘンなことを思いつく人がこれから先も出てくるのであろうな、と考えると少し気が重くなった。
言うまでもなく予約、リクエストは趣味で訊いてくる人だけでなく年間数千人にのぼり、リクエストされた本が現在購入できるかどうか、本当に出版されていたのかどうか、所蔵している館はあるのかといったことを調べ、利用者に提供することは図書館のごく基本的な仕事である。司書が図書館に配置されておらず、利用者が読みたい本を探して貸し出すというだけの仕事ができていない図書館が存在しているのは事実であるが、だから、よそは探さないのだから、探さなくても良い、サービスのしすぎである、という論を本気で正しいと思いこんでいるとしたら、どうかしている。ただの意地悪で言ってみただけかもしれないが。良いサービスをしているから他市町からも利用者が来るというのはいけないことなのか。実際、その数は多すぎて、自分の住んでいる町の図書館を利用してほしいものだ、と思うことはあるが、広域行政だの市民サービスの拡充だなどと言っている市の幹部職員が、他市町の利用者を呼ぶようなサービスをする必要はない、などと発想すること自体おかしいと思う。例えば市立病院の医者に、「どうもこの病院は患者をよく治しすぎる。ほかの病院は治らなくて死んだりしているから、ここにばかりよその町からも患者が来て困る。もっとテキトーに治療をして、他市町からの患者を減らしたらどうだ」とは決して言わないであろう。読みたい本が読めることと病気の体が治ることとの距離の大きさは個人個人でかなり異る。が、切実に読みたい本のある人に本を提供するのはそれほどサービスのしすぎであろうか。図書館や司書を理解しようとせず、現象のうわべだけを見てものを言う人はしかし決して少なくはないし、司書の仕事についての無理解は簡単に治るものではないであろうなぁ。
- 8月10日(日)
日曜日なのでばたばたであった。
昨日、岡山県から旅行かなにかで来ている人がいて、登録して借りてゆかれたが、今日のうちに皆返ってきた。県外の人も旅行者であっても登録可能という図書館は全国的にも珍しいらしいが、私の勤務先は以前からそうなのであった。市誌など、そこにしかない資料を旅行のついでに部屋で読むとか、郷土関連のビデオを借りて観て、観終えたら郵送で返すといったこともできるのでした。返ってこない恐れがあるという話もあるけれども、今のところ、遠方の人に貸して返ってこなかった例はないのでした。近辺の人に貸して返ってこなかった例はいくつもありますが。ま、件数に差がありすぎますが、遠方の人だから返さないという考え方は違うような気がするのでした。アメリカなど海外では旅行者が登録できるのは普通のことだ、と聞いたことがあります。
閉館時にも返却図書を本棚にしまいきれないことが多いが、今日は2000冊くらいしまえずじまいであった。13日の水曜日の朝には1000冊以上の本がブックポストに返ってくるであろうなぁ。あまりその状態を考えたくない(^^;)。
- 8月9日(土)
朝、一枚ものの地図がケースに入っていないまま、棚にあったというので調べると、先日、ケースだけあったので、除籍していたことが判明。おお、これでこの資料は復活できるな、よかったよかった、と地図をよくよく見ると、だいだい色のマーカーで行き先までの道に線が引いてあったり、赤鉛筆で○が書いてあったりしてめちゃめちゃ。ケースから中身だけを盜んで行き、あれこれ書き込んだ後、良心がとがめて棚に戻したのであろうか。世の中にはおかしな人が多い。除籍にするしかない。
登録が少なかったせいか、比較的楽な土曜日であった。貸出は3700冊ほどで普段の土曜日と変わらないのだが。平日もずっと来客数が多いので、体が慣れてしまっているのかもしれない。
年下の職員に「市報」に載せる新刊を選ぶよう指示。ノンフィクション10冊とフィクション10冊。ノンフィクションは興味を惹きそうなタイトルのものを中心にできれば0分類から9分類まですべてに渡って選ぶ。有名な人の著作、名の通った出版社のものを選んでおく。なかに1冊、2冊、玄人好みの本を混ぜる。フィクションは海外の小説を1冊か2冊入れる。いわゆる純文学のものを2、3冊入れる。堅くなりすぎず、柔らかくしすぎず、といった点に注意する、というかなる難しい注文をつける。「としょかんだより」と違い、今まで図書館に来たことのない人、図書館の本は難しいと思っている人、柔らかい本ばかりだと思っている人、若い人、お年寄り、などなど、あらゆる人を対象にして、図書館をアピールするためなので、「市報」に載せる本の選択が一番難しいのである。選んできた1冊1冊について、コメントする。ほぼ良い選択であった。ばたばたの合間にこういう業務をするのは気ぜわしい。職員数が少ないのである。
- 8月8日(金)
休みの職員が多い上に出張の職員もおり、さらに悪いことに家庭で起きた事柄で急に帰らねばならない職員もいて、午後は6人の司書で仕事をした。図書のカウンターに3人、視聴覚のカウンターに2人、残りは1人。予約の連絡をしなければならないし、閉架の資料を取りにゆかねばならないしで、ばたばたであった。
午前中に、ローテーション表を作ったのだが、13日にOA委員会(OA機器などの購入予定のある部署の機器の選択が妥当かなどを判断する会議)があるとの連絡が入り、組み直す。
- 8月7日(木)
夏休みが早く終わらないものであろうか、と思える日々である。
朝、先日の佐藤内閣の時のなにやらというところから、電話があった。パンフレットが少し前に来ていたのだが、恐らくは白書などと重なるであろう資料で、値段はなんと38000円。司書で相談し、購入しないことに決めていたので、電話に出た副館長に伝え、断ってもらったところ、断った途端、電話を叩き切られたとのこと。無礼な奴だ。電話とパンフレットで簡単に38000円の本を買ってもらえると考えている方がどうかしているのだが、それで売れてもいるのであろうなぁ。
館内を全力疾走しているのをほったらかしている母親に注意。書架の狭い間を走り回っているのだから、危ないことこの上ない。あんなものにぶつかって怪我でもされたら、ぶつかった人がたまらない。ほかのお客さんでその子供を叱っている人がいたので、その人が親かと思って注意をしてしまったところ、違っていたのでお詫びをする。今はよその子を叱る人が減ったので間違えてしまったのであった。よその子どころか自分の子がほったらかしだったりするものなぁ。いい子に育つことを願う。
- 8月5日(火)
休みあけのブックポストは本が一杯。800冊ほど。午前中だけでは書架に仕舞えない。
休みあけの朝は人が一杯。宿題の中高生が続々。すでに沢山貸し出してしまった分野もある。
休みあけには新刊図書見計らいがある。短時間で見落とさないように選ぶ。
古本屋に注文しておいた「伊藤整全集」が届く。現在では絶版になってしまっている著作の多い作家の個人全集は多少高くても古本屋で購入しておかねば、図書館では何かと不便なので、ぼちぼちと買っているのだが、書庫内の本を移動しないとすぐには入らないのが難である。
- 8月3日(日)
夏休みは何をしていたのかを忘れてしまうくらいばたばたなのであった。数としては、先週の日曜日よりは随分貸出が少なかったのだが(先週6197冊、今日4668冊)、登録は多いし、宿題の調べものは多いし、閉架の資料の利用は多いし、なんだかとても慌ただしい一日であった。
昼休みに昼御飯を食べながら、臨時職員の人から恐ろしい話を聞く。以前に芳香剤の匂いのする本の返却を受けたことがあるのだそうだ。トイレに本棚が作ってあって置きっぱなしになっていたに違いないという結論。風呂に入って読んでるに違いない人もいるし、なんだかめちゃめちゃであるなぁ。O157に気をつけねば。
- 8月2日(土)
夏休みの土曜日である。ばたばたである。
今週は休みをとっていないので、一週間のうちにしないといけない仕事が楽に済んでゆく予定でいたのだが、「としょかんだより」を作らないといけなかったり、中学生の体験学習があったり、沢山のレファレンスが入ったりした為、まったく終わっておらず、来週のカウンターローテーション作成と今週の新刊本発注の仕事を今日のうちにしなければならない、という恐ろしい状況に陥っていた私であった。大ばたばたの一日であった。
- 8月1日(金)
朝、来年度再来年度予算のヒアリングが急に今日に決まったのだが、分館長と副館長が休みのため、少しばたばた。主査二人と館長が出かけ、無事、終わる。
朝、中学生が「体験学習」に来る。どうやら仕事とはどういうものか、を中学生に体験させるのが目的らしく、数年前から行われているようなのだが、高校生にアルバイトを禁止させている県教委が中学生にただで働く体験をさせる発想が私にはよくわからない。以前は余裕があったので、労働体験(図書館には素人が来てすぐにできる仕事はあまりないので、簡単な書架の整理か廃棄する新聞を縛る仕事をしてもらっている)のあとで、図書館についての説明をしていたのだが、今は職員の手が足りないこともあって、小人数に限らせてもらい、午前中だけ、作業をして終わってもらうことにしている。割と涼しい日だったので良かった。閉架から廃棄する新聞を外に運び、縛ってもらう作業は暑い日にはたまらないのである。閉架は外よりも暑い。閉架にしょっちゅう本を取りにゆくと大汗をかく我々である。
昼休みに参考資料を使って調べ物をしようとしていたら、利用者につかまってしまい(^^;)、自分の調べ物が進まなかった。夏休みである。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]