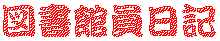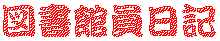
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 7月31日(木)
比較的空いている日だった。
図書の見計らい作業と「としょかんだより」の作成。どうも「としょかんだより」をつくることを忘れ気味の昨今。
- 7月30日(水)
本の売り込みの電話は多いのだが、今日受けたのはとても感じが悪かった。「佐藤内閣の時のなにやらの事務所のものですが、高齢化対策についての本を出したので、購入して欲しいのですが」とのことなので、「送ってくだされば、見させていただいて、購入するかどうかを決めて、もし買わない場合にはお返しするということでよろしいでしょうか」と訊くと、「返してもらっちゃ、困るんだよ」と言う。「返せないということでしたら、送ってくださらなくても結構です。高価な図書なのですよね」と言うと日本が世界中でも高齢者が多い国であることやら何やらを色々教えてくれる。また、「高いというけれども今は子供のおもちゃでも何万円もする時代だよ」とおっしゃる。「高齢者の問題や国の対策についての資料はほかにも多く購入しておりますし、二、三千円の図書も多くあります。同じような本で高価であれば必要ありません。電話一本で何万円もする本を『はい、買います』とは言えません。税金で購入するのですから」と言うと、「それならば送るから」と言うので、「返送は着払いでもよろしいのですか」と訊く。「いや、本を送って着払いではたまらないので、パンフレットを送る」とのこと。パンフレットがあるのならば、電話なぞせず、パンフレットを送ってくれば、時間がかからないのに、つくづく失礼な話だ。「最近は本を送ってくださって、不要ならば、着払いで返してください、という出版社が八割以上になっていますよ」と言ってやると、「うちはそういうことをしていない」と言う。電話一本で数万円の本を買う図書館や企業があったりするのかもしれないな、とふと思った。議員だか何だかが本当か嘘か知らないが、唐突に電話でものを売ることが無礼であるという程度の常識もないのは困ったことだ。図書館をよほど暇なところだと思っているのであろうか。
予約の電話の際、「お忙しいなか、ご連絡くださり、ありがとうございました」と言ってくださった利用者がおられた。この頃では「ありがとうございました」とも言わない人が多いので、なんだかとてもうれしかったのでした。
- 7月29日(火)
朝、ブックポストへの返却本が500冊ほどだったのでほっとしたのもつかの間、開館と同時にすごい人。登録者が38人、貸出4218冊、返却3252冊。
本棚がだいぶ空いてきた。
夏休みの間に職員の誰かが倒れるのではあるまいかというあわただしさである。
- 7月27日(日)
あまりにばたばたで、何をしていたのかよくわからないほどであった。貸出6197冊。返却4621冊。登録30人。レファレンス数不明。所蔵調査の数不明。へとへとになった。
- 7月25日(金)
館内整理日。利用者が来ない日になぜかほっとする。貸出冊数の見直しというテーマを出しておいたのだが、現状で良いとの意見ばかりであった。職員がこれ以上大変になることを避けたいとの心情である。ま、貸出冊数30冊では少ないという意見は多くはないので問題ではないとも言えるのだが、30冊でも無制限でも仕事はそれほど変わらないと私は思う。
閲覧室に椅子を置き、寄贈の雑誌を置き、館内資料閲覧に使ってもらうことにする。
送付されてきたパンフレット、書籍の入っていた段ボールなどの資源ゴミの整理。
- 7月24日(木)
登録者多し。登録していたことを忘れている人も多し。紛失届や再発行の仕事が随分あった。
学習目的の学生や資格試験の勉強の一般人、はたまた生徒の成長なにやらとかいうのをつけている教師などが閲覧室に来ていた。延べ30人ほど。なんとかならないものであろうか。
- 7月23日(水)
本格的に夏休みである。入館者約1400人。貸出3585冊。と土日並。そこに夏休みの調べ物の質問が山のようにくるのであった。登録者も多い。とてもばたばた。これから毎日こういう日が続くかと思うと気が重くなってくる。
分館からの連絡で、市内のどこかの中学校の社会の宿題で、郷土に関連した調べ物を十個ほどあげてあって、その中からどれかを選んでレポートを書けというのがあるのだが、市誌にも載っていない、他の資料もありそうにない、中学生には難しすぎる資料しかない、といったものばかりだそうだ。その宿題を出した先生に、参考資料を教えてもらったらどうだろうか、と分館の職員に話しておく。中学一年生といえば、調べ物を初めてする頃である。学問とは何か、知的好奇心とは何かといったようなことを教えるのに一番良い年頃ではなかろうか。調べようのない調べ物や簡単に調べられない調べ物をまさか宿題にはしていないと思うが、このところ宿題を出すのに手を
抜く先生がときどきいるようなので、心配である。
- 7月21日(月)
中学生の学年全体に出ている社会科の宿題で、ある国について調べて、B4の用紙一杯に書いてきなさいというのがあるらしい。貸出のできる資料はきっとすぐに借りられてしまうであろうから、夏休みの終わり頃にはジュニア朝日年鑑やイミダス、知恵蔵、現代用語の基礎知識の奪い合いとなることであろう。図書館資料が必要な小中高生の宿題に対して丁寧に対応してゆけば、いずれその子達が良い図書館利用者となってゆき、町の文化水準というか知的水準が上がるのではないかと考える私である。子供はいずれ大人になるのだ。
閲覧席で菓子を食っていた学生グループを注意。おそらく初めて図書館に来たのであろう。夏休みが大変なのは、初めて来館する子供に図書館の使い方を説明したりなんだりであれやこれやするからなのだなぁ、としみじみ思う。
今日も閲覧席に閲覧以外の利用者が延べで20人ほど。席の利用をご遠慮いただく。理由を説明すると、みなさん、にこやかに動いてくださる。説明の最後には「調べ物の宿題などがあったら、お気軽に利用してくださいね」ともつけ加えている。
4年前には学習スペースもあったわけだが、一体どのように対処していたのか今では想像がつかない。思い出したくもないと言った方が正確である。資料閲覧スペースの確保に今よりももっとずっと沢山の労力を費やしていたことは間違いない。「ここは館内資料閲覧スペースです。学習のための席はすでに満席です」などと言っても、動かない学生の群れであったのだ。あれはひどい状態だった。何もせずにおけば、席が埋まってしまって、資料閲覧スペースがなくなるわけである。ま、それでも気にしない図書館というのが存在する。それは非常に楽な選択ではある。が、ものすごい数の学生をほったらかしておいたのでは、館内資料を閲覧する人が使いにくいに決まっているのである。家人が昨日、他の図書館に調べ物に出かけたところ、勉強に来ている学生だらけで、館外貸出のできない資料を読むスペースがまるでなく、書架下段の本をしゃがんで読んでいたら、痔になりそうだった、と話していた。あの図書館には夏休みの間、二度と行きたくないそうだ。ま、そりゃそうだ。資料が利用しにくい状況をなんともしようとしない図書館は怠慢である、と言ってしまっても良いと思う。読む場所のない館内利用資料を置いておいたのでは、資料費や資料を選ぶ人件費の無駄ではないのか。
- 7月20日(日)
朝から3時くらいまでは空いていたのだが、夕方、すごく混む。
さすがに夏休み。館内資料を使わない学生が閲覧席にぱらぱらと座っているのを注意。なにやら書き物をしている主婦もいた。「3年前から閲覧席のご利用は館内資料の閲覧のみに限らせていただいております。申し訳ありません」と席を空けてもらうようにお願いすると皆空けてくれた。資料を置いているだけの学生や、辞書を開いているだけの卑怯な学生(幾度か見回っても同じページを開いたままだったりする)にも、閲覧席の利用の限定の理由を説明し、席を空けてもらう。延べ約30人。これだけで閲覧スペースのほとんどが埋まってしまうことになるのである。面倒だけどまだまだ見回りを止めるわけにはゆかない。
ようやく机が片づいた。
発注業務を行う。
貸出3657冊、返却3206冊。
明日も仕事だ。
- 7月19日(土)
今日が終業式、明日から夏休み。図書館にとって地獄のような毎日がやってくるのであった。
火曜日が提出期限のレポートの為に女子大学生が来る。雑誌論文を読まないとどうしようもないようなテーマなので、その旨説明する。大学の先生も参考文献や調べ方について、授業のなかで少し教えておいた方が良いと思う。
幾つかの高校、中学で出されている読書感想文の本を探しに学生が沢山来る。課題図書への予約は先週あたりから殺到し、そろそろ夏休み中に順番が回ってくるかなぁ、大丈夫かなぁ、といった状況の本が出てきている。しかし、課題図書は学校図書館で揃えるか、個人で買うか、課題図書自体を無くすか、なんとかすべきであると思う。公共図書館で副本を何冊も買い、予約に対応しないといけない現状はなんだかヘンだと毎年思う。
机の上がパンフレットでいっぱいになっている。出版点数が多いのだよなぁ、としみじみ思う。
貸出4752冊、返却3617冊。沢山借りられていった。
- 7月18日(金)
大手出版社の系列会社から電話がある。昨日の美術全集の件。バラでは買えないとのことなので、返本することにする。1巻増えただけ、中身が完全に変わったのが2巻だけなのに、売り込みの際には変わっているところが沢山あり、写真もきれいになったと話していたことについて非難すると、「改訂はだいたいこうしたものです。ほかの図書館さんは何とも言ってきませんよ」などと言う。「ほかの図書館のことは知りません。こうした改訂もあるかもしれませんが、それならばその旨、説明すべきです。ともかくお返しいたします」と言うと、「わかりました。返本してくださって結構です。始末書を書かねばなりませんが」と泣き言のようなことを言う。彼の始末書のことなど私の知ったことではない。30巻の版と32巻の版を持っているので、あまり変わっていないようならば、必要ない、とはじめに私は言っているのである。多くの変更があると言うから注文したのだ。この会社の経理の人に返本方法について確認。その人は、「32巻の版を持っておられるのであれば、あまり変更はありませんし、必要ないかもしれませんね。申し訳ありませんでした」と言っておられた。人の問題なのであろうとは思うが、今後、改訂版については現物見計の後、購入決定をするという風にすべきかを検討することにする。
見計らい本を持った業者が来館。沢山の本を持ってきてくれたのだが、ほとんどすでに買っていた。
- 7月17日(木)
先日注文したが直販の美術全集が前の版とまるで同じだと職員が言うので、「そんなはずはないが。営業の話では紙がよくなり写真版がきれいになり、本自体の中身もかなりかわったというので購入することにしたのだぞ」と言うと、「しかし全く同じ中身だし、紙はきれいだけれど、写真は古くてきれいではない」とのことなので、確認すると、そのとおり。前の版は32巻だったのが、今回33巻になっている。33巻だけを購入すればすむことであるので、クレームの電話をする。「1巻と18巻は執筆者がかわっていますし、他の巻も少しずつかわっています。他の図書館ですでに納めたところもありますが、今のところクレームはありません。もう一度ご確認ください。」「他の巻というとどの巻ですか」と訊くと、「確か9巻は違うはずです。今、出先なのでとのことなので詳しいことはわかりません。また明日連絡いたします」とのこと。確かめてみると、1巻と18巻は執筆者、写真、記載とも異っていたので別の本と言える。9巻は白黒だった写真がカラーになっていたり、写真の配置がかわっていたが、本文内容はほぼ同じ。他の巻ははじめから終わりまで同じで、紙は新しくなったものの写真は国宝などのものなので撮り直しができないこともあってか古いまま。これでは詐欺に近いような気さえする。1巻と18巻と33巻だけを買うことができるのならば、そのようにし、もしできなければ類書もあるので、購入を見合わせることに決める。全巻だと20万円を越える、3冊ならば2万円弱である。前の版を所蔵している図書館への売り方にはもう少し配慮があっても良いのではないかと感じた。
先日の尾張部公共図書館連絡協議会の報告書を書く。
新刊の見計らいをする。
カウンター、ばたばた。平日なのにどうしてこんなに混むのであろうか。
業者二社が図書の見計らいに来る。どちらも本好きの人らしく、なごんだ時間を少し過ごす。
- 7月15日(火)
知多市立中央図書館で開かれた尾張部公共図書館連絡協議会に出席する。
知多市の利用者が減っているとのことで、「利用者サービスについて」という議題であった。広報活動、行事、予約、督促、弁償について事前にアンケートが来ていたのに答えておいたのであるが、いろんな館があって面白かった。今だに、「同じ人が沢山リクエストをすると不公平になるからリクエスト件数を制限しています」と不勉強で非常識なことを平気な顔をして答える館が何館かあったのには呆れてしまった。ま、宗教関係の利用者がいっぱい来ると大変だろうけれども、リクエストは総数が増えれば特定の人だけが沢山リクエストをする、という状態ではなくなり、沢山の人が沢山リクエストをするようになるのです。相互貸借も愛知県図書館にだけ尋ねて、ほかの図書館には全然尋ねてない館がいっぱい。どこにもない本だから図書館で訊いてみようと思って来館した人に、「絶版で愛知県図書館にもないので諦めてください」と答えているのだろうなぁ。隣町の図書館にあるかもしれないわけだが。相互貸借の為の郵送料を予算で取っている館が私の勤務先だけだったのにも驚きました。ま、役務費の枠に入っているわけだけれども、前年度実績で、「相互貸借の郵送料は資料費と同じです。本来は所蔵しているべきだけれども、絶版で買えない本を他の館から借りる為のお金なのですから」といった説明をしていることを協議会で発言したが、リクエストを増やしたくない館の人には何のことやらわからないことであろうなぁ、と思う。ま、でも、考えてみれば、司書の採用をしている館がほとんどなくて、役所からいやいやのように図書館に異動してきた職員も結構いるわけで、全体の水準が高いはずはないのだよなぁ、と変に納得もしてしまったのでした。久しぶりに出張したのでなんだかくたびれてしまいました。
- 7月13日(日)
大わらわの一日であった。貸出冊数約5700冊。登録者30人。何をしていたのか覚えていないくらいばたばたであった。雨が降っていても、来館者は多い。
開架がいっぱいなので、閉架に本が沢山動いている。閉架の図書を貸して欲しいという利用者がどんどん増えている。利用者用検索端末で、閉架の資料を探すことができることとも関係あるし、利用者自体が増えていることとも関係がある。資料が死蔵にならないのでとても良いことなのだが、ばたばた度が増す原因となっているのは言うまでもない。職員数が足りないのである。開架も狭い。
返却する図書を利用者に書架まで返してもらっているのだが、書架がいっぱいだったり、返却場所がわからない場合には返却用棚に返してもらっている。この返却用棚に返っている図書を書架に返す作業が閉館時間までに終わらないことがしばしば。利用者が多く、職員数が少ない為である。書架整理は土日などには頻繁に行わないとすぐにぐちゃぐちゃになるのだが、カウンター業務やレファレンス、予約の連絡業務などで手一杯でいつも書架が汚い。なんとかしたい、といつも思うのだが、なんともできない。書架整理に出たら、てんでばらばらの本を一旦棚から取り出して元の棚に治めるまでに最低一時間くらいはかかる為、人手に余裕のないときにはできないからである。
- 7月12日(土)
以前に私が借りた本の記録は残っていないだろうか、との問い合わせ。プライヴァシー保護の為、残していないけれど、書名か著者名の断片とか書架のどのあたりから借りてゆかれたかを覚えていないかを訊く。単語を二つとどのあたりの書架から借りたかを覚えておられたので、電算検索で絞り込んで該当図書を見つける。この作業、なかなかスリリングで好きだったりする私であるが、混雑しているときには大変である。
難しいレファレンスがいくつかあった。江戸期の地方誌の所在について。「国書総目録」を見ると明治期に活字で出ていることがわかったので、愛知県図書館に国会図書館所蔵明治期刊行図書目録所載分のマイクロフィルム版があるからあるのではなかろうか、と国会図書館の明治期刊行図書目録を確認したり。
女子大学生が沢山くる。不幸な宿題というか、参考文献が全部絶版でどうすれば調べられるんだという言語学関連の書籍の照会があった。当館には一冊もなかった。しかし、こんなのどうすると入手できるのだろうか。専門書籍が常時置いてあるような古書店は愛知県にはない。参考文献を読むことができたのは大学図書館か愛知県図書館(あたりしか多分持っていないであろう本なのである)で本を借りることができた学生のみということになってしまう。この参考文献リストを書いた大学教員は入手方法までは考えていなかったのか、ただの意地悪をしたのか。はて。
読書感想画コンクールの表彰式のため、ばたばた。表彰式が終わったあと、閲覧室に受賞作品を展示する作業。コンクールのたぐいは一度はじめたらなかなか中止できないので大変である。学校のカリキュラムにも入ってしまっているため、「利用者が増えたので、コンクールをやめます」とはなかなか言えないのである。ほかにも行事をいろいろしたいのだが、職員数に余裕がないとできないのである。
感想画の展示作業が長引いた為に、予約の連絡電話をかけるのが終業後となる。約百件。一時間かかる。電算打ち出し葉書による連絡にすると楽になるのだが、金額が電話の5倍になるので、予算をとれないのであるが、人件費を考えれば安いわけで、来年度は検討すべきだと思う。ま、多分取れないだろうけれども。
- 7月10日(木)
来週のカウンターローテーションを組む。組んでいるうち、段々腹が立ってくる。食事を三交代で取らないといけない日が七日のうち四日ある。三交代のローテーションを組むのはめちゃめちゃややこしいのだ。職員の数さえ多ければ二交代でローテーションは組めるのだが、と思うとすごく腹が立つのであった。一人が一日五時間カウンターに出る日もあるわけで、よくこれでほかの仕事を片づけていっているなぁ、と感心したりもした。
カウンターばたばた。登録者が多い。登録者が多いということはその後、貸出返却、予約リクエストの業務も増えるということである。嬉しい悲鳴というかなんというか、職員数が増えないことを前提として進んでいるのであるから、将来のことを思って憂鬱になる。
- 7月9日(水)
久しぶりに出勤。中日新聞の記事についての質問は市民から出ていないようだ。一安心。
午前中、カウンター。大学生が訳本探しにくる。プリントを片手に著者が誰かもわからぬまま訊きにくる神経はなんだろ。手にしているプリントを見るとはじめの数行の単語の意味を引いているだけ。「授業のテキストの翻訳を探しているということであれば、せめて訳している本があるのかどうかを調べてからお越しください」と言う。日本の学校制度はどこか絶対ヘンだ。家の事情で大学へ行けない若者だっているだろうに、ここまで巫山戲た大学生が多いのはどうしたころなのだろ。20歳くらいになっているというのに、自分が何のために何をしているのか、と考えた形跡がどこにもないのはなぜなのだろうか。そうした大学生がそのまま社会へ出てゆく。
午後、電算のSEが来館。統計プログラムについての打ち合わせ。
- 7月7日(月)
中日新聞にフォロー記事のような記事が載った。どうも事実誤認がいくつかあるようである。投書がきっかけとなって閲覧室を開放するようにしたわけでもないし、「三年ほど”あかずの間”」にしていたわけでもない。今年、書架を増やしたことにより閲覧スペースが減ったことと、閲覧利用者が増えている点、また、開架スペースに出しきれない逐次刊行物も多くあることからそうしたものを閲覧室に置いて、開けることにしたのである。今までも開かずの間ではなく、閲覧利用者が多い日には閲覧室として利用してもらっていた。そのことについて記者氏には説明をしたはずなのだが、投書をきっかけに開放と記事ではなっている。卑怯者の手による匿名の投書で図書館運営が左右されているわけではない、とここで強く反論しておきたい。管理職でもない職員は新聞記事に反論できる場は多くはないし、管理職が反論したところで、訂正記事が大きく載ることはあるまい。
それにしても「生涯学習センター」というのは一体どんな役割を担う施設なのであろうか、といつもこの名称の施設の話が出る度、思う。記者氏が頭の中で描いているのは席が沢山あって市民誰もが使えるところ、といった空間なのであろうか。飲食物のない無料のファミリーレストランのようなところが生涯学習の為に役立つので、図書館の中にそういうスペースがあると良い、ということなのだろうか。私にはこの発想がよくわからないのだが、市民の多くが望めば、そういうものを「図書館の中に」作らねばならないのだろうか。過去、そして現在も多くの図書館は館内資料閲覧以外の利用者の利用に制限を設けていない。そうした図書館の現状が「生涯学習センターの役割」を果たしているということなのだろうか。学校の勉強や会社の仕事をすることのできる大きな机のある場所を「生涯学習センター」とする発想はしかし何もこの記者氏だけが思っているわけではなく、何の役に立つのかよくわからないまま、誰が使うのかもよくわからないまま、新しいメディア関連の機材を入れた机と椅子が沢山ある箱が今後多く建設されてゆくようである。土建屋国家の面目躍如といったところである。まず箱が必要なのである。生涯学習センター、万歳。
生涯学習が当たり前になっている昨今、図書館で為しうることはまだまだ沢山あるはずである。図書館資料の充実、貸出、予約、レファレンスに対応できる専門職員の配置、資料を気楽に利用できる閲覧スペースの設置。こうしたことがしっかりとできていない館の多さは嘆かわしいばかりである。私の勤務先もまだまだであると思う。こうした点を充実させることと、席をおいただけの空間を作ることのどちらが生涯学習の為になるのかな、とこの記事を読んで考えこんでしまったのは私だけだろうか。どっちつかずの記事は結局多数の無責任な要求を表面化させるだけになるのではないのか。この記事によって、もしかするとどこかからの圧力により、私の勤務先の閲覧スペースを学習利用者や仕事のための利用者に開放せねばならなくなるかもしれないが、そうした事態になったら、生涯学習センターの役割も果たすことができるようになった、と我々は喜ばねばならないのであろうか。
学校教育関連の機関が学習センターを作るべきだという発想に行かず、社会教育施設である図書館内に学習利用のできる場をとする根拠や自信はどこからくるのだろうか。
多数の人にとって司書などはどうでもいいのであろうなぁ、としみじみいじけた気持ちになる昨今である。
- 7月4日(金)
朝、中日新聞の地方版に閲覧室の件についての記事が出ていた。学習利用禁止、調べものだけに限るといったあたりを強調しているのは良いが、過去250席ほど開放していても席が足りなかった点について書かれておらず、一部学生の素行の悪さに手を焼いて閉めたかの如く書いてあった。書架が増え、席が減り、手狭になったことも書かれていたのだが、一部学生の素行の悪さについて書いてあると、うちの子供は素行が良いのだから使わせて欲しい、といった親が出てくるのではないかという危惧がある。そこまですごくはなくとも、一部学生が悪いから良い学生まで使えなくなるのはおかしいという話は出てくるのではあるまいか。だから私は、「素行の善し悪しは問題ではなく、席の数を大幅に上回る数の学生が来館し、閲覧用に設けた席にまで座り、注意をすると空けてくれる学生もいるが、そのまま座る学生もい、空けてくれた席に数分後にはまた別の学生が座り、注意をしても動かない。そんな風に閲覧用の席がすべて学生で占められたため、事務室内で館内資料を閲覧してもらわねばならないような事態となった。館内の資料を気楽に使っての調べものができないような状態ではなんの為に資料を購入しているのかがわからないわけで、また、テスト期間以外の日の閲覧利用者はかなりいらっしゃった。そこで職員間で相談をして、閲覧室を閉め、閲覧席のみを館内資料閲覧に限ることにし、閲覧席に人がいっぱいになったときには閲覧室を開放するという方針をとった」という説明をしたのだ。学習利用者の数が多すぎる際にとれる方法は沢山はないと思う。ほおっておくか、制限を設けるか、だ。制限をしてなくて困っている館は「困った困った」と言いつつ、館内資料閲覧目的の来館者に不自由をかけているのだ。その利用者は他の図書館へ行くことになる。そのように逃げている館が多いうちは図書館全体の質の向上など望めるはずはない、と私は思う。席を貸すだけならば大きなプレハブ小屋にエアコンを入れ、机と椅子を置けば良いのである。そこに資料は不要だ。図書館はそういう場所ではないと思うし、どちらを選ぶかと言われて資料閲覧者への迷惑のかかる席貸業務を選択するのは図書館員ではないと私は考える。
- 7月3日(木)
新聞記者が閲覧室の件で取材に来た。6月13日分に書いた匿名の投書についてである。先週金曜日にも来ていたので、過去の経緯について書かれたものを渡し、説明をし、終わっていたかと思ったのだが、さらに詳しく聞きたいとのこと。上司が今月末に閲覧室を開けるが、飽くまで館内資料閲覧に限定すると説明。学習に使わせている館は困っているところが多いみたいですね、と記者氏は言う。県図書館はすぐ近くに予備校がある為、テスト期間や夏休みだけでなく、毎日、席を借りるための学生が沢山来て、荷物を置いて予備校に行き、予備校の授業が終わると取っておいた席について勉強をはじめるそうですよ。大変ですよね、などと話してゆく。資料を使わない利用者が沢山来すぎて困った経緯の説明などをしたのだが、果たしてどんな記事になることであろうか。
本人以外の貸出券が使えないのはどうしてなのだ、との質問が利用者から出た。事務室に入っていただき、話を聞く。複製絵画を借りてきて欲しい、と父親に頼まれて、父親の券を持ってきたのだが、貸してもらえないと言われた。納得できないとのこと。複製絵画は所蔵の数が少ないので一人一点という制限を設けている。この利用者は自分の券で複製絵画を一点借りている為、借りられないわけだ。図書の場合、貸出数制限を三十点にしているので、家族の分を借りてゆける余裕があるのだが、複製絵画は無理である。プライヴァシーについての説明をし(「一図書館員から見た日本」の第二回参照)、貸出点数を増やすよう、条例規則を変更できないかどうかを検討してゆきます、と答え、納得していただく。
明日から長い休みを取るため、発注業務などでばたばたした。
利用者は多くなかったが、レファレンスや、閉架の資料の利用が多かった。
- 7月1日(火)
今日から7月。時の流れは早いものだな、などと思いながら、ブックポストに返却された本の返却処理をし、三交代なので11時から休憩をとり、12時にカウンターにつき、ううむ7月、7月、何かすることがあったような気がするが、と、はたと気がついたら毎月1日に発行する「としょかんだより」を全然作っていなかったことに気づく。きれいさっぱり忘れていたのであった。これは表が一般書、裏が児童書のB4サイズの新刊案内と行事案内なのだが、載せる本を選ぶのが大変。ほかの一般書担当が選んでおいてくれればよかったものを誰も何もしていない。ま、いつもは私が「としょかんだよりの本を選ぼう」と言って選びはじめるわけであるが、誰か何か言ってくれたって良いと思うのである。が、担当者は私だから忘れていた私が悪いのであった。児童書の分はすでに刷り上がっていた。「どうして教えてくれなかったんだよぉ」と駄々っ子のようなことを言いながら、カウンターを替わってもらって大急ぎで作り、印刷。しかし、慌てて作るとろくなことはない。間違いが数カ所、すぐに見つかる。大きな問題はなさそうなので第一版はこれでゆくことにし、次からの分の原稿を作っておく。
私の勤める市では、7月8月9月のうちに夏休みをとることになっているのだが、学校の夏休み期間や特にお盆の頃には利用者が多いので取りにくい為、7月の頭か9月に休みが集中する。今週に沢山休む予定の私はなるべく来週に仕事を持ち越さないようにあれこれしたのであった。ばたばた。
- 6月28日(土)
台風が来ているというのに来館者多し。貸出返却、どちらも約4000冊。
昨日の館内整理日に出た話で私の中でくすぶっている事柄がある。参考書や問題集を持ちこんでの勉強をする利用者について、「しかし、県営住宅に大勢の家族と住んでいるなど、家庭環境がよくなくて家では勉強できない生徒もいる。そのことも考慮すべきではないのか」と意見した庶務担当の上司に対して私は「しかし、学習的な席の利用を親の年収が少ない人に限るわけにもいかないではないですか」と答えた。「そういうことを言ってるわけではない」と彼は言ったのだが、そういうことを言いたかったのではないことなど初めからわかっていて私はそう答えたのだ。彼の意見に沿った方向を取ることは即ち、館内資料の閲覧以外の利用者にも閲覧席を使わせることになるのであり、数年前、200席を開放していても全然席が足りなくて、館内資料閲覧利用者が席を使えない状態に逆戻りになるわけである。私には話の方向がずれるだけの発言であるように感じられたのだ。だが、私が茶化したような答え方をした理由はほかにあるのではないか、とあとから思ったのである。家庭環境がよくない人のことや、障害者のことを視野におくことは図書館経営において当然のことであり、常日頃から考えているに決まっているのである。彼の発言が司書をバカにしているように私は思ったのではあるまいか。世の中の底辺の人の例を出して、君たちはそうしたことを考えたことがないだろうけれど、と言わぬばかりの彼の態度に、私は大人げなく腹を立てたのだと思う。けれども、その場面で、「私はそうした人たちのことを常に念頭に置いているが、かといって学習のみの利用の為に閲覧席をすべての人に開放するわけにはいかない」などという答えをしたとして、福祉畑から来た彼は納得したであろうか。何をどのように考えてるのかを事細かに話さねば恐らく納得してはもらえなかったであろう。そもそもそこに問題はないのだ。すべての人に平等に接することが重要なのである。平等にできないことはすべきではない。また、弱者の為に、との意図で、図書館の本来的な業務に支障をきたすようなことをすることはまずいのである。強者の為に、との意図で、支障をきたすことをするのがまずいのと同じことなのである。私は社会的弱者のことについて、こんなことやあんなことやあれこれ考えているのですよ、と事例を挙げて人前で話すことを、私はかっこ悪いと思ってしまう。そうした話をする人の多くは偽善者ではないか、とさえ思っている。私はひねくれているのである。きっと彼は私のことを「弱者のことを考えない思いやりのない人間」だと感じたであろうなぁ、と考えるとなんだかうんざりするのだが、誤解を解こうという気もないのである。困ったことだが、そんなダサいことをするくらいならば死んだほうがましだと考えるような性格の私なのである。こういうところ、図書館員に向かないような気がする。いや、勤め人に向かないのではなかろうか。そんなことを考えていると気分が鬱ぐ。
気分が鬱いでいるところに憂鬱な事件の犯人逮捕のニュース。
中学生が殺した猫をボストンバッグに詰めているという事件を15年ほど前に聞いたことがある。その時、これからの世の中はさらに悪い状態になるだろうな、と感じたのだが、その15年の間に私は少しでも世の中がましになるような何かをしたであろうか、と考えこんでしまった。そしてまたさらにこの国の状況はひどくなってゆくのではないか、と思える。酒鬼薔薇聖斗の事件がただの特殊な事件のように思えないのが哀しい。犯人が中学生だと聞いても少しも驚かない自分が情けない。
- 6月27日(金)
館内整理日。長年の懸案事項である二階の閲覧室を常時開けておくべきか否かについて検討。机椅子を沢山置いて開けておくと、参考書や問題集を持っただけの学生や、仕事だけを持ち込む社会人で塞がってしまい、さらにその席が塞がっていれば、一階の閲覧席にまで館内資料を利用しない人たちが押し寄せてくることは間違いないわけで(「一図書館員から見た日本」第4回をご参照ください)、そのようにはできない。閲覧席は隣の会議室と可動壁で仕切られており、二つの部屋をぶち抜きで使うこともあり、たとえば、マイクロフィルム閲覧室というような使い方をするわけにはいかない。となれば、机を多く置かず、スツールなどを置き、寄贈される雑誌を並べておくという方法しかないのではないかという結論になった。机が必要な利用者が多く来た時には移動できる机を出せば良いという話にもなった。現在は一階の閲覧席がいっぱいになった時に二階の閲覧室を開けている。が、夏休みなどには、その開けている少しの時間に、館内資料閲覧ではない利用者がわさわさと来るのである。表示もしてあるし、時折、閲覧室に説明にゆくのだが、聞いてはもらえないことが多いのである。
館内資料を使っていない利用者がいないかどうかと閲覧席、閲覧室を見回る仕事について否定的な意見を言う職員が何人かいた。実際に見回ったことがないから言うのか、見回りたくない、苦情を言われたくないからの意見かはわからないが、館内資料を利用しにきた人に気持ちよく使ってもらう為には見回りは必須の仕事なのである。見回らなければ確実に館内資料を使わずに閲覧席を占領する利用者が増えてくる。館内資料利用者以外の利用はご遠慮くださいと言いはじめてからの三年間を検証すればすぐにわかることなのだが。誰だって、見回って、「すみませんが、館内資料のご利用以外はご遠慮くださいね」などと言う仕事はしたくない。したくないからしない、お前がすると私もしないといけなくなるではないかとの思いがそうした意見から感じられてしまう。
他の図書館でも学習のみの利用についての問題は生じていると聞く。制限をはじめるには覚悟がいるに決まっているが、その覚悟というのは、日本の国民は読みたい本を読めているのか、調べものを満足にすることができるのか、自分の勤務している図書館はその為に何をしているのか、図書館員として自分のすべき仕事はこれで正しいのであろうかとの問いかけをしているか否かということと一直線に繋がっているように思う。
- 6月26日(木)
今週は空いている。特別整理期間のため、返却日になっていないことと関係していると思う。
きびしいレファレンスがあった。小学生がCDで聴いた短い曲のピアノ楽譜を3曲分借りたいとのこと。日本語で書かれた楽譜集には見あたらず、ドイツ語で書かれた楽譜からそれらの曲を探す。目次に出だしの譜と元タイトルが書いてあるだけなので、元タイトルがわかるかはじめのフレーズの譜がわからないと探せない。音楽事典等で元タイトルを探すのだが、ある曲の中に入っている短い曲だったりするので、その元となる曲がわからないと探せない。CDも図書館から借りたものだが、現在貸出中である。30分ほどかけて2曲はなんとか見つけたが、もう1曲は元々がピアノ曲でないので、どうやら所蔵していないことが判明。一般に利用できる音楽専門の図書館が都道府県に一つ二つくらいはあっても良いのではないかと思った。
- 6月24日(火)
珍しく空いた日だなぁ、と思っていたら、閉館時間近くにばたばたした。貸出冊数1547冊、返却冊数1918冊。
朝、笛のついた靴を履いた子供をつれた母親が計三人。
「今度から、図書館ではご遠慮くださいね。笛の穴のところをセロテープでふさぐか、笛をとりはずしていただくと、音がしなくなりますので、そのようにしてくださっても良いのですけども」と、一刻も早く音を止して欲しいことを婉曲にお願いするのだが、とりあえず今日は構わないな、と思われるのか、そのままぴいぴいぴいぴいと子供が大きな音を立てて歩き続けるのを放置している母親が一名。あの音、隣で聞いていて気にならないのかなぁ。長く聞いていると私は吐きそうになってくるのだが。日本人は音のするものが昔から好きなのかもしれない、と、豆腐屋のラッパ、火の用心の拍子木などのことを少し考える。本を読む人のいるスペースでぴいぴいぴいぴいと大きな音を立てることなど想像もつかないのだけれども、音を立てていても平気な人が随分いるのだから、特別変だということではないのだろうか。よくわからなくなってくる昨今である。
- 6月22日(日)
かなりばたばたの一日であった。朝、昨日の返却本がまだ500冊ほど書架に返せないままであるところに、ブックポストへの返却本が300冊ほど。土曜の晩にブックポストに返す人は今まであまりいなかったのだけれどもなぁ。
開館して間もなく、全人口に対する老齢者人口の比率が昨年、新聞に載っていたはずだが、確認してほしいと電話によるレファレンス。オンラインデータベースにアクセスしてあれこれして探す。レスポンスが今一つなので手間取る。しかし思えば、このオンラインデータベースの使用料金という予算が数年取れなかったのである。恐らく今も取れていない公立図書館が多いのではあるまいか。或いは必要だと思っていない図書館とかさ。新しい情報を検索するために図書館がオンラインデータベースを利用することは今や必須だし、使うことのできる職員がいるべきだし、その為の増員も当然でもあると思うのだが、そう思っていない人が多いような気がする。4年前にオンラインデータベース使用料、年間20万円の予算が必要だ、とある委員会にはかった際、「新聞の記事なんか、客に新聞をめくらせて探させればいいんだ。そこまでサービスをしなくてもいい」と幹部職員に言われたことをふと思い出す。年間億の単位の事業がいっぱいあるのに、直接利用者の為になる20万円のお金はなかなか出てこない。地方の役所は案外こんなものです。まだ新聞をめくらせている図書館はいっぱいあるはず。レファレンスのツール(道具)がいくら進歩しても、使わなければ無意味なのだが。
朝は利用者の数がそれほど多くなかったのだが、午後から殺到。貸出返却の窓口は息をつく暇もないほどであった。
貸出冊数5301、返却冊数5053冊。
- 6月21日(土)
ばたばた。貸出冊数約4400冊、返却冊数約4800冊。どたばたであった。
それにしても若い親たちのひどさといったらない。利用者用検索コンピュータ端末の前(カウンターの上である)に3歳くらいの子供をどっかと乗せている父親、ふたりの子供に館内を走り回らせて知らぬ顔をしている両親、階段で遊ぶ数人の未就学年齢の子供をほったらかしている親たち。カウンターがばたばたしてる時に開架は子供たちによってアナーキーな空間となっているのである。事務室から職員を呼び、開架に出て注意してもらう。なんでいい加減な親の為に人員を割かねばならないのであろうか。が、事故でも起きたら、図書館の責任になるのであろうなぁ。未来の日本のことを思うとうれしくなってくる。
最近の事柄を調べている高校生に、関連学部のある近くの大学図書館の利用を勧めたのだが、そこは18歳未満利用不可と言われたとのこと。知らずに教えたことを侘びる。一般利用者に公開しているというので、高校生ならば何の問題もなかろうと思ったのだが、18歳以上でないといけなかったとは。ま、小学生はともかく中高生が大学図書館を利用するのは悪いことではないように思えるのだが。それぞれの方針だから仕方がないのだけれども。オンラインデータベースで新聞の関連記事を探して、新聞を閲覧してもらう。
- 6月19日(木)
午前、来週のカウンターローテーション表を作る。今月は特別整理期間があったため、週休日(役所が毎週土曜休みなので、そのかわりの分を個々で休みをとるのである)が重なってしまい、5日のうち3日が三交代となる。うなり声をあげていたら、上司が寄ってくるので、人手が足りないためこうしたことになっています。登録者は増え続けており、レファレンスも増えるので、今後はカウンター要員も増えることになるわけで、ローテーション組みの仕事も大変なのです、と説明すると、「仕事が増えるのはどこでも同じだ。今の情勢では正職員が増員されることはまずない」と言うので、「例えば視聴覚資料の貸出を取りやめるとか、リクエスト予約を市内在住在勤の利用者に限るといったようなことをして、市民へのサービスを落として、職員の負担を減らす方向も考えてゆくべきなのでしょうか。そうだとすると徐々に準備をする必要もありますが」と言うと、「現状と逆行するようなことはできない。人数を増やせばいくらでも仕事はできるだろうが、増やさずにできる方向を考えるべきだ」とのこと。さらに「繁忙な夏休みに臨時職員を増員してはどうだろう」と言われる。「夏休みは確かに大変なので臨時職員を増やしてもらえば、楽にはなるのだけれども、平日でも今までよりずっと大変で、職員が若いからもっているようなものの、閉架へ走ったり、書架をあちこちまわったりといった仕事の合間に選書や入力などをしている現状であり、また臨時職員は元々同じ人を一年しか雇えないはずではないのでしょうか。ほかも同じとは言え、利用する市民が増えたという課が沢山あるというわけではないでしょう。仕事をしてきたからこそ利用が増え、仕事が増えたのです。仕事をすればするほど大変になるというのはおかしいのではないでしょうか」などと話したが、現状は厳しいのだそうだ。30分ほど口論のようになった。「役所の他の部署にはもっとひどいところがある」といったことを横から言う上司もいた。「ひどいところの例をあげて、だからここもひどくてもいいというのはおかしい。下にあわせてゆくべきだということですか」と言うと、「上はしかし際限がない」と言う。「上の話をしているのではなく、現状がきついと言っているのです」と話す。カウンター業務とややこしい業務を兼ねている奉仕担当の中身についての想像はむずかしいのかもしれないが、間違いなく仕事が増え、このままでは来年再来年あたりに、利用者に迷惑がかかるやもしれぬ事態でもあるのだが、そうしたことはそれほど大したことだと思っていないのかもしれない。図書館の本来あるべき姿、などと大層なことではないのだが、読みたい本を誰にでも気楽に提供する、知りたいことを極力早く調べることができる図書館にすることだけを目指してここ数年、私は仕事をしてきたつもりであり、また年若い同僚もそのようにしてきたのであり、数年で約20万冊の貸出冊数の増加があったのであるが、職員は増員されないわけで、つまりは誰からも評価されていないという現状は大変空しいものがある。金の話はしたくないが、土日に出勤したってはじめからわかっているではないか、と手当はついていない。司書の資格手当もない。一般行政職と給与体系は同じである。仕事をすればするほどバカを見るところが役所なのだろうか。我々の仕事は臨時職員でまかなえる仕事なのであろうか、と考え込んでしまった。少なくとも未利用者からはそのように見られているのであろうな。他の課が最近忙しいというのは県や国からの指導などによったりするらしい。確かに忙しいところはあるだろうし、残業だらけの課もあるわけだが。利用者がいる間にそれらの利用者に満足のゆく仕事をしてゆかねばならぬ特殊性というのはどうしたら理解してもらえるのであろうか。そんなことは多くの人にとって無価値なのであろうか。だとしたら私のしている仕事は価値がない、ただの自己満足なのか。読みたい本を誰もが読める状態を維持したって維持しなくったって大したことがないと、この国では多くの人が思っているのだろうか。と、上司が大したつもりがなく口にしているであろう事柄からあれこれ考え込んでしまった私であった。実際、市が貧乏で人を増やせないであろうことはわかるのだが、現状の人数でこのまま進めというのはできることではない。閉架書庫も近く一杯になる。閉架の資料を沢山電算で除籍か異動の処理をして、別置するか廃棄するかせねばならないが、その選択は経験のある司書でなければできない仕事であり、時間もかかる。新しい電算のデータベースに伴う様々な業務、郵便番号変更に伴ういくつかの業務、と仕事は増える一方なのだ。司書でなく、カウンターにでない上司はそういったあれこれについて真剣に考えているのであろうか。
午後、カウンター業務。小学生が調べものの宿題で来館。「ブラジルの衣食住について」「アメリカの衣食住について」「トリハロメタンについて」と、なかなか難しいことを調べている子供たちであった。正職員の司書はいらないのか。宿題などほおっておけばよいのか。資料は素人でも選べるのか。評価されるために仕事をしているわけではないが、まるで評価されない仕事に力を入れているのは情けない。
貸出約1900冊、返却約2500冊。
- 6月18日(水)
レファレンス多し。ばたばた。
「前に見たことがある」との利用者の記憶の本を探すことがままあるのだが、その本、私も見たことがある、と大探し。若い職員に尋ねると知らないとのことなので、古くからの職員に尋ねると、「確かにあった」とのこと。どうやらかなり古い本で、傷んだかなにかで廃棄したのではなかろうか、と結論。他館では恐らく参考資料にしている類の本なので、相互借り受けもできない。類書を購入するということで納得していただいた。
大学生の宿題。どうやら訳本さがしなのだが、かなり特殊なものであり、そもそもその訳本が存在するかどうかもわからない。また文中の人物についても調べているのであるが、アジアの俳優とのこと故、一般的な人名辞典にはなく、日外アソシエーツのオンラインデータベースや新聞記事を検索してみるが見あたらなかった。
幼児を二人連れた女性利用者が多くのコピーを取っている。当然のように二人の子供は暴れる。本を投げたりもしているので、注意した。こうした場合、コピーの受付をした職員がコピーをとり、利用者に子供を見ていてもらった方が安全である。「私がコピーを取っておきますのでお子さんをご覧になっていてください」と言い、残り少ないコピーを取る。複数人の幼児を連れて外に出ることは大変だと思う。しかし産む前に、産むとあれこれ大変なことになるとの想像はつくような気もする。いや、産む前の行為をするときにすでにわかっているように思える。子育てによる行動の制約は当然起きるはずなのだが、公共施設や飲食店、展覧会、書店などでよく見かける情景から想像するに最近はこの種の規制が親の内部に生じなくなっているらしい。そうした状況に施設が合わせてゆかないといけないのだろうなぁ、きっと。将来の日本はどうなってゆくのであろうか。暮らしやすくはなさそうな気がするのは私だけだろうか。
- 6月17日(火)
電算のトラブル。LANで繋がっているネットワークプリンタに印刷できない。パソコンのアプリケーションで作った文書が印刷待ち状態になったまま、中止もできないし、印刷もされない。電算屋さんに連絡してあれこれするが駄目。
合間を縫って、文部省からのアンケートに記載。CD-ROM、商業データベース、インターネットの利用状況について。ところで図書館での電子テキストの著作権の問題を文化庁は検討しているのだろうか。図書館における複写の問題ももう少しなんとかしてもらいたいと思う。現行の条文を真剣に守ろうとすると、百科事典の一項目が一著作にあたるため、項目全文の複写ができないことになるわけで、そうしている図書館は現状ではほとんどないと思われる。また逐次刊行物は一定期間が過ぎれば全冊複写ができるのだが、その雑誌に載ったエッセイや詩が単行本に入ると、それぞれが一著作となり、全文が複写できないのだが、これは矛盾ではないのだろうか。電子データについてはさらにややこしい問題があるだろうが、実務に困らないように考えていっていただけるとありがたいな、と思う。
ネットワークプリンタの件は原因不明のまま起こり、なぜか治ってしまった。こういうのは怖い。
- 6月15日(日)
貸出冊数約4500冊。登録者は10人ほど。
大学生が郷土人資料を閲覧請求。明治期の雑誌など。目録を見て、必要な本を探してもらい、利用表に記入してもらう。多数の資料を少しずつ多量に見てゆかねばならない(一度に机に置ける資料は限られているし、調べるにつれて必要な資料がさらに出てくる)この手の調べものは経験のある司書が長時間その業務に関わることになる。レファレンスが増えれば司書が多く必要となるのは当然なのだが、世の中の情勢はそうはなっていないようだ。
受付業務の合間を縫って、特別整理の間にたまってしまった仕事を片づける。来週の受付ローテーション、二週分の新刊発注、大量のパンフレットからの選書。どれも集中力の要る頭を使う作業なのでふらふらになる。こうした仕事の間に、「レファレンスをお願いします」とか「貸出の受付をお願いします」と声がかかるので、カウンターに出てゆく。
来週の受付ローテーションは食事が三交代(11時、12時、13時)の日が二日ある。役所の土曜日の代わりの休みを交代でとる為である。特別整理期間には仕事が多く、休めないから休みの人が集中してしまうのである。臨時職員が平日四人もいるのだが。さらに夏休みに入ると受付に出る人数が増えるので毎日三交代となる。職員の絶対数が不足しているのだ。しかし職員は増えない。
- 6月14日(土)
10日ぶりの開館なので、朝からばたばた。なぜか登録者が40人もいた。登録者が増えるということは、貸出や予約、レファレンスが増えるというわけで、仕事量がとても増えることになるのである。職員は来年も増やしてもらえないことになったとのこと。憂鬱になる。
新聞記事の検索希望の方が3人。オンラインデータベースから関連記事の載った日付を調べるのだが、結構時間がかかる。新聞にあたりをつけてめくって調べることに比べれば随分短時間ではあるのだが。これらの記事はダウンロードしてもよいのか、そのダウンロードしたデータを画面で見せても良いのか、プリントアウトして良いのか、プリントアウトしたものを利用者に渡してもいいのか、といった著作権上の問題がある。現在のところは掲載日付から、所蔵している新聞の該当記事を見つけ、新聞を閲覧してもらっている。こうしたサービスを有料化してゆくべきか否かといったあたりも今後の課題となるであろう。いわゆるニューメディアと図書館の問題はいくつもあるのだが、マスコミでほとんどとりあげられていないのは多くの人の興味をひかない為なのだろうか。まだ多くの図書館が外部電算データを取り入れていない為であろうか。
排架場所を少し変えたのだが、それほどの混乱は起きなかったのは幸い。恐らく多くの利用者は、「本の場所が少し変わったな」というくらいにしか感じておられないだろうな、と思う。10日間ですべての本を動かしたのだけれども。中には「長い休みがあっていいね」とおっしゃるお客さんもいたりするのであった。肉体労働をしていたことはなかなか想像できないだろうけれども、特別整理期間に何をしているかのPRもしてるんだけどなぁ。図書館について色々なことを多くの人に知ってもらうことからはじめていかないと状況は悪くなる一方だと思うが、今現在すでに随分悪すぎるような気がする。
- 6月13日(金)
特別整理期間の最終日。終業時間までに作業が終わらず、全員一時間の残業。ばたばたであった。
休憩時間にすごい話を聞く。学校の先生の母親が、「息子が学校で教えるのに必要だから」と、調べものに来たというケースが数件あったというのだ。大学生の母親、父親が息子や娘のレポートの資料を探すということが増えてきていることには気づいていたが、先生の母親というのは恐ろしすぎる話である。そんな先生に教わる生徒はいい迷惑である。この国はどこか完全に狂ってきているのではないか。「なんのために」という部分が欠けたまま、様々なことが進んでいるような気がする。
- 6月11日(水)
市長宛に匿名で閲覧室で学習をさせて欲しい旨の手紙が来ていたとのこと。差出人は女子高校生を装っているのだが、文面から推測するとどうも年輩の人らしい。疑問があるのであれば、まず図書館に問い合わせるべきではないかと思うのだが。それで納得がゆかねば、市長宛に手紙を出せば良いが、匿名である上、「この手紙と同じ文面のものを中日新聞社にも出しました」と脅迫めいたことも書いている。卑怯な人間というのはどこにでもいるものである。
閲覧室を館内資料のみの利用に限った理由については「一図書館員から見た日本」の第四回をご参照ください。
資料移動はほぼ終わった。見出しをつける作業が思いのほか時間がかかる。
親戚に不幸があったので一時間早退。
- 6月8日(日)
みんなだいぶばててきたが、今日も本の移動。参考資料は終わる。一般書も目途がついてきた。が、まだ見出しをつけたり、書架配置図を書いたりといった細かい仕事もいっぱいあるな、と終業時間が近づいて来たときに考えていたら、頭がくらくらしてきた。
- 6月7日(土)
大がかりな本の移動。私は参考資料を担当。大きな本が多いことと幅の違う書架を使うことで考えなければならない箇所が多く、動かしてから、やややしまった、分類が割れてしまうなどといった事態が起きる。もう少しで半日分の仕事がパーになるところであったが、妙案を思いつき、なんとかなった。
休み時間に先週の中学生の宿題のレファレンスの話をしていて思い出したのだが、ひどいのがあった。「教科書に載っている俳句の解釈を図書館などで調べなさい」というものなのだが、その俳句が、多くの本に載っているようなものでなく、俳人の自選集にも載っていなかったりするもので、解釈の載っている本があるのかどうかはなはだ疑問。いくつかの句誌を追ってゆけば恐らくあるだろうが。その宿題を出した先生は参考文献も何も指示していなくて、副読本のようなものがあるだけなのだ。教師用の教科書には解釈が載っているのだろうが、こんな宿題を出してたんじゃ、中学生が俳句を嫌いになってしまうのではあるまいか、と同じレファレンスを受けた国文科出身の職員と話したのだった。
- 6月6日(金)
昨日に引き続き、大がかりな本の移動。美術書のあたり、大きな本が多くて大変なのだが、棚の計算を間違えてやり直したりする。そろそろ職員に疲れが見えてくる。
- 6月5日(木)
特別整理期間二日目。
新しい本棚の搬入。本の大がかりな移動をする。どれくらい空けてゆくとよいのかが難しい作業なのであった。
あちこちが筋肉痛。
- 6月4日(水)
特別整理期間、はじまる。
本棚を空にし、本棚を動かし、本を移動させる。と、書けばこれだけのことであるが、なかなかの重労働であり、本をどこに収めるかは長年の経験がものをいうのである。明日は筋肉痛になることであろう。
- 6月3日(火)
明日から特別整理期間なのであれこればたばたなのに加えて、利用者多し。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]