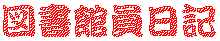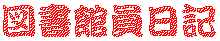
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 3月30日(日)
とてもばたばたした一日だった。年度末。利用者は多いし、「としょかんだより」をつくらなければならないし、明後日からのことをあれこれ準備しないといけない。
今日が最後となる臨時職員の大学生に図書券と観葉植物を職員から贈る。学校の先生になり、一人暮らしをはじめるとのこと。
春だからなのか、図書館に入ってくると同時に走り出す子供多数。注意をするのに忙しい。これからの時代、防音であぶなくない児童室を作るのは必須かもしれない。が、そこにはカウンターを置き、司書を配置せねばならないわけで、少なくとも二名の増員は必要となるのである。また走っても多少暴れても危なくない書架配置をするためには広いスペースが必要となる。文化行政にはお金がかかるのである。「図書館では走ったり暴れたりしないように」と、親がしっかりと注意し、となりについていれば問題はないのだが、もはや望める状況ではないように思う。猫を追うより皿をひけ、といった感じ。十年、十五年経つと、そうしたあまり注意されないで育った子供たちが大人になり、この国を支えてゆくことになるのだなぁ、としみじみ思う。ま、もちろんしっかり注意している親も子供をつれた来館者の三割くらいはいるのですけれども。
- 3月29日(土)
来週の受付のローテーションを作る。新しく受付に入る臨時職員が二人もいるし、正職員は一人減ることになるしでローテーションを組んでいるうちに頭がくらくらしてくる。土日が食事三交代となるし、ぐちゃぐちゃである。
引き継ぎもばたばた。
春休みの土曜日なので利用者が多い。長く延滞していた本をもう一度借りたいという利用者に、「同じ方がずっと同じ本を借りることになってしまいますので、一旦お返しいただき、しばらく後にまたお借り願えませんか」というと、「私でなく家族が読むのだ」と言うので(この方法を使うと同じ本を永遠に一家族が借りることができるようになる)、「ご本人がいらしていれば、構いませんが、常識の範囲内でご利用いただけないでしょうか」と言うと、「今来ていない。嫌な思いをしてまで借りたくない」と借りずに帰ってくれた。嫌な思いをしたのはこちらだと思うが、客商売なので仕方がない。相変わらず色々な人が来る。
館長が今日で最後。私が図書館に入ってから三人目の館長だが、実に良い人であった。議員から質問が出たり、利用者から苦情がくると、それだけで嫌がるものだが、それにめげず二年近く戦い、閲覧室、閲覧席を「館内資料閲覧者以外使用不可」にできたのはこの館長のおかげであった。また貸出冊数を5冊から30冊にできたのもこの館長が現状をよく理解し、いろいろなところに説明をしてくれたおかげであった。三年間ありがとうございました。
- 3月28日(金)
館内整理日。来年度(といってもあと4日だが)からのあれこれについて話しあう。大変そうである。
「図書館史」ができあがる。なかなか綺麗な本になった。役所の関係部署に配りにゆく。
引き継ぎやらなにやらでばたばた。
- 3月26日(水)
人員配置について主査と話しあう。4月にはすぐに小学3年生の図書館見学行事がある。ばたばたすることであろう。
来たばかりの館長と記念館から本館へ来る主査にいろいろ訊かれるのが私であろう、と考えると少し憂鬱になってくる。今度の館長も司書ではない。公共図書館の理念といったようなことを理解してもらえるかどうか。3年前に記念館に異動した主査は図書館のヴェテランであるから心配はないが、3年の間に多くのことが変化している。カウンターローテーション、資料の整理方法、電算機などなど。はじめのうちに質問が集中することもないとは思うが。
図書館だよりに載せる本の選書。この業務も若い職員に説明しながらゆっくりとしたいのだが、そういう時間さえなかなかとれない。
- 3月25日(火)
春闘。行政改革推進計画に載っていた一般職と専門職の異動の件についてが図書館について大きな問題。個別の人員配置の事柄については後に行うというようなことで、進展なし。組合の人は長時間かけて交渉を行うしかないとのこと。
朝、ブックポストへの返却本、本館が約850冊、分館が約250冊。休館日あけはいつものことだが、書架まで戻すのに二時間かかる。
人事異動の発表。館長がかわることになった。今の館長は司書資格はないが、図書館について理解があり、随分勉強もしておられた。閲覧席を館内資料閲覧者以外使わないようにしてもらうことができたのはこの館長のおかげである。次に来る館長はどういう人なのだろうか。ほかの異動は図書館勤務35年の主査が分館に、記念館に図書館勤務7年の司書が行き、記念館に3年間行っていた司書の主査が本館に、また退職する分館長の代わりとして庶務担当主査が1人本館に勤務。受付要員の正職員が一人減って、庶務担当が一人増える。庶務担当の臨時職員が資料整理などの仕事に就くことになる。利用者、利用冊数が増えているのに窓口の力を落とす人員配置となる。大きな配置変更なので、来月からしばらく大変な状態になるだろう。
- 3月22日(土)
職場に風邪が蔓延。三人寝ている。これで三日連続、カウンターのローテーション変更。
利用者多し。ばたばた。第四土曜日で春休み前なので小中学生が多かった。
三歳くらいの男の子が利用者用端末の置いてあるカウンターにのっかって、利用者用端末を触っていたので降りるように注意したところ、暴れて大変だったとのこと。母親は遥か彼方にいたそうだ。階段で遊ぶ幼児も多かった。両親揃って来ているのに、家族ばらばらで館内にいた。館内に託児施設が要るなぁ、この調子では。が、職員は司書さえ増えないのである。児童室も別にしてそこにもカウンターを置きたいところであるが、職員は増えないし、建物も建たないのである。利用者がどれだけ増えても駄目らしい。
- 3月21日(金)
乳幼児をほったらかしにして遠くまで行ってしまう母親がいた。一歳か二歳の子が紙芝居架の下やブックトラックの近くに一人でいるのはすごく怖い。乳幼児を抱えた母親だった人から以前いただたメールにブックモビル(自動車図書館)が近くに来てくれたのはありがたかったという内容のことが書かれていたことがあった。分館に近くない地域や団地などにブックモビルで行けると良いなと思う。職員が増えなければできるはずもないのだが。
読書感想文の宿題が出ている高校生から所蔵調査依頼。夏休み冬休み春休みに出るこうした宿題の図書探しだって考えてみれば司書と司書でない職員、長年勤めている司書と数年勤めただけの司書とでかなり探す時間に差が出ることに気づく。
- 3月20日(木)
朝から混む。レファレンスがとても多い一日だった。夕方にかなり空いた。
同僚が少し前に視察に行った千葉県の図書館の案内を読んでいると、市内在住在勤在学の方以外のリクエスト(予約)を断っているとのこと。私の勤務先はどこに住んでいる人でも旅行者でも貸出券を作り、他市町村の人にの予約も受けている。図書館のある隣町の人からの予約本が私の勤務先になく、その人の住んでいる図書館にある、などというケースがこれからは出てくる可能性もある。図書館のある町の人については住んでいる町に予約リクエストをしてもらう、というのはその町の図書館の蔵書構成にも関わるわけで、発展にも繋がるし、さらにまたこちらの仕事の量が多少減ることにもなり、悪いことではないかもしれない、と考えはじめたのだが、在勤在学の証明を現在登録時に確認していないので、登録更新をした後でないと、予約の制限をはじめるのが難しいのではなかろうかという気がしてきた。職員が多くないので、いちどきに全登録者の更新を行うのは無理である。館内整理日に相談してみることにする。
- 3月19日(水)
小学校の卒業式なので、低学年の子は朝から休みで、かなり利用者が多い一日であった。
年に一度の貸出文庫の打ち合わせ会。四十年ほど前に図書館から離れた地域の公民館に本を貸し出し、地域の人に本を利用してもらおう、とはじまった文庫なのであるが、貸出に携わるのは地域の奉仕の方であり、置ける本も少なく、さらにまた職員数が増えない為、図書館から本を持っていったり、古い本を引き上げてきたりといった業務ができなくなっているのである。
年度末で予算の調整などでばたばた。
- 3月16日(日)
14時51分に地震。レファレンスの真っ最中。はじめふわっと揺れ、後に縦揺れ。震度4とのこと。はじめの揺れで利用者をほったらかしにしてカウンターにもぐった私であった。先日カウンターの上の蛍光管が地震で落っこちてきたら怖いだろうね、と話していたばかりなのである。揺れがおさまってから、「大丈夫でしたか」などと言いながら、開架を回る。児童書架の上の分類表示用の看板が床に落っこちていた。子供に当たらなくてよかった。天井の空調の吹き出し口の部品が落っこちていた。下に人がいなくてよかった。閉架の本が飛び散っていた。開架の書架の耐震工事は先日終えたばかり。あの工事をしていなかったら、高い書架から本が飛び散ったのではなかろうかと思うとぞっとする。美術書や写真集が当たったら大怪我をすることであろう。この地震が起きた時間が一番利用者が多かった。
レファレンスが多い一日だった。
- 3月15日(土)
雨が降っていたせいか、土曜日にしては利用者が少なかった。しかし閲覧席はなかなか混んでおり、館内資料を使っていない人に、「申し訳ありませんが、館内資料の閲覧だけに限らせていただいております」と言ってまわる。この頃では学生はほとんど居ず、大人が多い。資格試験の問題集を持ってきて勉強している人、家計簿をつけている人、仕事をしている人等など。少人数のうちはさして困らないわけだが、この人たちの閲覧席利用を認めれば、学生が家から持ってきた問題集を認めないわけにはいかず、そうなれば三年前に逆戻りとなる(一図書館員から見た日本第四回をご参照ください)また、大人だけにしても月に延べ30人ほどいる。この問題が県内の他図書館でさして問題にされていないことが実に不思議だ。利用者が少ないのか、こういうものだ、と思っているのか。図書館の資料を使う人が使いにくい図書館って変です。使ってもらうために選んだ資料を使う場所がない状態で平気でいるとしたらどこかおかしな人です。資料を使いにくい図書館がもしあったら、苦情を言いましょう。もちろんそのほかのことについても、私の勤務先であろうと。納得のいかない、理由のはっきりしない事を改めてゆかなければ、勝手に変わってゆくことはまずないのですから。
子供が書架の真ん前に足を投げ出して座って長時間、本を読んでいる。その横に母親。「ほかの方がその棚をご覧になれないので、椅子にかけてお読みいただけますか」と注意にゆく。私の勤務先は椅子が多くない。というよりも、スペースが狭い。開館当初はすごく広く感じたのに、本が増え、書架が増えて、空間がなくなってきてしまった。増築するスペースはあまりないため、数億円かけて増築しても数年分の本で満杯になってしまう。購入した本をかならず1冊は保存するようにしてきたが、見直さねばならないかもしれない。新館建設となると、現在の館が分館になるにせよ本館として残るにせよ、職員がかなり増員しないことには利用者に迷惑をかけることになる。あれこれ考えると将来の暗さにめまいがする。
「資格試験の問題集は置いてありませんか」との問い合わせ。これは多分どこの図書館でも置いてない。借りていった人が空欄に答えを書いて返す例が多いためである。ボールペンや万年筆で書かれたら次の人はもう使えない。
このところ新刊文庫本の下半分が水につかってふやけて返ってくる例が二軒。いずれも返した人がそうしたのかどうかの確認をしなかったとのこと。もしかして風呂で読んでいるのではあるまいな、との疑惑。なんにせよ困ったことである。
- 3月14日(金)
契約方法の見直しについて役所から呼ばれ、副館長と出かける。図書購入の方法についての再検討が必要とのこと。念のためいくつかの図書館に問い合わせの電話をかける。書籍の購入方法は各図書館、まちまちの購入方法であり、いろんな悩みがあるようだ。独禁法適用除外の再販売維持商品であること、購入点数が多いため、購入時毎の契約が難しいことなどが問題となっているのだが、すべての問題をクリアできる方法を見つけた。少しでもおかしい点があることは直してゆくべきであると思う。
登録者が平日だというのになかなか沢山。
労働組合の話について複合施設で隣り合っている博物館からクレームがあったとのこと。明日また話し合わねばなるまい。憂鬱。
このところ、楽しい話題があまりない。
- 3月13日(木)
年度末でばたばた。契約書関係の確認。沢山ある。市報原稿の締切が明日。本を選ぶ。コンピュータのバグ修正依頼。利用者多し。
- 3月12日(水)
ブックポストへの返却本1300冊。棚へしまうのに午前いっぱいかかる。職員はしかし増えない。
「図書館史」の三回目の校正終了。
地元の自然観察をしておられる方から、学術資料の複写物の入手法について質問の電話。近くに大学図書館があり、一般に開放しているので、ここから相互複写依頼をすると早いのではないか、と答える。地元の自然科学研究雑誌の収集についても問われる。地元の逐次刊行物がいくつか寄贈されていると思うが、本来は図書館が購入すべきものではなかろうかとのご意見もいただいた。購入どころか、1部しかいただいていないけれど、もう少し貰えないだろうか、と数年前にあちこちに連絡をした記憶が蘇り赤面する。早速郷土資料担当と検討します、と答える。電話を切った後、いつも寄贈でいただいている逐次刊行物の編者であることに気づく。
終業後、職場集会。人員要求と専門職の異動について話し合う。見通しが明るそうでない。
- 3月10日(月)
ある都市の図書館友の会の方から私のホームページを見たとのメールをいただく。図書館に興味のある市民の団体とのことで、下手な図書館員より図書館に詳しい。私の無知をさらけ出さないかとびくびくしながら返信。
私の勤務先の街にもこういう団体があると良いな、と思う。図書館を使う人が図書館活動に参加してゆくべきだと思う。少なくとも一度も図書館を使ったことのない行政の上層部にゆだねておくよりずっとましである。司書が要るのか要らないのか、今の人数で適正だと思うか否かといったあたり、多くの利用者に尋ねてみたい。あ、アンケートを取るという手もあるな。しかし真に図書館を思う市民団体がある街はうらやましいな。
- 3月8日(土)
第二土曜日はやはり混む。人だらけで書架を通り抜けるのが難しいほど。本当はもっとスペースが欲しいところだ。建て直すといいのにな、と思うが夢のような話である。
発注業務。先週出版された本は多かったようで、選ぶ分量が大変であった。担当者すべてが新刊情報に目を通して、選書発注する。
- 3月7日(金)
利用者がとても少ない一日だった。第四金曜日が休館日なので、「なんか休みの金曜日があったなぁ」と、利用者が金曜を避ける傾向があるのか、金曜日は利用者が少ないのだが、今日は特に少なかった。毎日がこれくらいだと楽だろうけれども張り合いがないだろうな、と思った。それでも入館者500人、貸出冊数1200冊ほどなのだけれども。開館当初、ピーク時に700人くらいとの予想だったのが、常に700人くらいは利用者がある。利用者が離れぬよう、日々の仕事の手を抜かずに過ごしてゆかねばと思う。
組合に司書の資格、司書の専門性についての簡単な説明をメールで送る。
- 3月6日(木)
昼休みに専門職と一般行政職の人事交流についての話を職場でとりまとめる。組合についていくつかの点について不信感を抱いている職員が幾人かいる為(私もそう)、直接委員長に電話で問い合わせる。今一つ腑に落ちないが、回答を得たので、この件については一応了解、職員に伝える。さて、今後どうなることやら。
「図書館史」の再校を渡す。表紙の布の色を選ぶのが大変。先回、「蔵書目録 和装本編」の時も随分迷った。あまり見たことのない色を選びたくなるので困るのである。一体今までどれだけの本を見てきたというのか、見たことのない色の表紙の本なんてそもそもあるのか、と冷静に考えれば思うのであるが、見本布を見ているときには憑き物が憑いているかのような状態になっている私なのであった。あとから紙フェチのツツイストの人を変人よばわりできない私であるな、と思ったりもした。
柏書房が見計らい本を持って来館。年に数回、色々な出版社や巡回図書の会社が来る。以前は二、三十の会社が来ていたが、今は予算が多いので、ほとんど購入が済んでいるため、普通の案内には載らないようなものとか、絶版寸前のものを扱っているところだけに来てもらっている。一般書担当全員が受付を替わってもらい、あれやこれやと出版社の人と話しながらする見計らいはなかなか楽しい仕事である。
- 3月5日(水)
専門職と一般行政職の人事交流についての件、組合も反対姿勢のようだ。交渉によって撤回されるとも思えないが、少なくとも文言の変更の要求はしてゆかねばならない。当局が現状を把握しているか、といった点についても確認しておかねば。博物館の学芸員も怒っている。それにしてもあれやこれやと面倒くさい。
不景気になると、文化施設の縮小といった話がすぐに出ます、と図書館史編纂の為、二代目の館長にインタビューしたとき言われたが、まさにそう。「医者が資格なくしてできますか。図書館に司書が必要なのは当たり前のことです」と、90歳を過ぎたその人は激しい調子で言っておられた。その当たり前のことがほとんどなされていない。公共図書館に勤務している職員のうち、司書の比率は三割にも満たないのである。あれこれ考えていると、力が抜けてくる。
- 3月4日(火)
行革の説明会があったので、「勤労意欲の衰退している職員」とは一体どこの誰であるか。一般行政職が専門職と替わって手当もつかない土日出勤の職場で勤労意欲がわくのか、児童書担当などはすべての新刊に目を通しているのだが、そうしたことを何年も続けている職員と一般行政職が同じ仕事ができるのか、土日夏休みには入館者平均1500人、貸出冊数平均4000冊を越えるというのに現在本館に9人しかいない司書を異動させて、回ってゆくと考えているのか、と続けざまに一気に質問して疲れる。予想していた通り、当局から明解な返事はもらえなかった。再度確認をとってゆかねばならない。勤労意欲が衰退するようなヘンテコなおはなしである。
- 3月2日(日)
比較的利用者の少ない日曜日だったな、と閉館してから統計を見たら、入館者が1600人くらい、貸出冊数が4000冊だった。決して少なくはなかったのだが、最近は入館者が1800人、貸出冊数が5000冊くらいが普通になってしまっているので体が人の多さに慣れてしまったのかもしれない。
毎度のことだが著作権法上の複写できる範囲に頭を悩ます。図も当然著作物なわけで、その一部分しか取れないと解釈するのが正しいはずだが、参考資料に図はつきもので、またそれは複写されることが当然であると考えられて作成もされているように思われるわけで、調査研究の用に使われるわけでもあり、さして問題があるとは思えず、そのままの複写を利用者に認めたのだが、釈然としない感じが残る。著作権法の図書館での複写規定は恐らく日本全国どこの図書館でも厳密に守られてはいないはずなのだが、訴訟が起きた事例がないためか、実に曖昧な状態で運用されている。図書館によってまちまちだ、という苦情はあとを絶たない。文化庁に問い合わせて、できるだけ著作権者の利益を守る方向で私の勤務先は進んできたのだが、館によっては利用者の要望にできるだけ沿うように、と運用しているところもある。それはもうほんとにまちまちだろうな、と思う。電子媒体も増えてきているので、著作権法は整備されてゆくことだろうとは思うのだが、毎日悩まねばならないのは困ったことである。悩まないもの勝ちかもしれないのだけれども。
- 2月28日(金)
館内整理日。午前に教育長との懇談会。はじめてのことである。私と上司四人、それと教育長、部長の七人だが、八割くらいは私が話をした。職員の絶対数が足りない為、手が付けられずにいる仕事のあれこれについて、土日祝日夏休みにどのような状態であるか、本来図書館がどうあるべきかなどについて説明。教育長はずっと学校図書館に関わってきたので、公共図書館について理解していると認識していたが、知らなかった点がいくつかあった、と言ってくれる。が、しかし、行革をすすめよう、といった状況でもあり、簡単に人を増やそうと言うことはできない。それでも現状がわかったので、機会があるごとに話してゆこう、とのご返事。少し光が射してきたような気がする。
来年度の特別整理期間に書架を増やす予定であるので、配置を検討。開架自体のスペースに限りがある為、どこに書架を置くかは限られている。どう置いても暗く狭くなりそう。閲覧スペースも減ってしまう。外に閲覧用の椅子を置こうか。雨降りは困るなぁなどと話していると、館長が「テントを張れば雨が降っても大丈夫」と妙案を出す。「中で暖をとるのに火鉢を置いて一酸化炭素中毒になったりすると大変ですね」と私が言う。私の勤務先での会議は話を円滑に進める為の冗談が少し多いかもしれない。
- 2月27日(木)
暖かくなると、いろんな人が来館なさる。毎年何度かいらっしゃるので、いつの間にか覚えてしまったりもする。良くないことであるが。今日、久しぶりにいらした方がいたのでした。その方は法律について勉強をなさっているらしく、「地方公務員法の何条には何が書いてあるか。言ってみろ」とカウンターで職員に尋ねたりする。大抵は答えられなくて叱られる。「法令集の書架にご案内しましょうか」と言うと、「わしは知っておる。公務員の癖にそんなことも知らんのか」とご機嫌を損なうことになる。気むずかしいところのある方なのである。たまたま知っていたりすると、「ほお、本当にそうか」と疑われたりする。「前に見たこんなような絵の載っている画集を見せてくれ」というお尋ねもよくなさる。書名著者名出版社名判型、何も覚えておられない。ここで見たことがあるとのこと。開架スペースが狭い為、美術書は半年に一度、開架と閉架のものを交換しているため、開架でご覧になられたものが閉架に入ってしまっていることもままある。これではないか、とあれこれ出してくるのだが、「こんなもん、一般の人間にわかると思うのか。一般の人がわかる絵は例えば・・・」と絵画についての講義をはじめられる。混んでいるときだとかなり大変なのだが、今日は比較的利用者が少なく、それほどご気分を害することなく、ほぼ目的のものを借りていっていただくことができた。時折、この方から鋭いご指摘をいただくことがある。それは資料選択についてのことであったり、排架方法についてのことであったり。気むずかしい、ややこしそうな方だからと言って、無闇に敬遠することもない、と私は思う。
この方が帰られた後、小学生の宿題調べや、新聞の記事検索など時間のかかるレファレンスがかなりあった。ばたばたの一日だった。
- 2月26日(水)
時々ある質問に、「私が前に借りた本を教えてほしい」というのがある。今日来た人は、「返却台に置いてあった本だったので、どこの分類かもわからないのだけれども、哲学のような本だった。随分前に借りたんだけど、読む時間がなくて返してしまった。書名も著者名もいつぐらいに出版されたのかも出版社も全然わからないのだが、わからないだろうか」とのこと。わからなかったのでした。書名の断片でも記憶にあればなんとかなるのですけれども。誰が何を借りたかという記録はプライヴァシー保護の為、図書館では一切残さないようにしているのでした。
幼児の野放し状態が多い一日だった。大声で歌を歌う女の子がいたのだが、親は近くにいない。遠くにいたのだろうか。「お歌が上手だねぇ。だけど、図書館では歌っちゃいけないんだよ。ご本を読んでる人の迷惑になるからね」などと、注意をしにゆく。
床に変なものが落ちているので拾い、ゴミ箱に捨てる。「変なものだけど、なんだったんだろ」とカウンターの職員に尋ねてみると、「さっき靴の中から何かを出して捨てていたお客さんがいた」とのこと。子ども連れの若い母親が子どもの目の前で捨てていたんだそうな。そういうのは現行犯で注意をすべきだ、と職員に注意する。受付が混んでいた時間で、すぐにその母親はどこかへ行ってしまったとのこと。すぐ近くにゴミ箱があるのに公共施設の床に捨てるとは大したものである。
「注意をしない」、という苦情が時々ある。カウンターが混んでるときはしかし無理でもあるのだ。貸出返却で手をとられている間に沢山来ている子どものうちから騒いだり走ったりしている子どもを見つけて、空いた時に母親に注意に行くのだが、注意に行く前に帰ってしまったり、別の子どもの母親を間違えて注意したりと、あれこれあったりする。パトロールをしないといけないような状態になりそうだ、と早めに職員を呼ぶと静かだったりする。職員に余裕が欲しい。今日の苦情はこんなのだった。「どうして子どもを叱らないのだ。わしは以前、寝ないでください、と恥をかかされた。どうしてわしにだけ恥をかかせるのだ」だって。他の職員が説明したのだが、なかなか時間がかかったようだ。以前、この人へ注意をしたときの仕方に問題もあったのだろうが、「○○君は叱られないのに僕だけ叱られる」と60歳を過ぎて言う大人はなかなかかわいいかもしれない。
- 2月25日(火)
年度末が近いのでばたばたしている。予算を使いすぎないように工夫をせねばならないし、来年度の人員配置案の意見を参考までに、と上司から尋ねられ、ここだけはどうしてもなんとかしておいてもらわないと、四月にエラいことになります、といったようなところを強調しておく。一般書、児童書、郷土資料、視聴覚資料などに担当が別れているわけだが、過去一度もその担当についたことがない人ばかりになってしまうと春に仕事がすすまない、とか、手一杯仕事を持った人が新たな担当に説明をしながら作業ができるかどうか、といったようなややこしい話をする。人員にまるで余裕がない上、四月五月に小学生の見学があるので、このあたりがしっかりしていないとものすごいことになるのであった。せめて毎日二交代でご飯が食べられる程度の人員配置をしておいてもらえたら、と思うのだが。
小さな子どもが電話に出るのも困るが、あまりに耳の遠いご老人がお一人でいらっしゃるところで、電話に出ていただくのも考えものだと思う。とてつもない声を張り上げて、「とーしょーかーんでーすーけーど、まーたーおーかーけーしーまーーーーす」と言うと、「どちらさまですかのぉ。だーれもおらんのですが、おつたえしますが」とおっしゃるのだが、お伝えしていただけるような状況ではなかったりすることがしばしば。ま、しかたがないといえばしかたがないのですけども。
- 2月24日(月)
名古屋の某デパート内の書店に一ヶ月ぶりくらいに行って驚く。本が減っていたのだ。日本の現代文学が充実していたのに、本棚から随分作家がいなくなってしまっている。力を入れて揃えているらしい幻想文学の棚はそのままのようであったが、私の買おうと思っていた本が数冊なかった。哀しい。もしも上からのお達しで棚を変更させられたのだとすると、担当者はかなりつらかったことであろう。ここは開店当初、マンガが一冊もなく、活字の本だらけで圧倒されたのだが、柔らかめの本が徐々に増え、ついに日本の小説は半分ほどになってしまった。豊田市の某デパート内の本屋ができたばかりの時の充実度もすごかったが、一年ほどで様変わりしてしまった。地域の問題なのか、出版状況の問題なのか、書店の方針の問題なのか、いずれにしても残念なことである。思えば書店回りマニアの傾向がある私である。もしかすると本よりも本屋、古本屋が好きなのではないかと自分で思えるときがある。
- 2月22日(土)
来年の職員体制の予定を上司からちらと聞き、少し血圧があがる。が、しかし、そのように本当にするのであれば、利用者に迷惑がかからないように運営ができるように全体を見直さねばならない。本決まりになる前にあれやこれやをしておかねばならない。このところろくな話がない。
近くの小学生がまた図書館についての質問にくる。土日に来られると困るぞ。学校に苦情を言わねばならぬのだが、第4土曜日は誰もいなかったりする。しかし学校週5日制というのは一体なんなんだろ。
レファレンスが相変わらず多い。貸出も4500冊ほど。ばたばたである。
- 2月21日(金)
ひどい延滞の本を1冊返しにきた利用者。まだ1冊借りている。延滞図書が1冊でも貸出券に残っていれば貸出をしないので、当然この本も返却期限を過ぎている。「もう1冊借りておられますね」と言うと、「ええ」と簡単に答える。「期限を過ぎている図書があると貸出券を使うことができませんので、お早めにお返しくださいね」と言うと、「ええ、知っています」とのこと。何をしにきたのだろうか、と思う。
図書館史の再再校が来る。また校正をせねば。
来春に行う小学三年生の図書館見学の打ち合わせがある。来年で五度目であるが、利用者が増え過ぎて、開館時間に沢山の児童を連れて書架を回るのがむずかしいため、来年からは中止することも考えてはどうか、と私が半年ほど前に言い出して、検討をしたのだが、若い職員が皆、早出をしてでも実施すべきだ、と言うので行うことになったのである。勤労意欲の減退などどこにあるか。図書館のことを書いたのではないにしても本当に無神経である。と、昨日のことを思い出して腹が立つ私である。さて、この見学、図書館に来たことのない子どもに、図書館では君たちがどんな本を借りたかを先生にも親にも教えないんだよ、とか、閲覧席は図書館の本や新聞を閲覧する為の席だから、家から持ってきた問題集を解くだけの為に使うと図書館の資料を見たい人の席がなくなっちゃうからしないでね、とか、開架だけじゃなくて、閉架もあるんだよ、などといった図書館のいろはを説明するとてもよい機会なのである。今日は代表の先生と日程についての話し合いだけだったが、各学校の先生が出席する打ち合わせ会ではいろんな先生がいて、システム的にできない、ほかの利用者に迷惑がかかる提案などもあり、説明するのだが、わかっていただけなくて紛糾したりするので面白かったりする。先生には日本の未来を背負う子どもたちを素敵な大人に育ててもらいたいと思う。図書館を使って自分の頭で物事を考える子ども、自分の好きなことは人はどうであれ好きと言える子どもが増えると良いななどと思う。
- 2月20日(木)
発注業務をする。って、毎週しているのだけれども、この日記に書いたことがなかったような。先週に出版された本のリストを見て、類書があるかどうか、高額でも購入しておくべきかどうかなどといったことを検討しながら、選んでゆくのである。頭の中にある程度現在の蔵書構成が入っていないとその度多くの本の検索をせねばならず、経験がものをいうのである。
行革の推進計画とやらができあがったとのことで、来月説明会があるので目を通しておくようにと言われ、ぱらぱらと見ていると、専門職と行政職の人事交流を行う予定があるようなことが書かれている。そこには専門職は長い間人事異動がないので勤労意欲が減退しているところもあり云々と書かれている。平成10年度実施とのこと。平成10年度に異動のあった専門職は勤労意欲が減退した職員ということか。失礼な話である。専門職といったって医者や看護婦、保母、運転手を行政職に変えることはできないわけで、法的に専門職を必要とされていない図書館司書博物館学芸員あたりを指しているのではないかと思われる。どうして司書が要るのかなどと、図書館を利用したことのない職員からしばしば質問があるそうだし。それにしても私の勤務先は利用者が多すぎて勤労意欲を減退させている暇もないぞ。行政職が異動で来れば土日出勤で手当がつかず、利用者だらけでわからぬことばかりを訊かれて勤労意欲が減退するであろうことは容易に想像がつくが。文化施設はぐらぐらの土台の上に建っているのだ、としみじみ思う。
- 2月19日(水)
小学三年生が図書館についての質問にくる。市内の三年生を対象に毎年春に図書館見学会をしているのであるが、社会科の調べ学習で来たとのこと。春に説明した事柄も訊かれる。事前の連絡もなにもないし、学校側はもう少し配慮があって良いのではなかろうか。図書館というところは暇に違いないと思っているのかもしれない。
新刊案内に載せる本を選ぶ。私がとりあえず選んだあと、「これとこれとこれとこれとこれは変えたほうがいいかもしれない。選んでおいてくださいな」と若い職員に指示。20冊選ぶのだが、新刊でもあり、読んでない本のほうが多いわけで、中身をぱらぱらしながら唸るのである。本のことをある程度知っていないと本を選ぶという作業はできないのである。
机があまりに汚いので整理をしようとしたところ、抽出の中からわけのわからないものがいっぱい出てくる。持ち主の現れなかった落とし物の消しゴム、まつぼっくり、黄ばんだメモ用紙などなど。捨てるのがもったいなくてなんとなくとっておいたものであろうが、どうしてとっておいたのかまるで想像のつかないものも沢山あった。長くとっておくと捨てるのがもったいなくなるのだが、今回は思い切ってあれこれ捨てた。昔の登録用紙や図書館でくばっていた栞などはとっておいたために今回「図書館史」を編纂するのに役だったが、まつぼっくりは役にたたないことであろう。
- 2月18日(火)
なんだか疲れた。終業後の組合の職場集会。90年の職員数と現在の職員数が同じで、貸出冊数、予約冊数、レファレンス件数、複写件数がみな倍近く増えているのに、職員増員どころかヴェテラン司書の代わりに事務職員が配置されることについて話す。が、しかし、近隣図書館には司書が配置されていないのにこのまちでは司書で運営しているのだが、そうでなければならないのかとか、行革をすすめようとしている現状では難しいといった話からはじまってしまうのであった。暮れの話が執行部内でどうやら話し合われていなかったらしいともわかり愕然とする。今日来た人たちがたまたま聞いていなかっただけならば良いのだけれども。
もちろん、ここ数年間での利用の質量の増加と本庁の土曜日完全閉庁の影響をしっかり説明して職員要求を館長等がしてきてくれたのかどうかが現在の状況を招いているわけではある。が、しかし、現状でもかなりきついところへもってきて、正規の司書の減員をされるという事態に対応してくれる気があるのかないのかわからない組合はなんだかなぁ、なのであった。どうなることであろうか。執行部で話し合うとは言ってくれたのだけれども、かなり厳しいことになるであろう。何やら政治の匂いが見えかくれするのであった。私は政治は面倒だからかかわりたくないというわがままな性格である。
職員が増えないとなれば、視聴覚資料の貸出をやめるか、他市町村の利用者に制限を加えるか(登録不可とか予約不可)、昼の一時間、窓口を閉めるか、それくらいしか手だてがなくなる。
郷土資料のレファレンスが多い一日だった。ほとんどが閉架に入っているので、以前はそれほど利用されていなかったのだが、閉架の存在、郷土資料の存在が口コミででも広がったのであろう。「○○について調べたい」という形での訊かれ方がほとんどなので、慣れた職員でないとどんな資料があるか見当がつかない。
藤沢周平氏が亡くなってから、氏の本の貸出予約がとても多い。本棚はがらがらである。
- 2月16日(日)
大失敗をする。ある詩人の本について書架案内をし、「この本にはほとんどの主要な作品が入っているのですね」と訊かれたので、「確か亡くなってから編まれたと思います」と答えたところ、「まだご健在ですよ」と言われてしまったのでした。以前にも電話で所蔵の有無を問われて、作家を殺してしまい、ひどく叱られたことがあったのに迂闊な私は平謝り。どうも80歳を過ぎた人は死んでしまっているかのように思っているところが私にはあるので危険なのでした。反省。
所蔵調査、レファレンス、コピーがものすごく多い一日。日曜日だから仕方がないのだけれども。書架の間が人だらけで、案内をするのも大変なほどであった。
- 2月15日(土)
普段の土曜日よりも利用者が少なかったな、と思い、記録を見てみると、入館者は約1200人、貸出は3500冊ほど。昨年度の土曜日の平均値くらいなのであった。このところ混みすぎているので、感覚が馬鹿になっているようだ。
- 2月14日(金)
昔の統計を調べていたら、7年前には貸出冊数が半分以下、司書が今よりも一人多かったことに気づく。コピー件数などは三分の一だったのだ。体がエラいのも無理はない。
今月は予約電話の当番である。昔から腹が立つのが、ものが言えないくらいの小さな子どもが電話口に出る家である。「○○さんのお宅ですか」「そうだよ」
「図書館です。こんにちは。お母さんはいらっしゃいますか」「だれ?ぼく××くん」「図書館だけど、お母さんはいるかな」「だれなの?ママァ、知らない人から」「だれなの、ちょっとまってね」(と、遠くで何やらしている)「もしもし」「図書館ですけど、こんにちは」「あ、なぁんだ」などというとんでもないやりとりをしなければならぬ家が年々増えている。無礼である。「失礼しました」のひとこともないのである。電話は誰からかかってくるかわからないのだから、まともな対応のできる年齢まで子どもにとらせるべきではない、と私は思う。天皇陛下や総理大臣からかかってきたら、どうする。ってかかってこないだろうけれども。私など、小さい頃、「電話機をさわるとビリビリくるから触っちゃだめだよ」と親に言われたのを真に受けて、小学五年生まで触ったことがなかったぞ。かけるときも「○○君のところにかけます」と高校生の時までは親に断って使っていたものである。親に知られてまずい電話は公衆電話からしたものである。自分の名前もまともに言えないような年齢の子どもに電話をとらせて平気でいる感覚が普通になるのだろうか。そのまま大きくなった子どもは街なかどこでもかまわず電話をかける立派な大人になるのかなぁ。なるだろうな。ヤだな、と思う私である。
- 2月13日(木)
返却資料が多い。土曜日並み。貸し出した地図帳にインデックスシールをつけて返した利用者がいたとのこと。尋ねたら、「もともとこうなっていた」と言われたそうで、そのまま帰してしまった由。インデックスシールは20ほどもついており、普通は前回の返却、貸出時に気づくはずであり、借りる際に利用者も気づかねば不思議なわけで、今日返した人が限りなく怪しいのであるから、一度事務室にお通しして、詳しいお話を伺った方が良かったのだよ、と対応した職員に一言言っておいた。以前、ページの三分の二ほど切り取って返した利用者がいて、「借りたときからこうだった」と頑なにおっしゃっていたのだが、なんとか弁償していただいた。その方は入れ墨を入れていたので私も上司も少し怖かったのだけれども、ゆっくりと尋ねたところ、「実は人に又貸しをしたらこうなって返ってきた」とおっしゃったのであった。ページが三分の一になってたら貸す時に気がつくってば。しかしこうした例外的事例が増えてくるとそれに対応するマニュアルが必要になるのだろうか。困ったことである。
図書館史、再校終了。
- 2月11日(火)
朝、ブックポストに返却された本多し。書架に戻す作業が開館時間前に到底間に合わず、続けていると利用者だらけで書架の行き来も大変なほど。返却本を載せるブックトラックは次から次へと返される本でいっぱいになっている。昼から雪が降ったため、客足がやや鈍ったが、朝の勢いが一日続いたとしたらエラかったことであろう。
面白いレファレンスがあった。時代劇の主人公とその時代背景について知りたいというもの。三田村鳶魚の著作になにかあったな、と見たが、その利用者の調べているものと一致しなかった。水戸黄門や、鬼平=長谷川平蔵は実在の人物で本も何冊か出ているので実際と小説の違いを調べやすいが、あとのは調べるのが大変だろうな、と思いながら、時代劇の原作の小説本と歴史関連の辞書の場所へ案内する。あとになって「新潮日本文学全集」に架空の人物まで載っていたことを思いだし、案内した。
- 2月9日(日)
利用者多し。中学生に宿題が出ているようで、調べもの多数。返却図書を利用者に本棚かブックトラックまで返してもらっているのだが、本棚が一杯になってきているため、沢山の人がブックトラックに載せるのは仕方がないのだが、ばらばらぐちゃぐちゃな本が悪くなるような置き方をする人が随分いるのが困りものである。
小口を見るとページが沢山折れているので、はてどうしてこんなに折れたのだろうか、と本を開けてみると折るつもりで折ってある。しおりの存在を知らないのかもしれない。しおり代わりにティッシュがはさんであったり、レシートがはさんであったり、手紙がはさんであったりということもままある。古本屋では時々お札がはさんであったりするらしいが、私の勤務先ではまだお札ははさんでない。洟をかんだティッシュが本の間から発見されたときにはのけぞった。洟をかんだティッシュといえば、時折書架になにげなく置かれていたりもする。いろいろな人がいるぞ。傍線が引かれている本も多い。鉛筆ならば、消せるからまだましだが、ボールペン、マーカー、マジックで引いてあるものまである。そういう読み癖のある人は図書館の本を読む際、充分注意していただきたいと思う私である。
- 2月8日(土)
利用者多し。小学生が「この雑誌に僕の写真が載ってるんだよ」とカウンターで見せてくれる。「へえ、すごいね」などと少しやりとりしていると、「僕、ずっとこの雑誌続けて借りるんだ」と言う。「こらこら、君がずっと続けて借りたら、ほかの人が借りられないじゃないか」と言うと、「だめなの」と訊かれる。丁度空いているときだったので懇々と説明する。
複写多し。いつものことだが、著作権法上、とれないものが多々ある。「著作物の一部分」しかとれないから、写真全部とか図全部はとれないのである。が、しかし、まともに解釈すると執筆者の名がしっかり入った(入ってなくてもそうだけれども)百科事典の一項目まるまる取ることができないわけで、図書館によって対応がまちまちだったりするらしく、「あそこの図書館ではとってもらえた」などというトラブルもしばしばなのである。この法律なんとかならないものか、とずっと思っているのだが、自館での基準を作る以外はなんにもしていなかったりする私である。
- 2月6日(木)
終日「図書館史」の校正。
- 2月5日(水)
「○○という本は今ありますか」と、よくある質問。検索すると貸出中なのだが、全集に入っているかもしれないと調べる。全集にもない。「貸出中ですので、予約をしていってください。返ってきたら電話で連絡します」と言うと、「××図書館に予約をしているのだけれども、早く読みたいと思ってないかな、と来てみた」と言う。気持ちはわからないでもないが、××図書館の予約処理の手間のことをまるで考えていない。どうしても早く読みたいのであれば、まずあちこち探してみるべきだと思う。
「図書館史」の校正をする。
- 2月4日(火)
レファレンスが多い。名字から家紋を探したいというのがあった。なぜだがよくあるレファレンス。名字からの確定は無理なのですけども、と説明する。中世の画家のそれほど知られていない絵を見たいとのこと。日本の美術作品についてはどの全集に載っているかを調べるレファレンスツールが日外アソシエーツから出版されているのだが、外国の作品についてはまだないので、書架にある美術全集をひっくり返すが、ない。他館へレファレンス依頼をしても良いのだけれども、急ぐようならば、県立図書館か名古屋市鶴舞図書館に直接行かれた方が良いと連絡。解明できないレファレンスは気分がすっきりしない。
4年延滞していた利用者が本をなくしたので弁償する、と来る。4年ともなると督促状の郵送料も馬鹿にならないのだが、郵送料や電話料金は徴収していない。事務がひどく繁雑になるからだ。ともあれ、資料の代金を弁償してもらう。
貴重な郷土資料は事務室内で見てもらっているのだが、どうしてかと訊かれる。「開架の閲覧席で見てもらうと、盗難の恐れがあるのです」と答えると、「そんな人はいないでしょう」と驚かれたのだが、困ったことに実例があるので、説明する。
- 1月31日(金)
県外出張に行った職員の話を聞いてめまいがした。数年前に10人ほどの司書しかいなかったのに新館を建てるため、3年で30人の職員を増やした図書館を見学にいったのだそうだ。教育長が理解と力があり、日本図書館協会にいた人を館長にして、新館計画を練っていったとのこと。毎年10人ずつの司書募集というのはすごすぎる。私の勤務先では30人どころか3人でも難しいぞ、と思う。
週末で月末なので受付ローテーションと図書館便り作成が重なってばたばた。も少し前にとりかかっておけばばたばたせずにすむわけだが。
- 1月30日(木)
先日の館内整理日に「21世紀に向けて」というテーマで、図書館の今後について出し合った意見を整理したプリントをもらう。分館や大規模な本館建設を、との意見が若い職員から出されている。当然考えねばならぬ事柄である。が、しかし、新しい建物が建つからといって、職員がそれほど増えるわけではない。多くて二、三人の新人、悪くすれば、現状のまま、異動、或いは臨時職員、或いは事務職員、と今までの経緯から想像すると憂鬱になる。新しい建物にはヴェテランの司書が必要なのである。そこにヴェテランを出すということは、今ある館に多くの本職の司書が居なければならず、新館建設前に、ヴェテランが減っても運営ができるような状態になっていなければ、すぐに困るのだ。それを思うと新しい建物を建てるという話を聞いてすぐに危険だ、と感じてしまう。心配性なだけだろうか。
市内施設とのオンラインの話を館長とする。数年前から役所ではオンラインという言葉が流行っていて、多くのことがオンラインで可能となると考えられている。他の図書館とのオンラインにより、相互貸借が簡単になる、との話に、「FAXもオンラインですし、こちらが検索しなくても相手館が検索してくれます。複数の資料の貸出申込が電話代10円でできます。オンライン検索だとこちらが調べねばならず、電話代は随分かかります」と言って、なぜか嫌われたことがあったが、オンラインで必要とするデータそのものが取り出せるのでなければ、例えば、図書がある館で返却済みとなっているのをオンラインで見ることができたからといって、その本が実際に本棚にあるかどうかはわからず(開架では時折盗難等で本が行方不明となる)、オンライン検索後、ひとつの動作(オンラインによる予約、所蔵確認後FAXで予約申込)を経ねばならず、その後、申し受けた館では本棚を探し、本を郵送せねばならないわけで、相互貸借について電算オンラインはそれほどの意味をなさないのである。今の館長はすでにこのことは理解している。ほかに何ができそうか、どういう形でのオンラインが良いのだろうかといった内容について話す。インターネットのwebページを持つ予定があるので、そこから検索画面に行けるようにすれば、市内施設だけでなく、どこからでもオンライン検索はできるようになるから、それで良いのでは、その為にはプライヴァシー保護を考えねばならず、サーバー機が必要だと電算屋さんが言っていたと話す。オンラインで役に立ちそうなのは郷土資料目録をそのまま入れたり、郷土資料そのものを入れることであろうとも話す。いずれにしてもお金のかかる話。
- 1月29日(水)
なんだかばたばた。平日なのにヘンだな、と思っていたら、15日に貸した本の返却期日が今日であった。相変わらず、大学生の宿題が多い。無理だってば。書架案内は思えば随分増えた。書架まで一緒に行き、本を探す。これだけのことを以前は甘く考えていたというか、開架の棚の配置図を見せて、「ここですよ」と言っていた職員がいた。これだけでは目的の本を探すのは困難なのである。書架まで一緒に行くことを徹底するだけで、利用者からの質問は増えてくるのである。配置図を見せての説明よりも時間は少なくてすむ。簡単なことが見落とされていたりするのである。
- 1月28日(火)
朝、机の上に謎のメモがおいてある。暗号のようであった。日曜日に休みを取った私への意地悪であろうか、と近くにいた職員に問うと、風邪をひいていた職員が利用者から受けた依頼だという。なんとか解読するとある洋雑誌を某国立大学の図書館からコピーして欲しいとのこと。依頼人は学生ではないので、入手手段は普通公共図書館経由くらいしかないのだが、実は私の勤務先の近くの街に大学があり、一般開放もしている為、大学間相互の方がしっかりしているので入手が早いので、できればそちらでお願いします、と今までは専門雑誌の相互複写を、ま、悪く言えば利用者をたらい回しにしてきたのであった。なぜ、そんなひどいことをするのか、と言うと、相互複写依頼はかなり手間がかかるのである。一般の人だけに限定しても、企業の研究者などは随分多い。さらに学生からの依頼をどうするのか、という問題もあり、学生は通っている大学図書館へ(これは当然だと思うけれども)、一般の人は公開している大学図書館へ行っていただき、私の勤務先の仕事を増やさないようにしよう、としてきたのであった。これはおかしい。職員が増えないことが前提になってるのがまずおかしい。が、増えないのである。それどころか司書を減らそうとしているのである。職員数に余裕があれば、相互複写くらいなんということはないのだ。が、しかし、仕事を増やさないようにと考えるよりも、こういう仕事もしているのだと宣伝する方が前向きだ(今までだって前向きであり、レファレンス、予約などの数が随分増えていて、これだけの仕事をしているのだ、と説明すると、そこまでしなくても良いなどと言われたりするのであった)。折角の機会であるから受けてゆこうではないかと、職員間で少し話す。
さて、今回の件。某国立大学の図書館に電話をかける。なんだかとても横柄で威張った人が出る。まず公立図書館への相互複写の可不可を尋ねる。資料があれば可能とのこと。利用者が調べたのでそれは間違いないはずです。ああ、でもこちらでも確認しないとわからないから。料金はおいくらですか。一枚35円と送料、現金払いで先払い(ですもなにもない)。申込書をFAXで送ります。利用者に再度確認してから申し込みます。とりあえず申込書を送ってくださいますか。なんだまだ確定ではないのか確認してからもう一度連絡して。大抵は申し込むことになりますので、申込書だけ送っておいてください。こちらも沢山複写の仕事があるから申し込みが確実になってから連絡してくれないと送れない。はいわかりました。ではまた連絡いたします。
なんだなんだ。私は先払いで良いかを利用者に確認して、構わないということであれば、申し込むのである。そうでなく、ほかにいろいろ確認することがあるにしても申込書をFAXするのがそんなに大変なことなのだろうか。国家公務員にはすごいのがいるなぁ、としばし感動の後、利用者に確認。ところで、個人からの申し込みはできなかったのでしょうか。はぁ、頼んでみたのですが、図書館経由でなければできない、と言われたのです。ま、そうだろうなぁ、と思う。これまたものすごい数の個人からの複写依頼が来ては大変なのである。国立大学の図書館の職員数は多いところもあるような気がするが。ともあれ、先払いでも構わないとのことなので、再度大学図書館に連絡。書式がものすごい。同じ事柄を三枚書かねばならない。きっとコピー機がないころの名残であろう。役所は簡単に書式を変えられないところではある。やはり大学との相互複写など受けたくないぞ、と個人的な感想を持ったりもした。しかし、利用者は図書館を介さねば入手できないのである。大学や研究機関との相互複写は公共図書館にとって必須の仕事なのであると改めて認識した。それにしてもなんと貧しい現状であろうか。知の自由にほど遠い。
最近の資料は電子テキスト化が進んでいるのでインターネットからの入手が可能であるが、バックナンバーの遡及入力はなかなか進まないことであろう。今回の利用者の検索手段はインターネットからであったようだ。インターネット利用により、図書館に対する世間の認識が変わってゆくのだろうか。あまり期待できないが。
- 1月25日(土)
貸出返却とも約5,000冊。何をしているのやらわからぬほどの混み方。大学生の宿題も多い。書架の間に人が多すぎて、目的の場所になかなか行けなかったりもする。若い職員がJ-BISC(国立国会図書館所蔵図書目録のCD-ROM)を使って利用者と受け答えをしていたのだが、「なさそうですね」と答えたので、「NDC(日本十進分類)でも調べてみた?」と問うと「調べていない」とのこと。最近は書誌データを購入していることもあって、困ったことにNDCになじんでいない職員が増えている。大学で習った知識さえも何年か経って抜けてしまっているようだ。職員研修を行いたいのだが、終業後くらいしか時間がとれないし、研修用プログラムを作ろうとすれば、残業をせねばならない。ま、残業すればよいのだが、自己研修をしなさい、と言って済ませてきたのである。昨日の研修で名古屋市の職員研修の話を聞いて、大人数の研修ができることを羨ましく思ったことを思い出した。職員数がぎりぎり以下だといろいろなことに当然余裕がなくなり、それが直接利用者にはねかえることにもなる。職員数ばかりやたらに多くて余っているというのもかんがえものだけども。
- 1月24日(金)
館内整理日。他館からの借り受け資料を貸し出す際に利用者に書いてもらう帳票が面倒なので省略できないかと提案。「よそから借りた貴重な図書を借りるのだから、利用者にその自覚を持ってもらわねばならない。多少面倒でも書いてもらうべきだ」と、ヴェテラン職員が言ったのに一瞬愕然とするが、ま、一理あるとも言える。あれこれ意見が出て、結局来年度から簡略化することが決定。利用者がすべての図書を責任を持って返すという自覚があるわけではないという現状が問題なのではある。当然、他館から借り受けた資料は自館の資料より以上に大切に扱っていただくよう、お願いはすべきでもある。ただ、利用者に自覚云々という司書の感覚が邪魔をして相互借り受けが進んでいかなかった過去が私の勤務先にはあり、他館ではもしかするとまだ、そういうことがあるかもしれない。絶版の本は図書館間借り受けか古本屋を大探しするかしないと読めないのである。いくら古本屋を探しても見つからないことはよくある。利用者が読みたい本を読めるという状況を作ることは図書館にとって当たり前のことなのだ。ほぼ達成できたのだが、実は途方もなく難しく、長い道のりだった、としみじみ振り返って思ってしまった。しかしまだまだ世間の図書館専門職に対する関心認識は薄く、多くの市町で行政は司書を図書館に置きたがらないし、ヴェテランの司書を市役所の他の部署へ異動させることもしばしばなのである。国中の図書館の現状が変わらねば、私は安心して誇りを持って司書の仕事をできないとさえ時々思う。
内規集については来月までに再確認をすることに決まる。
午後、愛知県内の主任主査級の図書館員の研修に出席。元新聞記者の大学教授の記者時代のお話。大変面白かったのだが、図書館員の研修としての意味は何かあったのかと疑問に思う。まるで図書館の世界は天下泰平であるかのようだ。
- 1月23日(木)
今日もまた大学生多し。大学生の息子を持つ母親が宿題関連の図書を探してもいた。今シーズンは特に多い。今後ますます増えるとしたらヤだな。どうしたら減るのだろ。やまだ紫の「お勝手に」(毎日新聞社)に、「腐ったような人間が増えている」というフレーズがあったのに全く同感の今日この頃である。
恐ろしいことに内規集というものが今まで私の勤務先に存在しなかったため、案を作っている。明日の館内整理日に皆で協議する予定。
- 1月22日(水)
大雪。渋滞が嫌いなので単車で出かけたら、数度転んだ。左手にひどい打撲。開館前に入り口の雪かき。
雪だから利用者が極端に少ないかというと、そうでもないのが私の勤務する図書館の恐ろしいところである。普段の日とほぼ変わらぬ人出であった。
- 1月21日(火)
猫事件、図書館の近所に住んでいるため、立ち会った可哀想な職員の話によるとセンサーで侵入者がいることを知った警備会社が警察に連絡をとってくださり、お巡りさんが四人も出動して特殊警棒を持って見回ったとのこと。猫も罪作りである。お巡りさん、忙しい中、すみませんでした_●_。
どうも年が開けてから登録者が多い。図書館の人気が高まってきている感じだ。ありがたいことである。職員数が増えないのが頭の痛いところである。どうやら近隣の図書館のどこもが不景気で来年度の資料費が削られるらしいという話を聞く。元々少ないところから削られる館は大変である。景気が悪いからと出版点数が減るわけではないのだから。しかし出版点数、少しは減っても良いように思うのだけれども。
大学生、相変わらず多し。
- 1月19日(日)
昨日の帰りに猫が館内に入ったまま施錠をしたため、警備会社から連絡が入ったとのこと。少しの間だけでも、戸が開いていると入ってしまうわけで、なかなか困ったことであるが、猫も寒いから入りたいことでもあろう。ま、開けたらこまめに閉める以外に手はない。
レファレンスとコピーがとても多い一日だった。大学生は昨日よりも多い。
専門雑誌を探した方がずっと早く書けそうなレポートが一杯。締切がぎりぎりなのだそうだ。公共図書館は大学生の駆け込み寺か。
新聞の閲覧も多かった。新聞は綴じ方が難しい。長い間保存しようと思うしっかりと綴じないといけないのだが、コピーをする際、真ん中あたりがとれないのではずさないといけない。結構時間がかかるのである。簡単に綴じておくと保存に具合が悪い。
- 1月18日(土)
レファレンスが多い一日だった。大学生多し。大学図書館で調べなければなんともならない事柄も多し。登録者多し。古い新聞の閲覧者多し。
- 1月17日(金)
ど派手な女子大生が調べものにくる。公共図書館でもなんとかなりそうなレポートなので関わりのある分類を説明。1冊でなんとかしようとしている。枚数が2枚とのことなのでなんとかなるのかもしれない。謎だ。
暮れに変態がいたとのこと。椅子に座って本を読んでいた小学生のスカートの中を覗こうとした男がいたことを母親が教えてくれた。あぶなそうな人がいるとあとを職員がついてまわるようにはしているのだが。なんとも困ったことだ。図書館には変態痴漢のたぐいが毎年のように現れる。なぜだ。
- 1月16日(木)
昨日は沢山混んだとのことで、統計を見ると返却冊数が6200冊ほど。記録である。年末年始に貸し出した分の返却期日を今日にしておいたので、混んだのだな、と朝に思っていたら、今日も大忙しであった。返却が4600冊ほど。普段の日曜日並。大学生がレポートのタイトルだけ持って、尋ねてくる。大学図書館の使い方を説明する。中には締切ぎりぎりで、大学図書館に行く余裕もないというのもいる。訳本がないかを尋ねる大学生もいる。探し方だけを一応教える。しかし、ほんと、何か根本で間違ってると思うぞ。
- 1月11日(土)
利用者多し。宿題の中学生、小学生。専門的な理系のレファレンスを年輩の男性から受ける。何の領域に当たるのかさえ、見当がつかず、尋ねると、「実は私もわからないのです。娘の宿題に必要な本を探しにきたのです」とのこと。大学生の娘の宿題を調べにきたお父さんであった。世も末だなとしみじみ思う。
- 1月10日(金)
リクエスト本で事件がおきた。所蔵していない本で絶版の為、相互借り受けをお願いしようと十館ほどに問い合わせたのだが、どこも持っていない。あるシリーズの真ん中あたりの巻。担当者に確認したところ、出版社にも尋ねたが、「出版されたが、現在は絶版」との返事だったとのこと。J-BISC(国立国会図書館所蔵和図書目録のCD-ROM版)を見るとその巻のほかいくつかの巻が抜けている。その巻号がうちの館と全く同じ。89年から90年にかけて出版されているシリーズなので、念のため、「日本書籍総目録」の92年版を見てみるとやはり抜けている巻が同じ。出版社に「以前に現在入手可能かどうかをお尋ねしたのですが、出版されなかった巻がもしかしてあるのではありませんか」と尋ねると、少し調べたのち、「出ていませんでした」との返事。利用者にその旨連絡。担当者の段階で気がつけば他館に手間をかけさせずに済んだのだが、なかなかこういうケースは難しい。刊行予告された多巻本が中途で出版中止となることはままあるのだが、1巻から順に出るものばかりではないから不慣れな職員はここに思い至らないのである。司書の仕事は探偵の仕事と少し似ているといつも思うのであった。経験を積めば積むほど奥行きが深くなってゆく。多くの図書館で司書を採用していない現状はどうすればなんとかなってゆくのであろうか。
- 1月9日(木)
コンピュータのプログラム修正にSEが来館。6月に新機種を導入したのだが、新しいプリンタで打ち出せる帳票がまだほとんどない。貸出返却まわりのプログラムもいくつかつくってもらった。本人以外の貸出券を使わないようにお願いしているのだが、男か女かわからないお名前の方に幾度も「ご本人ですか」と訊く為のクレームが出ていたりもするので(大迷惑な話です_●_)、貸出券をスキャンした時、男女の別が密かに職員にわかるようにしてもらった。
最近ASAHIネットでは家族がIDを使うことがいかに非常識であるかということが問題となっているのであるが、家族の貸出券を使うことも全く同様で、つまりは一人一人が別の人格であるという認識の甘さから起きているように思われるのだが、最近まで家族の券の使用を認めていたわけでもあり、今のところ条例にも組み込んでいない事柄なので対応が難しかったりするのであった。プライヴァシーの概念がしっかりと確立されれば、この国の風通しが多少はよくなるように思うのだが。
- 1月8日(水)
利用者多し。冬休みの宿題の小中学生がまだまだいる。コピーとレファレンスに忙殺される。
- 1月7日(火)
風邪で休む。
- 1月6日(月)
御用始。ブックポストに返ってきた本を返却処理。全部で2000冊ほど。私が出しに来た日が一番多かったようだ。風邪気味。受付のローテーション作成ととしょかんだよりに載せる本の選定。この時悩むのがいくつかの主張のある問題を片側の視点から取り上げた本を載せるか否かである。例えば反原発の本など。同じ時期に原発推進の本が出版されていれば、両方載せることでバランスをとるという方法もとれるのだが。
リクエストされたある本を購入すべきかどうかでミーティング。書評などにも多くとりあげられている本なのであるが、ヌード写真の数が多く、すぐに盗難に
合うおそれのある本にリクエストが入ったのであった。発売された当初から購入すべきか否かで意見が分かれ、討議の末、購入を見送った本なのだった。再検討し、購入することにした。風俗を取り扱った本、ヌード写真集の購入非購入の線引きがとても難しくなってきた昨今である。普通に読む利用者ばかりであればなんということもないのだが、先日のように精液まみれになって返ってきたり、窓口を通さずに自宅へ持ちかえる利用者の数が少なくなく、ヌード写真が載っているというだけで盗難されるケースが随分あるのだ。数は少ないが、「こういう本を図書館に入れても良いのか」というクレームもある。「どういう本ですか」と尋ね、「図書館の自由に関する宣言」の資料収集の自由についての説明、収書方針の説明をして納得していただくまで帰宅させぬつもりで事務室内で対応する。大抵は理解していただける。こうした本をすぐに閉架に入れて、人目に多く触れぬようにしておくという方法もあり、多くの図書館で行われており、私の勤務先でも盗難防止目的でいくつかの図書に対して行っている。だが、これは一種の検閲行為でもあることを職員は認識していないといけない。性に関する本への読者の反応の問題はつきつめれば我が国の文化程度の問題でもあるように思う。
- 1月1日(水)
ブックポストの本を出しにゆく当番。SECOMの解除をしくじったことに気づかずに入館し、仕事をしているとSECOMの人がやってきた。謝る。1000冊ほどの本があり、1時間ほどかかる。
- 12月27日(金)
御用納。毎年のことではあるが、大掃除が結構大変である。箱につめた燃えるごみ燃えないごみを軽ライトバンに乗せ、処理場まで運ぶ。いつもより念入りに書架の整理をする。今年の仕事も終わり。
- 12月26日(木)
今日が今年最後の開館日。利用者、多し。筆記台の上、カウンターの上に乳幼児を乗せる親、高校生の息子の宿題の資料探しに来る親などあり。高校生の息子はアルバイトで忙しいのだそうだ。ううむ、なにかがヘンだ。中学生の宿題、こちらが驚くほど熱心。彼らがノレる内容なのであろう。中学の頃、ノッて勉強をした記憶がない私はなんだか羨ましく思った。
リクエストされた本が新刊MARCにもJ-BISCにもなく、書誌事項のわからない箇所があったので、利用者に尋ねると、雑誌に載っていたとのこと。幸い出版社がわかっていたので訊いてみると、「確かにうちから出ていたが、出版年、著者、形態などはわからない」とのこと。割と大きな出版社なのにそういうことがあるのだなぁ。京都の芸艸堂などは明治時代に自社で出した本の書誌事項をたちどころに答えてくれたものであるが。出版社によって自社本の把握が随分違うのである。いくつかの近隣の図書館にFAXで尋ねると、雑誌の別冊でそういう題のものがあるとの由。とりあえず相互借り受けをお願いする。しかしとうの昔に絶版になった入手しにくい書籍の載っていたという雑誌はいったいいつのだろ、と不審に思う私であった。
- 12月25日(水)
大学生の宿題の資料探しに親御さんが御来館。「大学の先生が近所の図書館で資料を探すように」とおっしゃったとの由。息子さんは図書館の年末年始休み以後でないと帰ってこられないとのこと。下宿しているところの県立図書館の電話番号と住所をお教えする。雑誌論文を読まないとどうしようもない調べもの。中規模の公立図書館では手の打ちようもない。それにしても大学生は勉強するのが一番の仕事ではないのだろか。
中学生の宿題。自分でテーマを選択する方式のものが多い。調べものの基礎がこれくらいの年齢でできると変な大学生にならないのではないかと思う。
図書館史、一回目の校正が済み、原稿を業者に渡す。
- 12月23日(月)
今日も中学生の宿題多し。民族音楽について各自テーマを決めてのレポートというのが出ている。面白いのだが、まだまだ関連図書が少ない分野。中学生が読んですんなりわかるものがなくて大変。先生がある程度調べ方について説明をしておいてくれると助かるのだが。
大学生の宿題も来る。どうも大学の図書館が閉まってから宿題にとりかかる学生が多いらしい。日本の教育ってヘンだと思う。
- 12月22日(日)
大学生の宿題、テスト勉強、二人、三件。どれも雑誌論文を使わないと無理。「大学図書館の本はほかのみんなが借りていってしまっているから、ここへ来た」とのこと。閉架の存在、貸出できない雑誌紀要のことなどまるで知らないらしい。大学が知らせていないのではないかと思われる。学生がガイダンスに出ていないだけかもしれないけれども。
学生時代に授業で講読した短編小説の日本語訳がないかとのお問い合わせ。数年前ならばほとんどお手上げのレファレンスなのだが、日外アソシエーツのいくつかのレファレンスツールやJ-BISC(国立国会図書館所蔵図書目録)のおかげで探しやすくなった。が、しかし、どうやらご所望の小説の翻訳は出ていなさそうであった(出ていないとは言い切れないのが難しいところである。国会図書館に収められていない図書もあるし、アンソロジーの一編にあって、J-BISCからは検索できないというケースもある)。
今年最後の日曜日なので利用者がとても多い。閉架の資料要求、開架の書架案内で足にマメができた。腿とふくらはぎが筋肉痛。歳を感じる。
- 12月21日(土)
中学生の宿題、多くの生徒が来る。北海道の歴史、風土について、というのといろんな国の人工、面積などについて、という宿題が近所の中学で出ているらしい。皆、感じがいい。
大学生の宿題。ある作家の地味な作品についてレポートを書きたいとのこと。中規模の公立図書館では無理だってば。どうして大学図書館を使わないのだろうか。
- 12月20日(金)
冬休みが近い。中学生の社会科の宿題調べが来はじめる。いつもなかなか良い宿題が多いので楽しみでもある。
- 12月19日(木)
昨今暗い話題の多い中、うれしいニュース。筒井康隆氏、断筆解除。今後も用語規制については予断を許さぬ状況であろうが、ともあれほっと息をつく。この国に実質的な言論の自由はあるのだろうか、との疑問を多くの人が抱くべきだと思う。あると思うにしてもないと思うにしても。
- 12月17日(火)
昨日停電があったためか、CD-ROMサーバーを認識できない。メーカーに連絡するとサーバーを正常終了していなかったためかもしれないとのこと。設置したCEとなかなか連絡がとれなかったのだが、電話があり、「CD-ROMのお皿をイジェクトして、もっかい入れてみてください」と言う。14枚のCD-ROMすべてを出し、もっかい入れるとなぜかなおる。メーカーに話すと驚いていた。
昼休みに組合の人と話し合い。
- 12月14日(土)
朝、女子大生の二人連れが来る。三冊の本の所蔵調査を頼まれる。一冊を除いて、小さな公立図書館にはなさそうな本。我が館にはない。他館からの相互借り受けをしようと思い、「お急ぎでなければ、予約用紙にご記入ください」と言うと、明後日のテストに使うとのこと。「ならばお急ぎですね。学校は愛知県内ですよね。先生からの指示の資料でしょうから県内の図書館ではほとんどすべて貸出中になっているのではないかと思われます。校内の書店にはないのですか」と言うと、「教科書なんです」という。一人は持っているが、もう一人は買わなかったとのこと。呆れはてる。
終業後、来年の人員配置について職員で話し合い。五年前に定年退職した一般職のかわりに司書を入れたのだから、今回司書のかわりに一般職を入れ、司書の臨時職員増員となるから一人増だと当局は認識しているという話に、一理ある、とは思うが、当時から貸出冊数はほぼ倍に増えているのにその間、司書は増えていないことをまるで問題にしていないらしい。職員はどのような要求を出し、戦略を立てるかを相談するが、ともあれ現状の維持ができないと困るということで一致。
- 12月12日(木)
司書が一人減って事務職が入るという問題、担当課と話がついている、と組合のニュースに書かれていたため、館長に訊くと世間話のような感じでそういったことを聞いたけれど、あれで決まったわけではないだろ、とのことだったので、確認してもらいにいくと、当局側は正規職員の司書のかわりに臨時職員の司書との意向であり、変えるつもりはない、とのこと。組合と相談せねばなるまい。面倒なことになってきた。
- 12月11日(水)
今日も研修。昨日書いた来年度は司書が一人減って事務職が入るという話が労組のニュースに載っていたと聞き、確認。本決まりになってしまっては大変である。現在カウンターに要する人数は繁雑時本館5名分館2名であり、事務室内に閉架書庫からの出し入れの為の職員が本館に1名必要。昼御飯を3交代で取っているのだが、本館は最低9名(3人ずつ食事にゆく)となる。カウンターは1階2階に最低一人は司書の正職員を配置。分館は昼を二交代にしてカウンターに一人になってしまう場合もあるが、かならず司書の正職員が残るようにしている。司書は正職員が本館に9名分館に2名。分館の職員が休むときには本館から1名応援に行く。また本館内の事務室内のレファレンス、閉架出納も慣れた司書でなければできぬ作業である。本館の土日夏休みの平均入館者1500人、貸出冊数平均が3500冊。今現在ほとんど限界のような状況で利用者と接しているのである。司書は一生図書館に勤務するつもりで入庁している。役所が休みの土日に出勤したからといって手当がつくわけでもなく、司書手当もない。そこに今まで土日休みだった事務職が何年か交代でやってくる。どんな利用者が来ても困らないようになるまでには5年ほどはかかる。事務職の人は5年もいない。けれども司書の採用をしている役所は現実に少なかったりする。他市ではこうだ、と主張してくるだろうなぁ。はてこの話、どうなってゆくだろうか。
- 12月10日(火)
本当は勤務を要しない日なのだけれど、役所のCS(customer satisfaction)研修のため、出かける。市役所内のいろいろな課から主任クラスの職員が参加。図書館業務はサービス業であり、いろいろな利用者からの様々なレファレンスに答え、自館になければ他館から資料をとりよせ、と、日々の仕事がそんな塩梅なわけで、私とてかれこれ12年そうした仕事をしてきており、サービス業務についてはいささかの自信がある。講師は研修会社の知的できれいな女性。研修の内容はわかりやすく、仕事に役立てることのできる部分もあり、悪くはない。ただ気になるのは、この研修を企画した課が、利用者増加とサービス向上の為、正規職員を要求をした際、「サービスを落とせば良い」と言ったのと同じ課であることだ。今年度定年の司書のかわりに事務職の職員を入れようとしている課であることだ。図書館はサービスを上げれば、利用者が増え、要求のレベルも量もアップする。臨時職員はレファレンスや難しい書架案内はできず、長年にわたって図書館に勤めねば、利用者の質問内容の性格で的確な把握ができない。そうした説明を図書館の上司がその課にしてきているはずなのだが。役所とは不思議なところだ、としみじみ思った。
- 12月8日(日)
レファレンスがとても多い。大学生が卒論のための調べものに来ていたりする。いつも思うのだが、大学図書館のガイダンスを大学はもっとしっかりすべきである。閉架があること、論文は書籍だけでなく学術雑誌や紀要にも載っていることを知らない学生が多すぎる。「大学の図書館には本がないんです」と言う学生が頻繁にやってくるのである。
今日もアナーキーな、乳児の親が幾人かいた。ま、毎日のことだが。利用者が多いので事故が怖い。どうして子どもをつくったのかな、と時折疑問に思う。
- 12月7日(土)
土日はいつも利用者が多い。事務室にいてもカウンターから頻繁に呼ばれる。書架案内もとても多い。図書館によっては、カウンターに居る職員が、「その本はどこそこにあります」と棚の場所を口頭で説明するだけのところも多いようだが、他の棚に本が紛れていることもあるし、本棚の数が多いと、口で説明しただけではなかなか利用者はたどり着けない、と偉そうに書いたりするが、実は私の勤務先も数年前までは書架案内をおろそかにしていたのであった。職員数が少ないと、何かの仕事を省かないと回っていかないのだが、何を省いてはならないかを常に考えねばならないと思う。
- 12月6日(金)
「図書館史」に載せる写真を選ぶ。1950年代の図書館の催しものに集まる人はみんな知的に見える。戦後日本人はどんどん頭が悪くなったのではないかとふと思う。外国人講師の講演会に一般の人が集まっている風景もあるが、この講師、日本語での講演だったのだろうか。女性座談会に出席している女の人の半分くらいが着物なのにも驚く。この作業はなかなか楽しい。
- 12月5日(木)
時折、わがままな利用者がいらっしゃる。著作権の問題についてはいずれ「図書館から見た日本」に書く予定でいるが、著作権法によると図書館で複写できる範囲は、調査研究の用に供するため、一人につき一部、一著作の一部分(半分未満)となっている。ところが、「全部コピーさせろ。どうしてできないんだ」
著作権法の条文を見ていただき、説明する。「法律なんかわしは知らん」ま、いろんな方がいるから世の中は楽しいのですけど。
- 12月3日(火)
定期休館日開けの朝はブックポスト(休館日用返却口)がいっぱい。今日は500冊くらいであったが、多いときには1000冊ほど返っている。スキャン忘れをしないよう気をつけて電算処理をし、本棚に返す。午前中ほとんどこの作業で忙殺されるのであった。
- 11月30日(土)
この頃とてもレファレンスが増えた。というか、利用者用検索端末の台数を増やした為(といっても1台から2台に増やしただけなのだけれども)、検索端末の前で悩んでいる人が多くなり、「探しているものは見つかりましたか」と訊くと、書名や著者名でなく(利用者用端末では書名と著者名からの検索しかできない)、テーマから調べようとして、適当な単語を入れてみたりして、題名にその語が入っていないなどという例が割とある。しかもそれがものすごく出版点数の少ない分野の本であったりして、実に楽し苦しい。書名や著者名から探している人も間違えて名前を覚えている人が随分いて、コンピューターは融通がきかないので、出てこない。こういうことは以前からよくあって、書名をしっかり正しく覚えていて尋ねる人は七割にも満たないと思う。「唐沢寿明の『ひとり』を探しているのですが、出てきません」「それは『ふたり』ですね」「スティーブン・キングの『図書警察』という本はないのですか」「『図書館警察』ですね」などという会話が利用者と司書の間ではよく交わされているのである。司書は疑り深くなくてはつとまらない。まるきり違う題名著者名を覚えている人も時々いる。
利用者用検索端末を置いたからといって司書の仕事は減るどころか増えるに決まっているのであった。書誌データをしっかり入力して、利用者用端末を沢山置けば司書はそれほど要らないなどという話を時々耳にするが、とんでもない間違いだと思う。J-BISC(国会図書館の図書データCD-ROM)や『著者名総目録』などのレファレンスツールを使って利用者の探していた本を見つけるのはなかなかスリリングである。言われたテーマがどんな分野かさえ、こちらにわからない、という情けないケースもある。ああ不勉強であるなぁ、と思い、精進せねば、と励みになるのである。司書の仕事は果てがない。
- 11月29日(金)
としょかんだよりに載せる新刊と館内新刊表示のための新刊を選ぶ。としょかんだよりにはやや固めの本を、館内表示には手にとってみたくなるような本、知られている作家の本、人気の出そうな本を選ぶように心がける。ほかに市報に載せる本を選ぶ作業もあり、これは柔らかめの本と渋目の本を混ぜる。このあたりの選択は重要で、わけのわかんない本やしょうもない本ばかりが挙げてあったりすると、利用者にそっぽを向かれることになると思う。司書がいない図書館では
類書の多いハウトゥものや多作作家のエンターテインメントばかり挙げられているのを時々目にする。選書だけはある程度本を読み、司書としての経験を積まねばできない、と私は思う。本を読まない、図書館を利用しない人の多い行政側に説明が簡単にできないことが難なのだが。
朝、すごい利用者が来る。幼児を横抱きに抱えた母親がクリスマスコーナーの絵本を開いて選んでいるらしいのだが、横から子どもがページの真ん中を折り曲げたりひっぱったりしているのに注意しない。たまりかねて、「恐れ入りますが、本が傷みますので扱いにご注意願えますか」と頼むと、「はぁ?」と怪訝な顔。「多くの方が読む本ですので、紙を折り曲げたりしないでください」と言い直すと、「あぁ、はいはい」とこちらを見ずに返事をする。カウンターに戻り、しばらく様子を眺めていたが、相変わらず。その人、棚から出した本を空きの棚に積んでいるので、借りてゆくのであろうと思っていると、そのまま帰ってしまった。カウンターが混んでいた為、その件については注意できなかったが、恐らく何を言っても無駄であろう。極端に不思議な親が増えている。誰か世の中から減らしてくれないだろうか。
- 11月28日(木)
毎日、新刊のパンフレットが山のようにくる。多い日には50件くらいある。地味な良い本はこまめに宣伝をしないと売れないのだろうか。ほとんどが発注済か購入を予定している未刊のものなのだが、当然すべて目を通し、購入するかしないかを検討し、ほかの担当者に回す。
近くの大学がインターネットのノードとなっていて、近隣の公共施設がそこに
アドレスを持って、なにやらする(何ができるのかを模索しながら運営する)という事業が先日はじまっている。パソコンの使い方の説明に学生が来館。インターネット接続用のパソコンが設置された日からすでに図書検索の為などにインターネットを利用しているので、説明はほとんど不要だった。私の勤務先の図書館のホームページをこの先作ることになるらしいが、あまり世間の役に立つような気がしない(理由はいずれ「図書館から見た日本」に書く予定。気になる方がもしおられましたら、メールでお問い合わせください)。
督促電話、今日も多数。本の予約をしている人が延滞をしていたりする。
「図書館史」の校正をはじめる。
- 11月26日(火)
恐ろしい事件があった。本に気違いじみたいたずらをする利用者が時々いる。各ページに髪の毛をはさむ人、ところどころに鼻毛を植える人、口紅でキスマークをつける人、ふけを入れる人などである。今日のはなんとページが精液らしきもので糊づけしてあった。女子職員が書架から発見して何のコメントもつけずに私の机に置いたのであった。知らずに開けてぎゃっと叫んだ。この本は廃棄するしかない。
先日から督促電話の当番が回ってきたので楽しい。ほかの職員は督促電話をかけるのが好きではないようなのだが、私は割と好きなのである。世の中に「私は正しく、相手は正しくない」などということはほとんどない、と私は思っているのだが、督促電話は正しいのである。延滞している利用者はとりあえずいけない人であり、「お早めにお返しくださいね」と電話をする私は正義の人と化すのである。こんな機会はめったにない、と私は思うのである。ま、不毛な仕事であることは確かなのだが。
- 11月25日(月)
休み
- 11月24日(日)
日曜日はお客さんが多い。職員数が少ないので大変なのである。貸出返却ともに4500冊くらいであった。ここ数年、悩んでいそうな利用者に職員から積極的に声をかけるという姿勢で仕事をしていたため、資料についての問い合わせがとても増えた。開架がいっぱいになったので閉架に入れた本が増え、利用者用検索端末を二台入れたことによって閉架資料の閲覧貸出希望が増え、予約リクエストも増えた。図書館らしくなるにつれ仕事量は確実に多くなっているのだが、職員は増えない。増員要求を出すと、「残業をしていない」「ほかの課にももっときついところがある」「サービスのしすぎなのではないか」などといった理由で却下される。残業は嫌いだからしないのであるが、慌ただしいのは土日、夏休み春休みであり、これらの日には資料整理の仕事が滞る。平日に経験を積んだ職員が資料整理を手早くこなしているから回っているのである。私の勤務先では司書職制の維持が危ぶまれてもいる。ま、財政状況が厳しい自治体はこんなものなのであるが。図書館など利用しない人にとっては司書がいてもいなくてもあってもなくってもなくってもなくっても構わないものであろうし。
- 11月23日(土)
勤労感謝の日だというのに仕事。テストの時期なのか、中高生が自宅から参考書などを持ち込んで勉強しているので、「館内の本や新聞を使っての調べもの以外はご遠慮ください」とそれぞれに説明。いずれ「図書館から見た日本」に書くが、1970年に「市民の図書館」(日本図書館協会)によって打ち出された、貸し席をやめて、図書館の参考資料などを使う席だけを設けようとの真っ当な意見は都市部である程度根付いたようだが、愛知県内で貸し席のない図書館が極めて少ないため、説明に時間を要する。私の勤務先では数年前まで200席ほど貸し席をしていたのだが、館内資料利用者の閲覧場所を学生に占領され、テスト期間に事務室内で参考資料を閲覧する利用者が常に十人ほどいる状態に、思い切って貸し席を無くすことにしたのである。
最近の学生には気味が悪いのが増えている。「テスト勉強の人や仕事だけ持ち込んでしている人が沢山席を占めると、調べものの人の席がなくなるので、図書館の本や新聞をご覧になる方のためだけの席にさせてもらっています。申し訳ないのですが、また調べもののときなどに使ってくださいね」などと当方が説明しているのに途中で横を向き、そのまま居続ける輩がいる。反論をする訳ではなく、無視をするのである。こういう人たちが良い大学に行って偉くなったりすると大変だろうな、と思う。
- 11月22日(金)
ひどくさぼってしまっている日記である。今日、いよいよホームページ登録をしようと決心。さて、心を入れ替えて毎日日記をつけることにしよう。
今日は館内整理日なのでミーティングがあった。図書館が手狭になり、来年書架を増やすことになっているのであるが、元々建物自体に限界が来つつあるので、配置をどうするかで頭を痛める。まだ建てて十年と少しなのだが、予算に恵まれたことと国内の出版点数が増えていることにより収容能力を越えてしまうのである。財政状況が厳しいため、増築、新築は難しい。分館を作るという手段もあるわけだが、本館から地域的に離れた分館には新刊書も入れねばならず、収納の問題は解決しないし、また職員数を事前にかなり増やしておかねば本館から長年勤めた職員が出向くことになるわけで、建物だけ建てば済むということではないあたりが大変である。
午後、開架の図書を閉架にしまう作業。
- 10月30日(水)
朝から高校生の宿題で母親が本を探しにくる。げんなり。ま、大学生の母親よ
りはましだが。
- 10月29日(火)
休み明けはいつものことであるが、ブックポストへの返却本が多い。
ひどいときには2000冊以上も返ってくる。
印刷、出版会社の営業の人からある役所で依頼されたものすごい仕事の話を聞く。役所の人に儲けにならない仕事を、「仕事をさせてやっているのだから」という理由でさせられるケースをしばしば聞くが、今日聞いた話はひどすぎる。役人の感覚というのは一体どうなっているのだろうか。
毎日のことだが、3時間受付にいるあいだに2、3歳の子どもを野放しにしている母親が数人。階段を登っていこうが、本の上を歩こうが、数十メートル離れたところにいる母親には無関係である。先日野放しの父親(だと思った)に、「お子さんを見ていてくださいね。床はコンクリートですし、危険です」と注意したところ、組関係の方が頼まれて連れてきていたお子さんだったとのことで、叱られたばかりでもあり、「小さいお子さんを見ていてください」との張り紙もしてあるし、利用者も多かったので、目の前を走るお子さん以外への注意は止した。
リクエスト予約相変わらず多し。レファレンスもこのところ毎日数件。
予算時期なのでばたばたしている。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]